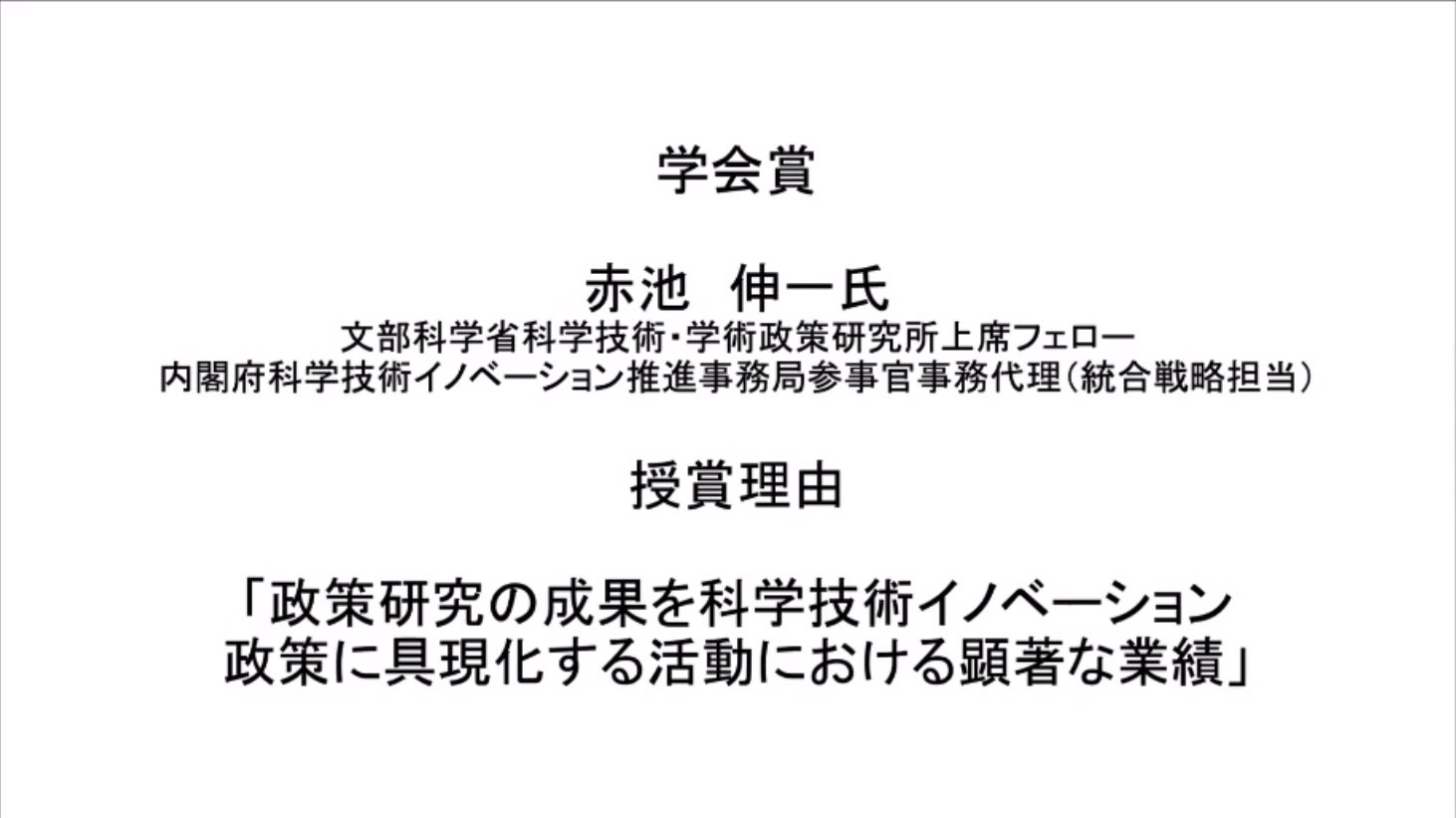科学技術・学術政策研究所(NISTEP)では、次期科学技術予測調査の基礎情報収集及び政策検討の基礎情報提供のため、専門家ネットワークに対し現在注目される科学技術についてのアンケートを行いました。
アンケートでは延べ533件の回答がありました。また同時に、それらの科学技術の実現に必要な事項や実現した際のインパクト等、様々なコメントが寄せられました。なお本調査は、専門家が注目する科学技術を「注目科学技術」とし、専門家の最新の知見を毎年幅広く収集・蓄積し公表するものです。
詳細につきましては、以下のリンクよりご覧ください。