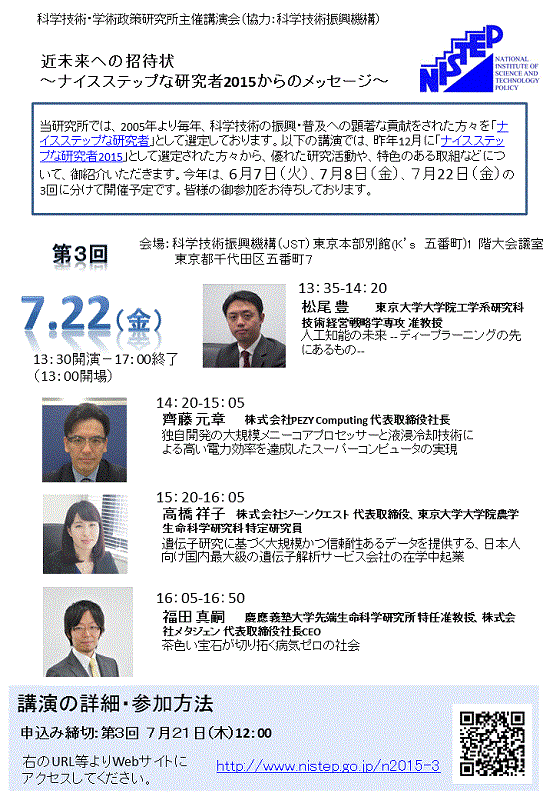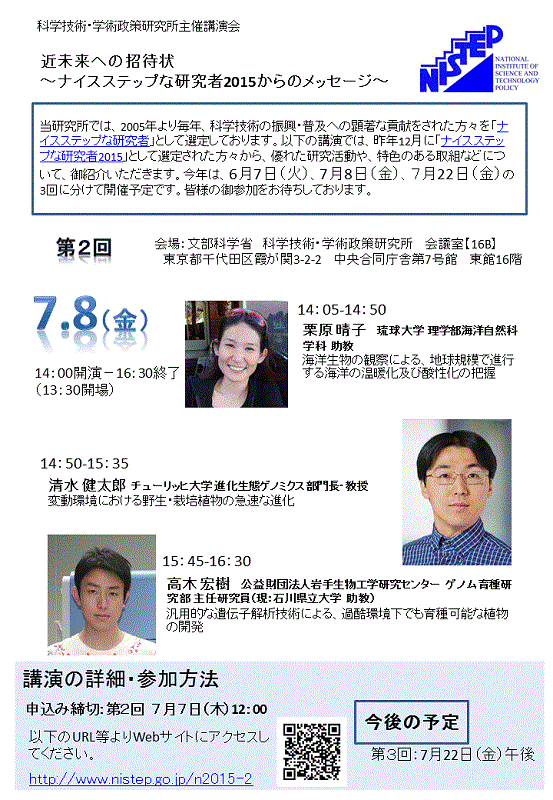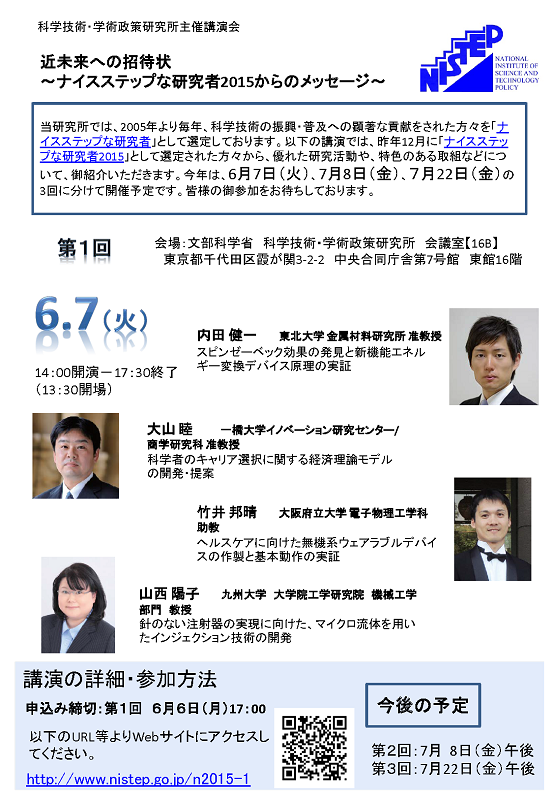科学技術・学術政策研究所(NISTEP)では、以下のとおり講演会を開催します。
開催概要
○演題:「新経済連盟の活動とその目指すところ」
○講師:小木曽稔 新経済連盟事務局(政策統括)
○日時:2016年6月28日(火)15時00分~16時30分(受付開始14時40分)
○場所:文部科学省科学技術・学術政策研究所会議室(中央合同庁舎第7号館東館16F)
講演趣旨
新経済連盟は、日本が将来にわたり国際競争に勝ち抜き、経済成長を続けていくために情報通信技術の利活用を軸としたイノベーション創出のための環境整備が喫緊の課題であるとの認識から、未来の社会・経済を開拓する企業が構成する団体として、2012年から一般社団法人としての活動を始めています。イノベーション(創造と革新)、グローバリゼーション(国際競争力の強化)、アントレプレナーシップ(起業家精神)の促進を旗印に掲げ、従来の技術やサービスの限界に縛られず、来るべき未来の社会・経済を構想・提示することを主旨としています。現在、三木谷浩史氏(楽天株式会社会長兼社長)を代表幹事とし、創設後間もない新しい企業を中心に一般会員332社・賛助会員192社の計524社から成る経済団体に発展しています。海外のスタートアップとの交流も積極的に進め、成長戦略策定プロセスなど政府への具体的政策提言にも力を入れています。
本講演会では、新経済連盟の活動の紹介とともに、イノベーション創出へ向けた考え方や望ましい人材育成の姿などへのご意見をいただきます。
講師略歴
国土交通省勤務を経て、現在、楽天株式会社渉外室渉外課長。新経済連盟事務局では政策関連業務を統括。
参加申込先
参加を希望される方は、件名に「6/28講演会参加希望」と記載の上、氏名・所属を以下の参加申込先(e-mail)にメールにてお申し込みください。なお、会場の都合により参加者を調整させていただく場合がありますので、御了承ください。
※締切り:2016年6月27日(月)17時
担当:文部科学省 科学技術・学術政策研究所 総務課
E-mail宛先:seminar-fellow(at)nistep.go.jp
※(at)は@に置き換えてください。