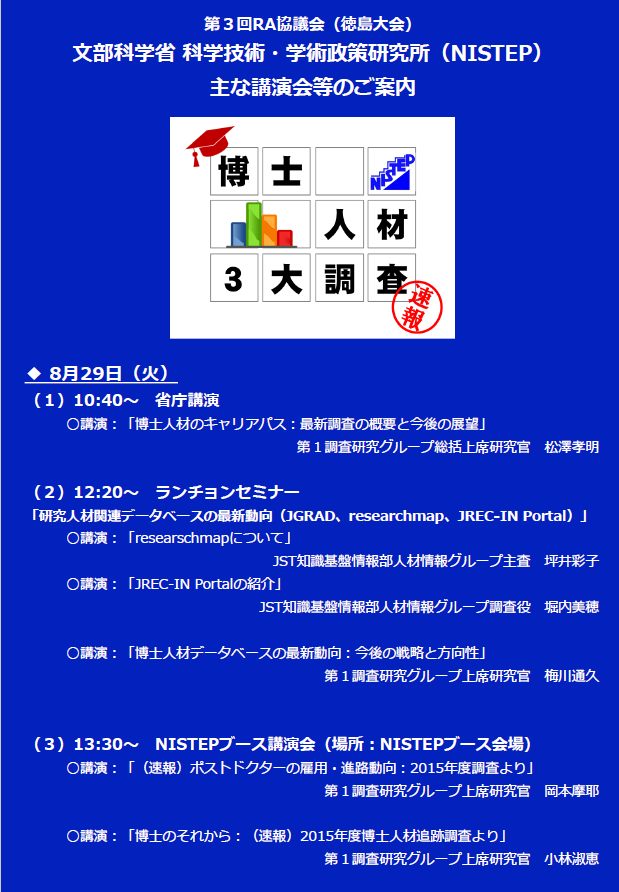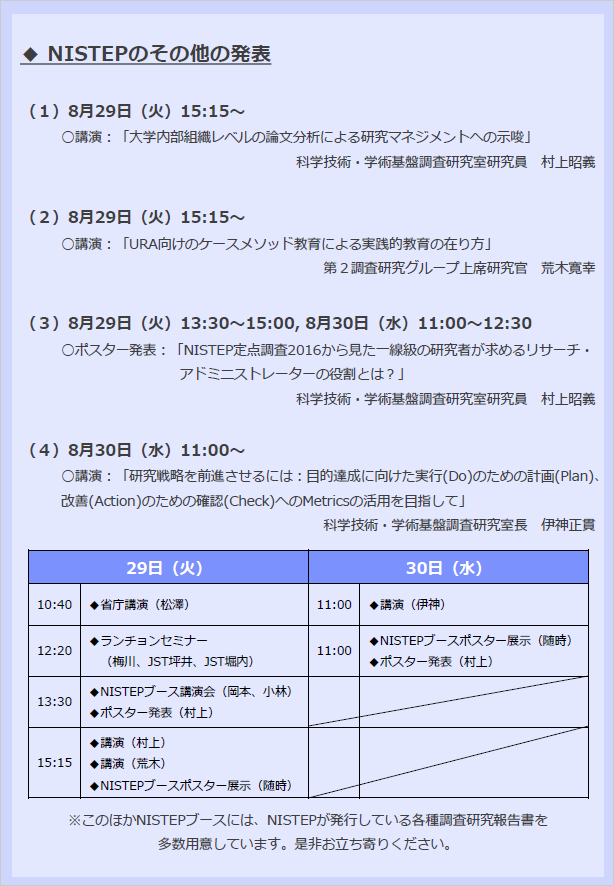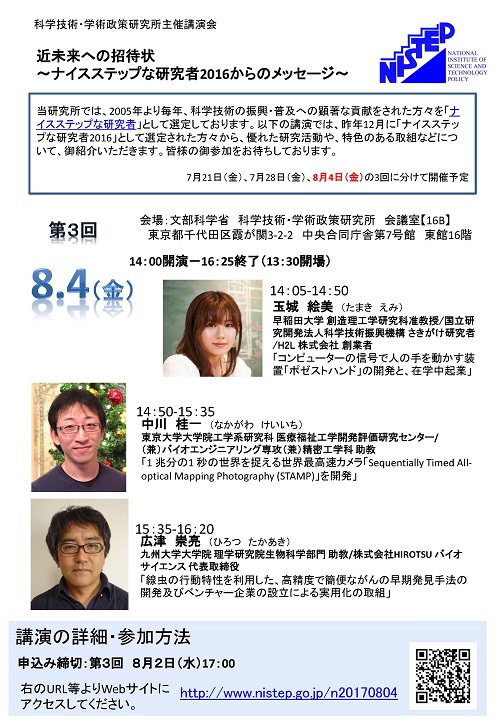※参加登録終了しました※
科学技術・学術政策研究所では、将来社会の課題発見・予測に関する講演会(フォーサイト・セミナー)を下記のとおり開催いたしますので、御案内申し上げます。聴講を希望される方は、御所属・御名前を7月25日(火)18時までに参加申し込みメールにて事前にお知らせください。(会場の都合により出席者を調整させていただく場合があります。)
記
○演題: 「Future Agenda -Six Challenges for the Next Decade -」
「将来課題 ―今後10年の6つのチャレンジ―」
○講師: Tim Jones博士 (Future Agenda, Founder and Programme Director)
○日時: 2017 年7 月27 日(木) 13 時 30 分~15 時 30 分 (受付開始 13 時 00 分)
○場所: 文部科学省 科学技術・学術政策研究所会議室(16B)
(東京都千代田区霞が関3-2-2 中央合同庁舎第7号館東館16階)
https://www.nistep.go.jp/about/maps (地図)
○使用言語:英語(日本語通訳はありません)
○講演会趣旨:
現在のグローバル化した社会では、人々の生活の場、居住環境、国際関係とともに、人々の行動様式や倫理・価値規範も含めて大きく変わりつつあります。こうした変化によって、社会経済も、シェアリングエコノミーの進展などにより、企業組織やビジネスの在り方の根本も変容を迫られるものと予測されています。こうしたマクロの社会変化を体系的に予測するには、異なる文化、産業セクター、国の多様なステークホルダーがオープンな形で将来社会の課題の予測を行う必要があります。当講演会では、オープンなマルチステークホルダーでの予測を行うプラットフォームのFuture Agendaを創設・運営し、公的機関、企業、大学等での予測のファシリテーションの経験が豊かな講演者から、社会的な変化の兆しを捉えるための方法論の実務についてお伺いします。
○講師の御略歴:
Tim Jones博士は、英国ケンブリッジ大学で工学修士号、Royal College of ArtとImperial College Londonで産業デザイン工学に関する修士号を取得後、Salford大学で博士号取得。ジェミニコンサルティングなどイノベーション関係のコンサルタントとして活躍した後に、2000年に新事業創出・機会発見のための民間企業向けのサービスを行うInnovaroを創業し、Shell Technology Futures programmes などの予測プロジェクトに従事。2008年に同社のサービス・ブランドを戦略コンサルティング会社Strategosに売却後、2009年に、幅広く社会課題の予測をオープンな形で行うプラットフォームとしてFuture Agenda を創設し、代表に就任。世界各地で、産学官の関係者を顧客に数多くのワークショップのファシリテーションを行ってきた。また、イノベーション創造関連の著書10冊程度あり、2016年英国で出版の「Future Agenda -Six Challenges for the Next Decade -」は邦訳が出版予定。
○講演内容についてのお問合せ
科学技術・学術政策研究所 科学技術予測センター (白川) Tel:03-3581-0605
○参加申込みは、御氏名と御所属を添えて以下のメールアドレスにお送りください。
Email: seminar-stfc-b@nistep.go.jp
講演会の前日に受講票を添付したメールをお送りします。当日は受講票を印刷のうえ御持参ください。
○申込み締切り: 2017年 7 月 25 日(火) 18:00