科学技術活動を支える重要な基盤である人材を取り扱う。この章では研究開発人材、すなわち、研究者、研究支援者について、日本及び主要国の状況を示す。研究者数に関する現存のデータには、各国の研究者の定義や計測方法が一致していないなどの問題があり、厳密な国際比較が難しい面もあるが、各国の研究者の対象範囲やレベルなどの差異を把握した上で各国の状況を把握することはできる。
2.1各国の研究者数の国際比較
ポイント
- 日本の研究者数は2024年において70.1万人であり、中国、米国に次ぐ第3位の研究者数の規模である。
- 日本の労働力人口当たりの研究者数は、2008年までは主要国の中で、最も多かったが、各国最新年では、韓国がトップであり、ドイツ、フランス、米国、日本、英国、中国と続いている。
- 各国の研究者数を部門別に見ると、「企業」部門の割合が大きい。米国、韓国では約8割、日本は約7割、ドイツ、フランス、中国が約6割である。
- 日本の女性研究者数(HC値)は増加傾向が続いており、2024年では18.3万人、全体に占める女性研究者割合は18.5%である。
- 日本の大学等において、2023年度の「自然科学系」の新規採用研究者における女性割合は34.6%である。分野別の詳細を見ると、「保健」における女性割合は大きく40.0%である。最も小さいのは「工学」の21.0%であるが、2016年度と比較すると6ポイントの増であり、他分野と比較して最も増加している。
- 企業の新規採用研究者における博士号保持者は、2023年度の製造業では726人(新規採用研究者に占める割合は3.5%)、対前年比は2.7%減少した。非製造業では440人(同8.0%)であり、対前年比は100.9%と大きく増加した。
2.1.1各国の研究者の測定方法
「研究者」とはOECD「フラスカティ・マニュアル2015」によると「新しい知識の着想又は創造に従事する専門家である。研究を実施し、概念、理論、モデル、技術、測定、ソフトウェア又は操作工程の改善もしくは開発を行う。」(1)とされている。
a
一般に研究者数は、研究開発費と同様に、質問票調査により計測されているが、一部の国の部門によっては別の統計データを使用しているところもある。また、研究者数を数える場合、二つの方法がある。一つは研究業務を専従換算(FTE:Full-Time Equivalents)し、計測する方法(2)である。この場合のFTEとは研究開発活動とその他の活動を区別し、実際に研究開発活動に従事した時間や割合を研究者数の測定の基礎とするものである。研究者の活動内容を考慮し、研究者数を数える方法であり研究者数の計測方法として国際的に広く採用されている(3)。
もう一つは研究者の活動の内容にかかわらず、実数(HC: Head Count)として計測する方法である。
図表2-1-1は各国の研究開発費の使用部門と同じ4部門について、研究者の定義、測定方法を表したものである(各国のデータはFTE値である。HC値の場合のみ、そのことを明記している)。各国ともに上述したOECD「フラスカティ・マニュアル」の研究者の定義を基に研究者数を質問票調査で測定しているが、部門によっては質問票調査を行っていなかったり、研究専従換算をした研究者数を計測していなかったりと、国や部門によって差異がある。特に大学部門の研究者数の計測には国による違いがある。
日本では総務省が行っている研究開発統計調査(科学技術研究調査)で研究者数を測定しているが、研究者を研究専従換算した値で計測し始めたのは2002年からである。日本の研究者については、対象期間に応じて、以下の3種類の測定方法による研究者数を示した(図表2-1-2)。
図表2-1-2(A)は2001年以前の研究者の測定方法であり、FTEかHCについて明確な定義がされていない。本報告書では、①に○が付いている項目の人数を研究者数として計上している。
2002~2008年の測定方法を、図表2-1-2(B)に示す。FTE研究者数については②に○が付いている項目の人数を計上している。HC研究者数については③に○が付いている項目の人数を計上している。
2009年以降の測定方法を、図表2-1-2(C)に示す。FTE研究者数については②に○が付いている項目の人数を計上している。HC研究者数については③に○が付いている項目の人数を計上している。FTE係数は定期的に更新される。
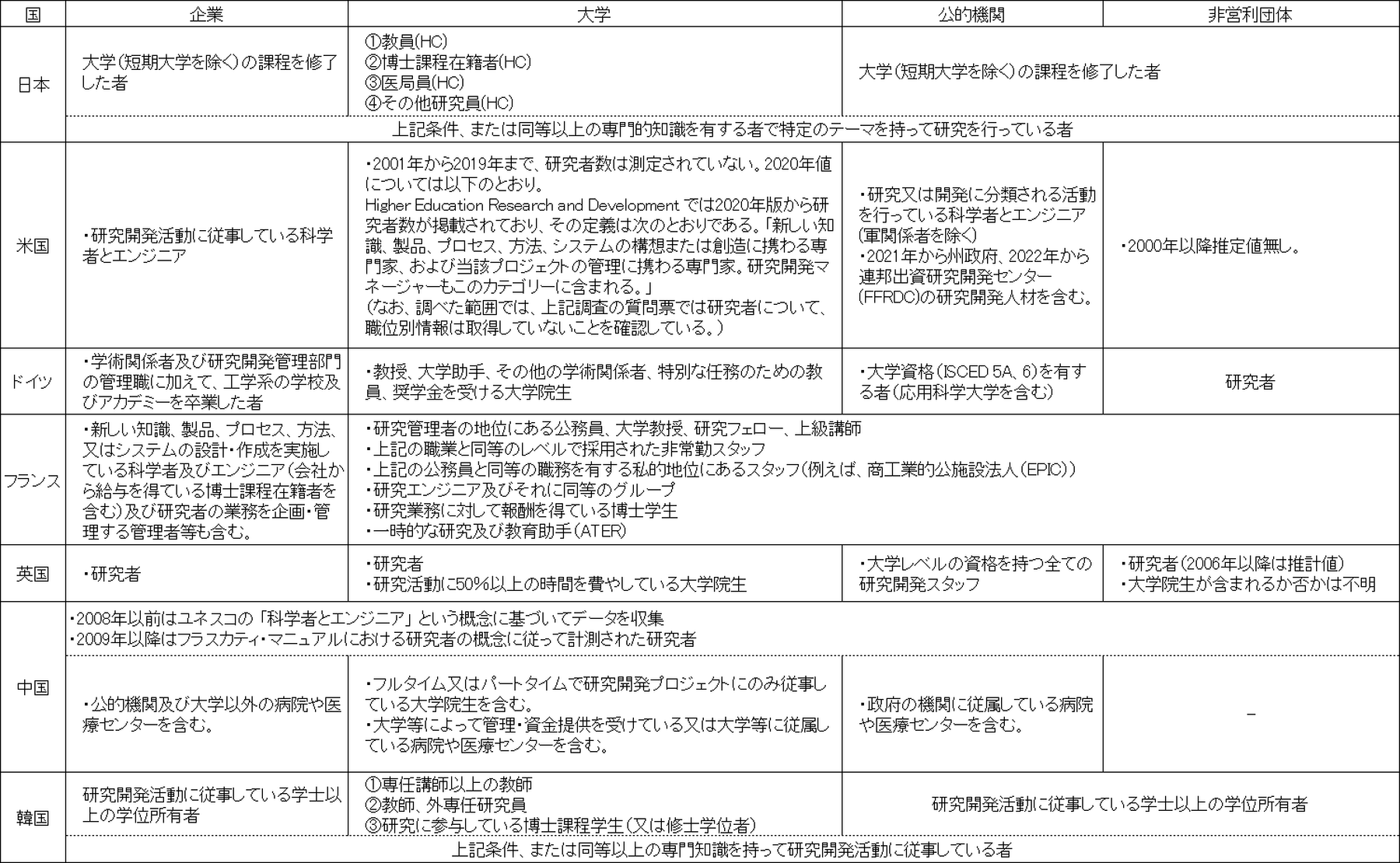
注:
1) 研究者とだけ表記している部門についての研究者の定義及び測定方法の情報は得られなかった。
2) 各国とも研究専従換算した値を計測しているが、していない部門では(HC)と示した。
3) 日本の大学の②博士課程在籍者は後期(3~5年)の者。
資料:
科学技術政策研究所、「主要国における研究開発関連統計の実態:測定方法についての基礎調査」(調査資料-143)(2007年10月)
総務省、「科学技術研究調査報告」
OECD, “R&D Sources and Methods Database”
NSF, “Higher Education Research and Development: Fiscal Year 2020”
MESR, “Higher Education & Research in France, Facts and Figures”
科学技術情報通信部・KISTEP、「研究開発活動調査報告書」
(A)2001年以前
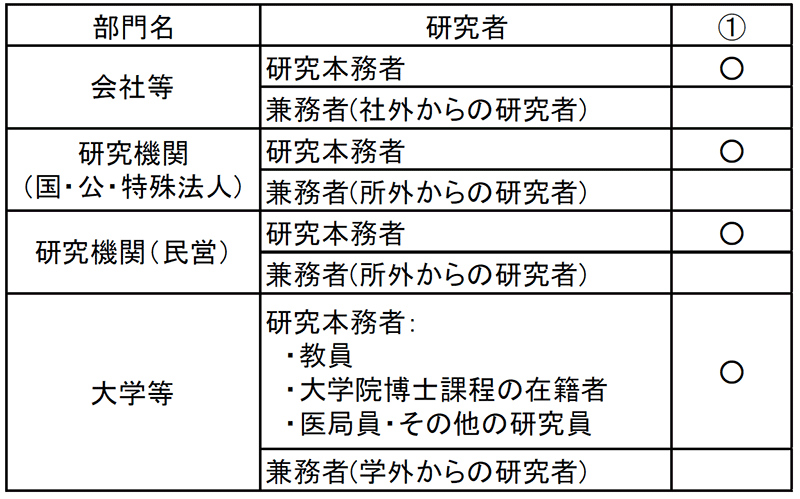
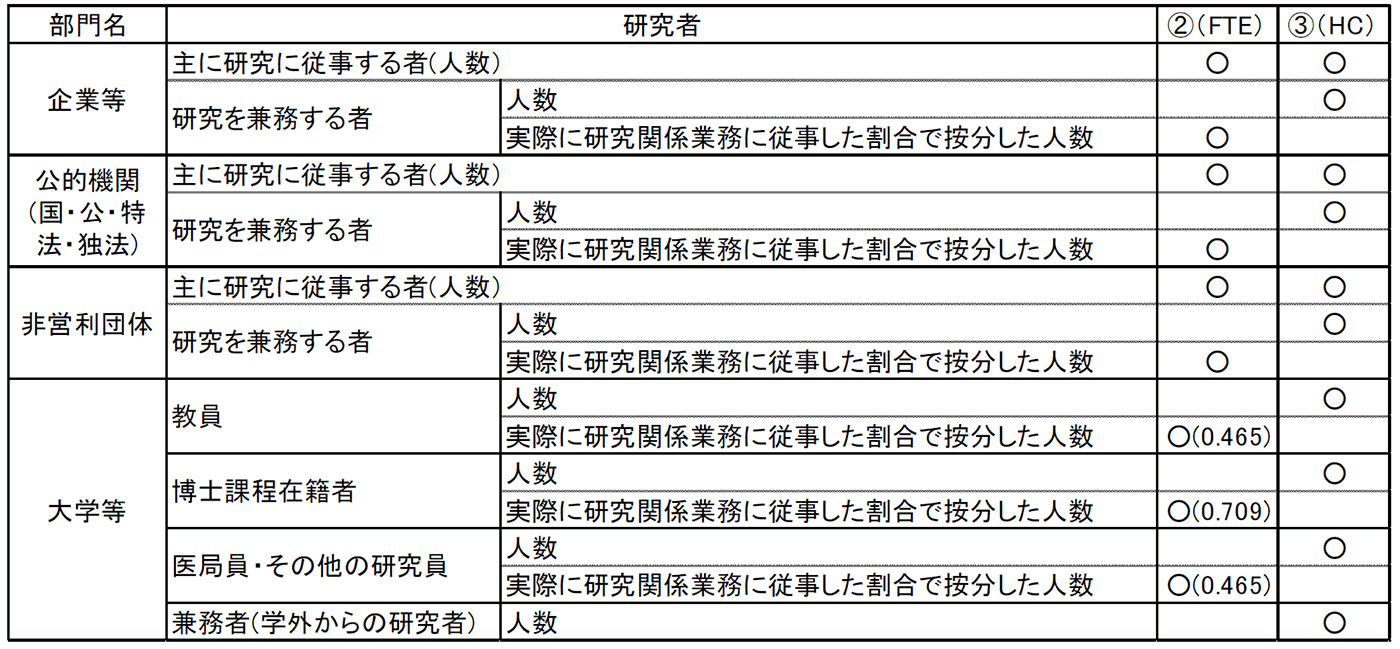
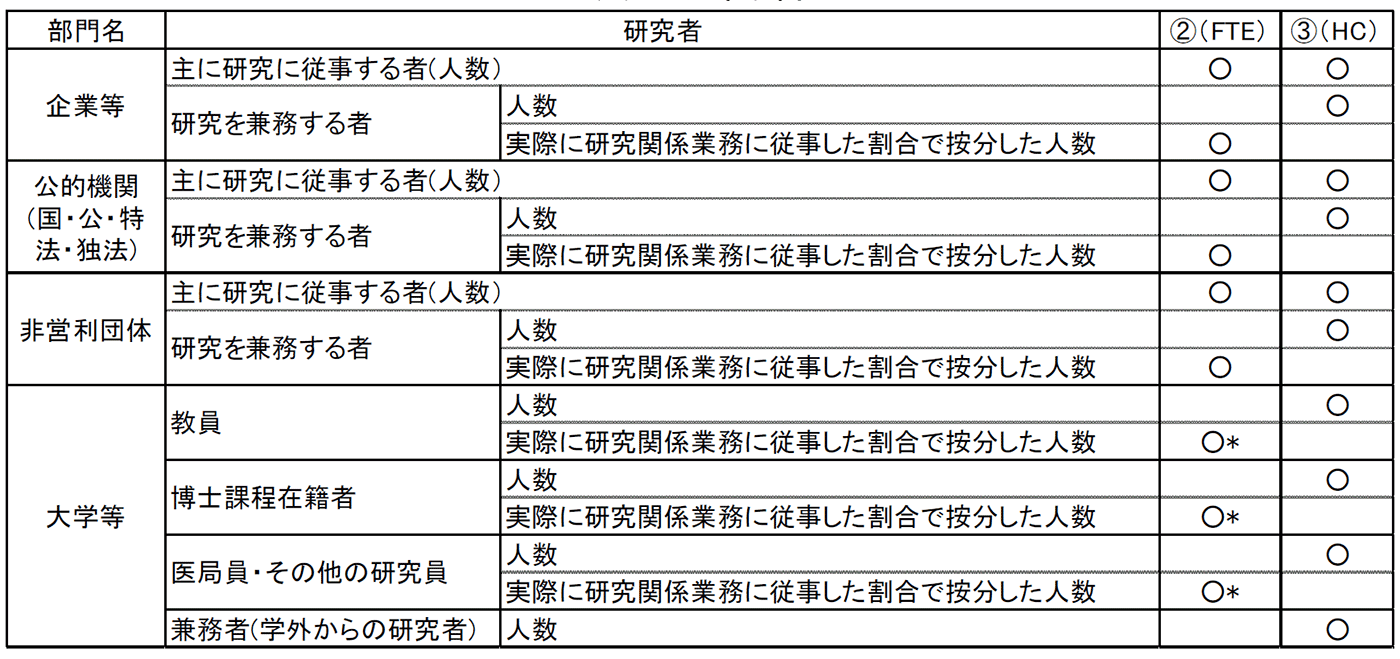
注:
1) 日本の研究者は3種類のデータがある。①FTEかHCについて明確な定義がされていない値、②FTE研究者数、③HC研究者数。それぞれで計上されている項目に○を付けている。
2) 図表2-1-2(B)の大学等に示す数値はFTE係数。該当する人数にFTE係数をかけて計測している。大学等のFTE研究者数については、2002年に文部科学省で実施された「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査(FTE調査)」の結果を用いて、科学技術・学術政策研究所が計算した。ただし、「医局員・その他の研究員」については「教員」と同じFTE係数を使用した。
3) 図表2-1-2(C)の大学等のFTE研究者数(*)は、分野ごとの人数に分野ごとのFTE係数をかけて計測している。2009~2012年のFTE係数は2008年のFTE調査の結果、2013年~2017年のFTE係数は2013年のFTE調査の結果、2018年以降は2018年のFTE調査の結果を用いている。
資料:
総務省、「科学技術研究調査報告」
2.1.2各国の研究者数の動向
図表2-1-3を見ると、日本の研究者数は2024年において70.1万人、HC値は98.9万人である。中国(2023年:300.1万人)、米国(2022年:168.2万人)に次ぐ第3位の規模である。他国の最新年の値を多い順に見ると、ドイツ(2023年:49.9万人)、韓国(2023年:49.0万人)、フランス(2023年:34.6万人)、英国(2017年:29.6万人)である。
日本のFTE研究者数は2002年から計測されており、2008年、2013年及び2018年において、FTEの研究者数を計算するための係数が変更された。そのため2009年、2013年及び2018年のFTE研究者数は、前年からの継続性が損なわれている。
米国については、各雇用部門の公式データが不足していたため、研究者総数は2021年までOECD推計値であった。2022年以降は、各部門の公式データに基づいている。2020年と2021年については、「企業」、「非営利団体」、「大学」部門の公式データと、「公的機関」部門(FFRDCs(4)の欠落部分を推定するため)のOECD推計値に基づいている。それ以前の年については、OECD推計値は2000年まで遡って調整されている。このため、科学技術指標2024以前の数値とは異なることに留意されたい。
ドイツは企業部門、公的機関・非営利団体部門では研究開発統計調査を実施している。大学部門に関しては教育統計を用いて計測しており、研究者の研究専従換算値は、学問分野ごとの研究専従換算係数を使用して計測している。1990年の東西統一の影響を受けて1991年に研究者数が増加したため、データの継続性は損なわれている。長期的に研究者の増加傾向は続いている。
フランスは全ての部門で研究開発統計調査を行い、研究者数を計測しており、1980年代から継続して増加している。
英国については、英国国家統計院(ONS)が2022年11月に発表した研究開発統計において、「企業」部門と「大学」部門の研究開発費の推計値が大幅に修正された。これらの変更は、研究開発を実施する企業のサンプリングが不十分であること(5)を考慮した数値の再調整と、高等教育機関への支出に関する包括的な管理データの採用(6)を反映している。これを受けてOECDは英国の総研究者数及び企業の研究者数については、2015年~2017年まで改訂、最新値は2017年としている。そのため科学技術指標2022以前の数値とは異なることに留意されたい。英国については、掲載している期間においては、長期的に漸増している。
中国は研究開発統計データは公表されているが、統計調査の詳細は不明である。また、2009年からはOECDのフラスカティ・マニュアルの定義に従って研究者数を収集し始めたため、2008年値と比較してかなり低い数値となった。その後は継続的に増加しており、主要国中では一番の規模となっている。2023年の数値が最新値であり、2010年代後半から大きく伸びている。
韓国は部門ごとに研究開発統計調査を実施しているが、2006年までは対象分野を「自然科学」に限っており、2007年から全分野を対象とするようになった。研究者数は継続的に増加しており、2000年代後半に、フランスや英国を上回った。近年ではドイツと同程度となっている。


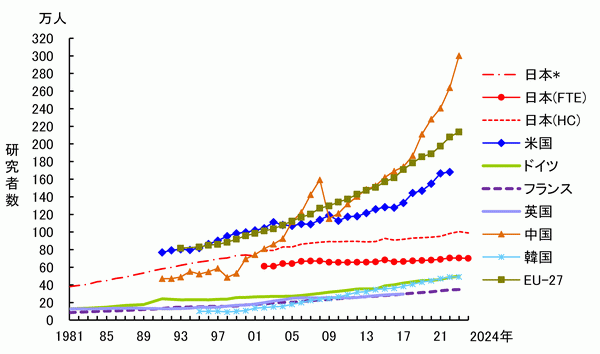
注:
1) 国の研究者数は各部門の研究者数の合計値であり、各部門の研究者の定義及び測定方法には国によって違いがあるため、国際比較する際には注意が必要である。各国の詳細については図表2-1-1を参照のこと。また、時系列の連続性が失われている年があるため、時系列変化を見る際には注意が必要である。
2) 各国の値はFTE値である(日本についてはHC値も示した)。
3) 人文・社会科学を含む(韓国は2006年まで自然科学のみ)。
4) 日本は2001年以前の値は該当年の4月1日時点の研究者数、2002年以降の値は3月31日時点の研究者数を測定している。「日本*」は図表2-1-2(A)①の値。「日本(HC)」は図表2-1-2(B)、(C)の③の値。「日本(FTE)」の2002年から2008年までは図表2-1-2(B)②の値。「日本(FTE)」の2009年以降は、図表2-1-2(C)②の値。
5) 米国は見積り値である。 2022年において時系列の連続性は失われている。定義が異なる。過小評価されるか、過小評価されたデータに基づく。
6) ドイツは1990年までは旧西ドイツ、1991年以降は統一ドイツ。1987年において時系列の連続性は失われている。1996、1998、2000、2002、2008、2010年は見積り値。2023年は暫定値。
7) フランスは1997、2000、2010、2014年において時系列の連続性は失われている。2008、2009年値の定義は異なる。2012、2013年は見積り値。2023年は暫定値。
8) 英国は1991、1992、1994、2005年において時系列の連続性は失われている。1999~2010、2012、2014、2016年は見積り値。
9) 中国は1991~2008年まで定義が異なる。1991~1999年までは過小評価されたか、あるいは過小評価されたデータに基づく。そのため、時系列変化を見る際には注意が必要である。2000年、2009年において時系列の連続性は失われている。
10) EU-27は見積り値である。
資料:
日本:総務省、「科学技術研究調査報告」、文部科学省、「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」
その他の国:OECD,“Main Science and Technology Indicators March 2025”
参照:表2-1-3
次に各国の規模を考慮した人口当たり及び労働人口当たりの研究者数を用いて国際比較を行う。なお、2.1.2項で述べたように、米国については、研究者数が下方推計されていることから、科学技術指標2022以前の数値とは異なる傾向を見せている。英国については改訂された数値が2017年までの掲載となっていることに留意されたい。
人口1万人当たりの研究者数(図表2-1-4)を見ると、日本(FTE)は2009年までは、主要国の中で、最も多い数値であったが、2010年には韓国、2019年にはドイツが上回った。2023年の韓国は94.8人である。次いでドイツが59.0人、日本(FTE)が56.7人、フランスが50.7人、米国が50.4人(2022年)、英国が44.8人(2017年)、中国が21.3人である。
労働力人口1万人当たりの研究者数(図表2-1-5)についても、人口当たりの研究者数と同様の傾向にある。2023年において、多い順に見ると、韓国が167.9人、ドイツが112.3人、フランスが112.1人、米国が102.4人(2022年)、日本(FTE)が101.9人、英国が88.2人(2017年)、中国が38.7人である。ほとんどの国で人口当たりの研究者数との順位の差はあまりないように見えるが、フランスについては、労働人口当たりの方が順位は上である。
2000年代初めには、日本(FTE)は、人口、労働力人口当たりの研究者数のいずれにおいても主要国の中で最も大きな値であった。ただし、過去20年の間で他の主要国と比べて日本の伸びは相対的に小さく、最新データでは日本は他の主要国と同水準は少ない状態となっている。


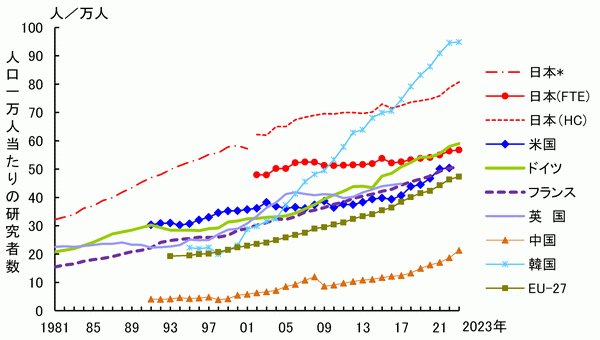
注:
国際比較注意、時系列注意及び研究者数についての注記は図表2-1-3、人口は参考統計Aと同じ。
資料:
図表2-1-3と同じ、人口は参考統計A
参照:表2-1-4


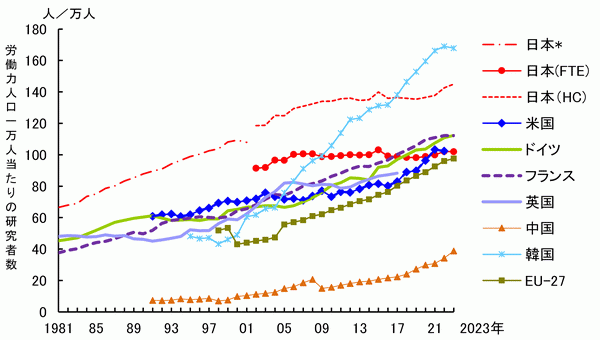
注:
国際比較注意、時系列注意及び研究者数についての注記は図表2-1-3、労働力人口は参考統計Bと同じ。
資料:
図表2-1-3と同じ、労働力人口は参考統計B
参照:表2-1-5
(1)日本については、総務省「科学技術研究調査報告」における「研究者」の定義に従っている。総務省「科学技術研究調査報告」の研究者の定義は、フラスカティ・マニュアルの"Researcher"の定義にほぼ対応していると考えられる。
(2)例えば大学等の高等教育機関の研究者は、研究とともに教育に従事している場合が多いが、このような研究者を、専ら研究を業務とするフルタイム研究者と同等に扱うのではなく、実際に研究者として活動した人的リソースを測定しようとする方法が研究専従換算である。具体的には、例えば、ある研究者が1年間の職務時間の60%を研究開発に当てている場合、その研究者を0.6人と計上する。
(3)OECDは、研究開発従事者の人的リソースは研究専従換算によって測定するべきとの指摘を1975年に行い、多くのOECD加盟国等が研究専従換算(FTE)を採用している。研究専従換算の必要性やその原理については、研究開発統計の調査方法についての国際的標準を提示しているOECDのフラスカティ・マニュアルに記述されている。なお、2015年版では、HCとFTEの両方を測定することを推奨している。
(4)連邦政府資金による研究開発センター(FFRDCs : Federally funded research and development centers)
(5)英国の企業の研究開発統計であるONS, “Business enterprise re-search and development survey” では、これまで小規模の企業の捕捉率が小さかったとされている。
(6)英国ONSの資料によると、これまでの英国の大学部門の研究開発費のデータには、大学の内部で実施かつ資金提供されている研究開発や、研究開発にかかる一部の間接経費が含まれておらず、それらをデータに含めるようにしたとされている。これらの分析には、Office for Studentsが提供するTransparent Approach to Costing(TRAC)システムが使用されている。


