本コラムでは、企業が研究開発を重視しているのかを見るために、売上高当たりの研究開発費に注目し、分析した結果を示す。
(1) 日本の長期的傾向
コラム図表1-1は、日本の企業の売上高当たりの研究開発費について、長期的な傾向を示したものである。1969年度時点では、製造業が1.4%、全産業が1.3%とほぼ同程度の値であった。1980年代に入ると全産業、製造業ともに急激に上昇したが、1980年代後半からは製造業の伸びの方が大きくなった。1990年代以降は年ごとの変動を見せつつ、長期的に緩やかに上昇した。全産業、製造業のいずれも2020年代に入ってから下降していたが、2023年度では製造業が4.0%、全産業が3.1%となった。

注:
1) 2001年度から金融・保険業を除く全産業
2) 科学技術研究調査産業分類を用いている。科学技術研究調査産業分類は日本標準産業分類の改訂を踏まえた分類に変更されている。(2003、2008年)
資料:
科学技術庁、科学技術政策研究所「平成12年度版科学技術指標 データ集 改訂第2版」
文部科学省、科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2016」
総務省、「科学技術研究調査報告」
参照:コラム表1-1
(2) 日本と米国における短期的傾向
次に2008年からの日本と米国の売上高当たりの研究開発費の状況を比較する(コラム図表1-2)。日本では製造業、非製造業ともにほぼ横ばいに推移しているが、製造業は2020年度から2022年度にかけて0.5ポイント減少した。
米国では、製造業については2009年から2013年まで0.8ポイント減少した後に増加に転じた。その後は2020年度から2021年度にかけて0.5ポイントの減少した以外は大きな減少は見られなかった。非製造業については2009年から2010年にかけて0.7ポイント減少した後は継続して増加している。2008年と比較すると、非製造業は1.9ポイント、製造業は0.8ポイント増加した。2022年では製造業5.1%、非製造業4.7%となり、非製造業と製造業の差が小さくなっている。
(A)日本
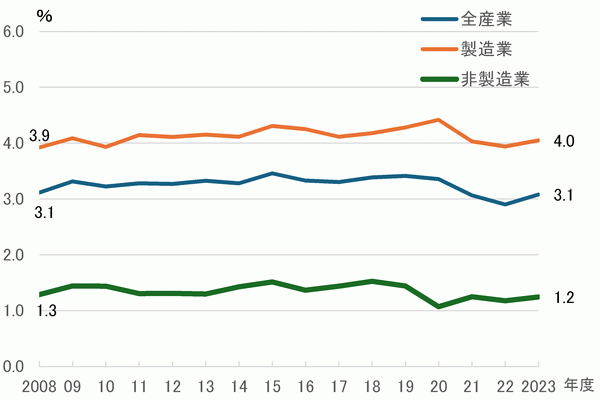
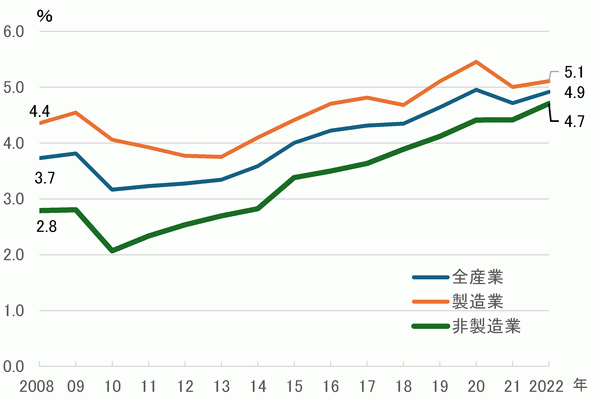
注:
日本はコラム図表1-1と同じ。
米国
1) 北米産業分類システム(NAICS:North American Industry Classification System)について、2008年は2002NAICS、2009~2013年は2007NAICS、2014~2019年は2012NAICS、2020年からは2017NAICSを使用している。
2) 2016年まで国内従業員数が5人未満の企業は含まれない。
3) 2017~最新年まで国内従業員数が10人未満の企業は含まれない。
資料:
日本はコラム図表1-1と同じ。
米国:NSF,
“Business Enterprise Research and Development Survey(2020~2022)”
“Business Research and Development Survey(2017~2019)”
“Business R&D and Innovation Survey(2011~2016)”
“Business Research and Development and Innovation: 2008?10”
参照:コラム表1-2
(3) まとめ
日本の企業の売上高当たりの研究開発費は第2次オイルショックを過ぎた1980年代に全産業、製造業ともに急激に上昇、いわゆるバブル景気に入って大きく伸びた。特に製造業の伸びが大きかった。平成不況を過ぎた1990年代では製造業、全産業ともに伸びは止まり、その後は増減を繰り返しながら、ほぼ横ばいに推移していった。リーマンショック直後の世界金融危機でも大きく落ち込むことはなかった。COVID-19の世界的な流行時では製造業の売上高当たりの研究開発費が2020年度から2022年度まで下降したが、非製造業では大きな変化は見られなかった。
米国企業の売上高当たりの研究開発費を見ると、リーマン・ブラザース破綻から端を発した世界金融危機の時期に、一時的な減少を見せた後は、増加している。COVID-19の世界的な流行時では製造業が2021年に一旦減少しているのに対して、非製造業では減少に至らず、伸び続けていることが分かった。
日米を比較すると、過去15年程度の間、日本の売上高当たりの研究開発費は製造業、非製造業とも横ばいであるのに対して、米国では製造業、非製造業ともに、その値を増加させており、特に非製造業において増加が大きい。つまり米国の企業、特に非製造業は、日本と比べて、研究開発に注力していると言える。
コラム2:研究用消耗品における物価高騰:貿易統計を用いた分析
日本の消費者物価指数は2022年以降、毎年3ポイントの上昇を見せ、ここ数年は物価高騰が続いている[1]。このような物価上昇は、研究開発活動にも少なからぬ影響を及ぼしていると考えられる。
総務省の科学技術研究調査では、研究開発費を費目別に把握している。科学技術指標では、これらを人件費、原材料費、有形固定資産購入費、リース料、その他の経費に整理してデータを掲載している。このうち、原材料費には研究に必要な試作品費、消耗器材費など、その他の経費には研究のために要した図書費、光熱水道費、消耗品費などを含む。
こうした研究開発費の構造に関連して、科学技術・学術政策研究所が実施している科学技術の状況に係る総合的意識調査(NISTEP定点調査)では、第6期科学技術・イノベーション基本計画期間中に、円安や人件費・光熱費・物価高騰が研究活動に与える影響を指摘する記述が増加している[2]。
本コラムでは、こうした背景を踏まえ、財務省の貿易統計を用いて、研究活動に必要とされる消耗品の輸入単価の動向を分析した結果を紹介する。
(1) 分析対象
研究用消耗品には、多様な品物が含まれるが、ここではコラム図表2-1に示す統計品目に注目した。ヘリウムは、超伝導体の冷却や低温物理実験に不可欠な希ガスであり、物理学に加えて、磁気共鳴画像装置などでも用いられる。培養用培地や診断用・研究用試薬品については主に生命科学、医学、化学で用いられる研究用消耗品である。研究用ガラス器具は、実験室で用いるビーカー、フラスコ、メスシリンダー等のガラス製器具である。
(2) 研究用消耗品の単価の時系列変化
コラム図表2-2は2010年を基準とした、研究用消耗品の単価(1Kg当たりの価格)の変化である。最も上昇率が高いのは、ヘリウムであり2024年の単価は2010年の7.2倍である。なお、ヘリウムについては長期的に単価が上昇しており、2000年と比べた2024年の単価は12倍である。これに続く単価の上昇が見られるのは、診断用・研究用試薬類であり、2024年の単価は2010年の4.6倍となっている。研究用ガラス器具、培養用培地については、2024年の単価は2010年と比べて、共に2.7倍となっている。4つの研究用消耗品の中で、ヘリウムと診断用・研究用試薬類については、2010年代後半になってからの単価の上昇が大きい。
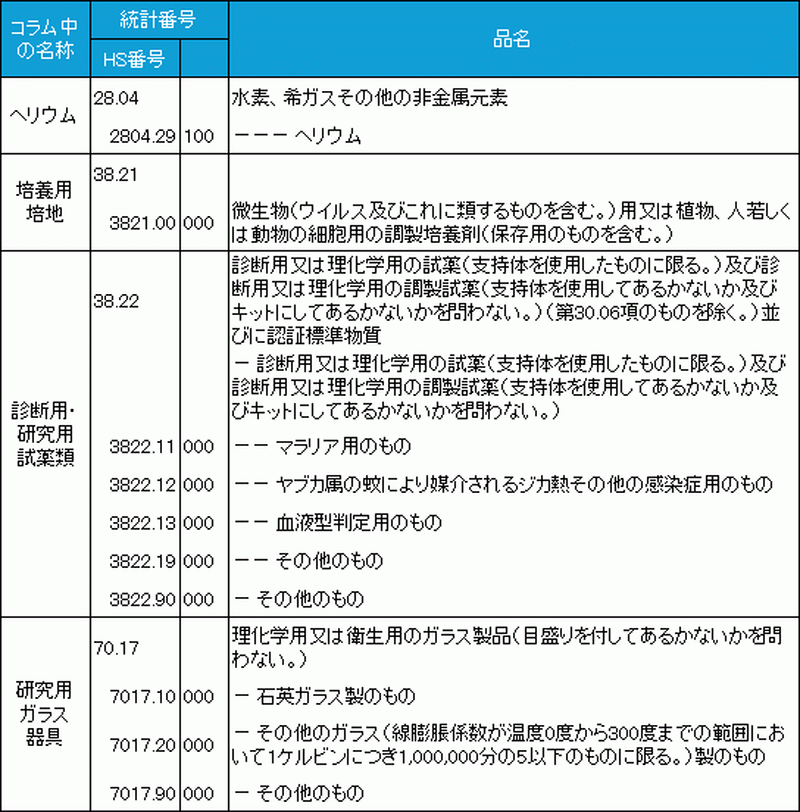
資料:
財務省、「貿易統計」
参照:コラム表2-1
(3) 研究用消耗品の輸入国・地域
コラム図表2-3には、4つの研究消耗品のそれぞれについて、2024年時点で上位5の輸入国・地域別の輸入額・輸入量・単価を示した。ヘリウムについては、米国とカタールの2か国で輸入額のほぼ全てを占めている。培養用培地については、輸入額の約5割を米国が占めており、これにポーランド、英国、プエルトリコ(米)、フランスが続く。診断用・研究用試薬類については、輸入額の約4割を米国が占めており、これに中国、ドイツ、アイルランド、英国が続く。中国について、単価が8千円/Kgと他国・地域と比べて小さい。研究用ガラス器具については、他の研究用消耗品と比べて、輸入国・地域が分散しており、米国、中国、ドイツの輸入額が10%を超えている。
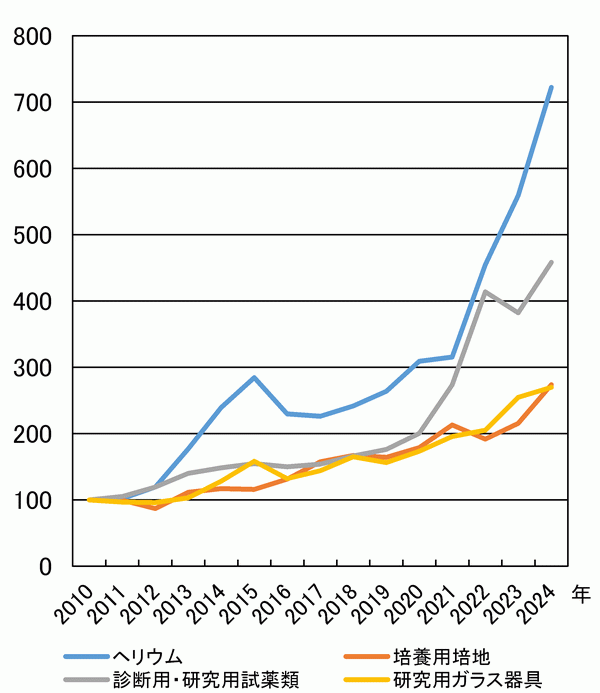
注:
2010年の価格を基準(100)とした変化。データは財務省の貿易統計のホームページ(https://www.customs.go.jp/toukei/search/futsu1.htm)から2025年4月14日に取得。
資料:
財務省、「貿易統計」
参照:コラム表2-2
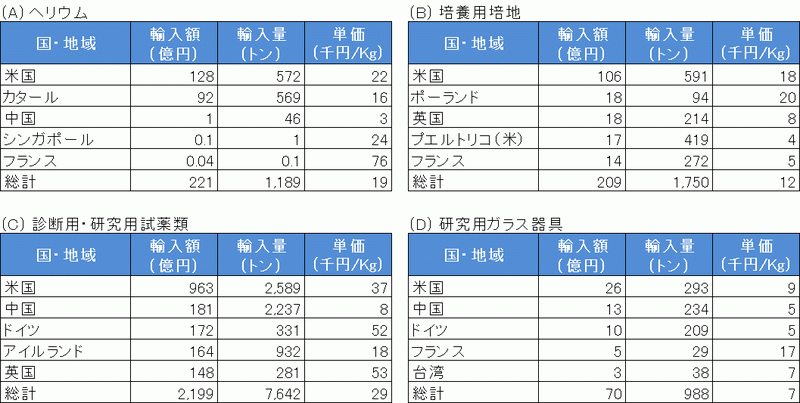
注:
2024年の値。データは財務省の貿易統計のホームページ(https://www.customs.go.jp/toukei/search/futsu1.htm)から2025年4月14日に取得。
資料:
財務省、「貿易統計」
参照:コラム表2-3
(4) まとめ
図1-3-13で見たように、2000年代の日本の大学等における研究開発費(OECD推計)は、おおむね横ばいという状況である。他方で、本コラムで見たように研究用消耗品の単価については、2010年基準で見ても大きく増加している。これらの結果を踏まえると、大学等において実質的に研究開発に使用できる研究開発費の額は減少しており、その度合いは2010年代後半以降加速している可能性がある。研究用消耗品の価格変動は、研究活動の持続可能性に大きな影響を与えていると言える。
なお、本コラムでは、輸入した研究用消耗品について分析を行っているので、その単価の上昇の影響は、研究用消耗品の輸入品への依存度によっても異なる。例えばヘリウムについては、日本国内では産出しないので、単価の上昇がそのまま研究活動に影響する。
[1] 総務省 消費者物価指数(CPI)結果, https://www.stat.go.jp/data/cpi/1.html (2025年4月28日アクセス)
[2] 文部科学省 科学技術・学術政策研究所 科学技術の状況に係る総合的意識調査(NISTEP定点調査),
https://www.nistep.go.jp/research/science-and-technology-system/nistep-teiten-survey (2025年5月30日アクセス)


