ポイント
- 2023年の日本の性格別研究開発費のうち「基礎研究」の割合は全体の14.4%、「応用研究」は20.5%、「開発」が65.2%である。2010年頃から、「応用研究」が減少し、「開発」が増加傾向にある。
- 研究開発費を性格別に分類して見ると、他国と比較して、「基礎研究」及び「応用研究」の割合が最も大きいのはフランス、「開発」が最も大きいのは中国である。
- 「企業」の性格別研究開発費は、いずれの国でも「開発」が最も大きく、「基礎研究」が小さい傾向にある。「大学」の性格別研究開発費は、ほとんどの国で「基礎研究」が最も大きい傾向にあるが、中国では「応用研究」が最も大きい。最新年の「基礎研究」の割合は、米国、フランスが約6割、日本が約5割、中国、韓国が約4割となっている。
- 「公的機関」の性格別研究開発費の最新年では、多くの国で「開発」の割合が最も大きい。米国、中国、韓国は約5割、日本は約4割を占める。フランスについては、「応用研究」の割合が大きく、最新年では約6割を占める。
- 日本の企業における「基礎研究」の研究開発費を産業分類別に見ると、最も多いのは医薬品製造業(3,042億円)である。これに、輸送用機械器具製造業(2,329億円)、化学工業(964億円)と製造業が続いている。2007年度と比較して最も伸びているのは輸送用機械器具製造業(2.9倍)である。
1.4.1各国の性格別研究開発費
性格別研究開発費とは、基礎、応用、開発という大まかな分類に分けた研究開発費を指す。この分類はOECDのフラスカティ・マニュアルによる定義に基づいて各国が分類している。そのため回答者による主観的推計が分類結果に少なからず影響していることを考慮する必要がある。以下に、最新版フラスカティ・マニュアル2015に掲載されている性格別の定義を簡単に示す。
基礎研究(Basic research)とは、何ら特定の応用や利用を考慮することなく、主として現象や観察可能な事実のもとに潜む根拠についての新しい知識を獲得するために実施される、試験的あるいは理論的な作業である。
応用研究(Applied research)とは、新しい知識を獲得するために企てられる独自の研究である。しかしながら、それは主として、特定の実用上の目的または目標を目指している。
(試験的)開発(Experimental development)とは、体系的な取組であって、研究または実用上の経験によって獲得された既存の知識を活かすもので、新しい材料、製品、デバイスの生産、新しいプロセス、システム、サービスの導入、あるいは、これらの既に生産または導入されているものの大幅な改善を目指すものである。
なお、日本の性格別研究開発費(25)は自然科学分野を対象に計測されており国全体の研究開発費総額ではない。また、韓国は2006年まで自然科学分野を対象にしていたが、2007年から全分野を対象にしている。
図表1-4-1は主要国の研究開発費の性格別割合である。「基礎研究」、「応用研究」が最も大きいのはフランス、「開発」が最も大きいのは中国である。
2023年(26)の日本の性格別研究開発費のうち「基礎研究」の割合は全体の14.4%、「応用研究」は20.5%、「開発」が65.2%である。他国と比べて割合の変化は小さいが、2010年頃から、「応用研究」が減少し、「開発」が増加傾向にある。
米国の最新年における「基礎研究」の割合は14.5%、「応用研究」は18.0%、「開発」は67.3%である。米国は、性格別のバランスが日本と似ていたが、2010年頃から、「基礎研究」の減少、「開発」の増加が見られる。
フランスは、他国と比較して「基礎研究」及び「応用研究」の割合が最も大きく、最新年ではそれぞれ20.4%、43.1%である。「開発」は36.4%である。
中国は「基礎研究」の割合が他国と比較して最も小さい。ただし、2010年頃から漸増し、最新年では6.8%となった。「開発」の割合は82.3%であり、他国と比較しても最も大きい。
韓国では、2000~2010年にかけて「基礎研究」の割合は増加、「応用研究」の割合は減少した。2010年以降は「基礎研究」の割合は減少し、「応用研究」の割合は増加したが、近年はほぼ横ばいに推移している。「開発」の割合は増減を繰り返しながらも、長期的には横ばいに推移している。最新年の値はそれぞれ14.9%、19.7%、65.4%である。
なお、ドイツは国全体の性格別研究開発費のデータを公表していない。ただし、「企業」部門は2007年から、「政府(非営利団体を含む)」部門は2006年から、性格別研究開発費の計測データが公表されるようになった(OECDデータによる)(27)。また、英国については改訂されたデータ(1-1-1項参照)に基づく性格別研究開発費のデータが公表されていないため今般の科学技術指標では掲載していない。

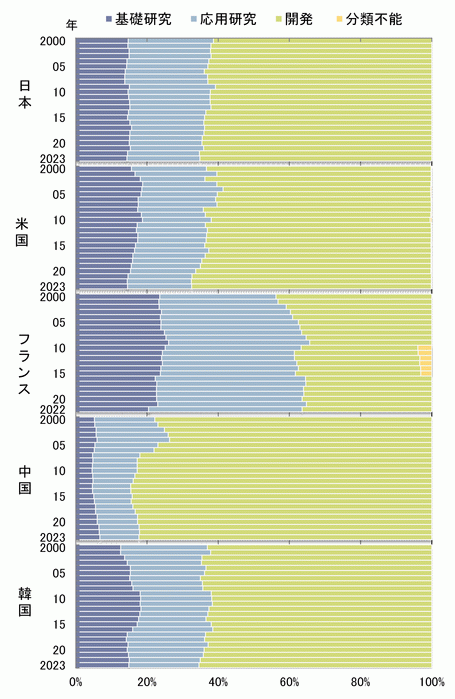
注:
1) 日本の研究開発費は自然科学のみ、韓国は2006年まで自然科学のみである。他の国の研究開発費は、自然科学と人文・社会科学の合計であるため、国際比較する際には注意が必要である。
2) 日本は年度の値を示している。
3) 米国は定義が異なる。2003、2021、2023年に時系列の連続性は失われている。2023年は暫定値。
4) フランスは2004、2010年において時系列の連続性は失われている。2016、2018、2019年は見積り値。
5) 中国は2009年において時系列の連続性は失われている。
資料:
日本:総務省、「科学技術研究調査報告」
その他の国:OECD,“Gross domestic expenditure on R&D by sector of performance and type of R&D”
参照:表1-4-1
1.4.2主要国の部門別の性格別研究開発費
主要国の各部門における研究開発費を性格別の割合で見る。
「企業」の研究開発費を性格別で見ると(図表1-4-2(A))、いずれの国でも「開発」が最も大きく、「基礎研究」が小さい傾向にあるが、そのバランスは異なる。各国最新年において、「開発」の割合が最も大きいのは中国であり96.5%を占める。日本、米国では約8割、韓国では約7割である。フランスでは「開発」、「応用研究」共に大きく、約5割と約4割である。日本、韓国では「応用研究」の割合は約2割である。また、「基礎研究」の割合はほとんどの国で1割程度である。
「大学」の研究開発費を性格別で見ると(図表1-4-2(B))、最新年において「基礎研究」が最も大きい国は米国、フランス(約6割)であり、日本(約5割)、中国、韓国(約4割)と続いている。長期的に見て日本の「基礎研究」がほぼ横ばいなのに対して、米国、フランスでは2010年代後半まで減少、その後は横ばいに推移していたが、最新年のフランスは大きく減少した。中国では2010年代後半あたりまで増加した後に減少、近年は横ばいである。「応用研究」の割合が大きいのは中国(約5割)であり、韓国の「開発」は他国と比較すると大きい(約3割)。
「公的機関」の研究開発費を性格別で見ると(図表1-4-2(C))、最新年では、多くの国で「開発」の割合が最も大きく、米国、中国、韓国は約5割、日本は約4割を占める。日本の「公的機関」については、2001年に国営研究機関の一部と特殊法人が独立行政法人化により、特殊法人・独立行政法人となったことに留意されたい。フランスについては、「応用研究」の割合が大きい傾向にあり、最新年では約6割を占める。最新年の「基礎研究」の割合は、日本、米国、中国は約2割、フランス、韓国は約3割である。


| (A)企業 | (B)大学 | (C)公的機関 |
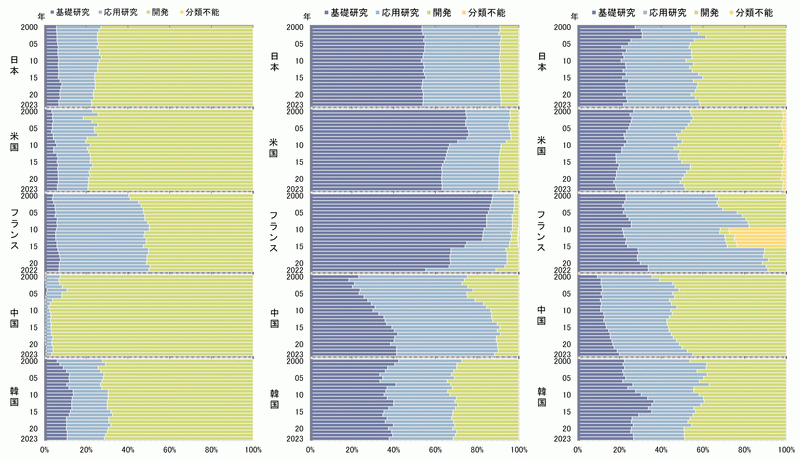 |
||
注:
1) 日本の研究開発費は自然科学のみ、韓国は2006年まで自然科学のみである。他の国の研究開発費は、自然科学と人文社会科学の合計であるため、国際比較する際には注意が必要である。時系列比較注意については、各国の注記を参照のこと。
2) 日本は年度の値を示している。日本の「公的機関」については、2001年に国営研究機関の一部と特殊法人が独立行政法人化により、特殊法人・独立行政法人となった。
3) 米国は企業の2000~2014年、公的機関の2000~2008、2021年以降、大学の全てにおいて定義が異なる。企業の2015、2016、2021、2023年、大学の2003年に時系列の連続性は失われている。2023年は暫定値。
4) フランスは企業の2001、2004、2006年、大学の2004、2014年及び公的機関の2010年において時系列の連続性は失われている。大学の応用研究及び公的機関の2016、2018、2019年は見積り値。
5) 中国は企業、公的機関の2009年において時系列の連続性は失われている。
資料:
日本:総務省、「科学技術研究調査報告」
その他の国:OECD,“Gross domestic expenditure on R&D by sector of performance and type of R&D”
参照:表1-4-2
1.4.3日本の企業部門の基礎研究
ここでは日本の「基礎研究」の研究開発費を産業分類別に見る(図表1-4-3)。
2023年度において、「基礎研究」の研究開発費が最も多いのは医薬品製造業(3,042億円)である。これに、輸送用機械器具製造業(2,329億円)、化学工業(964億円)と製造業が続いている。非製造業では、学術研究,専門・技術サービス業(594億円)が多い。
2007年度と比較すると、医薬品製造業は1.3倍、輸送用機械器具製造業は2.9倍、化学工業は1.9倍、学術研究,専門・技術サービス業は1.3倍となっており、輸送用機械器具製造業の伸びが著しい。他方で、電子部品・デバイス・電子回路製造業は0.4倍、情報通信機械器具製造業は0.5倍、電気機械器具製造業は0.6倍となっており、2007年度から減少している。
「基礎研究」に注力している度合いを産業別に見ると、2023年度では、研究開発費全体に占める「基礎研究」の割合は医薬品製造業が20%、輸送用機械器具製造業は5%、化学工業は9%、学術研究,専門・技術サービス業は6%となっている。
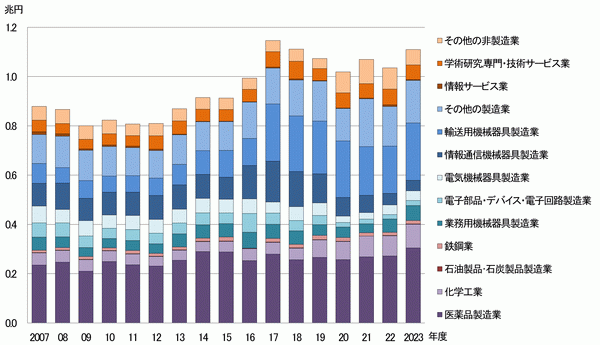
資料:
総務省、「科学技術研究調査報告」
参照:表1-4-3
(25)日本の「科学技術研究調査」での性格別研究開発費の定義は以下のとおりであり、対象は自然科学分野のみである。
基礎研究:特別な応用、用途を直接に考慮することなく、仮説や理論を形成するため、又は現象や観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的研究をいう。
応用研究:基礎研究によって発見された知識を利用して、特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる研究や、既に実用化されている方法に関して、新たな応用方法を探索する研究をいう。
開発研究:基礎研究、応用研究及び実際の経験から得た知識の利用であり、新しい材料、装置、製品、システム、工程等の導入又は既存のこれらのものの改良をねらいとする研究をいう。
(26)この項の日本は、国際比較の際には「年」を用いている。本来は「年度」である。日本のみを記述している項では「年度」を用いている。
(27)「企業」部門は隔年のデータを示している。2021年は、基礎研究:7.2%、応用研究:41.8%、開発:50.9%である。「政府(非営利団体)」部門では、2013年から毎年のデータを示している。2021年は、基礎研究:48.0%、応用研究:46.8%、開発:5.2%である。


