企業及び大学部門の研究者数は、中国が主要国中1番の規模である。企業部門の研究者数では、米国と中国が拮抗しつつ伸びていたが、2021年以降中国が大きく増加した。日本は2000年代後半からほぼ横ばいに推移し、2017年以降は微増していたが、2024年は52.4万人、対前年比は1.3%減となった。大学部門についても、中国の研究者数は大きく増加している。ドイツは2000年代中頃から研究者数が増加しており、日本に迫っている。日本の伸びは緩やかであり、最近は横ばい傾向である。
2024年において、博士号保持者数が最も多い部門は「大学等(14.1万人)」である。「企業」は同年で2.8万人と他部門と比較すると小さいが、2002年と比較して1.7倍となっている。
研究者(大学院博士課程在籍者を除く)に占める博士号保持者の割合は「大学等」で大きく、2024年で61.4%である。最も割合が小さいのは「企業」であり、同年で4.6%である。
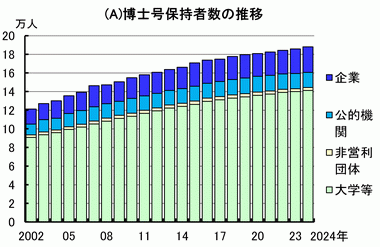
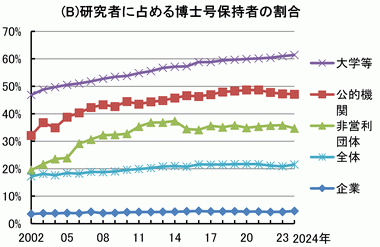
注:
1) 研究者はHC(実数)である。
2) 概要図表8(B)における「大学等」の研究者は、「教員」、「医局員・その他の研究員」を対象とし「大学院博士課程在籍者」を除いている。博士号保持者はこの内数である。また、学外からの兼務者は除いている。
3) 該当年の3月31日時点の研究者数を測定している。
2024年の日本の女性研究者数は18.3万人、全体に占める割合は18.5%である。そのうち博士号保持者は3.8万人であり、着実に増加している。
「大学等」における任期有り研究者の割合を見ると、「保健」分野では任期有り研究者の男女差が見られないのと比較して、「理学」、「工学」、「農学」では、男女差が大きい。
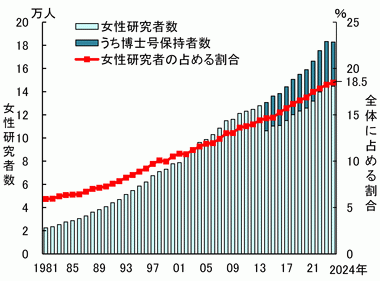
注:
1) 2001年までは研究本務者の値である。2002年以降はHC(実数)である。
2) 2001年以前の値は該当年の4月1日時点の研究者数、2002年以降の値は3月31日時点の研究者数を測定している。
参照:科学技術指標2025図表2-1-12
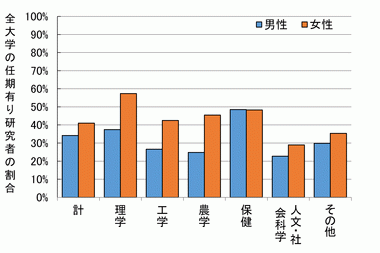
注:
1) 教員及びその他の研究員を対象としている。HC(実数)である。
2) ここでの任期無し研究者は、教員及びその他の研究員のうち、雇用契約期間の定めがない者(定年までの場合を含む)をいう。任期有り研究者とは、任期無し研究者以外を指す。
3) 該当年の3月31日時点の研究者数を測定している。
参照:科学技術指標2025図表2-2-15

