ポイント
- 各主要国におけるプロダクト・イノベーション実現企業割合を1として、企業規模別の状況を見ると、ほとんどの国で大規模企業における数値が高い傾向にある。このことは中小規模企業より大規模企業においてイノベーションが実現されていることを示唆している。
- 日本の大学と民間企業等との「共同研究」の受入額は継続的に増加し、2022年度には1,000億円に達した。
- 日米英の最新年度の大学における知的財産権収入を見ると、日本は65億円である。英国は373億円であり、日本は2005年と比較すると約7倍となっている。また、米国は3,649億円と桁違いの規模を持っている。
- 日本の大学発ベンチャー企業数は順調に増加しており、2023年度では4,288社である。また、大学発ベンチャー企業全体での従業員に占める博士号保持者の割合は19%であり、一般企業の研究者のうちの博士号保持者の割合(4%)と比較しても、博士号保持者の割合は大きい。
- 日本は開業率、廃業率共に、他の主要国と比較して低い。
5.4.1主要国における企業のイノベーション実現状況
イノベーションの定義は、「オスロ・マニュアル(イノベーションに関するデータの収集、報告及び利用のためのガイドライン)」に基づいている。「オスロ・マニュアル」は、1992年に初版が公表され、その後、1997年、2005年にそれぞれ改訂版が公表され、2018年10月に公表された第4版が最新の「オスロ・マニュアル2018」である。
「オスロ・マニュアル」第3版でのイノベーション実現企業とは、「自社にとって新しいものを導入すること」、「他社が導入していても、自社にとって新しければ良い」ことを前提にし、4類型のイノベーション(①プロダクト、②プロセス、③組織、④マーケティング)を導入した企業を指した。
「オスロ・マニュアル2018」では、一般的な「イノベーション」の定義がされている(8) とともに、企業部門におけるイノベーションを実現するための“プロセス”としての「イノベーション活動」が、「企業によって着手された、当該企業にとってのイノベーションに帰着することが意図されている、あらゆる開発上、財務上及び商業上の活動を含む」と定義されている。企業におけるイノベーション活動、すなわち「ビジネス・イノベーション活動」について、その構成要素を図表5-4-1に示した。なお、第3版での4類型のイノベーションのうち②、③、④の3類型が、第4版の「ビジネス・プロセス・イノベーション」とおおむね対応するものとなっている。
この項では、プロダクト・イノベーションに着目し、主要国における企業部門のイノベーション実現状況を紹介する。なお、ここでの「単位」は「企業」である(従業者数等で考える企業規模にかかわらず、1社は1単位である)ことから、企業数の多い相対的に規模が小さい企業の状況が反映されるとともに、プロダクト・イノベーション実現が、市場に導入された新たな1つの製品に対応しているわけではないことに留意する必要がある。
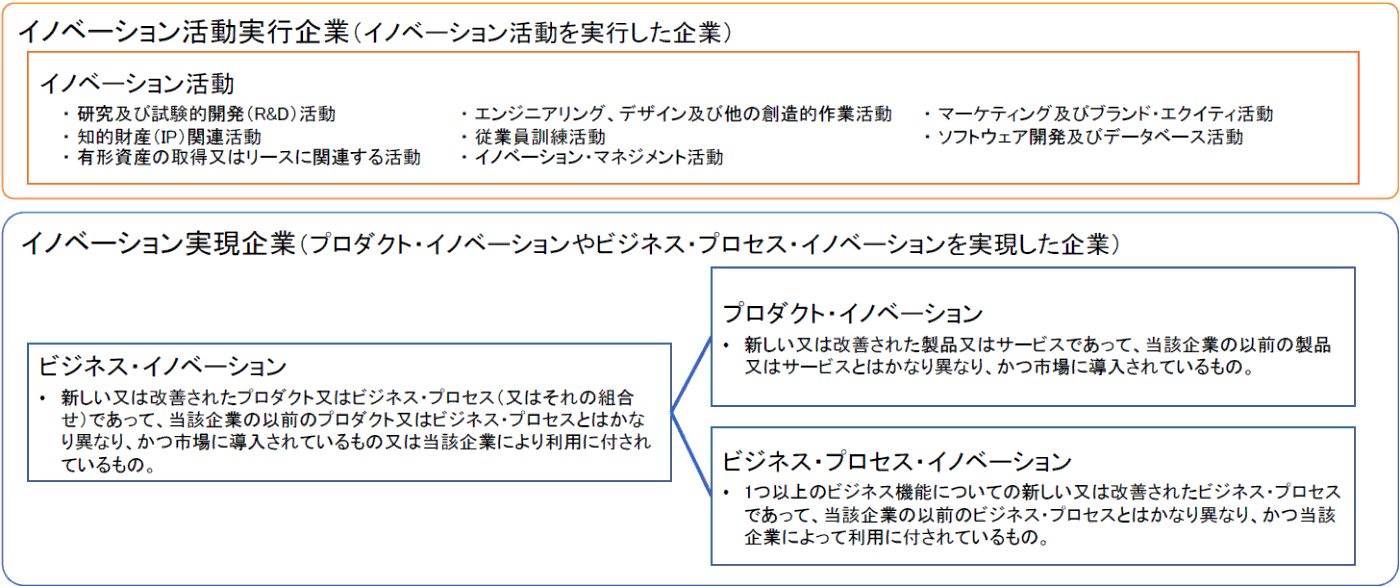
資料:
文部科学省科学技術・学術政策研究所、「全国イノベーション調査2018年調査統計報告」及び「STI Horizon 2019 Vol.5 No.1」
(1)プロダクト・イノベーション実現企業割合
研究開発は、イノベーションの実現と関連している可能性が高い活動である。しかし、企業によっては研究開発活動を実行しない戦略を取る企業もあるだろうし、また、研究開発活動を実行している企業でもイノベーションを実現しているとは限らない。そこで、研究開発活動の実行の有無別にプロダクト・イノベーションを実現した企業の割合を見ると(図表5-4-2(A))、全ての国において、研究開発活動を実行した企業の方が、プロダクト・イノベーション実現企業割合が高い。最も高い国はフランスであり67.4%、次いでドイツ63.1%、英国48.8%、韓国39.0%、日本36.1%となっている。なお、本データの出典はOECDのInnovation Indicators 2023であり、「オスロ・マニュアル2018」に準拠した調査に基づく結果が掲載されている。
研究開発活動を実行しなくとも、プロダクト・イノベーションを実現した企業もある。ドイツは、研究開発活動を実行しなかった企業のうち、22.6%がプロダクト・イノベーションを実現しており、他国と比較すると高い数値である。最も低い国は韓国であり、0.3%と研究開発活動を実行しなかった企業は、ほぼプロダクト・イノベーションを実現しなかったことがわかる。
なお、当該国の企業部門において、研究開発活動を実行した企業の割合を見積もると、英国が32.6%と最も高い。次いで、ドイツが31.9%、フランス31.0%、韓国29.2%、日本13.0%である。欧米で国全体としてのプロダクト・イノベーション実現企業の割合が高いのは、このように企業の研究開発活動の実行割合が高いことも要因の一つと考えられる。

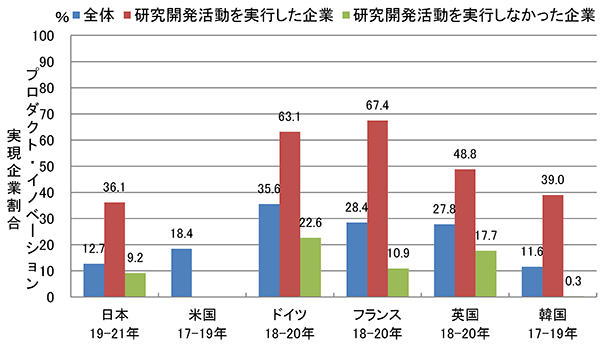

注:
1) CIS(欧州共同体イノベーション調査)が指定した中核対象産業のみを対象としている。
2) (B)研究開発を実行した企業の割合は推計値である。
3) 米国は研究開発を実行した企業及びしなかった企業の数値は掲載されていなかった。
4) 韓国は「製造業」は2017-2019年、「サービス業」は2018-2020年を参照。
資料:
OECD, “Innovation indicators 2023”
参照:表5-4-2
次に、各国のプロダクト・イノベーション実現企業割合を1として、企業規模別、製造業、コアサービス業、その他の非製造業の状況を見る。
企業規模別に見ると、全ての国で大規模企業における数値が高い傾向にある。このことは中小規模企業より大規模企業において、より多くの割合の企業でプロダクト・イノベーションを実現していることを示している。日本は他国と比べて中小規模企業と大規模企業におけるプロダクト・イノベーション実現企業割合の差が比較的大きいことがわかる。大規模企業と中小規模企業における数値の差が少ないのは、英国、米国である。
製造業では日本、米国、ドイツ、フランスが1.0であり、英国、韓国は1.2である。コアサービス業では、日本、米国、ドイツ、フランスが1.0であり、英国0.9、韓国では0.8である。また、その他の非製造業では、いずれの国でも1を下回っている。最も高いのはフランス、最も低いのは米国である。
多くの国で、その他の非製造業においてプロダクト・イノベーション実現企業の割合は相対的に少ないことを示している。
(プロダクト・イノベーション実現企業割合を1とした企業規模別、産業別)
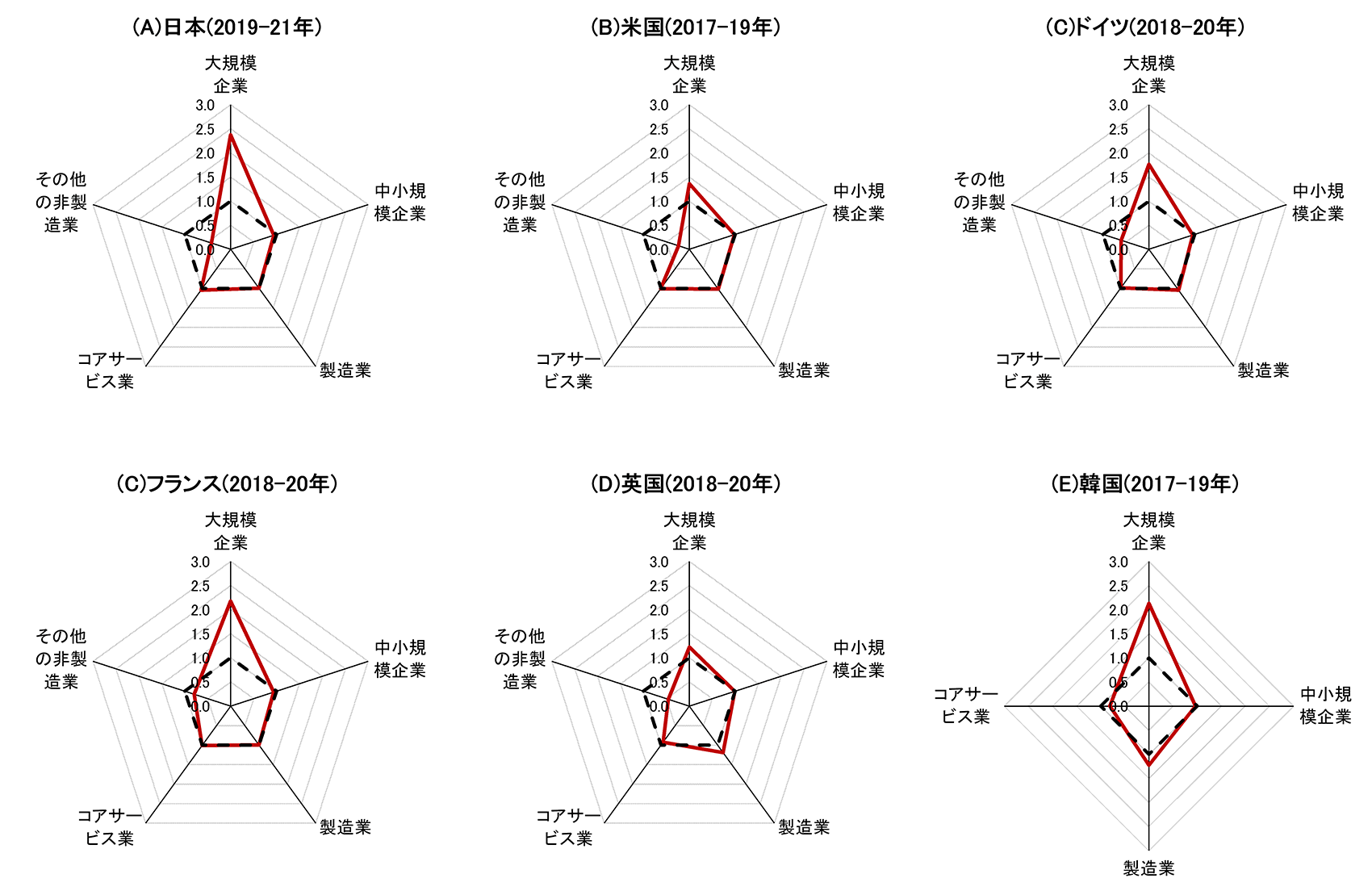
注:
1) CIS(欧州共同体イノベーション調査)が指定した中核対象産業(ISIC Rev.4/NACE Rev.2)のみを対象としている。
2) コアサービス業には、国際標準産業分類第4次改訂版(ISIC Rev.4)/北米産業分類第2次改訂版(NACE Rev.2) Section and Divisions G46(卸売業(自動車及びオートバイを除く。))、H(運輸・保管業)、J(情報通信業)、K(金融・保険業)、M71-72-73(建築・エンジニアリング業及び技術試験・分析業-科学研究・開発業-広告・市場調査業)が含まれる。
3) 韓国は「製造業」は2017-2019年、「コアサービス業」は2018-2020年を参照。「その他の非製造業」の値は記載されていなかった。
資料:
OECD,“Innovation indicators 2023”
参照:表5-4-3
(2)市場にとって新しいプロダクト・イノベーション実現企業割合
前述したように、プロダクト・イノベーションには「自社にとって新しいもの」も含まれている。ここでは、プロダクト・イノベーションの新規性の程度をより詳しく見るために、「市場にとって新しい」プロダクト・イノベーションの実現企業割合を見ることとし、図表5-4-4にその状況を示した。
日本のプロダクト・イノベーション実現企業のうち、市場にとって新しいプロダクト・イノベーションを実現した企業の割合は37.4%である。主要国中最も高いのはフランス66.8%、英国は54.6%であり、半数を超えている。ドイツは25.0%であり、韓国は24.3%と他国と比較すると低い数値となっている。
このように、プロダクト・イノベーションの実現といっても、市場にとって新しいものか、自社にとって新しいものかの傾向は、国によって異なることがわかる。
プロダクト・イノベーション実現企業の割合

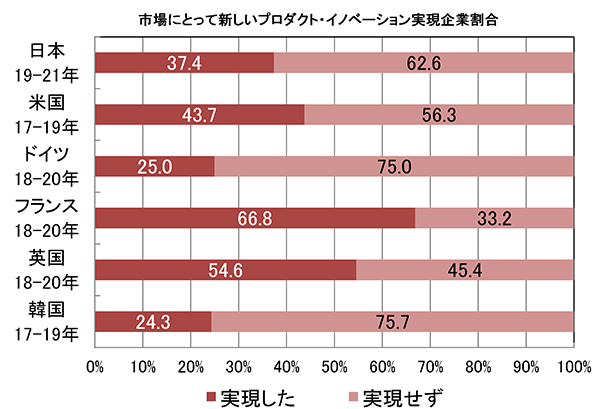
注:
プロダクト・イノベーション実現企業を対象としている。その他の注は図表5-4-2と同じ。
資料:
OECD,“Innovation indicators 2023”
参照:表5-4-4
(8) 新しい又は改善されたプロダクト又はプロセス(又はそれの組合せ)であって、
当該単位の以前のプロダクト又はプロセスとかなり異なり、かつ潜在的利用者に対して利用可能とされているもの(プロダクト)
又は当該単位により利用に付されているもの(プロセス)である。


