ポイント
- 主要国への商標出願数は、居住者からの出願が多くを占める。非居住者からの出願については多くの国で1~2割程度であるが、米国や英国については4~5割を占める。
- 国境を越えた商標出願数と特許出願数(三極パテントファミリー数:日米欧に出願された同一内容の特許)について、人口100万人当たりの値で比較すると、最新年で商標出願数よりも特許出願数が多い国は、日本のみである。最新年で商標出願数が特許出願数より多い国は、英国、韓国、米国、ドイツ、フランスである。韓国、英国、ドイツについては2002~2021年にかけて、商標の出願数を大きく増加させた。
- 日本は技術に強みを持つが、国全体で見ると、それらの新製品や新たなサービスの導入という形での国際展開が他の主要国と比べて少ない可能性がある。
5.3.1世界における商標出願
企業が市場に新製品や新サービスを出す場合、市場の中で差別化を行うことを目的として商標が出願される。商標の出願数は、新製品や新サービスの導入という形でのイノベーションの具現化、あるいはそれらのマーケティング活動と関係があり、その意味で、イノベーションと市場の関係を反映したデータであると考えられる。
ここでは、WIPO(世界知的所有権機関),“WIPO statistics database”を用いて、世界における商標出願の状況を見る。商標出願数は、商品およびサービスの国際分類であるニース国際分類(5) で区分されたクラス数(6) を計測している(図表5-3-3は除く)。具体的には一つの出願がふたつのクラスになされていた場合、2件とカウントしている。
(1)世界での商標出願状況
図表5-3-1は、世界における商標出願数を、「出願人が居住している国・地域へ出願した商標数」と「出願人が居住していない国・地域へ出願した商標数」に分類し、示したものである。2022年における世界の商標出願数は1,554万件である。内訳を見ると、居住者からの商標出願数が1,298万件、非居住者からの出願は257万件である。2004年から2009年にかけては緩やかな伸びであったが、2009年から2014年にかけて伸びが加速し、その後は更に大きく伸びていたが、2022年では、居住者、非居住者ともに大きく減少した。全体での対前年度比は14.5%減であり、商標出願が減少したのは2009年以来である。
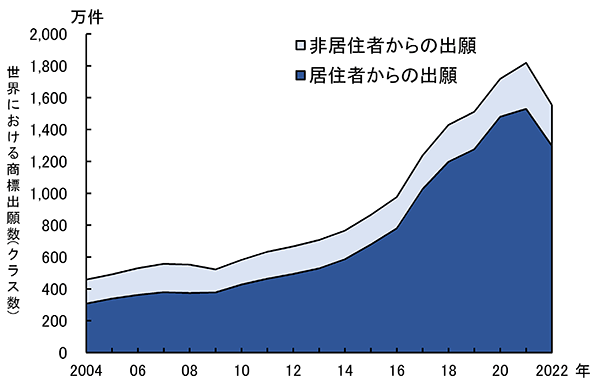
注:
1) マドリッド制度を利用した国際登録の出願(国際出願)と直接出願である。
2) クラス数を計測している。Absolute countである。
資料:
WIPO,“WIPO statistics database”(Last updated: December 2023)
参照:表5-3-1
(2)主要国の商標出願状況
この項では日本、米国、ドイツ、フランス、英国、中国、韓国への商標出願数と主要国からの商標出願状況を見た。図表5-3-2(A)では、主要国への商標出願数を居住者と非居住者からの出願に分類した。日本とフランスについては、出典となるWIPOのデータで居住者と非居住者の内訳が、利用可能な2013年以降について値を示している。
日本への出願数は、中国、米国、英国に次ぐ規模である。2022年では34万件であり、居住者からの出願が多く全体の約8割を占める。推移を見ると、2019年をピークに大きく減少しているが、2021年から2022年にかけての減少は他国と比較すると小さい。居住者からの出願の対前年比率は3%減であり、非居住者からの出願の対前年比率は13%減である。
米国への出願数は2009年に落ち込んだ後は順調に増加したが、2022年では減少し、77万件となった。非居住者からの出願数は全体の約4割を占めており、2022年では27万件と主要国中最も多い。ただし、非居住者からの出願の対前年比は21%減、居住者からの出願は対前年比10%減である。
ドイツへの出願数は、2007年をピークに減少し、その後2012年を境に増加していたが、2022年では減少し23万件となった。居住者からの出願数が多く、全体の9割を占める。対前年比は、居住者からの出願は15%減、非居住者からの出願は10%減である。
フランスは居住者からの出願が多く、全体の9割以上を占める。2022年の出願数は28万件であり、2021年と比較すると居住者からの出願は11%減、非居住者からの出願は14%減である。
英国への出願数は2021年に増加し(7) 、特に非居住者からの出願を伸ばしたが、2022年の出願数は減少し35万件となった。非居住者からの出願数は全体の半数を占めているが、対前年比は26%減と主要国中最も減少した。居住者からの出願は対前年比17%減である。
韓国への出願数は長期的に見て増加傾向にあったが、2022年では減少し、32万件となった。居住者からの出願が多く、全体の約8割を占めるが、2022年の対前年比は10%減である。
中国への出願数は、主要国中トップの規模であるが、2022年では減少し751万件となった。対前年比は21%減である。中国については、居住者、非居住者の出願数が共に約20%減少した。居住者からの出願数が多く、全体の97%を占めている。非居住者からの出願数の割合は3%であるがその数は主要国と比較しても多く21万件である。
図表5-3-2(B)では、主要国からの商標出願数を居住国への出願、非居住国への出願に分類した。日本とフランスの居住国への出願数のデータは2013年以降の値を示している。
日本は非居住国より居住国への出願数が多く、非居住国への出願数は少ないが、非居住国への出願数は長期的には増加傾向にある。最新年の2022年では12万件である。
米国は、居住国への出願と非居住国への出願数の規模の差異が少ない。非居住国への出願数は増加傾向にある。2021年に大きく伸びた後、2022年では減少し45万件となった。主要国中トップの規模である。
ドイツでは非居住国への出願数が居住国への出願数より多い。非居住国への出願数は2022年で27万件であり、米国、中国に次ぐ規模である。
フランスは2004年時点では非居住国への出願数がドイツ、米国に次いで多かった。その後の伸びは緩やかであり、2022年では15万件となった。
英国では非居住国への出願数は長期的に増加傾向にある。2019年で大きく伸びた後は20万件前後で推移しており、2022年では19万件となった。
韓国では、非居住国への出願数は居住国への出願数より少ないが、長期的には増加傾向にある。2022年では7万件である。
中国では、非居住国への出願数は増加傾向が続いていたが、2022年では大きく減少し、37万件となった。対前年比は27%減である。
(A)主要国への出願数
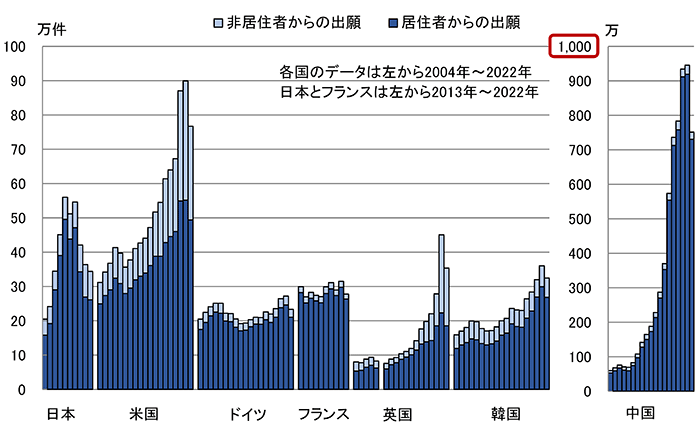
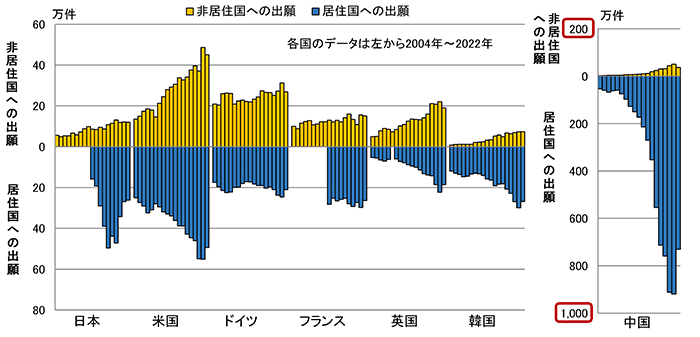
注:
1) 出願数の内訳は、日本を例に取ると、以下に対応している。
「居住者からの出願」:日本に居住する出願人が日本特許庁に出願したもの。
「非居住者からの出願」:日本以外に居住(例えば米国)する出願人が日本特許庁に出願したもの。
「居住国への出願」:日本に居住する出願人が日本特許庁に出願したもの。
「非居住国への直接出願」:日本に居住する出願人が日本以外(例えば米国特許商標庁)に出願したもの。
2) マドリッド制度を利用した国際登録の出願(国際出願)と直接出願である。
3) クラス数を計測している。Absolute countである。
4) (A)主要国への出願数については、日本、フランスの2004年~2012年、英国の2009年は示していない。
5) (B)主要国からの出願数については、日本、フランスの2004年~2012年、英国の2009年の居住国への出願は示していない。
資料:
WIPO,“WIPO statistics database”(December 2023)
参照:表5-3-2
5.3.2国境を越えた商標出願と特許出願
図表5-3-3は主要国の国境を越えた商標の出願数と特許出願数の推移である。商標、特許の値とも各国の人口で規格化されている。
これまで見てきたように、商標を出願する際には自国への出願が多くなる傾向があり、また、国の規模や制度の違いにより出願数に差異がある。そこで、日、独、仏、英、韓については、米国特許商標庁へ、米国については日本と欧州へ出願した商標の数を補正した値(図表5-3-3の注:1参照のこと)を使用し、国境を越えた商標出願とした。
国境を越えた特許出願は、三極パテントファミリーを使用した。特許も自国への出願の有利さがあり、また、地理的位置の影響のためにバイアスがかかる事があるため、それらの影響を受けにくい三極パテントファミリー数を使用している。
主要国の状況を見ると、最新年で商標出願数よりも特許出願数が多い国は、日本のみである。商標出願数の方が特許出願数より多い国は、英国、韓国、米国、ドイツ、フランスである。
2002年から2021年の推移を見ると、日本は、商標出願数は微増、特許出願数は微減である。ただし、特許出願数が顕著に大きい状況に変化はない。
米国、ドイツ、フランス、英国は、商標出願数は増加、特許出願数は減少している。なお、商標出願数が最も大きいのは英国である。韓国については、商標出願数が大きく増加し、特許出願数も増加している。
以上の事から、日本は技術に強みを持っているが、新製品や新たなサービスの導入などといった活動の国際的な展開に課題があり、この状況に大きな変化は見られないと考えられる。
英国は他国と比べて新製品や新たなサービスの導入などといった活動に特に重みを持っており、国際的な展開も進展していると考えられる。
ドイツは、特許出願に見る技術の強みは相対的に弱まっているが、新製品や新たなサービスの導入などといった活動において国際的な展開が進んでいると考えられる。韓国については、技術の強みは維持しつつ、国境を越えた商標出願が増えている。
本指標については、製造業に強みを持つ国では、商標よりも特許の出願数が多くなり、サービス業の比重が多い国では、商標出願数が多くなる傾向が過去には見られていた。しかし、2002年と比べると、韓国、ドイツは商標を大きく伸ばしていることから、製品を用いたサービスの国際展開をはかっている可能性がある。
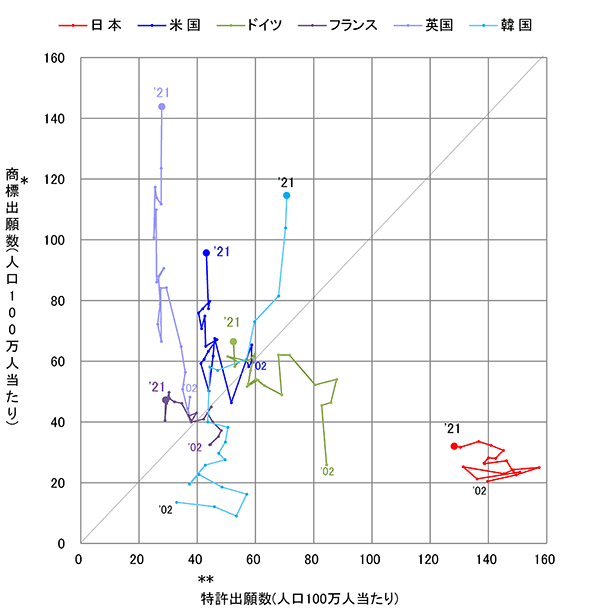
注:
1) *国境を越えた商標数(Cross-border trademarks)の定義はOECD,“Measuring Innovation: A New Perspective”に従った。具体的な定義は以下のとおり。日本、ドイツ、フランス、英国、韓国の商標数については米国特許商標庁(USPTO)に出願した数。
米国の商標数については①と②の平均値。
①欧州連合知的財産庁(EUIPO)に対する日本と米国の出願比率を基に補正を加えた米国の出願数=(米国がEUIPOに出願した数/日本がEUIPOに出願した数)×日本がUSPTOに出願した数。
②日本特許庁(JPO)に対する欧州と米国の出願比率を基に補正を加えた米国の出願数=(米国がJPOに出願した数/EU14と英国がJPOに出願した数)×EU14と英国がUSPTOに出願した数。
2) **国境を越えた特許出願数とは三極パテントファミリー(日米欧に出願された同一内容の特許)数(Triadic patent families)を指す。
資料:
商標出願数:WIPO, “WIPO statistics database”(Last updated: December 2023)
三極パテントファミリー数及び人口:OECD,“Main Science and Technology Indicators March 2024”
参照:表5-3-3
次に、米国へ出願された商標は、どのような産業に関連しているのかを見るために、産業分類にニース国際分類のクラス番号を対応させ、産業分類ごとの商標数のバランスと特化係数を見た(図表5-3-4)。
多くの国で「科学研究、情報通信技術」の産業に関連する商標出願の割合が最も大きい。ドイツ、フランス、韓国の場合、二番目に大きい割合の産業は「医薬品、保健、化粧品」である。日本、米国、英国については「レジャー、教育、トレーニング」に関連する産業の割合が大きい。なお、中国の商標出願については、「家庭用機器」に関連する産業の割合が最も大きく、次いで「テキスタイル-衣類とアクセサリー」となっており、他国とは異なる傾向を見せている。
特化係数をみると、各国において最も特化しているのは、日本、ドイツ、フランスは「化学品」、英国は「科学研究、情報通信技術」、中国は「家庭用機器」、韓国では「医薬品、保健、化粧品」である。米国は「管理、通信、不動産、金融サービス」が最も特化している。
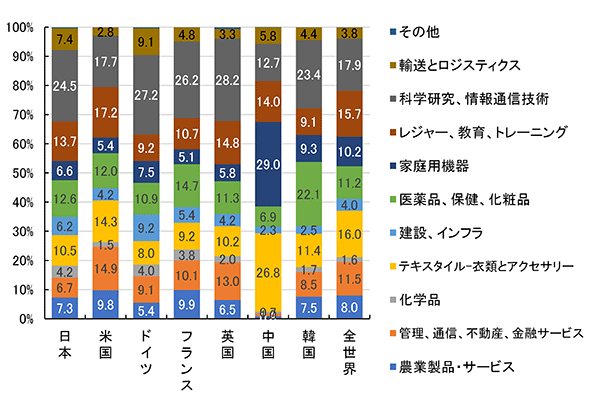
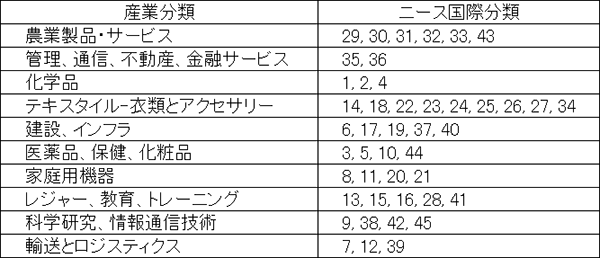
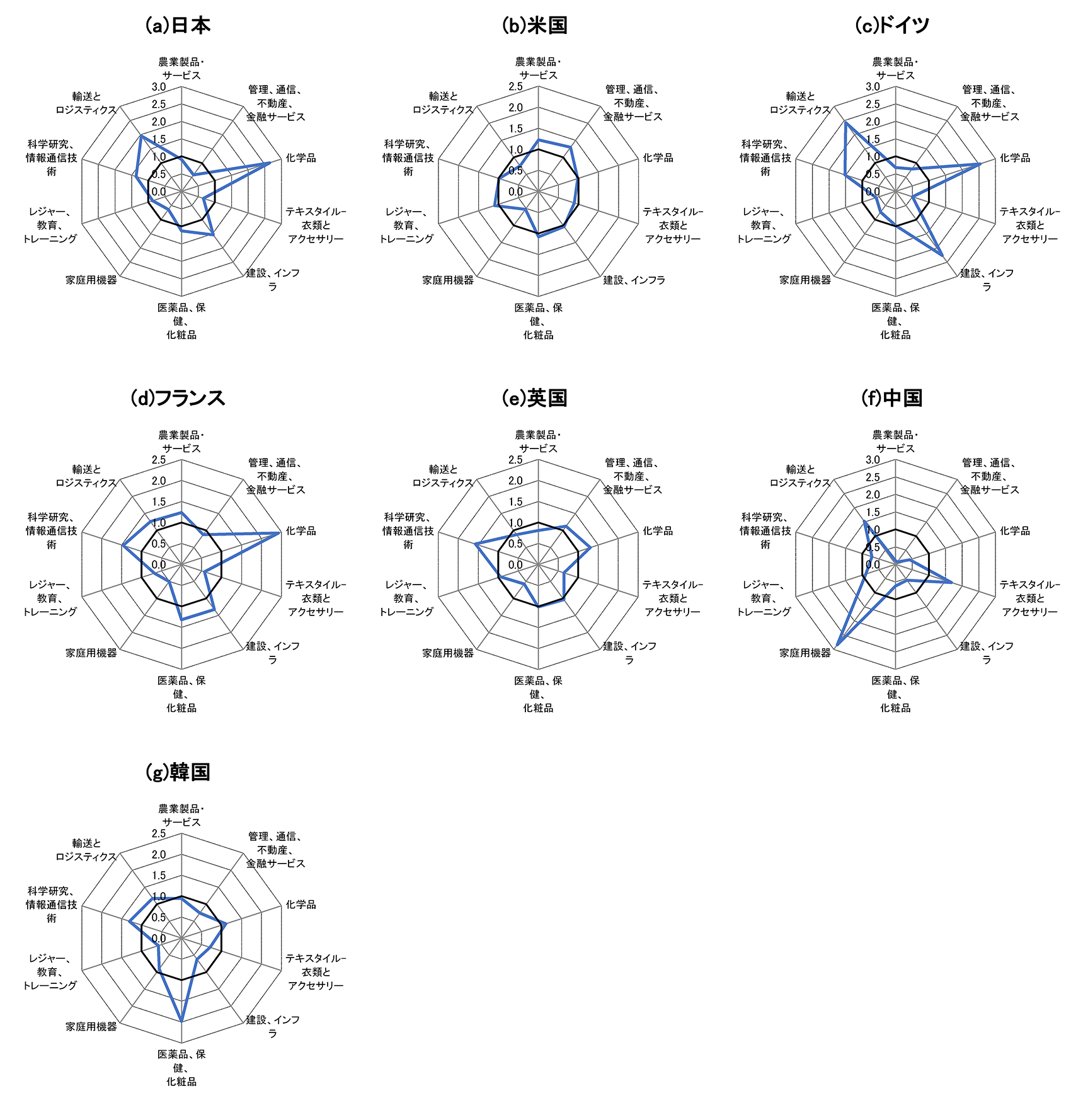
注:
1) 2020-2022年の合計値での割合である。
2) ニース国際分類と産業分類の対応表はWIPO, “World Intellectual Property Indicators 2020”の“Annex B. Composition of industry sectors by Nice goods and services classes”を参照した。日本語訳は科学技術・学術政策研究所が仮訳した。
3) マドリッド制度を利用した国際登録の出願(国際出願)と直接出願である。
4) クラス数を計測している。Absolute countである。
5) 特化係数=各国の産業分類の構成比/全世界の産業分類の構成比
資料:
WIPO,“WIPO statistics database”(December 2023)
参照:表5-3-4
(5)「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に基づく、国際的に共通の商標登録のための分類(https://www.wipo.int/classifications/nice)。
(6) ニース国際分類に基づくもので、指定商品・役務を分野別に大きく区切られている。第1類から第45類まであり、出願人が出願時に指定する。全ての商標がいずれかの区分に属している。


