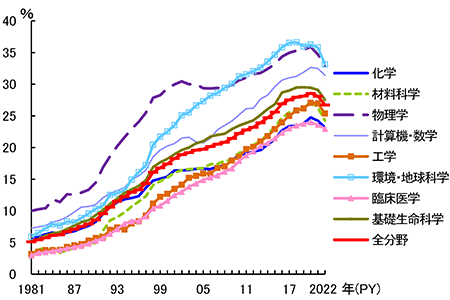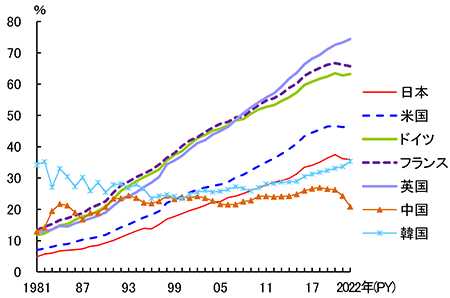3.研究開発のアウトプットの状況
(1) 日本の論文数(分数カウント法)は世界第5位、注目度の高い論文を見るとTop10%・Top1%補正論文数で第13位・第12位である。中国は全ての論文種別で世界第1位である。
論文の生産への貢献度を見る分数カウント法では、日本の論文数(2020-2022年の平均)は、中、米、印、独に次ぐ第5位である。注目度の高い論文を見るとTop10%補正論文数で第13位、Top1%補正論文数は第12位である。中国は論文数、Top10%、Top1%補正論文数において世界第1位である。
(自然科学系、分数カウント法)
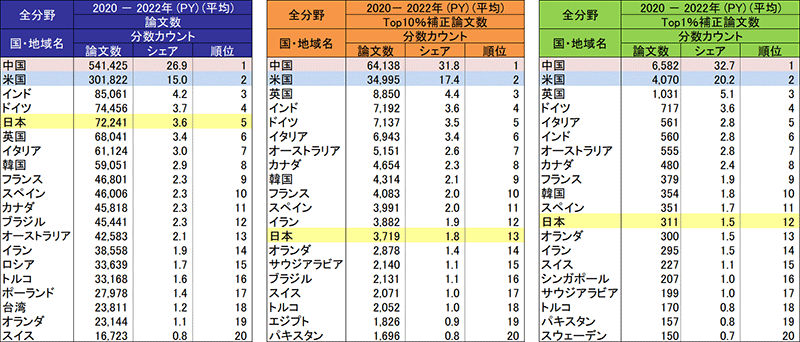
(2)過去20年で論文の被引用数構造が変化し、中国やグローバルサウスの存在感が増してきている。
2020-2022年のTop10%補正論文で上位25に入る国・地域の被引用数構造において、自国・地域からの被引用数割合は中国が最も大きく、その割合は2000-2002年の40%から2020-2022年の62%に上昇している。後半の期間では米国、インド、イラン、エジプトにおいて自国・地域からの被引用数割合が比較的大きい傾向にある。2020-2022年において、イラン、エジプト、パキスタン、サウジアラビアは、「自国・地域+中国+グローバルサウス」からのTop10%補正論文における被引用数割合が約7割を占めている。
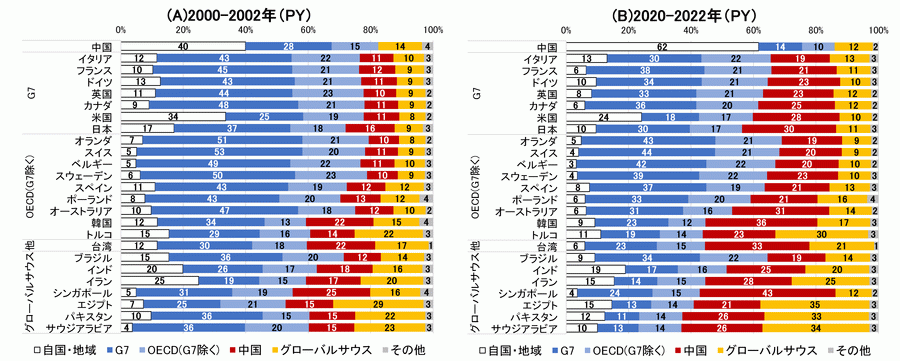
注:
1)Article, Reviewを分析対象とし、各国・地域の論文を引用している論文を国・地域別に分数カウント法により分析。年の集計は出版年(Publication year, PY)を用いた。Top10%補正論文数(分数カウント法、2020-2022年平均)で上位25か国・地域のTop10%補正論文の被引用数構造を分析した。各国・地域の自国・地域からの被引用数は、自国・地域に計上し、他の該当する区分から除いている。
2)グローバルサウスの国・地域は、グローバルサウスの声サミット2023参加国(https://mea.gov.in/voice-of-global-summit.htm)及び国連における途上国の協力グループ(G77現加盟国, http://www.fc-ssc.org/en/partnership_program/south_south_countries)を参照した。
参照:科学技術指標2024コラム図表5-2
(3)科学知識の産出及び知識の交換において、過去20年で、G7やOECD諸国に加えて、中国やグローバルサウス諸国の存在感が増し、注目度の高い論文の意味が変化している。
被引用数構造から、各国・地域のポジションを可視化した。ここで、ポジションの値がプラスの場合は、被引用数構造においてG7やOECD諸国からの被引用数割合が大きく、マイナスの場合は中国やグローバルサウス諸国からの被引用数割合が大きいことを意味する。なお、ここでは、概要図表12で示している自国・地域の割合を各国・地域の該当区分に含めて計算した。
2000-2002年では、G7やOECDの国・地域がTop10%補正論文数で大きな規模を持ち、被引用数構造のポジションもプラスに位置している。つまり、科学知識の産出及び知識の交換においてG7やOECD諸国が主要な役割を果たしていた。
2020-2022年になると、中国やグローバルサウスの国・地域の規模が大きくなるとともに、それらの国・地域については、被引用数構造のポジションがマイナスに位置している。また、G7やOECDの国・地域についてもマイナス方向にポジションが移動している。これらの結果は、科学知識の産出及び知識の交換において、過去20年で、G7やOECD諸国に加えて、中国やグローバルサウス諸国の存在感が増し、注目度の高い論文の意味が変化していることを示唆している。
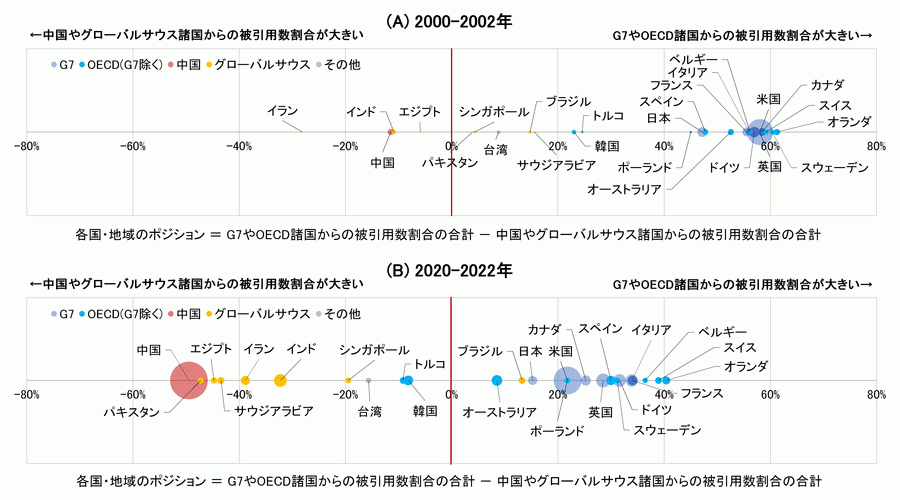
注:
1)Top10%補正論文数(分数カウント法、2020-2022年平均)で上位25か国・地域のTop10%補正論文の被引用数構造を分析した。
2)各国・地域の被引用数構造のポジションは、各国・地域ごとに、G7やOECD諸国からの被引用数割合の合計から中国やグローバルサウス諸国からの被引用数割合の合計を引いた値を集計した。ここでは、概要図表12で示している自国・地域の割合を各国・地域の該当区分に含めて計算した。
3)図表中の円の面積は、各国・地域の当該期間におけるTop10%補正論文数を示す。
参照:科学技術指標2024コラム図表5-3
(4) Top10%補正論文数の世界ランクは、どこの国・地域からの被引用数(注目度)を見るかによって、結果に違いが生じる。
米国からの被引用数を用いてTop10%補正論文数を試行的に集計した結果を見ると、2020-2022年の日本の世界ランクは第9位で、概要図表11で示す第13位よりも世界ランクが高い。他方、インド、イランなどの国・地域の世界ランクは、同図表で示す順位より大きく低下し、サウジアラビア、エジプト、パキスタンは上位20位の圏外であった。
このことは概要図表12及び13とも関連するが、これらの国・地域の論文を引用する国・地域は、米国以外が中心であることに起因している。このようにTop10%補正論文数の世界ランクは、どこの国・地域からの被引用数(注目度)を見るかによって、結果に違いが生じる。

注:
米国からの被引用数は、各国・地域の論文を引用している論文における米国の論文数を分数カウント法により集計した。米国からの被引用数を用いて、各年各分野(22分野)の上位10%に入る論文数を抽出後、実数で1/10となるように補正を加えた。
参照:科学技術指標2024コラム図表5-4(B)
(5) 国際共著論文割合は上昇基調であったが、2020年頃から、全ての分野で低下している。主要国の中でも中国の低下が大きい。
各分野の2022年時点の割合を見ると、環境・地球科学は33.1%、物理学では32.9%であり、他分野に比べ国際共著論文割合が高い。臨床医学は22.9%であり、国際共著論文割合が一番低い。2020年頃から、全ての分野で国際共著論文割合は低下している。
主要国の状況を見ると、米国とドイツは2020年頃から横ばい、日本とフランスは2020年をピークにやや低下している。中国は2018年を境に低下している。特に2022年は前年から3.4ポイント低下した。