2.高等教育と科学技術人材から見る日本と米国の状況
(1) 日本の大学院博士課程の入学者数は2003年度をピークに、長期的に減少傾向にある。
日本の大学院修士課程の入学者数は2010年度をピークに一時的な増加はあるが減少に転じた。2020年度を境に増加しており、2022年度は対前年度比1.9%増の7.6万人となった。また、社会人修士課程入学者数は全体の10~11%で推移していたが、2019年度から微減している。
大学院博士課程の入学者数は、2003年度をピークに長期的には減少傾向にあり、2022年度は1.4万人となった。うち社会人博士課程入学者数は増加傾向にあったが、2018年度を境に減少している。2022年度では全体に占める割合は41.7%である。専攻別の構成について見ると、修士・博士課程ともに「その他」の入学者数が長期的に増えている。
(A)専攻別入学者数の推移(修士課程) (B)社会人入学者数の推移(修士課程)
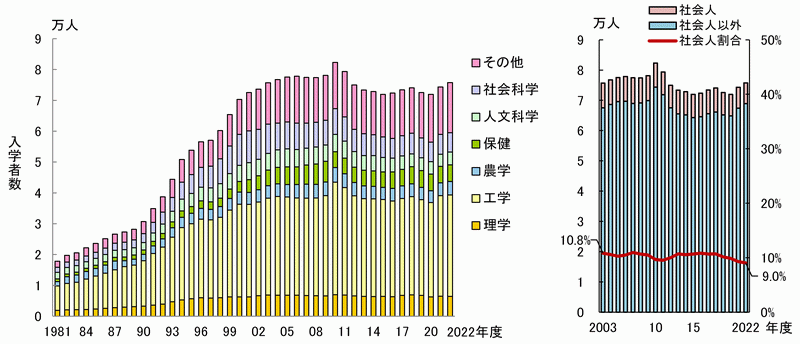
(A)専攻別入学者数の推移(博士課程) (B)社会人入学者数の推移(博士課程)
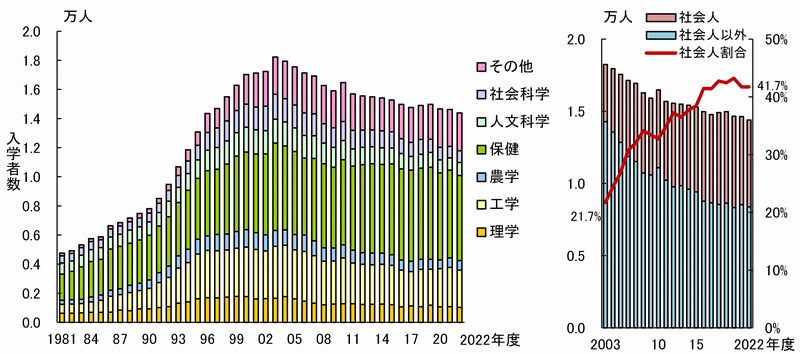
注:
修士及び博士課程の専攻の「その他」は、「教育」、「芸術」、「商船」、「家政」、「その他」である。そのうちの「その他」とは「学校基本調査」の「学科系統分類表」のうちのその他であり、専攻名を構成する単語には「環境」、「人間」、「情報」、「国際」等が多くみられる。
(2) 大学院修士課程修了者の進学率は減少傾向が続いたが2019年度を境に微増しており2022年度は9.9%である。
修士課程修了者の進学率(全分野)を見ると、1981年度では18.7%、その後は長期的に減少傾向にあったが、2019年度を境に微増しており2022年度は9.9%である。分野別に見ると、多くの分野で長期的に減少していたが、2010年度代後半に入ると、横ばいや微増に転じる分野も出てきた。継続して減少傾向にあるのは「社会科学」である。
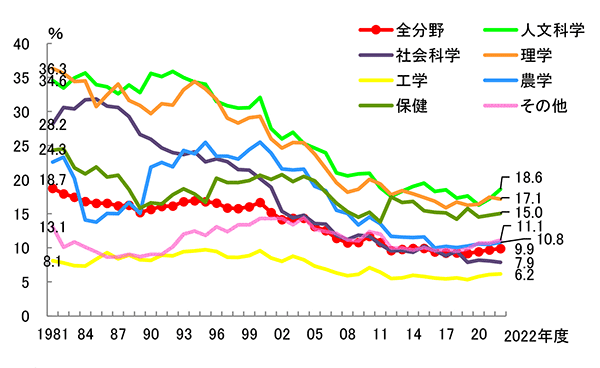
注:
修士課程修了者の進学率とは各年の3月時点の修士課程修了者のうち、大学院等に進学した者の割合。専修学校・外国の学校等へ入学した者は除く。
参照:科学技術指標2022表3-2-4
(3) 米国の企業における博士号保持者数は過去10年で1.4倍になった。「研究活動」を主要業務とする者が多いが、「経営、営業もしくは管理職」や「専門サービス」に従事している者も一定数存在する。
米国の博士号保持者は大学等や企業に同程度の規模で所属している。また、企業の博士号保持者数は過去10年で1.4倍になった。主要業務別で見ると、企業、政府、非営利団体では、「研究活動」を主要業務としている博士号保持者が最も多い。大学等では「教育」が最も多く、これに「研究活動」が続く。企業では「経営、営業もしくは管理職」や「専門サービス」を主要業務としている博士号保持者も多い。
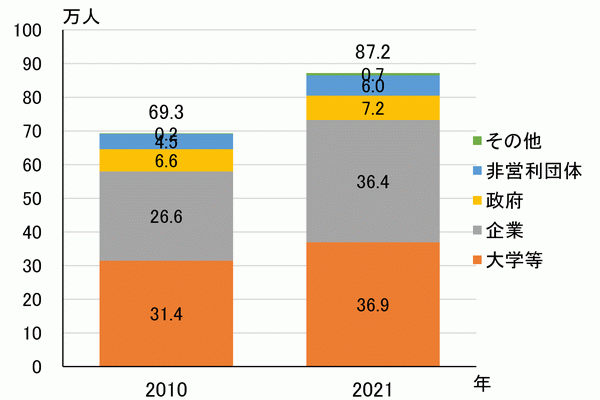
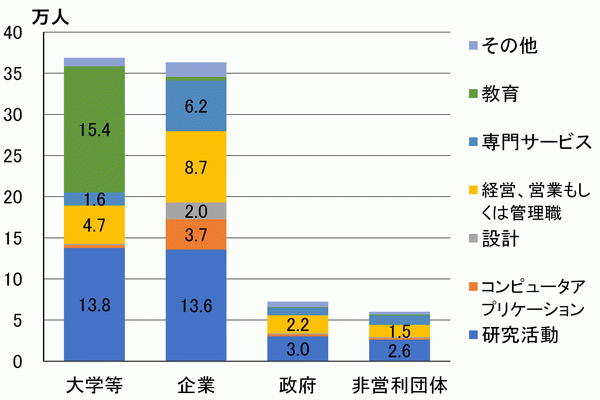
注:
1) 米国の学術機関でScience, Engineering, and Health (SEH) research doctorateを取得し米国在住の博士号保持者のうち就職している者を対象。
2) 主要業務活動(primary work activity)とは典型的な週の労働時間の少なくとも10%を占めている仕事のうち通常週に最も多くの時間を費やしたもの。
3) 研究活動は、基礎研究(主にそれ自体のために科学的知識を得ることを目的とした研究)、応用研究(認識されたニーズを満たすために科学的知識を得ることを目的とした研究)、開発(材料、デバイスの製造のための研究から得られた知識の使用)を対象としている。コンピュータアプリケーションとはコンピュータプログラミング、システムまたはアプリケーション開発である。専門サービスとは、例えば、医療、カウンセリング、金融サービス、法律サービスなどである。

