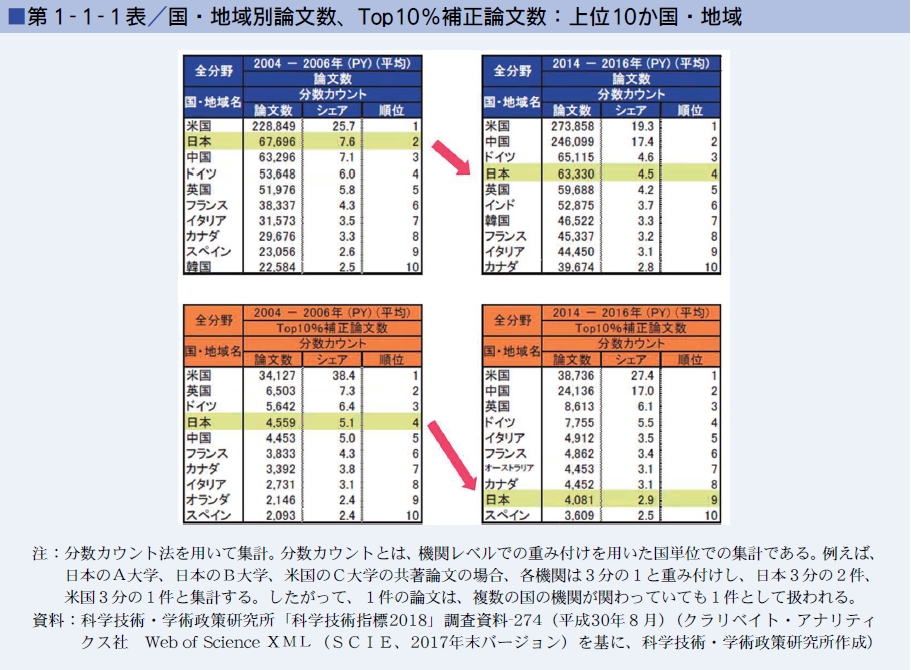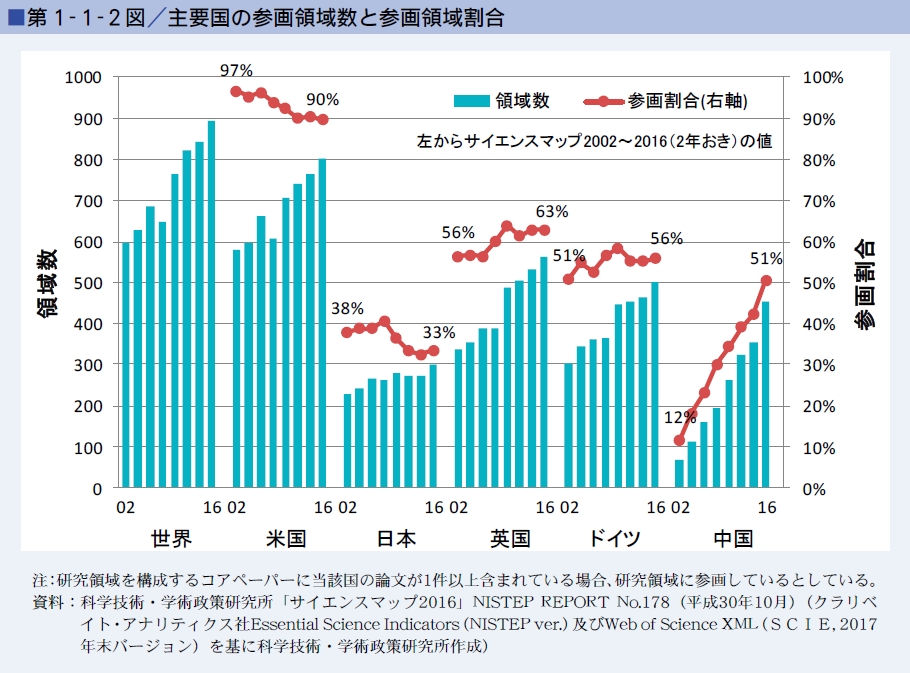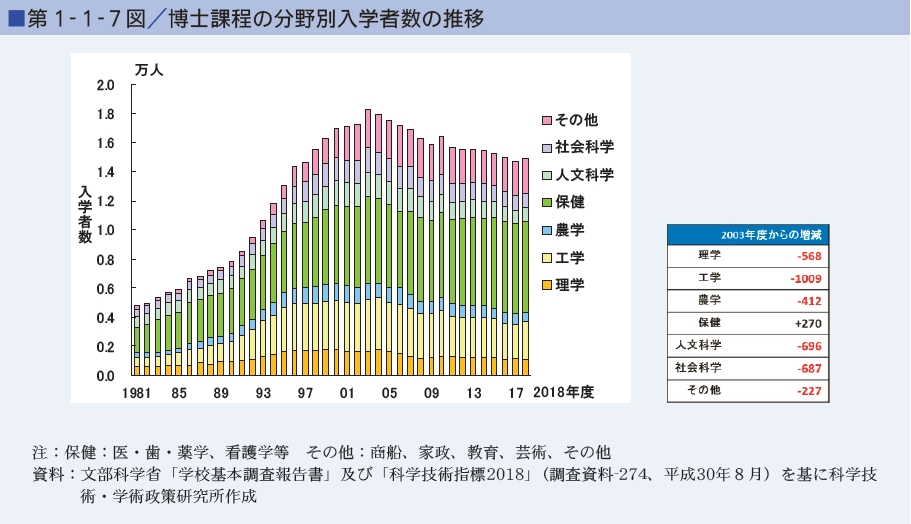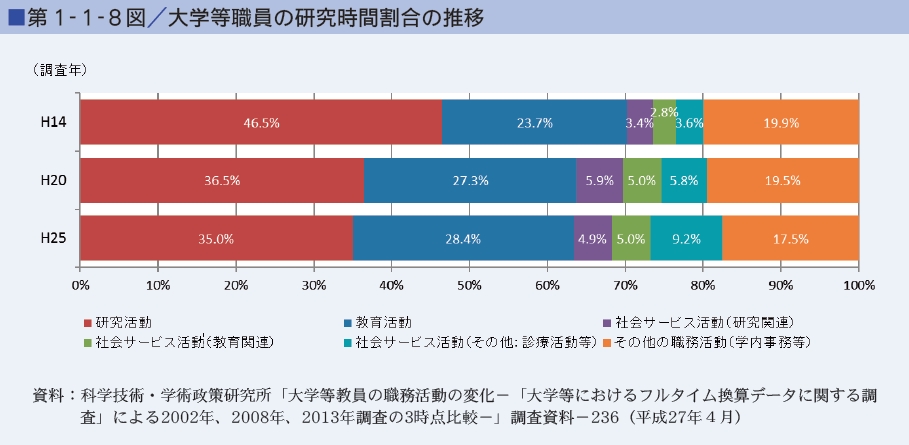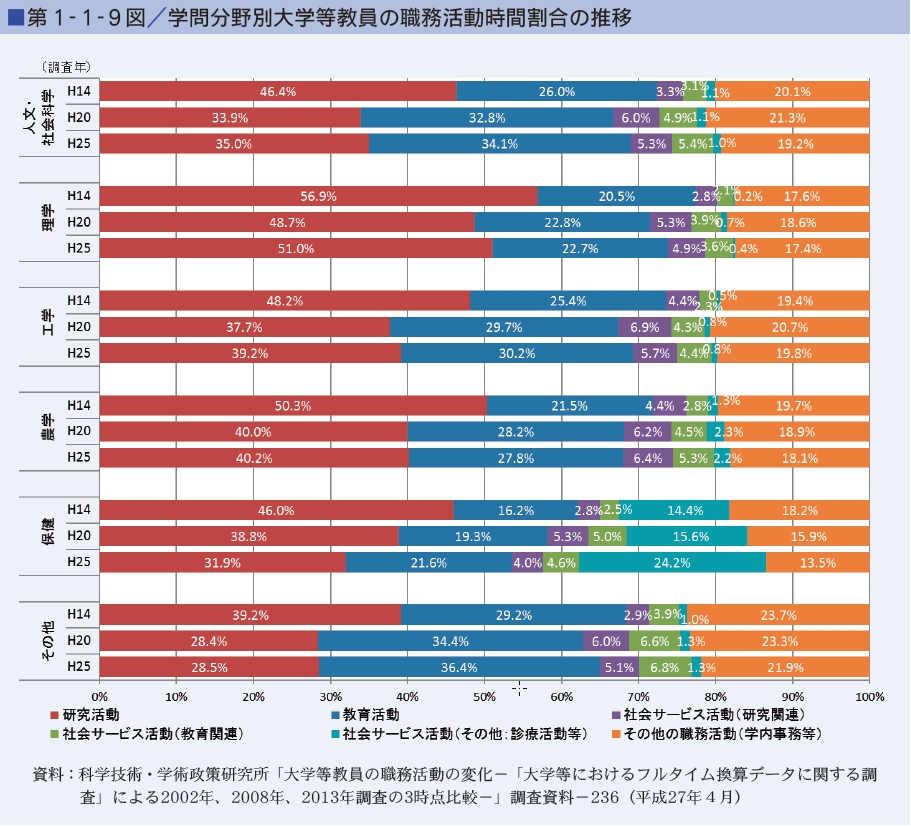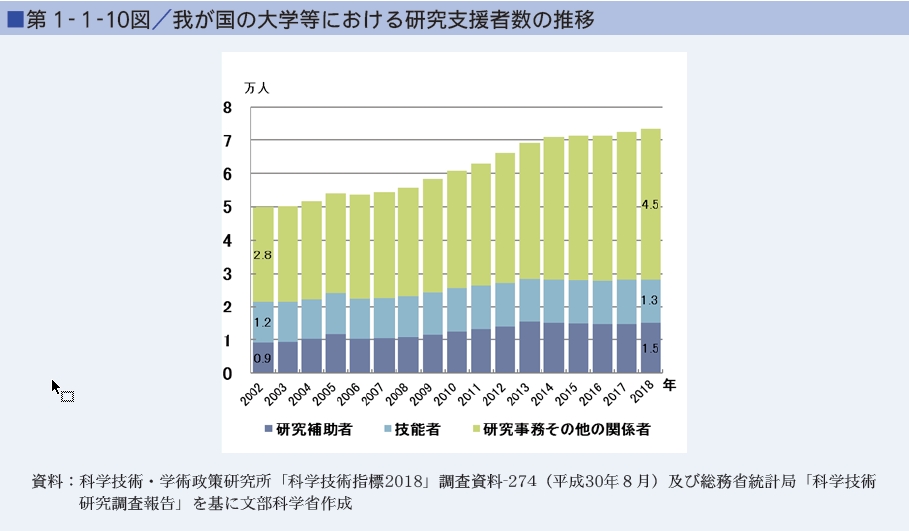科学技術・学術政策研究所(NISTEP)による講演会を、下記のとおり開催いたしますので、御案内申し上げます。皆様、奮って御参加くださいますようお願い申し上げます。参加を希望される方は、以下の参加申込みメールにて御所属・お名前の登録を5月27日(月)17時までにお願いいたします。
概要
○演題:「研究データの利活用を促進するFAIR原則の背景とGoFAIRの実践(仮)」
○講師:Ms. Shelly Stall (AGU, アメリカ地球物理学連合)
○日時:2019年5月29日(水)14:00-16:00(受付開始13:30)冒頭に主旨説明を行います。
○場所:文部科学省 科学技術・学術政策研究所会議室(16B)
(東京都千代田区霞が関3-2-2 中央合同庁舎第7号館東館 16階)
○使用言語:英語
申込締切:5月27日(月)17:00
講演会趣旨
世界で注目を集めているオープンサイエンスは、現状研究データの利活用による科学、社会、及び“科学と社会”の変容を狙っており、政策的なトップダウン、研究者コミュニティの自発的な活動によるボトムアップ双方の取組が行われています。
その一方で、研究データは研究論文とは異なり、そのフォーマットや公開・共有までの作法、及びその利用について幅広い共通性を持っていないため、“研究データの利活用”が何を指すか自体も分野やセクターによって千差万別となっています。このため、一つの現実的な取組として、研究論文に付随するデータや、これまでデータベース等で公開、共有されてきた研究データに関して、効率の良い利活用を目指した活動が活発化しています。実際に、データ公開の適切な実施方法と共有の原則として、Findable, Accessible, Interoperable, Reusableの頭文字を取った「FAIR原則」が、研究者、図書館員、出版関係者などが集まり立ち上がったFORCE11という団体で生まれました。この原則は、政策側、研究者コミュニティ側の活動双方で頻繁にとりあげられ、例えば、欧州サイエンスクラウド(EOSC)はこの原則をデータ共有と管理における基礎として位置づけ、日本でも昨年の6月に公開された研究データリポジトリの整備・運用ガイドラインにも取り上げられています。さらに、この原則の実践を進める「GoFAIRイニシアチブ」が立ち上がり、「FAIR原則」の本格的な実装が始まっています。
このセミナーでは、この課題に対して最前線で活動を行っている講師をお招きし、「FAIR原則」と「GoFAIRイニシアチブ」が生まれた背景について解説とその実践のポイントについて御紹介いただきます。あわせて、オープンサイエンスを実際に進めるための障壁や課題について議論し、今後の日本の政策作りに役立てます。
講師経歴: Ms. Shelly Stall
アメリカ地球物理学連合(AGU)のデータプログラムディレクター。科学データリポジトリや他の組織と協力し、世界中の研究データの管理方法を向上させるという目標を掲げ、データ管理方法の改善に取り組む。大規模データ管理で20年以上の経験があり、規制、相互運用性、データガバナンス、メタデータ管理、マスターデータ管理、及び組織変更管理などの課題について、非営利団体、企業、市民コミュニティを支援した実績を有する。
講演内容についてのお問合せ
科学技術・学術政策研究所 科学技術予測センター (担当:林)
Tel:03-3581-0605
講演会の参加申込み
科学技術・学術政策研究所 科学技術予測センター
E-mail: seminar-stfc-b[at]nistep.go.jp
なお、 お申込みに際しては、お手数ですが上記アドレスの[at] を”@”に変更し、御氏名、御所属を記入の上、御連絡をお願いいたします。