主要国におけるハイテクノロジー産業貿易の相手先国・地域については、科学技術指標2022(2022年8月公表)において分析した。その結果からは、次のようなことが確認された。日本では過去は米国が最も大きな輸出相手であったが、中国及びアジアへの輸出が多くなった。米国、ドイツ、中国については属する大州(アメリカ州、ヨーロッパ州、アジア州)への輸出が一定の規模を保っていた。輸入については、日本、米国、ドイツとも中国からの輸入が多くなり、 中国では日本・米国に代わってアジア(日中韓以外)が最も多くなっていた。本コラムは主に当時から2~3年後の状況を見る。
日本について2021年と2023年を比較すると、輸出入額共に減少した。輸出額では中国、ドイツ及びアジア(日中韓以外)が2割減少した。輸入額ではフランス、ドイツ、欧州(独、仏、英以外)が3~4割減少した。中国も2割減少した。
米国について2021年と2023年を比較すると、輸出額はほとんどの国・地域で増加した。特にフランス、英国、欧州(独、仏、英以外)が4割増加した。輸入額ではアジア(日中韓以外)が3割、英国、欧州(独、仏、英以外)が2割増加した。一方で中国は2割、韓国は3割減少した。なお、対中国の貿易収支比は入超が継続している。最新年では0.2であり、ここに示した相手先国・地域中では最も低い。日本については、1990年に0.4であった収支比が、2023年では0.8となっている。
ドイツについて2021年と2023年を比較すると、輸出額では、米国と北米・中南米(米国以外)が3割増加、中国は1割減少した。輸入額では規模の大きい欧州(独、仏、英以外)、中国が1割減少している一方で、アジア(日中韓以外)、米国、フランスは2~3割増加した。
中国について2021年と2023年を比較すると、輸出額では規模の大きいアジア(日中韓以外)及び米国が2割減少した。輸入額では韓国が3割、アジア(日中韓以外)が2割減少した。なお、中国の貿易収支比は、約20年間で入超から出超に変化した国・地域が多く、米国は0.3(1992年)から3.7(2023年)になった。
韓国について2021年と2023年を比較すると、輸出額では規模の大きいアジア(日中韓以外)が2割、中国が3割減少した。輸入額ではほとんどの国・地域が増加したが、規模の大きい中国が2割減少した。
2021年から2023年において、各国相手先国としての中国の輸出入額が減少しているが、日本、米国のハイテクノロジー産業の輸入額は依然として中国の規模が大きく、入超の度合いも大きい。

資料:
OECD,“Bilateral Trade in Goods by Industry and End-use (BTDIxE)”
参照:コラム表5
コラム6:将来の科学技術と社会の関係性についての専門家の認識と現状
生成AIの急速な発展と社会への浸透が注目を浴びるなど、新興科学技術の正負の影響が議論されている。科学技術と社会の関係性が将来どのように変化していくと専門家は認識しているか又現状はどうか、科学技術・学術政策研究所(NISTEP)が行った調査を基に紹介する。
将来については、第12回科学技術予測調査の結果を用いる。予測調査の一環として行ったデルファイ調査の中で、今後30年間の科学技術と社会の関係性の変化について、研究側と社会側のそれぞれで質問した。調査対象は産官学の専門家であり、6,231名が回答した。
現状については、NISTEPで実施している研究者への意識調査(NISTEP定点調査2024)の結果を用いる。本調査では、研究者は社会との関係性をどのように深めているのかの現状を聞いている。調査対象は研究開発に取り組む研究者であり、1,223名が回答した。
(1)研究側における変化
「今後30年間における科学技術と社会の関係について、研究側の変化としてどのような変化が強くなると考えるか」(コラム図表6-1参照)という質問に対して、「研究活動の様々なプロセスにおいて、積極的に社会とのコミュニケーションを取り入れる(対話)」を選択した回答者が最も多かった(37.4%)。次いで、社会との対応においてより義務的なニュアンスを含む「社会の期待・ニーズに応じた研究を行うことが要請される(服従)」を選択したのは30.6%であった。これとは対照的に、研究者の自律性がより広がる「社会を考慮しながらも、研究者自身の興味関心や、自律性がより重視される(自律)」を選択したのは23.4%であった。研究者の自由を重視する「社会に関係なく、知識生産によりまい進している(無視)」を選択したのは3.8%と少数であった。
年代別の違いに注目すると、「対話」を選択したのは30代以下では32.1%であったが、それ以上の年代層は38%以上であった。「服従」は30代以下の37.2%が選択し、年代が若くなるほどより多く選択された。「自律」及び「無視」は、60代以上では、それ以外の年代よりも多く選択された。
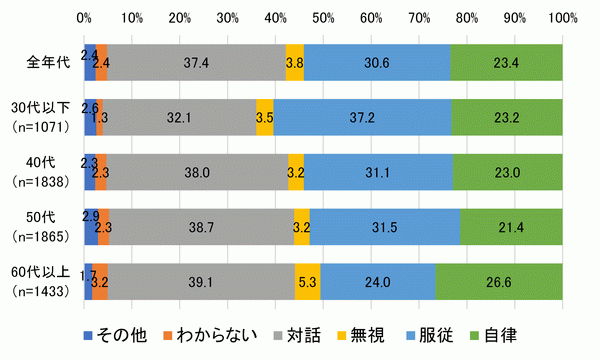
注:
「今後30年間に、科学技術と社会の関係はどう変化するとお考えですか? 研究側の変化として、どのような変化がより強くなると考えるか、お答えください。(自身の専門分野に関して最も近いものを1つ選択)」への回答。
資料:
「第12回科学技術予測調査 科学技術等の中長期的な将来予測に関するアンケート調査(デルファイ調査)」,調査資料-346,文部科学省科学技術・学術政策研究所.
参照:コラム表6-1
(2)社会側における変化
続いて、「今後30年間における科学技術と社会の関係について、社会側の変化としてどのような変化が強くなると考えるか」(コラム図表6-2参照)という質問に対しては、「社会は、科学技術の推進における対話・合意形成を求める(合意)」を選択した回答者が最も多かった(36.9%)。次いで、「社会は、科学技術への関心が低く、その成果をたんたんと受容する(無関心)」が25.1%であった。「社会は、科学技術に対する期待・信頼を高め、その推進を委任している(信頼・委任)」を選択したのは19.7%、「社会は、科学技術の推進への懸念・批判や対立的姿勢を強める(批判・対立)」は11.6%であった。
年代別の違いに注目すると、「合意」を選択した割合は年代が高いほど多く、60代以上(44.0%)と30代以下(27.1%)では大きな差があった。これとは逆の方向性を持ったのが「無関心」であり、年代が低いほどより選択された(30代以下の33.2%、60代以上の17.3%)。「信頼・委任」については年代間で大きな差はなかった。「批判・対立」は30代以下では16.9%であったが、それ以外の年代は10-11%程度であった。
30代以下の回答者で、社会は「無関心」となる、あるいは「批判・対立」を深めると認識する割合が、他の世代よりも大きいことが注目される。
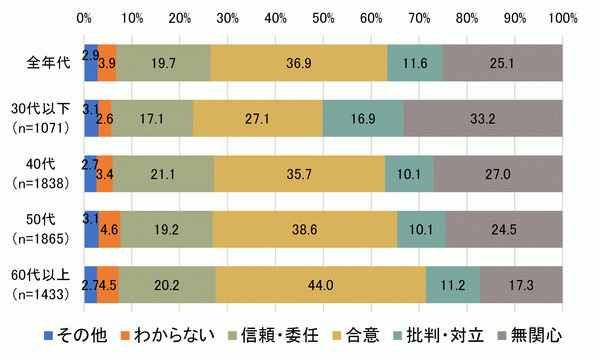
注:
「今後30年間に、科学技術と社会の関係はどう変化するとお考えですか? 社会側の変化として、どのような変化がより強くなると考えるか、お答えください。 (自身の専門分野に関して最も近いものを1つ選択)」への回答。
資料:
コラム図表6-1と同じ
参照:コラム表6-2
(3)全体としての変化の方向性
研究側の変化と社会側の変化の回答を組み合わせると、全体としてどのような変化の方向性が見えるか(コラム図表6-3)。研究側が、「対話」あるいはより義務的に「服従」という形で社会に歩みより、同時に社会側も「合意」を求めるか「無関心」にたんたんと受け入れるとした「研究者側の社会側への歩み寄り」が全体の45.1%と最も多かった。研究者側が歩み寄る状況で、社会から「信頼・委任」されるとしたのは11.1%であったが、逆に社会からの「批判・対立」が高まるとしたのは8.6%であった。
また、研究側が「自律」度を高める又は知識生産へまい進し社会を「無視」するが、社会側が「合意」を求める、あるいは「批判・対立」を強めるとした「研究側と社会側のすれ違い」は10.1%であった。同じ状況で、社会側も科学に「無関心」になるとしたのは7.7%であり、そうであっても社会からは「信頼・委任」されるとしたのは8.3%であった。
(4)現状における研究者の社会との関わり(NISTEP定点調査2024より)
これまで紹介したのは、今後30年後に起こりうる科学と社会の関係性変化の方向性についての専門家の認識に関する調査結果であった。
次に、現状ではどのような変化が起きているのか、研究側の変化のみであるが紹介する。ただし、回答者も目的も異なる別の調査であることに注意されたい(文末のデータについての説明を参照)。
NISTEP定点調査2024では、深掘調査(研究活動と社会との関係)において、過去5年間の自身の研究活動について、社会や市民と能動的につながる機会があったかについて尋ね、あった場合にその機会の頻度の変化について聞いている。
回答者の大半が社会や市民と能動的につながる機会があったと回答したが、年代別に見ると、年代の高い回答者ほど機会があったと答える割合は大きかった(コラム図表6-4)。
機会があったとした回答者のうち、約半数以上が、過去5年間に頻度が増加していると答えた。年代別に見ると、30代以下では62%、40代では58%と、それより上の年代よりも増加していると答えた割合が大きかった(コラム図表6-5)。
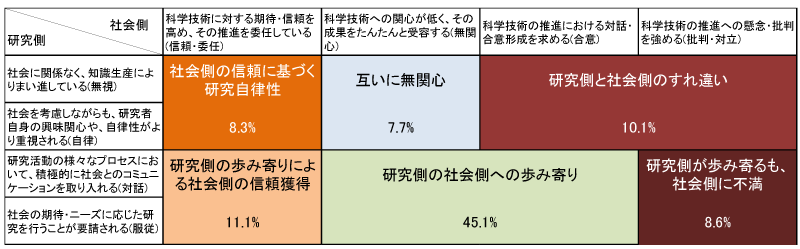
注及び資料:
コラム図表6-1と同じ。
参照:コラム表6-3
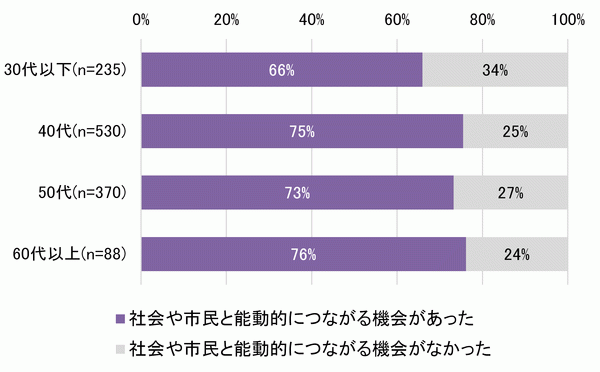
注:
「自身の研究活動における社会や市民と能動的につながる機会の過去5年間の有無」への回答。
資料:
「科学技術の状況に係る総合的意識調査(NISTEP定点調査2024)報告書」, NISTEP REPORT No.204, 文部科学省科学技術・学術政策研究所
参照:コラム表6-4
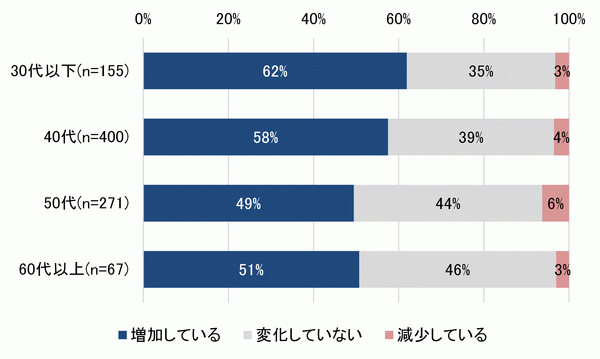
注:
「自身の研究活動における社会や市民と能動的につながる機会や頻度の過去5年間の変化」への回答。コラム図表6-4で「社会や市民と能動的につながる機会があった」を選択した回答者のみの集計。
資料:
コラム図表6-4と同じ。
参照:コラム表6-5
(5)まとめ
本コラムでは、第12回科学技術予測調査における、将来の科学技術と社会の関係性についての専門家の認識についての調査結果とともに、NISTEP定点調査2024の深掘調査における、現状での研究活動と社会との関係についての実態を紹介した。
第12回科学技術予測調査の結果からは、研究側が「対話」あるいは「服従」という形で社会に歩みより、同時に社会側も「合意」を求めるか、あるいは「無関心」にたんたんと科学技術を受け入れるとした「研究側の社会側への歩み寄り」が45.1%と最も多かった。年代別で見ると、若い世代ほど、研究側の社会への歩み寄りの程度がより強くなる「服従」と答えた割合が大きく、また、社会は科学技術に対してより「無関心」になると認識する割合が大きかった。
回答者は異なるが、研究活動において社会や市民と能動的につながる機会が増えている実態については、NISTEP定点調査2024の深掘調査からも確認ができた。回答者の大半が社会や市民と能動的につながる機会が過去5年の間にあったと回答し、そのうち、約半数がそれらの機会の頻度が増していると回答した。より若い世代ほど、その割合は大きかった。
これらの結果からも、現在までの変化としても、社会や市民と能動的につながる機会が増えている実態が明らかになったとともに、今後30年においてもその傾向は続き、研究側が社会に歩み寄る形でコミュニケーションを深めていくという認識を持つ専門家が多いことが分かった。ただし、将来認識については年代間で大きな差が見られることから、全体の趨勢も今後変化していく可能性がある。そのため、引き続き推移を注視する必要があると考えられる。
全体注:
[第12回科学技術予測調査デルファイ調査]
今後30年間の科学技術等の未来を展望する調査として、多数の専門家の見解を収集するため、デルファイ法による大規模アンケート調査を実施。
産学官の専門家を対象に、学協会90団体以上、researchmap (JST)の登録者やユーザー、NISTEPの運営する科学技術専門家ネットワーク等に回答を依頼した。1回目(2024年6月20日~7月31日)に6,073名、2回目(2024年8月19日~9月25日)に4,761名が参加した。本コラムで対象とした設問は全分野の回答者を対象とした共通質問として1回目調査のみに設定されており、回答者は6,231名である(共通質問のみに答えた回答者もいるため、デルファイ調査の回答者よりも多い)。
科学技術予測・政策基盤調査研究センター,「第12 回科学技術予測調査 科学技術等の中長期的な将来予測に関するアンケート調査(デルファイ調査)」,調査資料-346,文部科学省科学技術・学術政策研究所.DOI: https://doi.org/10.15108/rm346
[科学技術の状況に係る総合的意識調査(NISTEP定点調査2024)]
NISTEP定点調査は、第一線で研究開発に取り組む研究者や有識者への継続的な意識調査を通じて、我が国の科学技術やイノベーション創出の状況変化を把握する調査である。毎年一回、同一のアンケート調査を同一集団に継続実施している(一部、調査時点の情勢を踏まえた深掘調査も実施しており、本コラムではNISTEP定点調査2024で実施した「研究活動と社会との関係」の深掘調査のデータを用いて集計を行った)。NISTEP定点調査2024は、2024年9月17日~2025年1月6日にオンライン調査として実施した。調査全体での調査票送付者数2,204名に対して1,891名から回答を得た(回答率85.8%)。
「科学技術の状況に係る総合的意識調査(NISTEP定点調査2024)報告書」, NISTEP REPORT No. 204, 文部科学省科学技術・学術政策研究所.
DOI: https://doi.org/10.15108/nr204


