図表4-2-5は、整数カウント法で求めた国・地域ごとのパテントファミリー+単国出願数(A)、パテントファミリー数(B)である。
日本のパテントファミリー+単国出願数は、1997-1999年時点、2007-2009年時点では第1位であったが、2018-2020年時点では中国に次ぐ第2位である。2018-2020年時点では、これに韓国、米国、ドイツ、台湾がつづく。
パテントファミリー数に注目すると、1997-1999年は米国が第1位、日本が第2位であったが、2007-2009年時点、2017-2019年時点では日本が第1位、米国が第2位となっている。2007-2009年~2017-2019年にかけて、日本のパテントファミリー+単国出願数は減少しているが、パテントファミリー数は増加している。これは、図表4-2-4でみたように、日本からの複数国への特許出願が増加したことを反映した結果である。
パテントファミリー数について、第3位以降に注目すると、2017-2019年時点では、中国が第3位であり、これにドイツ、韓国、台湾、フランスがつづく。中国からのパテントファミリー+単国出願数は著しく増加しており図表4-2-4でみたように、現状では出願の多くが中国国内で行われているが、パテントファミリー数についても中国は着実に増加しており、ドイツを上回る規模となっている。
(A)パテントファミリー+単国出願数
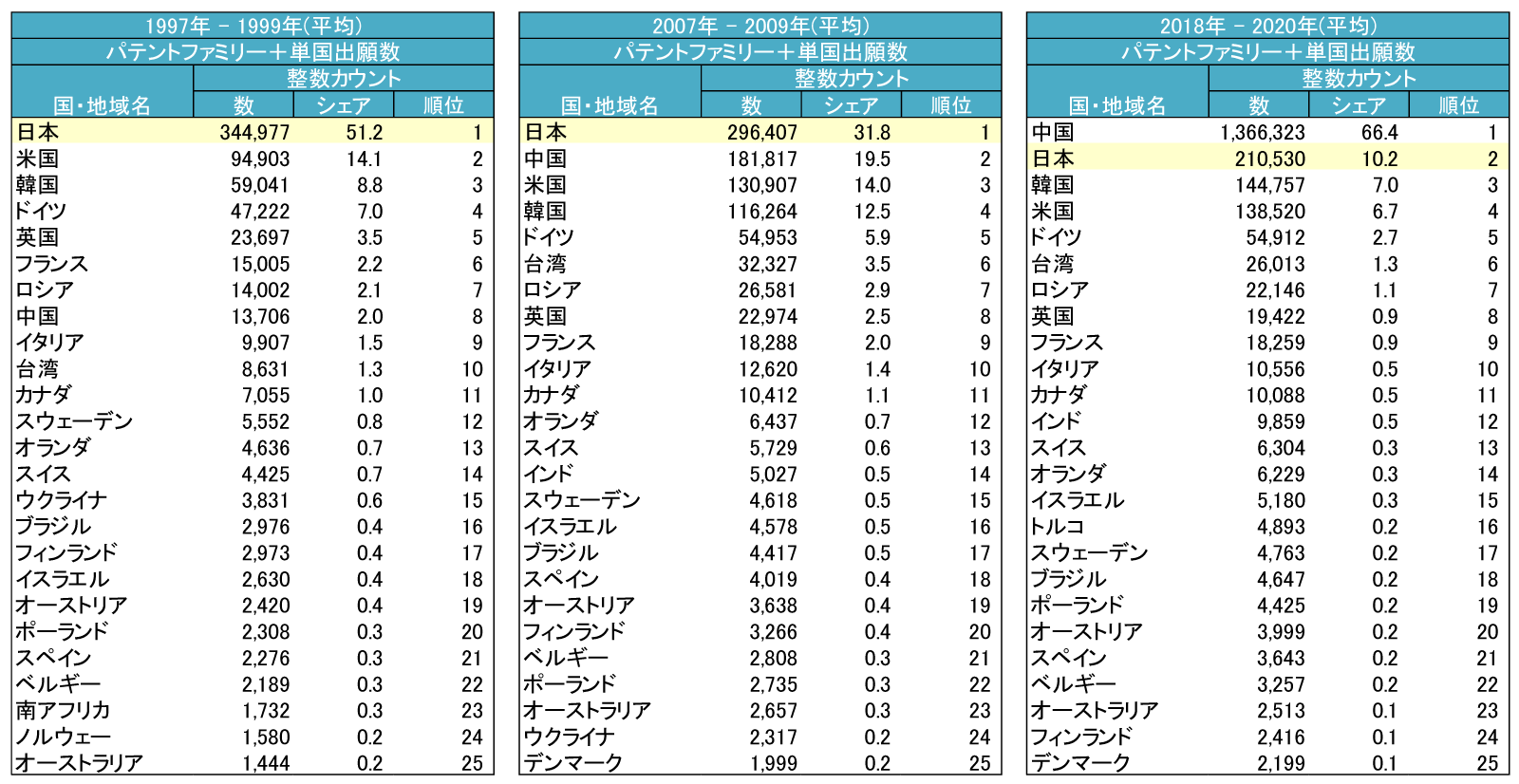
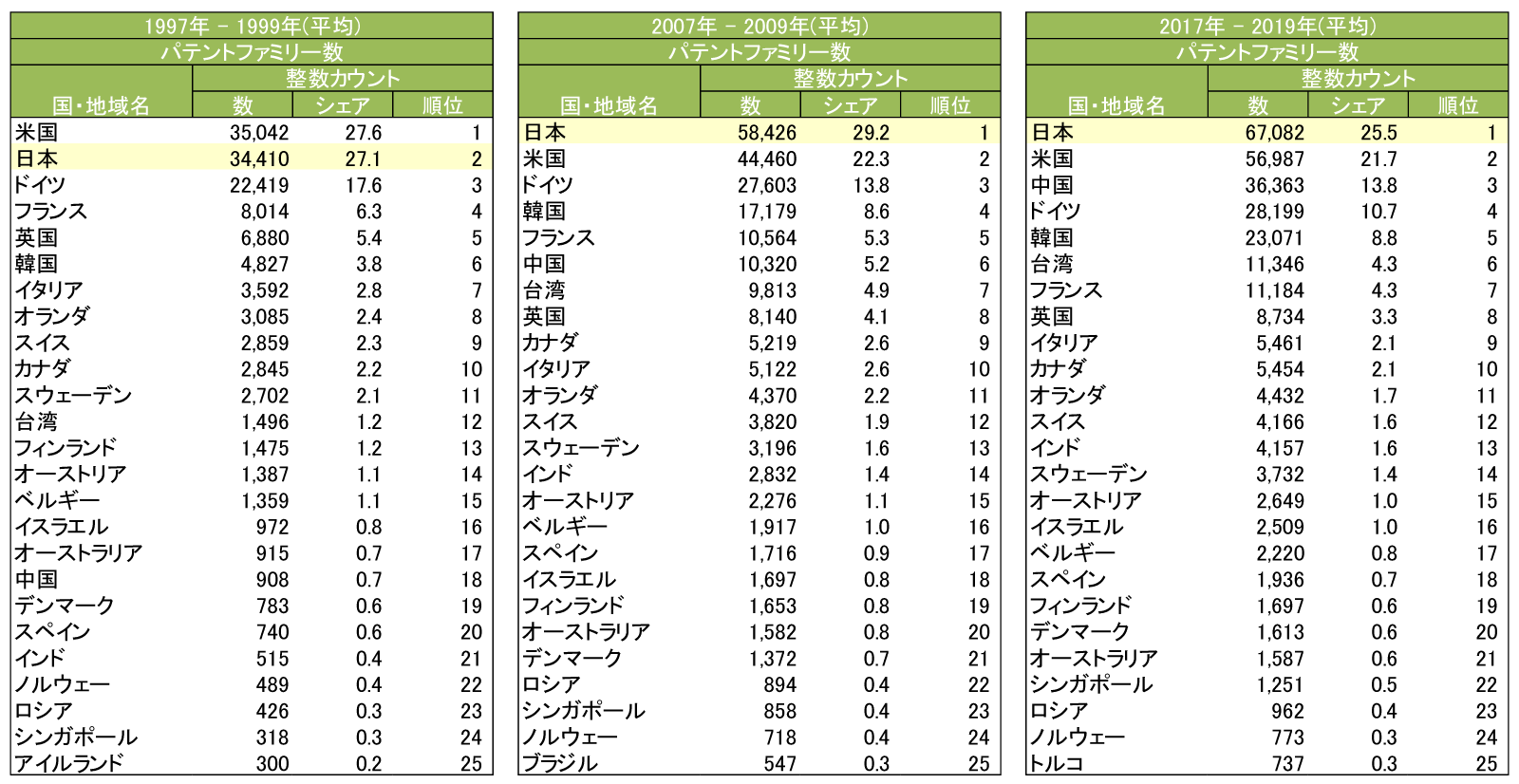
注:
オーストラリア特許庁への出願データを集計対象から除いているので、オーストラリアの出願数は過小評価となっている。パテントファミリーの分析方法については、テクニカルノートを参照。
資料:
欧州特許庁のPATSTAT(2023年秋バージョン)を基に、科学技術・学術政策研究所が集計。
参照:表4-2-5
図表4-2-6(A)では、主要国の特許出願の量的状況を把握するため、パテントファミリー+単国出願数の各国シェアを整数カウント法で比較した。
パテントファミリー+単国出願数シェアを見ると、日本は1980年代から1990年代にかけて、他国を大きく引き離している。1990年代の前半には、日本のシェアは60%近くに達したが、1990年代半ばから急激に減少している。この間、1980年代後半から米国、1990年代前半から韓国、2000年代前半から中国が、パテントファミリー+単国出願数を大きく伸ばしている。2010年以降、日本と中国の順位が入れ替わり、2019年(2018-2020年の平均)時点では中国のシェアが66.4%、日本のシェアが10.2%となっている。中国が急速にパテントファミリー+単国出願数シェアを増加させるのに伴い、近年は全ての主要国でパテントファミリー+単国出願数シェアは低下傾向にある。
次に、質的な側面を加味したパテントファミリー数の変化を見ると(図表4-2-6(B))、米国は1980~1990年代にかけて25%以上を保っていたが、2000年代に入ってからシェアは低下傾向にある。米国と日本の順位は1990年代後半に入れ替わり、2000年代は日本が第1位となっているが、2000年代中頃からそのシェアは減少傾向にある。2018年時点の日本のシェアは25.5%である。
中国のパテントファミリー数におけるシェアは、2000年代前半から増加をみせている。その勢いはパテントファミリー+単国出願シェアと比べると鈍いが、2016年に韓国、2017年にドイツを抜いて、2018年では13.8%のシェアとなった。
ドイツは1980年代前半には、日本と同じ程度のシェアを持っていたが、その後、パテントファミリー数におけるシェアは減少している。2018年におけるシェアは10.7%となっている。
韓国のシェアは、1980年代後半から増加しはじめ、1990年代後半や2005年以降に一時的な停滞を見せたのち、再び上昇傾向にあった。2014年をピークにシェアは低下し、近年は横ばいである。
(全技術分野、整数カウント法、3年移動平均)
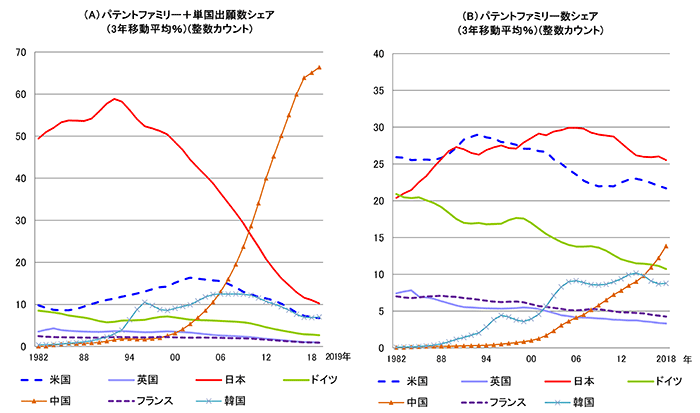
注:
全技術分野でのパテントファミリー数シェアの3年移動平均(2018年であれば2017、2018、2019年の平均値)、パテントファミリーの分析方法については、テクニカルノートを参照。
資料:
欧州特許庁のPATSTAT(2023年秋バージョン)を基に、科学技術・学術政策研究所が集計。
参照:表4-2-6
特許システムは、国によって異なることから、発明者や出願人の居住国のみへの出願も含むパテントファミリー+単国出願数は、各国の特許システムへの依存度が大きいと考えられる。
他方、パテントファミリーは、発明者や出願人が居住する国以外での権利化を目指して、2か国以上に出願されていると考えられ、パテントファミリー+単国出願の中でも相対的に価値が高い発明と考えられる。そこで、以降の分析では、パテントファミリーを用いた分析を示す。


