ポイント
- 日本における外国人大学院生は、2023年度において中国が最も多く、約3.8万人である。次いで韓国・朝鮮、インドネシアが約2,000人であり、1位と2位以降に大きな差がある。
- 米国における外国人大学院生は、インドと中国が拮抗しつつその数を伸ばしている。2022年ではインドは16.6万人、中国は12.6万人となった。
- 日本、米国ともにアジアからの大学院生が多いが、その国・地域のバランスに変化が起きている。
この項では、高等教育のグローバル化を示す指標の一つとして、研究者や高度専門家の養成を行っている大学院における外国人大学院生の状況を見る。
図表3-5-1は、日本と米国の大学院に在籍する外国人大学院生の数を、最新年のランキングで10位程度の国と主要国・地域について掲載したものである。全分野を対象としている(4) 。
日本における外国人大学院生数を見ると(図表3-5-1(A))、中国が最も多く、2023年度では約3.8万人である。次いで韓国・朝鮮、インドネシアが約2,000人である。10位以内にはアジアの国・地域が多いが、フランス(9位)、米国(10位)も入っている。2001年度と比較すると、規模の大きい中国の増加が目立つが、多くの国・地域で増加している。ただし、韓国・朝鮮は減少傾向にあり、インドネシア、ベトナム、台湾についても2010年代後半になると減少に転じている。
米国における外国人大学院生数を見ると(図表3-5-1(B))、2002~2009年にはインドが最も多かったが、その後は2012年まで大きく減少した(非EC国の学生に対して学生ビザの取得が厳密になった影響などが考えられる)。その後は増加に転じたが、2016年をピークに再び減少に転じた。他方、中国は2010年にインドに追いつき、増加し続けたが2020年では減少した。2020年では多くの国・地域で減少が見られ、その後は増加していることから、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響により、学生の渡航が滞った可能性がある。その後は中国、インドともに増加したが、インドが2021年、2022年に対前年比でそれぞれ48%、63%増加したのに対し、中国は4%、2%の増加であり、増加の度合いは大きく異なる。2022年のインドは16.6万人、中国は12.6万人となった。
3位以降の国・地域について、2001年時点と比較すると、韓国、台湾、日本、ドイツは30%以上減少している。最も減少しているのは日本である(64%減)。500%以上増加したのはナイジェリア、イラン、ネパールである。バングラデシュ(467%増)、サウジアラビア(246%増)も増加率は高い。サウジアラビアについては、2010年代半ばまでは継続して増加していたが、その後は減少に転じている。イランも同じような動きをしている。
日本、米国ともにアジアからの大学院生が多いが、その国・地域のバランスに変化が起きている。
(A)日本
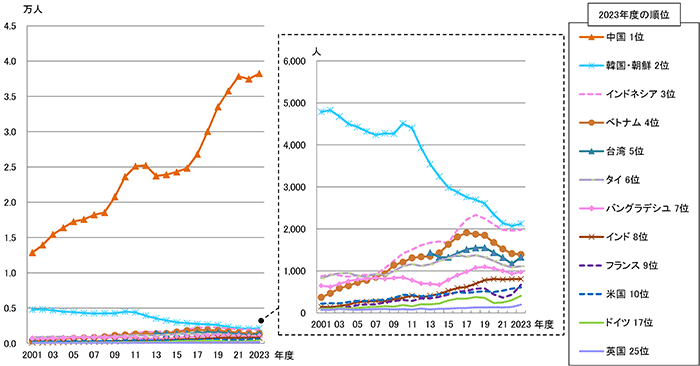
(B)米国
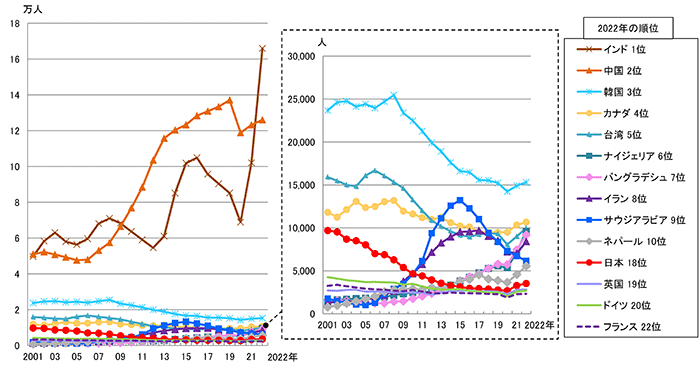
注:
1) 全分野を対象としている。
2) 日本の場合の外国人とは、日本国籍を持たない者。2012年7月に新しい在留管理制度が導入されたことにより、中国と台湾の学生を分けて集計している。
3) 米国の場合の外国人とは、教育課程を履修可能な非移民向けの一時的なビザを用い、米国内で現に教育課程を履修している者である。
資料:
日本:文部科学省、「学校基本調査報告書」
米国:Institute of International Education, ”Open Doors“ (https://opendoorsdata.org/, 2024年3月26日アクセス)
参照:表3-5-1
(4)科学技術指標2023までは、日本は自然科学分野、米国は科学工学分野についてのデータを掲載していた。米国の出典としていたNSF, “Sceine and Engineering Indicators”は外国人大学院生の数を上位の国・地域に限定して掲載しているため、近年日本や他の主要国について値が取得できなくなった事を受け、出典をInstitute of International Education, ”Open Doors“に変更し、分析対象の分野も全分野とした。米国の変更に合わせて、日本についても全分野の状況を見ている。


