ポイント
- 日本の企業部門の2022年の研究開発費は15.1兆円である。対前年比は6.4%増である。米国は2010年代に入ってから増加し続けており、2022年では69.2兆円となった。対前年比は9.5%増、主要国中第1位の規模を示している。
- 主要国における企業部門の研究開発費の対GDP比率を見ると、日本の2022年の対GDP比率は2.67%である。韓国は2010年から日本を上回り、2022年の4.14%は、主要国の中では著しく大きい値となっている。米国とドイツは、2010年頃から同程度の規模で推移していたが、米国は伸び続け2.83%になったのに対し、ドイツは横ばいに推移し2.11%となっている。
- 企業部門の研究開発費のうち、製造業の割合は日本、韓国では約9割である。ドイツ、中国は約8割である。米国では製造業の割合が約6割であり、先述した国と比較すると、非製造業の割合が大きい傾向にある。フランスの製造業の割合は約5割であり、非製造業の重みが最も大きい。
- 最新年の企業部門の研究開発費を産業分類別で見ると、米国は「情報通信業」、日本、ドイツは「輸送用機器製造業」、フランスは「専門・科学・技術サービス業」、中国、韓国は「コンピュータ、電子・光学製品製造業」が大きな規模を持っている。
- 日本の企業部門において、研究開発費が最も大きいのは「輸送用機械器具製造業」であり、売上高に占める研究開発費の割合が最も大きいのは「医薬品製造業」である。また、企業規模で見た場合、研究開発費に占める大企業の割合が大きい。研究開発の集約度は大企業で大きい傾向にある。
- 企業の研究開発に対する政府による直接的支援を従業員規模別で見ると、米国、日本では大規模企業に政府からの支援が集中しているが、ドイツや韓国では中小規模企業への支援に重みが置かれている。
- 日本の企業の外部支出研究開発費は、長期的に増加している。国内と海外を比較すると、海外への支出の増加の度合いが大きい。
(1)各国企業部門の研究開発費
企業部門の研究開発費は各国の研究開発費総額の大部分を占める。従って企業部門での値の増減が、国の研究開発費総額に及ぼす影響は大きい。図表1-3-3(A)を見ると、日本の2022年(18)の研究開発費は15.1兆円である。2009年に落ち込んだ後は漸増傾向にある。対前年比は6.4%増である。
米国は2010年代に入ってから増加し続けており、2022年では69.2兆円となっている。対前年比は9.5%増であり、主要国中第1位の規模を示している。
中国は2000年代に入ってから増加が著しい。2021年では50.8兆円、対前年比は12.7%増である。
ドイツは長期的に増加している。2010年代半ばから増加の度合いが大きくなった。2020年にはいったん減少し、再び増加している。2022年では11.2兆円、対前年比は5.0%増である。
韓国は継続して増加しており、フランス、英国を上回り、2022年では10.5兆円となった。対前年比は8.7%増である。
英国は、研究開発を実施する企業のサンプリングが不十分であることを考慮した数値の再調整により、値が上方修正されている(1.1.1項参照)。そのため、科学技術指標2022以前の数値とは異なることに留意されたい(2020年の値(ポンドベース)を比較すると約6割の増加が見られている)。英国は2014年以降増加しており、2022年では7.3兆円となった。対前年比は1.4%増である。
フランスは長期的には漸増している。2022年では5.3兆円、対前年比は1.4%増である。
次に、2000年を1とした場合の各国通貨による研究開発費の名目額と実質額の指数を示し、2000年からの伸びを見る(図表1-3-3(B))。名目額で見ると、日本の最新年の値は1.4であり、その伸びは他国と比較すると小さい。フランスが2.0、ドイツが2.3であり、米国が3.6の伸びを示しているのに対して、中国は40.0、韓国は8.7と急激な伸びを示している。
実質額の最新年値を見ると、日本は1.5、フランスは1.4、ドイツは1.6、米国は2.2である。中国、韓国は名目額よりは少ないが、それぞれ20.0、5.7と他国と比較すると際だって大きな伸びを示している。
(A)名目額(OECD購買力平価換算)
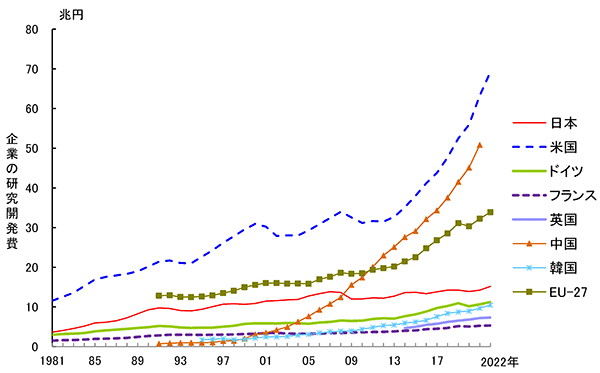
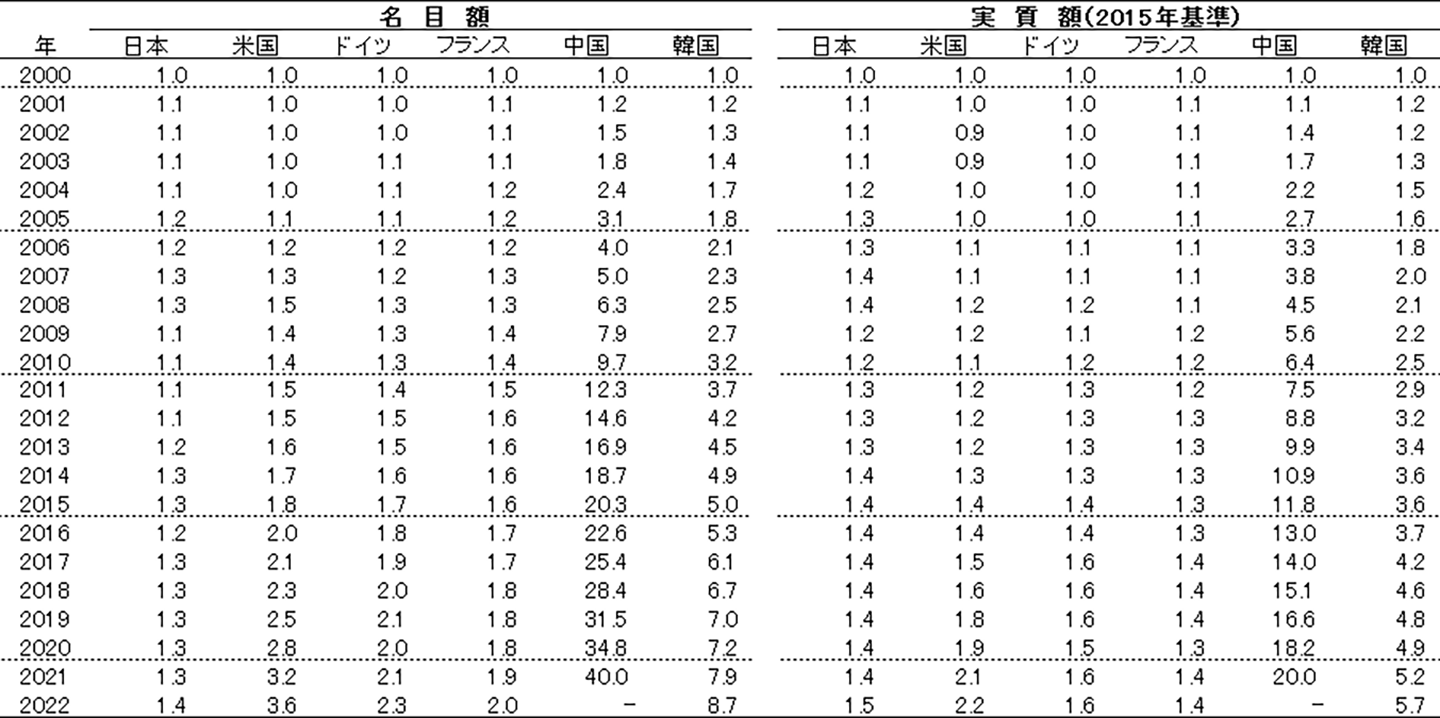
注:
1) 各国企業部門の定義は図表1-1-4を参照のこと。
2) 研究開発費は人文・社会科学を含む(韓国は2006年まで自然科学のみ)。
3) 購買力平価は、参考統計Eと同じ。
4) 実質額の計算はGDPデフレータによる(参考統計Dを使用)。
5) 日本は年度の値を示している。
6) 米国の2014年以前は定義が異なる。2015、2016、2021年において時系列の連続性は失われている。 2022年は暫定値。
7) ドイツは1990年までは旧西ドイツ、1991年以降は統一ドイツ。1982、1984、1986、1988、1990、1992、1994、1996、1998年は見積り値である。1993年値は定義が異なる。
8) フランスは1992、1997、2001、2004、2006年において時系列の連続性は失われている。2022年は暫定値である。
9) 英国の2014~2021年は暫定値である。2014、2022年において時系列の連続性は失われている。
10) 中国は2000、2009年において時系列の連続性は失われている。
11) EU-27は見積り値である。
資料:
日本:総務省、「科学技術研究調査報告」
その他の国:OECD,“Main Science and Technology Indicators March 2024”
参照:表1-3-3
各国の経済規模の違いを考慮して研究開発費を比較するために、企業部門における研究開発費の対GDP比率を見る(図表1-3-4)。
日本の2022年の対GDP比率は2.67%である。1989年以降、主要国第1位であったが、2010年からは韓国が日本を上回った。
韓国の2022年は4.14%であり、主要国の中では著しく大きい値となっている。
米国は2013年以降GDP比率が継続して増加している。ドイツは1990年代の中頃から増加し続けている。2010年頃から両国とも同程度の規模で推移していたが、米国は伸び続け2.83%になったのに対し、近年のドイツはほぼ横ばいに推移し2.11%となっている。
英国については、企業部門の研究開発費が上方修正されたことにより(1.1.1項参照)、対GDP比率も大きく上昇した。科学技術指標2022以前の数値とは異なることに留意されたい。2022年では1.99%を示している。
中国の値は急激に上昇し、EU-27、フランスの値を超えており、2021年では1.87%である。
2010年代に入って、フランスはほぼ横ばいに推移している。2022年は1.43%である。
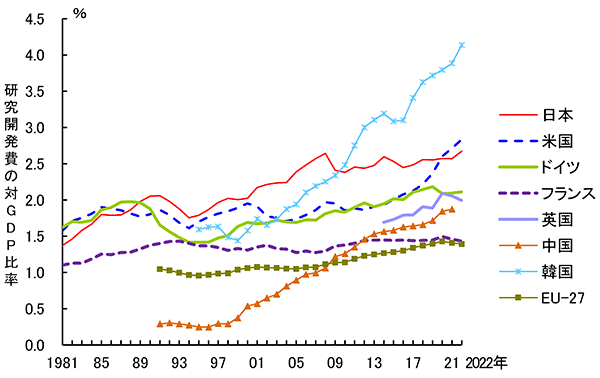
注及び資料:
研究開発費は図表1-3-3と同じ。GDPは参考統計Cと同じ。
参照:表1-3-4
(2)主要国における産業分類別(19)の研究開発費
主要国における企業部門の製造業と非製造業の研究開発費について、各国最新年からの3年平均で見ると(図表1-3-5)、製造業の割合は日本、韓国では約9割、ドイツ、中国は約8割であり、製造業の重みが大きい。米国では製造業の割合が約6割であり、上述した国と比較すると、非製造業の割合が大きい傾向にある。フランスの製造業の割合は約5割であり、非製造業の重みが最も大きい。2008年~2010年(3年平均)と比較すると、ほとんどの国でバランスに大きな変化が見えないが、米国では非製造業が3割から4割に増加している。

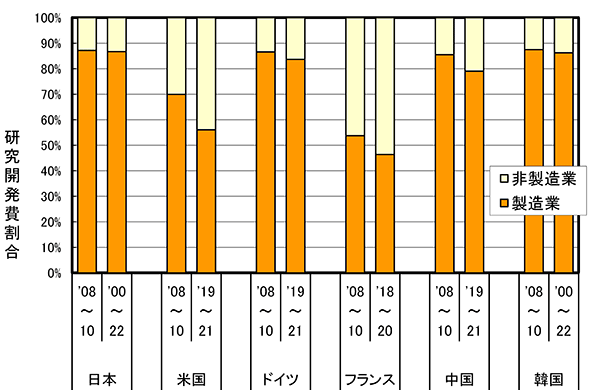
注:
1) 国際標準産業分類第4次改定版(ISIC Rev.4)に準拠しているため、各国の産業分類とは異なる。
2) 各国とも研究開発を行う企業の主な経済活動(Main economic activity)に応じて分類している。
3) 米国では、「Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting」及び「Public Administration」は除かれている。よって、他国の非製造業と異なっているため、国際比較する際は注意が必要である。
資料:
OECD,“Analytical Business Enterprise R&D by ISIC Rev.4 industry (ANBERD database)”
参照:表1-3-5
さらに詳細な産業分類別での研究開発費を見ると(図表1-3-6)、米国は2008年時点では、「コンピュータ、電子・光学製品製造業」が最も多かったが、非製造業である「情報通信業」が増加し続け、2014年以降は最も研究開発費の多い産業となった(2021年で17.5兆円)。
中国は製造業の伸びが著しい。特に「コンピュータ、電子・光学製品製造業」が大きく伸びている(2021年で9.2兆円)。非製造業についての内訳はなく、製造業と比較すると規模も小さいが、2010年代半ばから、製造業を上回るペースで増加している。
日本の製造業は、2008年時点では、「コンピュータ、電子・光学製品製造業」が最も多かったが、その後は減少している。これに代わって「輸送用機器製造業」が増加し、2013年以降は最も多くなっている(2022年で4.3兆円)。非製造業では、「専門・科学・技術サービス業」が最も多く、次いで「情報通信業」が多い。2020年の「専門・科学・技術サービス業」は大きく減少したが2022年では1.0兆円と2008年以降最大となっている。
ドイツは、継続して「輸送用機器製造業」が最も多い(2021年で3.9兆円)。次いで多いのは「コンピュータ、電子・光学製品製造業」である(2021年で1.3兆円)。非製造業では「専門・科学・技術サービス業」が多くかつ増加傾向にある。
フランスは非製造業である「専門・科学・技術サービス業」が最も多く、2020年で1.5兆円である。非製造業で次いで多いのは「情報通信業」の0.7兆円である。製造業では「輸送用機器製造業」が多い(0.8兆円)。
韓国は「コンピュータ、電子・光学製品製造業」が最も多くかつ増加の度合も大きい。2022年では5.2兆円である。2008年と比べると2.8倍の伸びである。非製造業では「情報通信業」が最も多い。
2010年から最新年にかけての製造業、非製造業の研究開発費の伸びに注目すると、規模は製造業の方が大きいが、いずれの国でも非製造業の伸びの方が大きい。
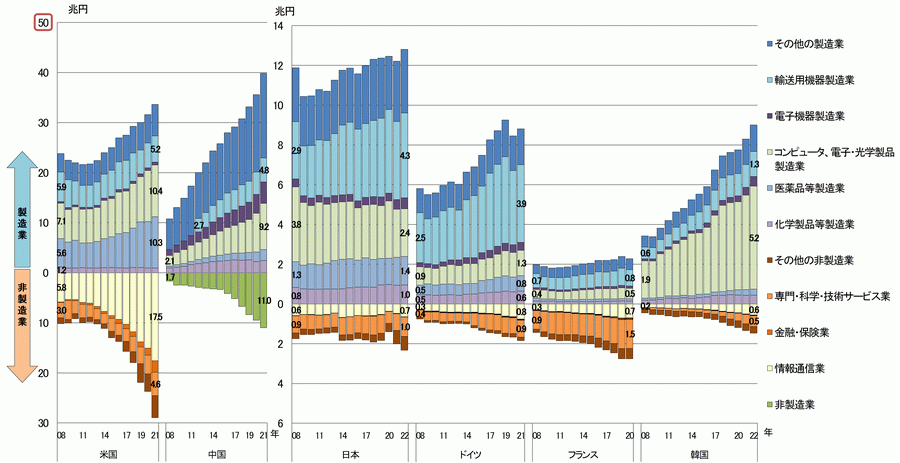
注:
1) 国際標準産業分類第4次改定版(ISIC Rev.4)に準拠しているため、各国の産業分類とは異なる。
2) 各国とも研究開発を行う企業の主な経済活動(Main economic activity)に応じて分類している。
3) 米国では、「Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting」及び「Public Administration」は除かれている。よって、他国の非製造業と異なっているため、国際比較する際は注意が必要である。
4) 米国の2009~2012年の「輸送用機器製造業」、2008~2010年の「情報通信業」、2008~2010、2016、2021年の「専門・科学・技術サービス業」は見積り値。
5) ドイツの2020年の「専門・科学・技術サービス業」は見積り値。
6) フランスの2013、2014、2018、2019年は見積り値。
資料:
OECD, “Analytical Business Enterprise R&D by ISIC Rev.4 industry (ANBERD database)”
参照:表1-3-6
(3)日本の産業分類別研究開発費
日本の研究開発は、どの業種において、より多く実施されているのかを見るために、売上高に占める研究開発費の割合(研究開発の集約度)を産業分類別に見た(図表1-3-7)。
まず、製造業と非製造業を比較すると、前者が2.8%であるのに対して、後者は0.4%となっており、売上高に占める研究開発費の割合が7倍異なる。日本の企業部門における売上高に占める研究開発費の割合が最も大きいのは「医薬品製造業」であり8.5%を示している。これに「情報通信機械器具製造業」が5.9%、「業務用機械器具製造業」が5.4%、「電子部品・デバイス・電子回路製造業」が5.2%と続いている。研究開発費の集約度は産業によって異なる傾向を示している。
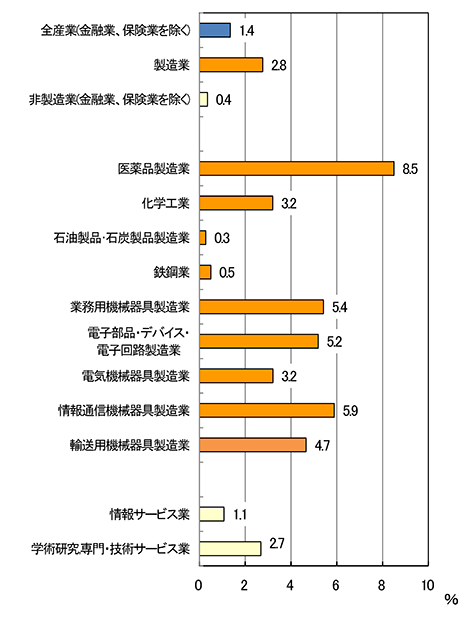
注:
1) 研究開発を実施していない企業も含んでいる。
2) 全産業及び非製造業は金融、保険業を除く。
資料:
総務省、「科学技術研究調査報告」
参照:表1-3-7
(4)企業規模別の研究開発費
主要国の企業の研究開発における、企業規模による研究開発の実施状況を見るために、企業の従業員数を一定数で区切り、従業員規模別に研究開発費に占める割合を見た(図表1-3-8)。
各国最新年を見ると、従業員数500人以上の企業が占める割合が多い。特に日本、ドイツでは全体の約9割を占める。米国では約8割、韓国では約7割、フランスでは約6割である。フランスでは従業員数50人以上249人以下の企業の割合が、韓国では従業員数49人以下の企業の割合が、他国と比較すると最も大きい。フランスや韓国は従業員規模の小さい企業の割合が比較的大きい傾向にある。
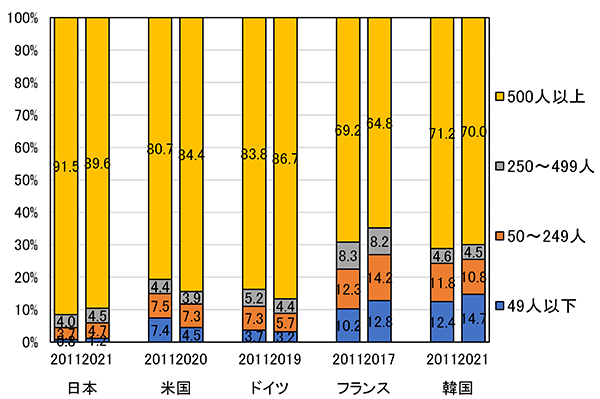
注:
2011、2019年のドイツと2011年の米国の「従業員数49人以下」の値は定義が異なる。フランスの2017年は暫定値である。
資料:
OECD, “R&D Statistics”
参照:表1-3-8
次に、企業規模による研究開発の集約度を見る。具体的には、企業の従業員数を一定数で区切り、企業規模別に売上高に占める研究開発費の割合を見た(図表1-3-9)。
日本は従業員数1万人以上の企業において、売上高に占める研究開発費の割合が最も大きく、4.5%である。従業員数が少なくなるにつれて、その割合が小さくなる傾向にあり、最も小さいのは従業員数1~299人の企業の1.5%である。
ドイツは従業員数従業員数5,000~9,999人の企業において、売上高に占める研究開発費の割合が最も大きい(4.3%)。また、従業員数1万人以上の企業と従業員数0~249人の企業が3.9%と同程度に大きいことが特徴である。最も小さいのは従業員数1,000~4,999人の企業の2.4%である。
韓国では、従業員数0~99人の企業において、売上高に占める研究開発費の割合が最も大きく、4.1%である。規模が大きくなるにつれて割合は小さくなる傾向にあるが、従業員数1,000人以上の企業で再び大きくなる(3.5%)。最も小さいのは従業員数300~999人の企業の1.9%である。
いずれの国も大規模企業で研究開発の集約度が高いのに対して、ドイツや韓国では小規模企業においても研究開発の集約度が高く、国によって集約度が異なる。
図表1-3-9(D)では日本の推移を示した。時系列で見ても従業員数1万人以上の企業の集約度が一貫して大きい。2008年時点では、従業員数300~999人の企業が最も小さく、従業員数1~299人、1,000~2,999人、3,000~9,999人の企業の順に割合が大きくなっている。その後、長期的な動きに注目すると従業員数3,000~9,999人の企業の割合が大きくなり、従業員数1~299人の企業の割合は最も小さくなっている。

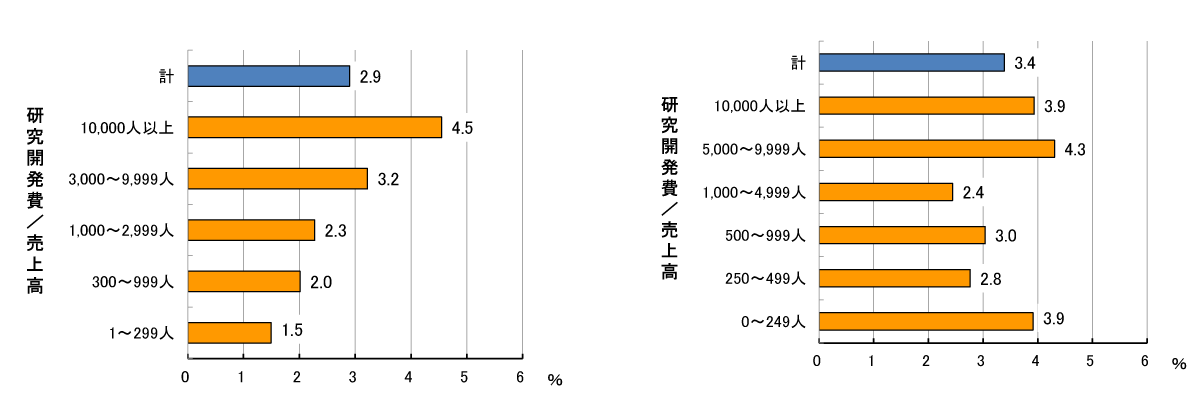
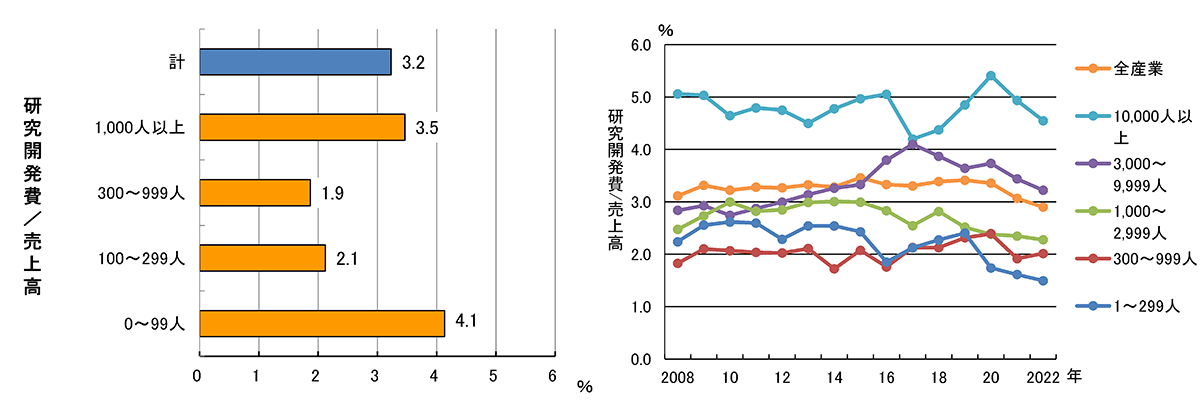
注:
研究開発を実施している企業を対象としている。各国の研究開発統計により、従業員数の分類が異なるため、国際比較する際には注意が必要である。
日本は年度の値を示している。金融・保険業を除く。
資料:
日本:総務省、「科学技術研究調査報告」
ドイツ:Stifterverband Wissenschaftsstatistik, “arendi-Zahlenwerk”
韓国:韓国科学技術企画評価院、「研究開発活動調査報告書」
参照:表1-3-9
(5)企業への政府による直接的・間接的支援
企業の研究開発のための政府による支援の状況を示す。
「直接的支援(企業の研究開発費のうち政府が負担した金額)」及び「間接的支援(企業の法人税のうち、研究開発税制優遇措置により控除された税額)」を対GDP比で見ると(図表1-3-10(A))、日本はここで示した国の中で直接的支援が最も小さく、直接的支援より間接的支援が大きい。他国を見ると、直接的支援が最も大きいのはロシアであり、これに韓国、ハンガリーが続く。間接的支援が大きいのはアイスランド、英国、フランスなどである。
次に、日本について政府からの直接的、間接的支援の対GDP比の推移を見ると(図表1-3-10(B))、政府から企業への直接的支援は長期的には減少傾向にあったが、2019年を境に上昇の兆しも見える。間接的支援は変動が大きく、2004年に著しく増加した後、2008年には減少し、2013年には再び増加した。その後は長期的に見ると減少していたが、2021年では再び増加した。
間接的支援の変化には、いくつかの要因が考えられる。一つめは研究開発税制優遇措置の変更である。二つめは特定企業の税制優遇措置額の変化である(20)。最後に、市場経済(景気・不景気)の変化である。税法上の所得(=益金?損金)がない場合、優遇税制措置の適用が発生しない。
間接的支援の2004年の急増については、2003年に導入された「試験研究費の総額にかかる税額控除制度」による制度上の税額控除額の増加が主な理由と考えられ、この制度を活用する企業が2004年に増えたと推測される。2008年の減少については、法人税全額の減少が、控除額の減少につながったと考えられる。2013年の増加については、特定企業による税制優遇措置額の増加によるものと考えられる。2015年度には「特別試験研究費税額控除制度(オープンイノベーション型)」の拡充と総額型の控除上限の引き下げ、繰越税額控除制度の廃止の3つの制度変更が同時に行われた。
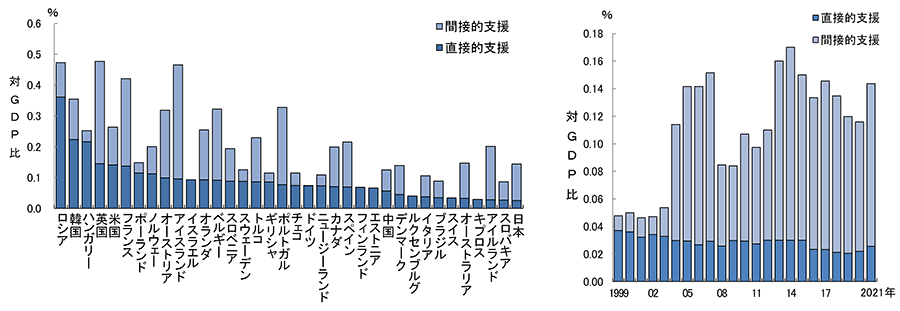
注:
直接的支援とは、企業の研究開発費のうち政府が負担した金額の対GDP比率である。
間接的支援とは、企業の法人税のうち、研究開発税制優遇措置により控除された税額の対GDP比率である。
各国からの推計値 (NESTIが行った研究開発税制優遇調査による)、予備値も含まれる。
中国は2017年、ロシアは2019年、米国、デンマーク、ブラジルは2020年、その他の国は2021年。
資料:
OECD,“R&D Tax Incentive Indicators ”
参照:表1-3-10
次に、政府からの企業の研究開発における直接的支援を従業員規模別で見る(図表1-3-11)。
日本では、従業員数500人以上の企業に対する政府による直接的支援の割合が全体の79.1%を占める。これに次いで従業員数50~249人の企業の割合が大きいが7.3%である。
米国では、従業員数500人以上の企業の割合が全体の81.4%を占める。これに次いで従業員数49人以下の企業が大きいが7.2%である。
ドイツでは、従業員数500人以上の企業の割合が最も大きく44.4%を占める。ただし、従業員数49人以下の企業が26.0%、従業員数50~249人の企業が22.7%となっており、この2つの企業規模においても割合が大きい。
フランスでは、従業員数500人以上の企業の割合が70.7%を占める。これに次いで大きいのは従業員数49人以下の企業であり17.4%を占めている。
韓国では、従業員数49人以下の企業が47.6%と最も大きい。また、従業員数50~249人の企業でも21.2%と大きく、249人以下の企業で政府による直接的支援の約7割を占める。
米国、日本では大規模企業に政府からの支援が集中しているが、韓国やドイツでは中小規模企業への支援に重みが置かれていることが分かる。
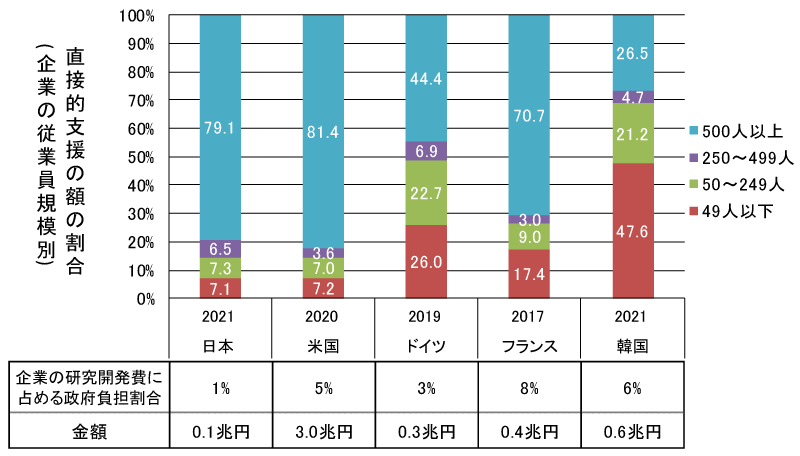
注:
1) 日本は年度の値を示している。
2) 米国は定義が異なる。
3) フランスは暫定値である。
4) 購買力平価は、参考統計Eと同じ。
資料:
OECD, “R&D statistics”
参照:表1-3-11
(6)日本企業の外部支出研究開発費に見る研究活動のオープン化・グローバル化
企業の製品やサービス等に、人工知能や機械学習等の新しい知識を迅速に導入するには、自社における研究開発活動に加えて、社外の知識や研究開発能力を活用していく(オープン化していく)必要がある。また、企業活動がグローバル化するにつれ、研究開発活動もグローバル化することが予想される。そこで、ここでは企業の外部支出研究開発費の動向に注目することで、研究開発活動のオープン化・グローバル化の状況を把握する。
図表1-3-12(A)に、企業の外部支出研究開発費の時系列変化とその内訳を示した。2000年代後半に一時的に落ち込む時期があるものの、外部支出研究開発費は長期的に増加傾向にあったが、2020年度に大きく減少した。1999年度から2018年度にかけては、企業の内部使用研究開発費が33.9%増であるのに対して、外部支出研究開発費は約2倍となっており、企業の研究開発活動のオープン化が進展していた。しかし、2019年度から2020年度にかけては、前者が2.5%減なのに対して、後者は12.1%減となっており、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが研究開発活動のオープン化にも影響を与えたことが分かる。2022年度では外部支出研究開発費は増加し2.6兆円となった。対前年比16.6%増であり、国内外ともに会社への外部支出研究開発費が増加している。
国内と海外を比べると2001年度から2019年度にかけて、国内への外部支出の増加率が24.9%であるのに対して、海外への外部支出の増加率は474.5%である。この結果として、外部支出研究開発費における海外への支出分の割合は、2001年度には9.9%であったものが、2019年度には33.6%となった。2019年度から2020年度にかけては、国内への外部支出は23.3%減であったが、海外への外部支出は10.0%増であった。国内の減少は主に会社への外部支出の減少、海外の増加は会社への外部支出の増加によるものである。後者については2022年度も対前年度比17.1%の増加を示しており、研究開発のグローバル化は進展し続けている。
図表1-3-12(B)は、外部支出先として大学のみを取り出し、その割合を見たものである。最新のデータを見ると国内の国・公立大学への外部支出が一番多い。海外の大学の割合は長期的に低下している。企業から大学への外部支出という点では、日本の大学が主要な支出先であることが確認できる。
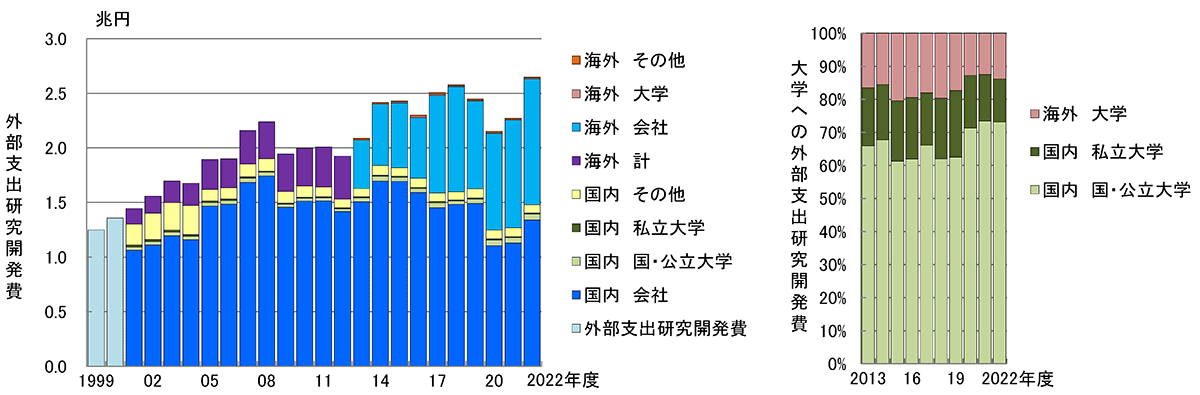
注:
国内のその他には国・公営の研究機関、特殊法人・独立行政法人の研究所、公庫・公団、非営利団体などを含む。
資料:
総務省、「科学技術研究調査報告」
参照:表1-3-12
(18)この節の日本は、国際比較の際には「年」を用いている。本来は「年度」である。日本のみを記述している節では「年度」を用いている。
(19) 企業部門の産業分類の方法には、主な経済活動(Main economic activity)によるものと、産業方向性別区分(Industry orientation)によるものがある(OECD フラスカティ・マニュアル 2015 [7.48-7.50])。前者は企業の経済的アウトプットの重みが最も大きい産業分類に基づく分類であり、後者は研究開発活動を報告する際に、最も適当であると思われる産業分類に分類する方法である。
(20)例えば、連結法人の法人税額の特別控除額について、2013年では上位10社で全体の約70%を占めており、対象年における特定企業の研究開発税制優遇措置額によって全体の額が大きく変化する事が分かる。出典:財務省、「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」


