- PDF:PDF版をダウンロード
- DOI: https://doi.org/10.15108/stih.00399
- 公開日: 2025.05.02
- 著者: 池田 雄哉
- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.11, No.2
- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)
特別インタビュー
早稲田大学商学学術院 清水 洋 教授インタビュー
-イノベーションへの処方箋:
リスキリング、基礎研究、数値化の罠-
早稲田大学商学学術院の清水洋氏は、2021年、その顕著に優れたイノベーション研究が認められ、国際シュンペーター学会「シュンペーター賞」注1を受賞した。日本人の受賞は、青木昌彦氏以来2人目の快挙である。本インタビューでは、歴史的分析を通してイノベーションに関する新たな知見を発見している清水氏に、イノベーション、リスキリング、スタートアップ政策、企業の基礎研究力、自身の研究キャリアなどについて幅広くお話を伺った。
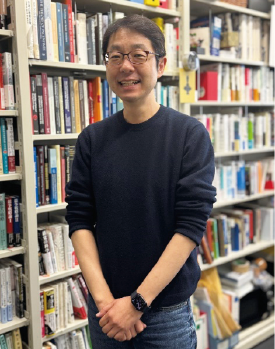
(略歴)
早稲田大学商学学術院教授。専門は経営学(イノベーション、アントレプレーナーシップ)。2007年ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス博士(経済史)。一橋大学イノベーション研究センター教授などを経て、2019年より現職。第33回組織学会高宮賞、第59回日経・経済図書文化賞、国際シュンペーター学会シュンペーター賞。著書に『ジェネラル・パーパス・テクノロジーのイノベーション』(有斐閣)、『野生化するイノベーション』(新潮選書)、『イノベーションの考え方』(日本経済新聞出版)など多数。
イノベーションによって破壊される人
- 新著『イノベーションの科学』(中公新書)注2では副題にもあるように、なぜ「創造する人・破壊される人」に注目されたのでしょうか。
私は英国にあるロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス(LSE)で経済史を専攻していました。当時、英国では産業革命の研究が依然として盛んで、経済成長への影響を分析する研究も数多く行われていました。その中でも興味深かったのは、新しい技術が次々と生まれても、それが経済成長につながるまでには時間がかかるという話です。その理由の一つが、優れた技術の台頭によって一時的に失業率が上昇すると、労働市場の調整に時間がかかるということでした。
帰国してからはイノベーションがどのように起こるのかということばかり考えていたのですが、あるとき学部生から、「先生、イノベーションとはいうけれど、そんなことをやっていて幸せなのですか」と聞かれたのです。素朴な疑問でしたが、産業革命では一時的に失業者が増加したという例もありましたし、イノベーションによって破壊される人という側面を考えるきっかけになりました。
- イノベーションによる破壊という点で、今後、日本ではどのような問題が生じるでしょうか。
高度経済成長期、古くは明治維新の頃から、日本でもイノベーションによる破壊が何度も起こってきました。当時は経済成長が続いていたため、新たな産業が次々と生まれ、失業した人々を吸収することができたのだと思います。しかし最近は経済成長が鈍化し、企業が多角化を控えるようになってきています。これから企業内で吸収できる余地がなくなってきたとき、日本でも大きな問題になるのかもしれません。
- イノベーションによって破壊された人には、何らかの補償が必要なのでしょうか。
恩恵を受ける人と破壊される人という構図は、以前から様々な場面で指摘されています。ダムや空港の建設、TPP(環太平洋パートナーシップ)もその一例でしょう。TPPに加盟すれば自由貿易の恩恵は社会全体に広がりますが、一部の農業セクターは大きな打撃を受けるかもしれません。破壊される側に立たされた人々は強く反対しますし、多くの場合、失ったものは人生の時間軸では回復しないのだと思います。ですから破壊される人々が明確に特定できる場合には、十分な補償がなされないといけません。
しかし、イノベーションの場合は影響が広範囲に及ぶので、誰をどのように補償すべきかが分かりにくくなります。さらに、イノベーションにおいては、スキルが陳腐化すると予想されているにもかかわらず、なぜリスキリング(職業能力の再開発)しなかったのかという自己責任論が持ち出されることもあります。一口にリスキリングといっても限界はありますし、自助努力が足りないということを突き詰めると米国のような社会になってしまうのだと思います。
リスキリングは柔軟な労働市場とセットで
- リスキリングは政策的にも注目されていますが、日本企業による人的資本投資は国際的にも低い水準です。何が問題なのでしょうか。
リスキリングは、柔軟な労働市場とセットでなければ意味がありません。企業内でリスキリングの機会を提供しよう、リスキリングのための補助を出しますといっても、それは基本的に企業特殊的なスキルのための投資にすぎません。特定の企業でしか通用しないスキルをどれだけ習得しても、労働者がますます企業の外へ出にくくなるだけでしょう。リスキリングの本来の目的は、労働者が新しい産業セクターに移動して、より高い所得を得られるようになることです。ですから、リスキリングは柔軟な労働市場とセットでないと意味がないのです。
- リスキリングへの投資は個人が負担するしかないのでしょうか。
いまやっているビジネスの範囲を越えたリスキリングをしようと思っても、企業はやってくれないでしょう。ドイツでは自動車産業の労働組合が強く、容易に解雇できません。中国のWTO(世界貿易機関)加盟によって安価な部品が流入した際、ドイツの企業は労働者を解雇するのではなく、リスキリングによってデジタル設計などの新たなスキルを身につけさせました。しかし、作っている製品自体は変わっているわけではないので、既存のビジネスモデルの延長線上にある適応にすぎません。今後、自動運転やシェアリングエコノミーが本格的に普及すると、設計や製造の枠組み自体が根本的に変わる可能性があります。そうなると、お手軽なリスキリングでは対応できません。
- リスキリングにおける政府の役割は何でしょうか。
例えば国立大学のMBAプログラムなど、高品質なリスキリングの機会を安価で用意しておくことです。年齢を重ねてから新しいことを学ぼうとしても、リターンの回収期間が短いので大きな投資はできません。ですから、安価で質の高い教育の機会があるということは重要だと思います。
経済史家のクラウディア・ゴールディンは『教育と技術の競争(原題:The Race between Education and Technology)』(未邦訳)の中で、教育投資が不足すると所得格差が大きくなるということを論じています。なぜ所得格差が拡大するかというと、イノベーションが起きてイノベーションに補完的な仕事が生まれたとき、それに適応できる高スキル人材の供給が少ないと彼らの所得だけが上昇してしまうからです。しかし供給が十分に多ければ所得格差は開きにくくなる。だから教育投資は重要というわけです。
米国や中国など成長投資が盛んな国や地域に学生を送ることも重要です。イノベーションは投資の関数なので、投資が活発なところで新規性の高いものは生まれます。日本人の留学生は依然として不足していますし、国として後押しできることも少なくないと思います。
企業の基礎研究力への懸念
- 大学のみならず企業部門のTop10%補正論文数も低下しています注3。企業の基礎研究の現状をどのように評価されていますか。
日本企業の基礎研究力が低下しているということは、かなり実感しています。中央研究所が次々と閉鎖されていますし、ホールディングス(持株会社)制の導入も進んでいます。ホールディングス制を採用すると事業の組替えがしやすくなり、時々のニーズに応じた技術を外部から調達してくることも容易になります。しかし、その結果として、かつて中央研究所が担っていた「10年後、20年後のビジネスを見据えた長期的な研究開発」という役割が希薄になってしまっています。
中央研究所の役割には新しい技術を生み出すことだけでなく、知識吸収能力を高めることや、その企業では活用されない新しい技術がスピンアウトを通して外部へ普及していくということもあります。近年、これらの機能がかなり縮小してしまっているのではないかと危惧しています。
日本の強みの一つは、累積的なイノベーションを着実に進めることにあります。その基盤となっていたのが中央研究所の存在でした。中央研究所が基礎研究を担えなくなっているのであれば、産業技術総合研究所や理化学研究所といった国の研究機関の役割がさらに重要になるでしょう。
- スタートアップの役割はどのようにお考えでしょうか。
スタートアップの主な役割は、既存の基礎研究の成果をビジネスとして展開することです。新規性の高いビジネスを期待できるかもしれませんが、「新規性の高い技術を開発してほしい」という期待は誤解といえます。
スタートアップがビジネスに転換できるような重要な技術は、どこかで開発されなければなりません。米国では、企業の研究所や大学がその役割を担うことが一般的です。しかし日本の場合、この基礎研究の部分が十分に強化されないままスタートアップを推進しようとしています。そのため、短期的には優れたビジネスが生まれるかもしれませんが、中長期的にはシーズが枯渇してしまう懸念があります。
- 政府は担当大臣を設置するなどスタートアップの支援を進めています。政策への評価はいかがでしょうか。
スタートアップは初期段階から何が成功するか分からないため、例えば、数十社のみを支援するという方式に対して、より幅広い支援が必要だという意見もあるでしょう。しかし、現段階では、とにかく投資することを前向きに評価しています。
国民も成果を焦って評価するべきではないです。政府が支援したスタートアップが期待どおりに成功しないこともあるでしょうけれど、それ自体はあまり問題ではありません。むしろ波及効果の大きさを狙った取組である以上、不確実性が高いのは当然です。民間と同じような取組では意味がありませんし、「国の支援だから非効率だ」という先入観を持たずに理解を深めていく必要があります。

専門家の信頼が失われると数値化が進む
- 行政だけでなく、企業からもよく相談を受けるそうですね。
「新しいことをやりたいのですが、何かいいモデルはないですか?」という質問をよくいただきます。そうした場面で全く異なる産業の事例を紹介すると、「いや、それは〇〇産業の事例なので違います」と却下されることが少なくありません。自分たちの産業で少し先を行っている事例を模倣するという、いわゆる“タイムマシン経営”ですね。
他にこういう事例があるからやりましょう、模倣しましょうと言わないと意思決定できないのでは困ります。新しいことに挑戦するのですから、実績がなくて当然です。
- 日本型〇〇というのは、名前を付ける段階から敗北しているのかもしれません。
とても表層的で、これだけはやりましたという理由づけにしか聞こえません。それで本当に機能するかまで真剣に考えているのでしょうか。
科学史家のセオドア・ポーターが『数値と客観性』(みすず書房)の中で、「専門家に対する社会の信頼が失われると数値化が進む」ということを論じています。例えば、「橋をかけることでどれくらいの効果があるのか、数値で示せ」と求められるケースを考えてみましょう。ある地域には学校があり、もう一方には駅がある。橋を1つしかかけられない場合、どちらにかけるのが良いのか。経済効果は試算できるとして、子供たちが安全に遊べるなど、数値化しにくいけれども重要な要素もあるわけです。
しかし、意思決定者が専門家の判断に疑いを向けたとき、「数値化されたものが客観的である」という圧力が加わりやすくなります。どの変数を用いるかには恣意的な判断が含まれるにもかかわらず、その点が見落とされてしまうのです。そうすると数値化できるデータばかりが重視され、手続き上の客観性さえあればいいという風潮が生まれます。これが実際に米国で起きたことです。一方、フランスではシビルエンジニア(土木技術者)に対する社会的信頼が厚かったため、「こちら側に橋をかけるべきだ」という彼らの判断が受け入れられやすく、数値化の進行が比較的抑えられていました。
日本でも同じような問題があるように思います。イノベーション政策に限った話ではありませんが、政府や専門家への信頼が揺らいでいるように感じます。
企業の社会的責任への関心
- なぜ研究者を志したのでしょうか。
父が大学院卒のエンジニアだったこともあり、何となく自分も大学院に進もうと考えていました。しかし友人に就活くらいしておけと言われて、それもそうかと思っていた矢先、1990年代半ばに総会屋の問題など企業の不祥事が立て続けに起きたのです。会社のためを思って行われた不正も少なくなかったのですが、会社のためにそこまで強いられるのは不健全だと感じました。
一橋大学の修士課程では、水俣病を研究テーマにしました。水俣病の原因が有機水銀の廃水によるものと認識した後も、なぜ新日本窒素肥料(以下、新日窒)はアセトアルデヒドの生産を続けたのか、その背景を分析しました。
アセトアルデヒドの生産が続けられた理由の一つには、石炭化学(カーバイド)から石油化学への技術転換が背景にあります。新日窒は石油化学工業への進出を計画していたのですが、当時、海外からの技術導入には通商産業省(通産省)の許可が必要でした。通産省は、企業間で技術導入計画が競合した場合には、既存製品の生産シェアを許可の基準の一つとしており、それが新日窒の生産活動に影響したのではないかと考えました注4。
「清水、お前は島流しだ!」
- その後、ノースウェスタン大学(米国)とLSE(英国)に進学されています。海外留学のきっかけを教えてください。
指導教官だった米倉誠一郎先生はボストンに御自宅があって招待していただいた折、『組織は戦略に従う』を書いたアルフレッド・チャンドラー先生とお話しする機会があったのです。ペーペーの私にもどんな研究をしているのかとか、優しく聞いてくださったのですが、英語ではぜんぜん答えられなくて。将来、チャンドラー先生のような多くの人に注目されるような研究をするには、留学した方がいいと痛感しました。米倉先生には、「清水、お前は島流しだ!」みたいなことも言われました。いま考えると、米国の方が大陸ですよね。
- 米国と英国で何か違いはありましたか。
米国は研究の流行がとても早いです。私が専攻していた歴史学も流行がなさそうにみえてあります。その当時は、ミシェル・フーコーに感化された認識を問うような話とか、アイデンティティがどのように形成されるのかとか、そういった研究がすごく流行していました。経済学に対するアンチテーゼでもあったのでしょうね。
LSEでは、実証的な経済史の研究も盛んでした。英国は米国と違って流行りに疎いというか多様性があります。米国は流行に敏感である反面、注目されない分野はすぐになくなってしまうので研究の多様性が失われがちです。
今後の研究の展望
- 今後の研究テーマについて教えてください。
1つ目は、経営資源の流動性が高まると、イノベーションのパターンにどのような影響が出るのかという研究です。
2つ目は、汎用性の高い技術がどのように生まれるのかに関する定量的な研究です。これまでレーザーや蒸気機関というようなケースを扱ってきたのですが、より網羅的に研究できないかと考えています。例えば、いろいろな異なる分野で引用されている汎用的な特許(技術)がどのように発明され、それがどのような科学によって支えられているのかを明らかにします。
- NISTEPにはどのような調査研究を期待されますか。
やはり、日本のナショナル・イノベーション・システムを検討するということではないでしょうか。過去に実施されてきた政策が大学などにどのような影響を及ぼしてきたのかを総括する、あるいは政策の効果を検証するということが求められていると思います。
(キーワード:イノベーション、基礎研究、研究キャリア、スタートアップ、リスキリング、インタビュー日:2025年2月3日、早稲田大学清水研究室)
※本記事は、インタビュー対象者個人の見解を幅広い観点からまとめたものであり、インタビュー対象者の所属組織やNISTEPの公式見解ではない点も含まれます。
* 所属はインタビュー当時
注1 受賞対象となった著書は、「General Purpose Technology, Spin-Out, and Innovation: Technological Development of Laser Diodes in the United States and Japan」(Springer, 2019)である。日本語版に『ジェネラル・パーパス・テクノロジーのイノベーション 半導体レーザーの技術進化の日米比較』(有斐閣,2016年)がある。
注2 清水洋(2024)『イノベーションの科学 創造する人・破壊される人』,中央公論新社.
注3 2020年における企業部門のTop10%補正論文数は157件であった。全体に占める割合は4%(大学等部門は75%)であり、1995 年頃から低下傾向がみられる(村上昭義・西川開・伊神正貫「科学研究のベンチマーキング2023―論文分析でみる世界の研究活動の変化と日本の状況―」,調査資料,No.329,文部科学省科学技術・学術政策研究所,2023.DOI: https://doi.org/10.15108/rm329)。
注4 清水洋(2000)「新日本窒素肥料株式会社の石油化学工業への進出と水俣病問題―目的と手段の非一貫性」,『経営史学』,第35巻第2号,pp.75-94.


