- PDF:PDF版をダウンロード
- DOI: http://doi.org/10.15108/stih.00041
- 公開日: 2016.09.25
- 著者: 林 和弘
- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.2, No.3
- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)
ほらいずん
OECD グローバル・サイエンス・フォーラム(GSF)の新潮流と日本の役割:OECD 松原 太郎 政策分析官インタビュー
経済協力開発機構(OECD)は、経済・社会分野において多岐にわたる活動を行っている国際機関である。本部はパリに設置されており、特に、経済政策・分析、規制制度・構造改革、貿易・投資、環境・持続可能な開発、ガバナンス、及び非加盟国協力などの分野において活発な活動を行っている1)。近年では、グローバル環境における持続可能で包摂的な成長に向け、OECDにおける科学技術イノベーション分野の活動に関心が集まっている。
本記事では、2016年1月から、OECDグローバル・サイエンス・フォーラム(Global Science Forum:GSF)事務局に出向している松原太郎政策分析官(科学技術・学術政策研究所(NISTEP)前企画課長)に、OECD/GSFについて紹介いただき、最近の活動やグローバルな課題解決において果たす役割、情報通信技術(ICT)の発展に伴う対応、そして日本の貢献についてお話を伺った。(文中の組織名や肩書は2016年6月現在のもの)
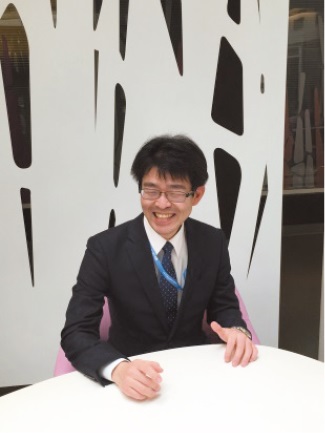
松原 太郎 OECD/GSF政策分析官
― OECDとは、どのような組織なのでしょうか。
OECDは、第二次世界大戦で荒廃した欧州の経済を支援するための米国によるマーシャル・プランの受入れ機関として設立された欧州経済協力機構(OEEC)が元となって、1961年に設立された国際機関です。日本は、1964年にOECD加入し、現在は、34か国がOECDに加入しています。
OECDは、欧州の政策フォーラムのようなところだと言われます。確かに、加盟国の8割程度が欧州及び北米の先進国(1人当たりのGDPが4~5万ドル程度)で占められています。他の国際機関と比べ、OECDは、2,500名のスタッフを擁する「世界最大のシンクタンク」として、様々な政策トピックについて議論・提言しているところに特徴があります。経済政策・分析や構造改革、税制、科学技術イノベーション、教育からエネルギー・原子力まで、ほとんどの政策分野の議論を網羅しています2)。
私が所属している科学技術イノベーション局(DSTI)では、科学技術政策に加え、ICT政策や消費者政策、造船に関する政策等の幅広い政策分野を取り扱っています。科学技術政策については、科学技術イノベーションが経済成長に果たす役割や研究体制の強化、国際的な研究開発協力の在り方等について検討を進めるとともに、日本の科学研究統計調査も準拠している研究開発統計調査のガイドラインであるフラスカティ・マニュアル3)の策定・改定等の科学技術政策に有用な指標の開発やデータの収集・分析も行っています。
― 松原分析官が従事しているOECD/GSFの活動について教えてください。
GSFは、OECDの科学技術政策委員会(Committee for Scientific and Technological Policy:CSTP)の下に設置されています。加盟国間の科学技術協力を促進し、科学技術政策を向上させることを目的としたフォーラムです。28か国と欧州連合(European Union:EU)がメンバーとなっており、さらにOECD加盟国外からも7か国が参加しており、全体の6割を欧州の国が占めています。欧州以外では、日本のほか、米国、オーストラリア、韓国、イスラエル等が参加しており、OECD加盟国外からは、中国や南アフリカ等が参加しています。
GSFでは、CSTPと同様、1年に2回、春と秋に定期会合が開催され、GSFの下の各プロジェクトの提案・立ち上げ、進捗状況、今後のGSFの方向性や各国の科学技術政策の動向について報告・議論されます。現在は、議長及び4名の副議長が、GSFの議事の管理を行っており、日本から、永野博氏(NISTEP元所長)が、議長を務めています。
GSFは、1992年に、OECD加盟国や関係する国々の間で、巨大な研究インフラ(RI)の運営や国際協力を議論するため、メガ・サイエンス・フォーラム(MSF)として発足しました。このため、90年代には、高エネルギー物理学分野の研究インフラや、中性子源、遺伝子工学のような個別の専門分野の議論を行うテーマが取り上げられていました。
このMSFにおいて、次第に研究インフラにとどまらず、より広い科学技術政策の課題について議論するようになり、その役割を明確にするため、1999年にGSFと名前を変えました。このような背景を踏まえ、2000年代になると、科学教育や研究不正のような科学技術政策一般に関するテーマも進められるようになりました。
最近では、2014年に就任したカッセージ・スミス事務局長の下、GSFの役割として、
① 研究システムの強化に向けた政策の発展
② 効果的な国際連携及び協力の推進
③ 地球規模課題の解決に資する研究に向けた効果的な政策の推進
④ 科学への国民参加や信頼醸成、政策決定・推進に向けた科学的知見の活用
という四つの優先順位の高いテーマを定め、各国の取組を紹介・議論しつつ、報告書や勧告を取りまとめています。現在GSFの下で進められている八つのテーマのうち、「研究インフラの持続可能性」や「宇宙素粒子国際フォーラム」のような研究インフラ等に関するテーマが進められる一方、「競争的研究資金システム」のような科学技術政策一般に関するテーマも進められています。日本からは、「研究インフラの持続可能性」では、井口聖 国立天文台教授が共同議長を務めているとともに、「宇宙素粒子国際フォーラム」でも、鈴木洋一郎 東京大学教授と戎崎俊一 理化学研究所主任研究員が参加しています。
2016年5月に開催された第34回GSF会合では、新たに、「研究インフラの社会・経済的インパクト」と「危機的状況下における科学的助言」の二つのテーマが採択されました。後者は、これまで、有本建男 科学技術振興機構(JST)研究開発戦略センター(CRDS)副センター長が共同議長を務めるなど、日本も大きく貢献している「政策形成のための科学的助言」のフォローアップ・プロジェクトです4)。
― 2016年1月に閣議決定された第5期科学技術基本計画でも、ICTの発展に伴う対応が重要な政策課題として取り上げられていますが、OECD/GSFでは、どのような取組が行われていますか。
OECDでも、ICTの発展に伴う「デジタル化」への対応は、非常に重要なテーマです。2015年10月に韓国で開催されたOECD/CSTP閣僚級会合(日本からは、島尻科学技術政策担当大臣及び冨岡文部科学副大臣が出席しました)で採択された「テジョン宣言」5)において、デジタル技術の急速な進展が、科学技術イノベーションを革新していることから、オープンサイエンスに向けた政策を進めていくことが合意されました。さらに、2016年6月に開催されたOECD閣僚理事会の閣僚声明6)でも、「デジタル化とイノベーションの利益の享受」の文脈の中で、テジョン宣言のコミットメントが再確認されました。
このようなOECD全体の動向を踏まえ、GSFでも、2015年11月の第33回会合で、オープンサイエンスに関する二つのテーマが採択されました。一つ目のテーマは、個別のデータインフラの持続可能性に焦点を当てた「データ・リポジトリ注1のための持続可能なビジネスモデル」です。1年半程度の期間で、世界中のデータ・レポジトリを調査し、有用なビジネスモデルを明らかにするとともに、経済的な分析を行う予定です。もう一つのテーマは、データインフラの国際的な協調やネットワークに焦点を当てた「オープンサイエンスに向けたデータインフラの国際的協調」です。国際的なネットワークに関するケース・スタディを通じ、国際的な協調に必要な特性を明らかにしていく予定です。
GSFでは、それぞれのオープンサイエンスに関するテーマに関して、報告書を取りまとめ、国際的なスタンダードに向けた勧告(Recommendation)を示す予定です。このようなテーマに対し、日本からも、それぞれ、林和弘上席研究官(NISTEP)及び村山泰啓研究統括(情報通信研究機構)を中心に積極的に議論や調査に参画するなど、多大な貢献を頂いています。
― OECD/GSFでの取組を通じ、気付いたことを教えてください。
まず、OECDの科学技術イノベーション政策の方向性は、欧州における重層的な議論を、ある程度反映していることが挙げられます。欧州各国でも、それぞれ科学技術イノベーション政策が立案されています。それに加え、欧州連合(EU)においても、欧州各国が集まり、欧州で共通する科学技術イノベーション政策が議論されています。また、科学者レベルでも、スイスにある欧州原子核研究機構(CERN)注2や、パリに事務局がある国際科学会議(ICSU)注3のような欧州に立地する国際・地域機関で問題意識を共有することができます。
このような重層的な議論や人的交流を通じ、共同で進めるべき課題に関するコンセンサスが生まれてきます。このうち、グローバルに進めるべき科学技術政策に関する課題については、OECD/GSFに提案されます。OECD/GSFにおける研究インフラやオープンサイエンスのプロジェクトにおいても、このような欧州の問題意識7)が反映されています。例えば、先ほど紹介した「データ・レポジトリのための持続可能なビジネスモデル」は、前述のICSUの下に設置された科学技術データ委員会(CODATA)注4等が中心となって提案し、現在、GSFとCODATAの共同プロジェクトとして運営されています。また、「オープンサイエンスに向けたデータインフラの国際的協調」も、ICSUの下に設置された世界科学データシステム(WDS)注5等が中心となって提案し、GSFとWDSの共同プロジェクトとして進められています。
二つ目として、OECDにおいても、競争的環境の下、緊張感を持って仕事が行われているということです。「300の求人に対して4万人もの応募者が集まるというのがOECDの例年の採用状況」8)とのことです。厳しい選抜を通して採用された職員が、5年後の任期更新に向け、しのぎを削って仕事をしています。また、一つのポジションに採用されても、自動的に昇進するわけではなく、空席のポストに、改めて応募する必要があります。このため、OECD職員は、厳しい競争の下、新たなポジションの獲得に向け、成果を達成し続けることが求められています。日本政府からOECDに派遣された場合でも、一定の成果を達成するためには、緊張感を持って業務に当たることが求められています。
なお、OECDでは、それぞれの職員に、職務に対する相当の決定権が委ねられており、迅速な意思決定が可能です。例えば、GSF事務局では、カッセージ事務局長と相談すれば、プロジェクトの進め方や人選まで、相当な部分を決めることができます。ただし、OECDと日本政府とでは、所掌業務もステークホルダーも異なります。各国との調整を通じて感じることは、それぞれの国の政府は、その歴史的背景によって、複雑で固有な行政システムを運営しており、それが対外政策にも反映しているということです。
最後に、GSF事務局を含め、科学技術政策課(DSTI/STP)では、ICT技術を積極的に使っていこうという姿勢があるということを挙げたいと思います。世界中の専門家とプロジェクトを進めていくためには、地理的な影響や時差もあり、ビデオ会議やIP電話等でのコミュニケーションが、積極的に行われています。また、OECDは、世界銀行注6と共同で、Innovation Policy Platform(IPP:https://www.innovationpolicyplatform.org/)というインターネットを使った双方向のシステムの開発・活用を進めています。IPPを通じ、インターネットによる情報発信から、専門家との情報交換や共同作業までを可能とするプラットフォームの構築を目指しています。このように、OECDの重要テーマである「デジタル化」が、日常業務の進め方にも反映されています。
― これからのOECD/GSFの課題とは、どのようなことだと思いますか。
OECD/GSFが、加盟国にとって価値のあるフォーラムで在り続けるためには、様々な加盟国が関心を持つことのできる適切な議題(アジェンダ)を、設定していく必要があります。欧州における重層的な議論を反映しているという話をしましたが、そればかりでは、EUとアジェンダが重複してしまいます。科学技術政策を議論するグローバルなフォーラムとして、米国やアジアを含め、様々な加盟国の関心を踏まえたアジェンダを設定し、議論を進めていく必要があります。また、日本としてもOECDへのインプットや国際イニシアティブに貢献する際に、国内の議論を組織的に行っていくことも重要です。
一方、グローバルな科学技術イノベーション政策の議論を進めていく上で、G7科学技術大臣会合のような国際的な枠組みと、更に連携・協力を進めていく必要があります。2016年5月に開催されたG7茨城・つくば科学技術大臣会合の「つくばコミュニケ」においても、「オープンサイエンスに関する作業部会を設置して、OECD やRDA といった国際機関等との連携を視野に入れたオープンサイエンスのポリシーの共有、インセンティブの仕組みの検討、公的資金による研究成果の利用促進のための優良事例の特定を行うこと」を支援することとされています9)。
また、OECDにおいても、オープンサイエンスをはじめとして、科学技術政策とイノベーション政策の両方にまたがる課題が重視されるとともに、指標等を用いたエビデンスに基づく分析が重要となっています。GSFにおいても、CSTPやその下に設置された科学技術指標専門家作業部会(NESTI)やイノベーション技術政策作業部会(TIP)との情報共有・連携を強化しつつ、プロジェクトを進めようとしています。
― 今後の日本の貢献について、期待をお聞かせください。
GSFでは、永野博NISTEP元所長が議長として全体をリードし、2013年から2015年まで行われた「科学的助言」プロジェクトや、現在進められている「科学技術ファンディング」プロジェクトにおいても、有本建男 JST/CRDS副センター長が共同議長を務めるなど、日本は、大きく貢献しています。また、文部科学省から、任意拠出金の拠出や、MSFの発足以来、継続して職員を派遣するなど(自分が10代目となります)、リソース面でも大きく貢献しています。さらに、2015年4月に設立された「温帯農業における共同研究ネットワーク(TempAg)」に向けた議論では、農林水産省所管の農業・食料産業技術研究所が積極的に加わるとともに、現在進行中の「グローバル・ヘルスのための治験イニシアティブ」では、厚生労働省を中心に議論に貢献しています。
このような日本からの貢献に加え、OECD/GSFの議論が、グローバルに意味のあるものとなるためには、アジアで高い科学技術レベルを達成している日本からのインプットが欠かせません。その意味でも、GSFのプロジェクトに、日本の専門家が多数参画することは、非常に有り難いことです。2017年末には、現在進められているプロジェクトの多くが終了する予定です。GSFの趣旨を踏まえた日本からの新たなプロジェクトの提案も歓迎されると思います。
最後に、OECDで勤務する大変貴重な機会を与えていただいた文部科学省、及び、このようなインタビューの機会を与えていただいたNISTEPに、心から感謝の気持ちを申し上げたいと思います。本日は、誠にありがとうございました。
参考文献
1)OECD(経済協力開発機構)の概要(外務省):http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oecd/gaiyo.html
2)OECD Homepage:http://www.oecd.org/about/
3)伊地知 寛博.科学技術・イノベーションの推進に資する研究開発に関するデータのより良い活用に向けて:OECD『Frascati Manual 2015(フラスカティ・マニュアル2015)』の概要と示唆(前編).STI Horizon.2016.Vol.2 No.3:http://doi.org/10.15108/stih.00047
4)OECD, “Scientific Advice for Policy Making, The Role and Responsibility of Expert Bodies and Individual Scientists,”2015:報告書全文(英語)は、以下のサイトを参照:
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5js33l1jcpwb.pdf?expires=1465480435&id=id&accname=guest&checksum=D662731254007B84A708DCBA67C580DE
概要の日本語訳は、以下のサイトを参照:http://www.oecd.org/sti/sci-tech/ScientificAdvice-Japanese.pdf
5)Daejeon Declaration on Science, Technology, and Innovation Policies for the Global and Digital Age:http://www.oecd.org/sti/daejeon-declaration-2015.htm
6)2016 Ministerial Council Statement “Enhancing Productivity for Inclusive Growth,” Paris, 1-2 June 2016:https://www.oecd.org/mcm/documents/2016-Ministerial-Council-Statement.pdf
(閣僚声明仮訳)http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000162565.pdf
7)村山 泰啓、林 和弘.欧州オープンサイエンスクラウドに見るオープンサイエンス及び研究データ基盤政策の展望.STI Horizon.2016.Vol.2 No.3:http://doi.org/10.15108/stih.00044
8)OECD邦人職員インタビュー:宮迫純 人事部戦略ビジネス分析グループ長:
http://www.oecd.emb-japan.go.jp/work/miyasako.html
9)つくばコミュニケ(仮訳)、G7 茨城・つくば科学技術大臣会合、2016 年5月15-17日:
https://www8.cao.go.jp/cstp/kokusaiteki/g7_2016/20160517communique_jp.pdf


