- PDF:PDF版をダウンロード
- DOI: https://doi.org/10.15108/stih.00378
- 公開日: 2024.09.25
- 著者: 赤池 伸一、酒井 朋子、藤田 健一
- 雑誌情報: STI Horizon, Vol.10, No.3
- 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)
特別インタビュー
文部科学大臣科学技術顧問・量子科学技術研究開発機構
理事長 小安 重夫 氏インタビュー
-国立研究開発法人の役割と未来:
好奇心と自主性が育む科学技術の新時代-
科学技術予測・政策基盤調査研究センター 主任研究官 酒井 朋子
第2調査研究グループ 総括上席研究官 藤田 健一
研究者は、研究成果を創出することが最大の目的となるが、そのキャリア形成において、研究室を主宰運営するなどマネジメントに関わる経験を積むことが求められることもある。今回、ハーバード大学、慶應義塾大学、理化学研究所(理研)での研究活動に加えて、国立研究開発法人(国研)での研究組織を運営、現在は、文部科学大臣科学技術顧問及び量子科学技術研究開発機構(QST)の理事長を務める小安重夫氏にお話を伺った。
小安氏は、国研には、日本の科学技術研究を支え、「研究開発成果の最大化」に貢献することが求められているという。これまで所属した理研とQSTはいずれも世界最高水準の研究開発を推進するとともに、最先端の研究基盤施設や技術をアカデミアや産業界に提供する役割を担っている。また、人材の流動性の確保、産学連携や国際協力の推進の重要性、そのために魅力的な研究環境を整備することが必要である。最後に、小安氏は、自主性を持って研究や仕事を進めることの大切さを強調した。
研究者が自らの研究業績によりキャリアを積み重ね、その後、大学、研究機関等の組織のマネジメントに携わることは研究者のキャリア形成において重要なことである。COVID-19や生成AIの影響など、科学技術・イノベーションを取り巻く環境が目まぐるしく変わる中で、組織運営に当たっては、研究とマネジメントの双方の視点を得ることは不可欠である。今回、ハーバード大学、慶應義塾大学、理化学研究所(理研)での研究活動に加えて、国立研究開発法人で組織のマネジメントを担い、現在、文部科学大臣科学技術顧問及び量子科学技術研究開発機構(QST)理事長を務める小安重夫氏に、幅広い観点から話を伺った。

国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 理事長
小安 重夫氏
(NISTEP撮影)
(略歴)
理学博士(東京大学)。専門は免疫学。
1978年東京大学理学部生物化学科卒業後、公益財団法人東京都臨床医学総合研究所研究員、ハーバード医科大学ダナファーバーがん研究所病理学助教授、慶應義塾大学医学部教授、理化学研究所統合生命医科学研究センター長等を歴任。2015年より2023 年3月まで理化学研究所理事。2023年より量子科学技術研究開発機構理事長、文部科学大臣科学技術顧問に就任。
日本の科学技術研究を支える国立研究開発法人
国立研究開発法人(以下、国研)は、日本の科学技術研究を支えるために重要です。国研は、国が設定する研究目標の実現に向けた研究開発を推進するとともに、国研だけではなく、大学や産業界等に、科学技術の進展に貢献する研究開発技術基盤を提供し、多岐にわたる研究開発を支援する役割を担っています。国研が掲げる「研究開発成果の最大化」を目指し、基礎研究から応用研究まで研究者が高い水準の研究開発成果を創出することを可能にしています。
例えば、以前に所属し、研究担当の理事を勤めていた理研は、大学に近く、研究室単位で構成されている組織であるとともに、非常に大規模な基盤施設を用いた研究プロジェクトを推進しています。また、SPring-8、富岳、RIビームファクトリー(RIBF)といった世界最高水準の大型の実験施設を有しています。これらの施設は国内外のアカデミア研究者や産業界に共用しており、多様な研究ニーズに応える役割を果たしています。SPring-8は、世界最大級の放射光施設であり、材料科学、生物学、化学などの分野で幅広く利用されています。富岳は、世界最高水準のスーパーコンピュータとしてシミュレーションやデータ解析において多くの研究者に利用されています。またRIBFは、不安定核の生成と研究において世界最高水準の装置であり、核物理学の最前線での研究を可能にしています。
現在、理事長を務めているQSTもまた、世界最先端の研究開発を推進するとともに、先進的な技術開発に立脚した世界最高水準の実験施設、研究開発技術基盤を構築しています。前身となる放射線医学総合研究所が世界で初めて開発、実用化したがん組織のみを高精度で攻撃可能な重粒子線によるがん治療、エネルギー問題解決に向けた取組となるフュージョンエネルギー研究、仙台に新たに整備し共用を開始した3GeV高輝度放射光施設NanoTerasuなど、国内外からの高い期待が寄せられています。いずれも、世界に誇る技術力に基づくすばらしい成果です。日本の科学技術の推進を支える科学技術基盤、特に、一研究室や大学では整備することが難しいような大型研究開発技術基盤を開発、整備、提供する役割を担っていると強く感じています。
さらに、QSTでは、国の戦略等に基づき中核と指定を受け、量子技術イノベーション拠点(量子技術基盤拠点及び量子生命拠点)、フュージョンテクノロジー・イノベーション拠点、基幹高度被ばく医療支援センター、脳神経科学統合プログラム、NanoTerasuでの研究開発を推進しています。
現在27 ある国研は、日本の科学技術の未来を担う重要な機関であり、その役割と特徴は多岐にわたります。いずれも先進的な研究を支え、新しい知見と技術を生み出し、それを社会に還元することで、日本の科学技術の発展に貢献することが期待されています。
多様な分野の研究開発を担う国立研究開発法人
QSTは、旧放射線医学総合研究所(放医研)、日本原子力研究開発機構のフュージョンエネルギー研究と量子ビーム・レーザー研究に関わる組織を前身として2015年に設立された研究機関であり、異なる背景、文化が融合しています。最大の魅力は、量子科学技術研究を柱に、エネルギー開発から医学・医療研究まで幅広い研究開発を推進し、それに必要な量子ビーム施設、フュージョンエネルギー施設、研究病院など多彩な大型研究開発施設群を有することです。唯一無二の大型研究開発施設群を開発し、維持し、そして供用できることが大きな特徴です。大型施設群はQST内での研究開発のみならず大学や他機関にも利用されており、国内外を問わず他機関の研究者から非常に高い評価を受け、その必要性を問われることも多く、正に国研に求められる「研究開発成果の最大化」に多大な貢献をしています。世界最先端かつ高性能の大型研究開発施設群とその基盤技術を活用して、QSTと国内外の研究者の協創や施設供用により、量子科学技術のみならず幅広い分野で世界を牽引するという大きなミッションを担っています。もちろん、研究人材、特に、技術系の人材、エンジニアの育成という役割も担っています。
QSTでは、発足後、分野を超えて、その前身で培われた研究成果を最大限に活かした連携を進め、発展させ研究成果につなげてきています。
重粒子線によるがん治療研究は、「量子メス」と称し、レーザー加速技術や核融合研究で使用する超伝導磁石を用いることで、多くの病院に整備導入するに当たって最大の課題である重粒子を回転加速させる円形加速器の小型化を進めるとともに、マルチイオン源による精度の高い治療法の開発に取り組んでいるほか、骨軟部腫瘍への治療を開始しました1)。保険適用の拡充にも取り組み、多くのがん患者への期待に応えていきます。重粒子線治療用の加速器は、医療分野にとどまらず、その装置の安定性から、国内外の物理学者からも非常に高い評価を受け、最先端の研究に活用されています。
NanoTerasuにも加速器の小型化技術は応用されています。NanoTerasuでは、その高い技術力により、当初の計画より前倒しての整備を実現、また、初ビームが加速器内を回周するという偉業を達成しました2)。2024年4月より、官民地域パートナーシップという新たな枠組みのもと運用を開始、成果の創出が期待されています。
そして、人類社会の最難の課題であるエネルギー問題を解決する取組となるフュージョンエネルギー研究を推進、国内の中核として核融合超伝導トカマク型実験装置JT-60SAを開発、2023年ファーストプラズマの発生に成功しました3)。世界7極により人類初の核融合実験炉を実現する超大型国際プロジェクトITER 計画においても非常に重要な役割を担っています。
発足後に新たに設定した量子生命科学研究は、量子力学的な現象が生命現象にどのように関与しているかを解明する新しい基礎研究分野です。現在、学会も発足し、世界的にも非常に注目されています。例えば、ダイヤモンド結晶に閉じ込められた「量子センサ(NVセンター)」4)を用いて、細胞内の微小な磁場や電場の変化を検出し、細胞内の量子現象を測定するための新しい技術の開発や、量子もつれを利用した光量子技術による、古典理論の限界を超えた飛躍的に高い感度を持つ量子センシング技術の開発などが進められています。生態機能を担っている酵素反応は常に常温常圧で起こります。同じ温度・圧力で全ての反応が起きているということは化学の見地から驚異的です。それを可能にする構造的、システム的な特性を、量子の視点で説明することができるのであれば、新たな現象の解明も可能になると期待されています。
科学技術・イノベーション政策に関する現状と課題:研究環境・産学連携・国際協力
科学技術イノベーション関連の政策には、統一的かつ長期的な展望からの検討が必須です。科学技術の分野細分化が進んだ結果、分野融合、横断的な取組の重要性が謳われるようになって久しい一方、政策や戦略は個別の検討に終始し、全体最適になっていないと感じています。国として、全体を俯瞰した上で、さらには、短期的な視点ではなく、長期的な検討に基づく科学技術の推進を図り、限りある研究資源を投じ、最大のアウトプットにつなげる必要があります。
研究環境の整備という観点では、研究者が研究活動に集中できる環境を提供することが重要です。研究費の獲得に向けた申請準備、特に、研究課題の検討、設定は、研究者にとって非常に重要なことである一方、書類の作成過程での作業負荷は大きく、書式の統一、自動入力など、効率化を図るべきだと感じます。科学技術研究関連の予算が増えることは非常に重要ですが、新たな事業や研究費が増える一方、優れた事業であってもその継続性が担保されない、研究者にとってそれぞれの特性がわかりづらく最適な申請に至らないなど状況になっていることを懸念しています。そして何より、研究費の特性にもよりますが、短期的な成果を求める報告や評価が、研究の発展を妨げている場合があると感じます。十分な審査を経て採択をしている以上、助言は必要となりますが、基本的には、その実施や成果創出までの過程を研究者に委ねるという判断も大切だと思います。
人類社会が抱える課題解決に向けた社会導出、イノベーションの創出は、研究開発の目標であり、そのために基礎的な研究が必須なことは論を俟ちません。国は、十分に基礎研究を支援する必要があります。
研究人材の育成、確保については、若手研究者が活躍できる環境、人材が流動しやすい環境の整備が喫緊の課題であり、ポジションの確保、研究費の獲得、共用可能な実験装置や研究施設の整備のいずれにおいても、世代交代を促す仕組みも検討する必要があります。特に、頭脳循環、人材の流動化には、日本固有の退職金や年金の制度が障害になっています。キャリア形成において、組織を超えた異動によりプロモーションをすることが求められているにもかかわらず、待遇として不利益を被ることになります。研究者にかかわらず、優秀な人材にとって日本が魅力的な国であり、活躍できる国であるために、日本社会全体として見直すべきです。
また、人材育成と技術の継承のため、国は主導的かつ計画的に、世界最先端となる唯一無二の大型研究基盤施設を一定期間ごとに高度化・アップグレードするべきです。私はこれを〝式年遷宮〟と称していますが、古来、各社殿を20年に一度、造り直す過程が、関わる宮大工の世代の更新、技術継承に大きな意義があり、後継が育成されました。同様の仕組みが、大型研究基盤施設にも必要です。
産学連携や国際協力の推進においては、仕組みや制度の整備はもとより研究者を含めた社会全体としての意識の醸成が何より大切です。経済安全保障の視点からも、予算措置支援だけではない支援、研究者の理解増進を進め、世界の潮流を見極めた最適な推進により国際的にも認められる科学技術立国として発展してほしいと思います。
新時代の科学技術研究を担う皆様へのメッセージ
私自身は、研究者としてのキャリアを積む一方で、研究室の主宰者から始まり、国研で研究センターのセンター長、理事、そして、現在の理事長と、マネジメントを担ってきています。研究室の規模では難しい大規模プロジェクトの企画立案から実施、さらには、自分の専門分野に限らず国研として戦略目標に応じた計画の策定、若手人材育成を含め研究環境整備、研究者のキャリアパス検討など、貴重な経験をしています。マネジメント職に就いたあとも、研究を続けたことは、研究現場の状況を知り、研究者としての感覚を維持して反映してきているという点で非常に有益でした。私にとっては、両者は対立するのではなく相乗的なものであり、どちらか一方を選択しなかったことが良かったのだと思います。
将来の科学技術を担うみなさんには、様々なことに好奇心を抱き、自らの興味を追求、本当にやりたい研究や仕事を見つけてほしいと思います。そして、失敗を恐れずに挑戦すること、自ら考え、判断して行動することを期待しています。その自主性は、研究や仕事に前向きに取り組み続けるためにとても大切な自信となり支えになります。私は常々、「希望のあるところに成功は訪れる」と言っております。希望を持って自分の道を進んでいただきたいと思います。
社会は減点方式ではなく、加点方式であるべきです。失敗による減点を恐れて、やらないという判断は研究開発とは対極であり、衰退、退化を意味します。たとえ最善の答えでなくても、みなさんには大切な仲間がいて、挑戦すること、自ら判断することを何より尊重し、助けてくれるということを忘れないでください。
(キーワード:科学技術イノベーション政策,研究とマネジメント,国立研究開発法人,量子科学技術研究開発機構,理化学研究所、インタビュー日:2024年 6月19日)
※本記事は、インタビュー対象者個人の見解を幅広い観点からまとめたものであり、インタビュー対象者の所属組織やNISTEPを代表するものではない。
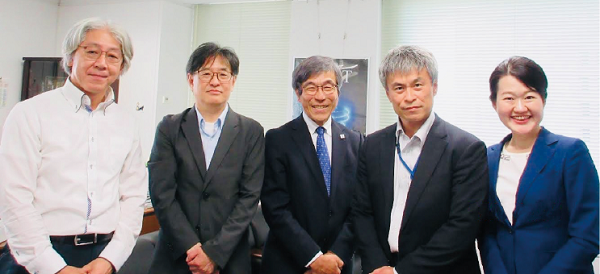
左からNISTEP 林、赤池、藤田、酒井(NISTEP撮影)
参考文献・資料
1) 世界初となるマルチイオンを用いた重粒子線がん治療を開始
~骨軟部腫瘍のような難治性がんの治療効果の向上に期待~. https://www.qst.go.jp/site/press/20240315.html
2) Status of beam commissioning at NanoTerasu.
https://accelconf.web.cern.ch/ipac2024/doi/jacow-ipac2024-tupg40/
3) World’s Largest Experimental Fusion Reactor Generates First Plasma in Japan.
https://www.science.org/content/article/first-plasma-fired-world-s-largest-fusion-reactor
4) 大島武. SiC 結晶中の単一光子源を利用した量子デバイス. 2021. 応用物理 90, 351-354.


