特許出願数の国際比較を困難にしている点の一つが、特許は属地主義であり、発明を権利化したいと考える複数の国に対して出願がなされる点である。このため、ある国Aからの特許出願を数える際、複数の国への特許出願を重複してカウントしている可能性がある。また、ある国Aへの出願を考えると、国Aからの出願が最も大きくなる傾向(ホームアドバンテージ)がある。
これらの特許出願の特徴を踏まえ、国際比較可能性を向上させるために、ここではパテントファミリーによる分析を行う。分析には、EPO(欧州特許庁)のPATSTATを用いた。また、パテントファミリーの分析方法の詳細については、本章の最後のテクニカルノートに示した。パテントファミリーとは優先権によって直接、間接的に結び付けられた2か国以上への特許出願の束である。通常、同じ内容で複数の国に出願された特許は、同一のパテントファミリーに属する。したがって、パテントファミリーをカウントすることで、同じ出願を2度カウントすることを防ぐことが出来る。つまり、パテントファミリーの数は、発明の数とほぼ同じと考えられる。
また、パテントファミリーをカウントすることで、特定の国への出願ではなく、世界中の特許庁への出願をまとめてカウントすることが可能となる。特許出願数の国際比較の際に、PCT出願数が利用されることが多いが、PCT出願はある国から海外への出願の一部を見ているに過ぎない。各国から生み出される発明の数を、国際比較可能な形で計測するという点で、パテントファミリーを用いた分析は、各国の技術力の比較を行う上で有用な指標と考えらえる。
以下では、2つの値を示す。一つはパテントファミリー数(2か国以上への特許出願)に1か国のみへの特許出願数(単国出願数)を加えた数であり、もう一つはパテントファミリー数である。ここでは前者を「パテントファミリー+単国出願数」、後者を「パテントファミリー数」と呼ぶ。パテントファミリーは、発明者や出願人が居住する国以外での権利化を目指して、2か国以上に出願していると考えられ、単国出願よりも価値が高い発明と考えられる。
図表4-2-3にパテントファミリー+単国出願数とパテントファミリー数の時系列変化を示す。1981年に41.2万件であったパテントファミリー+単国出願数は2009年を境に急激な増加を見せた。2019年には減少したが、2020年では増加し2021年では213.3万件となった。パテントファミリー数は1981年に5.7万件、2020年には27.4万件となった。パテントファミリー+単国出願数に占めるパテントファミリー数の割合は、1980年代は13%程度であった。その割合は2000年代半ばにかけて10ポイント程度上昇したが、その後は低下傾向にあり、2020年は12.9%となっている。
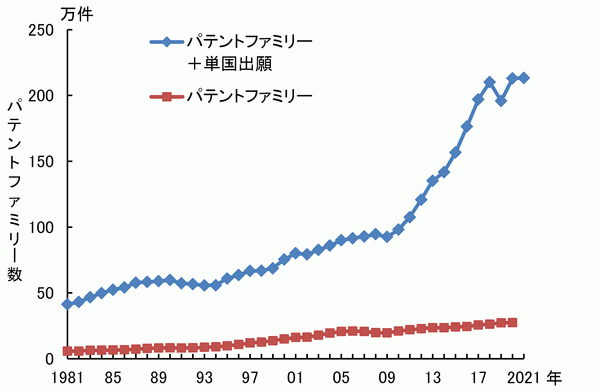
注:
パテントファミリーの分析方法については、テクニカルノートを参照。
資料:
欧州特許庁のPATSTAT(2024年秋バージョン)を基に、科学技術・学術政策研究所が集計。
参照:表4-2-3
図表4-2-4に、主要国のパテントファミリー+単国出願における単国出願と複数国出願の割合を示す。日本に注目すると1980年代の前半は約95%が単国出願であった。1980年代半ばから複数国出願の割合が徐々に上昇し、2020年時点では68.3%が単国出願、31.7%が複数国出願である。
米国については、2020年時点で、単国出願が55.6%、複数国出願が44.4%である。時系列による変化は小さい。
英国については、長期的に複数国出願の割合が上昇傾向にあるが、フランス、ドイツについては2000年代半ばからおおむね横ばいである。この3か国の中で、複数国出願の割合が一番高いのはフランスであり、2020年時点で61.7%である。
中国と韓国における複数国出願の割合は、それほど高くない。年によって割合に揺らぎがあるが、2020年時点で中国は3.2%、韓国は17.8%である。中国については、国内のみへの出願が増加した影響で、複数国出願の割合が減少している。
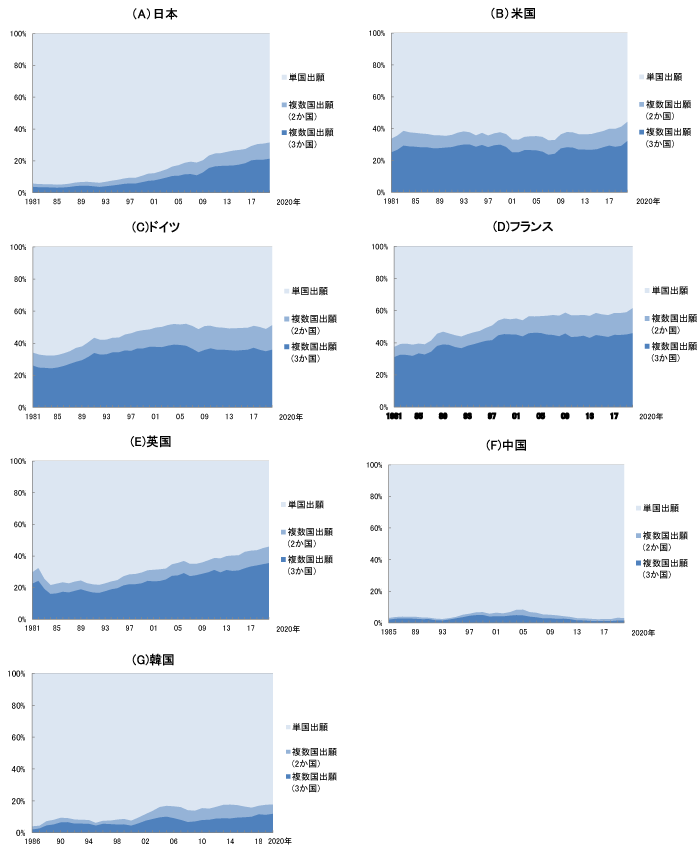
注:
パテントファミリーの分析方法については、テクニカルノートを参照。
資料:
欧州特許庁のPATSTAT(2024年秋バージョン)を基に、科学技術・学術政策研究所が集計。
参照:表4-2-4


