図表3-5-1では、日本における外国人大学院生について、上位10位までの国・地域と主要国に注目したが、10位以降においてもアジアの国・地域が多く出現している。それではアジアの学生は日本の大学院でどのような分野を専攻しているのだろうか。
本コラムではASEAN諸国に注目し、日本の大学院における学生の専攻分野を見る。
(1) 専攻分野別外国人大学院生の割合
まず、外国人学生全体の専攻分野別のバランスを見ると(コラム図表3(A))、2024年度において最も多くを占めているのは「その他」(27%)である。次いで、「工学」系が24%、「社会科学」系が18%、「科目等履修生・聴講生・研究生」が9%、「人文科学」系が8%である。2000年度と比較すると、「その他」、「工学」系は増加し、「社会科学」系、「科目等履修生・聴講生・研究生」、「人文科学」系は減少している。
(2) ASEAN諸国の専攻分野別大学院生の割合
次に、外国人学生数が上位5のASEAN諸国について専攻分野野別のバランスを見る。
インドネシアでは(コラム図表3(B))、2000年度において「工学」系が39%と大きく、次いで「農学」系が19%、「社会科学」系が12%を占めていた。2024年度では「工学」系が35%、「農学」系が11%、「社会科学」系が9%と減少した。これに対して、大きく増加したのは「その他」であり19%を占める。
ベトナムでは(コラム図表3(C))、2000年度において「工学」系が31%と大きく、次いで「社会科学」系が20%、「農学」系が12%を占めていた。2024年度では「工学」系が25%、「社会科学」系が18%、「農学」系が6%となり、いずれの割合も減少した。これに対して、大きく増加したのは「その他」であり26%を占める。
タイでは(コラム図表3(D))、2000年度において「工学」系が35%と大きく、次いで「科目等履修生・聴講生・研究生」が15%、「社会科学」系が14%、「農学」系が13%を占めていた。2024年度では「工学」系が33%、「科目等履修生・聴講生・研究生」が11%、「農学」系が9%となり、2000年度と比較して減少した。「社会科学」系は横ばいである。これに対して、大きく増加したのは「その他」であり16%を占める。また、「保健(医・歯学)」系は4%から7%に増加している。
フィリピンでは(コラム図表3(E))、2000年度において「農学」系が22%と最も大きく、次いで「工学」系が16%、「科目等履修生・聴講生・研究生」が14%、「その他」が12%、「社会科学」系が11%、「理学」系が10%を占めていた。2024年度では「工学」系、「社会科学」系、「その他」が大きく増加し24%となった。「社会科学」系は対象国の中でも最も大きい。これに対して、「農学」系が12%、「科目等履修生・聴講生・研究生」が6%、「理学」系が4%まで2000年度と比較して減少している。
マレーシアでは(コラム図表3(F))、2000年度において「工学」系が42%と大きく、これに次ぐ「社会科学」系の25%との合計で全体の約7割を占めていた。2024年度では「工学」系が40%、「社会科学」系が14%に減少したが、「工学」系の割合は対象国の中で最も大きい。


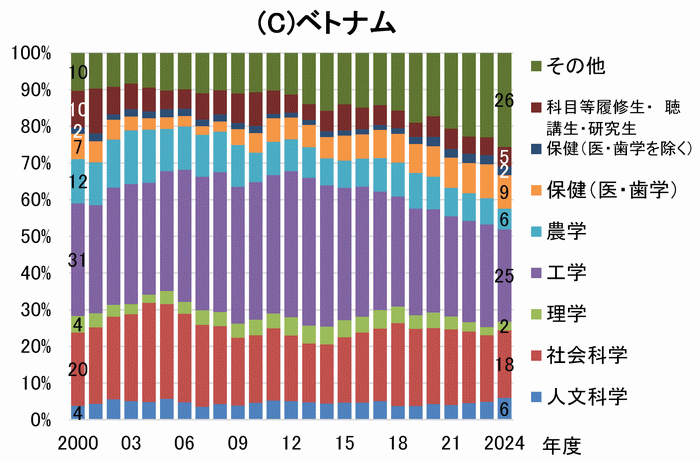
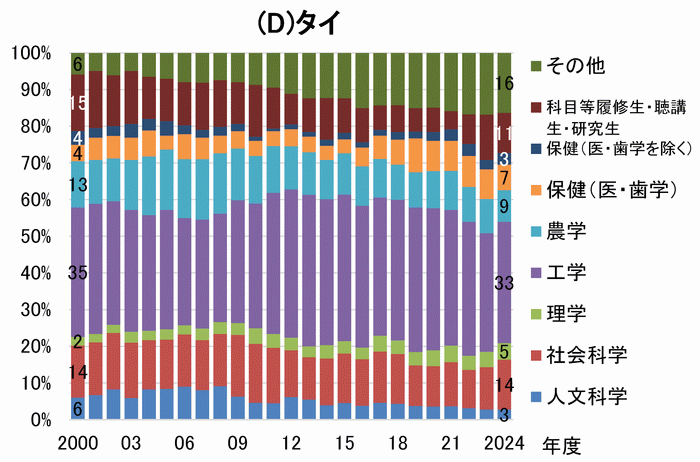
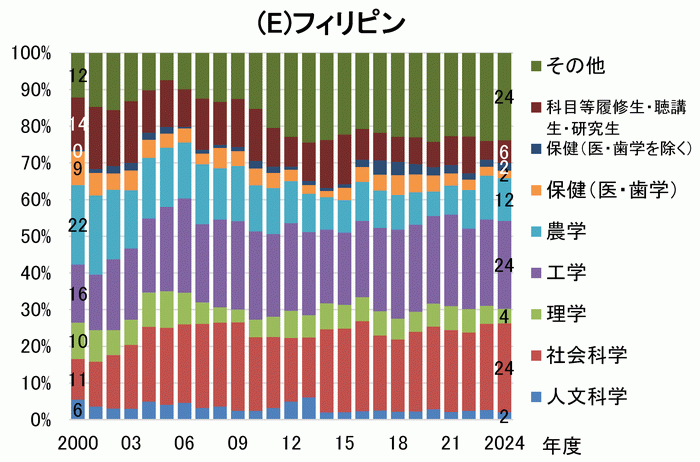

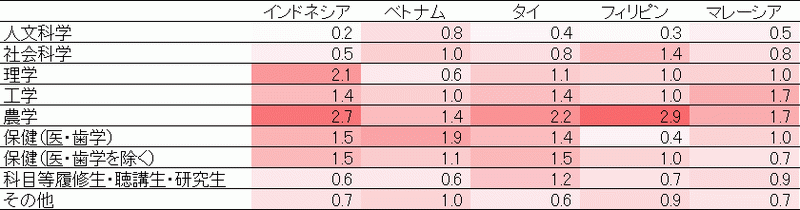
注:
1) 科目等履修生(当該大学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者)・聴講生・研究生には正規の大学院生ではない短期留学の学生を含む。
2) 特化係数=各国の専攻分野の構成比/全世界の専攻分野の構成比
資料:文部科学省、「学校基本調査報告書」
参照:コラム表3
(3) まとめ
日本の大学院における外国人学生の専攻分野は「工学」系が多いが、「社会科学」系を専攻する学生も一定数いる。また、「その他」が増えている。
ASEAN上位5か国については、全世界と比較して、「農学」系が大きい傾向にあったが、2000年度から2024年度にかけて、その割合は多くの国で減少している。また、「工学」系が多くを占めている国が多く、マレーシア、インドネシアは約4割をキープしている。
各国の専攻分野について特化係数を見ると(コラム図表3(G))、「農学」系の特化係数が最も大きい国が多い。ASEAN上位5か国の学生数は「工学」系が多いが、専攻分野のバランスという面では「農学」系に集中している国が多い。
コラム4:大学院の研究科名:学科系統分類表の大分類「その他」の変遷について
大学院入学者数の項で見たように専攻別の内、「その他」については長期的に入学者数が増加している。そこで本コラムでは、学科系統分類表において大分類「その他」に分類される研究科名の意味的特徴を数値化・グループ化して、大分類「その他」がどのように発展したかを考察するとともに、その変遷と政府施策の関連性を検討した。
図表3-2-3等における専攻別大学院入学者数の専攻区分は、文部科学省の学校基本調査付属資料の「学科系統分類表」(以下、「分類表」)に基づく。分類表は、大分類で専攻分野を大まかに分け、中分類、小分類へと段階的に細分化する方式である。大分類「その他」の専攻数は2003年度に220件、2012年度に379件、2024年度に512件と増加傾向にある。
(1)研究科名の可視化
分析には2003年度から2024年度までの各年度の分類表を用いた。2024年度時点で分類表に記載される研究科名は512件である。ここでは、研究科名の持つ意味的特徴を定量的に分析するため、科研費「基盤研究(C)」(2015~2024年度)の研究課題名、キーワード、要旨を用いてMeta社が公開しているWikipediaベースの日本語版FastTextモデルに追加学習を実施した。その後、次元圧縮を行い学術的専門用語にも対応した100次元の単語分散表現を獲得した。
次に、研究科名を構成する各単語の分散表現を合成し(5)、研究科名全体の意味的特徴ベクトルを生成した。これにより、研究科間の意味的類似性をベクトル間距離として定量的に評価することが可能となった。そこで、k-means++法を用いて意味的類似性が高いと思われる6つのクラスタに分類した。
各クラスタについて、単語の出現頻度も加味して示したワードクラウドがコラム図表4-1である。このワードクラウドにより、クラスタの全体的傾向を概観できる。ただし、解釈は分析者の専門知識にも依存し、一意的ではないことには注意を要する。その上でクラスタの解釈を試みると、例えば、クラスタ1は「健康・スポーツ」、クラスタ2は「地域社会・文化」、クラスタ3は「情報・システム」を軸とした自然科学と人文科学の統合、クラスタ5は「国際関係」など、大分類「その他」の中の意味的な凝集性の存在がうかがえる。

注:
分類表中の研究科名を単語ごとに分割し、その特徴に基づいてクラスタリングした結果である。
資料:
文部科学省「学校基本調査(2003年度~2024年度)」付属資料「学科系統分類表」を基に、科学技術・学術政策研究所が作成。
(2)研究科名の変遷
分類表の研究科名変化をクラスタ別に整理したものをコラム図表4-2に示す。図表中でその年度を含む3年間で増加した研究科数が全体平均より大きい箇所を濃色で強調した。特に2018年度以降に注目すると、「地域社会・文化」のクラスタ2(2018~2021年度)および「情報・システム」のクラスタ3(2018~2023年度)で顕著な増加が観察された。
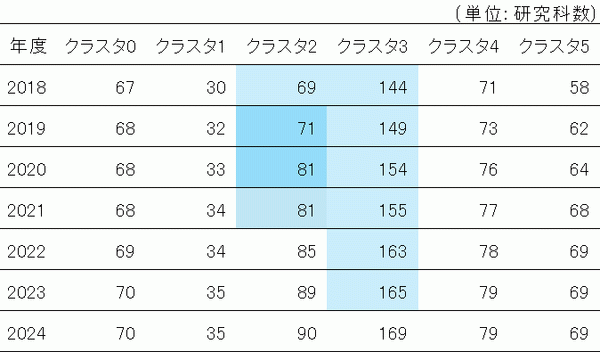
注:
該当年を含む3年間の増加数が平均より1σ大きい箇所に色をつけている。ここで、σは標準偏差を表す。
資料:コラム図表4-1と同じ。
参照:コラム表4-2
(3) 政府施策との関係
「地域社会・文化」のクラスタ2と「情報・システム」のクラスタ3について具体的な増加研究科名を示したものがコラム図表4-3である。クラスタ2では「地域創生」など「地域」を冠した地域連携型と思われる研究科が目立つ一方、クラスタ3ではデータサイエンス系研究科や分野横断的と考えられる研究科(創発科学、マス・フォア・イノベーションなど)が増加している。
これら研究科の具体的かつ詳細な内容はシラバスを参照する必要があるものの、例えば、分野横断型・地域連携型研究科の増加は、「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン(答申)(2018年11月26日中央教育審議会)(6)」(以下、「グランドデザイン」)において、分野横断的なコースワークの充実や大学の研究機能が地方創生に重要な役割を担うと記載された時期と一致する。本分析では因果関係や相関関係を確認していないが、各大学がグランドデザインに呼応して新たな研究科設立を行った可能性も示唆される。また、分野横断型研究科の増加は第5期科学技術基本計画(2016年1月閣議決定)(7)での人文社会科学や自然科学の知の総合的活用、第6期科学技術・イノベーション基本計画(2021年3月閣議決定)(8)での「総合知」の記載時期とも一致する。さらに、地域連携型研究科の増加は「まち・ひと・しごと創生総合戦略」(2014年12月閣議決定、「第2期」2019年12月閣議決定)(9)との時期的重なりがある。分野横断・地域連携といった研究科を既存の分類表に記載することの困難さから、分類表の大分類「その他」にカテゴライズされている可能性もある。また、2020年以降のデータサイエンス系研究科の増加は社会的要請を反映した可能性も考えられる。グランドデザインではクラスタ5に該当すると思われる国際連携の重要性も言及されているが、本分析の範囲では顕著な研究科数増加としては観察されなかった。
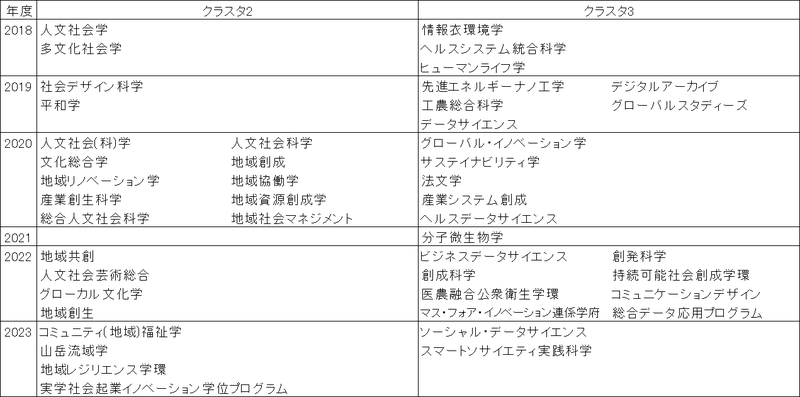
資料:コラム図表4-1と同じ。
参照:コラム表4-3
(4) まとめ
本コラムでは、学科系統分類表で大分類「その他」に分類される研究科名を意味的特徴から分類・解釈し、その変遷と政府施策の関連性を検討した。分析対象が研究科名というわずかな情報に限定されるため、政策や社会情勢との因果・相関関係を明確に示すことは困難である。しかしながら、新規研究科設立と政策動向や社会背景との関連性が示唆された。また、新研究科が既存分類を横断するため、大分類「その他」への分類が進んだ可能性も示唆された。
(5)この際、精度向上のため「学」「環」など単独で意味を持たない語や約150件の学科名に共通する「科学」を除外した。
(6)2040年に向けた高等教育のグランドデザイン
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1411360.htm
(7)第5期科学技術基本計画
https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index5.html
(8)第6期科学技術・イノベーション基本計画
https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index6.html
(9)まち・ひと・しごと創生総合戦略
https://www.chisou.go.jp/sousei/mahishi_index.html


