
研究開発活動の基本的な指標である研究開発費について、日本及び主要国(米独仏英中韓)の状況を概観する。研究開発費とは、ある機関で研究開発業務を行う際に使用した経費であり、研究開発活動のインプットに関する定量データとして広く用いられている。本章では、各国の研究開発費の総額や部門別、性格別などの内訳、研究開発費の負担構造など、様々な角度から研究開発費のデータを見ていく。また、政府の科学技術予算についても一部記載している。
1.1各国の研究開発費の国際比較
ポイント
- 日本(OECD推計)の研究開発費総額は、2023年(令和5年)において20.4兆円であり、対前年比は6.9%増である(日本:22.0兆円、対前年比6.5%増)。
- 日本(OECD推計)の研究開発費総額の対GDP比率は2008年までは長期的に増加していたが、その後、増減を繰り返しつつ漸増し、2023年では3.42%となった(日本では3.70%)。主要国中、第1位である韓国では、経済規模が拡大すると同時に研究開発費総額の対GDP比率も大きく上昇している(2023年:4.96%)。米国についても2015年から2023年にかけて、0.7ポイント増加した(2023年:3.45%)。
- 各国の負担部門から使用部門への研究開発費の流れを見ると、いずれの国でも「企業」の負担割合が大きく、ほとんどは同部門の「企業」に流れている。ただし、ドイツ、英国、中国については、「大学」への研究開発費の流れが他国と比較すると大きい。
- 「政府」からは、「公的機関」及び「大学」に研究開発費が流れている国が多く、「大学」に最も多く流れている国は、日本、ドイツ、フランス、英国である。「政府」から「企業」への流れはほとんどの国でそれほど大きくはないが、米国、フランス、英国、韓国では「政府」の約2割が企業に流れている。
1.1.1各国の研究開発費の動向
はじめに、主要国の研究開発の規模とその傾向を概観するために、各国の研究開発費の総額を取り上げる。研究開発費の調査方法については、国ごとに差異があり、厳密な比較は困難であるが、国ごとの経年的変化は各国の動向を表していると考えられる。なお、各国の研究開発費を比較するためには通貨の換算が必要である。しかし、その換算によって、その国の経済状況の影響を受けることは避けられない。ここでは、原則的に、各国の研究開発費の規模を国際比較するときは換算値を使用し、各国の研究開発費の経年変化を見るときは各国通貨を使用した。
日本の研究開発費については2つの値を示した。一つは総務省「科学技術研究調査」が発表している値、もう一つはOECD(1)が発表している値である。両者で異なる点は大学部門の人件費の取扱いである。大学部門の経費は研究と教育を厳密に分けることが困難であるという背景があり、「科学技術研究調査」における大学部門の研究開発費は、大学の教員の人件費部分に研究以外の業務(教育等)分を含んだ値となっている。他方、OECDは日本の大学部門の人件費部分を研究専従換算にした研究開発費の総額を発表している(詳細は1.3.3項、大学部門の研究開発費を参照のこと)。
この項ではOECDが発表しているデータ(図表では「日本(OECD推計)」と示す)も使用し、各国の研究開発費の状況を見る。
主要国における研究開発費の名目額を見ると(図表1-1-1(A))、日本(OECD推計)の研究開発費総額は、2023年(令和5年)において20.4兆円である。長期的には増加傾向にあり、対前年比は6.9%増である(日本:22.0兆円、対前年比6.5%増)。
米国は世界第1位の規模を保っている。長期的に増加傾向が続いており、2023年では91.0兆円であり、対前年比は6.2%増である。
中国は2000年代に入ると急激な伸びを見せた。2023年では87.4兆円である。対前年比は13.8%増と主要国中最も伸びており、米国に迫る勢いである。
ドイツは長期的に増加傾向が続いている。2020年に一旦減少したものの2023年は17.1兆円、対前年比は3.7%増である。
英国は、以前のMain Science and Technology Indicators (MSTI)に掲載されていた値と比較して大幅に改訂されかつ暫定値となっている。これは、英国国家統計院(ONS)が2022年11月に発表した研究開発統計において、「企業」部門の研究開発費と研究者数、「大学」部門の研究開発費の推計値が大幅に上方修正されたことによる。これらの変更は、研究開発を実施する企業のサンプリングが不十分であったこと(2)を考慮した数値の再調整と、高等教育機関への支出に関する包括的な管理データの採用(3)を反映している。これらの変更のため、英国の研究開発費については、科学技術指標2022以前の数値とは異なることに留意されたい(改訂された数値については、企業は2014年以降、大学は2018年以降がMSTIに掲載されている)。これらの理由により、英国は2014年以降の値を示している。2022年は10.5兆円、対前年比は6.5%増である。
フランスは漸増傾向である。2023年では8.3兆円、対前年比は3.4%増であり、主要国中、最も伸びが小さい。
韓国は長期的に大きく増加している。2023年では13.7兆円、対前年比は5.0%増である。
物価水準の変化を考慮した研究開発費を見ることのできる実質額(4)で見ると(図表1-1-1(B))、主要国の順位に変動はない。なお、今般の報告書からOECDのデータ変更を踏まえ物価水準の基準年を2015年から2020年に変更した。
次に、2000年からの研究開発費の変化に注目する。2000年を1とした場合の各国通貨による研究開発費の名目額と実質額を指数で示し、各国における研究開発費の伸びを見る(図表1-1-1(C))。
名目額での各国最新年を見ると、日本(OECD推計)は1.3、日本では1.4であり、他国と比べて伸びは小さい。他国を見るとフランスは2.0、ドイツは2.6、米国は3.6の伸びである。中国は37.2、韓国は8.6と大きな伸びを見せている。
実質額での各国最新年を見ると、日本(OECD推計)及び日本は1.4と名目額よりも大きな伸びである。フランスの伸びは1.4であり、日本と同程度である。ドイツは1.7、米国は2.1である。中国、韓国については、物価補正を考慮しても、それぞれ18.1、5.4と大きな伸びを見せている。
(A)名目額(OECD購買力平価換算)
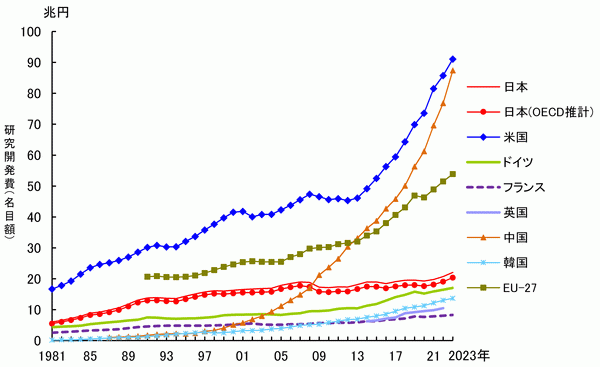
(B)実質額(2020年基準;OECD購買力平価換算)

(C)2000年を1とした各国通貨による研究開発費の指数
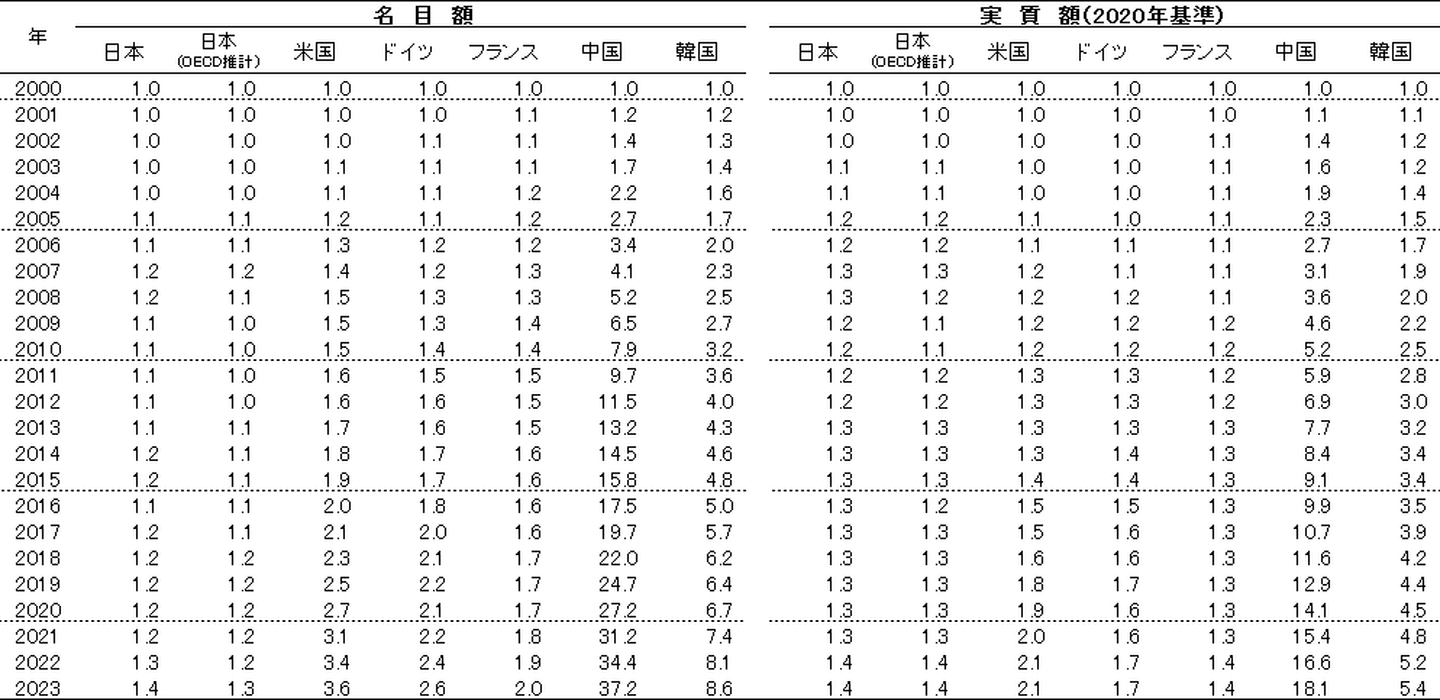
注:
1) 研究開発費総額は各部門の合計値であり、国により部門の定義が異なる場合があるため、国際比較の際には注意が必要である。各国の部門の定義については図表1-1-4参照のこと。
2) 研究開発費は人文・社会科学を含む(韓国は2006年まで自然科学のみ)。
3) 1990年までは西ドイツ、1991年以降は統一ドイツ。
4) 購買力平価換算は参考統計Eを使用した。
5) 実質額の計算はGDPデフレータによる(参考統計Dを使用)。
6) 日本は年度の値を示している。
7) 日本(OECD推計)は1995年までOECD基準に合うように、当該国の値をOECD事務局が調整。大学部門については、研究開発費のうち人件費を研究換算にした総研究開発費である(「1.3.3大学部門の研究開発費」を参照のこと)。1996、2008、2013、2018年において時系列の連続性は失われている。
8) 米国は定義が異なる。1998、2003、2015、2016、2021、2023年において時系列の連続性は失われている。2023年は暫定値。
9) ドイツの1982、1984、1986、1988、1990、1992、1996、1998年は見積り値である。1993、1994年値は定義が異なる。2023年は暫定値である。
10) フランスは1997、2000、2004、2010、2014年においては時系列の連続性は失われている。2023年は暫定値である。
11) 英国は暫定値である。2014、2018年において時系列の連続性は失われている。2014~2018年は見積り値である。
12) 中国は1991~1999年までは過小評価されるか、過小評価されたデータに基づく。2000、2009年においては時系列の連続性は失われている。
13) EU-27は見積り値である。
資料:
日本:総務省、「科学技術研究調査報告」
日本(OECD推計)、米国、ドイツ、フランス、英国、EU-27:OECD,“Main Science and Technology Indicators March 2025”
中国:1990年まで中華人民共和国科学技術部、中国科技統計数値2013(webサイト)、1991年以降はOECD,“Main Science and Technology Indicators March 2025”
韓国:1990年まで科学技術情報通信部、KISTEP、「研究開発活動調査報告書」、1991年以降はOECD,“Main Science and Technology Indicators March 2025”
参照:表1-1-1
次に、各国・地域の経済規模の違いを考慮して研究開発費を比較するために、「研究開発費総額の対GDP比率」(国内総生産に対する研究開発費の割合)を示す(図表1-1-2)。
2023年における日本(OECD推計)の研究開発費総額の対GDP比率は、世界の中で見ると、比較的高い水準にあると言える。最も高い国はイスラエル、次いで韓国であり、イスラエルは6%を超えている。
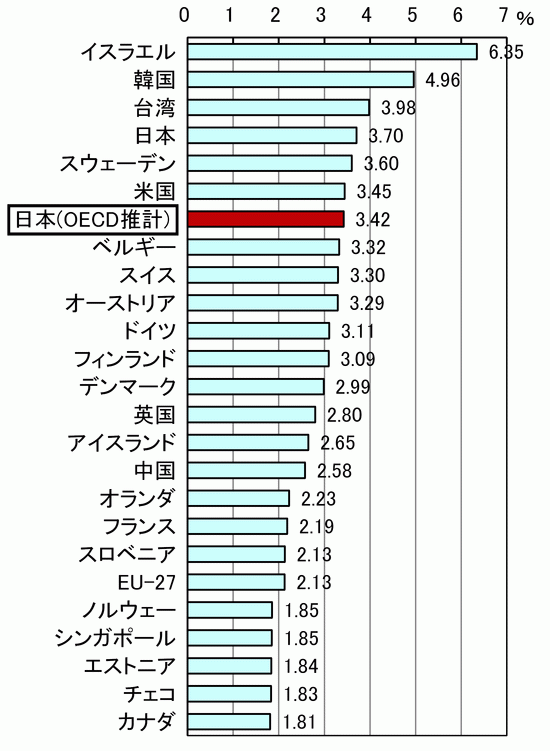
注:
1) スイスは2021年、英国、シンガポールは2022年、日本、その他の国・地域は2023年である。
2) イスラエル、EU-27は見積り値。
3) 米国、イスラエルは定義が異なる。
4) 韓国、米国、ベルギー、オーストリア、ドイツ、デンマーク、アイスランド、オランダ、フランス、スロベニア、ノルウェー、チェコ、カナダは暫定値。
資料:
日本:総務省、「科学技術研究調査報告」
その他の国・地域:OECD,“Main Science and Technology Indicators March 2025”
参照:表1-1-2
また、研究開発費総額の対GDP比率の経年変化により、主要国の研究開発への投資水準がどのように推移してきたかを見る(図表1-1-3)。
日本(OECD推計)は2008年までは長期的に増加していたが、その後、増減を繰り返しつつ漸増し、2023年では3.42%となった。また、日本の値についても同様の傾向にあり、2023年では3.70%である。主要国の中でも高い水準を保っている。
韓国は主要国中第1位である。2000年代に入ると急速に増加した。2023年では4.96%である。
米国は2010年代に入って、ほぼ横ばいに推移、2015年を過ぎると増加傾向となった。2023年は3.45%であり、日本(OECD推計)を上回っている。
ドイツは、1990年代中盤にかけて一旦減少した後、増加し続けていたが、近年は横ばいに推移している。2023年は3.11%である。
英国は数値を掲載している2014年以降、増加傾向にあったが、近年は減少している。2022年は2.80%である。
中国は、1996年を境に増加が続いている。2023年では2.58%である。2019年からフランスを上回っている。
フランスは1990年代後半から、ほぼ横ばいに推移している。2023年では2.19%である。
2000年以降の日本のGDPは一時的な減少も含め、微増に推移している一方で、他国のGDPは増加傾向にある(参考統計C参照のこと)。特に、韓国や中国では、経済規模が拡大すると同時に研究開発費総額の対GDP比率も上昇している。米国についても2015年から2023年にかけて、0.7ポイントの増加が見られる。
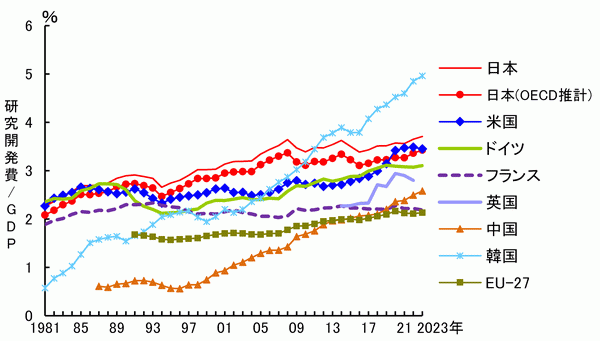
注:
国際比較注意及び研究開発費については図表1-1-1と同じ。GDPは参考統計Cと同じ。なお、日本のGDPは1993年まで1993SNAに基づいた数値であり、1994年以降は2008SNAに基づいているため、時系列比較をする際は注意が必要である。
資料:
研究開発費は図表1-1-1と同じ。GDPは参考統計Cと同じ。
参照:表1-1-3
1.1.2各国の部門別研究開発費の動向
国全体の研究開発のシステムを理解するためには、各国の研究開発活動の状況を部門別で見ることも必要である。
ただし、各国の部門分類については、研究開発活動を国際比較する際に、各国の制度、調査方法、あるいは対象機関の範囲に違いがあるため、単純な比較が困難になるという問題がある。よって各国の差を踏まえた上での比較をする必要がある。
この項では、研究開発活動を実施している機関を部門分類し、各国の違いを踏まえて研究開発費の構造を見る。
(1)研究開発費の負担部門と使用部門の定義
図表1-1-4は、研究開発活動を実施している機関を、OECD「フラスカティ・マニュアル(5)」に基づいた部門に分類し、研究開発費の負担部門(5部門)及び使用部門(4部門)に対応する各国の具体的な機関(内訳)を簡単に示したものである。図表中には、各国の研究開発統計及びOECDの資料等で使用されている名称を用いているが、表題の部門名は日本の研究開発統計である総務省「科学技術研究調査」で使用されている部門名を用いている。
(A)負担部門
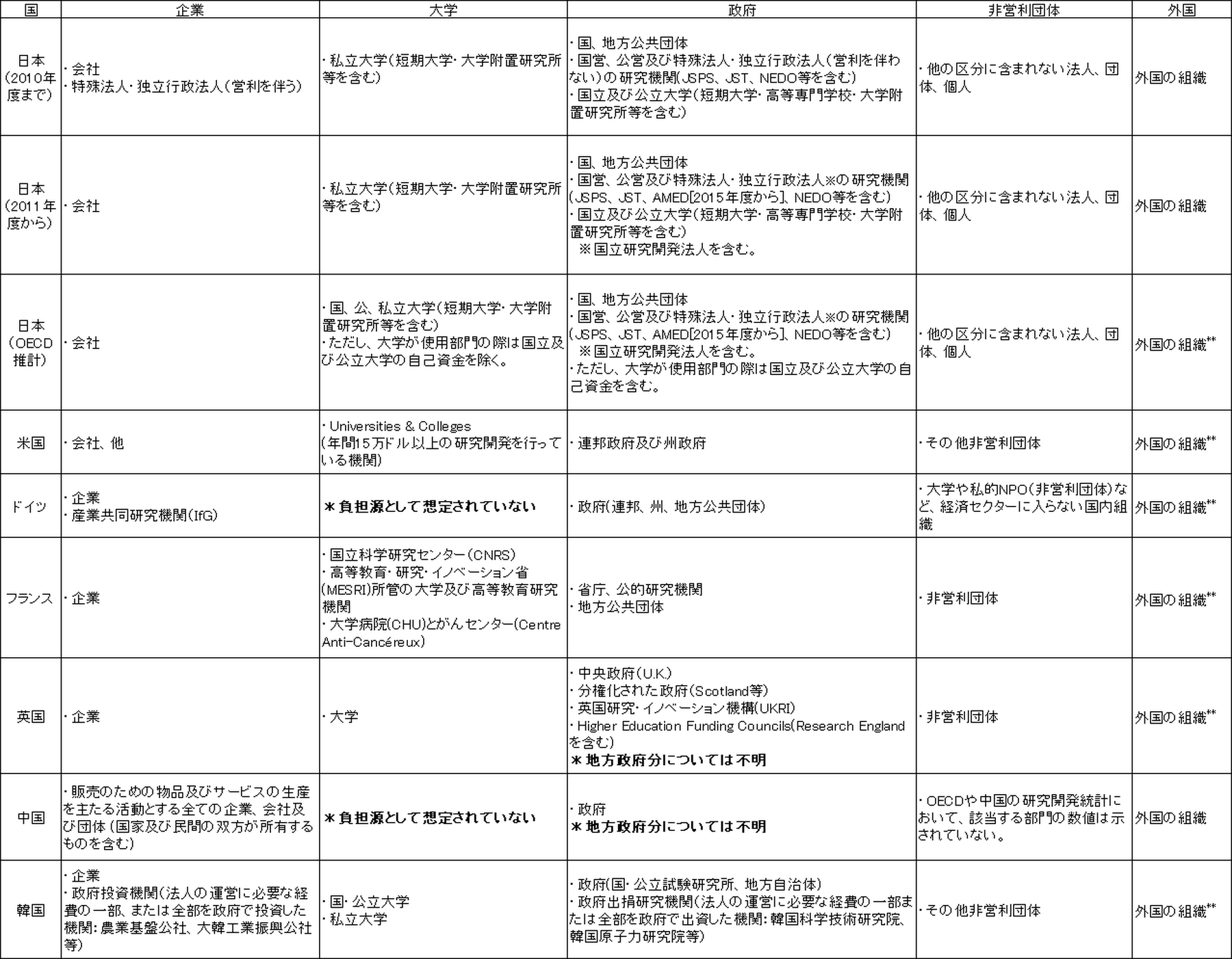
(B)使用部門
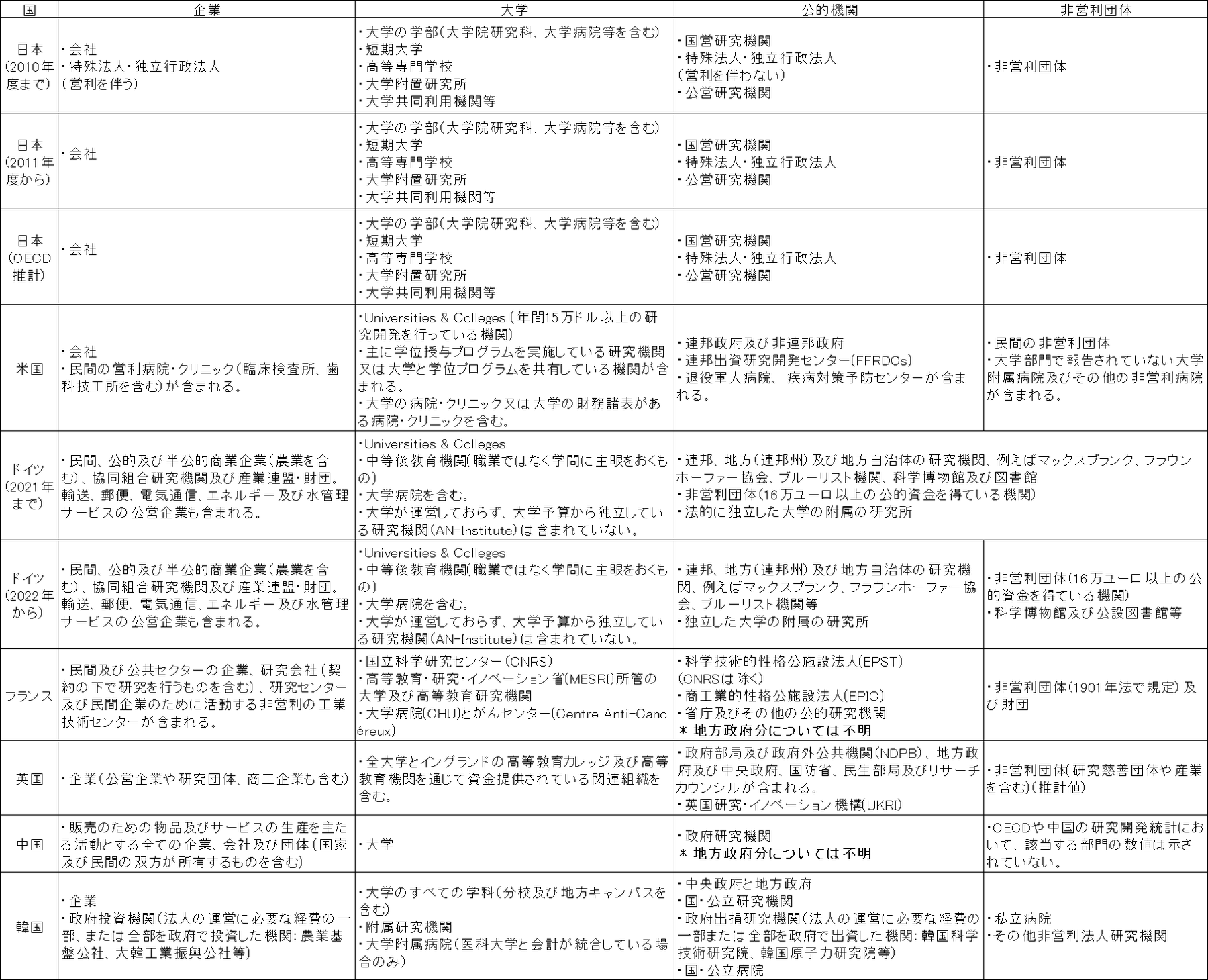
注:
1) 本表については適時更新しているが、各国の最新の情報ではない可能性がある。
2) EUについては各国の合計であるため、ここには記載しない。
3) 負担部門の外国のうち、「外国の組織**」についてはOECD,“Research & Development Statistics”の“Rest of the world (ROW)”を外国の組織とした。
4) 米国のFFRDCsとはFederally Funded Research and Development Center(連邦出資研究開発センター)である。
5) ドイツの負担部門に「大学」はない。IfGとはInstitutions for co-operative industrial research and experimental developmentである。
6) 中国の負担部門に「大学」はない。
資料:
科学技術政策研究所、「主要国における研究開発関連統計の実態:測定方法についての基礎調査」(調査資料-143)(2007年10月)
総務省、「科学技術研究調査報告」
NSF, “National Patterns of R&D Resources”
OECD, “R&D Sources and Methods Database”
Statistisches Bundesamt (Destatis) 2024
MESR, “Higher education & research in France, facts and figures”
科学技術情報通信部・KISTEP、「研究開発活動調査報告書」
(2)主要国の研究開発費の負担部門と使用部門
この項では、各国の研究開発費について、負担部門から使用部門へ、どのように配分されているか、また、どの部門でどの程度、研究開発費が使用されているのかを見る。図表1-1-5は各国の研究開発費を部門別の割合にし、その流れを見たものである。
負担部門、使用部門の内容については前述の図表1-1-4を参照されたい。負担部門、使用部門ともに、各国の制度や調査方法、対象機関の範囲に差異があるため、比較には注意が必要である。
各国の負担部門から使用部門への研究開発費の流れを見ると、いずれの国でも「企業」の負担割合が大きく、ほとんどは使用部門の「企業」に流れている。ただし、ドイツ、英国、中国については、「大学」への研究開発費の流れが他国と比較すると大きい。
「政府」については、「公的機関」及び「大学」に流れている国が多い。「政府」から「企業」への流れは、ほとんどの国でそれほど大きくはないが、米国、フランス、英国、韓国では「政府」の約2割が企業に流れている。
「大学」は、負担部門としての大きさはわずかである。特に、ドイツ、中国については負担部門に「大学」は想定されてない。また、日本の場合、負担部門としての「大学」は私立大学のみである。
「非営利団体」はいずれの国でも、その負担割合は小さいが、米国や英国では2%台である。
「外国」の負担割合は、日本、日本(OECD推計)、中国、韓国で小さく、欧米で大きい。
国ごとに見ると、日本については、「企業」から「企業」への研究開発費の流れが大きく、その他の部門にはほとんど流れていない。「政府」は「大学」への流れが大きいが、「公的機関」への流れも大きい。日本は、「大学」の負担割合が他国と比較すると大きい。なお、負担部門の「大学」は、私立大学であり、そのほとんどは使用部門の「大学」に流れている。この流れは、ほぼ私立大学の研究開発費の自己負担分である。
日本(OECD推計)では、「企業」間での研究開発費の流れが大きい。日本では負担部門の「政府」に分類されている「国・公立大学」は、日本(OECD推計)では大学部門に入っている。ただし、大学が使用する研究開発費のうち国・公立大学の自己資金は負担部門の「政府」に含まれる。「政府」からの研究開発費は「公的機関」への流れが最も大きい。
米国では、「企業」から「企業」への研究開発費の流れが大きい。「政府」から「公的機関」や「大学」への流れが約7割を占めるが、「企業」への流れも比較的大きい。また、「外国」からの流れはそのほとんどは「企業」へ向かっている。
ドイツでは、「企業」間の流れが大きいのは他国と同様であるが、他国と比較すると「企業」から「大学」や「公的機関・非営利団体」への研究開発費の流れが大きい。特に「企業」からの流れに占める「大学」の割合は、主要国の中でも大きい(使用側の「大学」で見た「企業」の負担割合は13.1%)。
フランスでは、負担部門のうち「企業」の割合が56.3%と、他国と比較すると最も小さい。その一方で「政府」の負担割合は32.0%であり、他国と比較して最も大きい。また、「外国」の負担割合が比較的大きく、そのほとんどは「企業」へ流れている。
英国は負担部門のうち「企業」の割合が61.9%と、他国と比較すると小さい傾向にある。「非営利団体」の割合は2.6%、「外国」の割合は8.4%であり、いずれも他国と比較すると最も大きい。「外国」の研究開発費は、多くが「企業」に流れているが、「大学」にも他国と比べると多く流れている。使用部門の「大学」は、他国と比較すると最も大きい割合である。
中国では「企業」の負担割合が大きく、そのほとんどが「企業」へ流れている。また、「企業」から「大学」への流れも大きく、「大学」が使用する研究開発費の31.5%を負担している。「政府」負担の研究開発費は「公的機関」に最も多く流れている。使用部門としての「大学」と「公的機関」を比較すると、後者の割合が顕著に大きい。
韓国では、「企業」の負担割合が大きく、そのほとんどが「企業」へ流れている。次いで「政府」の負担割合が大きく、その約4割は「公的機関」に流れている。また、「大学」への「政府」の負担割合も大きく、「大学」が使用する研究開発費の約8割を「政府」が負担している。
(A)日本(2023年)
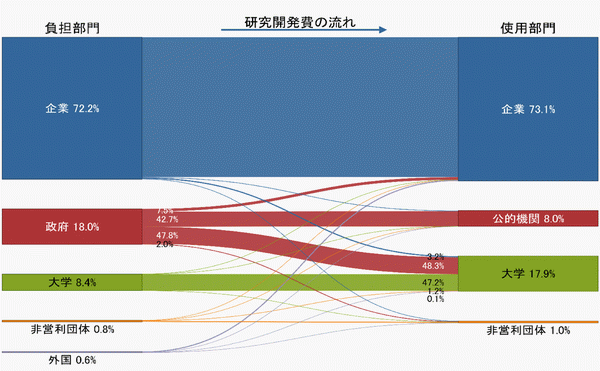
(B)日本(OECD推計)(2023年)

(C)米国(2023年)
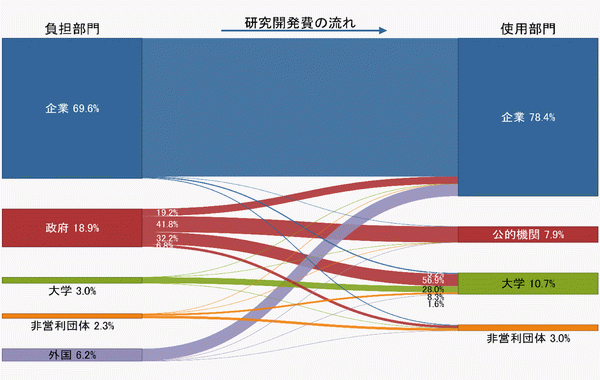
(D)ドイツ(2021年)
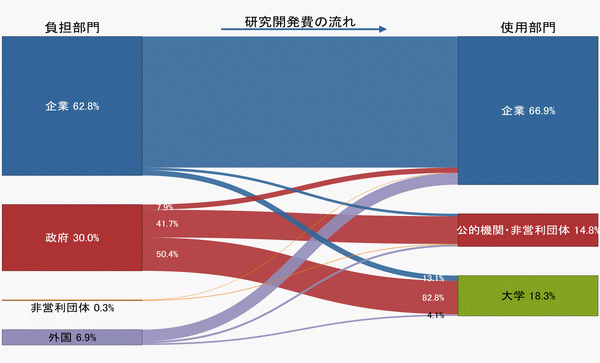
(E)フランス(2022年)
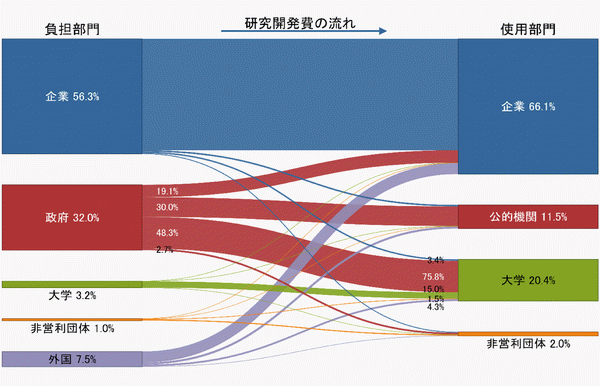
(F)英国(2022年)

(G)中国(2023年)
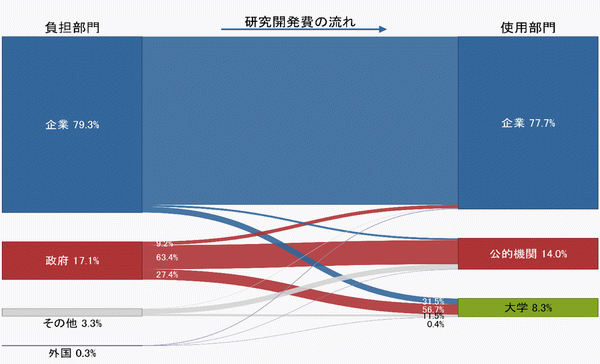
(H)韓国(2023年)
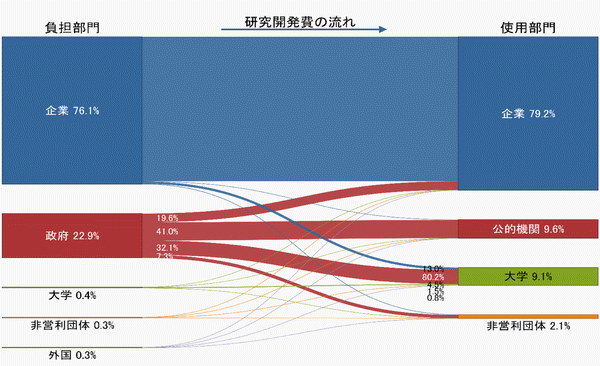
注:
1) 負担・使用部門については図表1-1-4を参照のこと。
2) 日本の負担側の政府には、国公立大学を含む。負担側の大学は私立大学である。日本(OECD推計)の負担側の政府、大学は見積り値である。負担側の大学は国公私立大学である。ただし、政府から大学の負担には、国・公立大学の自己資金を含む。
3) 米国は暫定値である。企業の使用者以外は定義が異なる。企業の使用者は見積り値であり、別のカテゴリーのデータを含む。
4) ドイツの公的機関は非営利団体を含む。
5) 英国の非営利団体の使用者は見積り値。
資料:
日本:総務省、「科学技術研究調査報告」
その他の国:OECD,“Gross domestic expenditure on R&D by sector of performance and source of funds”
参照:表1-1-5
(3)主要国の使用部門における研究開発費の推移
図表1-1-6は主要国の総研究開発費の使用額を部門別に分類し、その割合の推移を示したものである。
各国とも「企業」部門が一番大きな割合を示している。最新年の使用割合は、日本、ドイツ、フランス、英国は約7割、日本(OECD推計)、米国、中国、韓国は約8割を占めている。
日本の場合、1981年では6割であった「企業」部門の割合が7割まで増加する一方で、その他の部門は減少しつつある。ただし、2000年代に入ってからは部門間のバランスに大きな変化はない。
日本(OECD推計)は、「大学」部門の人件費分を研究専従換算した研究開発費を使用しているため、「大学」部門の割合が日本のデータと比較すると小さくなっている。なお、新規のFTE調査結果が反映された場合、その都度データが変化することに留意が必要である。前述した日本と、他の部門の推移については同様の傾向である。1981年と比較すると「企業」部門が6割台から8割に増加し、「大学」部門は2割から1割に減少している。
米国については、「企業」部門の割合は増減がありながらも長期的に見れば7割で推移していたが、2010年代に入り増加し始め8割となった。「大学」部門は、2004年までは漸増し、その後は横ばい、2010年代に入って漸減している。「公的機関」部門は、2000年代前半や後半に増加した時期もあるが、長期的に減少している。また、「非営利団体」部門は、小さいものの長期的に漸増傾向であったが、2000年代に入ると、ほぼ横ばいに推移し、近年は漸減している。
ドイツについては「公的機関」部門及び「非営利団体」部門の区分がされてなかったが、2022年から「非営利団体」部門についてもデータが取得できるようになった。1990年代に入ると、「企業」部門の割合の減少、その他の部門の増加が見られたが、その後、「企業」部門が増加し、それに伴い、他の部門は減少した。2000年代に入ってからは、各部門ともほぼ横ばいに推移していたが、「公的機関」部門については最新年では前述したように「非営利団体」部門と分離されたことにより数値が減少している。
フランスは、「公的機関」部門の割合が比較的大きな国であったが、その割合は長期的に減少している。「企業」、「大学」部門の割合は長期的に増加傾向にあった。ただし、「大学」部門については2010年代に入ってから横ばいに推移している。
英国は「企業」と「大学」の研究開発費の使用額が上方に改訂されている(1.1.1項参照)。このため科学技術指標2022以前の数値とは異なることに留意されたい。英国の研究開発費は「企業」部門が7割、「大学」部門が2割を占めている。「公的機関」部門については約5%と主要国中最も小さい。
中国は、1990年代には、「公的機関」部門が4~5割を占めていたが、1999年以降、減少傾向にある。これに代わって「企業」部門の割合は、1990年はじめの4割程度から、近年では約8割を占めるほどに増加している。また、「大学」部門より「公的機関」部門の使用割合が大きい。
韓国は、長期的に見ると、「企業」部門の増加、「大学」部門や「公的機関」部門の減少が見えていたが、2010年代後半頃からはほぼ同程度で推移している。
EU-27については、「公的機関」部門の割合が長期的に減少傾向にある。2010年頃まで、「大学」部門は微増、「企業」部門はほぼ横ばいに推移していた。その後、「大学」部門は微減、「企業」部門は微増している。



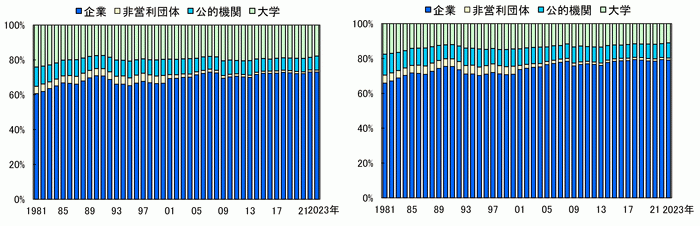

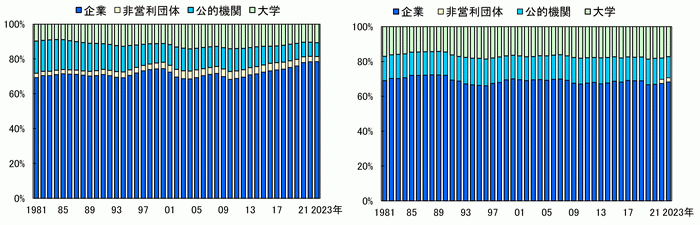

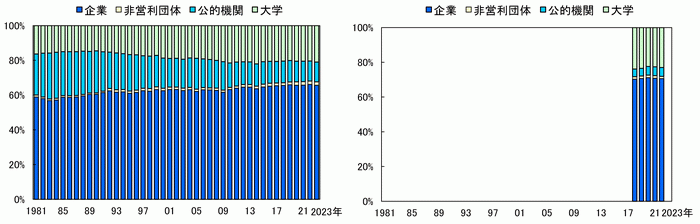
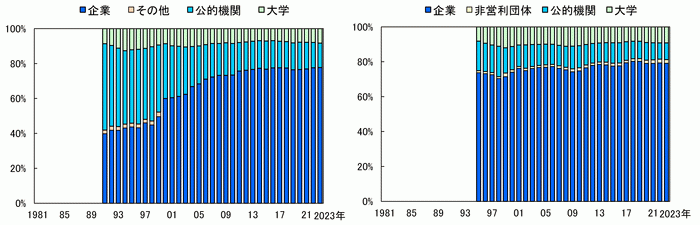
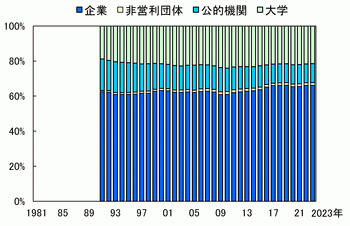
注:
1) 研究開発費総額は各部門の合計値であり、国により部門の定義が異なる場合があるため、国際比較の際には注意が必要である。各国の部門の定義については図表1-1-4参照のこと。
2) 研究開発費は人文・社会科学を含む(韓国は2006年まで自然科学のみ)。
3) 日本以外の国の非営利団体(中国は「その他」)は合計から企業、大学、公的機関を除いたもの。
4) 日本は年度の値を示している。
5) 日本、日本(OECD推計)は、2001年に、非営利団体の一部は企業部門になった。
6) 日本(OECD推計)は、1995年までOECD基準に合うように、当該国の値をOECD事務局が調整。大学部門については、研究開発費のうち人件費を研究専従換算した総研究開発費である。企業の1996年、大学の1996、2008、2013、2018年は時系列の連続性は失われている。
7) 米国の企業の2014年以前、大学、公的機関は定義が異なる。企業の2015、2016、2021、2023年、大学の1998、2003年、公的機関の2006年において時系列の連続性は失われている。企業の2023年は見積り値。大学、公的機関の2023年は暫定値。
8) ドイツは、1990年までは旧西ドイツ、1991年以降は統一ドイツ。公的機関については2021年まで非営利団体を含む。全ての部門の1982、1984、1986、1988、1990年、企業の1992、1994、1996、1998年、大学の1992年は見積り値である。企業、大学の1993年、公的機関の1991~2021年は定義が異なる。全ての部門の1991年、大学の2016年、公的機関の1992、2022年において時系列の連続性は失われている。2023年は暫定値である。
9) フランスは、企業の1992、1997、2001、2004、2006年、大学の1997、2000、2004、2014年、公的機関の1992、1997、2000、2010年において時系列の連続性は失われている。2023年は暫定値。
10) 英国は、大学の2018年、企業の2022年において時系列の連続性は失われている。企業の2018~2021年は暫定値である。
11) 中国は1991~1999年までは過小評価されるか、過小評価されたデータに基づく。 企業の2000、2009年、公的機関の2009年において時系列の連続性は失われている。
12) EU-27は見積り値である。
資料:
日本:総務省、「科学技術研究調査報告」
その他の国:OECD,“Main Science and Technology Indicators March 2025”
参照:表1-1-6
(1)経済協力開発機構(OECD)は、民主主義と市場経済を支持する諸国が①経済成長、②開発途上国援助、③多角的な自由貿易の拡大のために活動を行っている機関。現在38か国が加盟。国際比較可能な統計、経済・社会データを収集し、予測、分析をしている。
(2)英国の企業の研究開発統計であるONS, “Business enterprise research and development survey” では、これまで小規模の企業の捕捉率が小さかったとされている。
(3)英国ONSの資料によると、これまでの英国の大学部門の研究開発費のデータには、大学の内部で実施かつ資金提供されている研究開発や、研究開発にかかる一部の間接経費が含まれておらず、それらをデータに含めるようにしたとされている。これらの分析には、Office for Studentsが提供するTransparent Approach to Costing(TRAC)システムが使用されている。
(4)図表1-1-1(B)の場合、他国と共通の通貨価値で、物価水準の変化を考慮して研究開発費を見ることができる。物価水準の基準年は2020年であり、OECD購買力平価換算値は2020年値を使用している。
(5)研究開発統計の調査方法についての国際的標準を提示している。1963年、イタリアのフラスカティにおいて、OECD加盟諸国の専門家による研究・実験開発(R&D)の調査に関しての会合が行われた。その成果としてまとめられたのがフラスカティ・マニュアル-研究・実験開発調査のための標準実施方式案である。現在は第7版(2015)が発行されており、各国の研究開発統計調査はこのマニュアルに準じて行われていることが多い。

