ここでは、オープンアクセス(OA)論文の動向を見る。一般にオープンアクセスとは、論文がインターネット上で公開されており、無料で閲覧やダウンロードし、所定の条件のもとで再利用することが可能な状態のことを意味する。論文をOA化するには様々な方法があり、それに対応してOA論文の種類もゴールド、ハイブリッド、ブロンズ、グリーンに大別される(図表4-1-11)。これらのうちブロンズについては一時的に公開されている論文が含まれていることから、分析に用いるデータが作成された時期によって、その数は大きく変動し得る。このことから、本分析では、ブロンズを除外し、ゴールド、ハイブリッド、グリーンをOA論文として集計を行った。
なお、論文は過去に遡ってOA化されることもあり得るため、出版年別にOA論文数の集計を行う際、ある出版年のOA論文がその年にOA化されたと捉えることは必ずしも適切ではない。特に、各国においてOA推進政策が実施されるようになった2010年代以前に出版された論文については、どこかの時点で遡及的にOA化されたものが多いと考えられる。
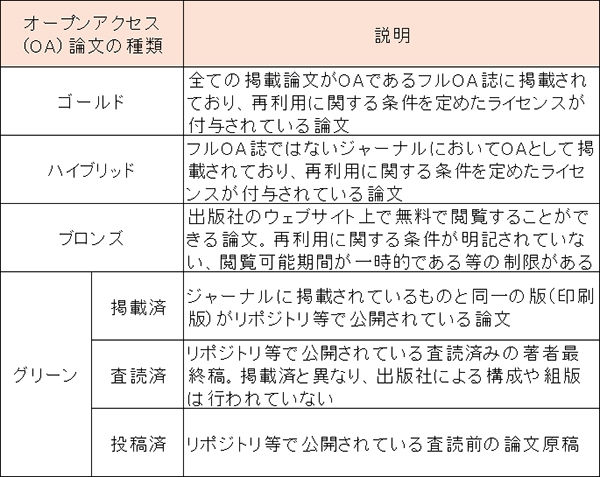
注:
1) クラリベイト社 Web of ScienceにおけるOAの種類に関するデータは、OurResearchとの連携により提供されている。このことから、本図表はクラリベイト社及びOurResearch(ひいてはそのプロジェクトの一つであるUnpaywall)のウェブサイトにおける説明を参照して作成した。
2) 「リポジトリ等」には、大学や研究機関等によって管理される「機関リポジトリ」や、特定分野に焦点を当てた「サブジェクト・リポジトリ」(例えばPubMed Central(PMC))が含まれる。なお、これらは「OAアーカイブ」と呼ばれる場合もある。
3) OA論文の種類の中で、いわゆるAPC(論文処理費用)を支払うことでOA化されている論文は、ゴールドとハイブリッドである(ただし、ゴールドの中にはAPCを徴収しないフルOA誌に投稿された論文も含まれていると考えられる)。また、ハイブリッドは、OAと判定されるまでにはタイムラグがあるため、特に最新年の論文においては注意が必要である。
資料:
クラリベイト社 オープンアクセスの種類の説明
https://webofscience.help.clarivate.com/ja-jp/Content/open-access.html
参照:表4-1-11
(1)世界におけるオープンアクセス(OA)論文
図表4-1-12に、全世界のOA論文数とOA化率の推移を示す。
2022年の世界の自然科学系のOA論文数は118万件である。OA論文数は継続して増加しており、世界的にOA化が進展している様子が伺える。
なお、同じ論文が複数の方法によってOA化されている場合も多いため、OA論文数を集計するにあたっては重複を排除した(ある論文がゴールドOAかつグリーンOAであった場合、その論文は1件のOA論文として集計した)。
2022年時点の全世界のOA化率は56.2%であり、世界の論文数の6割近くはOA化されている。
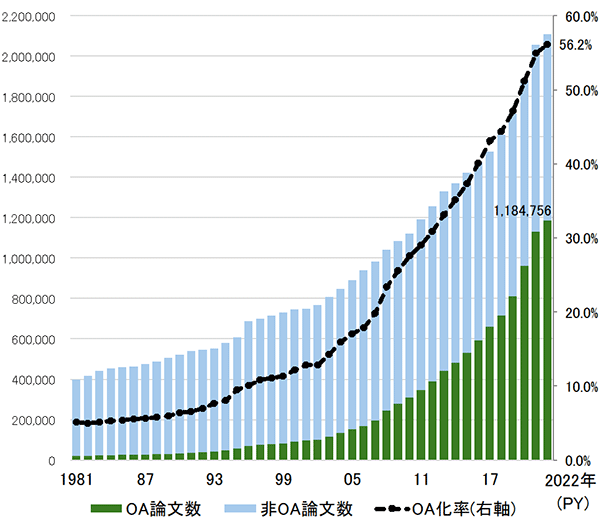
注:
1) 分析対象は、Article, Reviewとし、整数カウント法により分析。年の集計は出版年(Publication year, PY)を用いた。単年である。
2) 本分析におけるOA論文とは、ゴールド、ハイブリッド、グリーンのいずれかに該当する論文である。
3) OA化率とは、論文数に占めるOA論文数の割合である。OA論文数とは、OA化されている論文を重複排除して集計した数である(1つの論文が複数の方法でOA化されている場合も1件とカウントしている)。OA化されている論文やジャーナルは分析時点によって変わり得るものであるため、分析に用いたデータによって過去も含めて分析結果が変化する点には留意が必要である。
資料:
クラリベイト社 Web of Science XML (SCIE, 2023年末バージョン)を基に、科学技術・学術政策研究所が集計。
参照:表4-1-12
(2)主要国におけるオープンアクセス(OA)論文
図表4-1-13は、主要国のOA論文数及びOA化率を示している。
図表4-1-13(A)のOA論文数の推移を見ると、各国ともOA論文数は上昇基調であるが、2021年から2022年にかけて、多くの国で減少した。2022年時点では米国及び中国のOA論文数が多い。特に中国のOA論文数は2010年代より急激に増加している。日本のOA論文数はフランスに続いて主要国中第6位である。
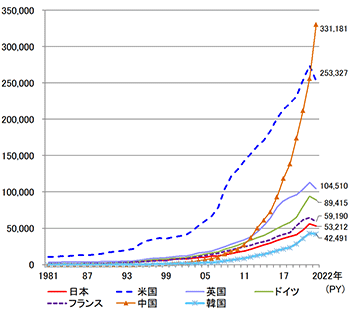
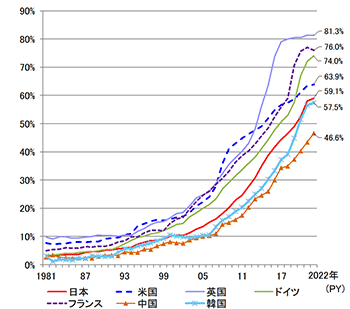
注及び資料:
図表4-1-12と同じ。
参照:表4-1-13
(3)分野ごとのオープンアクセス(OA)論文
図表4-1-14は、分野ごとのOA化率を示す。いずれの分野でもOA化率は上昇基調である。2022年時点の論文について、基礎生命科学と臨床医学はそれぞれ66.5%、65.6%と特にOA化率が高く、最も低い材料科学では36.4%と、分野によってOA化率には大きな違いが見られる。全分野の2022年時点でのOA化率(56.2%)を下回ったのは、計算機・数学、化学、工学、材料科学の4分野であった。
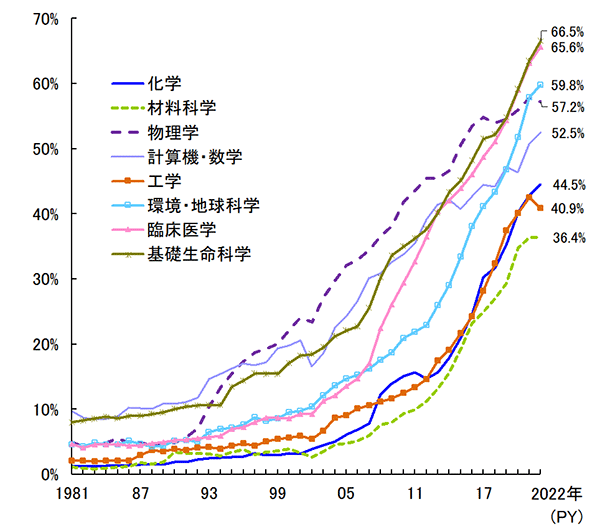
注及び資料:
図表4-1-12と同じ。
参照:表4-1-14
コラム4:オープンサイエンスに関する研究者の認識(日本と欧州の比較)
オープンサイエンスに対する取組みが各国で進む中(本文4.1.4項を参照)、研究者は、その意義や課題についてどのような認識を抱いているのか。日本及び欧州における研究者への質問票調査を用いて、大まかな相違について比較を試みる。
日本のデータは、科学技術・学術政策研究所が2022年に実施した2つの調査(オープンアクセスでの論文の出版経験等に関する調査及び研究データ公開に関する調査)を用いている。欧州のデータは、欧州連合(EU)により助成を受けたSuperMoRRIプロジェクトが実施した調査(The SUPER MoRRI Researcher Survey)を用いている。
両調査の回答者を比べると、自然科学・工学・農学分野の割合は日本が欧州より大きく、医学や人文・社会科学分野の割合は欧州が日本より大きいという特徴がある(詳細については統計集のコラム表4-8を参照)。それぞれ異なる設計に基づく調査を用いるため、厳密には比較ができないことは留意する必要がある。
(1)オープンサイエンスに関する活動状況
オープンサイエンスへの参画状況として、日本ではオープンアクセスでの出版経験を一回でも持つ回答者の割合は83%であり、欧州では92%であった。公開リポジトリにおけるデータ公開経験については、日本では特定分野リポジトリで13%、学術機関リポジトリで19%が一回以上の経験を持ち、欧州では70%であった(コラム図表4-1参照)。
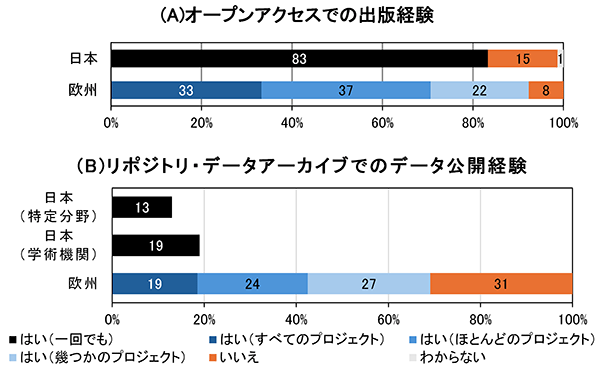
注:
1) 欧州のデータは2022年11月~2023年1月にかけて実施した調査に基づく。小数点以下の処理のため、各項目の合計が100%とならない場合がある。
2) 「リボジトリ・データアーカイブでの公開経験」に関して、「日本(特定分野)」は特定分野のリポジトリ・データアーカイブ(DDBJやICPSRなど)、「日本(学術機関)」は学術機関のリポジトリ・データアーカイブ(大学やNASAのリポジトリなど)での公開経験に対する回答(全回答者における割合)。欧州のデータは、Shared data in open repositoriesに対する回答。
資料:
日本:科学技術・学術政策研究所、「論文のオープンアクセスとプレプリントに関する実態調査2022:オープンサイエンスにおける日本の現状」(調査資料-327)、「研究データ公開と研究データ管理に関する実態調査2022:日本におけるオープンサイエンスの現状」(調査資料-335)
欧州:T. Kjeldager Ryan, S. Carlsen, R. Woolley, H. Berghäuser, M. Yorulmaz and E. Bories Hüttel, 「D2.5: 3rd Responsible Research and Innovation Monitoring Report」, Zenodo, 2023年9月
参照:コラム表4-1
(2)オープンサイエンスに参画する理由・動機
オープンサイエンスに参画する理由・動機は、両調査における選択肢が大きく異なるため、それぞれの結果を紹介した後に、比較可能な項目での大まかな相違を確認する。
日本では(コラム図表4-2参照)、オープンアクセス論文での出版及び公開リポジトリでのデータ公開経験の理由(複数回答可)として、「論文を投稿した雑誌がオープンアクセスだから(データの場合は投稿規定だから)」が一番多く選択された(論文74%、データ55%)。これに「研究成果を広く認知してもらいたいから(論文62%、データ50%)」、「引用される可能性が高まるから(論文45%、データ26%)」が続く。データ公開では、「他の研究者からのリクエストに応じて(26%)」や「オープンデータに貢献したいから(26%)」も多く選択された。
欧州では動機として(コラム図表4-3参照)、「優れた研究実践の一部だと考えるから」への同意割合が最大であった(91%)。これに「研究の広がり及びインパクトを最大化したいから(88%)」、「研究はオープンであるべきと確信しているから(85%)」、「研究結果の一般公開に個人的関心があるから(75%)」が続いている。
類似項目での大まかな比較を試みると、研究成果の認知度やインパクトを高めることに関しては、双方において選択される割合が大きかった。日本では「研究成果を広く認知してもらいたいから(論文62%、データ50%)」であり、欧州では「研究の広がり及びインパクトを最大化したいから」に対して回答者の88%が同意した。
オープンサイエンスへの意義に関して、日本では、「オープンアクセス(データ)に貢献したいから」を選択した割合は14%(26%)と比較的小さかったが、欧州では「優れた研究実践の一部だと考えるから(91%)」、「研究はオープンであるべきと確信しているから(85%)」に同意した割合は大きかった。
政策・組織等の方針・規範への遵守は、双方で、理由及び動機としてそれほど大きくなかった。日本では「所属機関のポリシーだから(論文13%、データ19%)」、「助成機関のポリシー(助成条件)だから(論文7%、データ7%)」は選択割合が小さかった。欧州では「自国法的要件を遵守したいから」へは回答者の38%が同意したが、選択肢の中では相対的に低い割合である。
業績としての評価についても同様の傾向であり、日本では8%が「業績になる場合があるから」を選択し、欧州では24%が「所属研究機関が報奨している」に同意した。
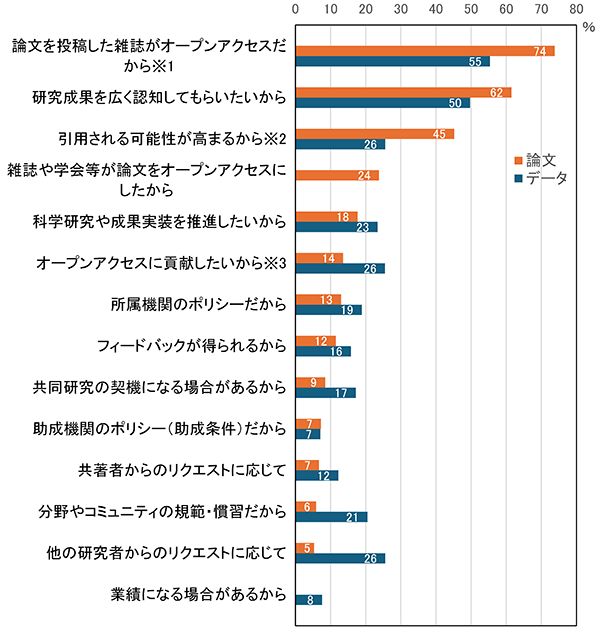
注:
1) 論文:「論文をオープンアクセスにした理由」への回答(複数回答可)
2) データ:「データを公開した理由」への回答(複数回答可) データでは※印を付けた項目は「論文を投稿した雑誌のポリシー(投稿規定)だから※1」、「データに紐づく論文が引用される可能性が高まるから※2」、「オープンデータに貢献したいから※3」
3) グラフから「その他」「特に理由はない」を除いている。
資料:
コラム図表4-1の日本と同じ
参照:コラム表4-2
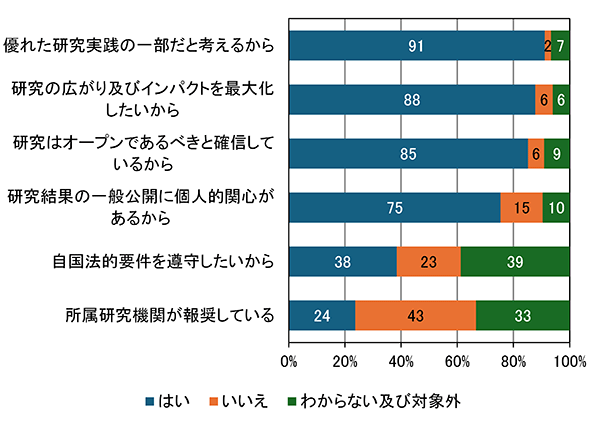
注:
「オープンサイエンスへの参画の動機」への回答(各項目において、はい、いいえ、わからない、対象外から回答)。小数点以下の処理のため、各項目の合計が100%とならない場合がある。
資料:
コラム図表4-1の欧州と同じ。
参照:コラム表4-3
(3)オープンサイエンスの便益の経験
日本では(コラム図表4-4)、研究データ公開に関して実際に得られた良い経験として最も選択されたのが、「特に良い結果は得られていない(33%)」であり、次は「データに紐づく論文が引用された(26%)」であった。
欧州では、オープンサイエンスの便益の経験及び期待について聞いている(コラム図表4-5)。すでに恩恵を受けているという回答割合が大きかった項目は、「研究コミュニティにおける認知度の向上(60%)」、「知識のより早い普及(56%)」であった。また今後に期待する割合が比較的大きいものとして、「研究の社会的インパクト増大(42%)」、「科学的成果の社会との関連の向上(39%)」、「新規研究テーマの出現(39%)」等があった。他方、便益として期待しない割合が比較的大きかった項目は、「科学的成果の質の向上(33%)」、「知識やデータへのアクセス向上によるコスト削減(32%)」であった。
類似項目での大まかな比較をすると、日本では「研究の認知度が向上した」を選択したのは22%と低かったが、欧州では「研究コミュニティにおける認知度の向上」に60%と多くが同意した。
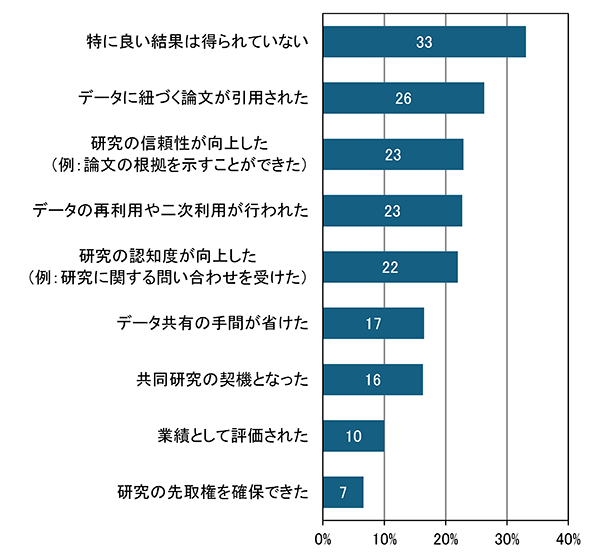
注:
「研究データの公開によって実際に良い結果が得られた経験」への回答(複数回答可)。グラフから「その他」は除いている。
資料:
コラム図表4-1の日本と同じ。
参照:コラム表4-4
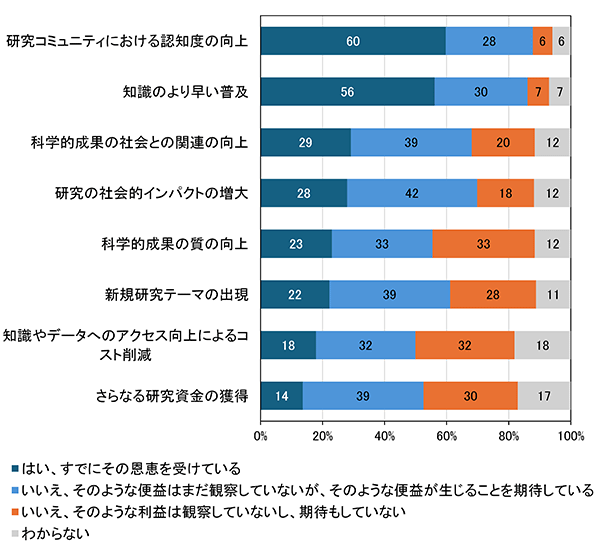
注:
「オープンサイエンスの実践にあたり、次のような便益を期待または観察していますか?」への回答。小数点以下の処理のため、各項目の合計が100%とならない場合がある。
資料:
コラム図表4-1の欧州と同じ。
参照:コラム表4-5
(4)オープンサイエンスにおける障壁の認識
オープンサイエンスにおいて何を障壁として認識しているかに注目すると、日本では、論文をオープンアクセスにしていない理由として、「資金がないから(55%)」、「投稿したい雑誌がオープンアクセスではないから(35%)」の選択割合が大きかった(コラム図表4-6)。
欧州では(コラム図表4-7)、「論文掲載料(APC)が高すぎる(85%)」、「オープンサイエンス活動を報奨する制度的インセンティブがない(53%)」、「所属大学によるオープンサイエンスへの支援(財政的支援等)がない(45%)」への同意割合が高かった。障壁ではないという認識が高い項目(不同意が高い項目)としては、「自分の研究には関係がない(83%)」、「どのようにすればよいかわからない(77%)」、「自分にとってメリットが少なすぎる(67%)」であった。
類似項目での大まかな比較を試みると、費用・資金が、双方で大きな障壁として認識されている。欧州では、「論文掲載料(APC)が高すぎる(85%が同意)」であり、日本でも論文をオープンアクセス化しない理由として「資金がないから(55%)」であった。
ジャーナルのオープンアクセスへの対応は、阻害要因として双方で比較的大きかった。日本では35%が「投稿したい雑誌がオープンアクセスでないから」を選択し、欧州では「自分野で最も重要なジャーナルがオープンアクセスを提供していない」に61%が同意した。
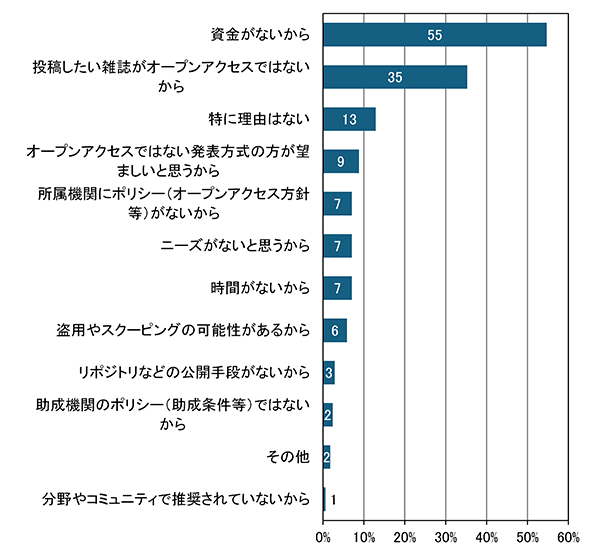
注:
「論文をオープンアクセスにしない理由」への回答(複数回答可能)。
資料:
コラム図表4-1の日本と同じ。
参照:コラム表4-6
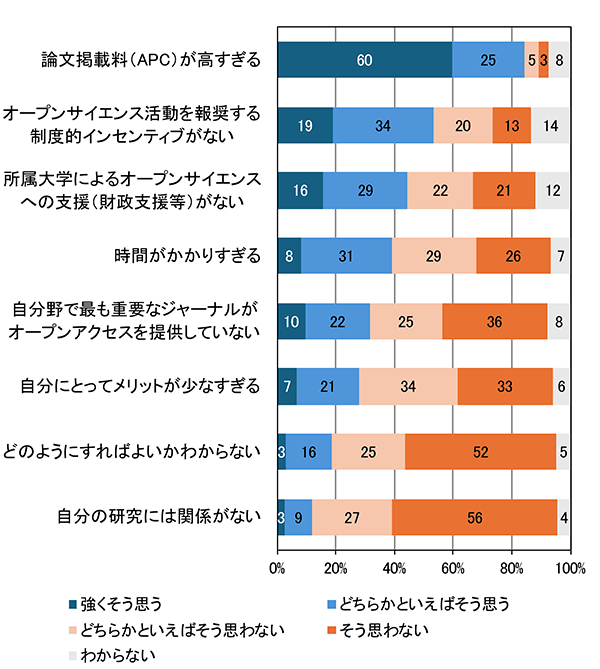
注:
「オープンサイエンスの実践における障壁項目への同意度」への回答。小数点以下の処理のため、各項目の合計が100%とならない場合がある。
資料:
コラム図表4-1の欧州と同じ。
参照:コラム表4-7
(5)まとめ
本コラムではオープンサイエンスへの参画状況と動機・理由、オープンサイエンスからの便益の経験及び障壁について、研究者への質問票調査に基づく日欧の大まかな比較を試みた。異なる調査設計によるため、厳密な比較はできないが、大まかな傾向として、論文及びデータ公開でみたオープンサイエンスへの参画度合いは欧州よりも日本のほうが小さく、その差はデータ公開においてより大きかった。
特徴として、欧州の研究者は、「研究はオープンであるべきと確信しているから」、「(オープンサイエンスは)優れた研究実践の一部だと考えるから」に大半が同意するなど、オープンサイエンスの意義をより重視している姿勢が浮かびあがった。日本では、投稿する論文がオープンアクセスであったという受動的な理由を選択した割合が大きかった一方で、「オープンアクセス(データ)に貢献したい」を選択した割合は低かった。この他の理由として、研究成果の認知を拡げたい、研究成果のインパクトを高めたいという項目の割合は、双方で大きかった。
また、オープンサイエンスからの便益の経験として、研究認知度の向上を実感していると答えた欧州の研究者の割合は大きく、日本では低かった。その一方で、研究活動自体への良い影響(研究の質の向上等)については、双方で、現時点ではそれほど大きく実感されていなかった。障壁として資金を挙げた割合は双方で大きく、ジャーナルのオープンアクセスへの対応がないことを挙げる回答者も双方で一定程度いた。
日欧比較においては、政策・ファンディングにおける違いも考慮に入れる必要がある。EUの研究・イノベーション枠組みプログラム「Horizon Europe」では、成果のオープンアクセス化などがすでに義務付け(一部推奨)されている。また各国政策においても、オープンサイエンスの様々な取組を進めている。日本でもリポジトリなどインフラ整備に加えて、即時オープンアクセスの対象となる競争的研究費については、2025年度新規公募分からの学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた準備が進められている。
今後日本においてオープンサイエンスが根付いていくためには、インフラ整備等に加えて、研究者のオープンサイエンスに対する認識も影響すると想定されることから、欧州等の実態を参照していくことも有用である。そのためにも、オープンアクセス、オープンデータ等の実態・動機等をより正確に把握することができる国際比較調査が、より重要になると考えられる
全体注:
[日本のデータ]
オープンアクセスでの出版経験等の論文に関するデータは、2022年7月から8月にかけてNISTEP科学技術専門家ネットワークに所属する研究者1,671名を対象としてオンライン調査(有効回答は1,173名、回答率70.2%)の結果を用いている。また、研究データ公開に関しては、2022年10月から11月にかけて同ネットワークに所属する研究者1,675名を対象として実施したオンライン調査(有効回答は1,237名、回答率73.9%)の結果を用いている。
池内有為, 林和弘 (2023a)「論文のオープンアクセスとプレプリントに関する実態調査2022:オープンサイエンスにおける日本の現状」, NISTEP RESEARCH MATERIAL, No. 327, 文部科学省科学技術・学術政策研究所. DOI: https://doi.org/10.15108/rm327
池内有為, 林和弘(2023b)「研究データ公開と研究データ管理に関する実態調査2022:日本におけるオープンサイエンスの現状」, NISTEP RESEARCH MATERIAL, No. 335, 文部科学省科学技術・学術政策研究所. DOI: https://doi.org/10.15108/rm335
[欧州のデータ]
The SUPER MoRRI Researcher Survey は、研究者の公共的関与、オープンサイエンス、ジェンダー、倫理に対する認識を対象として、2022年11月から2023年1月にかけて実施された。欧州の研究実施機関調査に基づき、29の欧州諸国における122の高等教育機関に所属するアクティブな研究者(127,395名)に調査票(Email)を送付し、5,420名が調査に協力し、3,382名が質問票を完了した。
T. Kjeldager Ryan, S. Carlsen, R. Woolley, H. Berghäuser, M. Yorulmaz and E. Bories Hüttel, 「D2.5: 3rd Responsible Research and Innovation Monitoring Report」, Zenodo, 2023年9月. doi: 10.5281/zenodo.10619884.
(岡村 麻子)
コラム5:「注目度の高い論文」の意味の変化: 中国やグローバルサウスの台頭
第4章の論文の節では、注目度の高い論文数であるTop10%補正論文数(分数カウント法)の世界ランクで、第12位のイランのように新興国が順位を上げている状況を示している。
本コラムでは、論文の注目度が、どこの国・地域からの被引用数(注目度)で構成されているのかに焦点を当てる。Top10%補正論文数(分数カウント法)が上位の国・地域に注目して、それらの国・地域の論文がどのような国・地域から引用されているかの分析を行う。また、米国からの引用に絞って、Top10%補正論文数を集計した結果を紹介する。
(1) 拡大する新興国の研究コミュニティ
コラム図表5-1は、地域区分別の論文数の推移を示す。世界の論文数は拡大しているが、その中でも中国の論文数は急激に拡大してきている。これに加えて、グローバルサウスと呼ばれるような新興国の論文数も2000年代後半から増加している。このような新興国の研究コミュニティの拡大は、論文の引用パターンにも影響を及ぼしていると考えられる。
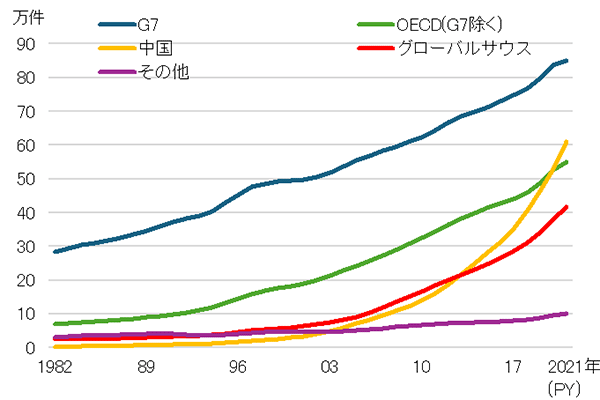
注:
Article, Reviewを分析対象とし、整数カウント法により分析。年の集計は出版年(Publication year, PY)を用いた。3年移動平均値である。
グローバルサウスの国・地域は、グローバルサウスの声サミット2023参加国(https://mea.gov.in/voice-of-global-summit.htm)及び国連における途上国の協力グループ(G77現加盟国, http://www.fc-ssc.org/en/partnership_program/south_south_countries)を参照した。
チリ、コロンビア、コスタリカはOECDに含めたためグローバルサウスから除外した。地域区分についてはコラム表5-1を参照のこと。
資料:
クラリベイト社Web of Science XML(SCIE, 2023年末バージョン)を基に、科学技術・学術政策研究所が集計。
参照:コラム表5-1
(2) Top10%補正論文の被引用数構造
コラム図表5-2は、Top10%補正論文数(分数カウント法、2020-2022年平均、本編図表4-1-6参照)における上位25か国・地域の被引用数構造を分析した結果である。ここでは、各国・地域の当該期間におけるTop10%補正論文を引用している論文を国・地域別に分数カウント法を用いて集計し、区分ごとに被引用数をまとめた。図表中では、その区分ごとの被引用数を全体の被引用数に占める割合で示している。また、各国・地域の自らによる被引用数は、自国・地域に計上し、他の該当する区分から除いている。分析期間は2000-2002年と2020-2022年の2時点とした。ここで、2時点で分析対象の論文群を引用することが可能な論文群の期間が異なっている点に注意が必要である。つまり、当該論文が掲載出版されてから2023年末までの期間が異なっており、2000-2002年の論文群は2023年末までの22~24年間分の被引用数、2020-2022年の論文群では2023年末までの数年間分の被引用数を分析している。
25か国・地域のTop10%補正論文の被引用数構造において、自国・地域からの被引用数割合は中国が最も大きく、その割合は2000-2002年の40%から2020-2022年の62%に上昇している。後半の期間では米国、インド、イラン、エジプトにおいて自国・地域からの被引用数割合が比較的大きい傾向にある。2時点の変化で大きな違いは、中国からの被引用数割合がいずれの国・地域においても拡大している点である。特にシンガポールは25%から43%へと18ポイント大きくなっている。
また、2時点に共通して、グローバルサウスに該当する国・地域では、中国やグローバルサウスからの被引用数割合が比較的大きい。特に、2020-2022年において、イラン、エジプト、パキスタン、サウジアラビアは、「自国・地域+中国+グローバルサウス」からのTop10%補正論文における被引用数割合が約7割を占めている。
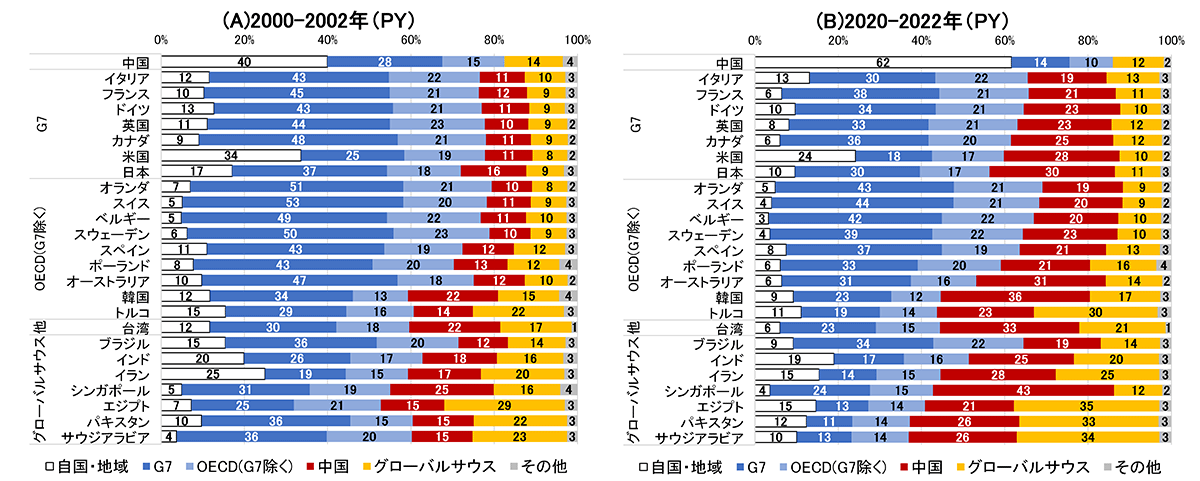
注:
Article, Reviewを分析対象とし、各国・地域の論文を引用している論文を国・地域別に分数カウント法により分析。年の集計は出版年(Publication year, PY)を用いた。Top10%補正論文数(分数カウント法、2020-2022年平均)で上位25か国・地域のTop10%補正論文の被引用数構造を分析した。各国・地域の自国・地域からの被引用数は、自国・地域に計上し、他の該当する区分から除いている。
資料:コラム図表5-1と同じ。
参照:コラム表5-2
(3) 各国・地域の被引用数構造のポジション
コラム図表5-3では、コラム図表5-2の被引用数構造から、各国・地域のポジションを可視化した。各国・地域の被引用数構造のポジションは、被引用数構造におけるG7とOECD諸国の合計割合から中国とグローバルサウス諸国の合計割合を引いた値で示した。ここでは、自国・地域の割合を各国・地域の該当区分に含めて計算した。ポジションの値がプラスの場合は、被引用数構造においてG7やOECD諸国からの被引用数割合が大きく、マイナスの場合は中国やグローバルサウス諸国からの被引用数割合が大きいことを意味する。
2000-2002年では、G7やOECDの国・地域がTop10%補正論文数で大きな規模を持ち、ポジションもプラスに位置している。つまり、科学知識の産出及び知識の交換においてG7やOECD諸国が主要な役割を果たしていた。
2020-2022年になると、中国やグローバルサウスの国・地域の規模が大きくなり、被引用数構造のポジションがマイナスに位置している。これらの結果は、過去20年で、G7やOECD諸国に加えて、中国やグローバルサウス諸国の存在感が増していることを示している。
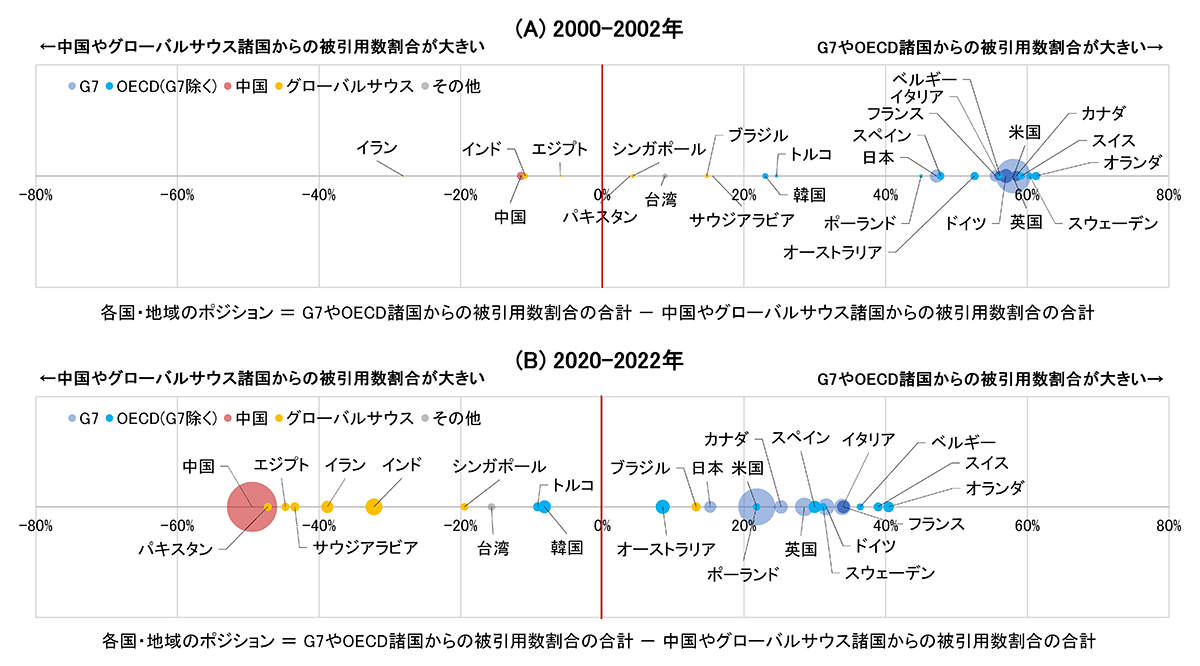
注:
Top10%補正論文数(分数カウント法、2020-2022年平均)で上位25か国・地域のTop10%補正論文の被引用数構造を分析した。各国・地域の被引用数構造のポジションは、各国・地域ごとに、G7やOECD諸国からの被引用数割合の合計から中国やグローバルサウス諸国からの被引用数割合の合計を引いた値を集計した。ここでは、コラム図表5-2で示している自国・地域の割合を各国・地域の該当区分に含めて計算した。図表中の円の面積は、各国・地域の当該期間におけるTop10%補正論文数を示す。その他の注はコラム図表5-2と同じ。
資料:コラム図表5-1と同じ。
参照:コラム表5-2
(4) 米国被引用によるTop10%補正論文数
これまで見たように、論文の注目度は、近年新興国の引用動向の影響を受けるようになっており、論文の注目度についても誰から注目されているかという観点も考慮が必要になりつつある。また、コラム図表5-3で見たように、近年では、中国やグローバルサウス諸国の存在感が論文数や被引用数構造において増している。
この状況を踏まえ、コラム図表5-4は、米国からの被引用数を用いた場合のTop10%補正論文数を試行的に集計した結果を示す。ここで米国に注目したのは、米国は2時点において、大きな存在感を示しているためである。
米国からの被引用Top10%補正論文数では、2020-2022年における日本の世界ランクは第9位で、本編で示す第13位よりも世界ランクが高い。他方、インド、イランなどの国・地域の世界ランクは、本編で示す順位より大きく低下した。また、本編で上位25位に入っていた、サウジアラビア、エジプト、パキスタンは上位25位の圏外であった。このことは、コラム図表5-2及びコラム図表5-3とも関連するが、これらの国・地域を引用する国・地域は、米国以外が中心であることに起因している。
(図表4-1-6(B)再掲)
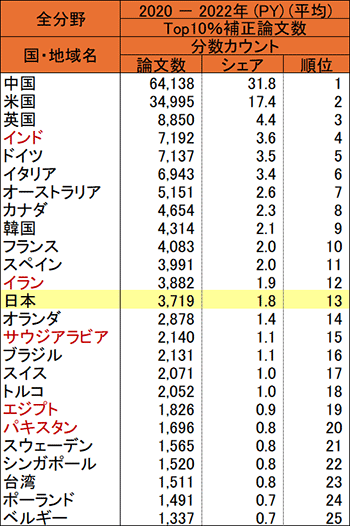
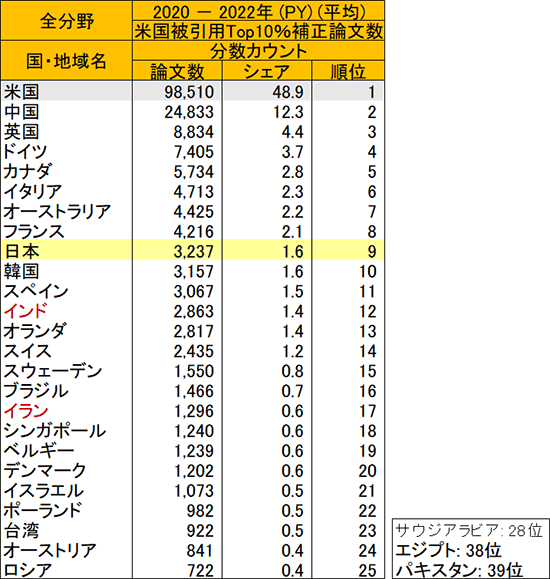
注:
米国からの被引用数は、各国・地域の論文を引用している論文における米国の論文数を分数カウント法により集計した。米国からの被引用数を用いて、各年各分野(22分野)の上位10%に入る論文数を抽出後、実数で1/10となるように補正を加えた。その他の注はコラム図表5-2と同じ。
資料:コラム図表5-1と同じ。
参照:コラム表5-4
(5) まとめ
本コラムで示した結果は、過去20年間で、中国やグローバルサウス諸国の存在感が増したことで、注目度の高い論文の意味が過去と比べて変化してきていることを示唆している。
(村上 昭義)


