研究者の流動性を高めることは、知識生産の担い手である研究者の能力の活性化を促すとともに、労働現場においても活力ある研究環境を形成すると考えられる。
(1)米国での博士号保持者の出身状況
研究者の流動性又は国際性を表すための指標として、外国人研究者の数といった指標が考えられる。しかしながら、日本においては、外国人研究者数は計測されていない。また、米国についてもScientists & Engineers といった職業分類で見た場合での外国人のデータはあるが、狭義の研究者についての数値はない。そこで、この項では、データが利用可能な米国の博士号保持者のうちの外国人の状況を見る。
図表2-1-14は、米国において、博士号保持者がどの国・地域から来て、どの職業分野で雇用されているかを2時点で見たものである。2021年の雇用者のうち37.2%が外国出身の人材である。そのうち、多いのはアジア地域出身者であり、全体のうち26.3%である。
職業分野別に見ると、2021年において、アジア地域出身者が多いのは「コンピュータ・情報科学」であり49.7%となっている。また、「工学」も47.2%とアジア地域からの出身者が多い。一方、米国出身者が多いのは、「心理学」(89.0%)、「社会科学」(71.1%)、「科学工学以外の職業」(71.1%)である。
2008年と比較すると、すべての職業分野で外国出身の人材が増えており、特にアジア地域の出身者の割合が増えている。アジア地域の出身者の割合が最も増加したのは「コンピュータ・情報科学」の職業分野であり(13.3ポイント増)、これに「工学」の9.7ポイント増、「数学」の9.3ポイント増が続く。
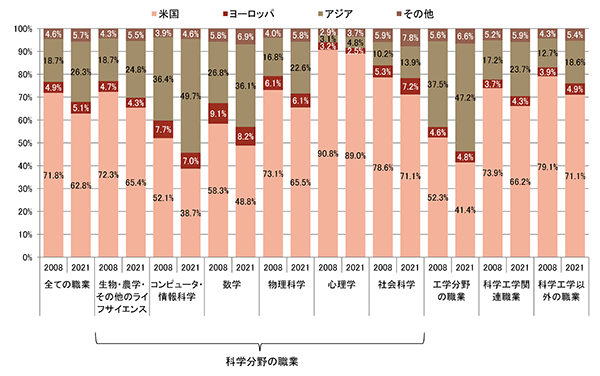
注:
出身地域別の合計値が全体の値と一致しない場合があり、各職業分野の割合の合計値は100%になっていない場合がある。
資料:
NSF,“Survey of Doctorate Recipients”
参照:表2-1-14
(2)日本の研究者の部門間の流動性
日本の研究者の新規採用(6) 、転入(7) 、転出(8) 状況を見る(図表2-1-15)。2022年度に全国で採用された研究者は7.6万人である。内訳は新規採用者が3.3万人、転入者が4.3万人である。転出者は5.6万人である。新規採用者は2006~2008年度をピークに一旦減少したが、2011年度以降、増加に転じた。2020年度に減少した後、2021、2022年度は増加した。
部門別に見ると、「企業」では、2000年代後半は、新規採用者が最も多かったが、2010年度から転出者が最も多くなっていた。新規採用者は2008年度を境に2011年度まで減少した後、2011年度以降増加に転じ、2018年度以降には転出者を超え最も多くなっている。
「非営利団体・公的機関」においては、転入・転出者の方が新規採用者よりも多い。転出者は2005年度以降、増減を繰り返しながら、漸減している。転入者は2010年代に入ると、ほぼ横ばいに推移している。
「大学等」では新規採用者よりも転入・転出者の方が多い。転出者数は長期的に増加傾向である。転入者は、2010年代半ばからほぼ横ばいに推移している。新規採用者については、長期的には微減している。
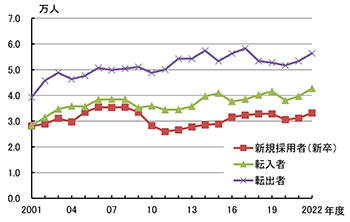
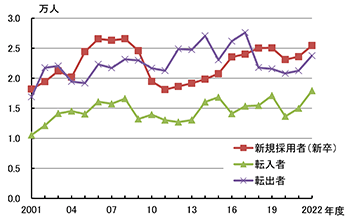
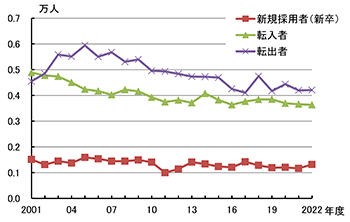
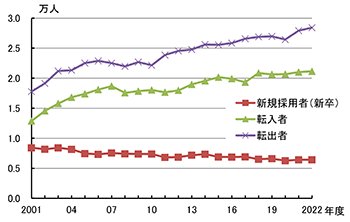
注:
1) 2010年度までの「企業」は営利を伴う特殊法人・独立行政法人が含まれた「企業等」である。
2) 2012年度までの転入者数は、採用・転入研究者数の総数から新規採用者数を引いた数である。
資料:
総務省、「科学技術研究調査報告」
参照:表2-1-15
部門間における転入研究者の流れを見る(図表2-1-16)。
多くの研究者の転入先となっている部門は「大学等」部門である。「企業」部門、「大学等」部門はそのほとんどが同部門に流れており、他部門への転入は少ない。また、「公的機関」部門や「非営利団体」部門については「大学等」部門へ転入している研究者が多い。転入者のうち博士号を持った研究者の割合を見ると、「公的機関」が最も大きく26.0%である。「非営利団体」は22.5%、「企業」は4.9%である。
各部門の研究者のうち博士号保持者の割合は「公的機関」では47.3%、「非営利団体」では35.8%、「企業」では4.3%である(図表2-1-8参照のこと)。「公的機関」、「非営利団体」部門において、転入研究者における博士号保持者の割合の方が小さい傾向にある。
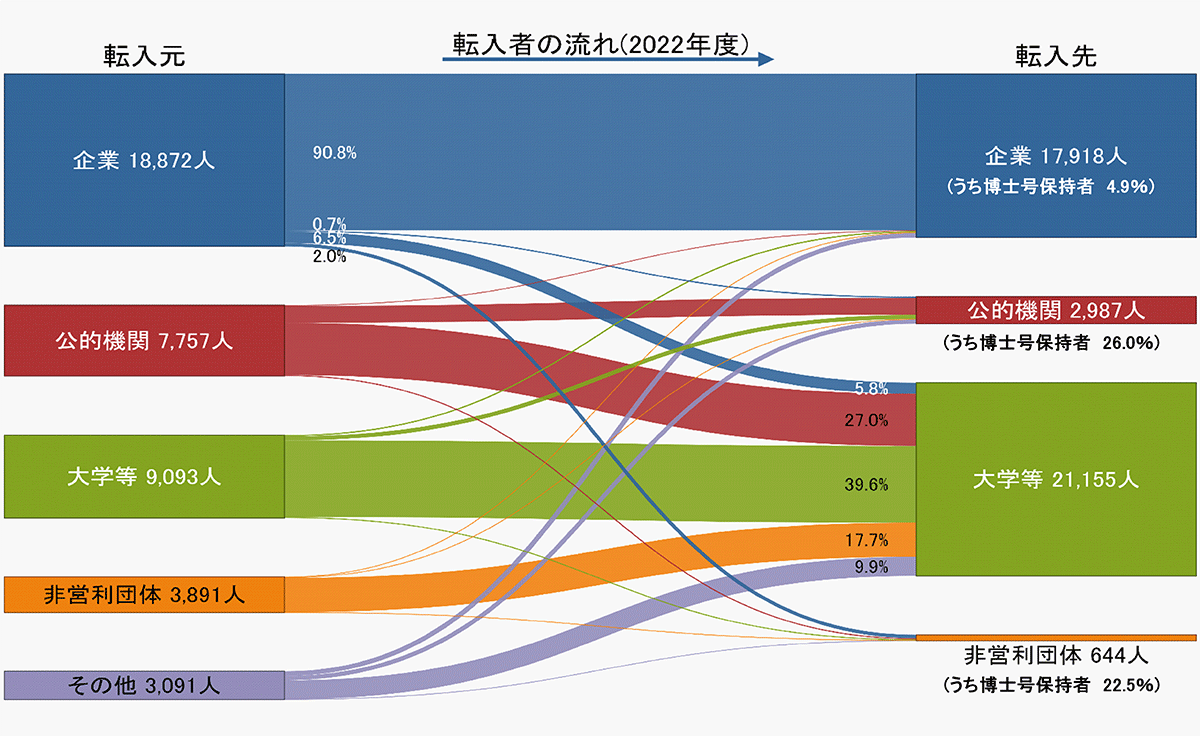
注:
1) 「その他」とは、外国の組織から転入した者の他、自営業の者、無職の者(1年以上)を指す。
2) 2022年度(2023年3月31日時点の研究者数を測定している)の各部門における研究者数(HC)は、企業:618,551人、公的機関:34,511人、大学等:342,478人、非営利団体:8,343人である。
3) 四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合がある。
4) 大学等の転入者における博士号保持者の数値はない。
資料:
総務省、「科学技術研究調査報告」
参照:表2-1-16
(3)日本の新規採用研究者の動向
新規採用研究者(新卒)における男女の状況を見ると(図表2-1-17(A))、いずれの部門においても女性と比べて男性の新規採用研究者が多い。2022年度における女性の新規採用研究者の割合は全体では25.4%である。部門別で見ると「企業」部門では22.5%、「公的機関」部門では31.3%、「大学等」部門では35.6%、「非営利団体」では26.6%である。いずれの部門においても、女性の新規採用研究者の割合は増加している。特に「企業」部門では2013年度時点に全体の14.4%であった女性の新規採用研究者の割合が1.6倍となった。
いずれの部門でも、研究者に占める女性の割合(図表2-1-11参照)よりも、新規採用に占める女性の割合の方が大きいことから、女性研究者割合は今後も増加すると考えられる。
大学等について、新規採用研究者における女性の割合を配属された部署での研究内容(9) 分野別に示した(図表2-1-17(B))。2022年度の「自然科学系」の新規採用研究者における女性の割合は33.9%である。分野別の詳細を見ると、「農学」、「保健」における女性の割合は大きく、それぞれ41.1%、39.6%である。最も小さいのは「工学」の18.4%である。
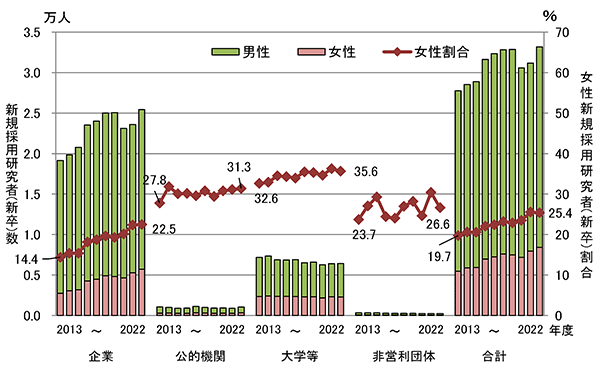
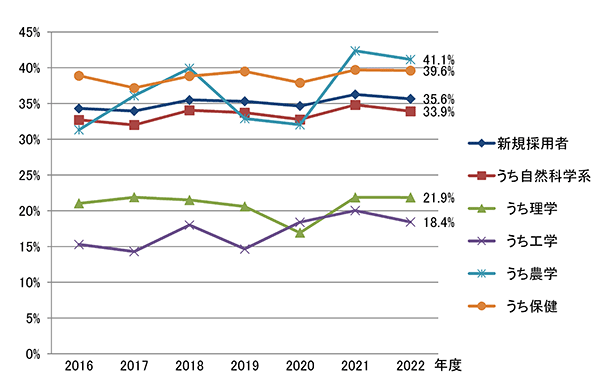
資料:
総務省、「科学技術研究調査報告」
参照:表2-1-17
新規採用研究者のうちの博士号保持者(以下、新規採用博士号保持者と呼ぶ)について、産業分類別に見た(図表2-1-18)。
2022年度の新規採用博士号保持者数は、製造業では746人(新規採用研究者に占める割合は4.0%)、対前年度比は6.4%増である。非製造業では219人(同3.2%)であり、対前年度比は7.4%増である。
産業分類別に見ると、製造業における新規採用博士号保持者数は「医薬品製造業」が最も多く、2022年度では180人(同14.2%)である。次いで「化学工業」が多く、同年度で113人(同6.3%)である。両部門ともに2020年度に減少、2021年度に増加、2022年度では再び減少した。「情報通信機械器具製造業」は2022年度では博士号保持者の数は著しく減少したが、割合では同程度の規模を保っている。研究開発費、研究者数ともに規模の大きい「輸送用機械器具製造業」は、他の産業と比較すると新規採用博士号保持者の数、割合ともに少ない。また、「石油製品・石炭製品製造業」については、絶対数は少ないなか、新規採用者に占める博士号保持者の割合は大きかったが、2018年度をピークに減少している。
非製造業に注目すると、2021年度の新規採用博士号保持者数は「学術研究,専門・技術サービス業」が最も多く135人(新規採用者に占める割合は6.1%)、対前年度比は35.0%と前年度に引き続き大きく伸びた。2017年度から増加傾向にあった「情報サービス業」の新規採用博士号保持者の数及び割合は、2020年度に大きく減少、2021年度では増加、2022年度は再び減少した。
企業の新規採用研究者において、博士号保持者を採用する傾向は産業により異なり、製造業のなかでも差異があることがわかる。また、博士号保持者の採用は全産業で見ると、2020年度に一旦落ち込んだ後、以前の水準に戻っているが、その後の個々の産業を見ると、回復している産業もあれば、引き続き低下している産業もある。
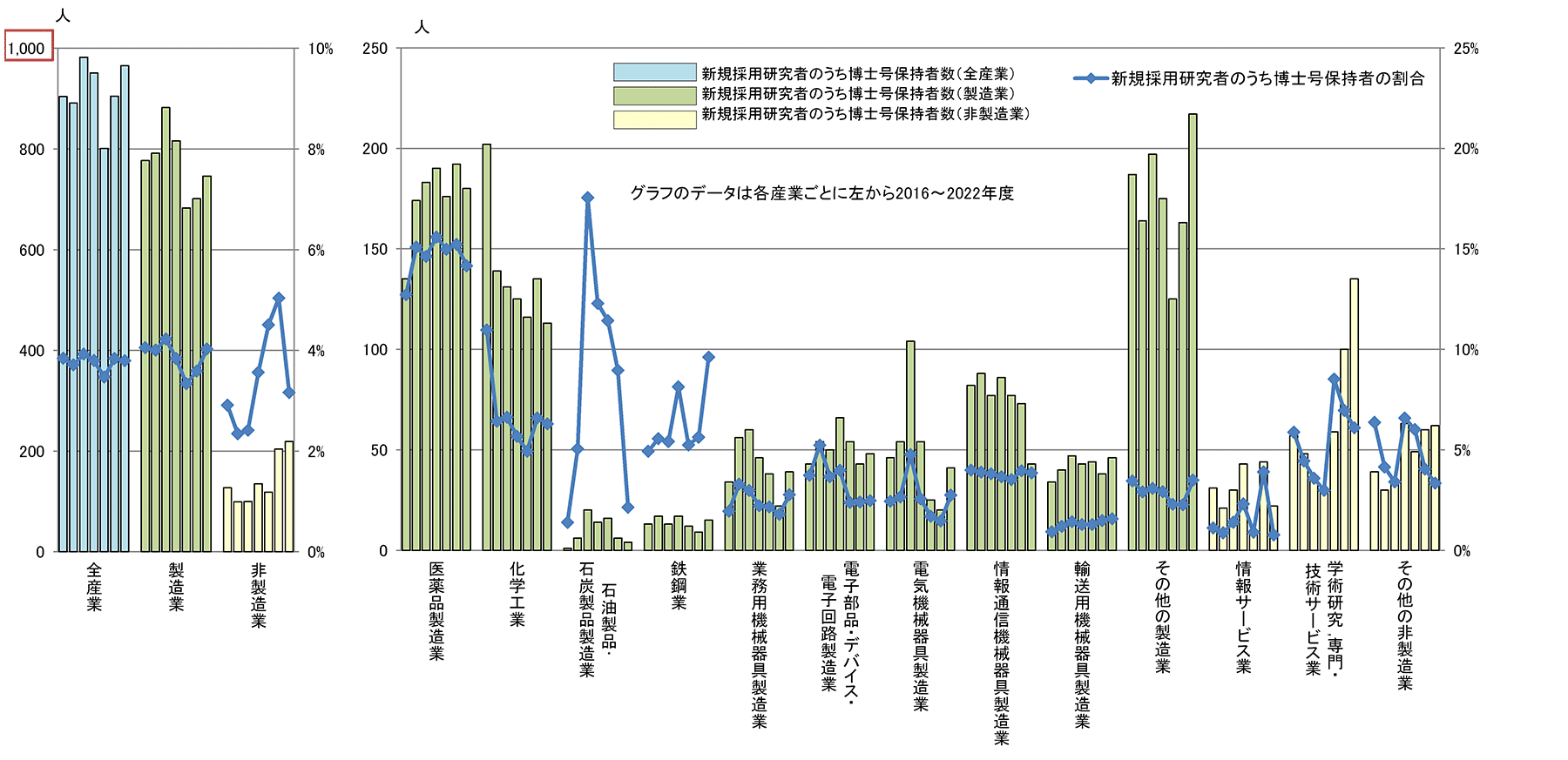
資料:
総務省、「科学技術研究調査報告」
参照:表2-1-18
コラム2:日本における外国人研究関連者数の変化
科学技術指標では過去、出入国者数の変化を月ごとに示すことにより、外国人研究関連人材の出入国状況に注目したコラムを掲載した。一つは2011年3月に起きた東日本大震災の時期である。未曽有の災害直後の外国人研究関連者は減少(出国)したものの、比較的短期間の中で例年並みに落ち着きを取り戻していた(入国)ことが記されていた(10)。もう一つは2020年の新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の時期である。日本における外国人研究関連者の動きはほぼ止まったことが明らかとなった(11)。本コラムでは視点を変え、フローではなくストックに注目し、どのような国・地域の人材が日本に在籍しているのかを見る。
なお、本コラムにおける外国人研究関連者とは、在留資格のうち、「教授」、「研究」、「高度専門職1号(イ)」の在留資格を交付された者とし、これらの在留資格を持つものは研究活動をしている者と考える(コラム図表2-1)。
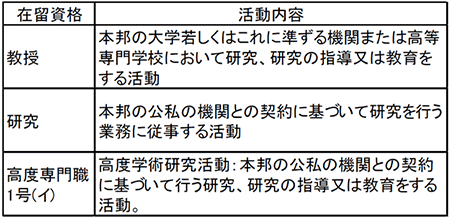
資料:
法務省、「在留外国人統計(旧登録外国人統計)」を基に、科学技術・学術政策研究所が作成。
参照:コラム表2-1
(1)在留資格別の内訳
コラム図表2-2を見ると、1990年代には在留目的が「教授」や「研究」である外国人登録者は順調に伸び続けた。その後は在留目的が「研究」である外国人登録者は2002年、在留目的が「教授」である外国人登録者は2006年をピークに減少し始めた。2015年度から導入された高度専門職人材は、日本の経済発展に貢献し得る外国人のための在留資格であり、他の在留資格にはない優遇措置がある。そのうちの一つである「高度専門職1号(イ)」を目的とする外国人登録者は増加傾向にある。2019年以降、それぞれの在留資格を持つ外国人登録者は減少傾向にあったが、2022年になるといずれも増加した。
なお、ここには示していないが、「教授」、「研究」の在留資格を持つ外国人登録者のうち、多くを占める中国は、両在留資格において、大きく減少している。一方で、「高度専門職1号(イ)」においても中国の数は多い。ただし、こちらでは著しく増加している。
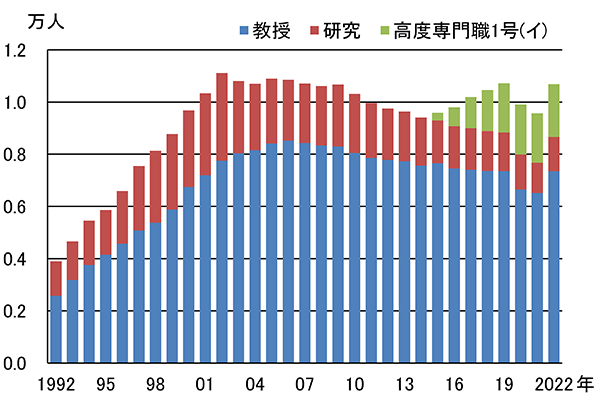
注:
1) 該当年の12月のデータである。
2) 在留資格が「教授」、「研究」、「高度専門職1号(イ)」を分析対象とする。
資料:
法務省、「在留外国人統計(旧登録外国人統計)」を基に、科学技術・学術政策研究所が集計。
参照:コラム表2-2
(2)主要国・地域別外国人研究関連者
外国人研究関連者を国・地域別で見ると(コラム図表2-3A))、2006年に最も多かったのは中国(3,458人)である。次いで韓国(1,275人)、米国(1,271人)が同程度であり、英国(532人)が続いていた。2022年になると、上位3位に変更はないが、中国(2,621人)、韓国(995人)、米国(951人)のいずれも減少した。英国(399人)も減少し、代わってインド(722人)が台頭し英国を大きく上回った。また、アフリカについても2006年から2022年にかけて1.6倍増加し、369人となっている。
研究関連者数の割合でも同様の傾向は見えているが、拡大が目立つのは「その他:アジア」である。2006年の11%から倍の22%となった。その内訳を見ると(コラム図表2-3(C))、2022年で最も多いのはインドネシアであり、台湾も同程度である。これにベトナム、タイ、バングラデシュが続いている。
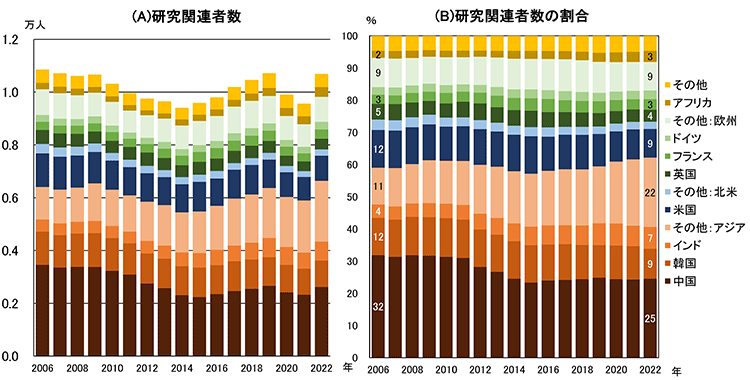

注:
1) 該当年の12月のデータである。
2) 「教授」、「研究」、「高度専門職1号(イ)」の在留資格を持つ外国人登録者である。
3) 2006~2014年までは「教授」と「研究」の在留資格のみの数値である。
4) 韓国の2014年までは、韓国・朝鮮の値。その他には、南米、オセアニア、無国籍を含む。
資料:
法務省、「在留外国人統計(旧登録外国人統計)」
参照:コラム表2-3
(3)まとめ
中国、韓国、米国は、長らく日本における外国人研究関連者の多くを占めていた国であった。しかし、過去15年程度の間に、この3か国からの外国人研究関連者は数、割合ともに低下した。この間、インドやASEAN諸国、アフリカの外国人研究関連者が、徐々に増えており、日本における外国人研究関連者の構造に変化が起きている。
(神田 由美子)
(6)いわゆる新卒者。最終学歴修了後、アルバイトやパートタイムの勤務、大学や研究機関の臨時職員としての雇用などの経験のみの者が採用された場合も含む。なお、任期付研究員については9か月以上の任期があれば新規採用者となる。
(7)外部から加わった者(新規研究者を除く)。
(8)転出者には退職者も含まれる。
(9)新規採用者が配属された部署の研究内容である(研究内容による分類が困難な場合には新規採用者の最終学歴を参考に判断している)。
(10)文部科学省 科学技術政策研究所、「科学技術指標2011及び2012」のコラム「3.11東日本大震災に伴う外国人研究関連者の出入国状況」
(11)文部科学省 科学技術・学術政策研究所、「科学技術指標2020」のコラム「日本における外国人研究関連者数の推移と新型コロナウイルス感染拡大に伴う外国人研究関連者の出入国状況」


