ポイント
- 日本の企業部門の2019年の研究開発費は14.2兆円である。2009年に落ち込んだ後は漸増傾向ににあったが、対前年比は0.1%減と横ばいである。米国は2010年頃から増加し続けており、2019年では50.3兆円となった。中国は同年で41.6兆円である。対前年比はそれぞれ8.9%増、11.4%増である。
- 主要国における企業部門の研究開発費の対GDP比を見ると、日本の2019年の対GDP比率は2.54%である。韓国は2010年以降日本を上回り、2019年は3.73%であり、主要国の中では著しく大きい値となっている。米国とドイツは、2010年頃から同程度の規模で推移している。2019年において米国は2.27%、ドイツは2.19%である。
- 企業部門の研究開発費のうち、製造業の割合は日本、ドイツ、中国、韓国では約9割である。米国では製造業の割合が約6割であり、上述した国と比較すると、非製造業の割合が大きい傾向にある。製造業の割合はフランスでは5割、英国では4割であり、非製造業の重みが大きい。
- 最新年の企業部門の研究開発費を産業分類別で見ると、米国は「情報通信業」、日本、ドイツは「輸送用機器製造業」、フランス、英国は「専門・科学・技術サービス業」、中国、韓国は「コンピュータ、電子・光学製品製造業」が大きな規模を持っている。
- 日本の企業部門において、研究開発費が最も大きいのは「輸送用機械器具製造業」であり、売上高に占める研究開発費の割合が最も大きいのは「医薬品製造業」である。研究開発費から見た研究開発の規模と集約度は産業によって異なる傾向を示している。
- 政府から企業の研究開発に対する直接的支援を従業員規模別で見ると、米国や英国では大規模企業に政府からの支援が集中しているが、ドイツや韓国では中小規模企業への支援も一定の重みを持つ。
- 日本の企業の外部支出研究開発費は、長期的には増加している。なかでも海外への支出の増加の度合いが大きい。大学への支出では、国内の国・公立大学への外部支出が多い。
(1)各国企業部門の研究開発費
企業部門の研究開発費は各国の研究開発費総額の大部分を占める。従って企業部門での値の増減が、国の研究開発費総額に及ぼす影響は大きい。図表1-3-3(A)を見ると、日本の2019年(18)の研究開発費は14.2兆円である。2009年に落ち込んだ後は漸増傾向にあったが、対前年比は-0.1%と横ばいである。
米国は2010年頃から増加し続けており、2019年では50.3兆円となっている。対前年比は8.9%増である。中国は、2000年以降の増加が著しい。2019年では41.6兆円、対前年比は11.4%増である。OECD購買力平価の更新に伴い、中国については2014~2019年の名目額が大きく減少した。
ドイツは長期的に増加している。2013年頃から増加の度合いが大きくなったが、近年は緩やかである。2019年では10.5兆円、対前年比は3.9%増である。
韓国は継続して増加しており、フランス、英国を上回り、2019年では8.5兆円となった。対前年比は3.5%増である。フランスは漸増しており、2019年では5.0兆円、対前年比は6.3%増である。英国は2000年代に入ると横ばいに推移していたが、2010年頃から増加しており、2019年では4.0兆円となった。対前年比は5.6%増である。
次に、2000年を1とした場合の各国通貨による研究開発費の名目額と実質額の指数を示し、2000年からの伸びを見る(図表1-3-3(B))。名目額で見ると、日本の最新年の値は1.3であり、その伸びは他国と比較すると小さい。欧米諸国が1.8から2.4の伸びを示しているのに対して、中国は31.5、韓国は7.0と急激な伸びを示している。
実質額の最新年値を見ると、日本、フランスは1.4、ドイツ、英国は1.6、米国は1.7である。中国、韓国は名目額よりは少ないが、それぞれ16.5、4.8と他国と比較すると際だって大きな伸びを示している。
(A)名目額(OECD購買力平価換算)
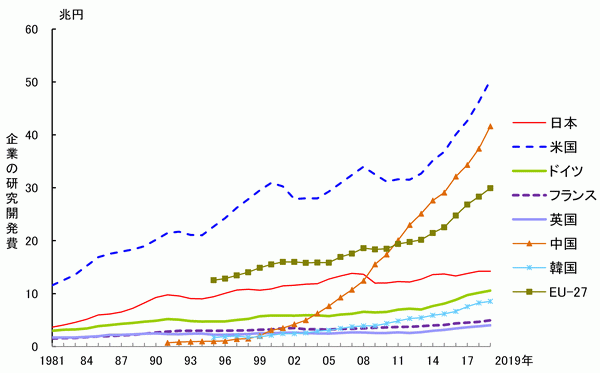
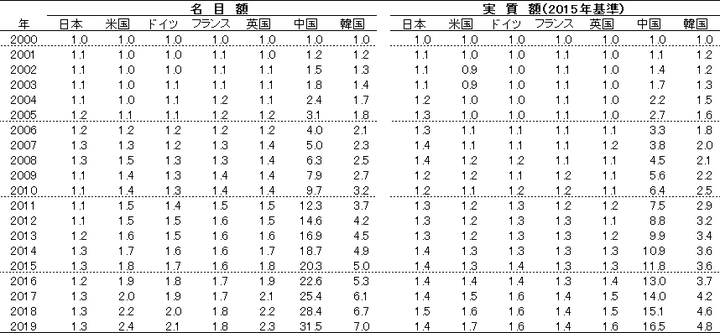
注:
1) 各国企業部門の定義は図表1-1-4を参照のこと。
2) 研究開発費は人文・社会科学を含む(韓国は2006年まで自然科学のみ)。
3) 購買力平価は、参考統計Eと同じ。
4) 実質額の計算はGDPデフレータによる(参考統計Dを使用)。
5) 日本は年度の値を示している。
6) 米国の2019年は見積り値。
7) ドイツは1990年までは旧西ドイツ、1991年以降は統一ドイツ。1982、1984、1986、1988、1990、1992、1994、1996、1998、2018、2019年は見積り値である。1993年値は定義が異なる。
8) フランスは1992、1997、2001、2004、2006年において時系列の連続性は失われている。2017、2018年は暫定値、2019年は見積り値である。
9) 英国は1986、1992、2001年において時系列の連続性は失われている。2019年は暫定値である。
10) 中国は1991~1999年は過小評価されるか、過小評価されたデータに基づく。2000年、2009年において時系列の連続性は失われている。
11) EU-27は見積り値である。
資料:
日本:総務省、「科学技術研究調査報告」
米国:NSF,“National Patterns of R&D Resources: 2018?19 Data Update”
ドイツ、フランス、英国、中国、韓国、EU:OECD,“Main Science and Technology Indicators 2020/2”
参照:表1-3-3
各国の経済規模の違いを考慮して研究開発費を比較するために、企業部門における研究開発費の対GDP比率を見る(図表1-3-4)。日本の2019年の対GDP比率は2.54%である。1989年以降、主要国第1位であったが、2010年からは韓国が日本を上回った。韓国の2019年は3.73%であり、主要国の中では著しく大きい値となっている。
米国は長期的に見ると漸増傾向にある。ドイツは、1990年代の中頃から増加し続けている。2010年頃から両国とも同程度の規模で推移している。2019年において米国は2.27%、ドイツは2.19%である。
中国の値は急激に上昇し、英国、EU-27、フランスの値を超えており、2019年では1.71%である。
2019年ではフランスが1.44%、英国は1.19%である。フランスは2010年代に入って、ほぼ横ばいなのに対して、英国は漸増している。
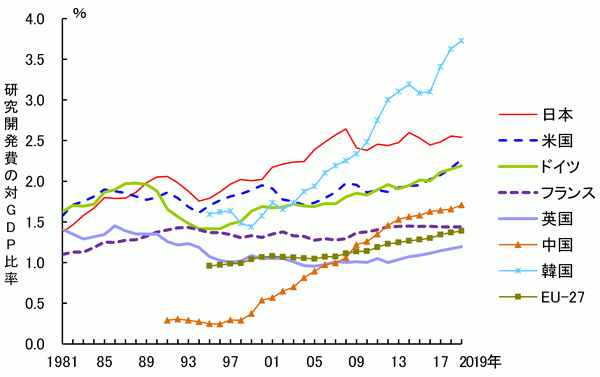
注及び資料:
研究開発費は表1-3-3と同じ。GDPは参考統計Cと同じ。
参照:表1-3-4
(2)主要国における産業分類別(19)の研究開発費
主要国における企業部門の製造業と非製造業の研究開発費について、各国最新年からの3年平均で見ると(図表1-3-5)、製造業の割合は日本、ドイツ、中国、韓国では約9割であり、製造業の重みが大きい。米国では製造業の割合が約6割であり、上述した国と比較すると、非製造業の割合が大きい傾向にある。製造業の割合は、フランスでは5割、英国では4割であり、非製造業の重みが大きい。

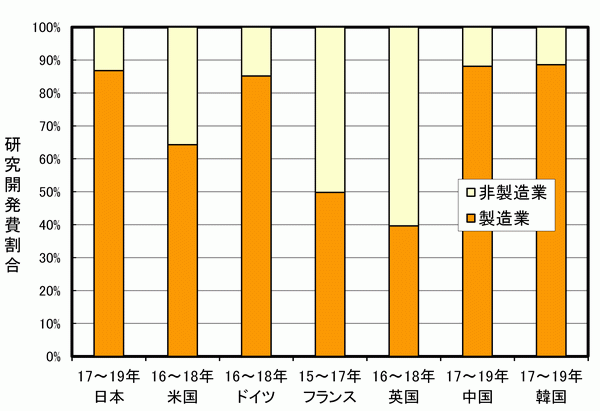
注:
1) 国際標準産業分類第4次改定版(ISIC Rev.4)に準拠しているため、各国の産業分類とは異なる。
2) 各国とも研究開発を行う企業の主な経済活動(Main economic activity)に応じて分類している。
3) 米国では、「Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting」及び「Public Administration」は除かれている。よって、他国の非製造業と異なっているため、国際比較する際は注意が必要である。
資料:
OECD, “Structural Analysis (STAN) Databases”
参照:表1-3-5
さらに詳細な産業分類別での研究開発費を見る(図表1-3-6)と、米国は2008年時点では、「コンピュータ、電子・光学製品製造業」が最も多かったが、非製造業である「情報通信業」が増加し続け、2014年以降は最も研究開発費の多い産業となった(2018年で11.4兆円)。
中国は製造業の伸びが著しい。特に、「コンピュータ、電子・光学製品製造業」が大きく伸びている(2019年で6.6兆円)。非製造業についての内訳はなく、製造業と比較すると規模も小さいが、増加傾向にある。
日本の製造業では、2008年時点では、「コンピュータ、電子・光学製品製造業」が最も多かったが、その後は減少している。これに代わって「輸送用機器製造業」は増加し続けており、2013年以降は最も多くなっている(2019年で4.0兆円)。また、「医薬品等製造業」は漸増していたが、近年は横ばい傾向である。非製造業では、「専門・科学・技術サービス業」が最も多く、次いで「情報通信業」が多い。
ドイツは、継続して「輸送用機器製造業」が最も多く、増加し続けている。次いで多いのは「コンピュータ、電子・光学製品製造業」である。非製造業では「専門・科学・技術サービス業」が多くかつ増加している。
フランスは非製造業である「専門・科学・技術サービス業」が最も多く、2017年で1.2兆円である。非製造業で次いで多いのは「情報通信業」の0.6兆円である。製造業では「輸送用機器製造業」が多い(0.7兆円)。
英国も非製造業である「専門・科学・技術サービス業」が最も多く、2012年以降は継続して増加している。これに加えて、「輸送用機器製造業」や「情報通信業」も規模が大きく、増加している。
韓国は「コンピュータ、電子・光学製品製造業」が最も多くかつ増加の度合も大きい。2019年では4.3兆円である。非製造業では「情報通信業」が最も多い。
2010年から最新年の製造業、非製造業の研究開発費の伸びに注目すると、中国は非製造業と比べて製造業、米国は製造業と比べて非製造業の伸びが顕著に大きい。
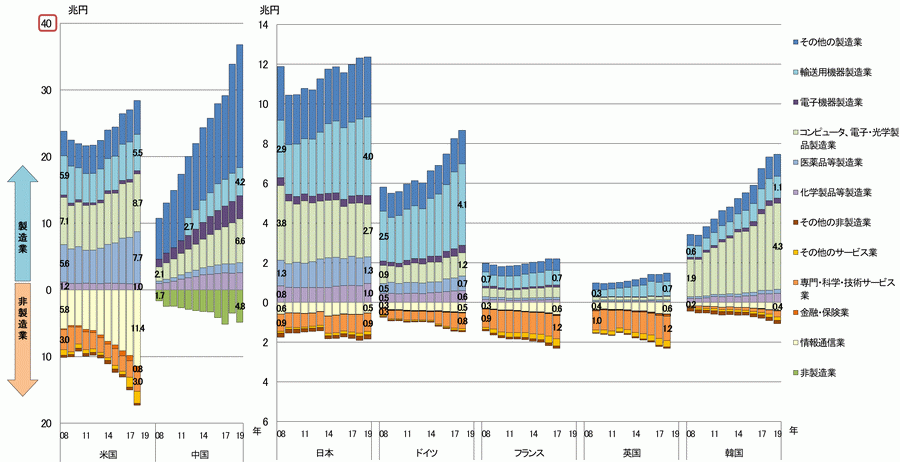
注:
1) 国際標準産業分類第4次改定版(ISIC Rev.4)に準拠しているため、各国の産業分類とは異なる。
2) 各国とも研究開発を行う企業の主な経済活動(Main economic activity)に応じて分類している。
3) 米国では、「Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting」及び「Public Administration」は除かれている。よって、他国の非製造業と異なっているため、国際比較する際は注意が必要である。
資料:
OECD, “Structural Analysis (STAN) Databases”
参照:表1-3-6
(3)日本の産業分類別研究開発費
日本の研究開発は、どの業種において、より多く実施されているのかを見るために、売上高に占める研究開発費の割合(研究開発の集約度)を産業分類別に見た(図表1-3-7)。
まず、製造業と非製造業を比較すると、前者が3.1%であるのに対して、後者は0.3%となっており、売上高に占める研究開発費の割合が10倍近く異なる。日本の企業部門における売上高に占める研究開発費の割合が最も大きいのは「医薬品製造業」であり8.3%を示している。これに「業務用機械器具製造業」が7.4%、「情報通信機械器具製造業」が5.4%で続いている。研究開発費の規模が大きい「輸送用機械器具製造業」(図表1-3-6参照)は売上高に占める研究開発費の割合が必ずしも大きいわけではなく、4.4%である。研究開発費の規模と集約度は産業によって異なる傾向を示している。
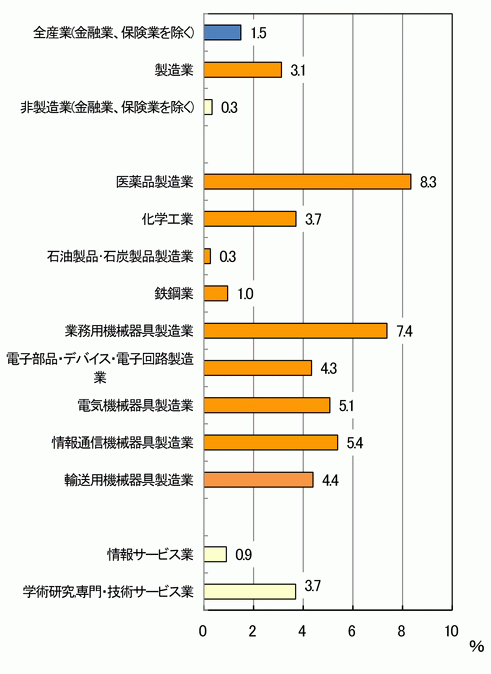
注:
1) 研究開発を実施していない企業も含んでいる。
2) 全産業及び非製造業は金融、保険業を除く。
資料:
総務省、「科学技術研究調査報告」
参照:表1-3-7
(4)企業への政府による直接的・間接的支援
企業の研究開発のための政府による支援の状況を示す。
「直接的支援(企業の研究開発費のうち政府が負担した金額)」及び「間接的支援(企業の法人税のうち、研究開発税制優遇措置により控除された税額)」を対GDP比で見ると(図表1-3-8(A))、日本はここで示した国の中で直接的支援が最も小さく、直接的支援より、間接的支援が大きい。他国を見ると、直接的支援が最も大きいのはロシアであり、次いでハンガリー、韓国と続く。間接的支援が大きいのはフランス、英国、イタリアなどである。
次に、日本についての政府からの直接的、間接的支援の推移を見ると(図表1-3-8(B))、政府から企業への直接的支援は長期的には減少傾向にある。間接的支援は変動が大きく、2004年に著しく増加した後、2008年には減少し、2013年には再び増加した。最近の間接的支援は、対GDPで0.11~0.12%となっている。
間接的支援の変化には、いくつかの要因が考えられる。一つは研究開発税制優遇措置の変更である。大きな制度改正は数年ごとにあるが、細かな制度改正はほぼ毎年実施されている。二つめは特定企業の税制優遇措置額の変化である。例えば、連結法人の法人税額の特別控除額について、2013年(20)では上位10社で全体の約70%を占めており、対象年における特定企業の研究開発税制優遇措置額によって全体の額が大きく変化する事が分かる。最後に、市場経済(景気・不景気)の変化である。税法上の所得(=益金?損金)がない場合、優遇税制措置の適用が発生しない。間接的支援の2004年の急増については、2003年に導入された「試験研究費の総額にかかる税額控除制度」による制度上の税額控除額の増加が主な理由と考えられ、この制度を活用する企業が2004年に増えたと推測される。2008年の減少については、法人税全額の減少が、控除額の減少につながったと考えられる。2013年の増加については、特定企業による税制優遇措置額の増加によるものと考えられる。
(A)各国比較(2018年)
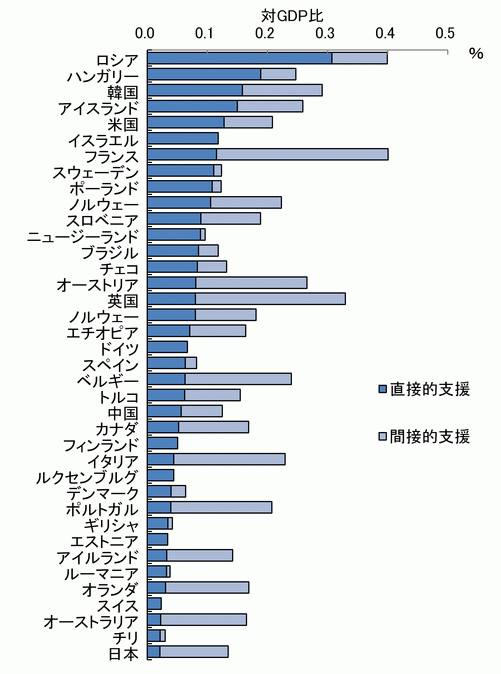
注:
1) 直接的支援とは、企業の研究開発費のうち政府が負担した金額の対GDP比率である。
2) 間接的支援とは、企業の法人税のうち、研究開発税制優遇措置により控除された税額の対GDP比率である。
3) 各国からの推計値 (NESTIが行った研究開発税制優遇調査による)、予備値も含まれる。
4) 米国、ルーマニアは2016年、フランス、ニュージーランド、ブラジル、ベルギー、中国、スイス、オーストラリアは2017年、その他の国は2018年。
5) イスラエルは研究開発税制優遇のデータが提供されなかった。
資料:
OECD,“R&D Tax Incentive Indicators ”
参照:表1-3-8
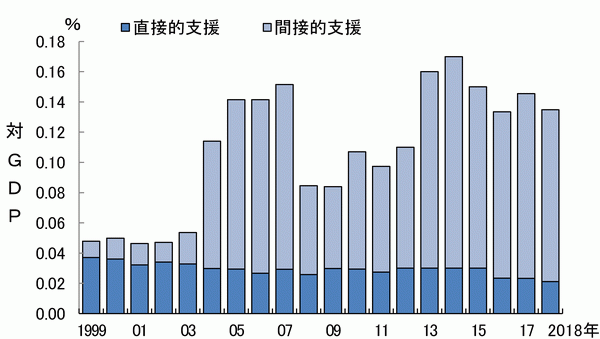
資料:
総務省、「科学技術研究調査報告」、国税庁、「会社標本調査」、2011年以降はOECD, “STI Scoreboard ”及び “R&D Tax Incentive Indica-tors”の各年
参照:表1-3-8
次に、政府からの企業の研究開発における直接的支援を従業員規模別で見る(図表1-3-9)。
日本では、従業員数500人以上の企業に対する政府による直接的支援の割合が全体の73.3%を占める。これに対して従業員数49人以下の企業の割合は16.7%である。
米国では、従業員数500人以上の企業の割合が全体の84.8%を占める。これに次いで従業員数50~249人の企業が大きいが7.8%程度である。
ドイツでは、従業員数500人以上の企業の割合が49.1%を占める。ただし、従業員数49人以下の企業でも21.9%、従業員数50~249人の企業でも21.4%と、この2つの企業規模においても割合が大きい傾向にある。
フランスでは、従業員数500人以上の企業の割合が70.7%を占める。これに次いで大きいのは従業員数49人以下の企業であり、17.4%を占めている。
英国では、従業員数500人以上の企業の割合が全体の76.9%を占める。これに次いで大きいのは、従業員数50~249人の企業であり9.7%を占める。
韓国では、従業員数49人以下の企業が46.2%と他国と比較して大きい。また、従業員数50~249人の企業でも22.3%と大きく、249人以下の企業で政府による直接的支援の約7割を占める。
米国や英国では大規模企業に政府からの支援が集中しているが、韓国やドイツでは中小規模企業への支援も一定の重みを持つことが分かる。日本については、49人以下の割合が2018年では6.2%であったものが、2019年では16.7%となっており、前年と比べて大幅に増加した。
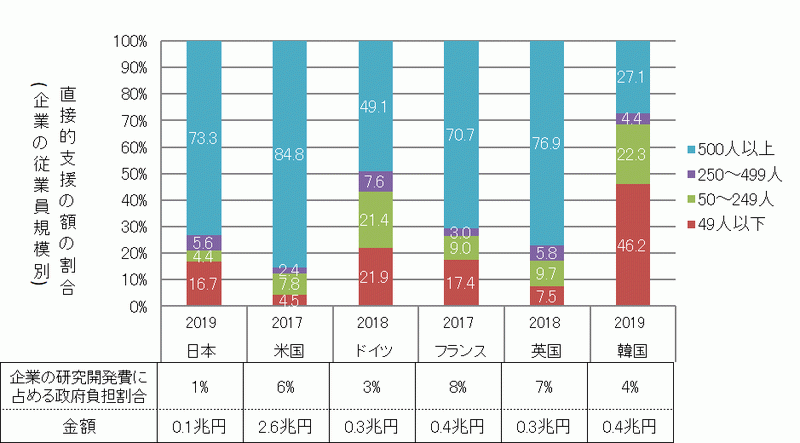
注:
1) 日本は年度の値を示している。
2) 米国は連邦政府のみの値である。定義が異なる。
3) フランスは暫定値である。
4) 購買力平価は、参考統計Eと同じ。
資料:
OECD, “R&D statistics”
参照:表1-3-9
(5)日本企業の外部支出研究開発費に見る研究活動のオープン化・グローバル化
企業の製品やサービス等に、人工知能や機械学習等の新しい知識を迅速に導入するには、自社における研究開発活動に加えて、社外の知識や研究開発能力を活用していく(オープン化していく)必要がある。また、企業活動がグローバル化するにつれ、研究開発活動もグローバル化することが予想される。そこで、ここでは企業の外部支出研究開発費の動向に注目することで、研究開発活動のオープン化・グローバル化の状況を把握する。
図表1-3-10(A)に、企業の外部支出研究開発費の時系列変化とその内訳を示した。2000年代後半に一時的に落ち込む時期があるが、外部支出研究開発費は長期的に増加傾向にある。2019年度では前年比5.1%減の2.4兆円となったが、1999年度の1.2兆円と比べると2倍に増加している。同期間における、企業の内部使用研究開発費は33.7%の増加であり、外部支出研究開発費の方が、増加の度合が大きい、つまり企業の研究開発活動のオープン化が進んでいることが分かる。
国内と海外を比べると2001年度~2019年度にかけて、国内への外部支出の増加率が24.9%であるのに対して、海外への外部支出の増加率は474.5%である。この結果として、外部支出研究開発費における海外への支出分の割合は、2001年度には9.9%であったものが、2019年度には33.6%となっており、研究開発のグローバル化が進展している。
次に、外部支出先の組織の形態に注目すると、2019年時点では外部支出研究開発費の60.9%が国内の会社、32.8%が海外の会社であり、会社が主要な支出先となっている。
図表1-3-10(B)は、外部支出先として大学のみを取り出し、その割合を見たものである。最新のデータを見ると国内の国公立大学への外部支出が一番多く、これに海外の大学、国内の私立大学が続いており、企業から大学への外部支出という点では、日本の大学が主要な支出先であることが確認できる。
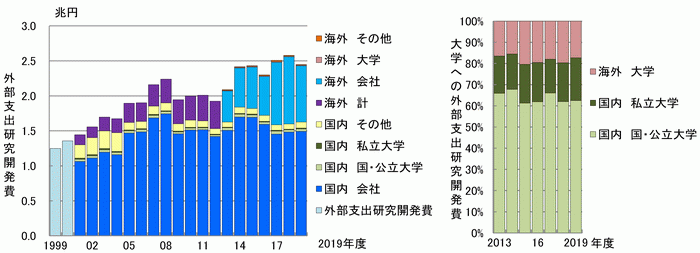
注:
国内のその他には国・公営の研究機関、特殊法人・独立行政法人の研究所、公庫・公団、非営利団体などを含む。
資料:
総務省、「科学技術研究調査報告」
参照:表1-3-10
(18)この節の日本は、国際比較の際には「年」を用いている。本来は「年度」である。日本のみを記述している節では「年度」を用いている。
(19)企業部門の産業分類の方法には、主な経済活動(Main economic activity)によるものと、産業方向性別区分(Industry orientation)によるものがある(OECD フラスカティ・マニュアル 2015 [7.48-7.50])。前者は企業の経済的アウトプットの重みが最も大きい産業分類に基づく分類であり、後者は研究開発活動を報告する際に、最も適当であると思われる産業分類に分類する方法である。
(20)財務省、「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」


