
「科学技術指標」は、我が国の科学技術活動を客観的・定量的データに基づき、体系的に把握するための基礎資料であり、科学技術活動を「研究開発費」、「研究開発人材」、「高等教育と科学技術人材」、「研究開発のアウトプット」、「科学技術とイノベーション」の5つのカテゴリーに分類し、約160の指標で我が国の状況を表している。本概要では「科学技術指標2018」において、注目すべき指標を紹介する。今版では、コラムに掲載したものも含めて、21の指標について、新規に掲載又は可視化方法の工夫を行った。
なお、本年は科学技術・学術政策研究所の創立30周年に当たることから、科学技術指標の生みの親である丹羽冨士雄氏に、科学技術指標の誕生期から開発期にかけてのエピソードとこれからへの期待を寄稿して頂いた。
1.研究開発費から見る日本と主要国の状況
(1)日本の研究開発費総額は、米国、中国に続く規模であり、2016年では18.4兆円(OECD推計:16.9兆円)である。
2016年の日本の研究開発費総額は、18.4兆円(日本(OECD推計):16.9兆円)であり、対前年比は-2.7%(日本(OECD推計):-3.0%)である。米国は世界第1位の規模を保っており、2016年では51.1兆円である。中国は2016年では45.2兆円となり、長期的に増加傾向にあるEUを超えている。
日本の研究開発費の対前年比を部門別で見ると、公的機関では-7.3%、企業では-2.7%、大学では-1.1%(OECD推計による大学では-2.7%)である。

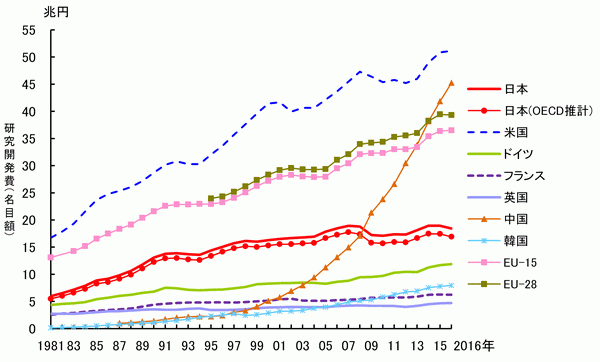
参照:科学技術指標2018図表1-1-1
(2)部門別で見ると、いずれの主要国でも企業が多くを占めている。
部門別では、いずれの主要国でも企業の研究開発費が最も大きい。この傾向はアジア諸国で顕著である。欧州主要国では比較的、企業とそれ以外の部門での差異が少ない。
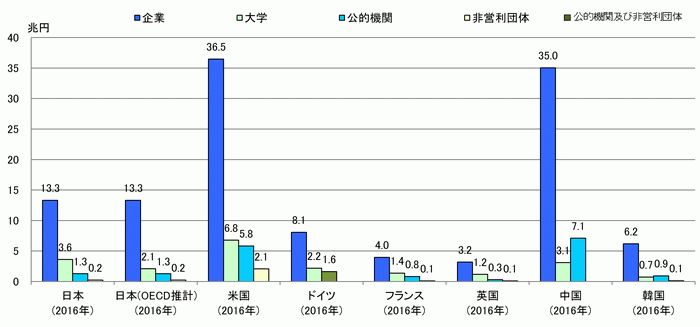
参照:科学技術指標2018図表1-1-6
(3)日本の研究開発費の流れを見ると、企業の負担割合が最も大きく、そのほとんどは企業へ流れている。企業から大学への流れは小さく、大学の使用額全体の2.8%である。
日本(OECD推計)を用いて負担部門から使用部門への研究開発費の流れを見ると、企業の負担割合が最も大きく、そのほとんどは企業へ流れている。企業から大学への流れは小さく、大学の使用額全体の2.8%である。政府から他部門への研究開発費は公的機関への流れが最も大きく48.6%であり、これに大学が42.9%と続く。
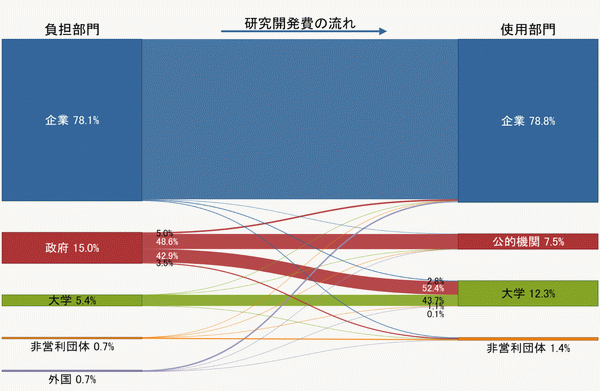
参照:科学技術指標2018図表1-1-5
(4)日本の製造業の研究開発費を見ると、「コンピュータ、電子・光学製品製造業」が減少する一方、「輸送用機器製造業」は増加し続け、2015年では3.6兆円となっている。
米国では、製造業、非製造業共に拡大している。なかでも「情報通信業」の増加が突出している。日本、ドイツ、韓国は、製造業が大きく、非製造業は小さい傾向にある。ドイツは、米国ほどではないが、製造業、非製造業共に拡大する傾向にある。フランス、英国では、他国と比べて非製造業の重みが大きい傾向にある。
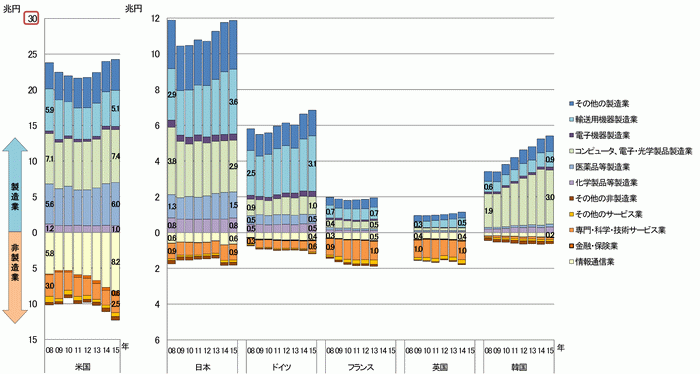
参照:科学技術指標2018図表1-3-6
(5)日本企業の外部支出研究開発費は、長期的に増加している。なかでも海外への支出の増加の度合が大きい。大学への支出に注目すると国内の国公立大学への外部支出が多い。
日本の企業が、外部に支出している研究開発費を見ると、長期的に増加している。国内と海外を比較すると、海外への支出の方が増加の度合が大きい。内訳を見ると、国内、海外ともに会社への外部支出が一番大きい。大学への支出に注目すると、国内の国公立大学への外部支出が一番多く、2016年度では、これに海外の大学、国内の私立大学が続いている。
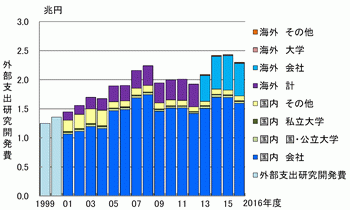
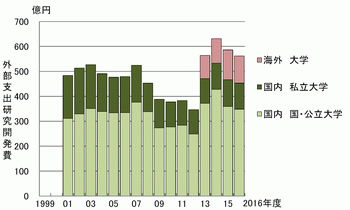
注:
1)1999、2000年度は総額のみを示している。2013年度より、海外への外部支出研究開発費の内訳(会社、大学、その他)が計測されるようになった。
2)概要図表5(B)において2012年度以前の海外の大学は掲載していない。
参照:科学技術指標2018図表1-3-11
2.研究開発人材から見る日本と主要国の状況
(1)日本の研究者数は2017年において66.6万人であり、中国、米国に次ぐ第3位の規模を持っている。部門別で見ると、ほとんどの国で企業の研究者数が最も多い。
日本の研究者数は2017年において66.6万人(実数(HC: Head Count)値は91.8万人)であり、中国、米国に次ぐ第3位の研究者数の規模を持っている。韓国の研究者数は2010年以降ではフランス、英国を上回り、最新年ではドイツと同程度となっている。部門別では、ほとんどの国で研究開発費と同様に企業の研究者数が最も多いが、英国については大学の研究者数が最も多い。


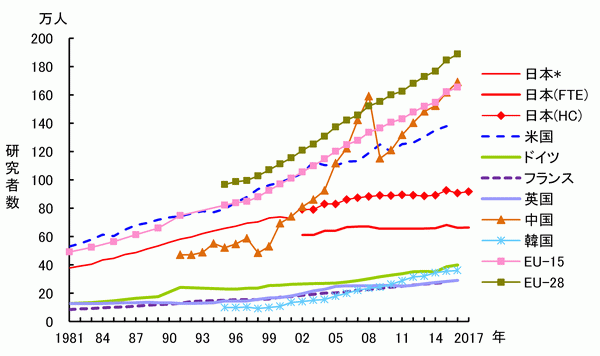
注:
中国の2008年までの研究者の定義は、OECDの定義には完全には対応しておらず、2009年から計測方法を変更したため、2008年以前と2009年以降では差異がある。その他の国の国際比較や時系列比較についての注意事項については、本編参照のこと。
参照:科学技術指標2018図表2-1-3
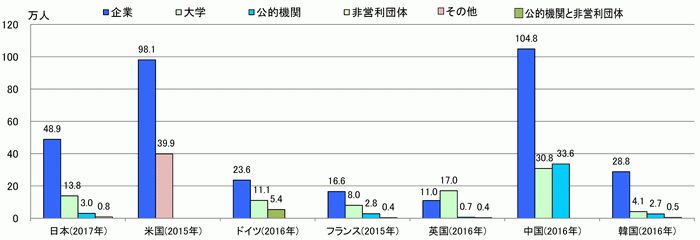
注:
1)全ての国はFTE値である。
2)米国はOECDによる見積もり数値であり、近年、企業部門以外の数値がないため、企業とそれ以外について数値を示した。
参照:科学技術指標2018図表2-1-7
(2)日本の製造業では工学系の専門的知識を持つ研究者が多くを占める。
産業分類別に、その業種に所属する研究者の専門分野を見ると、製造業で多くを占める「輸送用機械器具製造業」では「機械・船舶・航空」分野を専門とする研究者が多く、「情報通信機械器具製造業」では「電気・通信」分野を専門とする研究者が多い。非製造業の「情報通信業」では「情報科学」を専門とする研究者が多くを占めている。他の産業分類では「情報科学」を専門とする研究者は少ない。
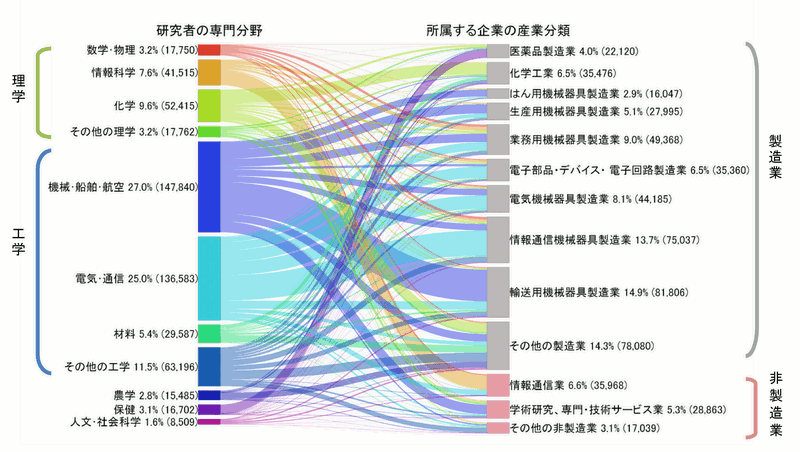
注:
HC値である。( )内は研究者数である。
参照:科学技術指標2018図表2-2-8
(3)日本の女性研究者の数は2017年時点では144,126人であり、ほぼ一貫して増加傾向にある。各国とも女性研究者の割合が小さいのは企業であり、大学での割合はどの国においても大きい傾向にある。
日本の女性研究者の数は2017年時点では144,126人であり、ほぼ一貫して増加傾向にある。割合についても、着実に増加している。また、2017年の女性の博士号保持者は29,114人である。2016年と比較すると5.6%の増加率であり、女性研究者数全体の増加率4.1%より大きい。部門別の状況を見ると、各国とも企業における女性研究者の割合は小さく、大学では大きい傾向にある。
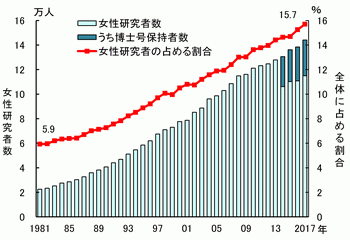
参照:科学技術指標2018図表2-1-11
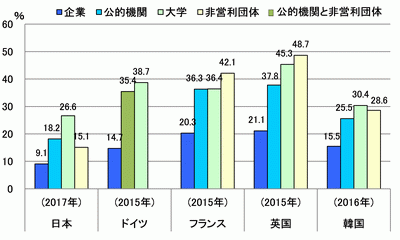
参照:科学技術指標2018図表2-1-10
(4)日本の新規採用研究者に占める女性の割合は、いずれの部門においても、研究者全体に占める女性の割合よりも大きい。
新規採用研究者においては、いずれの部門でも女性と比べて男性が多い。新規採用研究者に占める女性の割合は、研究者全体に占める女性の割合よりも大きい。なお、企業では、男性、女性共に新規採用研究者数が増加している。転入研究者においては、いずれの部門でも女性と比べて男性の転入研究者が多い。女性の転入研究者の割合は大学等で大きく、約3割である。
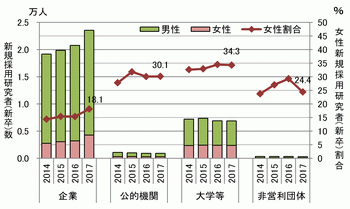
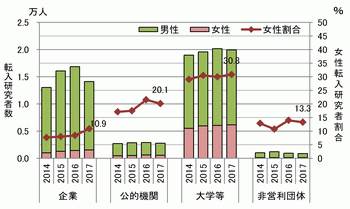
参照:科学技術指標2018図表2-1-20
(5)日本の大学等における任期有り研究者は、保健分野における割合が高い。男性研究者と比べて女性研究者の方が、任期有り研究者の割合が高い傾向にある。
大学等における任期有りの研究者の割合は、国公私立大学別、学問分野別で見ても、ほとんどの属性で、男性研究者と比べて女性研究者の方が高い傾向にある。
学問分野別では保健分野で任期有り研究者の割合が高く、国公私立大学別に見ると、国立大学で高い傾向にある。保健分野は男女差が少ない傾向であるのに対して、理学、工学、農学では、任期有り研究者の割合の男女差が著しい。
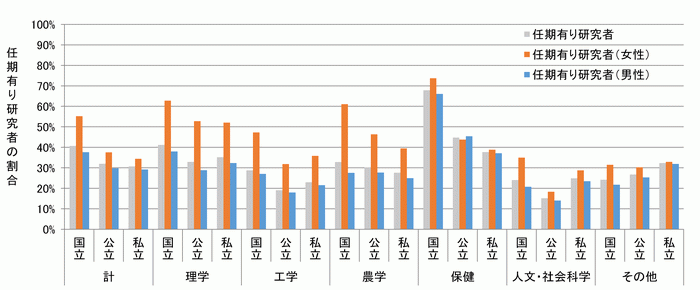
注:
1)教員及びその他の研究員を対象としている。
2)ここでの任期無し研究者は、教員及びその他の研究員のうち、雇用契約期間の定めがない者(定年までの場合を含む)をいう。任期有り研究者とは、任期無し研究者以外を指す。
参照:科学技術指標2018図表2-2-14
3.大学生・大学院生から見る日本の状況
(1)主要国の中では日本のみ人口100万人当たりの修士、博士号取得者数が減少している。日本は他の主要国と比べて、人文・社会科学系における修士、博士号取得者数が少ない。
人口100万人当たりの学士・修士・博士号取得者についての分野バランスを見ると、学士号取得者では人文・社会科学系が多くを占めている国が多い。日本においては、修士、博士号取得者になるにつれ、自然科学系が多くなる傾向にあるが、他国では修士号取得者でも人文・社会科学系が最も多い若しくは同程度であり、博士号取得者において自然科学系が最も多くなる傾向にある。
人口100万人当たりの学士・修士・博士号取得者について、日本以外の国は全ての学位で増加している。日本の学士号取得者数は増加しているが、修士号取得者は微減、博士号取得者は減少している。
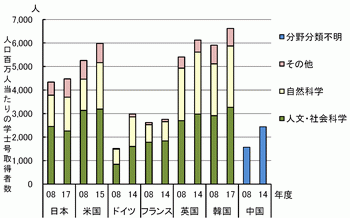
参照:科学技術指標2018図表3-4-1
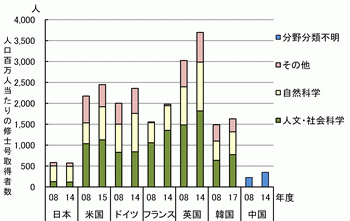
参照:科学技術指標2018図表3-4-2
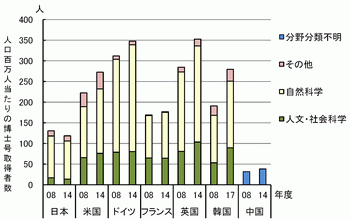
参照:科学技術指標2018図表3-4-3
注:
1)米国の博士号取得者は、“Digest of Education Statistics”に掲載されている“Doctor's degrees”の数値から医学士や法学士といった第一職業専門学位の数値のうち、「法経」、「医・歯・薬・保健」、「その他」分野の数値を除いたものである。
2)中国については、分野別の数値は不明。
3)各分野分類については以下が含まれる。
人文・社会科学:人文・芸術、法経等
自然科学:理学、工学、農学、医・歯・薬・保健
その他:教育・教員養成、家政、その他
4.研究開発のアウトプットから見る日本と主要国の状況
(1)10年前と比較して日本の論文数(分数カウント)は微減であり、他国の拡大により順位を下げている。順位の低下は、注目度の高い論文(Top10%補正論文数、Top1%補正論文数)において顕著である。
研究開発のアウトプットの一つである論文(自然科学系)に着目すると、論文の生産への貢献度を見る分数カウント法では、日本の論文数(2014-2016年(PY)の平均)は、米、中、独に次ぐ第4位である。また、Top10%補正論文数では、米、中、英、独、伊、仏、豪、加に次ぐ第9位であり、Top1%補正論文数では米、中、英、独、豪、仏、加、伊に次ぐ第9位である。
10年前と比較して、日本の論文数は微減であり、他国の論文数の拡大により順位を下げていることが分かる。順位の低下は、特にTop10%補正論文やTop1%補正論文といった注目度の高い論文において顕著である。
(自然科学系、分数カウント法)
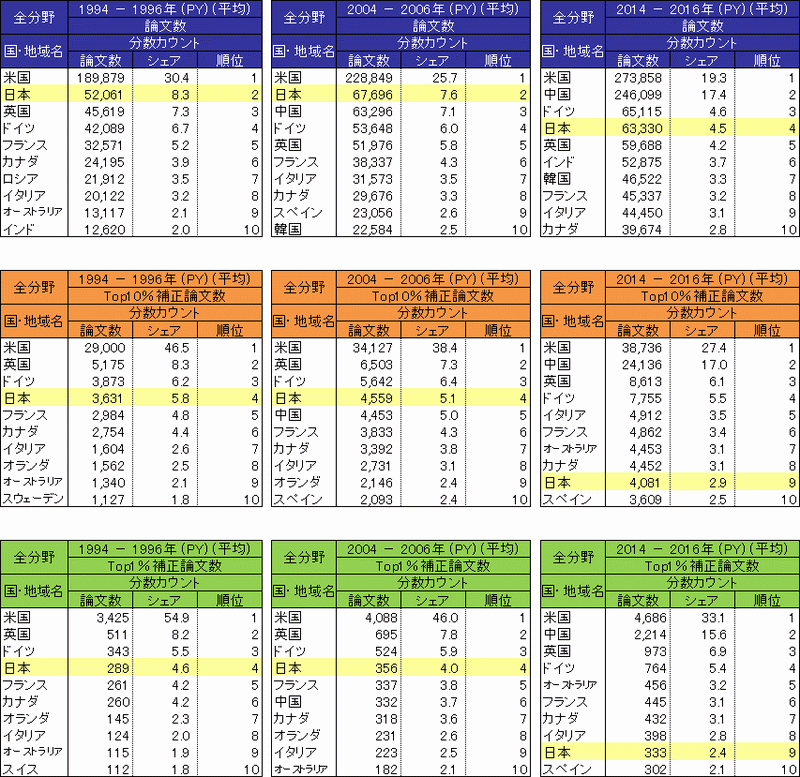
注:
分析対象は、Article, Reviewである。年の集計は出版年(Publication year, PY)を用いた。被引用数は、2017年末の値を用いている。
参照:科学技術指標2018図表4-1-6
(2)日本の「経済学・経営学」や「社会科学・一般」の論文数(整数カウント法)は、過去20年間で、世界全体の論文数よりも大きく伸びており、シェアも増加している。しかし、順位については、「経済学・経営学」では10位から15位、「社会科学・一般」では14位から24位となっている。
「経済学・経営学」及び「社会科学・一般」について、世界全体の雑誌数及び論文数(SSCI:Social Sciences Citation Indexに収録されているもの)を見ると、両分野ともに2005年以降、雑誌数・論文数が急激に伸びている。
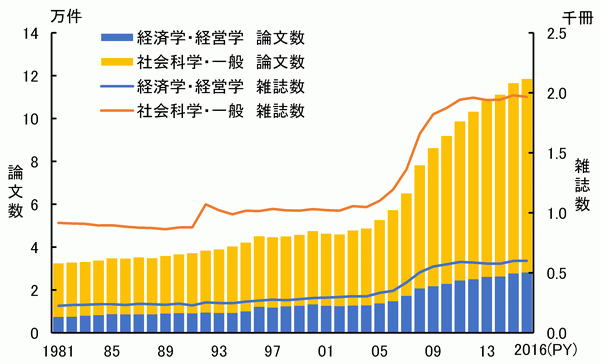
注:
1)社会科学・一般:教育学、社会学、法学、政治学等。
2)分析対象は、Article, Reviewである。整数カウント法による。年の集計は出版年(Publication year, PY)を用いた。
参照:科学技術指標2018図表4-1-11
日本の「経済学・経営学」の論文数は、過去20年間で136件から565件へと4.2倍に増加した。シェアも1.3%から2.1%に増加しているが、順位は10位から15位に低下している。日本の「社会科学・一般」の論文数も、同期間に188件から868件へと4.6倍に増加した。シェアも0.6%から1.0%と増加しているが、順位は14位から24位に低下している。国・地域別の論文数を見ると、社会科学の中でも、「経済学・経営学」と、法律・社会制度や言語に左右される研究対象を扱う教育学、法学、政治学などを含む「社会科学・一般」では、英語圏・非英語圏の国・地域で順位の傾向に違いがある。
ここでは、英語論文を中心に収録がなされているSSCIを用いて分析を行った。社会科学では、著書など論文以外の成果の発表手段が重視されることもあるため、社会科学全般の活動状況をSSCIによって計測することは難しい。しかし、世界の論文数は長期的に増加しており、英語論文も成果発表手段として一定の役割を果たすようになっていることから、社会科学の研究活動の一部を国際比較可能な形で計測する一手段となり得ると言える。
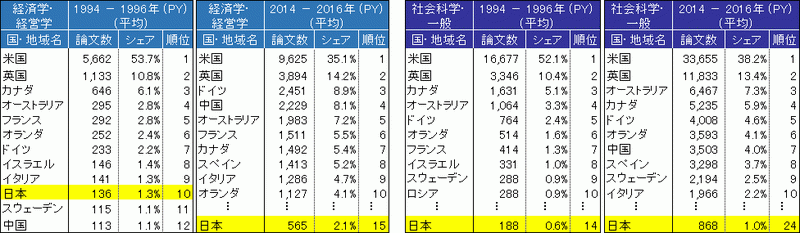
注:
概要図表15と同じ。
参照:科学技術指標2018図表4-1-12
(3)日本は10年前から引き続きパテントファミリー(2か国以上への特許出願)数において、世界第1位を保っている。韓国や中国のパテントファミリー数シェアの増加に伴い、「情報通信技術」、「電気工学」における日本のシェアは低下している。
特許出願に着目し、各国・地域から生み出される発明の数を国際比較可能な形で計測したパテントファミリー数を見ると、1991-1993年は米国が第1位、日本が第2位であったが、2001-2003年、2011-2013年では日本が第1位、米国が第2位となっている。日本のパテントファミリー数の増加は、単一国ではなく複数国への特許出願が増加したことを反映した結果である。中国はパテントファミリー数で見れば、2011-2013年で第5位であるが、着実にその数を増やしている。
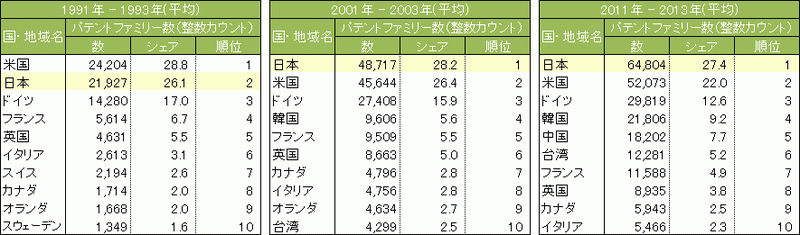
注:
パテントファミリーとは優先権によって直接、間接的に結び付けられた2か国以上への特許出願の束である。通常、同じ内容で複数の国に出願された特許は、同一のパテントファミリーに属する。
参照:科学技術指標2018図表4-2-5
2011-2013年のパテントファミリー数におけるシェアに注目すると、日本は「電気工学」、「一般機器」が35%を超えており、「バイオ・医療機器」、「バイオテクノロジー・医薬品」のシェアが相対的に低いというポートフォリオを有している。「情報通信技術」と「電気工学」の世界におけるシェアは、共に6ポイント程度減少している。これは、中国と韓国が急激に世界シェアを増加させているためである。
(%、2001-2003年と2011-2013年、整数カウント法)
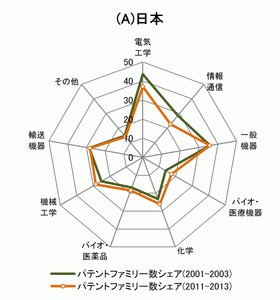
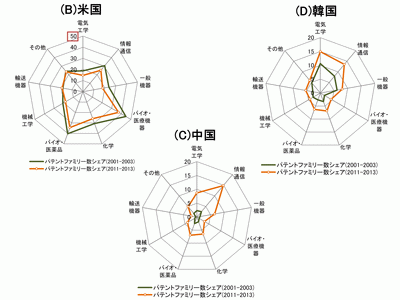
注:
概要図表17と同じ。概要図表18の項目「バイオ・医薬品」は「バイオテクノロジー・医薬品」の略であり、「情報通信」は「情報通信技術」の略である。
参照:科学技術指標2018図表4-2-10
(4)論文を引用している日本のパテントファミリー数は世界第2位であるが、日本のパテントファミリー数に占める割合は小さい。
科学と技術のつながり(サイエンスリンケージ)を見るために、パテントファミリーが引用している論文の情報を用いて分析を行った。論文を引用しているパテントファミリー数を国・地域別に見ると、日本は世界第2位である。しかし、日本のパテントファミリーの中で論文を引用しているものの割合は9.4%であり、日本の技術は他国と比べて科学的成果を引用している割合が低い。
他方、パテントファミリーに引用されている論文数では米国に次いで多く、日本の論文は技術に多く引用されている。
リー数:上位10か国・地域
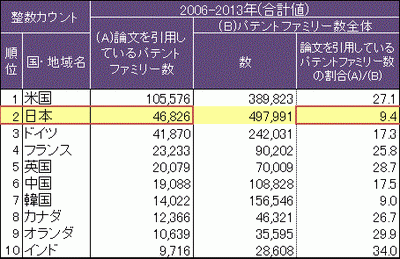
参照:科学技術指標2018図表4-3-2
る論文数:上位10か国・地域
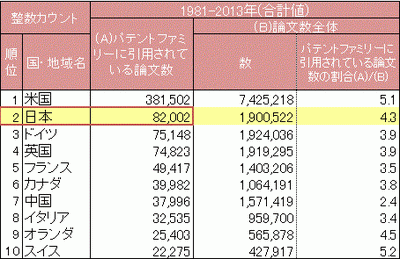
参照:科学技術指標2018図表4-3-3
(5)論文被引用度の高い論文ほど、パテントファミリーに引用されている論文数割合が高い。つまり、科学的成果として注目度が高い論文は、技術からの注目度も高い。
論文被引用度によってパテントファミリーから引用される度合に違いがあるのかを把握するため、パテントファミリーに引用されている論文数の割合を論文被引用度ごとに見る。
1994年以降に発行された世界の論文全体のうち4.2%が、2006-2013年のパテントファミリーに引用されている。論文被引用度別に見ると、Top1%論文では31.9%、Top10%論文では14.9%、Top20%論文では11.1%となっており、論文被引用度の高い論文ほどパテントファミリーに引用されている論文数の割合が高くなっている。Top20%論文までで、パテントファミリーから引用される論文の約半分を占める。
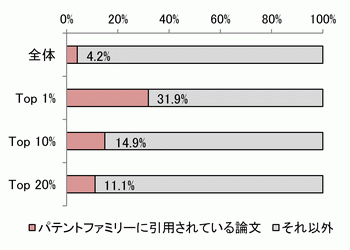
注:
2006-2013年に出願されたパテントファミリーに引用されている1994年以降(直近20年)に発行された論文を対象に算定。
参照:科学技術指標2018図表4-3-9
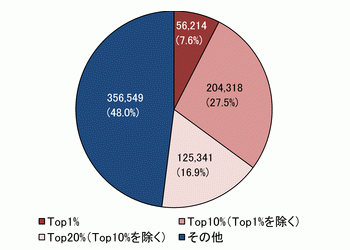
注:
概要図表21と同じ。
参照:科学技術指標2018図表4-3-8
5.科学技術とイノベーションから見る日本と主要国の状況
(1)主要国の産業貿易輸出の構造を見ると、ミディアムハイテクノロジー産業が最も多くを占める国が多い。日本の輸出の約6割をミディアムハイテクノロジー産業が占める。
2016年においてミディアムハイテクノロジー産業の割合が大きな国は日本(56.8%)、次いでドイツ(50.0%)である。中国では、ハイテクノロジー産業が最も多くを占めている(30.4%)。中国は、ミディアムロウテクノロジー産業の割合も27.6%と高く、それぞれの産業が一定の重みを持っている。
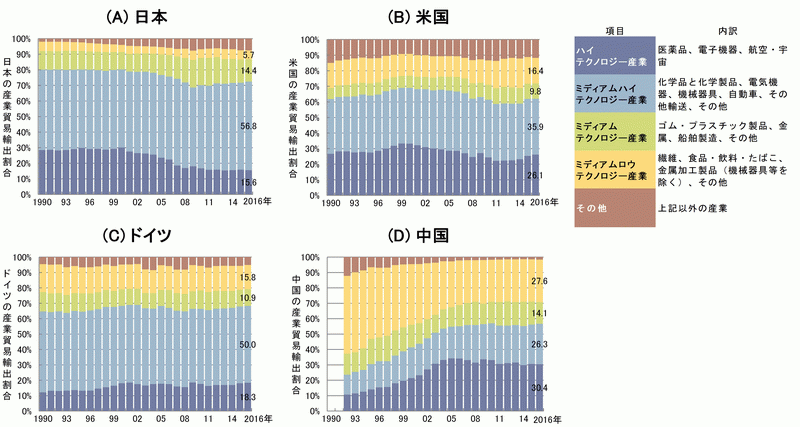
注:
各産業は研究開発集約のレベル(研究開発費/粗付加価値)に基づくOECDの分類による。
参照:科学技術指標2018図表5-2-1
(2)日本のハイテクノロジー産業貿易収支比は、主要国の中でも低い数値である。他方、ミディアムハイテクノロジー産業においては、日本は主要国で第1位を維持している。
ハイテクノロジー産業貿易収支比を見ると、日本は継続して貿易収支比を減少させており、2016年の日本の収支比は0.75である。日本のミディアムハイテクノロジー産業貿易収支比は2.73であり、主要国中第1位である。推移を見ると、1990年代中頃に、急激な減少を見せた後は漸減傾向にある。
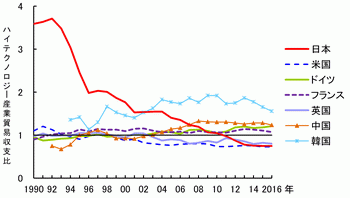
注:
1)ハイテクノロジー産業とは「医薬品」、「電子機器」、「航空・宇宙」を指す。
2)貿易収支比=輸出額/輸入額
参照:科学技術指標2018図表5-2-3
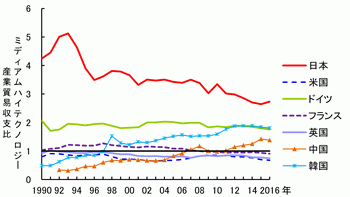
注:
1)ミディアムハイテクノロジー産業とは、「化学品と化学製品」、「電気機器」、「機械器具」、「自動車」、「その他輸送」、「その他」を指す。
2)貿易収支比=輸出額/輸入額
参照:科学技術指標2018図表5-2-5
(3)日本の大学と民間企業との共同研究実施件数及び研究費受入額は着実に上昇している。
民間企業等との共同研究等にかかる受入額と実施件数を見ると、受入額が最も大きいのは「共同研究」であり537億円、実施件数は2.3万件である。大企業からの受入額が多く、同年で429億円を占める。次いで、「治験等」の受入額が大きく、171億円である。
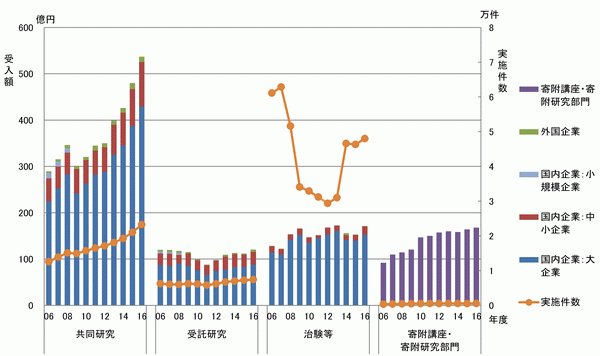
注:
共同研究:機関と民間企業等とが共同で研究開発することであり、相手側が経費を負担しているもの。受入額及び件数は、2008年度まで中小企業と小規模企業と大企業に分類されていた。
受託研究:大学等が民間企業等から委託により、主として大学等が研究開発を行い、そのための経費が民間企業等から支弁されているもの。
治験等:大学等が外部からの委託により、主として大学等のみが医薬品及び医療機器等の臨床研究を行い、これに要する経費が委託者から支弁されているもの。治験以外の病理組織検査、それらに類似する試験・調査も含む。
寄附講座・寄附研究部門:国立大学のみの値
参照:科学技術指標2018図表5-4-6
(4)日本の企業による論文数は減少しているが、そのうちの産学共著論文数の割合は増加している。
日本の企業による論文数は減少しているが、そのうちの産学共著論文数(日本の企業と大学等による共著論文数)の割合は増加している。産学共著論文数の割合は1982年には22%であったが、2015年には67%となっており、企業での論文を生み出すような研究活動における大学等の重みが増している。
分野別で見ると、企業の論文数は、多くの分野で減少している。物理学、基礎生命科学等における企業の論文数の減少は非産学共著論文数の減少による。臨床医学及び環境・地球科学では企業の論文数は増加しているが、それに対する産学共著論文の増加への寄与は大きい。
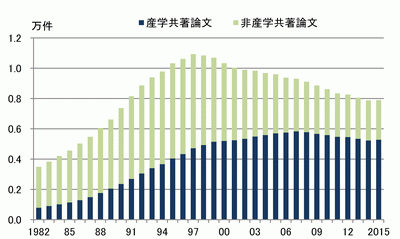
注:
分析対象は、Article, Reviewであり、整数カウント法を用いた。3年移動平均値である。
参照:科学技術指標2018図表5-5-1
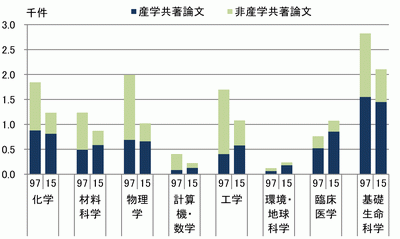
注:
概要図表27と同じ。
参照:科学技術指標2018図表5-5-2
科学技術・学術政策研究所創立30周年記念コラム:科学技術指標の開発に携わって
科学技術指標の生みの親である丹羽冨士雄氏に、科学技術指標の誕生期から開発期にかけてのエピソードとこれからへの期待を寄稿して頂きました。
1.はじめに
科学技術・学術政策研究所(1)が発足して30年を迎え、その間政府の科学技術政策のシンクタンクとして枢要な機能を果たし、進化し続けてこられたことは関係者の認めるところである。
科学技術指標の開発は研究所の活動として創立当初からの重要な役務の一つであり、最近は毎年報告書として公刊されている。
著者は指標の開発に関わり、その担当者として研究所発足時に第2研究グループの総括主任研究官に任じられた。本コラムでは、著者と指標との関わり、指標開発の様子、今後の期待等を紹介させていただきたい。
2.科学技術指標の誕生期
科学技術指標開発の始まりは、科学技術政策研究所の前身である資源調査所の時代に遡る。筑波大学の助教授であった筆者に当時の所長から電話があり、科学技術指標の開発に着手するので参加して欲しいとの依頼があった。
科学技術指標のための研究委員会が1984年に立ち上げられ、研究者の一人として、参加することになった。委員会は月に1回程度の開催だったと思うが、ほぼ毎回筆者が前回での議論の内容をKJ図解(2)にし、次回の議論の初めにスチールボードに貼り出し、簡単に説明した。議論は上からと下からの2方向から行った。上からとは指標の理念は何か、指標開発の目標は何か、必要とされる具体的な指標は何か、などである。例えば、新聞の発行部数や書籍、なかでも科学技術関連書籍の発行部数など、文化や歴史、思想に関するものまで幅広く提出された。存在するか否かは問わず、理念から必要な指標を列挙した。他方、下からとは具体的に入手できる統計は何か、どのように分析したら指標にできるのか、国際比較するためにどうしたらよいか、などを議論した。当時、指標の源になる統計は総務庁の科学技術研究調査ばかりでなく、文部省、科学技術庁、通産省、法務省など多くの省庁にあること、重要な調査も継続的でないものがあることなどが分かった。
指標の研究で最も参考にしたのは、当時世界で唯一の報告書型の指標であった米国の指標報告書(Science Indicators)だった。なお、報告書の初版は1972年刊行であるが、その2年前に専門家委員会を発足させ、我々と同じように目的や意義、内容等について充実した議論をし、それを報告書として発刊していた。そこで我々はNSF(National Science Foundation)を訪問し(3)、発行担当の責任者に会い、専門家委員会、意義、目的の他具体的な統計の収集方法や分析法、編集等について聞いた。編集にcompileという言葉を多用し、プログラムの機械語翻訳という意味に慣れていた著者には新鮮であった。報告書の利用については、全国会議員の事務室に数部ずつ配布されているということで、科学技術予算や研究施設、性別や人種差別問題などで引用されるとのことであった。日本の作業を報告したところ、随時協力するとのことであった。
また、著者はかなりの頻度で研究会に議論すべき論点等をメモと言う形で提出した。例えば、なぜ今指標の開発が必要かという点では、日本の科学技術の状況を全体的に計量的に把握する、海外に発信する(日本からの発信が強く求められていた)、我が国の科学技術政策の策定に活用する、国民に現状を知らせるなどである。また、個別の指標を論ずることは適切でなく、科学技術活動の全体を把握するものでなければならないこと、活動を直接支える活動から、それを支援するもの、さらにそれを支えるものと続き、活動の結果も直接的なものから間接的なものへと進む、など。研究会では、これを素材にしてさらに精緻に議論を進めていった。
3.科学技術指標の開発期
(1)指標の体系 カスケード構造
このようにして得られたのが科学技術指標の体系である。米国でもOECDでもこのような議論はされていなかったようである。構造は、一国の科学技術活動を把握するためには、全体的および総合的に理解する必要があり、そのためには細部から構造化された全体的な体系が必要であるという主張である。概要図表29では水が上から下へ階段に沿って流れ落ちるような形態をしているのでカスケード構造と名付けられた。
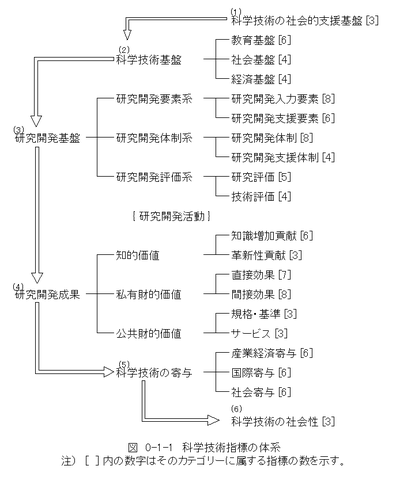
資料:
科学技術政策研究所、「体系科学技術指標一我が国の科学技術活動-」NISTEP REPORT No.19 (1991年9月)
上から下への流れは主要な影響の流れであり、当然至る所でフィードバックが発生することは言うまでもない。また、体系の頂点、即ち出発点にあるのは社会的支援であり、これは国民の支援が重要であることを意味している。一方、最底部にあるのは社会性であり、これは国民が製品の購入やシステムの活用で利便を得たり、ノーベル賞などで誇りを得たりすることを意味している。即ち、体系は、国民の支持から始まり、国民の受容で終わっていることを太い柱にしている。
後年になり評価論が議論されたが、この体系の下部は、Output、Outcome、Impactに合致する。またNational Innovation System論の視点からは、主体(Actor)間の関係ではなく、主体の活動による機能の関係を示すものと言える。特に機能間の相互関係を示唆するものになっている。
研究会では、指標の機能には、現状報告型、判定型(個別目的の達成度を判定する合成指標)、政策評価型の3つの型があると考えた。加えて、当初の報告書は現状報告型が望ましいとする方針を示した。図にはかっこ([ ])内に指標数が示してある。これはそのカテゴリーに属する具体的な指標を列挙し、その数を示したものである。これらをまとめた報告書は素案の段階から何度も資源調査会で報告し、調査会報告書となった。
(2)指標報告書の刊行と指標研究
1988年に資源調査所が科学技術政策研究所に改組された。筆者は第2研究グループの総括主任研究官になり、科学技術指標の更なる開発を進めることになった。
指標の開発は、先の資源調査会で承認された報告書の枠を基に進めて行った。具体的には、列挙された指標の存否を確認すること、継続性や定義との合致性など適切性を判断すること、他に適切な指標があるか捜すことなどであった。特に、最後の作業においては、カスケード構造という体系があるので、体系の位置から検討して適切性を判断できた。体系はまさに羅針盤という働きをしてくれた。このような作業を積み上げて、1991年に最初の報告書「体系科学技術指標」を発刊することができた。刊行は第2研究グループだけでなく全所をあげて尽力いただいた賜物であった。
一般に社会調査では、その目標が3分類されている。それは国勢調査など基盤的なもの、問題を解決するための支援になるもの、理論の構築に資するものの3つである。先述のように、最初の指標は基盤的なものをと決められていた。筆者達はその枠組みに従いつつも将来の展開を思えば、問題解決型、研究型も重要と考え、その開発に努力した。問題解決型では、例えば日本では科学技術活動の入力側が充実しつつあるのに対し、論文やその被引用数など出力側が相対的に弱いこと、技術は強いが科学や理論が弱いことなどを指標で示そうとした。その後ポスドク問題などいくつもの指標が開発されている。
(3)科学技術総合指標
研究型では、当初はレベルの高いものではなかった。まず、一変数の時系列分析に加えて、二変数の時系列関係を見ようとした。具体的には、研究開発費と研究者数やGDPとの関係、論文や特許とそれらの被引用数等、枚挙に暇がない。これらは二変数の関係を数量的に見て、その因果関係や各国の相違の背景にあるものを推定しようとしたものである。また、図表も工夫した。二変数の時系列表示もその例であり、その他研究開発費の負担側から使用側への移動はエネルギー変換で使用される例に倣って、流れ図で表現した。これらの成果は以後の指標報告書だけではなく、科学技術白書や科学技術要覧等の国内、さらに、外国の指標報告書にも採用されている。
科学技術総合指標(General Indicator of S&T、GIST)の開発は典型的な研究型である。日米英独仏5か国の12の基本的で比較可能な指標を対象に、因子分析と主成分分析を施した。因子分析では対象国の科学技術活動の構造を明らかにすることができた。それは、研究、技術、開発というものでOECDの論理を具体的な統計で支持するものとなった。同時に各国の時系列の動きを示すことができ、日本は開発側、フランスは研究側、米独はその中間にあり、各国とも開発側に移動している。これらの動きの解釈については様々な議論を楽しむことができた。
また、主成分分析法を用いた総合科学技術指標では、米国が大きいばかりではなく大きく伸びており、日本は2位だが欧州諸国と共にその伸びは小さかった。1990年頃にはほぼ人口比であった総合指標比は、2010年頃には米国の値は日本の4倍程になった。この図を紹介する度に科学技術総合力の格差の拡大に警鐘を鳴らし続けてきた。
指標の多変量解析についてはその後も続け、IMD(International Institute for Management Development)の科学技術の競争力に関するデータに共分散構造分析を応用した。その結果、科学技術競争力が、パワー、集約度、マネジメント政策、人材の4つで構成されること、科学技術活動は直接経済発展(GDP)に貢献せず、間に科学技術マネジメント政策(産学連携や知財制度の整備等)が充実している必要があることを示した。
(4)国際発信の取組
①日本での国際会議
研究所として重視したのは国際発信であった。まず研究所自身が1990年から3回にわたり国際会議(4)を主催した。アジアでこのような会議を開くのは初めてであり、参加者も国際的に著名な錚々たる研究者達(5)だった。筆者は、最初の国際会議では、指標の体系化、2年目では研究開発の多様化、3年目では科学技術活動の発展モデルを発表した。これは、産業、技術、科学、人材の諸相が順に発展し、各前者が各後者の発展の牽引力となり、各相内でもまず量が拡大し次いで質が高度化するというものである。いずれも指標で表示した。
②OECD NESTIへの参加
国際発信の第2はOECDの指標開発専門家グループ(NESTI)会合への出席で、著者はそのメンバーになった。グループはそれまで日本からのメンバーを希望していたにも関わらず、適切な窓口がなく、関連部署に招待状を出していたが、欠席の返事しかなかったと言う。
会合は年に2度ほどあり、フラスカティ・マニュアルを始原とする各種科学技術指標や既存以外の指標のマニュアル化を検討していた。グループには検討メンバーの他に、文書化や分析を担当するメンバーもおり充実していた。筆者は、まず日本が本格的に科学技術指標の開発に取り組み出したこと、検討委員会で議論した理念や体系の紹介、二変量解析の現状や途中経過の報告などを行った。メンバーは温かく迎えてくれた一方で、新参加者が既にかなりな検討と実績を積みつつあることに驚いた様子でもあった。
印象に残ったのは、NESTIの各国がマニュアル開発の担当を決める時、予測を引き受ける国がどこも無かった。著者が挙手して引き受ける旨発言したところ、議長から”Thank you, indeed.”と言われた。NESTIについてはその後日本から科学技術・学術政策研究所の所員や関係者が参加され大活躍されている。
研究発表も機会を見つけて精力的に行った。そのハイライトは指標の英語版(1992年刊)を紹介した時である。OECDの指標のかなり大きな会合で発表し、実際に指標の報告書を高く掲げて新刊ほやほやの報告書を示した。NESTIの友人からも祝福された。
科学技術指標は狭い分野なので、研究を含めて発表することに努めた。中心は研究・技術計画学会であったが、他に日本工学アカデミーでも発表し、それが縁で筆者はアカデミー会員になり、政策委員会委員になり、科学技術政策の体系化の提言書を作成し、政策委員会委員長になる出発点になった、また、国外では、OECD、IAMOT、後述するSTEPAN、AAASなどで発表した。
③アジア太平洋地域への展開
もう一つの海外発信はアジア太平洋地域である。当時STEPAN(Science and Technology Policy Asian Network)というアジア太平洋諸国を対象にした科学技術政策に関するユネスコのローカル組織があり、筆者もそのメンバーになった。年1回の会合であったが、筆者は毎回研究発表をした。それには先に紹介した我が国の指標研究の成果ばかりでなく、アジア諸国を対象にした科学技術経済データを分析したものも加えた。フランス、オーストラリア、フィリピン、インドネシアの研究者や行政官と情報や意見の交換を深めることができた。
日本の指標研究が進化していくとその評判を聞いて科学技術指標開発の研修を依頼されることもあった。1週間以上の研修を行ったのは、インドネシア、フィリピンそして中国であった。教材には指標報告書と研究論文を使用した。
4.おわりに:今後に期待すること
その後、指標報告書は毎年発行され、内容も充実していき、それを支える人材も育っている。また、新しい指標の開発等も随時実施されている。
筆者達の世代は戦後の貧しい時に育ち、汗水たらして一生懸命働けば世の中はよくなると確信して働いてきた。それなのにバブルがはじけて残ったのは格差である。筆者は今格差を対象にした政策策定と実施、それを適切に支援するエビデンス指標が必須であると考えている。既に格差の状況に関する統計(6)は充実しているようである。格差と科学技術は遠いようであるが、格差は世代を越えて再生産されるなど広がりと深みが大きいことを考えるなら、社会科学と科学技術との緊密な連携が必須である。格差の縮小を目標に、全体的に課題を把握し、その要因と対策を体系化し、関連する統計を収集して、指標化する必要がある。科学技術指標の開発検討委員会で行ったような熱い議論はできないものであろうか。
また基盤型では、いわゆるソフトパワーの指標が充実されることを期待したい。国力には経済力等ばかりでなく、ソフトパワー(文化力)の貢献も大きいと言われている(7)。現状の科学技術指標は経済力に関連の深いものが多い。しかし、科学技術活動は体系化でも示したように、文化に関係するものも多い。科学技術自身が文化の一部である。先端の科学技術は文化と関係して文化の発展に大きく寄与し、社会の急激な革新に貢献している。文化力と言っても未だ定義は曖昧のようであるし、どのような指標が収集できるか明確ではない。しかし、文化がパワーになることは確実であるし、そうだとすれば、その開発に着手しても遅くないであろう。
(客員研究官 丹羽 冨士雄)
科学技術指標の特徴
科学技術指標は、毎年刊行しており、その時点での最新値を紹介している。原則として毎年データ更新され、時系列の比較あるいは主要国間の比較が可能な項目を収集している。
- 各国が発表している統計データを使用
科学技術指標で使われている指標のデータソースは、できる限り各国が発表している統計データを使用している。また、各国の統計の取る方がどのようになっていて、どのような相違があるかについて、極力明らかにしている。 - 論文・特許データベースについて当研究所独自の分析の実施
論文データについては、クラリベイト・アナリティクス社Web of Science XMLの書誌データを用いて、当研究所で独自の集計をし、分析している。また、集計方法も詳細に記載し、説明している。
特許関連の指標のうち、パテントファミリーのデータについては、PATSTAT(欧州特許庁の特許データベース)の書誌データを用いて、当研究所で独自の集計をし、分析している。また、集計方法も詳細に記載し、説明している。 - 国際比較や時系列比較の注意喚起マークの添付
必要に応じ、グラフに「国際比較注意」 「時系列注意」
「時系列注意」 という注意喚起マークを添付してある。各国のデータは基本的にはOECDのマニュアル等に準拠したものであるが、実際にはデータの収集方法、対象範囲等の違いがあり、比較に注意しなければならない場合がある。このような場合、「国際比較注意」マークがついている。また、時系列についても、統計の基準が変わるなどにより、同じ条件で継続してデータが取られておらず、増減傾向などの判断に注意する必要があると考えられる場合には「時系列注意」というマークがついている。なお、具体的な注意点は図表の注記に記述してあるので参照されたい。
という注意喚起マークを添付してある。各国のデータは基本的にはOECDのマニュアル等に準拠したものであるが、実際にはデータの収集方法、対象範囲等の違いがあり、比較に注意しなければならない場合がある。このような場合、「国際比較注意」マークがついている。また、時系列についても、統計の基準が変わるなどにより、同じ条件で継続してデータが取られておらず、増減傾向などの判断に注意する必要があると考えられる場合には「時系列注意」というマークがついている。なお、具体的な注意点は図表の注記に記述してあるので参照されたい。 - 統計集(本報告書に掲載したグラフの数値データ)のダウンロード
本報告書に掲載したグラフの数値データは、以下のURLからダウンロードできる。
https://www.nistep.go.jp/research/science-and-technology-indicators-and-scientometrics/indicators
本編中の図表の下に示している参照とは、統計集における表番号を示している。
(1) 発足時は科学技術政策研究所。2013年に改組された。本稿では、基本的に、組織名等は当時の名称で記述している。
(2)KJ法 川喜田二郎氏(元東京工業大学教授)が考案した創造性開発(または創造的問題解決)の技法。蓄積された情報から必要なものを取り出し、関連するものをつなぎあわせて整理し、統合する手法の一つである。
(3)報告書はNSB(National Science Board)発行になっているが、実際に作成しているのはNSFである。
(4)1990年に開催された「科学技術政策研究国際コンファレンス」であり、第1回のテーマは「What should be done? What can be done?」
(5)主な研究者は、Richard R. Nelson (Columbia University, U.S.A)、Lewis M. Branscomb (Harvard University, U.S.A )、Don E. Kash (The University of Oklahoma, U.S.A)他、海外からの参加者は数十名に及ぶ。筆者とDon E. Kash教授とはオクラホマ大学を訪問し、最新の研究を交換していた。教授は日本の科学技術を研究されており、筆者の研究開発の多様化の研究(まず人材の専門が多様化し、次いで資金配分が多様化する)に興味を示された。
(6)「社会階層と社会移動調査(SSM調査)」など。
(7)Joseph Samuel Nye, Jr. (Harvard University, U.S.A )


