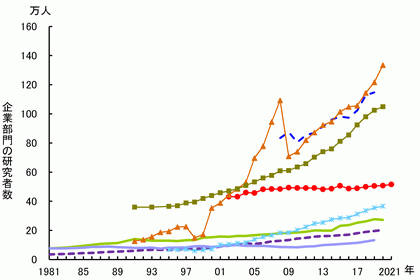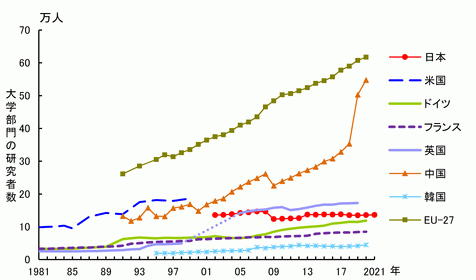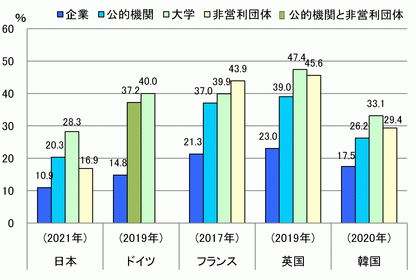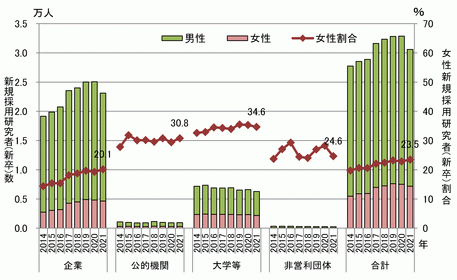(3) 日本の大学部門や企業部門の研究者数の伸びは他の主要国と比べて小さい。
企業及び大学部門の研究者数は、中国が主要国中1番の規模である。企業部門では、米国と中国が拮抗しつつ、両国ともに急速な伸びを見せている。日本の企業部門の研究者数は2000年代後半からほぼ横ばいに推移していたが、2017年以降は微増している。また、韓国の企業部門の研究者数は長期的に増加している。大学部門では、ドイツは2000年代中頃から研究者数が増加している。日本の伸びは緩やかであり、最近は横ばい傾向である。
(4) 2000年代前半に主要国中第1位であった、日本の労働力人口1万人当たりの研究者数は、最新年では第4位である。
労働力人口当たりの研究者数は、2020年において、多い順に見ると、韓国が160.4人、フランスが109.4人、ドイツが103.8人、日本が98.8人、米国が97.0人(2019年)、英国が93.1人(2019年)、中国が29.1人となっている。日本は2000年代前半では主要国の中で労働力人口1万人当たりの研究者数が最も多い国であったが、近年では主要国中第4位である。
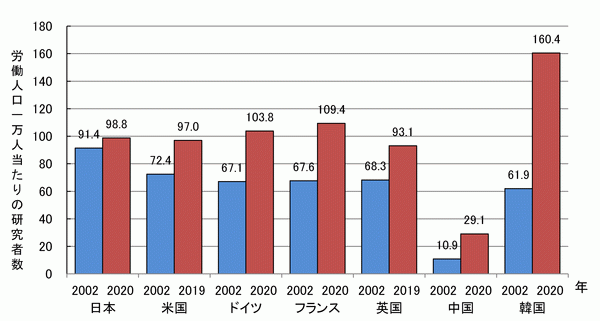
(5) 日本の女性研究者割合はOECD諸国・地域等の中で最も小さい。
日本の全研究者に占める女性割合は2021年で17.5%である。その割合は、OECD諸国・地域等の中で、最も小さいが、その数で見ると、英国、ドイツに次いで多い。
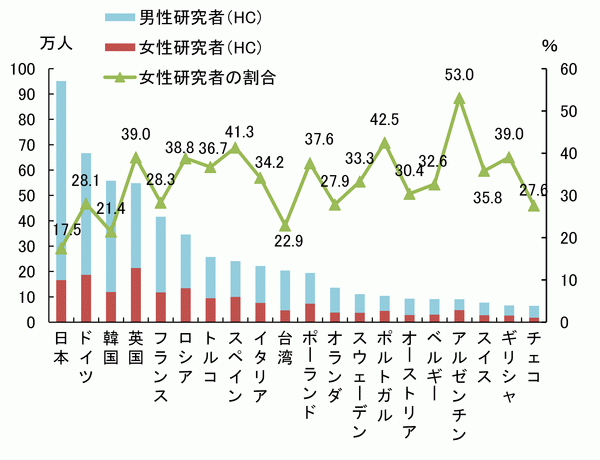
(6) 日本の女性研究者割合は主要国と比べて低いが、研究者の新規採用に占める女性割合は増加している。
研究者に占める女性割合は、主要国のいずれでも企業において低い傾向にある。日本の女性研究者割合は、いずれの部門においても他国と比較すると低い。日本における新規採用研究者の状況を見ると、いずれの部門でも新規採用研究者における女性の割合は、各部門の女性研究者割合よりも高い傾向にある。