
「科学技術指標」は、我が国の科学技術活動を客観的・定量的データに基づき、体系的に把握するための基礎資料であり、科学技術活動を「研究開発費」、「研究開発人材」、「高等教育」、「研究開発のアウトプット」、「科学技術とイノベーション」の5つのカテゴリーに分類し、約150の指標で我が国の状況を表している。本概要では「科学技術指標2017」において、注目すべき指標を紹介する。今版では、コラムに掲載したものも含めて、25の指標について、新規に掲載又は可視化方法の工夫を行った。
1.研究開発費から見る日本と主要国の状況
(1)日本の研究開発費総額は、米国、中国に続く規模であり、2015年では18.9兆円(OECD推計:17.4兆円)である。部門別で見ると、いずれの国でも企業が多くを占めている。
2015年の日本の研究開発費総額は、18.9兆円(日本(OECD推計):17.4兆円)である。米国は世界第1位の規模を保っており、2015年では51.2兆円である。中国は2015年では41.9兆円となり、長期的に増加傾向にあるEUを超えている。部門別では、いずれの主要国でも企業の研究開発費が最も大きい。この傾向はアジア諸国で顕著であるが、欧州主要国では比較的、企業とそれ以外の部門での差異が少ない。

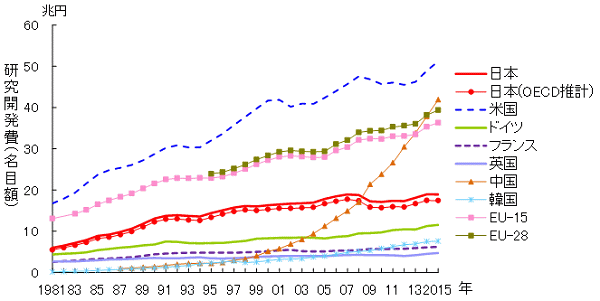
参照:科学技術指標2017図表1-1-1
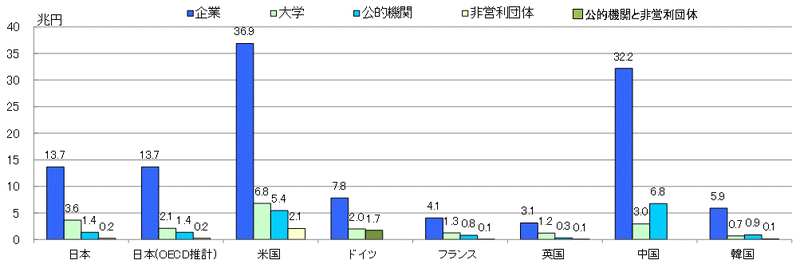
参照: 科学技術指標2017図表1-1-6
(2)日本の科学技術予算の対GDP比率は0.65%であり、主要国中では韓国、中国、ドイツ、米国に次ぐ規模である。
国の経済規模による違いを考慮して比較するために、科学技術予算の対GDP比率を最新年で見ると、日本が0.65%、米国が0.80%、ドイツが0.88%、フランスが0.63%、英国が0.54%、中国は1.02%である。韓国は1.21%と主要国中トップである。
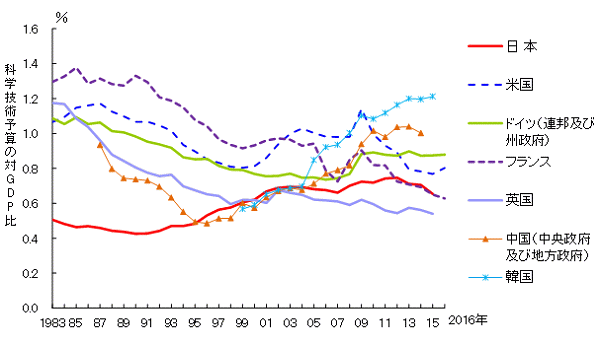
参照:科学技術指標2017図表1-2-2
(3)日本の研究開発費の流れを見ると、「企業」の負担割合が最も大きく、そのほとんどは「企業」へ流れている。「企業」から「大学」への流れは小さく、「大学」の使用額全体の2.6%である。
日本(OECD推計)を用いて負担部門から使用部門への研究開発費の流れを見ると、「企業」の負担割合が最も大きく、そのほとんどは「企業」へ流れている。「企業」から「大学」への流れは小さく、「大学」の使用額全体の2.6%である。「政府」から他部門への研究開発費は「公的機関」への流れが最も大きく、49.6%であり、これに「大学」が41.9%と続く。
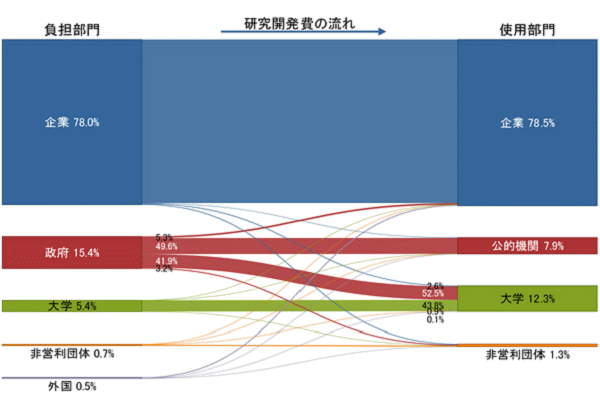
参照:科学技術指標2017図表1-1-5
(4)日本は政府から企業への直接的支援が他国と比較して最も小さく、間接的支援の方が大きい国である。
政府からの直接的支援(企業の研究開発費のうち政府が負担した金額の対GDP比率)、間接的支援(企業の法人税のうち、研究開発税制優遇措置により控除された税額の対GDP比率)を見ると、日本は直接的支援が小さく、間接的支援が大きい。他国を見ると、直接的支援が最も大きいのはロシアであり、次いで米国、韓国、ハンガリーと続く。間接的支援が大きいのはアイルランド、フランス、ベルギー、韓国などである。韓国は直接的支援、間接的支援ともに大きい。
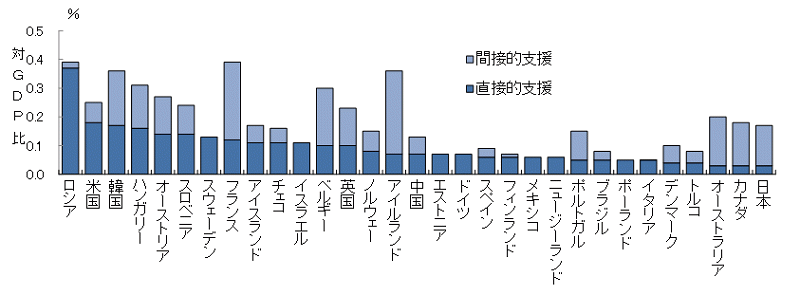
注:
ロシアは2011年、ベルギーは2012年、米国、フランス、中国、ニュージーランド、ブラジル、イタリア、オーストラリアは2013年。その他の国は2014年である。スウェーデン、イスラエル、ポーランドは研究開発税制優遇(間接的支援)のデータが提供されなかった。
参照:科学技術指標2017図表1-3-9
(5)日本や米国では政府からの直接的支援が、大規模企業に集中している。ドイツや韓国では小規模、中規模企業への支援も一定の重みを持つ。
政府からの研究開発における直接的支援(企業の研究開発費のうち政府が負担した金額)を従業員規模別で見ると、日本や米国は従業員数500人以上の企業の割合が大きく、全体の約9割を占める。他方、ドイツでは249人以下の企業で政府負担割合の約半数を占めており、韓国では半数を超えている。
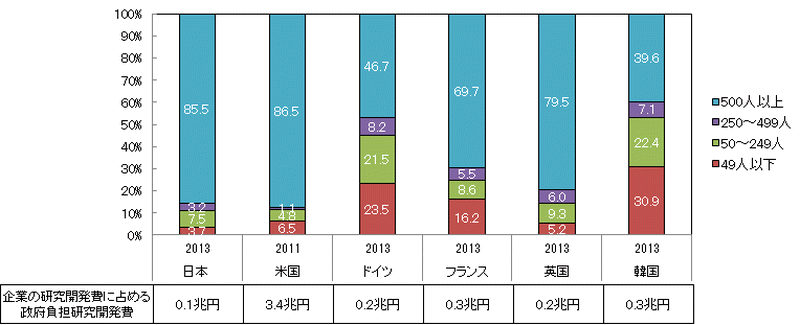
参照:科学技術指標2017図表1-3-10
2.研究開発人材から見る日本の状況
(1) 日本の研究者数は2016年において66.2万人であり、中国、米国に次ぐ第3位の規模を持っている。
研究開発資金と並んで重要なインプットが、研究者数である。日本の研究者数は2016年において66.2万人(実数(HC:Head Count)値は90.7万人)であり、中国、米国に次ぐ第3位の研究者数の規模を持っている。韓国の研究者数は2010年以降ではフランス、英国を上回り、最新年ではドイツと同程度となっている。部門別では、ほとんどの国で研究開発費と同様に企業の研究者数が最も多いが、英国については大学部門の研究者数が最も多い。


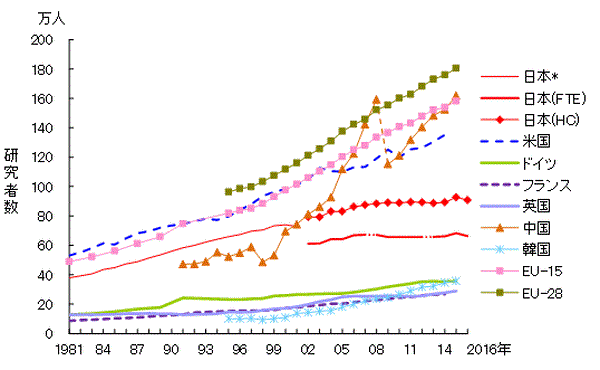
注:
中国の2008年までの研究者の定義は、OECDの定義には完全には対応しておらず、2009年から計測方法を変更したため、2008年以前と2009年以降では差異がある。
参照:科学技術指標2017図表2-1-3
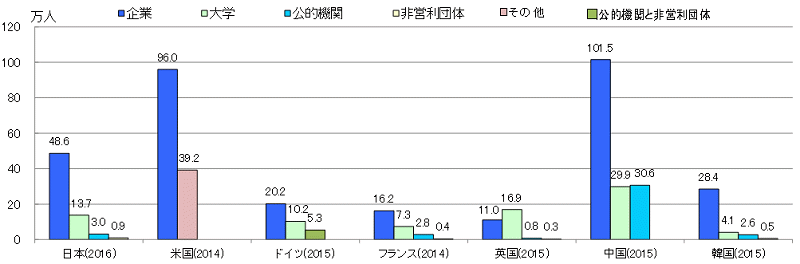
注:
1)全ての国はFTE値である。
2)米国はOECDによる見積もり数値であり、近年、企業部門以外の数値がないため、企業とそれ以外について数値を示した。
参照:科学技術指標2017図表2-1-7
(2)日本の製造業では工学系の専門的知識を持つ研究者が多くを占める。
産業分類別に、その業種に所属する研究者の専門分野を見ると、製造業で多くを占める「情報通信機械器具製造業」においては「電気・通信」分野を専門とする研究者が多く、「輸送用機械器具製造業」では「機械・船舶・航空」分野を専門とする研究者が多い。非製造業に注目すると、「情報通信業」では「情報科学」を専門とする研究者が多くを占めている。なお、他の産業分類では「情報科学」を専門とする研究者は少ない。また、「人文・社会科学」を専門とする研究者は絶対数が少ない。
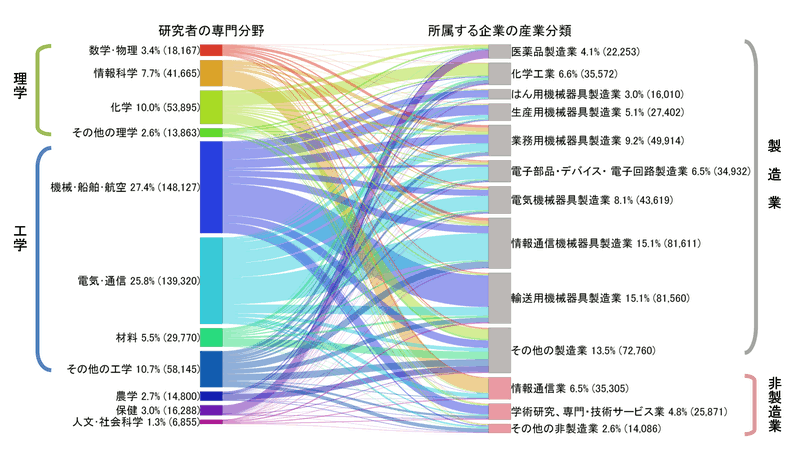
注:
HC値である。( )内は研究者数である。
参照:科学技術指標2017図表2-2-8
(3)研究支援者を業務別で国際比較すると、日本は「テクニシャン」より「その他の支援スタッフ」の方が多いが、他国では「テクニシャン」の方が多い傾向にある。
研究者一人当たり研究支援者数を部門別、業務別に見ると、日本は「テクニシャン」より「その他の支援スタッフ」の方が多いが、他国では「テクニシャン」の方が多い傾向にある。

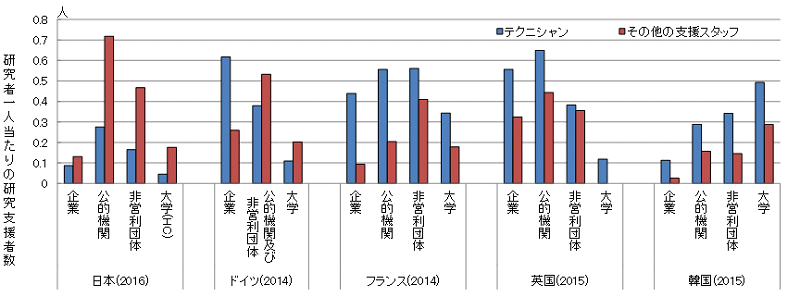
注:
1)テクニシャン(技能者及びこれと同等のスタッフ)とは、その主たる任務が、工学、物理・生命科学、社会科学、人文科学のうち一つあるいは複数の分野における技術的な知識及び経験を必要とする人々である。通常、研究者の指導の下に、概念の応用や実際的方法及び研究機器の利用に関わる科学技術的な任務を遂行することによって研究開発に参加する者が相当する。
2)その他の支援スタッフとは、R&Dプロジェクトに参加、あるいはそうしたプロジェクトと直接に関係している熟練及び未熟練の職人、管理、秘書・事務スタッフが相当する。
3)英国の大学における「その他の支援スタッフ」の数値は出典とした資料(OECD,“R&D Statistics”)に示されていなかった。
参照:科学技術指標2017図表2-3-2
3.大学生から見る日本の状況
(1)「理工」系修士課程修了者の「就職者」の割合は約9割であり、ほとんどが「無期雇用」の職員として就職している。「理工」系博士課程修了者の「就職者」の割合は約7割であるが、「無期雇用」の職員として就職しているのは約5割である。
2016年の「理工」系修士課程修了者(37,128人)の進路を見ると、「就職者」の割合は87.6%である。「就職者」の「無期雇用」の割合は全体の86.8%、「有期雇用」は0.8%である。2016年の「理工」系博士課程修了者(4,809人)の進路を見ると、「就職者」の割合は68.6%である。「就職者」の「無期雇用」は全体の51.4%、「有期雇用」は17.2%である。
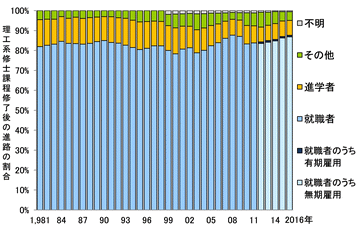
参照:科学技術指標2017図表3-3-2
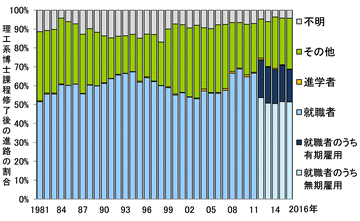
参照:科学技術指標2017図表3-3-3
(2)「人文・社会科学」系修士課程修了者の「就職者」の割合は増加し、全体の約6割が就職している。「人文・社会科学」系博士課程修了者では、全体の約5割が就職しているが、「無期雇用」の職員として就職しているのは約3割である。
「人文・社会科学」系修士課程修了者の進路を見ると、1980年代では、「就職者」、「進学者」ともに約30%であった。その後、「就職者」の割合は増加し、2016年では「人文・社会科学」系修士課程修了者(11,458人)の56.3%となった。2016年の「人文・社会科学」系博士課程修了者(2,135人)の進路を見ると、「就職者」の割合は45.1%である。ただし、「無期雇用」が全体の29.8%、「有期雇用」が15.3%である。
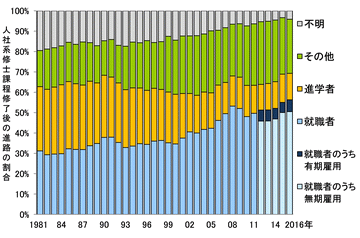
参照:科学技術指標2017図表3-3-10
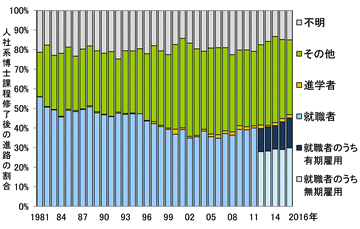
参照:科学技術指標2017図表3-3-11
注:
無期雇用とは、雇用の期間の定めのないものとして就職した者である。
有期雇用とは、雇用の期間が1年以上で期間の定めのある者であり、かつ1週間の所定の労働時間が概ね30~40時間程度の者をいう。
その他とは、一時的な職業やアルバイト等に就いた者をいう。
(3)日本においては、修士、博士号取得者になるにつれ、「自然科学」系が多くなる傾向にある。日本以外の主要国では修士号取得者でも「人文・社会科学」系が最も多く、博士号取得者において「自然科学」系が最も多くなる傾向にある。
人口100万人当たりの学士・修士・博士号取得者についての分野バランスを見ると、学士号取得者においては「人文・社会科学」系が多くを占めている国が多い。日本においては、修士、博士号取得者になるにつれ、「自然科学」系が多くなる傾向にあるが、他国では修士号取得者でも「人文・社会科学」系が最も多く、博士号取得者において「自然科学」系が最も多くなる傾向にある。
人口100万人当たりの学士・修士・博士号取得者について、日本以外の国は全ての学位で増加している。
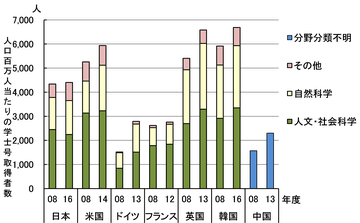
参照:科学技術指標2017図表3-4-1
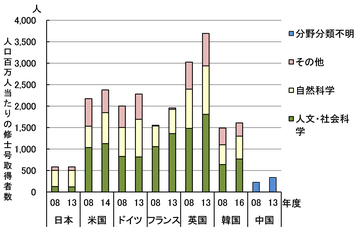
参照:科学技術指標2017図表3-4-2
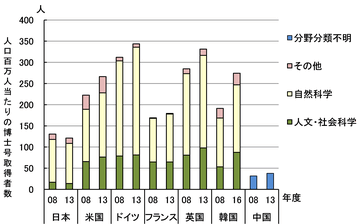
参照:科学技術指標2017図表3-4-3
注:
1)米国の博士号取得者は、“Digest of Education Statistics”に掲載されている“Doctor's degrees”の数値から医学士や法学士といった第一職業専門学位の数値のうち、「法経」、「医・歯・薬・保健」、「その他」分野の数値を除いたものである。
2)中国については、分野別の数値は不明。
3)各分野分類については以下が含まれる。
人文・社会科学:人文・芸術、法経等
自然科学:理学、工学、農学、医・歯・薬・保健
その他:教育・教員養成、家政、その他
4.研究開発のアウトプットから見る日本と主要国の状況
(1)10年前と比較して日本の論文数(分数カウント)は微減であり、他国の拡大により順位を下げている。順位の低下は、注目度の高い論文(Top10%補正論文数、Top1%補正論文数)において顕著である。
研究開発のアウトプットの一つである論文に着目すると、論文の生産への貢献度を見る分数カウント法では、日本の論文数(2013-2015年(PY)の平均)は、米、中、独に次ぐ第4位に低下した。また、Top10%補正論文数では、米、中、英、独、仏、伊、加、豪に次ぐ第9位であり、Top1%補正論文数では米、中、英、独、仏、豪、加、伊に次ぐ第9位である。
10年前と比較して、日本の論文数は微減であり、他国の論文数の拡大により順位を下げていることが分かる。順位の低下は、特にTop10%補正論文やTop1%補正論文といった注目度の高い論文において顕著である。
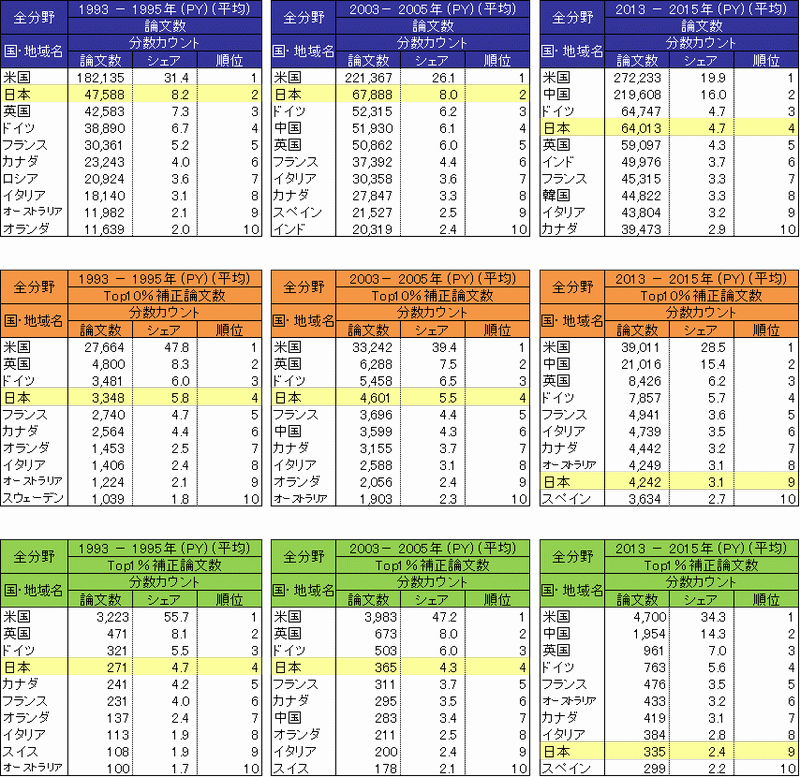
注:
分析対象は、article, reviewである。年の集計は出版年(Publication year, PY)を用いた。被引用数は、2015年末の値を用いている。
参照:科学技術指標2017図表4-1-6
(2)日本の分野別論文数割合を見ると、1980年代前半では、「基礎生命科学」、「化学」、「物理学」の割合が大きかったが、「化学」、「基礎生命科学」の減少、「臨床医学」の増加が見られた。
日本は、1980年代前半は、「基礎生命科学」、「化学」、「物理学」の占める割合が大きかったが、1981年と2015年を比較すると、「化学」は9.3ポイント、「基礎生命科学」は3.5ポイント減っている。他方、「臨床医学」の割合は13.7ポイント増加した。生命科学系(「臨床医学」と「基礎生命科学」)とそれ以外で見ると、生命科学系の割合が10ポイント近く増加した。
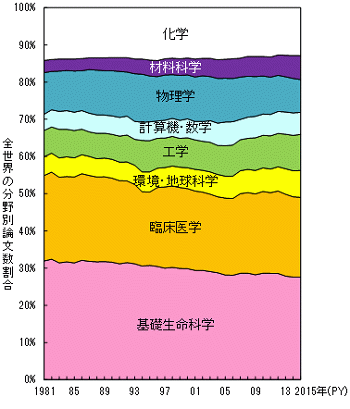
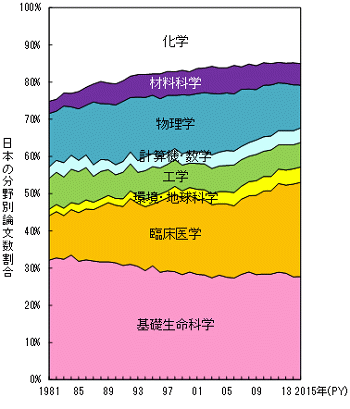
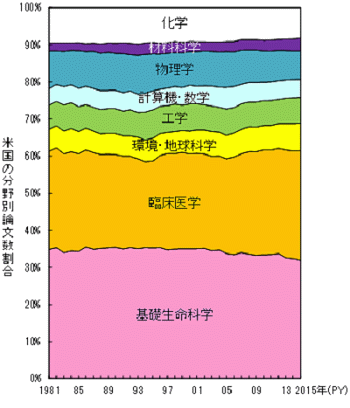
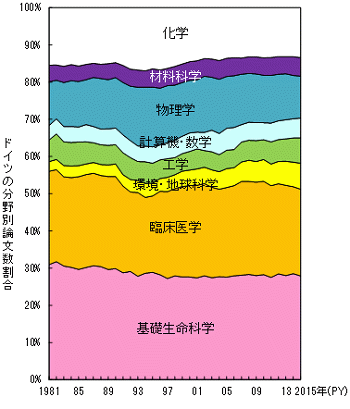
注:
分析対象は、article, reviewである。年の集計は出版年(Publication year, PY)を用いた。
参照:科学技術指標2017図表4-1-8、4-1-9
(3)日本は10年前から引き続きパテントファミリー2ヶ国以上への特許出願)数において、世界第1位を保っている。
次に特許出願に着目し、各国・地域から生み出される発明の数を国際比較可能な形で計測したパテントファミリー数を見ると、1990-1992年は米国が第1位、日本が第2位であったが、2000-2002年時点、2010-2012年時点では日本が第1位、米国が第2位となっている。日本のパテントファミリー数の増加は、日本からの複数国への特許出願が増加したことを反映した結果である。中国はパテントファミリー数で見れば、2010-2012年時点で5位であるが、着実にその数を増やしている。
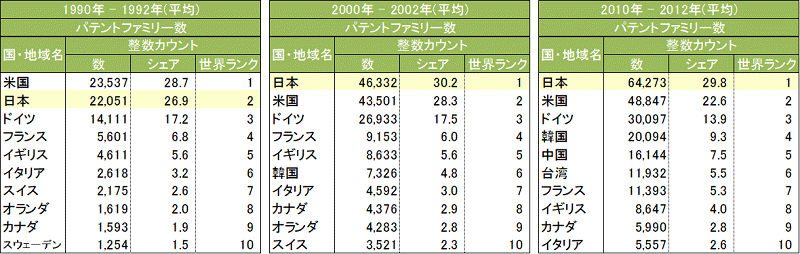
注:
パテントファミリーとは優先権によって直接、間接的に結び付けられた2カ国以上への特許出願の束である。通常、同じ内容で複数の国に出願された特許は、同一のパテントファミリーに属する。
参照:科学技術指標2017図表4-2-5
(4)2012年時点の日本の技術分野バランスを見ると、世界全体と比べて「電気工学」と「一般機器」の比率が高い。他方、「バイオテクノロジー・医薬品」と「バイオ・医療機器」の割合は、世界全体と比べて低い。
2012年時点の日本の技術分野バランスを見ると、世界全体と比べて「電気工学」と「一般機器」の割合が高い(世界はそれぞれ18.8%、10.9%、日本はそれぞれ25.3%、14.3%)。他方、「バイオテクノロジー・医薬品」と「バイオ・医療機器」の割合は、世界全体と比べて低い(世界はそれぞれ5.1%、5.0%、日本はそれぞれ3.4%、3.3%)。
日本の技術分野の割合の変化を見ると、「情報通信技術」の割合は1981年から長期的に増加し、2008年では、20.4%を占めるに至ったが、近年はその割合を減少させている。「電気工学」は1981年と2012年を比べると7.5ポイント上昇している。近年、「輸送用機器」の割合が増加している。
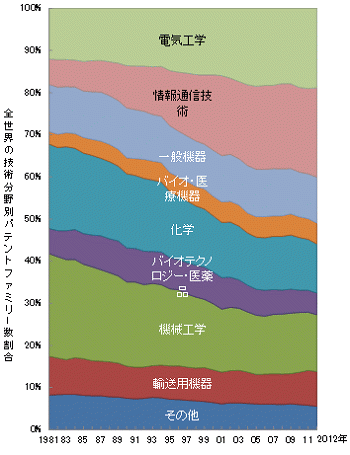
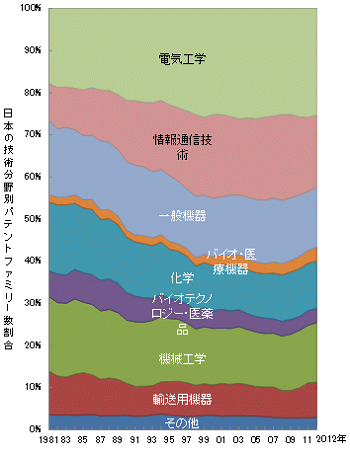
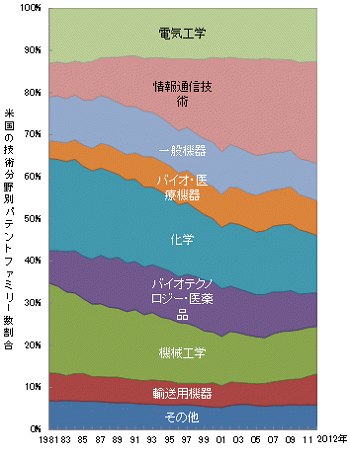
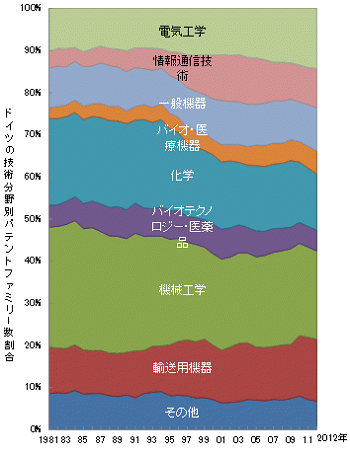
注:
パテントファミリーとは優先権によって直接、間接的に結び付けられた2カ国以上への特許出願の束である。通常、同じ内容で複数の国に出願された特許は、同一のパテントファミリーに属する。
参照:科学技術指標2017図表4-2-8
科学技術指標2017図表4-2-9
(5)科学と技術のつながり(サイエンスリンケージ)を見ると、日本の論文は世界のパテントファミリーから多く引用されている(世界第2位)。論文を引用している日本のパテントファミリー数も世界第2位であるが、日本のパテントファミリー数に占める割合は小さい。
科学と技術のつながり(サイエンスリンケージ)を見るために、パテントファミリーに引用されている論文の情報を用いて分析を行った。まず、論文を引用しているパテントファミリー数を国・地域別に見ると、日本は世界第2位である。しかし、日本のパテントファミリーの中で論文を引用しているものの割合は9.5%であり、日本の技術は他国と比べて科学的成果を引用している割合が低い。他方、パテントファミリーに引用されている論文数では米国に次いで多く、日本の論文は技術に多く引用されていることが分かる。
リー数:上位10カ国・地域
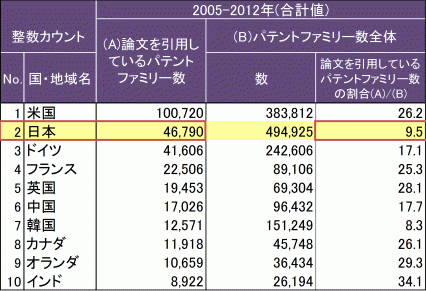
参照:科学技術指標2017図表4-3-2
る論文数:上位10カ国・地域
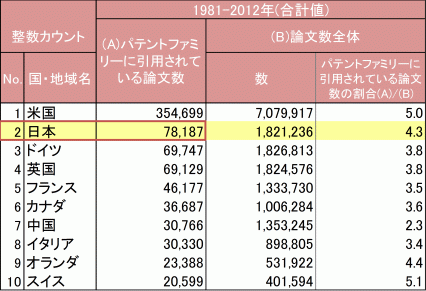
参照:科学技術指標2017図表4-3-3
(6)日本の技術分野構成において、世界と比較して比率が高い「電気工学」と「一般機器」では、 論文を引用しているパテントファミリー数割合は、欧米に比べて低い傾向にある。
技術分野別に、論文を引用しているパテントファミリー数割合を見ると、主要国のいずれでも「バイオテクノロジー・医薬品」で高く、「機械工学」や「輸送用機器」で低い。各国の「バイオテクノロジー・医薬品」を基準に、他の技術分野を見ると、「情報通信技術」、「一般機器」、「電気工学」において、米国、ドイツ、フランス、英国は、日本よりも論文を引用しているパテントファミリー数割合が高い。
日本の技術分野構成において、世界と比較して比率が高い「電気工学」と「一般機器」では(概要図表17参照)、論文を引用しているパテントファミリー数割合は、欧米に比べて低い傾向にある。
(各国における「バイオテクノロジー・医薬品」分野を1とした)
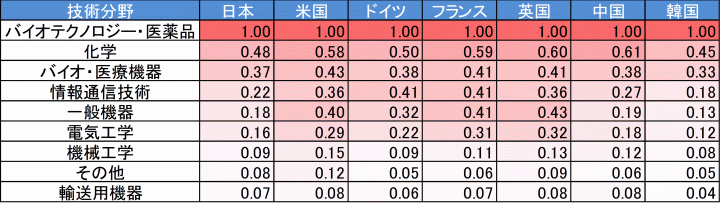
参照:科学技術指標2017図表4-3-5
(7)日本の「臨床医学」や「基礎生命科学」の論文は、日本のパテントファミリーに引用されている割合が「物理学」や「材料科学」と比べて低く、他国のパテントファミリーに引用されている。
世界において論文分野と技術分野のつながりを見ると、パテントファミリーに多く引用されている論文分野は、「基礎生命科学」、「臨床医学」、「化学」である。
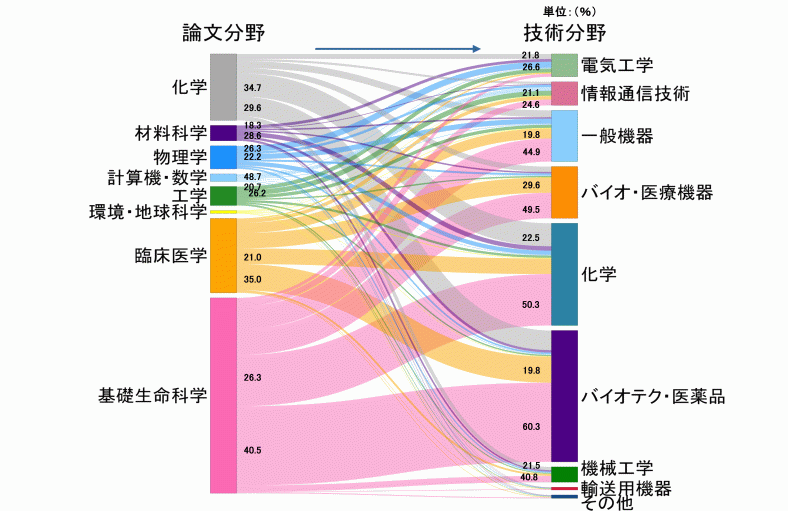
参照:科学技術指標2017図表4-3-6
日本の論文が、どの国のパテントファミリーに引用されているのかを各論文分野について見ると、自国のパテントファミリーに多く引用されている分野は、「物理学(46.9%)」と「材料科学(42.2%)」である。他方、「臨床医学(17.3%)」や「基礎生命科学(17.3%)」は、自国のパテントファミリーに引用されている割合は相対的に低く、日本以外の国に引用されている。
日本は「臨床医学」の論文数が増加傾向にあるが(概要図表15参照)、それを最も引用するパテントファミリーの技術分野である「バイオテクノロジー・医薬品」の割合は低い(概要図表17参照)ことから、現状では、日本の科学知識は日本の技術に十分に活用されていない可能性がある。
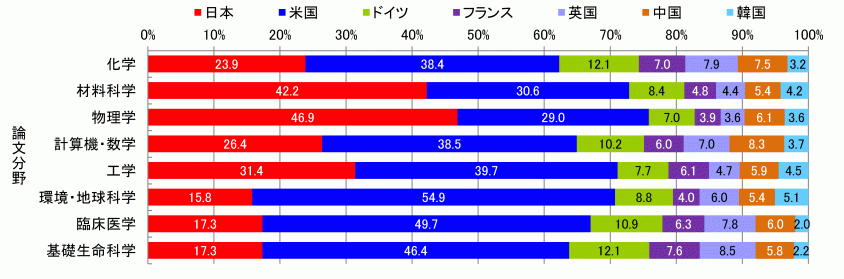
参照:科学技術指標2017図表4-3-7
5.科学技術とイノベーションから見る日本と主要国の状況
(1)日本のハイテクノロジー産業貿易収支比は、主要国の中でも低い数値である。他方、ミディアムハイテクノロジー産業においては、日本は主要国で第1位を維持している。
ハイテクノロジー産業貿易収支比を見ると、日本は継続して貿易収支比を減少させている。2011年以降1を下回り、入超となった。2015年の日本の収支比は0.75であり、もともと低かった英国、米国と同程度となっている。他方、中国、韓国は長期的に見れば、収支比を上昇させており、韓国は主要国中、最も収支比が高い(1.66)。
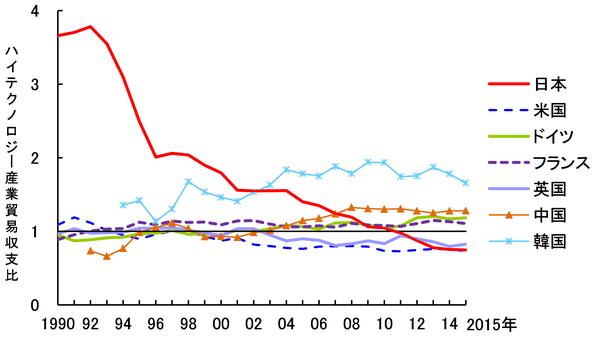
注:
1)ハイテクノロジー産業とは「医薬品」、「電子機器」、「航空・宇宙」を指す。
2)貿易収支比=輸出額/輸入額
参照:科学技術指標2017図表5-2-3
2015年の日本のミディアムハイテクノロジー産業貿易収支比は2.64であり、主要国中第1位である。推移を見ると、1990年代中頃に、急激な減少を見せた後は漸減傾向にある。米国、ドイツ、フランス、英国が横ばいに推移している中で、貿易収支比を増加させているのは韓国(1.84)と中国(1.43)である。
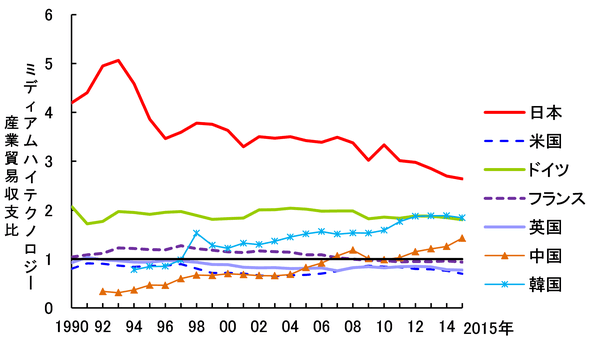
注:
1)ミディアムハイテクノロジー産業とは、「化学品と化学製品」、「電気機器」、「機械器具」、「自動車」、「その他輸送」、「その他」を指す。
2)貿易収支比=輸出額/輸入額
参照:科学技術指標2017図表5-2-5
(2)日本は開業率、廃業率共に、他の主要国と比較して低く、起業無関心者の割合が高い。ただし、起業後の起業生存率は高い。
日本は開業率の方が廃業率より高いが、他国と比較すると開廃業率共に低い水準であり、時系列でもほとんど変化していない。他国については英国、フランスは開業率の方が廃業率より高く、米国、ドイツは廃業率の方が開業率より高い傾向がある。

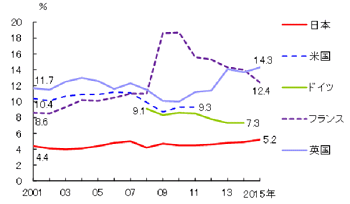
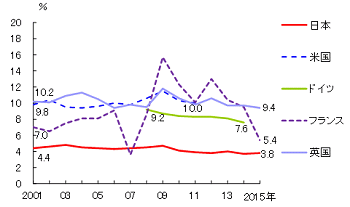
注:
開廃業率の算出方法は、国によって異なるため、国際比較には注意が必要である。
<日本>開廃業率は、保険関係が成立している事業所(適用事業所)の成立・消滅をもとに算出している。具体的には開業率は、当該年度に雇用関係が新規に成立した事業所数/前年度末の適用事業所数であり、廃業率は、当該年度に雇用関係が消滅した事業所数/前年度末の適用事業所数である。なお、適用事業所とは、雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業所数である。
<米国>開廃業率は、雇用主(employer)の発生・消滅をもとに算出している。
<英国>開廃業率は、VAT(付加価値税)及びPAYE(源泉所得税)登録企業数をもとに算出している。
<ドイツ>開廃業率は、開業・廃業届を提出した企業数をもとに算出している。
<フランス>開業率は、企業・事業所目録(SIRENRE)へのデータベースに登録・抹消された起業数をもとに算出している。
参照:科学技術指標2017図表5-4-9(中小企業庁よりデータの提供を受けた)
起業無関心者の割合の推移を見ると、最新年の日本は主要国中最も割合が高く77.3%である。他の主要国と比較すると約40ポイントも差がある。
日本の企業生存率は他の主要国と比較して高く、5年後であっても81.7%の企業が事業を継続させている。他方、他の主要国は5年後には全ての国で50%以下となっている。
割合の推移
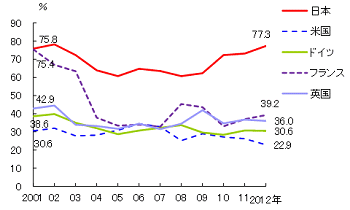
注:
1)グローバル・アントレプレナーシップ・モニター(Global Entrepreneurship Monitor:GEM)調査の結果を表示している。
2)「起業無関心者の割合」とは、「起業活動浸透指数」、「事業機会認識指数」、「知識・能力・経験指数」の三つの指数について、一つも該当しない者の割合を集計している。
参照:科学技術指標2017図表5-4-10(中小企業庁よりデータの提供を受けた)
存率の推移
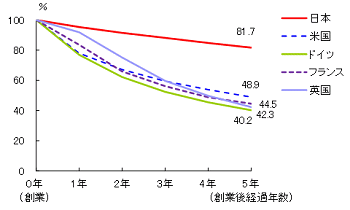
注:
1)日本の企業生存率は(株)帝国データバンク「COSMOS2(企業概要ファイル)」のデータベースに企業情報が収録されている企業のみで集計している。また、データベース収録までに一定の時間を要するため、実際の生存率よりも高めに算出されている可能性がある。
2)米国、英国、ドイツ、フランスの企業生存率は、2007年から2013年に起業した企業について平均値をとったものである。
参照:科学技術指標2017図表5-4-11(中小企業庁よりデータの提供を受けた)
科学技術指標の特徴
科学技術指標は、毎年刊行しており、その時点での最新値を紹介している。原則として毎年データ更新され、時系列の比較あるいは主要国間の比較が可能な項目を収集している。
各国が発表している統計データを使用
- 科学技術指標で使われている指標のデータソースは、出来る限り各国が発表している統計データを使用している。また、各国の統計の取り方がどのようになっていて、どのような相違があるかについて、極力明らかにしている。
- 論文・特許データベースについて当研究所独自の分析の実施
論文データについては、クラリベイト・アナリティクス社Web of Science XMLの書誌データを用いて、当研究所で独自の集計をし、分析している。また、集計方法も詳細に記載し、説明している。
特許関連の指標のうち、パテントファミリーのデータについては、PATSTAT(欧州特許庁の特許データベース)の書誌データを用いて、当研究所で独自の集計をし、分析している。また、集計方法も詳細に記載し、説明している。 - 国際比較や時系列比較の注意喚起マークの添付
必要に応じ、グラフに「国際比較注意」
 「時系列注意」
「時系列注意」 という注意喚起マークを添付してある。各国のデータは基本的にはOECDのマニュアル等に準拠したものであるが、実際にはデータの収集方法、対象範囲等の違いがあり、比較に注意しなければならない場合がある。このような場合、「国際比較注意」マークがついている。また、時系列についても、統計の基準が変わるなどにより、同じ条件で継続してデータが採られておらず、増減傾向などの判断に注意する必要があると考えられる場合には「時系列注意」というマークがついている。なお、具体的な注意点は図表の注記に記述してあるので参照されたい。
という注意喚起マークを添付してある。各国のデータは基本的にはOECDのマニュアル等に準拠したものであるが、実際にはデータの収集方法、対象範囲等の違いがあり、比較に注意しなければならない場合がある。このような場合、「国際比較注意」マークがついている。また、時系列についても、統計の基準が変わるなどにより、同じ条件で継続してデータが採られておらず、増減傾向などの判断に注意する必要があると考えられる場合には「時系列注意」というマークがついている。なお、具体的な注意点は図表の注記に記述してあるので参照されたい。
- 統計集(本報告書に掲載したグラフの数値データ)のダウンロード
本報告書に掲載したグラフの数値データは、以下のURLからダウンロードできる。
https://www.nistep.go.jp/research/science-and-technology-indicators-and-scientometrics/indicators


