この節では、企業の開業率、廃業率を見ることにより、企業の新陳代謝が活発に行われているかどうかを見る。
図表5-4-11に主要国の開業率、廃業率を示した。日本の場合、「雇用保険事業年報」をもとにしており、事業所における雇用関係の成立、消滅をそれぞれ開廃業とみなしている。他国については、各国で計測方法が異なる点には留意が必要である。
各国最新年の開業率を見ると(図表5-4-11(A))、日本の開業率は5.6%であり他国と比較して最も低い数値である。最も高いのはフランス、英国であり、それぞれ13.2%、13.1%となっている。2001年と比較すると、日本は漸増しているが、他国より低い水準で推移している。英国は2010年頃から増加傾向が続いているのに対して、フランスは同年から減少し、両国の値は同程度となった。また、ドイツは2000年代後半から減少傾向にある。
各国最新年の廃業率を見ると(図表5-4-11(B))、日本は3.5%であり、開業率と同様に他国と比較して最も低い数値である。最も高いのは英国であり12.2%、次いでフランスが10.3%となっている。
2001年と比較すると、日本やドイツは微減に推移している。英国は2013年を境に大きく増加している。
なお、フランスについては、開業率、廃業率ともに変化の度合いが大きいが、これは制度の変更等の影響だと考えられる。例えば、2007~2009年の変化は、2009年1月から施行された「個人事業主制度」により、簡易な申請のみで起業が可能になったことや、創業間もない企業への税制優遇措置の影響だと考えられる。

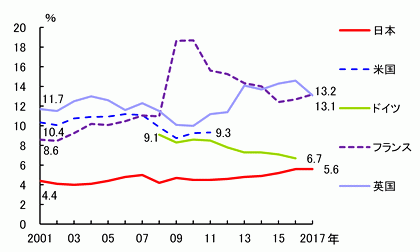
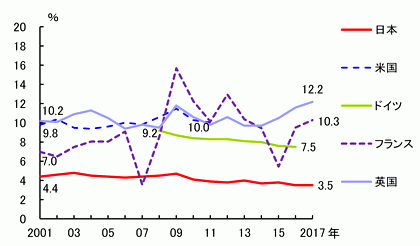
注:
起業の開廃業率の算出方法は、国によって異なるため、国際比較するには注意が必要である。
<日本>開廃業率は、保険関係が成立している事業所(適用事業所)の成立・消滅をもとに算出している。具体的には開業率は、当該年度に雇用関係が新規に成立した事業所数/前年度末の適用事業所数であり、廃業率は、当該年度に雇用関係が消滅した事業所数/前年度末の適用事業所数である。なお、適用事業所とは、雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業所数である。
<米国>開廃業率は、雇用主(employer)の発生・消滅をもとに算出している。
<英国>開廃業率は、VAT(付加価値税)及びPAYE(源泉所得税)登録企業数をもとに算出している。
<ドイツ>開廃業率は、開業・廃業届を提出した企業数をもとに算出している。
<フランス>開業率は、企業・事業所目録(SIRENRE)へのデータベースに登録・抹消された起業数をもとに算出している。
資料:
中小企業庁、「中小企業白書」
参照:表5-4-11
(2)起業意識の国際比較
ここでは、世界の国・地域が参加するグローバル・アントレプレナーシップ・モニター(Global Entrepreneurship Monitor:GEM)調査(6)の結果から、主要国の起業意識の違いを見る。
ここでいう「起業無関心者の割合」とは、GEM調査における、「過去2年間に、新しく事業を始めた人を知っている」、「今後6か月以内に、自分が住む地域に起業に有利なチャンスが訪れる」、「新しいビジネスを始めるために必要な知識、能力、経験を持っている」の3つの質問すべてに「いいえ」と回答した者の割合を集計している。
起業無関心者の割合の推移を見ると(図表5-4-12)、2017年の日本は主要国中最も割合が高く75.8%である。次に大きいフランスと比較すると32.3ポイントの差がある。最も小さいのは米国であり、21.6%である。
2013年から2017年を比較すると、日本、中国は微増(起業無関心者の割合が増加)しており、米国、ドイツ、フランス、英国は微減している。特に米国は、7.4ポイントと最も減少(起業無関心者の割合が減少)している。
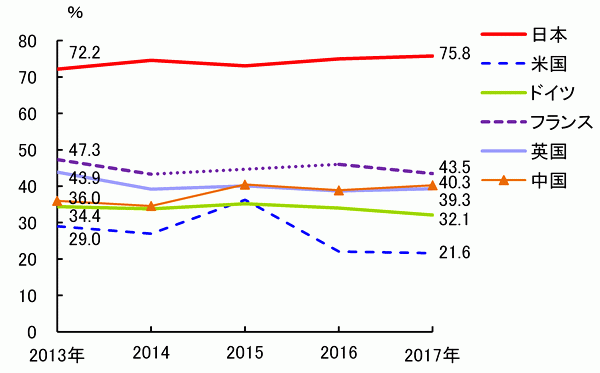
注:
1)グローバル・アントレプレナーシップ・モニター(Global Entrepreneurship Monitor:GEM)調査の結果を表示している。
2)ここでいう「起業無関心者」とは、「過去2年間に、新しく事業を始めた人を知っている」、「今後6か月以内に、自分が住む地域に起業に有利なチャンスが訪れる」、「新しいビジネスを始めるために必要な知識、能力、経験を持っている」の3つの質問すべてに「いいえ」と回答した人をいう。
3)3つの質問について、「わからない」と回答した人、無回答の人を除いて集計している。
4)フランスは2015年の値がない。
資料:
中小企業庁、「中小企業白書2019」
参照:表5-4-12
(3)ユニコーン企業数
この節では、米国CB Insightsの調査においてユニコーン企業とされた企業価値が10億ドル以上の未上場企業のデータ(2019年1月18日現在)を使用し、世界におけるユニコーン企業の状況を見る。
図表5-4-13を見ると、2010年から2018年にかけてユニコーン企業数は大きく増加し、2018年では119社となった。CB Insightsによる分類で見ると、2014年に、「インターネットソフトウェアとサービス」、「電子商取引」分類のユニコーン企業数が増加、その後は、「フィンテック」、「健康管理」も増加した。2018年になると、「インターネットソフトウェアとサービス」が大きく増加しており、また、「オンデマンド」分類のユニコーン企業数も増加している。
次に分類別・国別にユニコーン企業数の状況を見ると(図表5-4-14)、最もユニコーン企業数が多いのは米国であり、151社となっている。次いで中国が79社であり、3位の英国(16社)と大きく離れている。日本は1社(7)であり、他国と比較すると少ない数値である。分類別で見ると、米国では「インターネットソフトウェアとサービス」が最も多い。中国では「インターネットソフトウェアとサービス」と「電子商取引」が同程度に多い。
英国では「フィンテック」が最も多く、インドでは「電子商取引」が最も多い。各国におけるユニコーン企業の分類は多様であるが、大多数は情報通信サービスに関連したものとなっている。
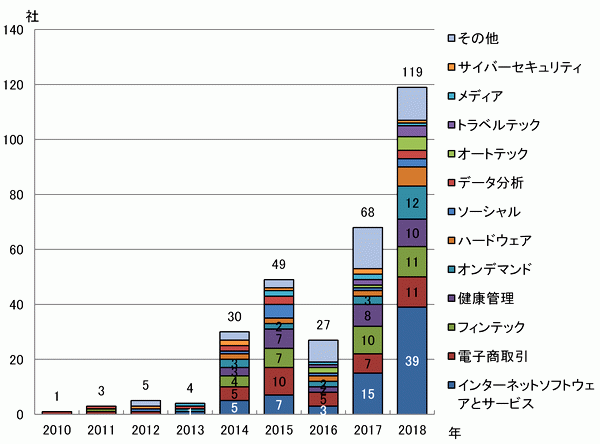
注:
1)CB Insightsの調査においてユニコーン企業とされた企業価値が10億ドル以上の未上場企業(2019年1月18日現在)のデータを基に科学技術・学術政策研究所が作成。
2)分類についてはCB Insightsが提示した項目を科学技術・学術政策研究所が仮訳した。
3)CB Insightsに企業価値が10億ドル以上と判断された年である。
資料:
CB Insightsのwebサイトより2019/04/23入手
https://www.cbinsights.com/reports/CB-Insights-Global-Unicorn-Club_2019.xlsx
参照:表5-4-13
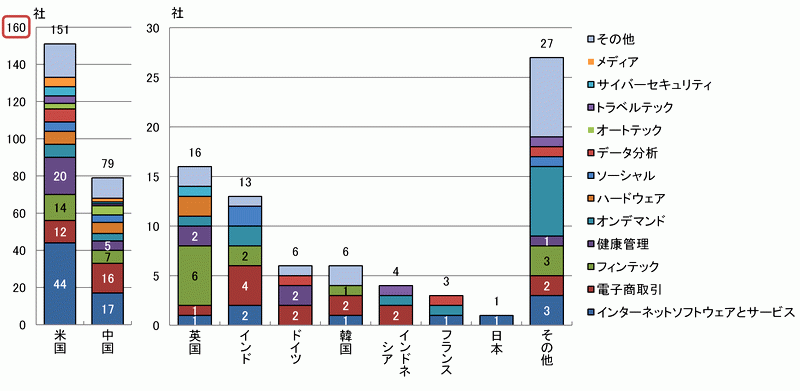
注:
1)CB Insightsの調査においてユニコーン企業とされた企業価値が10億ドル以上の未上場企業(2019年1月18日現在)のデータを基に科学技術・学術政策研究所が作成。
2)分類についてはCB Insightsが提示した項目を科学技術・学術政策研究所が仮訳した。
3)CB Insightsに企業価値が10億ドル以上と判断された年である。
資料:
CB Insights, “Global Unicorn Club: Private Companies Valued at $1B+(as of January 18, 2019)”(webサイトより2019/04/23入手)
https://www.cbinsights.com/reports/CB-Insights-Global-Unicorn-Club_2019.xlsx
参照:表5-4-14
(6)GEM調査の主要目的は、ベンチャー企業の成長プロセスを解明し、起業活動を活発にする要因を理解し、その上で国家の経済成長や競争力、雇用などへの影響を定量的に測定することにある。最終的には、国家経済の活性化につなげるための政策提言を目的としている。1999年に我が国を含め10か国からスタートし、2017年には54の国や地域が参加している。サンプル数は一つの国当たり最低2,000サンプル(サンプリングは無作為抽出)であり、全世界共通の調査票が使われている。なお、一度調査に参加した国でも毎年継続して参加するとは限らない。
(7)2019年7月1日時点のCB Insightsのweb上に掲載されている表では日本の企業数は2社であり、世界全体は362社である。


