1.3部門別の研究開発費
1.3.1公的機関部門の研究開発費
ポイント
- 日本の公的機関部門の研究開発費は、2010年度で1.42兆円であり、2000年代に入ってからは横ばい傾向にある。
- 各国通貨で研究開発費(名目額)の年平均成長率を見ると、2000年代後半(2005~各国最新年)では、日本とイギリスは1%以下の成長率にあるのに対して、他国は伸びており、特に中国は19.4%とかなり高い成長率である。
(1)各国公的機関の研究開発費
本節では研究開発実施部門としての公的機関部門について述べる。
ここで計測している各国の公的機関には以下のような研究機関が含まれる。日本は「国営」(国立試験研究機関等)、「公営」(公設試験研究機関等)、「特殊法人・独立行政法人」(営利を伴わない)といった公的研究機関である。
米国は連邦政府の研究機関(NIH等)と、FFRDCs(政府が出資し、産業・大学・非営利団体部門が研究開発を実施している)の研究機関である。
ドイツでは連邦政府と地方政府、その他の公的研究施設、非営利団体(16万ユーロ以上の公的資金を得ている)及び高等教育機関ではない研究機関(法的に独立した大学付属の研究所)である。ドイツについては、公的機関部門と「非営利団体」部門が分離されていないことに注意が必要である。
フランスは、科学技術的性格公施設法人(EPST)(ただし、CNRSを除く)や商工業的性格公施設法人(EPIC)等といった設立形態の研究機関である。イギリスは中央政府、分権化された政府の研究機関及びリサーチカウンシルである。中国は中央政府の研究機関、韓国は国・公立研究機関、政府出捐研究機関及び国・公立病院である(図表1-1-4参照)。
図表1-3-1(A)に主要国における公的機関部門の研究開発費(OECD購買力平価換算値)の推移を示した。日本の公的機関部門の研究開発費は、2010年度で1.42兆円であり、2000年代に入ってからは横ばい傾向にある。各国とも1990年代に入ってからの研究開発費は横ばい傾向にあったが、中国の研究開発費は1990年代中ごろから急速に増加しはじめ、2002年には日本を抜いている。また、米国も2000年代に入ると増加傾向にある。
次に、図表1-3-1(B)、各国通貨で研究開発費(名目額)の年平均成長率を見る。2000年代前半(2000~2005年)では、日本のみがマイナスの成長率であり、他の国はすべて伸びている。ただし、イギリスは1%以下の伸びである。2000年代後半(2005~各国最新年)では、日本とイギリスは1%以下の成長率にあるのに対して、他国は伸びており、特に中国は19.4%とかなり高い成長率である。
さらに物価の変動の影響を除いた実質額を各国通貨で見てみると(図表1-3-1(C))、2000年代前半では日本、イギリスがマイナス成長であり、他国は全て伸びている。2000年代前半と比較して、2000年代後半の伸びが大きい国は日本、ドイツ、イギリス、中国、韓国であるが、イギリスについては、マイナス成長が減少したに過ぎない。

(A)名目額(OECD購買力平価換算)
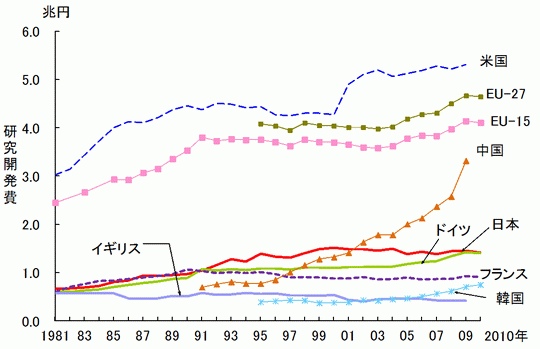
(B)名目額(各国通貨)
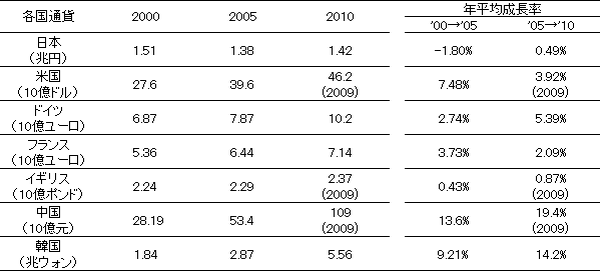
(C)実質額(2005年基準各国通貨)
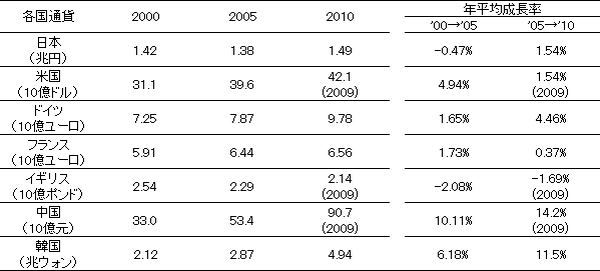
注:
1)公的機関部門の定義には国によって違いがあるため国際比較の際には注意が必要である。各国の部門の定義については図表1-1-4参照のこと。
2)研究開発費は人文・社会科学を含む(韓国は2006年度まで自然科学のみ)。
3)日本(OECD推計)、フランス、韓国、EUの非営利研究機関は合計から産業、大学、公的機関を除いたもの。
4)購買力平価は、参考統計Eと同じ。
<日本、日本(OECD推計)>2001年度に、非営利団体の一部は企業部門になった。
<日本(OECD推計)>大学部門の研究開発費のうち人件費をFTEにした総研究開発費。OECDが補正し、推計した値。
<ドイツ>1990年までは旧西ドイツ、1991年以降は統一ドイツ。
資料:
<日本>総務省、「科学技術研究調査報告」、OECD,"Main Science and Technology Indicators 2011/2"
<米国>NSF, "Science and Engineering Indicators 2012"
<ドイツ>Bundesministerium für Bildung und Forschung,"Bundesbericht Forschung 2004,2006"、"Bundesbericht Forschung und Innovation 2010"、2008年からはOECD,"Main Science and Technology Indicators 2011/2"
<イギリス>National Statistics website: www.statistics.gov.uk
<フランス、韓国、EU>OECD,"Main Science and Technology Indicators 2011/2"
参照:表1-3-1
(2)日本の公的機関の研究開発費
図表1-3-2(A)に日本の公的機関部門における研究開発費使用額の推移を機関の種類別に示す。いずれの研究機関とも2000年度までは、多少の増減はあるものの、増加を続けていた。これらのなかでは、特殊法人(図では2000年度までの「特殊法人・独立行政法人」)の金額が最も大きい。なお、国営研究機関と特殊法人の独立行政法人化により、2001年度以降は、「国営」と「特殊法人・独立行政法人」のデータの連続性が失われている。
図表1-3-2(B)では、公的機関部門のうち、公営機関(地方政府)と公営以外の公的機関に分類し、2000年基準で物価補正を加えた値での研究開発費の変化を見る。
1991年~2005年にかけて、公営機関の研究開発費は年平均成長率-0.89%で減少した一方で、公営以外の公的機関の研究開発費は年平均成長率3.59%で増加した。
2005~2010年をみると公営機関の研究開発費の年平均成長率は-4.08%と、減少の度合いが大きくなっている。この間の公営以外の公的機関の研究開発費の年平均成長率は2.52%であり、増加の度合いは小さくなった。

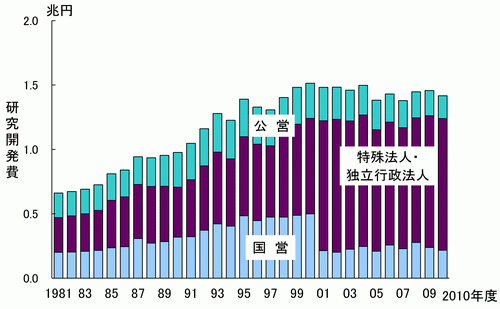
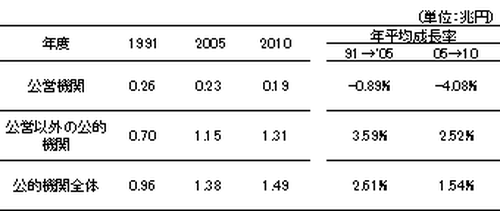
注:
1)2001年度に、国営の研究機関の一部が独立行政法人となっているので時系列変化を見る際には注意が必要である。
2)2000年度までは「特殊法人・独立行政法人」は「特殊法人」のみの値。
3)GDPデフレーターは参考統計Dを使用。
資料:
総務省、「科学技術研究調査報告」
参照:表1-3-2
1.3.2企業部門の研究開発費
ポイント
- 日本の企業部門の2010年度の研究開発費は12兆円で、前年と比較すると0.22%の増加とほとんど横ばいであり、2009年における大幅な減少から回復していない。研究開発費対GDP比を見ると、日本の値は1990年度以降、トップクラスにあるが、2009年度、2010年度と連続して減少し、最新年の対GDP比は2.51%である。
- 各国の政府による企業への直接的資金配分(直接的支援)と研究開発優遇税制措置(間接的支援)について見ると、直接的支援の方が大きいのは米国、フランス、韓国などであり、間接的支援が大きいのはフランス、カナダなどである。なお、フランスについては直接的支援、間接的支援ともに大きく、また韓国やスロベニアも同様である。
(1)各国企業部門の研究開発費
企業部門の研究開発費は各国の研究開発費総額の大部分を占める。企業部門での値の増減が、国の総研究開発費に及ぼす影響は大きい。
図表1-3-3(A)を見ると、日本の2010年(6)の研究開発費は12兆円、前年と比較すると0.22%の増加とほとんど横ばいであり、2009年における大幅な減少から回復していない。
主要国の企業部門の研究開発費をOECD購買力平価換算値で見ると、長期的に見れば、各国とも増加しているが、米国、日本、EUについては近年減少している。ドイツ、フランス、イギリスについては大きな変化が見えない。中国は、2000年代に入り大きく伸びており、2009年では日本を追い越している。
各国通貨(名目額)の年平均成長率でみると(図表1-3-3(B))、2000年代前半(2000~2005年)より2000年代後半(2005~各国最新年)に入ってからの成長率が高かったのは、米国、ドイツ、フランス、中国であり、その他の国は全て減少している。特に日本は2000年代後半ではマイナス成長である。
また、これを各国の物価事情を考慮した実質額(2005年基準各国通貨)の年平均成長率で見てみると(図表1-3-3(C))、2000年代前半より2000年代後半が高いのは米国、ドイツ、フランスである。
なお、中国、韓国についてはそもそも年平均成長率が他国より高い傾向にあり、かつ減少も少ない。日本は2000年代前半では4.65%であった成長率が後半に入ると-0.15%と減少している
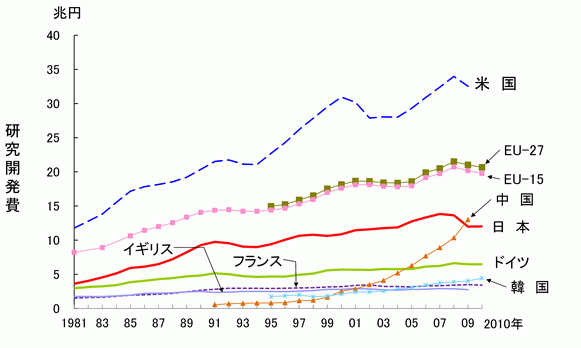
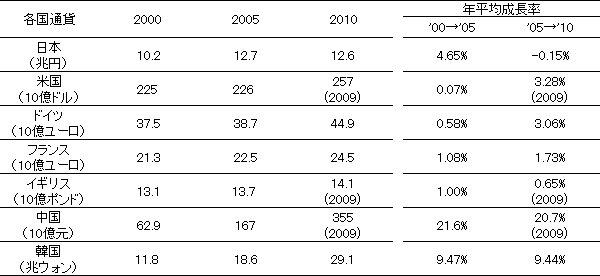
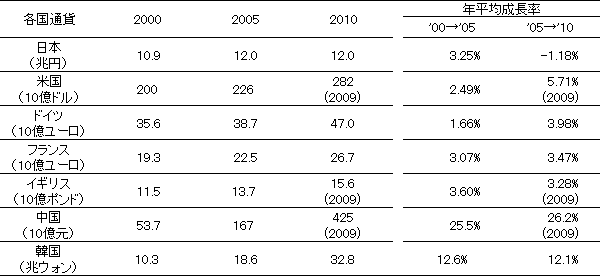
注:
1)各国企業部門の定義は図表1-1-4を参照のこと。
2)研究開発費は人文・社会科学を含む(韓国は2006年度まで自然科学のみ)。
3)購買力平価は、参考統計Eと同じ。
4)実質額の計算はGDPデフレーターによる(参考統計Dを使用)。
<日本>year scaleは、年度。
<ドイツ>1990年までは旧西ドイツ、1991年以降は統一ドイツのデータ。
資料:
<日本>総務省、「科学技術研究調査報告」、OECD,"Main Science and Technology Indicators 2011/2"
<米国>NSF,"Science & Technology Indicators 2012"
<ドイツ>Bundesministerium für Bildung und Forschung,"Bundesbericht Forschung 2004,2006"、"Bundesbericht Forschung und Innovation 2010"、2008年からはOECD,"Main Science and Technology Indicators 2011/2"
<イギリス>National Statistics website: www.statistics.gov.uk
<フランス、中国、韓国、EU>OECD,"Main Science and Technology Indicators 2011/2"
参照:表1-3-3
図表1-3-4に各国の経済規模の違いを考慮して研究開発費を比較するために、「研究開発費の対GDP比」を示す。
企業部門における研究開発費の対GDP比の推移について見てみると、日本の値は1990年以降、トップクラスにあるが、2009年、2010年と連続して減少し、最新年の対GDP比は2.5%である。また、2002年以降、韓国が2位を占めていたが、2009年からは日本を追い越しており、2010年では2.8%と高い比率となっている。米国は近年上昇傾向にあり、イギリス、フランスについては大きな変化は見られない。一方、中国の値はGDP当たりで見ると低いが、近年、他国のレベルに追い付きつつある。

注:
1)GDPは、参考統計Cと同じ。
2)図表1-3-3と同じ。
資料:
図表1-3-3と同じ。
参照:表1-3-4
(2)各国産業分類別の研究開発費
主要国における企業部門の製造業と非製造業の研究開発費について、各国最新年から3年平均で見ると、日本、韓国、ドイツは製造業の割合が9割合を占めている。イギリスは8割、米国に関しては、7割程度であり、非製造業の割合が他国より大きい。(図表1-3-5)。


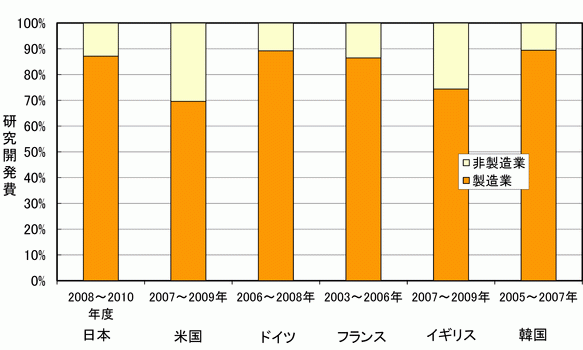
注:
1)各国、自国の産業分類を使用しているため、国際比較する際は注意が必要である。
2)各国企業部門の定義は図表1-1-4を参照のこと。
3)購買力平価は、参考統計Eと同じ。
<日本>産業分類は日本標準産業分類に基づいた科学技術研究調査の産業分類を使用。
<米国>産業分類はNAICSを使用。
<ドイツ>ドイツ産業分類2003版を使用。
<フランス>産業分類はフランス活動分類表(NAF)2003年版を使用。
資料:
<日本>総務省、「科学技術研究調査報告」
<米国>NSF,"S&E Indicators 2010,2012"," InfoBrife (NSF 12-309)"
<ドイツ>Bundesministerium für Bildung und Forschung,"Bundesbericht Forschung und Innovation2010"
<フランス>OECD,"STAN Database "
<イギリス>OST,"SET Statistics"
<韓国>韓国科学技術統計サービス(webサイト)
参照:表1-3-5
図表1-3-6は、日本、米国、ドイツの産業分類別研究開発費を示したものである。ここでいう産業分類とは、各国が標準産業分類を参照して、企業部門の研究開発統計調査のために設定した産業分類である。各国の標準産業分類はISIC(国際標準産業分類)に概ね対応するように設定されているが、やはり国によって多少の差異が出てくるため、国際比較可能性は低いデータであると思われる。そのため、ここでは産業ごとに比較するのではなく、その国の中での産業構造ごとの研究開発費を見ることとする。
以上を踏まえて、日本、米国、ドイツの産業分類別の研究開発費を見ると、日本は製造業がかなり多くを占めており、研究開発費全体の増加も製造業の影響が大きい。一方、非製造業の研究開発費には大きな変化は見えない。日本については2009年度に研究開発費の大幅な減少があり、製造業、非製造業ともに12%の減少であったが、2010年度では横ばいに推移している。産業分類別でみると、2009年度では、すべての産業が前年度と比較して減少したが、2010年度の対前年度比では、輸送用機械製造業、電気機械器具製造業、鉄鋼業といった製造業が増加し、また、非製造業では、情報通信業が増加した。
米国については非製造業がかなり大きいことがわかる。ただし、2004年以降は製造業も大きくなっている。2008年の値を見ると、製造業では、コンピュータ、電子製品工業、また化学工業の値が大きい。
ドイツは製造業、非製造業共に増加しているのが見える。なお、ドイツの非製造業の「不動産、賃貸、事業活動」分類にはいわゆる「ソフトウェア業」や「研究開発」などが入っている。このように各国の標準産業分類の違いに注意しなければならない。
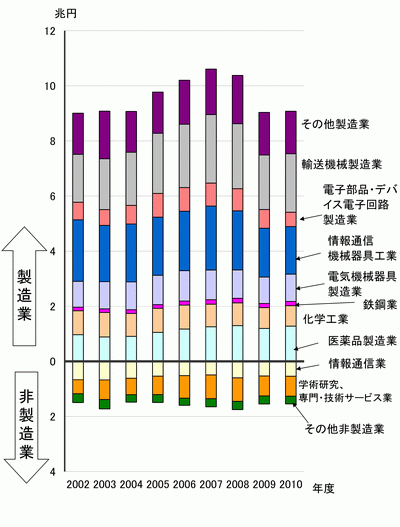
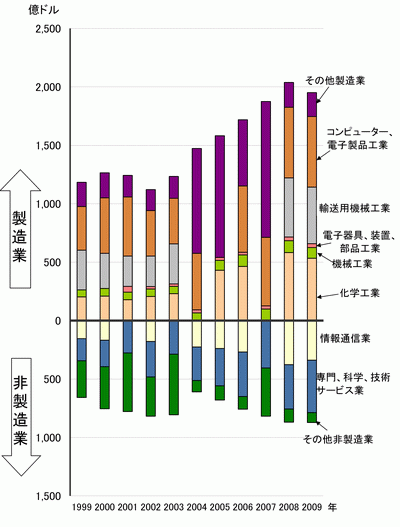
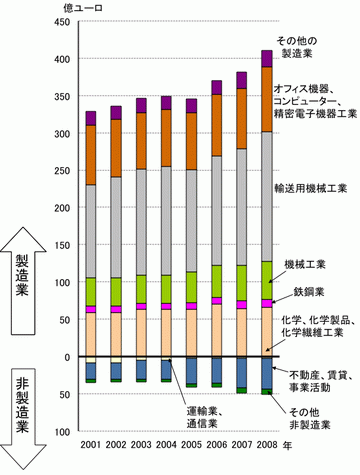
注:
各国企業部門の定義は図表1-1-4を参照のこと。
<日本>産業分類は日本標準産業分類を基に科学技術研究調査の産業分類を使用している。産業分類の改訂に伴い、科学技術研究調査の産業分類は2002、2008年版において変更されている。
<米国>産業分類はNAICSを使用。2002年、2007年に改定。それに伴い、2004年から産業の継続性が失われている。2001年からFFRDCSは除く。
<ドイツ>ドイツ産業分類は2003、2008年に変更されている。
資料:
<日本>総務省、「科学技術研究調査報告」
<米国>NSF,"Industrial R&D 各年" ,"S&E Indicators 2012", "In-foBrif (NSF 12-309)"
<ドイツ>BMBF,"Research and Innovation in Germany 2007"、"Bundesbericht Forschung und Innovation 2008,2010"
参照:表1-3-6
(3)企業の売上高当たりの研究開発費
図表1-3-7は日本と米国における企業部門の売上高当たりの研究開発費の割合の推移である。これを全産業と製造業のそれぞれについて示している。
日本の製造業の値は全産業の値より高く、製造業の方が非製造業より研究集約的である。一方、米国の値は、2000年代に入る前は製造業の方が、研究集約的であったが、2000年以降は全産業の方が値は大きくなり、近年その差を広げている。
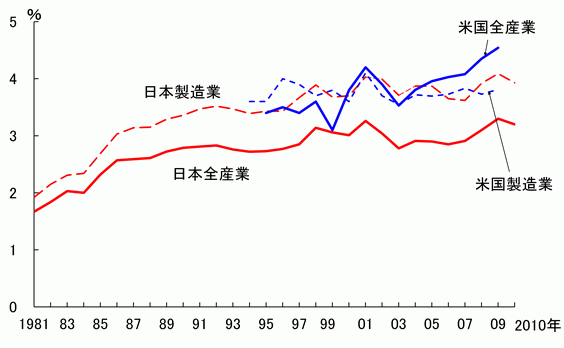
注:
図表1-3-6と同じ。
<日本>売上高あたりの研究開発費の全産業は2001年度値から「金融保険業を除く全産業」。
資料:
<日本>総務省、「科学技術研究調査報告」
<米国>NSF,"R&D Industry 各年","InfoBrif (NSF 12-309)"
参照:表1-3-7
(4)企業への政府による直接的・間接的支援
企業の研究開発費のうち政府が負担した金額(直接的資金配分)(直接的支援)の対GDP比と、企業が政府に支払う法人税のうち、研究開発優遇税制措置により控除された税額(間接的支援)の対GDP比を見る。
これを見ると、直接的支援の方が大きいのは米国、フランス、韓国などであり、間接的支援が大きいのはフランス、カナダなどである
なお、フランスについては直接的支援、間接的支援ともに大きく、また韓国やスロベニアも同様である(図表1-3-8(A))。
次に日本についての政府からの直接的、間接的支援の推移を図表1-3-8(B)に示した。これを見ると、政府から企業への直接的支援は年々減少している。間接的支援は、2004年に大きく伸びており、その後2008年には減少している。
間接的支援の2004年の急増については、2003年に導入された「試験研究費の総額にかかる税額控除制度」による税額控除の急増が主な理由と考えられ、この制度を活用する企業が2004年に増えたと推測される。2008年の減少については、法人税全額の減少が、控除額の減少を起こしたと考えられる。
(A)主要国比較
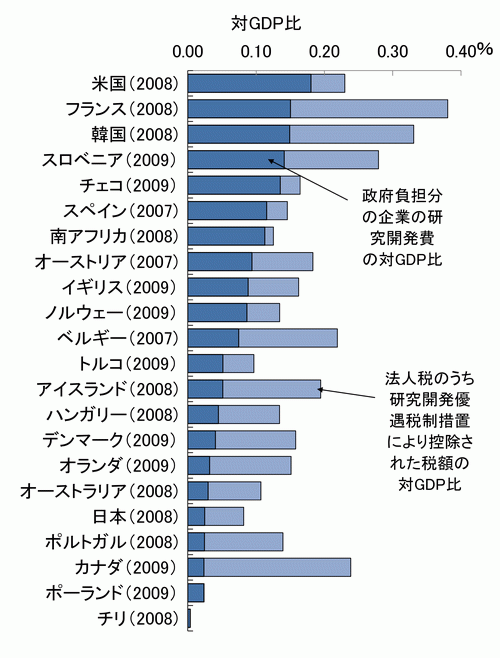
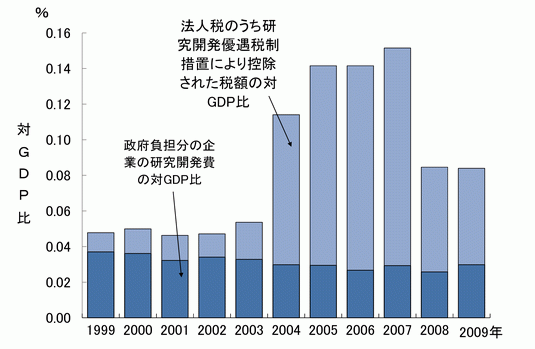
注:
各国からの推計値 (NESTIが行った研究開発税制優遇調査による),予備値も含まれる。
資料:
OECD, "STI Scoreboard 2011"、総務省、「科学技術研究調査報告」、国税庁、「会社標本調査」
参照:表1-3-8
コラム:世界経済危機のもとでの日本企業の研究開発
日本やいくつかの欧米主要国の企業部門の研究開発費は、2009年(7)に減少を記録した(前掲の図表1-3-3参照)。これは注目すべき現象であり、また、日本の減少は特に大幅であるため、本コラムでは、日本を中心に、その状況に関する指標を示す。
(1)2009年における研究開発費の減少
日本の企業部門の研究開発費は、2000年以降、増加が続き、特に、2005年から2007年の3年間には、年平均5%を超える増加率を示していた(図表1-3-9)。しかし、2008年に減少に転じ、続いて2009年は対前年増加率がマイナス12.1%と大幅な減少となった。これは、いわゆるバブル景気の崩壊が起きた1990年代前半を超える大幅な減少である。また、日本の研究開発統計が1953年に開始されて以来、最大の減少率となっている。2010年には対前年増加率0.2%とわずかながら増加したが、2009年の大幅な減少から回復したとは言い難い。
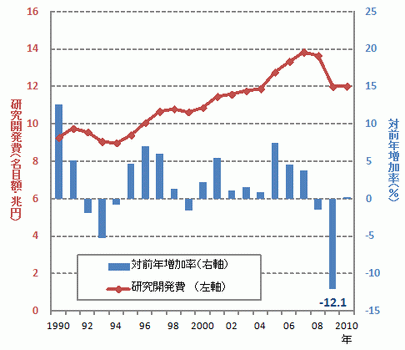
注:
研究開発費は名目値である。
資料:
総務省、「科学技術研究調査報告」
参照:表1-3-9
このような研究開発費の大幅な減少は、米国の投資銀行のリーマン・ブラザーズが2008年9月15日に破綻したことを契機として起きた世界的な経済危機(いわゆるリーマンショック)の影響と考えられる。図表1-3-10によると、米国、ドイツ、イギリスにおいても、2009年には、GDP成長率がマイナスになるとともに、企業部門の研究開発費も減少しており、日本と同様に、経済状況の悪化が企業の研究開発に影響したことがうかがえる。
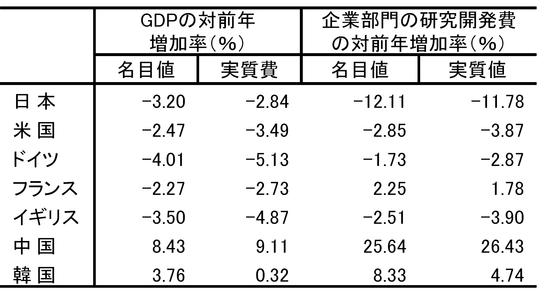
注:
GDPと研究開発費の実質値の計算はGDPデフレーターによる。
資料:
図表1-3-3と同じ。GDPは参考統計Cと同じ。デフレーターは参考統計Dと同じ。
参照:表1-3-10
しかし、主要国のなかで、なぜ、日本の減少が特に著しいのだろうか。それを説明するためには多様な分析が必要であるが、日本の場合、世界的な消費の減退や円高の進行により製造業を中心とする輸出産業が大きなダメージを受け、しかも、企業部門全体の研究開発費に占める製造業のシェアが大きいことが理由のひとつと考えられる。
(2)売上高と研究開発費の関係
日本の企業の研究開発費と売上高の推移(図表1-3-11)を見ると、売上高が減少した時期には、研究開発費も減少していることが多く、全般的に、両者は連動していることがわかる。そして、2009年における研究開発費の減少は、売上高の大幅な減少に連動していたことが明確に示されている。
一方、売上高当たり研究開発費は、2009年が最高の水準である。売上高当たり研究開発費は、企業の研究開発への注力度を示す指標と解釈でき、その意味で、2009年においても、日本企業の研究開発への注力度は低下していなかったと言える。
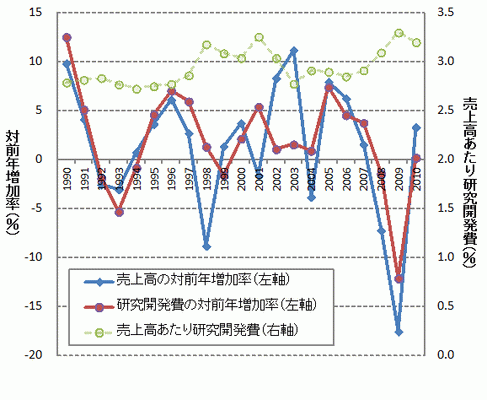
注:
研究開発費、売上高ともに名目値であり、研究を行っている企業(金融業、保険業を除く)の金額による。
資料:
総務省、「科学技術研究調査報告」
参照:表1-3-11
(3)2009年に企業は何を削減したか
日本企業が2009年に研究開発費を削減した際の費目別の内訳(図表1-3-12)を見ると、-12.1%の減少分のうち、「その他の経費」や「原材料費」の減少の寄与が大きく、この2つの費目だけで-8.34%の減少分を担っている。一方、研究開発費の総額のなかで大きな割合を占めている「人件費」の減少は、-1.95%と比較的小さな寄与に留まっている。
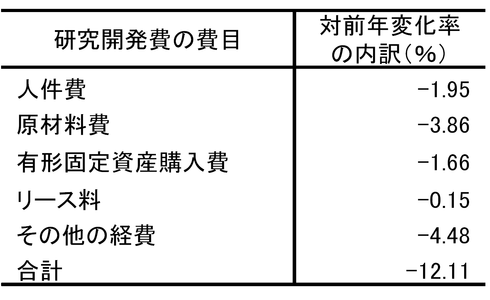
注:
名目値の研究開発費に基づく。
資料:
総務省、「科学技術研究調査報告」
参照:表1-3-12
研究開発費以外の統計データについても2009年の対前年増加率を見ると、ほとんどの項目でマイナスとなっている(図表1-3-13)。しかし、研究者のうち「主に研究に従事する者」の数のみは、対前年増加率が0.1%とわずかながら増加している。研究人材と研究開発費を単純に比較できないが、このデータからは、全般的に、日本企業は研究開発費を縮小したものの、中核的な研究者の数を削減するまでには至らなかったことがうかがえる。
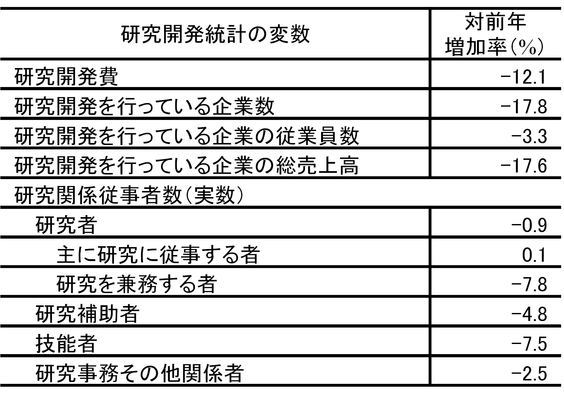
注:
1)総売上高は金融業、保険業を除く企業の値。
2)研究者のうち、「主に研究を行う者」とは、研究にフルタイムで従事する研究者を指し、「研究を兼務する者」とは、他の業務にも従事しつつ研究を行う研究者を指す。
資料:
総務省、「科学技術研究調査報告」
参照:表1-3-13
(4)まとめ
2009年に経済状況が悪化するなかで、日本企業は過去に例のない大幅な研究開発費の削減を行ったが、売上高当たり研究開発費は高い水準に保たれていることから、全般的に、企業が研究開発を重視する姿勢は保持されていたと考えられる。また、研究開発費のうち、一時的に縮小しやすい費目が主に削減されていることからも、少なくとも2009年時点においては、一時的な措置として研究開発費を削減した企業が多いと推測できる。
しかし、その後、2011年3月の東日本大震災や、欧州における財政・債務危機や円高の進行など、企業活動に影響を及ぼす可能性のある事象が起きており、今後、それらの影響が統計データに表れてくる可能性がある。経済の低迷が続くようであれば、企業が研究開発を一層、縮小せざるを得ない状況に陥る恐れもあり、今後、注意深く状況を見ていく必要がある。
(富澤 宏之)
1.3.3大学部門の研究開発費
ポイント
- 大学部門における2010年度の日本の値は3.4兆円であり、対前年度比では3.3%の減少率である。日本(OECD推計)の大学の研究開発費は、2.1兆円(2009年度)である。
- 研究開発費の実質額(2005年基準各国通貨)の年平均成長率を見ると、2000年代前半(2000~2005年)より2000年代後半(2005~各国最新年)の方が低くなっている国は、日本、米国、イギリス、中国である。
- 主要国の大学の研究開発費の政府負担割合を見ると、各国最新の3年平均で、政府負担分が最も大きいのはフランスであり89.9%、最も小さいのは日本で49.5%である。2003-2005年と比較すると、最も増加したのは韓国であり、最も減少したのは米国である。
- 主要国の大学の研究開発費の企業負担割合を見ると、各国最新の3年平均で最も大きいのは中国で34.7%と群を抜いている。一方、最も小さい国はフランスで1.9%である。日本は2.6%でフランスに次いで小さい。2003-2005年と比較すると、最も増加したのはドイツであり、最も減少したのは韓国である。
- 日本の大学部門の研究開発費を分野別で見ると、自然科学分野では国立大学が使用額の約5割を占め、人文・社会科学分野では私立大学が使用額の約7割を占める。
(1)各国大学部門の研究開発費
大学をはじめとする高等教育機関は、研究開発機関としての機能も持ち、各国の研究開発システムのなかで重要な役割を果たしている。1.1.2節で示したように、主要国では国全体の研究開発費の1割~3割弱程度を使用している。
高等教育機関の範囲は国によって異なるが、各国とも大学が主たるものである。また、どのレベルの機関まで調査をしているかも国によって差が出る。どの機関を対象としているかを簡単に示すと、日本は大学(大学院も含む)に加えて、短期大学、高等専門学校、大学附置研究所、および、その他の機関が含まれる(8)。米国に関してはUniversities & Colleges (FFRDCsは除く、年間15万ドル以上の研究開発をしている機関)、ドイツはUniversities、comprehensive universities、colleges of theologyなどである。フランスは国立科学研究センター(CNRS)、大学を含む高等教育機関及び、国民教育省(MEN)所管以外のグランゼコールである。大部分の国々では研究開発統計の調査範囲は全分野となっているが、米国についてはS&E(9)の分野であり、韓国は2006年まで自然科学分野のみを対象としていた(図表1-1-4参照)。
大学部門の研究開発費を算出するには、教育活動と研究開発活動を区別して、経費を集計する必要があるが、一般的にそれは困難である。
日本の大学の研究開発費は、総務省の研究開発統計「科学技術研究調査」による。この調査では研究開発費の内数として人件費についても集計しているが、この人件費は「研究以外の業務(教育など)」を含む総額データとなっている。
日本の研究開発統計では、大学部門についてフルタイム換算した研究者数の統計をとっておらず、さらにすべての教員は研究者として計測されている。しかしながら、教員全員が研究のみに従事していることはあり得ない。このため全教員の人件費が研究開発費に計上されている状態は、研究開発費としては過剰計上となっていると考えるのが自然であろう。
こうした事実はOECD側も認識しているため、OECD統計が発表する日本の研究開発費は1996年(10)以降人件費に対して、1996~2001年は0.53を乗じた値、2002年以降は0.465を乗じた値となっている。なお、2002年以降の補正係数である0.465は2002年に文部科学省が実施した「大学等におけるフルタイム換算データに関する調査」から得られたFTE換算係数である。この調査は2008年にも再度実施された。この時の調査では、教員のFTE換算係数は0.362となっており、2008年以降のOECDのデータでは、2008年調査のFTE換算係数が使用されている。
以下においては、日本の大学部門の研究開発費として、OECDで提供している値(「日本(OECD推計)」と明記)と総務省「科学技術研究調査報告」で提供している値(「日本」と明記)を掲載することとする。
図表1-3-14(A)は大学部門の研究開発費を名目額で示している。2010年の日本の値は3兆4,340億円であり、対前年度比では3.3%の減少率である。日本(OECD推計)の大学の研究開発費は、2兆1,212億円(2009年)である。
各国の状況を見ると、米国とEUの増加が著しい。
EUのなかで研究開発費使用額の大きいドイツ、フランス、イギリスについては、長期的に見ると漸増傾向にある。中国は2000年以降、着実に増加している。
次に各国通貨(名目額)で国毎の年平均成長率を見ると(図表1-3-14(B))、2000年代前半(2000~2005年)より2000年代後半(2005~各国最新年)の方が低くなっている国は、日本、米国、イギリス、中国である。また、2000年代後半の成長率の方が高い国はドイツ、フランス、韓国である。
物価を考慮した実質額で見ると(図表1-3-14(C))、2000年代前半より2000年代後半の成長率が低くなっている国は日本、米国、中国である。また、2000年代後半の成長率の方が高い国はドイツ、フランス、韓国である。中国では、年平均成長率は高い数値であるが、2000年代前半と比較すると、名目額、実質額ともに減少している。
(A)名目額(OECD購買力平価換算)

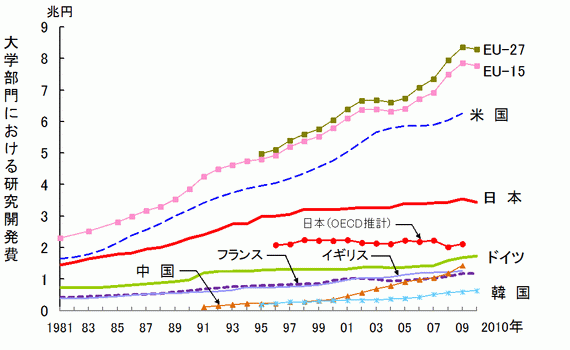
(B)名目額(各国通貨)
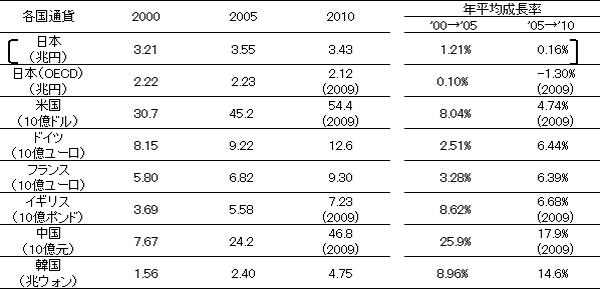
(C)実質額(2005年基準各国通貨)
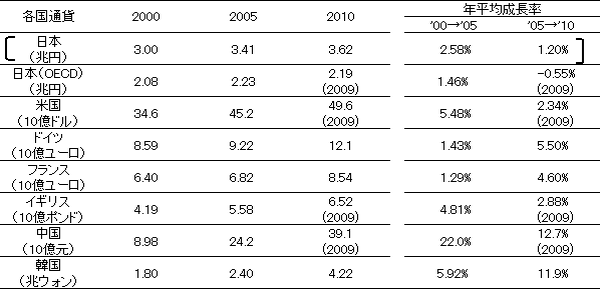
注:
1)学部門の定義は国によって違いがあるため国際比較の際には注意が必要である。各国の大学部門の定義については図表1-1-4参照のこと。
2)購買力平価は、参考統計Eと同じ。
3)研究開発費は人文・社会科学を含む(韓国は2006年度まで自然科学のみ)。
<日本(OECD推計)>1996年からOECDが補正し、推計した値(大学部門の研究開発費のうち人件費をFTEにした研究開発費)。
<ドイツ>1990年までは旧西ドイツ、1991年以降は統一ドイツ。
資料:
表1-1-5と同じ。
参照:表1-3-14
各国の総研究開発費使用額のうち大学部門が使用している研究開発費の占める割合の推移を図表1-3-15に示した。日本の大学部門の割合は、近年減少傾向にあったが、2009年では上昇した(ただし、この変化は企業部門の研究開発費が減少したことにより、総研究開発費が減少したため、結果として大学部門のシェアが増加した)が、2010年では0.5ポイント減少し20.1%となっている。イギリスは増加傾向にあり、特に2000年以降増加が著しい。これはイギリスの大学の研究開発費が増加していることに加えて、公的部門の研究開発費の伸びが悪いことなどが影響していると思われる。米国、ドイツは長期的に見ると、増減を繰り返しながら、近年は横ばいに推移している。

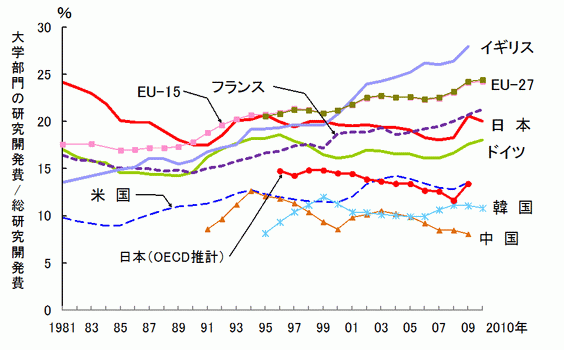
注:
図表1-1-1、図表1-1-5と同じ。
資料:
図表1-1-1、図表1-1-5と同じ
参照:表1-3-15
(2)主要国における大学の研究開発費の負担構造
図表1-3-16は主要国における大学の内部使用研究開発費の部門別負担割合、つまり大学の内部使用研究開発費のうち、各部門がどの程度、研究資金を負担しているか、また政府と企業部門が大学に負担している資金は、その部門の負担額において、どの程度の割合なのかを示したものである。
まず、大学の内部使用研究開発費の部門別負担割合を見ると(図表1-3-16(A)、①、②)、各国最新の3年平均で、政府負担分が最も大きいのはフランスであり89.9%、最も小さいのは日本で49.5%である。2003-2005年と比較すると、最も増加したのは韓国であり、最も減少したのは米国である。
企業の負担分を見ると、各国最新の3年平均で最も大きいのは中国で34.7%と群を抜いている。一方、最も小さい国はフランスで1.9%である。2003-2005年と比較すると、最も増加したのはドイツであり、最も減少したのは韓国である。
各国毎にみると、2008-2010年の日本の政府負担割合は49.5%、企業の負担割合は2.6%となっており、2003-2005年と比較すると、政府負担は0.8ポイント減少、企業負担は0.2ポイントの減少である。
米国については2007-2009年の政府負担割合は大学全体の65.6%、企業が負担している割合は5.8%となり、2003-2005年と比較すると政府負担割合は3.6ポイントの減少、対して、企業負担割合は0.7ポイント増加している。
ドイツは政府・非営利団体からの負担が大きく、2005-2007年では全体の81.3%を占めており、また、企業負担割合も各国と比較すると14.6%と大きい。2003-2005年と比較すると、政府・非営利団体の負担割合は2.4ポイント減少、対して、企業負担割合は1.3ポイント増加している。
フランスも政府負担割合が大きく、2008-2010年では全体の89.9%を占めており、主要国の中でも一番大きい。一方、企業負担割合は1.9%と主要国の中で一番小さい。2003-2005年と比較すると、政府負担割合は0.8ポイントの減少、企業負担割合は0.1ポイントの減少となっている。
イギリスに関しても政府負担割合は大きく、2007-2009年で68.4%である。企業負担割合は4.3%である。2003-2005年と比較すると政府負担割合は0.2ポイント増加、企業負担割合は0.5ポイント減少している。
中国の政府負担割合は、2008-2010年では58.2%、企業の負担割合は、他国と比較して最も大きく34.7%である。2003-2005年と比較すると、政府負担割合は3.6ポイントの増加、一方、企業負担割合は1.9ポイントの減少である。
韓国の政府負担割合は2008-2010年では79.1%、企業負担割合は11.5%である。2003-2005年と比較すると、政府負担割合は6.3ポイントの増加で、他国に比べて高い伸びを示している。対して、企業負担割合の伸びは1.9ポイント減少となっている。
次に、政府と企業部門の研究開発費負担分のうち大学への負担分の割合を見てみる(図表1-3-16(A)、③、④)。
政府負担分のうち大学への負担割合が最も大きいのはイギリスで、58.5%である。日本、ドイツ、フランスは約50%程度である。米国、韓国は約30%程度、最も小さいのは中国で20.4%である。
企業負担分のうち、大学への負担割合は各国ともかなり少ない。比較的大きいのは中国、ドイツであり、約4.0%となっている。対して約1%程度なのは日本、米国、フランスとなっている。
2003-2005年と最新年を比較すると、政府負担分のうち大学への負担割合が一番増加しているのはイギリスであり、6.1ポイント増加している。企業の場合はほとんどの国で成長がみられない。
また、図表1-3-16(B)~(G)を見ると、外国からの負担分は各国とも少ないが、イギリスは9.4%と比較的大きい数値となっている。

(A)一覧表
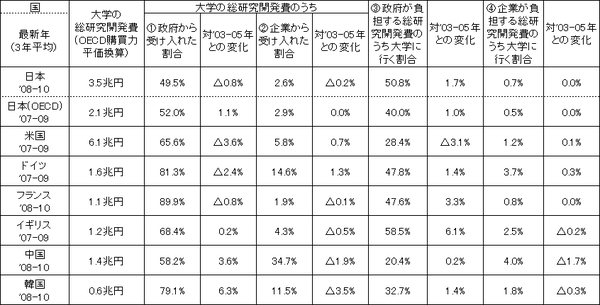
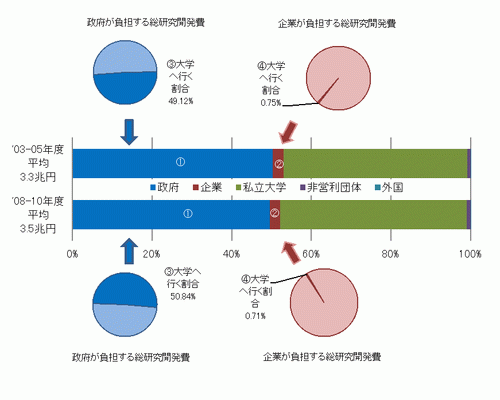

日本の統計において、大学で使用される研究開発費のうち、大学による負担分とは私立大学が負担している金額を指す。そのほとんどが私立大学の自己資金による研究開発費である。
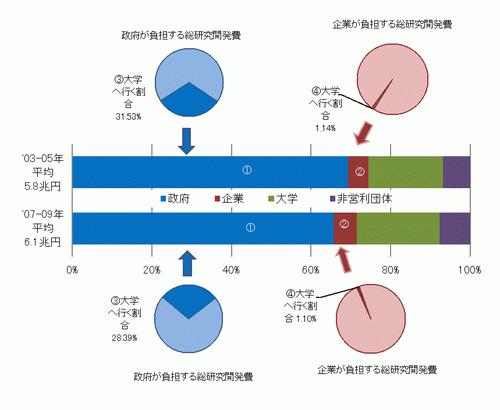
(D)ドイツの大学の研究開発費の負担構造
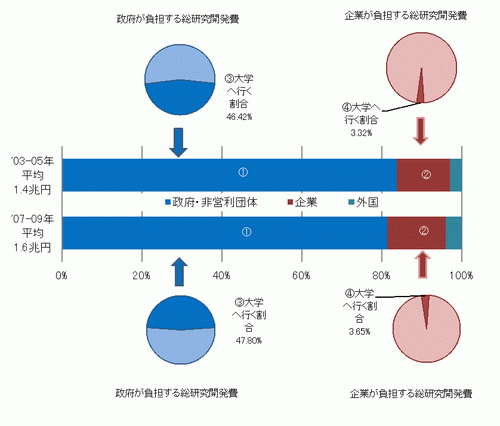
(E)フランスの大学の研究開発費の負担構造
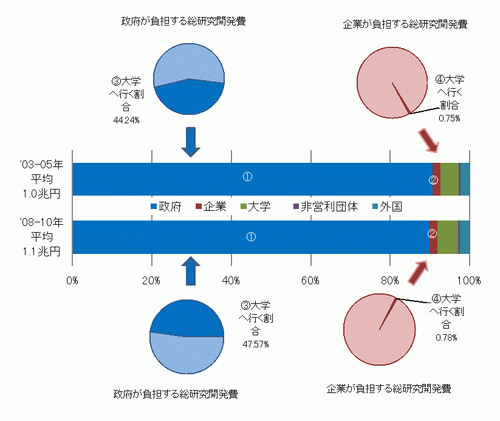
(F)イギリスの大学の研究開発費の負担構造
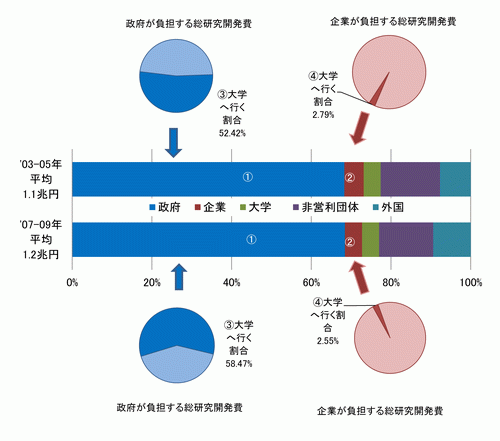
(G)中国の大学の研究開発費の負担構造
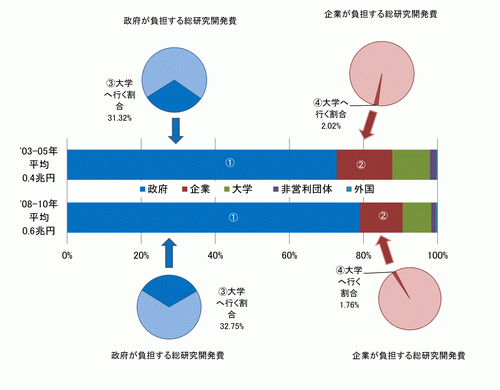
(H)韓国の大学の研究開発費の負担構造
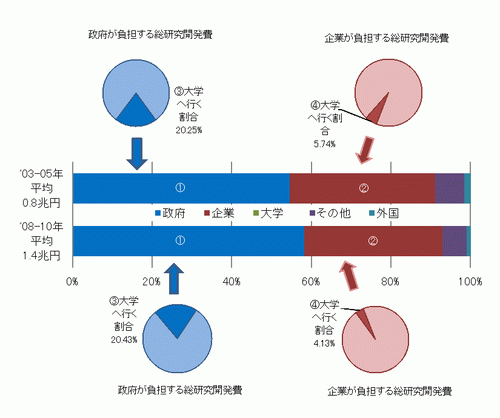
注:
1)3年平均値である。たとえば、08-10は2008年から2010年の平均値。
2)矢印の中の数値は各部門の研究開発費負担分のうち、大学部門へ負担する金額の割合。たとえば、08-10年度の日本の政府の負担分のうち、大学へ負担する金額は、負担分の50.84%である。
3)その他、国際比較等の注は図表1-2-3、4と同じ。
資料:
図表1-2-4と同じ。
参照:表1-3-16
(3)日本と米国の大学の研究開発費の設立形態別資金構造
図表1-3-17は日米の大学の研究開発統計の対象となっている機関数の変化である。米国(NSF)は研究開発予算を年間15万ドル以上執行している大学が対象であり、全大学を対象としているわけではない。一方、日本の科学技術研究調査では短大等も調査対象となっているが、ここでは日米比較のため4年制大学のみを取り上げている。
最新年の日本を見ると、国立大学86、公立大学76、私立大学607であり、推移を見ると私立大学が増加している。米国については州立大学403、私立大学294であり、推移を見ると私立大学が増加している。

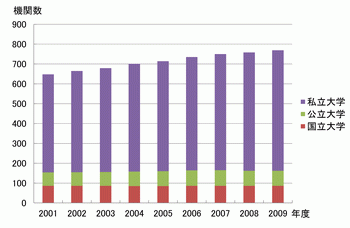
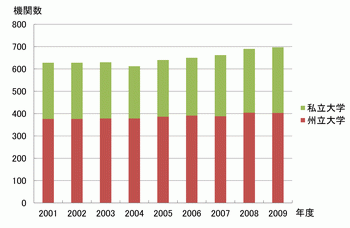
注:
日本と米国における大学の対象範囲には差異があるので国際比較する際には注意が必要である。日本の場合、4年制の大学。短大や大学共同利用機関等は含まない。米国の場合、研究開発予算を年間15万ドル以上執行している機関
資料:
<日本>総務省、「科学技術研究調査報告」の個票データを使用し、科学技術政策研究所が再計算した。
<米国>NSF."Academic R&D Expenditures"
参照:表1-3-17
次に日本と米国における形態別の大学の資金構造とその変化を示す。
図表1-3-18(A)は日本の大学(4年制大学)を国・公・私立大学別に分けて資金構造を示したものである。国・公立大学では政府からの資金が9割以上を占めており、企業やその他の部門からの資金は少ない。
2007-2009年の国立大学の割合を見ると、政府からの資金が92.7%を占めているが、2002-2004年と比較すると、0.8ポイントの減少と、ほとんど横ばいである。また、企業からの資金は5.1%と少ない数値である。一方2007-2009年の私立大学についてみると、私立大学からの資金が89.3%を占めているが、そのほとんどが自己資金である。政府からの資金は2007-2009年で8.9%であり、2002-2004年と比較すると、0.3ポイント増加と、ほとんど変化はない。なお、企業からの資金は1.4%と、国立大学と比較しても、かなり少ない。
図表1-3-18(B)は米国の大学の研究開発費の資金構造を州・私立大学に分けて示したものである。
米国の2007-2009年を見ると、連邦政府及び州・地方政府からの資金の割合は、州立大学(63.4%)より、私立大学(74.3%)の方が大きい。逆に機関資金(企業、財団、その他の外部資金源からの、使途が特化されていない資金。プロジェクトの間接経費を含む)の割合は州立大学(23.9%)の方が私立大学(11.7%)より大きい。

(A)日本
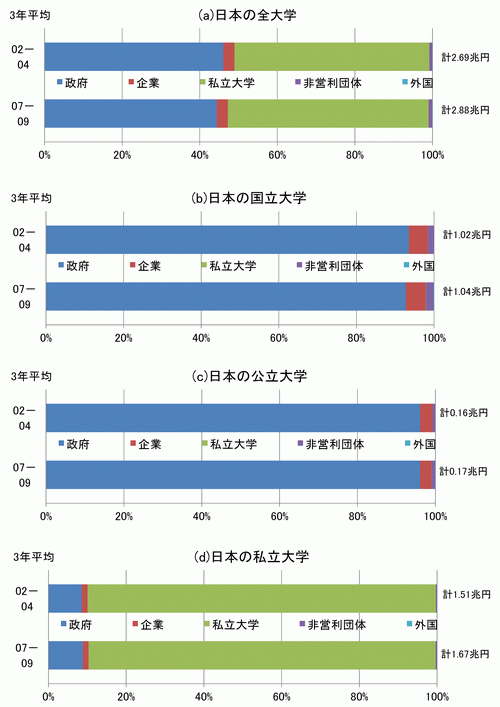
(B)米国
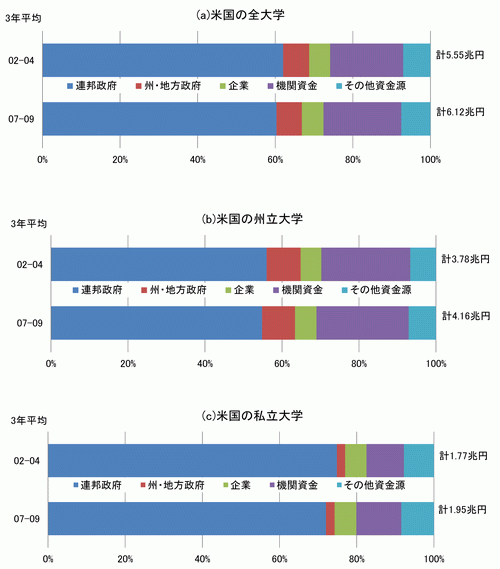
注:
国際比較注意については図表1-3-16を参照のこと。
<米国>
1)機関資金とは企業、財団、その他の外部資金源からの、使途が特化されていない資金。プロジェクトの間接経費を含む。
2)その他資金とは他に分類されない資金源。たとえば、研究の目的で個人が寄付した資金を含む。
資料:
<日本>総務省、「科学技術研究調査報告」の個票データを使用し、科学技術政策研究所が再計算した。
<米国>NSF."Academic R&D Expenditures"
参照:表1-3-18
(4)日本と米国の大学の総事業費に占める研究開発費の比較
日本と米国の大学の総事業費(総支出額)に占める研究開発費の割合を比較する。その際、日本、米国ともに学位授与権利のある4年制の大学を対象とし、2007年から2009年の3年間の平均値を用いた。
日本の場合、総務省が実施している研究開発統計で総支出額、研究開発費ともに計測されているためこのデータを使用する。図表1-3-19を見ると、全大学の総支出額に占める研究開発費の割合は39.9%である。大学形態別に見ると、国立大学が46.1%と一番大きく、公立大学が36%、私立大学37.2%となっている。
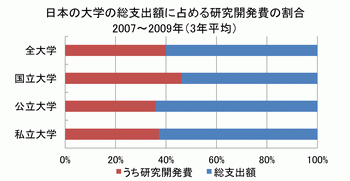
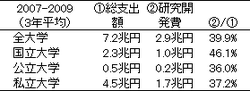
注:
4年制の大学。短大や共同利用機関等は含まれていない。
資料:
総務省、「科学技術研究調査報告」
参照:表1-3-19
米国の場合、NSFの研究開発統計には大学の総事業費(総支出額)がないので、NCES(National Center for Education Statistics:全米教育統計センター)のIPEDSのデータを使用する。IPEDSは米国の中等後教育(高等教育を含む)に関するデータベースであり、総支出額と研究経費(Research)があるので、その値を用いて日本と比較する。IPEDSでは研究に関連する予算で、教育などと明確に分離出来ない場合は教育経費(Instruction)に計上されている。そのため、研究経費(Research)については過少計上となっている。また、その他にもAcademic supportという項目があり、コンピューターセンターや図書館の運営といった費用が計上されているため、この項目にも研究に関連する費用が含まれていると考えられる。なお、IPEDSの統計では研究経費(Research)についても、他の項目同様にSalaries and wagesが計上されており、人件費を含む整理になっている。
図表1-3-20を見ると、全支出額に占める研究経費の割合は、全大学では11.2%であり、州立大学は11.9%、私立大学は10.1%である。
日本と比較すると、日本の大学の研究開発費は総事業費の4割を占め、一方米国の大学の研究経費の割合は1割である。日本、米国ともに公営の大学の方が研究開発費(経費)の占める割合は大きい。日本の国立大学の研究開発の割合は米国の州立大学の約4倍とかなりの差がある。
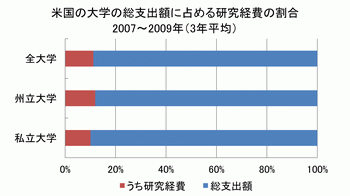
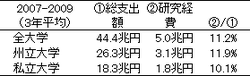
注:
4年制の大学(4-year institution)である。私立大学の一部である営利の大学についてはResearchにPublic serviceが加えられた値が計上されている。ただし、この値は全私立大学の研究経費のうち0.03%程度である。
資料:
NCES,IPEDS,"Digest of Education Statistics"
参照:表1-3-20
次に、IPEDSの研究経費に代えてNSFによる米国の大学の研究開発費を用いて比較する。
NSFの研究開発統計では研究開発費を年間15万ドル以上使っている大学を対象範囲としており、大学数も700弱であるが、2,780大学(うち678が州立大学)を対象としているIPEDSの研究経費より約1兆円多い。これは前述のとおり、IPEDSの研究経費が過少計上されているためであると思われる。また、NSFの対象となっていない大学の研究開発費は1大学15万ドル以下とすると、合計してもその寄与は小さいので、NSFによる研究開発費とIPEDSの総支出額を比較することは一定の合理性を持つ。
図表1-3-21を見ると、この場合、全大学の総支出額に占める研究開発費の割合は13.8%である。大学形態別に見ると州立大学が15.9%、私立大学が10.7%となっている。
なお、NSFでも研究開発費について、教育などと分けられないものは含めない、という方針で調査を実施している。
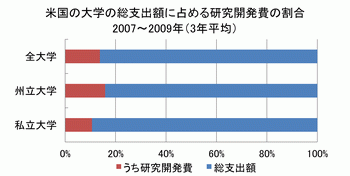
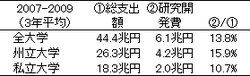
注:
4年制の大学(4-year institution)である。
総支出額:NCES,IPEDS,"Digest of Education Statistics"
研究開発費:NSF, "Academic R&D Expenditures"
参照:表1-3-21
日本の大学の場合、研究開発費は研究者(教員、医局員その他研究員等)の人件費を、研究専従率を考慮せずに計上しているため、過剰計上となっている。人件費分を研究専従率で補正したOECDの研究開発費を使用すると、約4割減少するが、それでも総支出額に占める研究開発費は、3割程度となる。
このような補正を試みても、日本と米国の大学における総事業費と研究開発費の関係には大きな差異があり、大学の研究開発費の日米比較を適切に行うためには検討すべき点が残されている(図表1-3-22)。
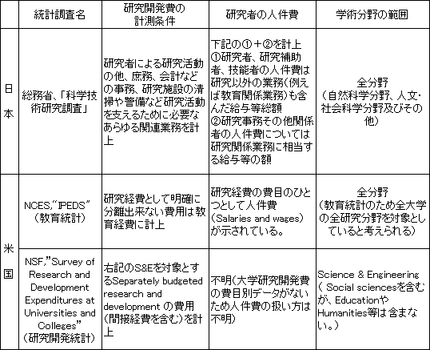
資料:
<日本>総務省、「科学技術研究調査報告」
<米国>NCES,IPEDS
NSF, “Survey of Research and Development Expenditures at Universities and Colleges”
(5)日本の大学部門の研究開発費
日本の大学における研究開発費は上述したとおり、人件費に研究以外の活動分も含まれているという点に注意しなければならないが、この節では、「科学技術研究調査報告」で公表している大学等の研究開発費のデータを用いて国公私立大学別の研究開発費使用額を見る(図表1-3-23)。
2010年度の日本の大学全体の研究開発費は、3兆4,340億円であり、うち自然科学分野では2兆1,838億円、人文・社会科学分野で1兆2,502億円となっている。対前年度比では全体で3.3%の減少率であり、うち自然科学分野では4.6%の減少率、人文・社会科学分野では0.8%の減少率であり、自然科学分野での減少が大きい。
研究開発費全体を国・公・私立大学別で見ると、2010年度では、国立41.4%、公立5.2%、私立53.4%である。自然科学分野のみで見ると、国立53.6%、公立5.8%、私立40.6%となり、人文・社会科学分野になると、国立20.2%、公立4.1%、私立75.7%となる。
即ち、国立大学は自然科学分野(理学、工学、農学、保健)において、研究開発費使用額の割合を多く占めていることがわかる。これに対して私立大学は、人文・社会科学分野の研究開発費使用額の割合が多いといえる。
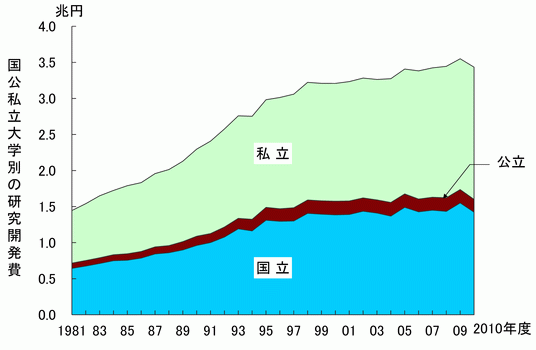
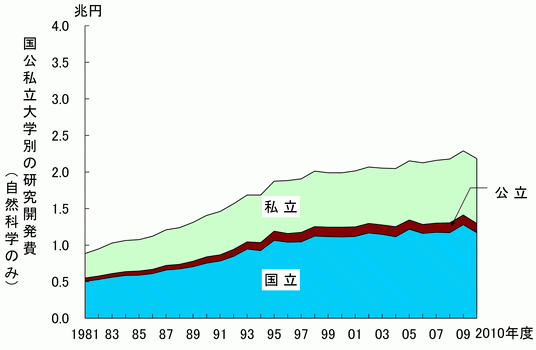
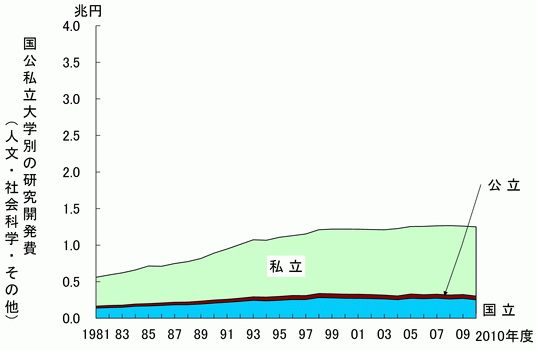
注:
「人文・社会科学」には「その他」も含む。
資料:
総務省、「科学技術研究調査報告」
参照:表1-3-23
大学等の研究開発費に関して学問分野別の割合の推移を見る。ここでの学問分野とは、学部、研究施設内で行われている研究の内容を指す。組織の中で研究分野が複数にわたる場合は最も中心であると判断された研究の学問分野を示している。
図表1-3-24を見ると、分野ごとの変化が小さいことがわかる。ここに示した学問分野は、上述のとおり学部等の組織の種類による区分であるため、この図から研究開発の内容面での変化は読みとりにくい。
しかしながら、長期的に見ると、理学、工学、農学分野の割合が減少し、代わって保健、人文社会科学が増加している。
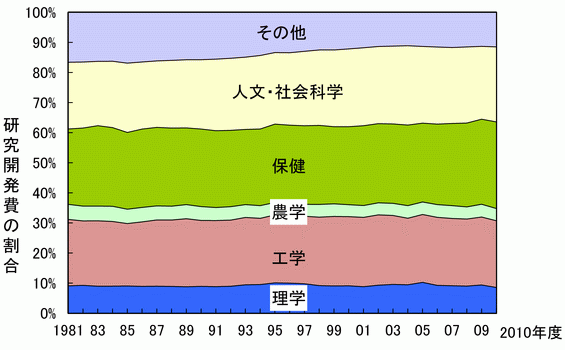
注:
学問分野の区分は、学部等の組織の種類による区分である。
資料:
総務省、「科学技術研究調査報告」
参照:表1-3-24
近年、大学のポテンシャルを活用しようとする取り組みが、世界の各国で進められている。大学は、イノベーションの源泉である知識の創造という点で、他に代替しえない組織であるが、その一方で、大学で産み出された知識を他に移転することは容易でない。このような認識を背景に、産学連携を強力に推進する機運が高まっている。
産学連携の状況を示す指標のひとつとして、大学が企業から受け入れた研究開発費をとりあげる(図表1-3-25)。大学等が企業部門より受け入れた研究開発費の推移は、1999年度以降、著しい増加を示していたが、2007年度をピークに減少に転じている。2010年度は832億円であり、同年度における大学等の内部使用研究開発費(3兆4,330億円)の2.4%に過ぎない。
国・公・私立大学の区分別に見ると、企業部門から受け入れた研究開発費は国立の金額が最も多く全体の約7割を占め、その割合に大きな変化は見られない。
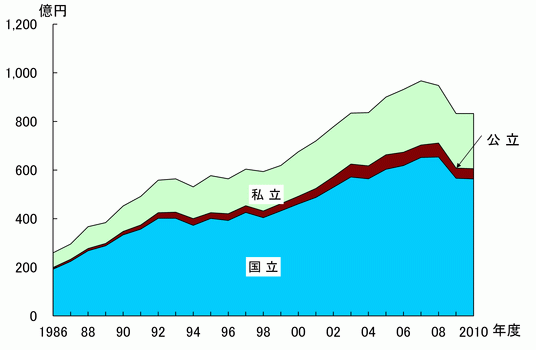
資料:
総務省、「科学技術研究調査報告」
参照:表1-3-25
(6)日本の大学部門の費目別研究開発費
大学等の内部使用研究開発費に関して費目別の内訳を見ると、「人件費」が多く、2010年度の「人件費」は2兆2,218億円で、全体の64.7%を占めている(図表1-3-26)。
国立・私立大学別でみると、2010年度の国立大学の「人件費」は7,924億円であり、2000年代に入ってからは横ばいに推移している。また、割合は全体の55.7%であり、長期的にみると減少している。
私立大学でも「人件費」の割合は大きく2010年度では、1兆2,986億円であり、増加し続けている。また、割合は全体の70.8%であり、長期的見ると漸増している。
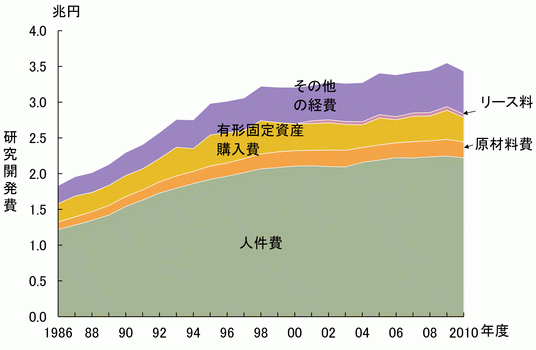
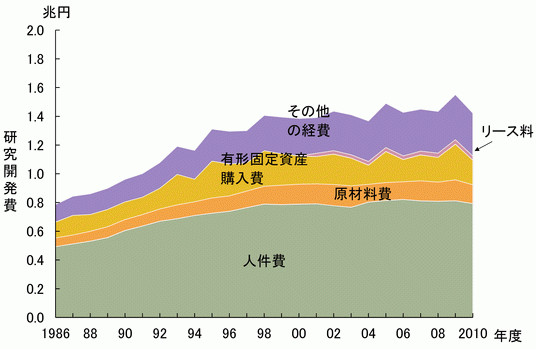
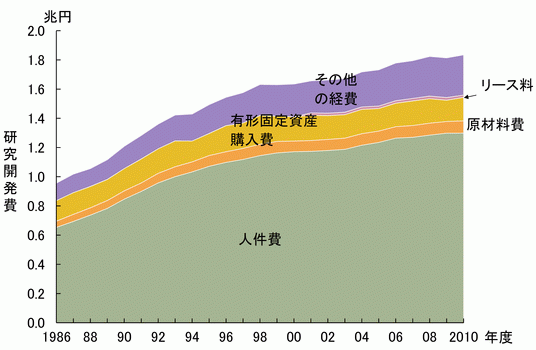
注:
2001年度より、新たに「リース料」が調査項目に加わった。
資料:
総務省、「科学技術研究調査報告」
参照:表1-3-26
(6)この節の日本の場合は、国際比較の際には「年」を用いている。本来は「年度」である。
(7)2009年度の金額による。本コラムでは、金額に関する日本のデータについては各年度の値を用いるが、人材データや米国データとの比較のため、便宜上、全て「年」と表示する。
(8)日本の大学部門の統計資料として本章で用いる総務省統計局「科学技術研究調査報告」においては、大学は学部(大学院の場合は研究科)ごとに調査されており、その総数は2010年3月31日現在では2,341である。また、「その他の機関」とは、大学共同利用機関法人、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター、独立行政法人メディア教育開発センター、大学に設置されている博物館、センター、施設等である。
(9)S&EとはScience and Engineering: Computer sciences,Environmental sciences, Life sciences, Mathematical sciences, Physical sciences, Psychology, Social sciences, Engineeringであり、EducationやHumanities等は含まれていない。
(10)この節の日本の場合は、国際比較の際には「年」を用いている。本来は「年度」である。

