4.2特許
ポイント
- 世界の特許出願数は、リーマンショックに端を発する不況の影響で2009年には大きな減少を見せたが、2010年には再び増加に転じた。その数は200万件に迫っている。
- 日本への出願数(約35万件)は米国に次ぐ規模であるが、2000年代半ばから減少傾向にある。米国への出願数(約49万件)は、ここ数年は横ばい傾向であったが、2010年には2009年と比べて約7%の増加を見せた。2010年の中国への出願数は約39万件であり、日本特許庁への出願数を上回った。
- 日本、米国、中国、韓国からの出願をみると、他国への出願数より、自国への出願数の方が多い。日本からの全出願数のうち、約6割が自国(日本特許庁)への出願である。国内への特許出願を増加させている中国であるが、他国への出願数は約1万4千件と、まだ少ない。
- 日本特許庁、米国特許商標庁、欧州特許庁への特許出願数をみると、10年前から引き続いて、日本は大きな存在感を示している。技術分野別の出願状況をみると、再生可能エネルギーにおける日本のシェアが 減少傾向にある。
4.2.1世界における特許出願
(1)世界での特許出願状況
図表4-2-1は、2011年12月時点でのWIPO(世界知的所有権機関),“Statistics on Patents”にデータが掲載されている約230国・地域への特許出願数の推移を示したものである。ここでは、世界における特許出願数を、出願人が、自らが居住している国・地域へ行った特許出願(Resident Applications; 居住者からの出願)、出願人が、自らが居住していない国・地域へ行った特許出願(Non-Resident Applications; 非居住者からの出願)に分けて示している。
出願数として、各国・地域の特許官庁に、直接なされた特許出願、PCT(Patent Cooperation Treaty)出願によってなされた特許出願の両方をカウントしている。PCT出願については、各国・地域の特許官庁へ国内移行されたものをカウントした。
全世界における特許出願数は、1990年代半ばから年平均成長率約5%で増加し、2010年には200万件に迫っている。1980年代半ばに約3割であった非居住者からの出願は、居住者からの出願よりも早いペースで増加し、近年は全出願数の約4割を占めている。
世界の特許出願数は、リーマンショックに端を発する不況の影響で2009年には大きな減少を見せたが、2010年には再び増加に転じていることが分かる。
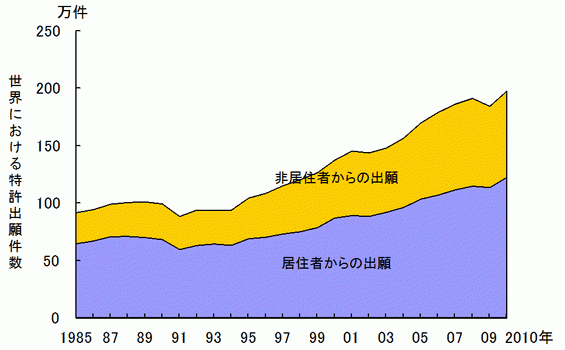
注:
1)居住者からの出願とは、第1番目の出願人が、自らが居住している国・地域に直接出願もしくはPCT出願すること。
2)非居住者からの出願とは、出願人が、自らが居住していない国・地域に直接出願もしくはPCT出願すること。
3)PCT出願とはPCT国際特許出願を通じた出願のこと。
資料:
WIPO,“Statistics on Patents”(Last update: December, 2011)
参照:表4-2-1
(2)主要国の特許出願状況
次に、主要国への特許出願状況と主要国からの特許出願状況についてみる。
主要国への特許出願状況を図表4-2-2(A)に示した。ここでは、日本、米国、欧州、中国、韓国、ドイツ、フランス、イギリスへの特許出願状況を対象としている。この8特許官庁への出願で、全世界の特許出願の約8割を占める。ここでは出願数の内訳を、居住者からの出願、非居住者からの出願の2つに分けて示した。
日本への出願数は米国に次ぐ規模であるが、近年は減少傾向にある。2009年の出願数は2008年と比べて約10%減少し、その状態が2010年も継続している。内訳を見ると日本に居住する出願人からの日本特許庁への出願が84%を占めている。
米国への出願数は、ここ数年は横ばい傾向であったが、2010年には2009年と比べて約7%の増加を見せた。居住者からの出願と非居住者からの出願の割合が、ほぼ半数ずつとなっている。これは米国の市場が海外にとって常に魅力的であることを示していると考えられる。なお、1995年から仮出願制度が導入された。このことも出願数が増加した理由の一つと考えられる。
欧州特許庁への出願数は2009年を例外とし、毎年、増加しており、2010年には15万件に達した。一方、ドイツ、フランス、イギリスへの出願数はほぼ横ばいである。欧州特許条約の締結国における特許出願は、欧州特許庁への出願により一括して行うことができるので、各国への出願数は横ばいもしくは減少傾向にあると考えられる。
中国への出願数は激増している。この10年(2001~2010年)で中国への出願数は、年平均成長率22%で上昇している。2010年の出願数は約39万件であり、日本特許庁への出願数を上回った。居住者からの出願数は2000~2002年は約5割であったが、2008~2010年は約7割となり、中国国内の出願人からの出願が特に増加していることが分かる。
図表4-2-2(B)にPCT出願数を示した。PCT出願は各国・地域の特許官庁への特許出願の束と考えることができ、一つの出願で一括して指定した国・地域への出願が可能な点が特徴である。PCT出願数は、ここ数年横ばいの状況である。
(1991~2010年)
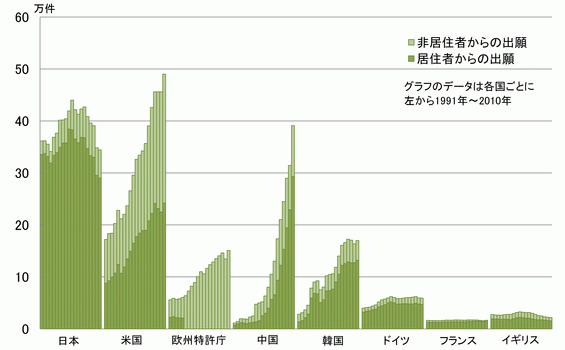
(1991~2010年)
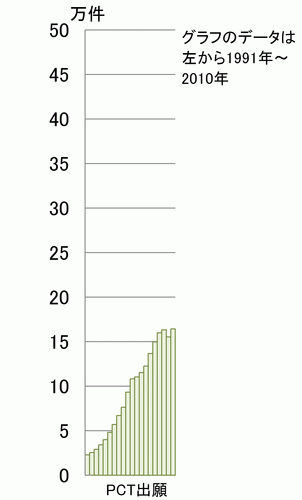
注:
1)出願数の内訳は、日本への出願を例に取ると、以下に対応している。「居住者からの直接出願」:日本に居住する出願人が日本特許庁に直接出願したもの。「非居住者からの直接出願」: 日本以外に居住(例えば米国)する出願人が日本特許庁に直接出願したもの。
2)欧州特許庁の「居住者からの出願」は1996年から値が掲載されていない。
資料:
WIPO,“Statistics on Patents”(Last update: December 2011)
参照:表4-2-2
次に主要国からの特許出願状況(図表4-2-2(C))を見る。ここでは出願数の内訳を、居住国への出願、非居住国への出願の2つに分けて示している。出願数として、各国・地域の特許官庁への直接出願、国内移行したPCT特許出願の両方をカウントしている。なお、欧州特許庁への出願は、すべての国で非居住国への出願としてカウントした。
ここで示す結果は2011年12月時点でのWIPO,“Statistics on Patents”による。この分析では、複数の出願人がいる場合、第1番目の出願人(applicants又はassignee)が属している国を用いて、各国のシェアを計算している。たとえば、日本(第1番目)と米国(第2番目)の出願人による共同出願の場合、日本のみがカウントされる。
日本、米国、中国、韓国からの出願は居住国への出願数が、非居住国への出願数より多い。日本からの全出願数のうち、約6割が居住国(日本特許庁)への出願である。
国内への特許出願を増加させている中国であるが、海外への出願数は1万4千件と、まだ少ない。
居住国への出願数の推移に注目すると、日本は近年減少しており、ピーク時(2000年)の約38万件の75%程度の出願数となっている。中国は増加が著しい。米国、韓国は2007年までは増加していたが、近年は頭打ちとなった。ドイツ、フランス、イギリスにおける居住国への出願数は、ほぼ横ばいか若干減少傾向にある。これまで居住国の特許官庁へなされていた特許出願の一定数が、欧州特許庁へなされるようになったことが、この要因の一つと考えられる。
非居住国への出願数に注目すると、日本からの出願数は、米国と並んで世界トップレベルにある。日本や米国からの出願数は2008年までは増加基調であったが、ここ数年は横ばいで推移している。
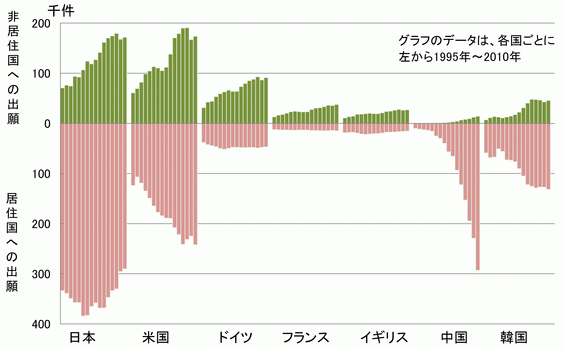
注:
1)出願数の内訳は、日本からの出願を例に取ると、以下に対応している。「居住国への出願」:日本に居住する出願人が日本特許庁に直接出願したもの。「非居住国への直接出願」:日本に居住する出願人が日本以外(例えば米国特許商標庁)に出願したもの。
2)各国ともEPOへの出願数を含んでいる。
3)国内移行したPCT出願件数を含む。
資料:
WIPO,“Statistics on Patents”(Last update: December 2011)
参照:表4-2-2
4.2.2主要国から三極特許庁への特許出願の状況
特許出願数の国際比較を困難にしている点の一つが、特許は属地主義であり、出願人が発明を権利化したいと考える複数の国に対して出願がなされる点である。一般に、ある国Aへの出願を考えると、国Aからの出願が最も大きくなる傾向(ホームアドバンテージ)がある。この点を考慮し、国際比較可能性を向上させるために、ここでは主要国から日本特許庁、欧州特許庁、米国特許商標庁の三極への出願状況を分析した。
2010年における世界の特許出願数は図表4-2-1でみたように、約200万件である。このうち、三極特許庁(日本特許庁、欧州特許庁、米国特許商標庁)への出願数は約半分を占めている。なお、近年、中国や韓国への特許出願数が急激に増加しており、世界における三極特許庁の重みは減少傾向にある。
図表4-2-3に日本特許庁、欧州特許庁、米国特許商標庁への特許出願における主要国のシェアを示す。ここで示す結果は2011年12月時点でのWIPO,“Statistics on Patents”による。この分析では、複数の出願人がいる場合、第1番目の出願人(applicants又はassignee)が属している国を用いて、各国のシェアを計算している。たとえば、日本(第1番目)と米国(第2番目)の出願人による共同出願の場合、日本のみがカウントされる。
日本特許庁への出願の各国シェア(図表4-2-3(A))を見ると日本のシェアが圧倒的であり2008~2010年で約84%である。米国は過去10年間、第2位のシェアを継続しているが、そのシェアは10%に届かない。ドイツは第3位のシェア(2008~2010年で約2.0%)である。韓国からの出願数は約1.4%(2008~2010年)で、ドイツに次ぐシェアである。
欧州特許庁への出願の各国シェア(図表4-2-3(B))を見ると、日本は米国とドイツに次ぐ存在感を示している。2008~2010年の特許出願における主要国のシェアを見ると、米国のシェアが約25%で第1位であり、ドイツが約18%、日本が約15%のシェアを持つ。これに、フランス(約6%)、イギリス(約4%)が続いている。韓国からの出願のシェアは約3%(2008~2010年)である。
米国特許商標庁への出願の各国シェア(図表4-2-3(C))を見ると、米国のシェアが最も大きい。米国のシェアは1996年から継続して、5割近くを保っている。日本は第2位のシェアを持ち、その割合は1996年から継続して約18%である。第3位のドイツのシェアは、2008~2010年で約6%である。韓国は順調にシェアを伸ばし、2008~2010年にはドイツに次ぐ第4位のシェア(約5%)を持つ。
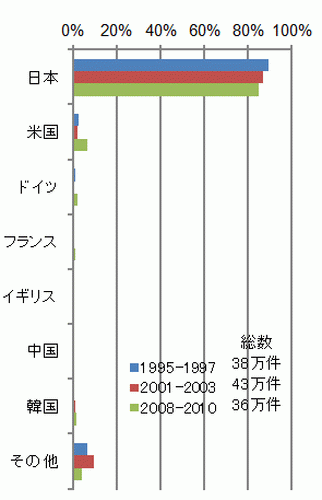
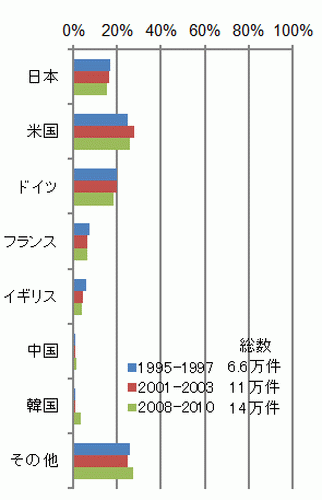
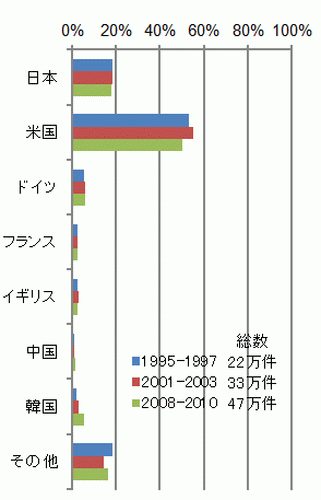
注:
件数は特許出願日に基づく。国は第1出願人の居住国である。3年平均の値。
資料:
WIPO,“Statistics on Patents”(Last update: December 2011)
参照:表4-2-3
4.2.3技術分野毎の特許出願状況
次に、技術分野毎に特許出願の状況を分析した結果について述べる。技術分野毎の国際比較を行うために、欧州特許庁への出願状況、米国特許商標庁への登録状況、PCT国際出願の状況を分析した。分析の対象とした技術分野は、バイオテクノロジー、再生可能エネルギー、情報通信技術、ナノテクノロジーの4技術分野である。
バイオテクノロジー、情報通信技術に対応する特許出願は、国際特許分類を用いて抽出した。同じ定義がOECDの特許分析でも用いられている。
ナノテクノロジーについては、欧州特許庁によるY01Nという分類を用いた。本分析では、欧州特許庁への特許出願、米国特許商標庁への登録特許、PCT特許出願の中で、Y01Nタグが付与されているものを分析対象とした。
再生可能エネルギーについては、欧州特許庁によるクリーンエネルギー関連技術の特許分類(Y02E)の中に含まれるY02E1を用いた。Y02E1には、風力、太陽光、地熱、水力、海洋を用いた再生可能エネルギーが分類されている。
なお、日本特許庁への特許出願については、特許データベースの接合上の問題から、ナノテクノロジー特許出願や再生可能エネルギー特許出願の抽出精度が低いために分析対象外とした。
(1)欧州特許庁への分野別特許出願状況
欧州特許庁への技術分野別の出願状況をみると、日本はナノテクノロジーや情報通信技術におけるシェアが大きい。ナノテクノロジーのシェアは1998~2000年では約30%近くあったが、2008~2010年では約18%となった。日本のバイオテクノロジーのシェアは10%程度で、全体としての日本シェアよりも小さい。再生可能エネルギーについても、1998~2000年には約30%であったシェアが、2008~2010年には約12%にまで減少している。
米国はバイオテクノロジーやナノテクノロジー、ドイツでは再生可能エネルギー、イギリスはバイオテクノロジーや再生可能エネルギーのシェアが相対的に大きい。韓国は、ここ10年間で大きくシェアを伸ばしている。特に情報通信技術やナノテクノロジーのシェアが大きいのが特徴である(図表4-2-4)。
中国はシェアを増やしつつあるが、他の6カ国と比べると存在感は小さい。
(2)米国特許商標庁の登録特許の分野別状況
米国特許商標庁における登録特許の技術分野別状況をみると、欧州特許庁の場合と同じく、日本はナノテクノロジーや情報通信技術におけるシェアが大きい。2008~2010年におけるナノテクノロジーのシェアは約26%である。再生可能エネルギーについては、1998~2000年には約29%であったシェアが、2008~2010年には約14%にまで減少している。
ドイツは再生可能エネルギー、イギリスはバイオテクノロジーや再生可能エネルギーのシェアが相対的に大きい。韓国については、特に情報通信技術やナノテクノロジーのシェアの伸びが大きいことが分かる(図表4-2-5)。
(3)PCT国際出願の分野別状況
PCT国際出願の状況をみると、1998~2000年に比べて、日本シェアが全体的に増加している。海外への特許出願の手段として、各国特許庁への直接出願とPCT国際出願を通じた出願の2通りの方法がある。各国からのPCT国際出願数をみると、1998~2000年から2008~2010年の間に日本からの出願は4倍に増えているのに対して、米国は1.7倍、ドイツは1.8倍となっている。つまり、各国と比べて日本からのPCT国際出願による海外への特許出願の増加が大きい。このことが、1998~2000年に比べて、日本シェアが増加している理由と考えられる。
大まかなポートフォリオの構造は、欧州特許庁への分野別特許出願の状況とほぼ同じとなっている。欧州特許庁、米国特許商標庁、PCT国際出願のいずれにおいても、再生可能エネルギーにおける日本のシェアは低下傾向である。
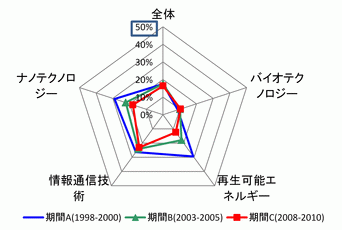
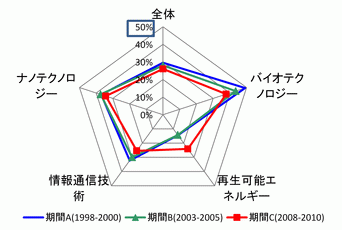
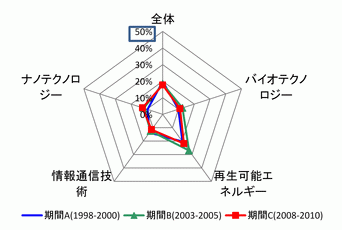
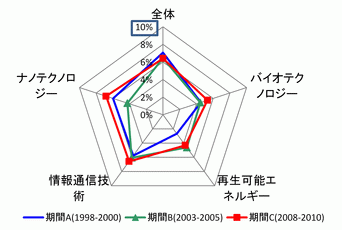
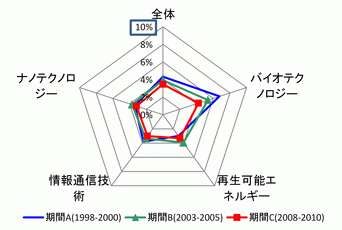
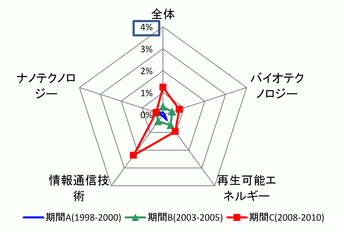
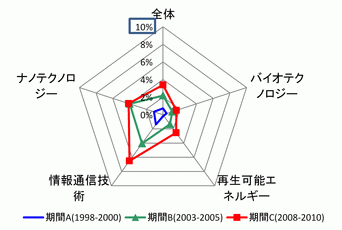
注:
1)公開公報数については、公開公報(A1, A2)をカウントした。公開日でカウントした。主要国のシェアは3年間の平均。
2)情報通信、バイオテクノロジーの技術分類には国際特許分類を使用。ナノテクノロジーの技術分類にはY01Nを使用。再生可能エネルギーの技術分類にはY02E1を使用。
3)出願人の割合については、出願人ごとに分数カウントをしてもとめた。
資料:
PATSTAT(2011年10月バージョン)に基づき科学技術政策研究所で集計。
参照:表4-2-4
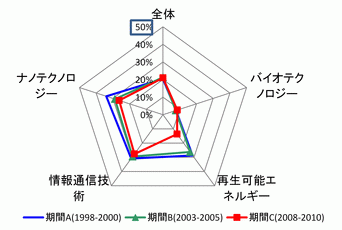
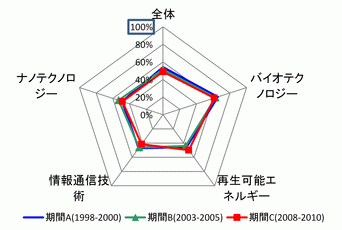
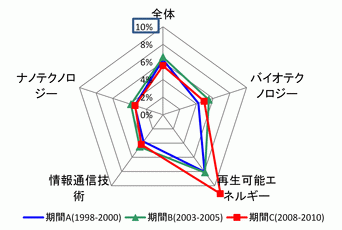
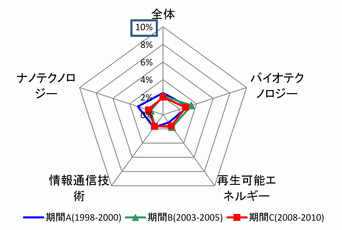
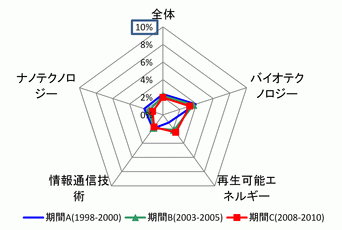
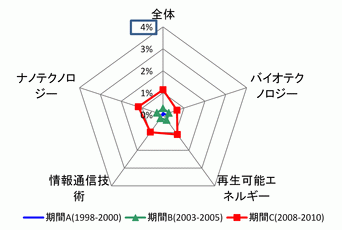
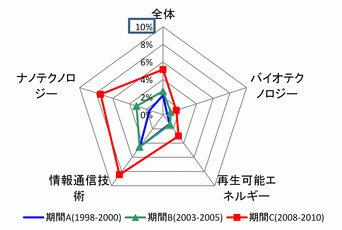
注:
1)登録日でカウントした。主要国のシェアは3年間の平均。
2)情報通信、バイオテクノロジーの技術分類には国際特許分類を使用。ナノテクノロジーの技術分類にはY01Nを使用。再生可能エネルギーの技術分類にはY02E1を使用。
3)発明者の割合については、発明者ごとに分数カウントをしてもとめた。
資料:
PATSTAT(2011年10月バージョン)に基づき科学技術政策研究所で集計。
参照:表4-2-5
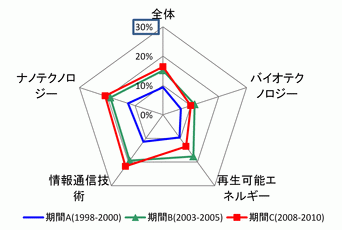
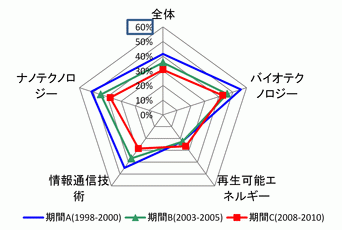
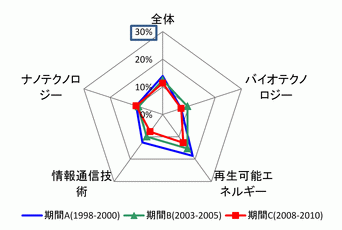
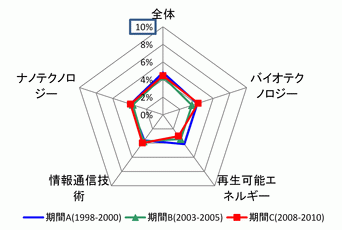
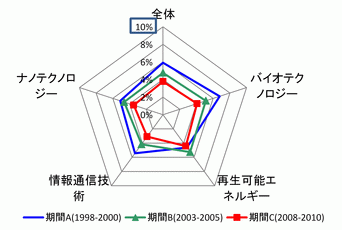
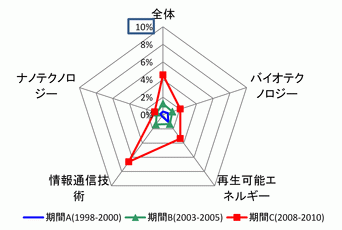
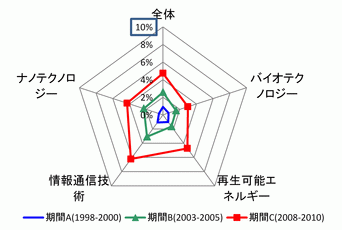
注:
1)公開公報数については、公開公報(A1, A2)をカウントした。公開日でカウントした。主要国のシェアは3年間の平均。
2)情報通信、バイオテクノロジーの技術分類には国際特許分類を使用。ナノテクノロジーの技術分類にはY01Nを使用。 再生可能エネルギーの技術分類にはY02E10を使用。
3)出願人の割合については、出願人ごとに分数カウントをしてもとめた
資料:
PATSTAT(2011年10月バージョン)に基づき科学技術政策研究所で集計。
参照:表4-2-6
コラム:クリーンエネルギー関連技術の特許出願状況
欧州特許庁では、世界各国の特許文献のなかで、クリーンエネルギーに関連するものを抽出・分類したY02Eという特許分類を2010年に新たに導入した。技術の分類には専門的な知識を要するが、欧州特許庁は特許文献の分類にあたって、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)など外部の専門家の協力を得ることで、その信頼性を高めている。ここでは、このY02E分類を用いて、特許出願からみたクリーンエネルギー関連技術における各国の状況を分析した結果を紹介する。
主要国からのクリーンエネルギー関連特許出願を比較するために、ここではパテントファミリーによる分析を行った。パテントファミリーとは優先権によって直接、間接的に結び付けられた特許出願の束である。パテントファミリーの定義にはさまざまなものが存在するが、ここではINPADOC(欧州特許庁が作成している世界各国の特許のデータベース)のパテントファミリーのなかで、日本特許庁、欧州特許庁、米国特許商標庁の全てに出願されたものを分析対象とした。データベースとして欧州特許庁のPATSTAT(2011年10月バージョン)を使用した。パテントファミリーのカウントの際には、OECD Patent Statistics Manualに準拠し、最も早い優先日、発明者の居住国を用い、国を単位とした分数カウントを行った。
なお、ここで分析対象としたパテントファミリーは、日本特許庁、欧州特許庁、米国特許商標庁の全てに出願されて初めて計測対象となる。PCT国際出願された特許出願が国内移行するまでのタイムラグは30カ月に及ぶ場合があり、パテントファミリー数が安定し分析可能な最新値は2007年である。
Y02E分類は図表4-2-7に示した7つのメイングループから構成されている。例えばY02E1には、再生可能エネルギー源からのエネルギー生成にかかわる技術が分類されている。Y02E1は、さらに太陽光、風力、地熱、水力、海洋といったサブグループに細分される。
Y02Eの6つのメイングループについて、パテントファミリー数の変化を図表4-2-8に示した。なお、Y02E7についてはパテントファミリー数が少ないため分析対象から除いた。もっともパテントファミリー数が多いのは、温室効果ガス排出削減に潜在的・間接的に寄与する技術(バッテリ技術・蓄熱技術、燃料電池など)であり、2007年のパテントファミリー数は約1,300件である。パテントファミリー数は1990年代半ばから急増を見せ、1990年代初頭と比べて約4.5倍となっている。おなじ期間に、全体のパテントファミリー数は約1.6倍の増加なので、それと比べて増加が顕著であることが分かる。サブグループレベルでみると燃料電池の増加が特に顕著である。
次にパテントファミリー数が多いのが、再生可能エネルギー源からのエネルギー生成にかかわる技術(太陽光、風力、地熱、水力、海洋など)であり、2007年のパテントファミリー数は約600件である。パテントファミリー数は1990年代初頭と比べて約7倍となっている。サブグループレベルで見ると太陽光によるエネルギー生成がもっともファミリー数が多い。
パテントファミリー数の増加に注目すると、非化石燃料の生産技術(バイオ燃料、廃棄物燃料など)も、1990年代初頭と比べて約9倍となっているが、パテントファミリーの絶対数は少ない(2007年で108件)。原子力によるエネルギー生成については、パテントファミリー数に大きな変化はない。
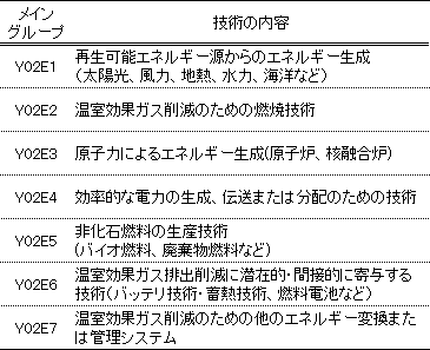
資料:
欧州特許庁PATSTAT(2011年10月バージョン)に基づき科学技術政策研究所で作成。
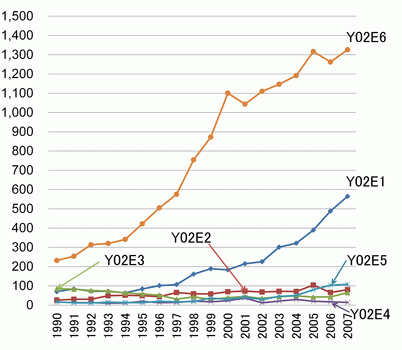
注:
クリーンエネルギーの技術分類にはY02Eを使用。INPADOCのパテントファミリーで、日本、欧州、米国の全てに出願されたものを分析対象とした。パテントファミリーのカウントの際には、最も早い優先日、発明者の居住国を用い、国を単位とした分数カウントを行った。
資料:
欧州特許庁PATSTAT(2011年10月バージョン)に基づき科学技術政策研究所で集計。
参照:表4-2-8
次に発明者でみた各国のシェアを示す。ここでは2003~2007年の5年間を優先日とするパテントファミリーを分析対象とした。この5年間の全パテントファミリー数は約30万件であり、その中での日本のシェアは32%である。これを基準に各メイングループにおける日本のシェアをみると、温室効果ガス排出削減に潜在的・間接的に寄与する技術、効率的な電力の生成、伝送または分配のための技術において、相対的にシェアが大きいことが分かる(図表4-2-9(A))。
温室効果ガス排出削減に潜在的・間接的に寄与する技術の細目をみると(図表4-2-9(B)参照)、日本のシェアはバッテリ技術・蓄熱技術(46%)、燃料電池(48%)のいずれでも高い。いずれの技術についても、米国のシェアが日本に次いで高いが、バッテリ技術・蓄熱技術については韓国のシェアも10%を超えている。
再生可能エネルギー源からのエネルギー生成については、日本のシェアはパテントファミリー全体と同じであるが、細目に注目すると技術による違いがみられる(図表4-2-9(C))。
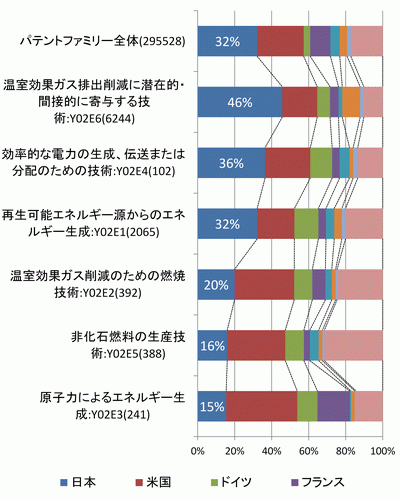
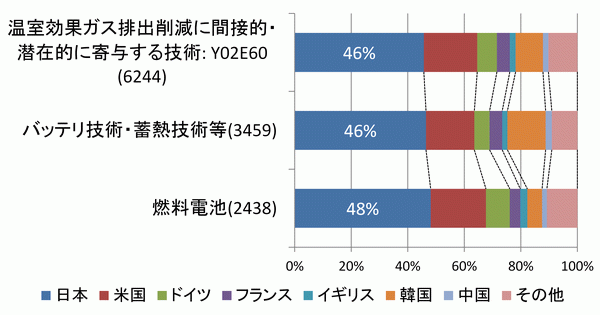
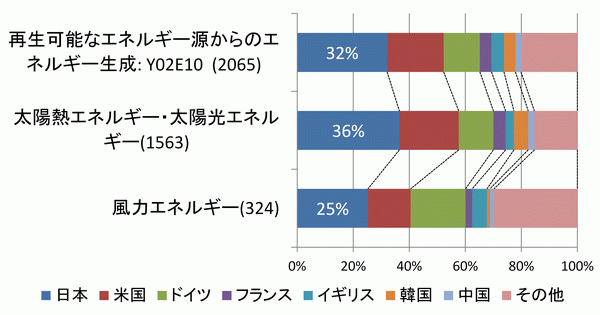
注:
1)図表4-2-8と同じ。
2)前年からY02Eの付与の仕方が一部変わっているので、科学技術指標2011の結果と一部異なる。
資料:
図表4-2-7と同じ。
参照:表4-2-9
太陽熱エネルギー・太陽光エネルギーにおける日本のシェアは36%とやや高く、風力エネルギーのシェアは25%と相対的に小さい。風力エネルギーではドイツも高いシェア(20%)を持つ。
原子力によるエネルギー生成、非化石燃料の生産技術では、日本のシェアは相対的に小さい。フランスのシェアは、原子力によるエネルギー生成で、突出して大きくなっているのが特徴である。
以上のように、クリーンエネルギー関連技術の中でも、バッテリ技術・蓄熱技術、燃料電池、太陽熱エネルギー・太陽光エネルギーにおいて、日本のシェアは、他の技術と比べて相対的に高くなっている。ただし、比較的最近の欧州特許庁への出願状況(2008~2009年)をみると、バッテリ技術・蓄熱技術、太陽熱エネルギー・太陽光エネルギーでは、5年前と比べると日本のシェアが低下傾向である。太陽熱エネルギー・太陽光エネルギーのシェアの低下が特に著しい(26%→16%)。燃料電池については、欧州特許庁における日本シェアが増加傾向にある。
近年の太陽電池市場が、他国のメーカーに席巻されているように、技術を産業競争力に結び付ける点での多くの課題も生じている。クリーンエネルギー関連技術は、世界的にも研究開発が活発化していることから、継続した状況の把握が必要である。
(伊神 正貫)

