近年、研究開発への投資に対する説明責任が強く求められるようになっており、研究開発におけるアウトプットの把握も大きなテーマとなっている。本章では、研究開発活動のアウトプットとして計測可能な科学論文と特許に着目し、世界及び主要国の活動の特徴や変化について紹介する。
4.1論文
ポイント
- 世界の研究活動のアウトプットである論文量は一貫して増加傾向にある。
- 研究活動自体が単一国の活動から複数国の絡む共同活動へと様相を変化させている。世界で国際共著論文が増えており、「世界の論文の生産への関与度(整数カウント)」と「世界の論文の生産への貢献度(分数カウント)」に差が生じるようになった。
- 日本の論文数(2009-2011年の平均)は、「世界の論文の生産への関与度」では、米国、中国、ドイツ、イギリスに続き世界第5位である。一方、「世界の論文の生産への貢献度」では、日本は米国、中国に次ぐ3位であるが、4位ドイツ、5位イギリスと僅差である。
- 1990年代後半より、中国が「世界の論文の生産への関与度」と「世界の論文の生産への貢献度」ともに高めており、2000年代後半では世界第2位のポジションとなっている。
- 日本国内の分野バランスをみると、化学のシェアが減り、臨床医学のシェアが増加している。
- 一方、各分野での世界シェアによる分野ポートフォリオをみると、日本は物理学、化学、材料科学のウェートが高く、計算機・数学、環境・地球科学が低い。
- 2011年の国際共著率はドイツ52%、イギリス54%、フランス54%に対し、米国35%、日本27%である。
4.1.1世界の研究活動の量的及び質的変化
(1)論文数の変化
図表4-1-1は、全世界の論文量の変化である。トムソン・ロイター社のデータベースでは、論文の書誌情報の見直しが適時反映されるようになっている。そのため、今回の図表と前回の「科学技術指標2011」(2011.8)との数値は一致しないことに留意頂きたい。
1980年代前半に比べ現在は、世界で発表される論文量は2倍以上になっており、世界で行われる研究活動は一貫して量的拡大傾向にある。なお、この間において、分析に用いたデータベースに収録されるジャーナルは順次変更されると共に、ジャーナルの数も拡大してきている。論文数の拡大にはこの要因の寄与も含まれている。
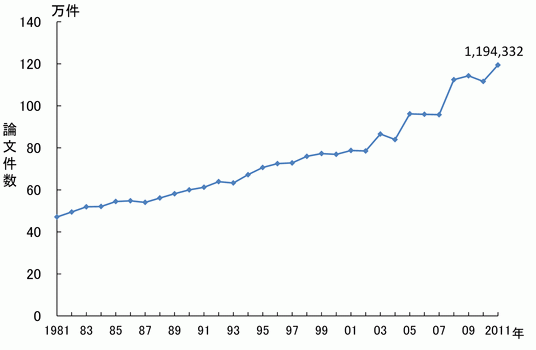
注:
article, letter, note, reviewを分析対象とし、整数カウントにより分析
資料:
トムソン・ロイター社 Web of Science (SCIE, CPCI:Science)を基に、科学技術政策研究所が集計。
参照:表4-1-1
(2)論文生産形態の変化
世界で行われる研究活動が量的拡大を示す一方で、研究活動のスタイルが大幅に変化している。図表4-1-2に、主要国の論文における論文共著形態の変化を示した。①単一機関論文(単一の機関に所属する著者による論文)、②国内機関間共著論文(同一国の複数の機関に所属する著者による論文)、③国際共著論文(異なる国の機関に所属する著者による論文)の3種類に分類した。
単一機関論文の割合が減少し、国内機関間共著論文や国際共著論文が増加していることが分かる。まず、1980年代では、単一機関内の論文が約8割を占めていたが、その後国内における機関間の共著論文や、国のボーダーを超えた国際共著論文が増加しており、機関や国といった枠組みを超えた形で知識生産活動が行なわれていると言える。2011年時点では、単一機関論文が42.5%、国内機関間共著論文が35.1%、国際共著論文が22.3%である。
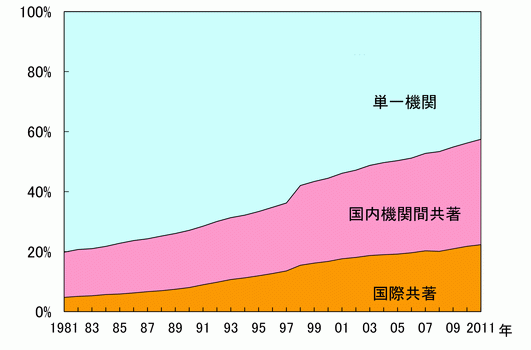
注:
article, letter, note, reviewを分析対象とし、整数カウントにより分析
資料:
トムソン・ロイター社 Web of Science (SCIE, CPCI:Science)を基に、科学技術政策研究所が集計。
参照:表4-1-2
また、国際共著論文は、国際的な研究の協力や共同活動によりつくられる成果であるため、分野ごとの背景に依存すると考えられる。例えば、大型研究施設で、各国で保有することが現実的に不可能な場合、当該大型研究施設設置国を中心とした共同研究が促進される。図表4-1-3は分野ごとの国際共著論文の割合の変化である。
いずれの分野においても、1980年代前半から現在に至るまで、国際共著論文比率は上昇基調である。環境・地球科学では31.6%、物理学では30.6%であり、他分野に比べ国際共著論文比率が高いことが分かる。一方、臨床医学は、18.5%であり、国際共著論文比率が一番低い分野である。
(A)比率の推移
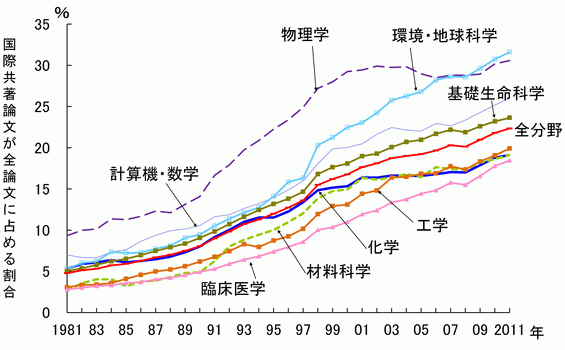
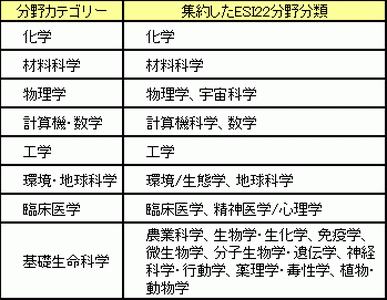
注:
1)articl,letter,note,reviewを分析対象とし、整数カウントにより分析をした。
2)(A)の分野分類は(B)を使用。
3)(B)の分野分類はWoSデータベース収録論文をEssential Science Indicators(ESI)のESI22分野分類を用いて再分類し、分野別分析を行なっている。雑誌の分類は、http://www.in-cites.com/journal-list/index.html(2011 December)による。分析対象は、経済学・経営学、複合領域、社会科学・一般を除くESI19分野分類とする。
資料:
トムソン・ロイター社 Web of Science (SCIE, CPCI:Science)を基に、科学技術政策研究所が集計。
参照:表4-1-3
4.1.2研究活動の国別比較
(1)「世界の論文の生産への関与度」と「世界の論文の生産への貢献度」による国際比較
国の持っている科学研究力を定量化する「分かりやすい指標」として、量を測る場合は論文数が用いられ、一方、質を示す場合には被引用数やTop10%補正論文数が用いられる。Top10%補正論文とは、論文の被引用数(2011年末の値)が各分野の上位10%に入る論文の抽出後、実数で論文数の1/10となるように補正を加えた論文数を指す。このように分野毎に算出するのは、分野毎に平均被引用数がかなり異なるため、その違いを標準化するためである。分野は、図表4-1-3に準ずる。
それらの計算を行う方法として、整数カウント法と分数カウント法がある(図表4-1-4)。整数カウント法では「世界の論文の生産への関与度」を、分数カウント法では「世界の論文の生産への貢献度」を測ると考えられる。
図表4-1-5は、整数カウント法と分数カウント法による各国・地域の論文数とTop10%補正論文数及び世界ランクを示した。カウント方法により各国の論文数が異なり、ランクが入れ替わることがある。
論文数の上位5ヶ国・地域をみてみると、1989-1991年には、整数カウント法と分数カウント法で、各国の世界ランクに差がみられないが、2009-2011年では、整数カウント方法であれば米、中、独、英、日となるが、分数カウント方法であれば米、中、日、独、英となり、日本の位置づけが変わることが分かる。これは、国際共著論文が増加したこと、また国毎の国際共著率の差が均一でないことによる。図表4-1-11に示すように国際共著率が高い国と低い国の差が大きくなっており、ヨーロッパでは国際共著率が高いが、日米では低めの傾向が出ている。
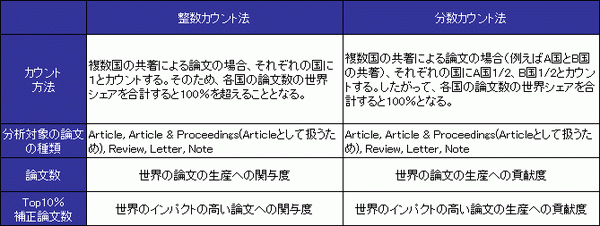
注:
Top10%補正論文数とは、被引用回数が各年各分野で上位10%に入る論文の抽出後、実数で論文数の1/10となるように補正を加えた論文数を指す。詳細は、科学技術政策研究所の「科学研究のベンチマーキング2011」(調査資料204)の2-2 (7) Top10%補正論文数の計算方法を参照のこと。分野は、図表4-1-3(B)の注釈に準ずる。被引用数は、2011年末の値を用いている。
参照:表4-1-4
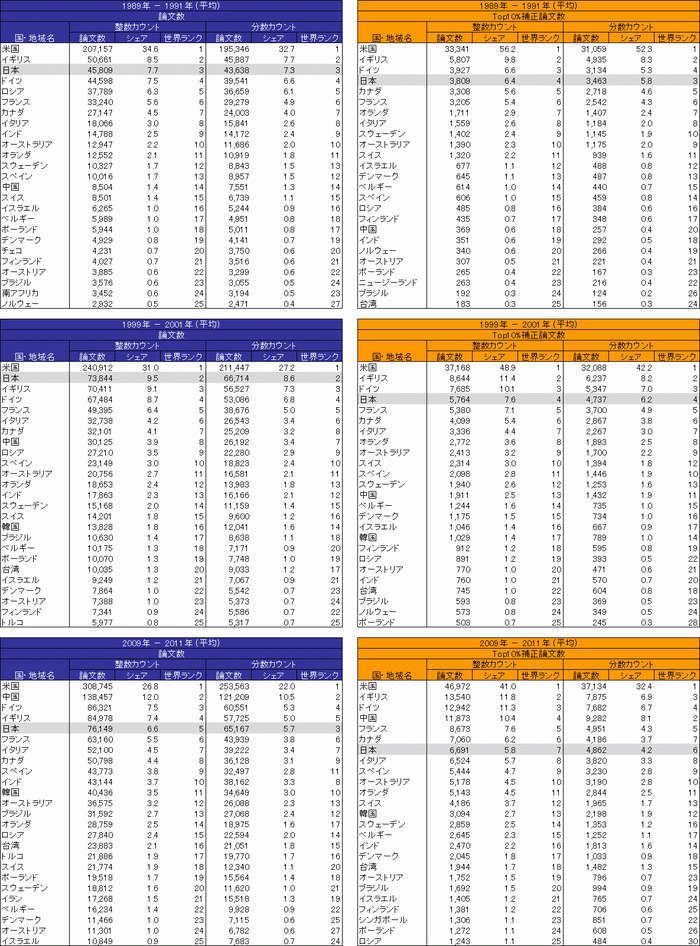
資料:
トムソン・ロイター社 Web of Science (SCIE, CPCI:Science)を基に、科学技術政策研究所が集計。
参照:表4-1-5
(2)論文数シェアの比較
図表4-1-6では、まず各国の研究活動の量的状況を把握するため、論文数の各国シェアを整数カウント法で求めた「世界の論文の生産への関与度」と、分数カウント法で求めた「世界の論文の生産への貢献度」を示す。「世界の論文の生産への関与度」を見ると、米国は、他国を大きく引き離し、論文生産量の多い国であると言えるが、1980年代からゆるやかな下降基調が続いている。米国の背中を、イギリス、日本、ドイツ、フランスが追いかける状態が1990年代中盤まで続いた。しかし、1990年代後半より、中国が急速に論文生産量を増加させている。日本は、2010年(2009-2011年の平均)において、米国、中国、ドイツ、イギリスに次ぐ、世界第5位のポジションである。
一方、「世界の論文の生産への貢献度」では、1995年以降、日本は世界第2位となり約10年間ポジションを維持していたが、中国に追い越され2010年(2009-2011年の平均)では世界第3位である。また、日本と、ドイツやイギリスとの差が縮まりつつある。
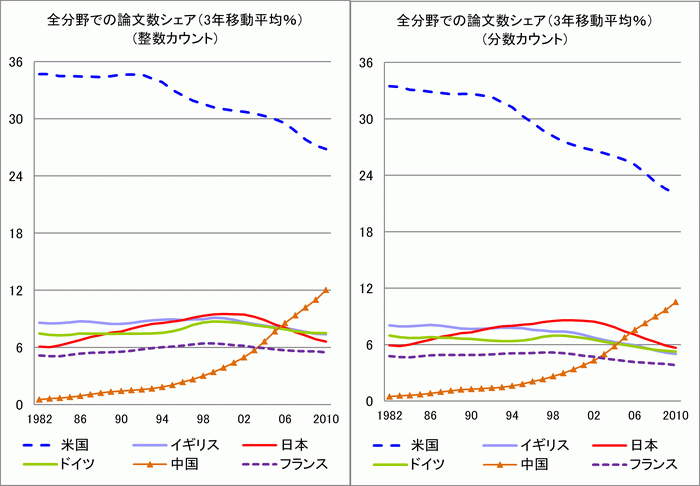
注:
全分野での論文シェアの3年移動平均(2010年であれば2009、2010、2011年の平均値)。(A)は整数カウント、(B)は分数カウントである。
資料:
トムソン・ロイター社 Web of Science (SCIE, CPCI:Science)を基に、科学技術政策研究所が集計。
参照:表4-1-6
(3)Top10%補正論文数シェア及び被引用数シェアの比較
次に、図表4-1-7では、各国の研究活動の質的状況を把握するため、Top10%補正論文数の各国シェアを整数カウント法で求めた「世界のインパクトの高い論文への関与度」と、分数カウント法で求めた「世界のインパクトの高い論文の生産への貢献度」を示す。
「世界のインパクトの高い論文への関与度」では、イギリスやドイツは1990年以降シェアを上昇させており、日本に大差をつけている。日本は、米英独中仏加に次ぐ、世界7位と順位を落としている。
一方、「世界のインパクトの高い論文の生産への貢献度」では、米国やイギリスは20年間で下降基調であり、ドイツは1990年以降シェアをゆるやかに上昇させたが、2000年代は横ばい状態である。
日本は、2000年代に入ると急激にシェアが低下しており、米中英独仏に次ぐ、世界6位である。
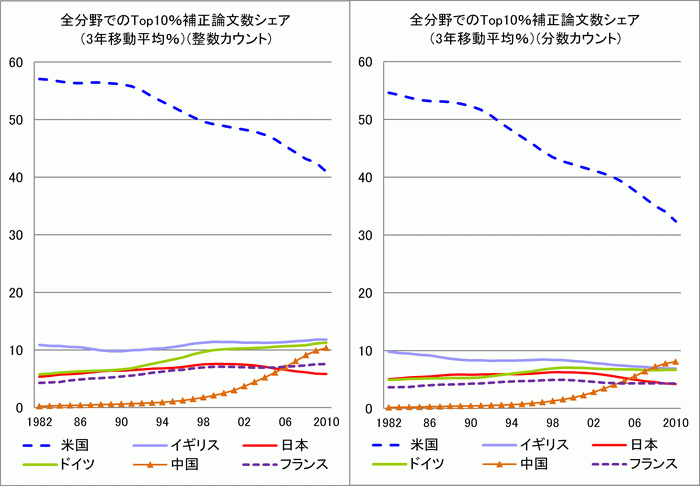
注:
全分野での論文シェアの3年移動平均(2010年であれば2009、2010、2011年の平均値)。(A)は整数カウント、(B)は分数カウントである。
資料:
トムソン・ロイター社 Web of Science (SCIE, CPCI:Science)を基に、科学技術政策研究所が集計。
参照:表4-1-7
4.1.3主要国の研究活動の特性
(1)世界及び主要国内の分野別論文数割合
研究の中には、様々な分野が包含されており、論文数や被引用回数は、それらの分野ごとの研究活動において論文生産がどの程度重視されているか、研究者数が多いか少ないか、一論文が引用する過去の論文数が平均的に多いか少ないかなどの影響を受ける。したがって、国の比較を行なう場合、論文や被引用回数の総数のみを見るのではなく、分野ごとの研究活動を把握することも重要である。なお、ここでは世界及び各国内の分野毎の割合を各国の関与度の観点から求めるため、整数カウント法を用いる。
まず、図表4-1-8では、全世界の論文に占める各分野の論文数割合の推移を示す。1981年と2011年を比べると、基礎生命科学は4.5ポイント、化学は1.4ポイント、物理学は0.7ポイント減少している一方、材料科学は2.0ポイント、工学は2.0ポイント、環境・地球科学は1.4ポイント、計算機・数学は1.3ポイント、臨床医学は0.6ポイント割合を伸ばした。
細かな動きはあるものの、基礎生命科学および臨床医学といった生命科学系の割合が約半分を占めている特徴は変わっていない。
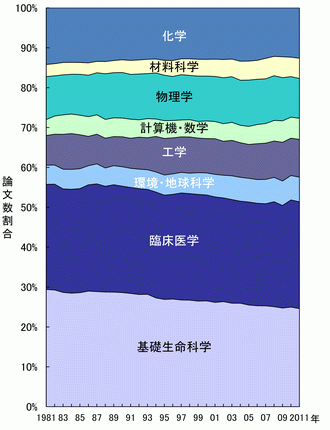
注:
分野は図表4-1-3(B)の注釈に準ずる。
資料:
トムソン・ロイター社 Web of Science (SCIE, CPCI:Science)を基に、科学技術政策研究所が集計。
参照:表4-1-8
次に主要国の内部構造をみるために、図表4-1-9では、主要国の論文における各分野のシェアの変化を示す。日本は、1980年代前半は、基礎生命科学、化学、物理学の占める割合が大きかったが、1981年と2010年を比較すると、化学は10.2ポイント、基礎生命科学は5.1ポイント減っている。一方、11.4ポイントの割合を増加させた臨床医学に加え、環境・地球科学や材料科学は拡大傾向にある。米国は、1980年代以降、基礎生命科学が4.2ポイント減少し、臨床医学が3.6ポイント増加している。ドイツは、化学や基礎生命科学の占める割合が減り、環境・地球科学や物理学、臨床医学の占める割合がやや増加した。フランスは、環境・地球科学、工学、計算機科学の割合が増加し、臨床医学や基礎生命科学、化学の割合が減少した。イギリスでは、基礎生命科学と化学の割合が減り、環境・地球科学や物理学、臨床医学の割合が増加した。中国に関しては、生命科学系(基礎生命科学及び臨床医学)の占める割合が、他の主要国と比較して低い。
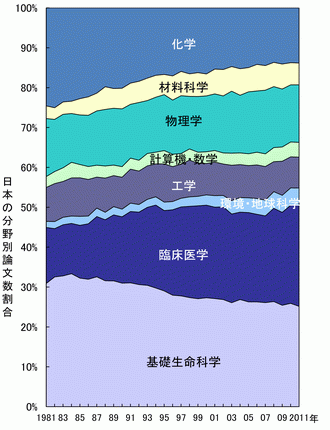
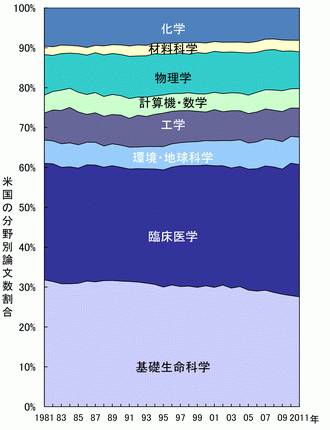
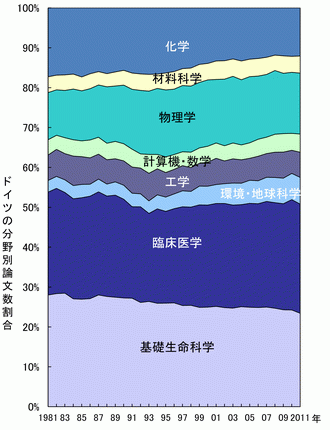
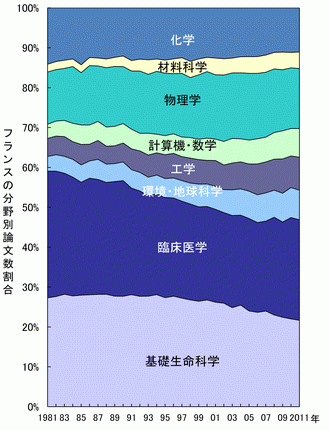
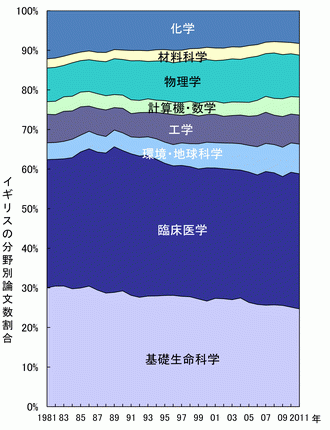
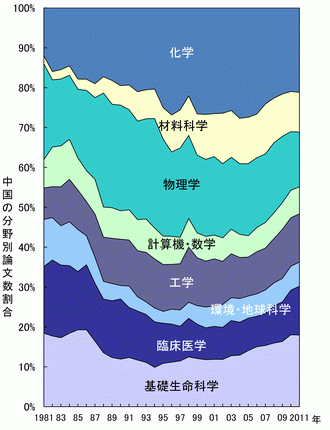
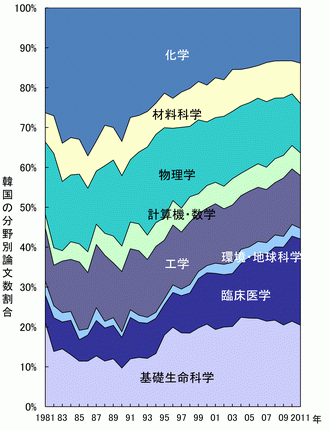
注:
分野は図表4-1-3(B)の注釈に準ずる。
資料:
トムソン・ロイター社 Web of Science (SCIE, CPCI:Science)を基に、科学技術政策研究所が集計。
参照:表4-1-9
(2)主要国における量的分野バランスと質的分野バランスの比較
図表4-1-10では、主要国の論文シェアとTop10%補正論文シェアの分野ポートフォリオ(2009-2011年)を作成し、比較を行なった。ここでは、世界及び各国内の分野の占める割合を関与度の観点から求めるため、整数カウント法を用いる。
論文シェアとTop10%補正論文シェアを比較すると、Top10%補正論文シェアが論文シェアより高い国(米国、イギリス、ドイツ、フランス)と、論文シェアよりTop10%補正論文シェアが低い国(日本、中国、韓国)に分けられる。Top10%補正論文シェアをみると、論文シェアでみる分野バランスより各国の強み弱みが強調される。
日本は物理学、化学、材料科学のウェートが高く、計算機・数学、環境・地球科学が低いというポートフォリオを有しているが、過去と比較してウェートの偏在度は低くなっている。図表4-1-9では、日本国内の論文に占める臨床医学のシェアは増加し、化学のシェアが減少していることが示されたが、世界の各分野の論文数に対してのシェアとなると、日本の場合は化学の方が臨床医学より高いことが分かる。
イギリスは臨床医学、環境・地球科学に強みがあり、ドイツとフランスは物理学に強みが見られる。中国は、特に材料科学、化学、物理学で論文シェアおよびTop10%補正論文シェアともに存在感を示している。
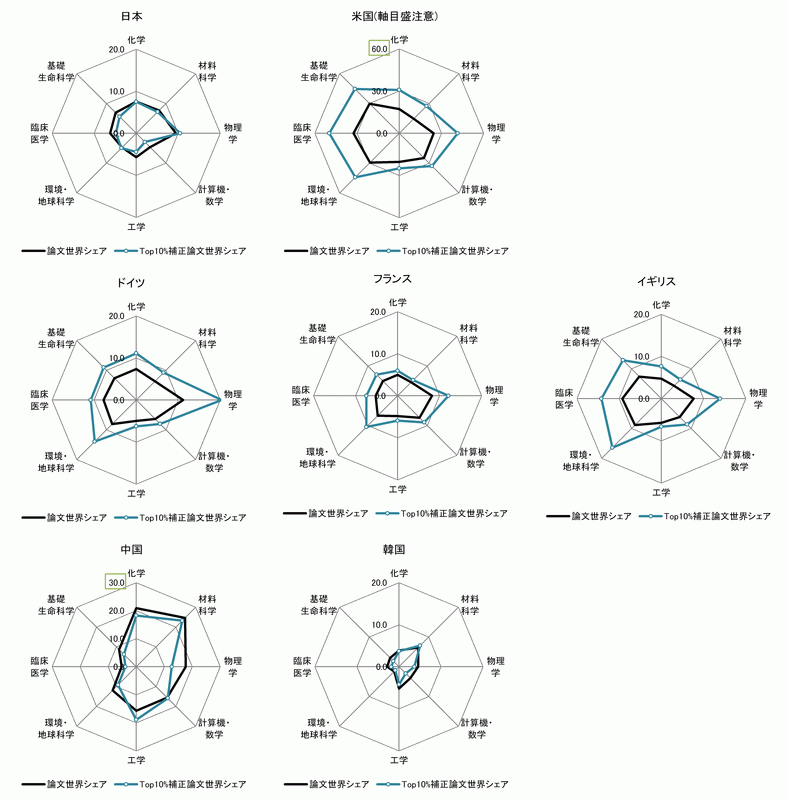
注:
article, letter, note, reviewを分析対象とし、整数カウントにより分析。分野は図表4-1-3(B)の注釈に準ずる。被引用数は、2011年末の値を用いている。
資料:
トムソン・ロイター社 Web of Science (SCIE, CPCI:Science)を基に、科学技術政策研究所が集計。
参照:表4-1-10
(3)主要国の論文生産形態の変化
図表4-1-11は、主要国における論文数の論文共著形態別割合の推移である。主要国の状況を比較すると、いずれの国においても国際共著論文の割合が増加している点は共通であるが、その割合は、2011年時点で日本27.3%、米国34.6%であるのに対し、欧州ではドイツ52.2%、フランス53.8%、イギリス53.8%と非常に高い。
一方、日本の特徴は、国際共著論文に加え、1980年代に比べ国内機関間共著論文の割合が20ポイントも増加していることであり、他国に比べ国内における研究機関間の関係が大きいことが分かる。
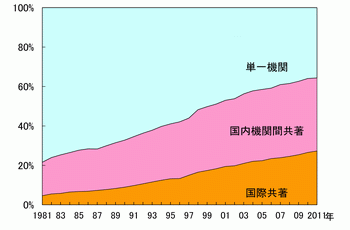
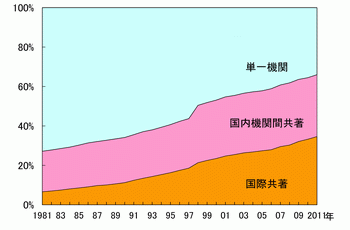
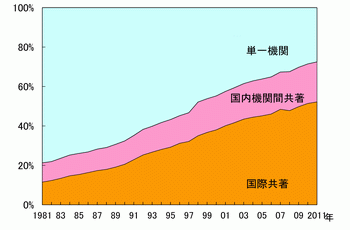
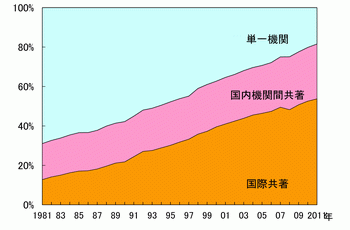
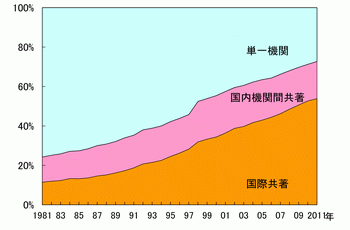
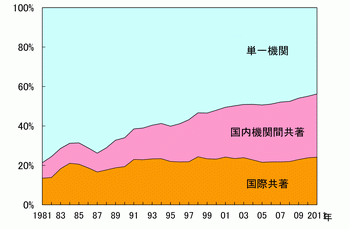
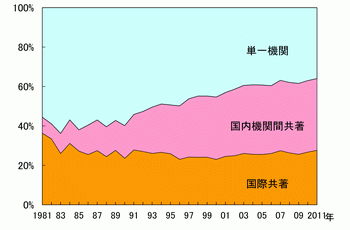
注:
article, letter, note, reviewを分析対象とし、整数カウントにより分析。
資料:
トムソン・ロイター社 Web of Science (SCIE, CPCI:Science)を基に、科学技術政策研究所が集計。
参照:表4-1-11



