
科学技術指標2013
科学技術・学術政策研究所 科学技術・学術基盤調査研究室
概要
「科学技術指標」は、我が国の科学技術活動を客観的・定量的データに基づき、体系的に把握するための基礎資料であり、科学技術活動を「研究開発費」、「研究開発人材」、「高等教育」、「研究開発のアウトプット」、「科学技術とイノベーション」の5つのカテゴリーに分類し、関連する多数の指標で我が国の状況を表している。今回の「科学技術指標2013」では、「研究開発のアウトプット」の構成を変更した。論文数のカウント方法の概念をより詳しく説明し、論文の質的観点から見たTop1%補正論文数についても新たに分析した。また、パテントファミリーを用いた特許出願数の国際比較を実施した。「科学技術とイノベーション」の章では、ミディアムハイテクノロジー産業の貿易額の推移といった指標を追加し、充実を図った。
今回の「科学技術指標2013」では、昨年版と比較して様々な指標で変化が見られた。近年、減少が続いていた日本の研究開発費総額は、前年度と比較して1.6%増加した。研究者の新規採用者数については、2009年をピークに減少し続けている。大学学部入学者、修士課程の入学者、博士課程入学者数は、いずれも2011、2012年度と連続して減少している。日本の論文数は、分数カウント法(論文の生産への貢献度)によると、世界第3位である。また、Top10%補正論文数は第6位であり、Top1%補正論文数では第7位である。また、各国の発明の数を国際比較するための指標であるパテントファミリーを用いた特許出願数では、日本は世界第1位である。
Japanese Science and Technology Indicators 2013
Research Unit for Science and Technology Analysis and Indicators
National Institute of Science and Technology Policy
ABSTRACT
"Science and Technology Indicators" is a basic resource for understanding Japanese science and technology activities based on objective, quantitative data. It classifies science and technology activities into five categories, R&D Expenditure; R&D Personnel; Higher Education; The Output of R&D; and Science, Technology, and Innovation. The multiple relevant indicators show the state of Japanese science and technology activities. Structure of the chapter of "Output of R&D" was changed in the Japanese Science and Technology Indicators 2013. A detailed explanation of the concept of the counting method is provided, and the adjusted number of top 1% highly cited papers in the world, which provides a qualitative perspective of the output, was newly analyzed. An international comparison was made on the number of patent applications using patent families. The "Science, Technology and Innovation" chapter has been enhanced with the addition of an indicator, i.e. transition in the export value of medium high technology industry.
Changes in various indicators are registered in the Japanese Science and Technology Indicators 2013 compared with the previous year. Total research and development expenditure in Japan, which has continued to decline in recent years, showed a 1.6% increase over the previous year. The number of newly-hired researcher has been trending downward since peaking in 2009. The number of people enrolling in undergraduate, masters and doctoral programs declined both in 2011 and 2012.
Looking at the number of papers produced in Japan, Japan was third according to the fractional counting method (degree of contribution in the production of papers in the world). As for the adjusted number of the top 10% and top 1% highly cited papers in the world, Japan ranked sixth and seventh, respectively. In the number of patent families, which is the indicator for international comparison of the number of inventions, Japan ranked number one in the world.
概 要

「科学技術指標」は、我が国の科学技術活動を客観的・定量的データに基づき、体系的に把握するための基礎資料であり、科学技術活動を「研究開発費」、「研究開発人材」、「高等教育」、「研究開発のアウトプット」、「科学技術とイノベーション」の5つのカテゴリーに分類し、関連する多数の指標で我が国の状況を表している。
今回の「科学技術指標2013」では、昨年版と比較して様々な指標で変化が見られた。本概要では、主に変化のあった指標、新しく掲載した指標などを中心に紹介する。
第1章:研究開発費
(1)研究開発費の国際比較
日本全体の研究開発費総額は2011年で17.4兆円である。前年と比較すると1.6%の増加であり、2008年から続いた減少は止まった。これは企業部門の研究開発費が2009年における大幅な減少から回復しつつあることが主な要因と考えられる。
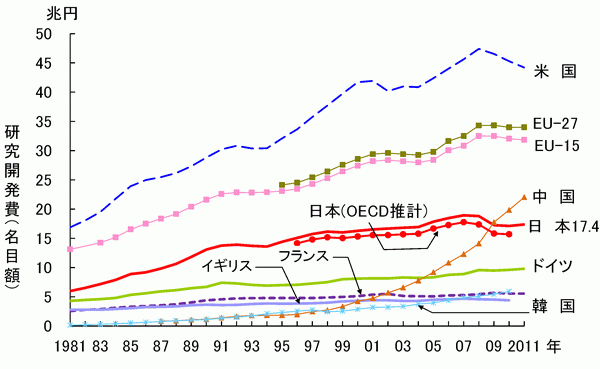
(2)日本の部門別の研究開発費の使用割合の推移
日本の部門別の研究開発費の使用割合を見ると、1990年代中期以降、「企業」部門が増加傾向にある一方で、「公的機関」部門は減少傾向があった。ただし、2009年以降は、「企業」部門の割合がそれまでよりも減少し、最近の2年間は「企業」部門の割合は回復傾向にある。
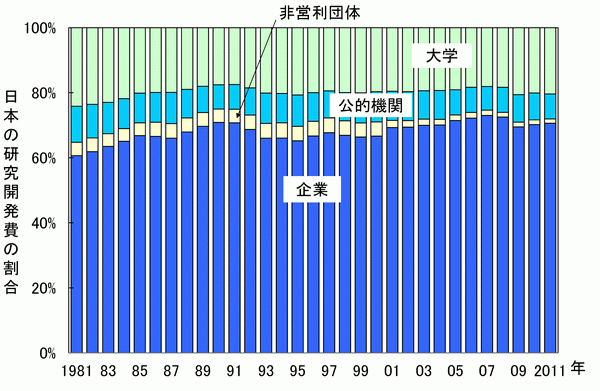
(3)主要国の政府の科学技術予算
2012年の日本の科学技術予算総額(当初予算)は3.7兆円である。長期的観点では、科学技術予算は増加傾向にあるが、2000年代に入ると、その伸びは鈍化している。
また、科学技術予算を国防関連の予算(国防用)とそれ以外の予算(民生用)に分類してみると、日本では、ほとんどが民生用科学技術予算で占められている。
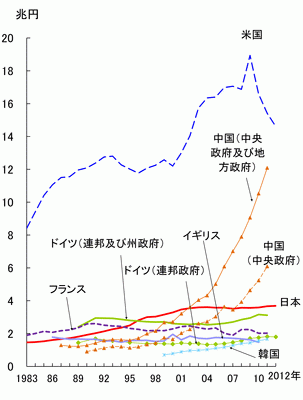
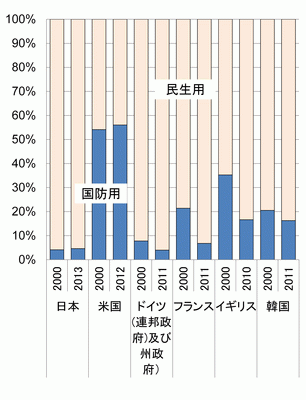
第2章:研究開発人材
(1)主要国の研究者の部門別内訳
主要国の研究者の部門別割合については、日本、米国、韓国では企業部門の研究者の割合が7割を超えている。一方、イギリスでは大学部門の割合が最も大きく6割を超えている。
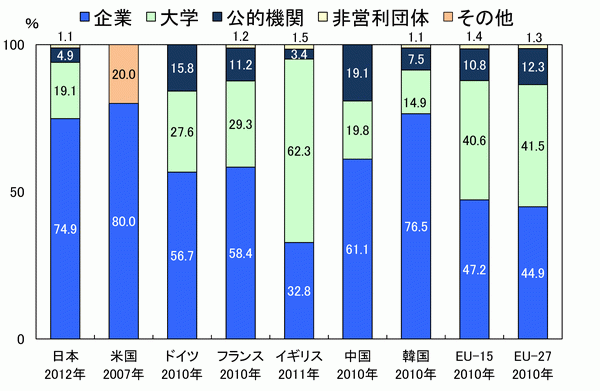
(2)日本の研究者における博士号取得者の割合の変化
日本全体の研究者のうち、2012年の博士号取得者の割合は20.3%である。部門別に見ると、「大学等」についての割合が大きく、同年で55.5%である。一方で、「企業等」については4.2%と、2002年からほとんど変化もなく、横ばいに推移している。
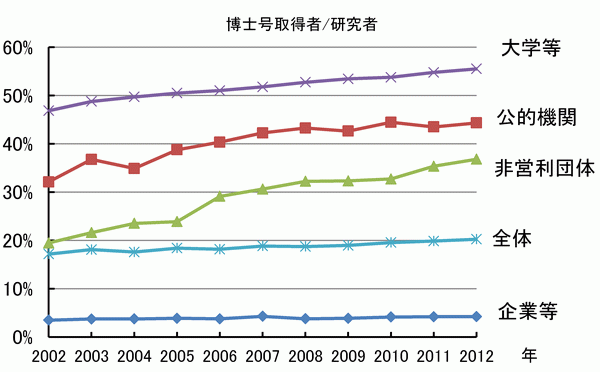
(3)日本の大学部門の研究支援者
研究支援者は研究者と共に研究開発の担い手として重要な役割を果たしている。そこで日本の研究支援者のうち、特に大学部門の内訳において、2000年代に入り増加しはじめたのは「研究事務・その他関係者」であり、2000年代後半から増加したのは「研究補助者」である。
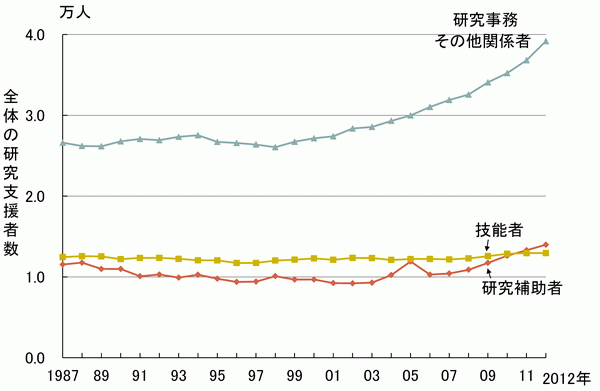
第3章:高等教育
(1)大学や大学院入学者数の状況
大学院博士課程の入学者数は1990年代に入り大きく増加した。これは修士課程の入学者数についても同様である。その後、博士課程の入学者数は2003年をピークに減少が始まった。また、修士課程の入学者は2000年代の中ごろから横ばいに推移し、2010年をピークに減少し始めた。一方、大学学部学生の入学者数は2000年頃から横ばいに推移している。
2012年度の状況を見ると、大学学部入学生は前年度より1.2%減少し、60.5万人となった。修士課程の入学生は前年度と比較すると、5.5%と大きく減少し7.5万人となった。博士課程の入学者数は前年度と比較すると、0.8%減少し1.6万人となった。
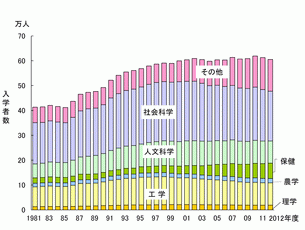
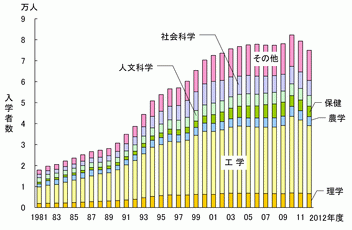
【図表9】 大学院(博士課程)入学者数
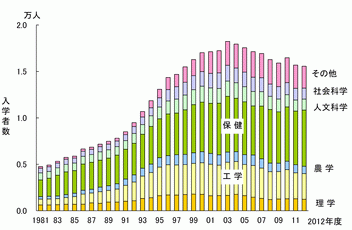
(2)理工系学生の進路
理工系学部卒業生の卒業後の進路については、長期的には「進学者」の割合が増加し、「就職者」の割合が減少する一方、最近の2年間は「進学者」が微減し、「就職者」が微増となっている。2012年における「就職者」の割合は48.5%である。理工系修士課程修了者については、「就職者」の割合は、8割前後で、ほぼ横ばいに推移しており、2012年では84.3%である。理工系博士課程修了者については、2000年代後半から「就職者」の割合が増加し、2012年の「就職者」の割合は73.7%と高い数値を示した。
2012年から、「就職者」について「無期雇用」と「有期雇用」の分類が導入されている。理工系学部卒業生については「就職者」のうち「無期雇用」の割合は97.7%である。また、理工系修士課程修了者については「無期雇用」の割合は99.1%である。一方、理工系博士課程修了者では、「無期雇用」の割合が72.8%であり、学部卒業生や修士課程修了者の「無期雇用」の割合と比較すると低くなっている。これは博士課程修了者の「有期雇用」にはポスドク、任期付き研究員等が含まれているためであると考えられる。
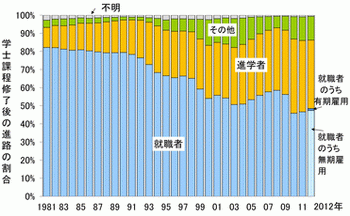
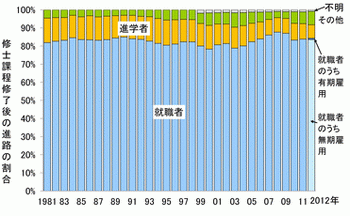
【図表12】 理工系博士課程修了者の卒業後の進路
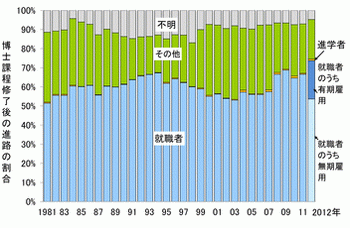
就職者:経常的な収入を目的とする仕事についた者
無期雇用:雇用の期間の定めのないものとして就職した者
有期雇用:雇用の期間が1年以上で期間の定めのある者であり、かつ1週間の所定の労働時間が概ね30~40時間程度の者をいう。
進学者:大学等に進学した者。専修学校・外国の学校等へ入学した者は除く。
不明:死亡・不詳の者
その他:上記以外
第4章:研究開発のアウトプット
(1)論文数、Top10%補正論文数、Top1%補正論文数の主要国の状況
研究開発活動のアウトプットとして計測可能な科学論文について、分数カウント法を用いて、主要国の「論文の生産への貢献度」について比較を行うと、日本の論文数は、2000-2002年の平均では世界第2位であったが、2010-2012年の平均では米国、中国に次ぐ第3位である。また、被引用数の高いTop10%補正論文数では、2000-2002年の平均では第4位であったが、2010-2012年の平均では第6位である。さらに、被引用数の高いTop1%補正論文数では、2000-2002年の平均では第4位であったが、2010-2012年の平均では第7位である。論文の量質ともに、世界における日本の相対的なポジションは低下傾向にある。
(分数カウント法)
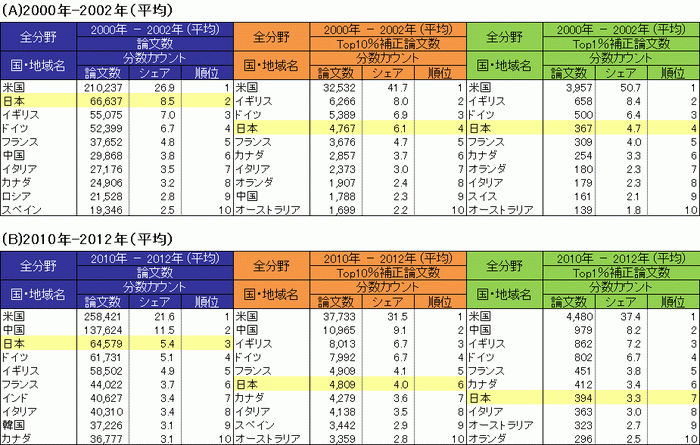
注:
Top10%(Top1%)補正論文数とは、被引用回数が各年各分野で上位10%(1%)に入る論文の抽出後、実数で論文数の1/10(1/100)となるように補正を加えた論文数を指す。
- 論文データベースは、最新年の論文の情報のみが追加されるのではなく、過去にわたって修正及び追加されている。したがって、論文に関する分析については、前回の科学技術指標2012と本調査資料の単純な比較は出来ない。
- また、科学技術指標2012までは、概要において、整数カウント法による結果を示していたが、今回から分数カウント法による結果を示している。
詳しい内容については本編第4章1節を御参照いただきたい。
(2)パテントファミリーを用いた特許出願の国際比較
特許出願数の国際比較可能性を向上させるために、科学技術指標2013では、パテントファミリーによる分析を初めて本格的に実施した。
パテントファミリー数(2006-2008年の平均)では、日本が世界第1位、米国が第2位となっている。パテントファミリー数とは、同じ内容で複数の国・地域に出願された特許を、重複を排除するために、同一のパテントファミリーとしてカウントした指標で、発明者の国・地域ごとに集計している。日米に次いでドイツが第3位であり、これに韓国、フランス、中国、台湾が続いている。
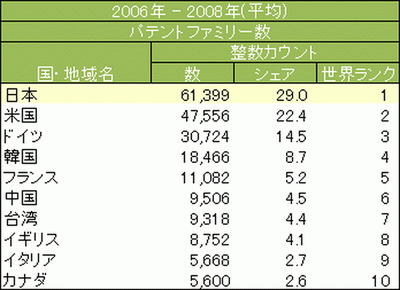
第5章:科学技術とイノベーション
(1)技術貿易の国際比較
各国の技術の国際的な競争力を示す指標である技術貿易収支比(技術輸出額/技術輸入額)については、日本の技術貿易収支比は増加し続けており、2011年で5.8である。1993年以降、技術輸出額が技術輸入額を上回る状態が続いている。なお、近年、特に増加が著しい理由は、技術輸入額が減少しているためである。
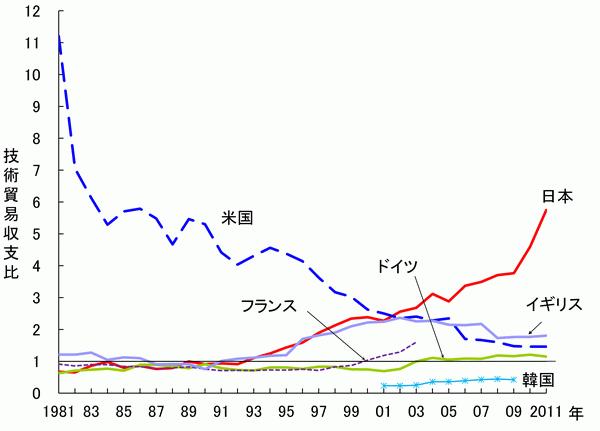
(2)ハイテクノロジー産業貿易
ハイテクノロジー産業貿易については、日本は輸出額が横ばいに推移する一方で、輸入額は2000年代後半から増加傾向にある。また、中国が輸出入額ともに急速に増加しており、2000年代後半には、輸出額が米国を上回った。米国は輸出入額ともに拡大しているが、2000年代には輸入額が輸出額を大きく上回っている。ドイツも輸出入額ともに増加している。いずれの国でも2009年にハイテクノロジー産業貿易額が減少しているのが見える。
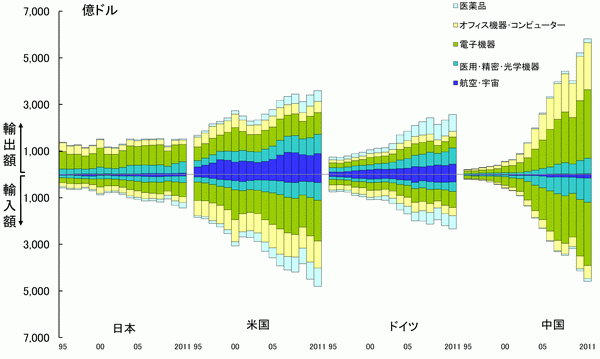
(3)ミディアムハイテクノロジー産業貿易
ミディアムハイテクノロジー産業貿易の輸出額はドイツが最も大きく、次いで米国であり、日本も存在感を示しているが、最新年では中国の輸出額が日本を上回っている。いずれの国でも2009年に、ミディアムハイテクノロジー産業貿易額が減少している。この要因の一つとして、リーマンショックの影響が考えられ、ハイテクノロジー産業貿易より、その影響が強く表れている。
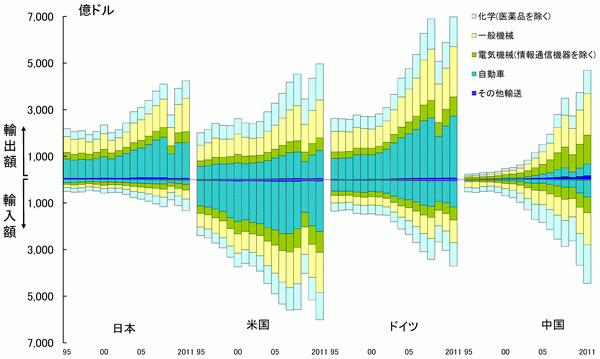
科学技術指標の特徴
科学技術指標は、毎年刊行しており、その時点での最新値を紹介している。原則として毎年データ更新され、時系列の比較あるいは主要国間の比較が可能な項目を収集している。
- 各国が発表している統計データを使用
科学技術指標で使われている指標のデータソースは、出来る限り各国が発表している統計データを使用している。また、各国の統計の取り方がどのようになっていて、どのような相違があるかについて、極力明らかにしている。 - 論文・特許データベースについて当研究所独自の分析の実施
論文データについては、トムソンロイター社"Web of Science"の書誌データを用いて、当研究所で独自の集計をし、分析している。また、集計方法も詳細に記載し、説明している。 特許関連の指標のうち、パテントファミリーのデータについては、PATSTAT(欧州特許庁の特許データベース)の書誌データを用いて、当研究所で独自の集計をし、分析している。また、集計方法も詳細に記載し、説明している。 - タイムリーな指標はコラムとして紹介
ベースとなっている指標の他に、その時々のタイムリーな話題に関した指標、または今後必要と考えられる指標についてはコラムとして紹介している。 - 国際比較や時系列比較の注意喚起マークの添付
必要に応じ、グラフに「国際比較注意」 「時系列注意」
「時系列注意」 という注意喚起マークを添付してある。各国のデータは基本的にはOECDのマニュアル等に準拠したものであるが、実際にはデータの収集方法、対象範囲等の違いがあり、比較に注意しなければならない場合がある。このような場合、「国際比較注意」マークがついている。また、時系列についても、統計の基準が変わるなどにより、同じ条件で継続してデータが採られておらず、増減傾向などの判断に注意する必要があると考えられる場合には「時系列注意」というマークがついている。なお、具体的な注意点は図表の注記に記述してあるので参照されたい。
という注意喚起マークを添付してある。各国のデータは基本的にはOECDのマニュアル等に準拠したものであるが、実際にはデータの収集方法、対象範囲等の違いがあり、比較に注意しなければならない場合がある。このような場合、「国際比較注意」マークがついている。また、時系列についても、統計の基準が変わるなどにより、同じ条件で継続してデータが採られておらず、増減傾向などの判断に注意する必要があると考えられる場合には「時系列注意」というマークがついている。なお、具体的な注意点は図表の注記に記述してあるので参照されたい。 - 統計集(本報告書に掲載したグラフの数値データ)のダウンロード
本報告書に掲載したグラフの数値データは、以下のURLからダウンロードできる。
http://www.nistep.go.jp/research/science-and-technology-indicators-and-scientometrics

