

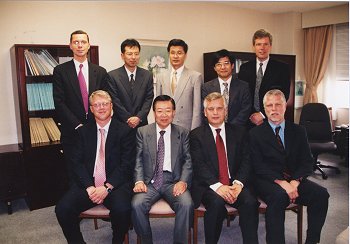 Drs. Rein Bemerオランダ経済省イノベーション局長 (前列右から2番目)他当所訪問 |
 群馬県立中央高校当所訪問 |
 Ⅰ.レポート紹介
Ⅰ.レポート紹介 |
| なかじま しのぶ 平成13年1月から平成14年3月まで 第1調査研究グループに在籍。 現在、カナダ・バンクーバーに在住。 |
当研究所では、急速に進展するわが国の科学技術活動の状況を的確に把握するため、科学技術指標を1991年に発行した。以来ほぼ3年毎にこれまで4版を重ねてきた。現在、2003年春を目途に第5版の検討が進められているが、初版以来作成に携わってきたメンバーが少なくなり、指標開発の背景、作成までのいきさつおよび現在までの指標の変遷に関する基礎的情報を整理しておく必要が出てきた。一方、日々進歩する科学技術活動をより実態に即して把握するために、時代に合致したモデルに基づく指標の体系化を試みる動きも出ている。
こうした認識に立ち、本調査資料は、これらの指標体系化作業および指標集の作成にあたり必要となるこれまでの情報を整理したものである。これにより、指標作成の担当者は、今後の作業を円滑に遂行でき、また、指標を利用する多くの研究者、研究管理者、行政担当者は指標の役割をより良く理解し、有効に活用できるようになる。そのため特に本資料では、主要な指標とそれを生み出す国あるいは組織に焦点をあて、「科学技術指標体系の比較と史的展開」としてまとめたものである。
指標の作成にあたっては、各種統計データを整理、加工するが、指標を作成するためのデータの選定段階から様々な議論の余地があり、1つの指標の中には様々な考え方を含んでいる。一般に、統計や指標は唯一の客観的データが存在すると考えられがちであるが、実際にはいくつもの数値が存在する。
例えば、現在検討中の科学技術指標第5版において、各国の人口の値として何を使うかが議論された。一例だが、1997年のフランスの総人口は、OECDの5種類のデータと、フランス国立統計経済研究所(INSEE)の数値がそれぞれ、59,736、58,600、59,736、58,207、58,608、59,835(単位:千人)と異なり、最大値と最小値の差は163万である。総人口は各国で定義に大きな違いが出にくいが、研究者数となれば各国の定義が微妙に食い違い、正確に比較することは更に難しくなる。そのうえ、研究費などの通貨が関わると、各年毎の為替レートの扱い、最近ではヨーロッパにおける統一通貨「ユーロ」への移行に伴う問題等、各国の状況を一つの物差しで比較したいと言う試みの前に、次々と障壁が立ちはだかってくる。
このような状況の中で本資料は、一国の科学技術力を出来るだけ正確に計り、他の国との比較の可能性を向上させるためになされてきた挑戦の歴史を、我が国及びOECD、米国を中心にまとめた。
OECD、米国、日本における特に重要な指標開発についての比較を以下に示す。
| 年代 | OECD、米国、日本における指標 |
|---|---|
| 1950 | 53米国:NSFによる最初の統計調査開始 |
| 1960 | '63OECD:フラスカティ・マニュアル初版発行 |
| '65日本:科学技術要覧初版発行 | |
| 1970 | '73米国:Science Indicators(SI)初版発行 |
| 1980 | '84OECD:Science and Technology Indicators 報告書初版発行 |
| 1990 | '91日本:「科学技術指標」初版発行 |
最新の科学技術指標について米国と日本の比較を行い、米国にあり日本で採用されていない主要な指標の項目を以下に示す。
 II. 海外事情
II. 海外事情 |
すぎうら みきひこ 平成元年(財)社会開発総合研究所入所。平成7年に兵庫県庁入庁。県庁科学技術政策課などを経て、平成14年4月から科学技術政策研究所第3調査研究グループ上席研究官。 |
現在、日本とインドネシア間では海洋、宇宙、原子力の各分野で二国間共同研究が積極的に行われています。
例えば、従来から海洋調査等を共同で実施してきたところですが、特に深海研究分野においては、2001年1〜2月に行ったスンダ海溝の調査に基づき、今年10月には有人潜水調査船「しんかい6500」による調査潜航が行われる予定です。また、宇宙分野においては、日本・宇宙開発事業団(NASDA)とインドネシア航空宇宙庁(LAPAN)により、スラウェシ島パレパレに開所されたNASDA受信局における地球資源衛星1号の直接受信に関する研究協力を実施してきました。
このように近年日イ両国の科学技術分野における協力関係が飛躍的に進展している中、筆者は、6月23〜24日に行われた「日本・インドネシア科学技術政策シンポジウム」に出席する機会を得ました。
同シンポジウムは、インドネシア科学技術政策の総合的・基本的方向を示す「科学技術総合戦略2000-2004(研究技術担当大臣決定)」が策定されたことを機に、日本・インドネシア両国が共通とする課題を中心に科学技術政策についての情報交換を行うことを目的として、国際協力事業団(JICA)、インドネシア研究技術省(RISTEK)及びインドネシア技術評価応用庁(BPPT)の共催で開催されたものです。
「科学技術総合戦略2000-2004」は「同1995-1999」に引き続いて、2000年2月15日に研究技術担当大臣により決定されたものです。一方で、経済危機からの脱出が緊喫の課題となっているインドネシアの状況下で、科学技術関係予算が大幅に削減されているとも聞き及びますから、今回のシンポジウム開催には、経済社会の発展を図るうえでの科学技術の重要性に目を向けさせようとする意図も含まれていると考えられます。
また、今回のシンポジウムでは、インドネシアにおいて地域科学技術振興が注目されていることを考慮し、セッションのテーマとして特に「Regional S&T Promotion」を取り上げています。その背景としては、最近の地方自治制度の改革により、地方政府の自治権が大幅に認められるようになり、地域独自の政策展開が期待されるようになったことがあります。
インドネシアの地方自治体は、基本的にDaerah Tingkat Ⅰ(DATI Ⅰ、1級自治体)とDaerah Tingkat Ⅱ(DATI Ⅱ、2級自治体)に区分されます。DATI Ⅰについては、29の州(Propinsi)及び特別州、DATI Ⅱについては、県(Kabupaten)及び政令市(Kotamadya)から成り、このほか郡や町がおかれています。これらの地方政府と中央政府間関係については、州知事や県知事が内務大臣に任命されるほか、中央政府への利権や税収の集中が指摘されてきました。
それが、スハルト体制の崩壊に伴い、新たな政権が経済改革、政治改革を進め、その正当性を確保しようとする中で、行政改革も俎上に載るようになったのです。そして、新たな地方自治法と中央・地方財政均衡法(およびそれに基づく多くの政令)が施行された2001年は、地方自治実施の最初の年とも位置付けられます。
もちろん、新制度移行後の混乱も各地で生じているようですし、地方自治制度が定着するまでには、まだ多くの時間を要するのでしょう。各地で県から州への格上げ運動が起きており、州の数が拡大する傾向にあるとも聞きます。しかし、同時に地方政府による施策に大きな期待が寄せられているのも確かなことだと思います。
こうした改革への期待を反映するかのように、会場においても熱心な討論が行われました。シンポジウムの1日目は、ハッタ研究技術担当大臣からのウェルカムスピーチに続き、山元文部科学省科学技術・学術政策局長他より基調講演が行われ、2日目は、各テーマ別のセッションとなりました。
 |
| 講演する筆者 |
地域科学技術振興をテーマとするセッションにおいては、筆者が、昨年当研究所が発表した「地域における科学技術振興に関する調査(第5回調査)」に基づき、①公設試験研究機関と理科系高等教育機関といった大型施設の基盤整備の時代から、これらの施設を活用した研究・技術開発の推進等の地域ニーズにあったより多様な科学技術政策が実施される時代へと、大きく転換しつつあること、②地域経済を活性化するためには、効率的な研究環境整備や研究交流を今後も一層促進する必要があることを報告しました。また、文部科学省が実施している知的クラスター創生事業についても簡単に紹介したところ、インドネシア側の質問がそこに集中したことから、産学官連携策に活路を見出そうとしていることがわかります。さらに、コーヒーブレークの間にも熱心に声をかけてくるなど、インドネシアの科学技術に携わる方々の熱意を感じさせられました。
短い滞在でしたが、インドネシアの方々との触れ合いを思い返しつつ、韓国−トルコ戦のテレビ放映で盛り上がる空港を後にしました。(インドネシアの方々は、アジア最初のW杯出場国ということを誇りにし、総じてサッカー好きだということでしたが、韓国系の方が多く住むこともあってか、韓国のサポーターしか見当たりませんでした。)
近年の政府間(中央-地方)の財政制度の改革を踏まえながら、国の管轄下にある研究開発には、人材開発、天然資源の活用、戦略的で高度な技術開発等の問題が含まれており、今後、両者の役割分担が重要になることを指摘。
また、国及び地域レベルの研究開発機関を取り上げ、最近、地域の研究開発機関が増加し、それらの役割等に混乱が生じている現状について言及。
そのうえで、多様な天然資源の有効利用を推進する方策(①資源の分布状況の把握、②資源の探索とその埋蔵量、③広範囲のサンプリングと経営的な観点からの実現可能性調査、④環境影響調査、⑤全面的な開発及び生産)を示すとともに、各主体による役割分担について提案。
また、天然資源に係る技術力は行政区域にとらわれないため、隣接地域との紛争を避けるためには、天然資源の活用に係る明確な政策が当面必要とされると主張。
 Ⅲ.トッピクス
Ⅲ.トッピクス |
| 「意識調査」に関する説明をする石井上席研究官 |
梅雨入り直後の6月12日、群馬県立中央高校2年3組の一行(男子・女子各5名)が「総合学習」の一環として当研究所を訪問、当所の日常業務、進路選択の経緯等についてヒアリングが行われました。(当方対応者:調査研究グループ=石井上席・柿崎主任研究官、研究グループ=古賀研究員、動向センター=横尾研究官、斎藤企画課長他)
当日は当方スタッフから"ミニ技術予測調査"や "科学技術理解度クイズ"を交え各々の担当業務について簡単に説明の後、大学での専攻と進路選択の関係、当所の研究活動の社会的意義等について活発な質疑応答が行われました。一行は全員が普通科(文科系)の生徒ながら、「スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール」にも指定された名門校だけあり、「理解度クイズ」では当研究所の行った「科学技術に関する意識調査」(2001年)での一般国民の平均点をかなり上回る好成績(全問正解も複数名)を上げた他、質疑応答では「政策研の成果は自分たちの日常生活にどう役立つのか」、「ベンチャー企業の成長性をどう予測するのか」、「将来のエネルギー・温室ガス増加問題解決の道筋は」、「地域科学技術推進の理想像は」など本質を鋭く突いた質問を連発、当所講師陣も思わずタジタジとなる場面が見られました。
当所としては、今後機会を捉え、こうした未来を担う若い世代への活動ぶりのアピールにも力を入れていきたいと思っております。

![]()
 |
| ふじわら しほ 平成12年4月 科学技術庁入庁 研究開発局宇宙政策課を経て平成13年4月より現職 |
当所では、調査研究成果を報告書として取りまとめ、印刷物の他、ホームページ(HP)を活用し、電子データでの提供も進めております。
右表は、平成13年4月から平成14年4月までの報告書ページへのアクセス状況を分析した結果(上位20件)です。当所の成果のうち、第7回技術予測調査(平成13年7月公表:概要、本文合わせ約1万5千件)、科学技術に関する意識調査(平成14年1月公表:約8千件)のアクセス数が突出して高くなっています。これらの報告書は新聞、テレビ等で広く取り上げられるなど、社会的インパクトの大きかった報告書であり、メディアの報道を見てアクセスされた一般の方が多かったようです。これら2つの報告書については、印刷物の入手希望が多かったことからも一般の関心の高さが裏付けられます。
また、平成13年4月より掲載を始めた科学技術動向(月報)がいずれも上位にランクインしており、多数の方に継続的にご愛読いただいているようです。
その他、特記すべきは、「新ビジネスモデルによる日本企業の強さの変革」(11位:平成11年5月)「日本のベンチャー企業と起業者に関する調査研究」(16位:平成11年3月)などです。 これらの報告書は、公表してから3年間を経た今もなお、高い関心を集めています。近年、技術移転、ベンチャー創出等が話題となっていますが、これらの課題を先取りした研究成果が評価されているものと思われます。
| 順位 | アクセス数(件) | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | 8,528 | 第7回技術予測調査(全文) |
| 2 | 8,157 | 科学技術に関する意識調査―2001年2〜3月調査―(概要) |
| 3 | 6,586 | 第7回技術予測調査(概要) |
| 4 | 4,671 | 科学技術動向2001年7月号 |
| 5 | 3,476 | 科学技術動向2001年8月号 |
| 6 | 2,954 | 21紀の科学技術の展望とそのあり方(全文) |
| 7 | 2,942 | 科学技術動向2001年10月号 |
| 8 | 2,654 | 科学技術動向2001年6月号 |
| 9 | 2,536 | 科学技術動向2001年11月号 |
| 10 | 2,343 | 科学技術動向2001年5月号 |
| 11 | 2,300 | 新ビジネスモデルによる日本企業の強さの変革(全文) |
| 12 | 2,209 | 科学技術動向2001年9月号 |
| 13 | 2,108 | 科学技術動向2001年12月号 |
| 14 | 2,093 | 科学技術指標 -日本の科学技術活動の体系的分析-(概要) |
| 15 | 2,090 | 科学技術動向2001年4月号 |
| 16 | 1,670 | 日本のベンチャー企業と起業者に関する調査研究(概要) |
| 17 | 1,516 | 科学技術指標 -日本の科学技術活動の体系的分析-(全文) |
| 18 | 1,441 | 日本の技術輸出の実態(平成10年度)(概要) |
| 19 | 1,391 | 科学技術動向2002年1月号 |
| 20 | 1,356 | R&D購買力平価の開発(概要) |
本分析より、これまでのような報告書入手希望からだけでは知り得なかった、当所調査研究成果に対する社会の関心度が明らかになりました。また予想していたよりもはるかに多くの方にアクセスいただき、報告書をご覧いただいていることも分かりました。
今後も皆様に当所の成果を一層活用いただけるよう、報告書の電子化・早期公表への取組みを進めて参ります。
 Ⅳ. 最近の動き
Ⅳ. 最近の動き| (・5/30 | Drs. Rein Bemer:オランダ経済省イノベーション局長他) |
| ・6/4 | Dr. Christopher T. Hill: 米国テクノロジー・ポリシー・インターナショナル プリンシパル |
| Mr. Patrick H. Windham: 米国テクノロジー・ポリシー・インターナショナル プリンシパル |
|
| Mr. George R. Heaton, Jr.: 米国テクノロジー・ポリシー・インターナショナル マネージング・プリンシパル |
|
| ・6/21 | Dr William A. Blanpied(NSF東京事務所長)、Dr. Larry Weber(NSF国際科学工学局プログラム・マネージャー): 当研究所機関評価委員会第4回会合に出席 |
| ・6/5 | 「免疫学の最近の動向」 高濱 洋介:徳島大学ゲノム機能研究センター教授 |
| ・6/27 | 「宇宙立国の要となるべき宇宙太陽発電所」 松本 絋:京都大学宙空電波科学研究センター教授 |
| ・ | 「科学技術動向 2002年6月号」(6月28日発行) |
| 特集 1 分子植物科学の動向 ライフサイエンス・医療ユニット 長谷川 明宏・茂木 伸一 |
|
| 特集 2 ブロードバンド時代におけるデジタルコンテンツ流通と著作権管理技術 情報通信ユニット 山崎 哲也 |
|
| 特集 3 CO2地中貯留技術を中心とした温暖化対策技術の開発動向 環境・エネルギーユニット 宮本 和明 |
梅雨に入りじめじめとした天気が続きますが、昨今頻繁に起きている夏の水不足、今年はどうなるでしょうか。
さて、当研究所が永田町合同庁舎から霞ヶ関郵政事業庁舎へ引っ越してから今月で1年になります。今後とも政策研ニュースやホームページによりその成果を発信していきますのでよろしくお願いいたします。(a)
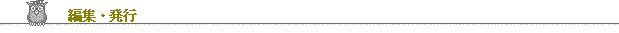
文部科学省科学技術政策研究所広報委員会(政策研ニュース担当:情報分析課 news@nistep.go.jp)