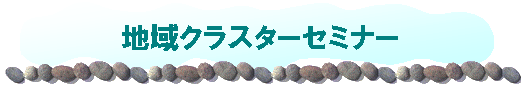第 13 回地域クラスターセミナー議事概要
| 日時 / 場所 | : |
2004 年 10 月 20 日 (水) 18:00 〜 20:00 於: 文部科学省 10 階会議室 |
|---|---|---|
| テーマ | : |
『ニューシャテル (スイス) ―時計産業集積から MEMS クラスターへ―』
|
| 講師 | : |
|
| 講演概要 | : | ニューシャテル大学は、1975 年に、マイクロ技術の教育と研究を推進するマイクロ技術研究所 (IMT) を設立した。IMT は、時計産業発祥の地といった、この地域特有の環境を活用しながら、関係機関及び産業界との協力の下、研究と教育によってスイスにおけるマイクロ・ナノ・システム・テクノロジー (MNST) のパラダイムの出現に大きく寄与してきた。また、1984 年には、連邦政府及び州政府の支援を受け、エレクトロニクス、材料学、マイクロメカニックスの分野の 3 つの研究所を統合した Swiss Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique 株式会社 (CSEM) が設立された。CSEM は、エレクトロニクスとマイクロ技術の広い活動分野で、大学の研究と企業との仲介役を果たし、その主な成果は、スイスにおけるスタートアップやスピンオフの創設となって現れている。本セミナーでは、このように、スイス・ニューシャテル市にあって、スイスの MNST 分野の研究・教育並びに研究成果の産業化のプラットフォームとして機能しているニューシャテル大学及び CSEM 社について、両機関のキーパーソンにご講演いただく。 |
| 主催 | : |
|
| 出席者数 | : | 33 名 (日本側参加者 28 名、海外アタッシェ等 5 名) |
| 配付資料 | : |
[開会の辞]
斎藤尚樹 科学技術政策研究所 第3調査研究グループ総括上席研究官 (以下、斎藤総括上席研究官)- 主催者側から本セミナーの趣旨の説明があり、講演者であるニコ・ドゥロイ教授とハリー・ハインツェルマン氏の紹介がなされた。
[講演 (18:05 〜 19:00)]
- 本講演では、最初にニューシャテル大学のドゥロイ教授が講演し、同大学マイクロ技術研究所 (IMT) の設立の経緯について説明がなされ、また、研究開発の実績が紹介された。ニューシャテル地方はスイス時計産業の発祥の地であったが、1970 年代のクォークの到来により伝統的な時計製造技術に基盤をおく産業地盤の沈下が起こり、失業者が増加した。IMT は時計産業の基盤強化を目的として設立され、他の研究機関との教育および研究の共同作業を通じてマイクロ・ナノテクノロジーの分野での研究・開発が進められたが、その成果は、時計産業のみにとどまらず他の産業分野でも多く利用される技術の開発として展開され、現在ではバイオ・宇宙産業等に深く関わるようになっている。製品化の実例として MEMS (Micro Electromechanical Systems) 技術を応用した製品である、圧力センサーや単結晶シリコン製のギヤなどの時計の部品、宇宙での実験用に開発されたマイクロバイオリアクター、ナノ・リットルまで計測可能なフローセンサーなどが紹介された。
- 次に、Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique (CSEM) 社のハインツェルマン副社長が、同社の機構および業務内容について講演を行った。CSEM は 1984 年に連邦政府及び州政府の支援を受け、マイクロ技術の推進、技術移転、製品開発等を目的として設立され、ニューシャテル大学その他の研究機関と企業の橋渡しとして、両者と緊密に連携している。CSEM はパブリック・プライベート・パートナーシップであり、その資金の約 40% は私企業から提供されているが、株主はスイスの企業のみならず、現在ではヨーロッパ諸国やアメリカの企業、あるいは多国籍企業が多くを占めている。株主への配当は一切行わず、利益は、技術プラットフォームを強化するために再投入されている。CSEM は CSEM 自体の増益は目標としていない。CSEM からのスピンオフ企業の成長やスタートアップ企業の創出にともなう雇用の増加など、産業および経済の活性化を目標としているが、すでに 20 社を超えるスタートアップ企業の創立に結びついており、目標は十分に達成されている。
[質疑応答]
モデレータ: 原山優子 東北大学教授/研究・技術計画学会地域科学技術政策分科会 東京地区幹事- 本日は台風が接近しているため、残念ながら終了時間を繰り上げたい。余り時間がとれないので、簡単に質疑応答を行う。
Q1
- CSEM はスタートアップ企業に資本参加をするのか、それとも技術移転のライセンス契約を結ぶのか。また、スタートアップ企業の経営者には技術者、あるいは経営の専門家のどちらを起用するのか。
A1
ハインツェルマン氏- まず、当初は CSEM が株式の過半数を持つ。例えば CSEM が 3 分の 2 を持ち、ベンチャーキャピタルなどが 3 分の 1 を持つ。新会社の価値を上げ、利益を上げてその利益を再投資していくことが理想だが、まだそうなっていない。残念ながらここ数年間ハイテク企業は厳しい状況に面しており、このようなモデルを現実にするのはなかなか難しい。
- 例えば 55 歳くらいの技術者は、有能であっても、新しいスタートアップ企業に転職するのは大変である。しかし、CSEM が新しい会社の過半数の株式を持つことによって、年金等、転職者の労働条件について配慮することもできる。また、企業文化的にも CSEM と新会社の間のギャップは小さいので、転職者にも馴染み易く、転職を容易にすることが出来る。
- 株式の過半数をもつのは当初のごく短い期間に通常は限っている。
- また、優秀な技術者であってもほとんどの場合、優れた経営者ではないので、基本的には経営者は外部から雇っている。
Q2
- 日本では、企業がナノテク研究の成果を活用した新製品を発売する場合の安全性や、生命科学関連会社における倫理の問題などに議論があるが、そのような社会的な側面について、将来どのような問題に直面しうるか。
A2-1
ドゥロイ教授- 生命科学の分野では我々は特に診断薬に関係している。診断薬ではスイスのロシュ社がドイツのべーリンガー・マンハイム社を買収し、世界最大の企業となった。診断薬や家庭にある身の回りのものにもナノテクノロジーが使われるようになってきており、欧州連合もこの分野には力を入れている。
A2-2
ハインツェルマン氏- ナノテクノロジーにおける問題は食品分野での問題と同様と考える。食品における遺伝子組み換え製品がおかした過ちを繰り返してはならない。遺伝子組み換え食品が最初に導入された時に、一般の人と十分なコミュニケーションをしなかった結果、遺伝子組み換え食品を阻止すべきという動きが広がってしまった。新技術はオープンにして危険性などの評価を行い、新技術に伴うリスクは今新しく現れたものではなく、以前からあるものが新しい研究によって分析可能になったことをきちんと理解してもらわなければならない。つまり、新技術によって新しい危険が生まれたのではなく、以前からあるものに対し、評価や研究が可能になったことへの説明が必要である。スイスでも他の国でも今、これが多くの議論になっている。
Q3
- ナノテクノロジー分野における新技術の産業化は、主に既存企業、それともスタートアップ企業のどちらへの技術移転によるものか。また、クラスター形成の視点からみて、ニューシャテル大学と CSEM の他のプレーヤーは誰か。
A3-1
ハインツェルマン氏- CSEM の製品については既存企業が 60%、スタートアップ企業が 40% を扱っている。ナノテクノロジーに関しては、まだ技術が新しすぎて、ナノテクノロジーを用いた製品を扱うスタートアップ企業は誕生していない。既存企業の協力を得て、技術の実証をしている段階である。
A3-2
ドゥロイ教授- 我々の地域では相当密度の高い企業ネットワークが存在する。また、CSEM には多くの株主がいる。また、地域、スイス全土、あるいは外国などを含め 50 社ほどの企業と協力関係にある。
A3-3
ハインツェルマン氏- 他のプレーヤーとしては、我々の近くに主に技術系の学生を育てる応用科学大学があり、連邦工科大学であるローザンヌ連邦工科大学 (EPFL) とも緊密に協力をしている。また、マイクロテクノロジーセンター (Institute of Microelectronics and Microsystems, IMM) も車で 40 分、60 km ほどの近距離にあり、大学に限らず様々な研究機関、工学系の専門学校等と緊密に協力している。更に Fondation Suisse pour la Recherche en Microtechnologie (FSRM) は CSEM の発足時の協力組織のひとつであるが、現在はこの組織が基本的には技術教育や文書作成などに重点をおくようになっており、また、技術教育などもしている。IMM なども大学、学会、産業界の関係者など希望するところには教育や研修をしている。
Q4
- 地域が経済的な困難に陥った後、新しい体制を作り上げてきた過程において、困難であったことは何か。コラボレーションは難しかったか。それとも基盤がもともとあったのか。
A4-1
ハインツェルマン氏- CSEM は、非常に大きな課題として検討されていたが、当初は政府から 2000 万スイスフランの年間予算をつけてもらうのは簡単ではなかった。現在も、政府の 4 年計画に入れば、その 4 年間は予算が確保できるので安心だが、次の 4 年計画策定時には、また、CSEM の役割や組織についての議論などが行われるので、そういう意味では不確実な要素あるいはリスクが常に付きまとっている。
A4-2
ドゥロイ教授- 当初は簡単ではなかったが、ビジョンをもった何人かの政治家の存在や産業界との協調など非常によいコンビネーションがあり、中央政府も強く後押しをしてくれ、年間 2000 万スイスフランの予算を獲得できた。予算も80年代初めは年間 1000 万フランだった。政府の資金を導入したため、いろいろ条件を提示されたが、次第に予算も引き上げられ、時間はかかったが今は大変スムーズにいっている。
- 各産業界との連携については、毎日が新しいチャレンジである。様々な人間が関わってきて複雑であるので、信頼関係が大事である。既定のルールやガイドラインに沿って進めている。
モデレータ
- 付け加えるが、1970 年代に CSEM が出来た当時、経済的な危機に面して、時計業界に加えニューシャテル州および市の受けたダメージも大きく、彼らが連邦政府にロビイングをした。また、時を同じくして、ナノマイクロテクノロジーが連邦政府によって重点政策に取り上げられたという背景もあり、連邦政府としては、CSEM のようなセンターを作ることとなり、ニューシャテルが選ばれた。ニューシャテルが自動的に選ばれたのではなく、地元の動きがあったから選ばれたこともひとつある。
- 先ほど FSRM の話が出ていたが、FSRM は当初は研究もしていた組織である。CSEM ができたことによって、研究組織を CSEM に移行して FSRM が教育やトレーニングをするようになり、今ではヨーロッパレベルでのトレーニングプログラムをも作っている。また、技術移転に関する相談の窓口にもなっている。つまり、CSEM と FSRM と大学は補完関係にある。
- キーとなるのは教育レベルのネットワークであり、ニューシャテル大学、ローザンヌ連邦工科大学また、ドイツと同様に職業分野の教育機関が大学に昇格された応用科学大学があり、工業大学、高専もある。このような様々のタイプのエンジニアを育てる組織がネットワークになっている。また、CSEM の人達も大学の人達もいろいろなレベルの大学に教えにいっている。そこから人のネットワークが形成され、人材育成もおこなわれる。さらには研究レベルのネットワーク、企業のネットワーク、それらがオーバーラップしている部分のコアとなっているのが、ニューシャテルである。
Q5
- CSEM で開発された知的財産権は株主の企業が権利を得るのか。また、CSEM の技術の製品化に関わる企業のうち、どの位の割合の企業が CSEM の株主なのか。
A5
ハインツェルマン氏- 原則として、当社は株主を優遇するが、実際に株主を優遇する必要があったケースはほとんど無い。株主を優遇すべき唯一のケースは、当社の株主企業と株主でない競合企業が同時に CSEM との共同開発を申し出た場合だが、その場合は株主企業を優先する。
- 知的財産権の扱いなどの会社の主要な決定については、通常、取締役会で行われる。主要な株主企業は取締役を出しているので、議題は全て把握できる。つまり、希望するものは他社より先に確保できることになる。
- CSEM のもともとの出発点が時計産業であった。しかし、その状況は今では相当変わっており、CSEM の株主は現在ではそれほど中心的な役割を果たしていない。例えば今でもシリコンの部品や時計産業向けの製品も幾つかは作っているが、当社の中心的な活動ではない。むしろ生命科学や宇宙関係のためのマイクロエレクトロニクスの製品などが中心となっており、大雑把ではあるが、株主企業が関わってくるのは 1 割から 2 割の製造に関してではないか。
[閉会の辞]
斎藤総括上席研究官- 次回の当セミナーの開催予定は、まだ決まっていないが、決定次第お知らせする。本日は台風にもかかわらずご出席いただいて感謝している。
この議事概要は主催者の責任で編集したものである。なお、質疑応答参加者で要修正箇所を発見した方は、主催者までご連絡願いたい。