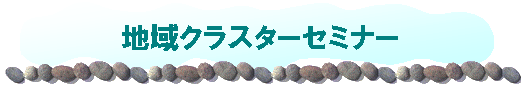第 3 回地域クラスターセミナー議事概要
| 日時 / 場所 | : | 2003 年 5 月 16 日(金) 18:00 - 21:00 / 独立行政法人経済産業研究所 1121 セミナー室 |
|---|---|---|
| テーマ | : | 「日本の知的クラスター創成を目指した取組み」 |
| 講師 | : |
|
| 講演概要 | : | 2002 年度に文部科学省が開始した「知的クラスター創成事業」は、現在 15 地域で展開されている。大学等の「知」を活用した地域クラスターの形成により科学技術駆動型の地域経済活性化を目指したこの取組みの概要(産業クラスターとの連携も含む)と事例を紹介するとともに、今後の課題について論じる。 |
| 主催 | : |
|
| 出席者数 | : | 72 名前後(日本側参加者 64 名、海外アタッシェ 8 名他) |
| 配付資料 | : | 講師資料 (日本語) [PDF: 156KB]、講師資料 (英語) [PDF: 172KB]。その他、関係機関のパンフレット、産業クラスター計画ならびに知的クラスター計画の小冊子など |
[開会の辞]
斎藤尚樹 (科学技術政策研究所第3調査研究グループ総括上席研究官)- 主催者側として本セミナーの趣旨、本日の講演者である中川健朗室長のプロフィール等を紹介した。
[講演]
- 最初の 1 時間で中川室長より、知的クラスター政策についてプレゼンテーションが行われた。
- 産学官連携施策の歴史的な背景、関連施策である都市エリア産学官連携促進事業の説明を含め、更に神戸や香川などの具体的な知的クラスター創成事業の活動状況についての説明がなされた。
[質疑応答]
Q1
経済産業省の産業クラスターと文部科学省の知的クラスターは、非常に似通った政策に感じる。どのようにすみ分けをし、また、連携をするのか。- このような地域活性化の施策としては、新産業都市計画やテクノポリス政策があるが、地域的にほぼ同じ地域において施策展開がなされているように見える。国の施策として、ある地域を更に発展させるため、同じ地域を指定して施策を進展させるのか、又はそのような地域は国の施策があっても自立できないため、絶えず活性化させる必要があるのか。
A1-1
中川室長:- 産業クラスター計画が 2001 年に、知的クラスター計画が 2002 年に始まり、縦割りになることなく、効果的な連携をするために、両省は議論を重ね、本日の資料に記載されている 3 つの方策 ((1)「地域クラスター推進協議会(仮称)」の設置、(2) 地域実施機関の連携、(3) 合同成果発表会) を推進することとした。
- 両方のクラスタープロジェクトともそれぞれの役割があり、区別をするということよりもむしろ、各地域ごとにそれぞれの役割を持って、かつそれが繋がっていくことがより重要と感じている。目的とする方向は地域経済の活性化なので、シーズに近いところから始めるか、産業にスポットを当てて始めるかの違いであり、それが連携をしたときに2倍ではなくて3倍、4倍の力になると実感している。
- クラスター毎に色々なタイプの連携があり、地域ごとに工夫をしている。高松希少糖バイオクラスターの場合、D-プシコースという、最も実用化に近いと考えられている希少糖があり、大量生産の技術、コスト低減を図る技術、こういうものについては四国の産業クラスター計画で民間企業に補助金を出しており、産業化を促進していく。
- 香川県の場合、両クラスター計画に加えて、県独自のクラスター構想を持っている。高松知的クラスターの本部長は香川県知事だが、地域自らがまず計画を持ち、これを知的クラスター、産業クラスターでアシストして、地域経済の活性化につなげていく。そして、法人化する大学が地域に貢献していく。これが特徴である。
- クラスターにおいて、大学と産業の関係、国と地方の関係の2つが重要である。知的クラスター創成事業は、自治体が自ら事業計画を考え、産学官のポテンシャルの総力をあげて組み上げ、クラスター作りを目指す、その初期段階を国が支援するというプログラムである。
- 地域の選定は、地域が策定した計画について、研究ポテンシャルがあるか、あるいは事業化につながるか、その地域が科学技術の振興にしっかり取り組んでいるか、そのための事務局の体制が整備されているか、などにより判断する。
- 国立大学の法人化を控えて、大学と大学が競争する。それから地域と地域も競争し、それぞれの地域はユニークさを活かしていくこととなる。経済状況が厳しい中で科学技術を、あるいは大学の研究を基に、やる気のある地域のアイデアを後押しするプロジェクトである。
- このクラスタープロジェクトに取り組んでいる地域を、このプロジェクトが始まって3年目となる来年に評価をする。その時に、地域が自ら汗をかいているか、努力をしているか等の地域の取組みの違いが色々なところに出てくる。
A1-2
井上裕行(経済産業省立地環境整備課長(併)産業クラスター計画推進室長):- 文部科学省が大学、経済産業省は企業ということで、もともと守備範囲はかなり離れていたが、実体経済の流れを見ると、大学のシーズから企業の製品に向けて1つの流れがあり、今回のこの滑らかな連携は、大きな進歩である。
- 元々経済産業省で進めているプロジェクトは、限定的ではなく、途中でまた柔軟に色々な対応を考えていくことになる。要は大学発ということで技術を中心に可能性のあるところから進めている。
A1-3
児玉俊洋(経済産業研究所上席研究員/研究・技術計画学会地域科学技術分科会東京地区幹事):- モデレータとして一言コメントを付け加えると、文部科学省と経済産業省の両省はお互いの連携にオープン、積極的であり、本当に連携の質が上がるか否かは、産学官連携コーディネータとかプランナーといわれる地域の人たちがうまく施策を使いこなすところにかかっている。
Q2
各地域の各クラスターで取り扱うテーマはどうやって選ばれているのか。A2
中川室長:- 各地域で取り扱うテーマは、各地域が自ら選んでいる。そのたくさん提出されたプランの中で、どの地域を選ぶかは、パンフレットに経緯が記載されているが、フィージビリティスタディを実施し、その中で優れた12地域、今は(その後試行地域から本格実施に移行した3地域を含め)15の地域を選んでいる。
Q3
この施策のターゲットとして、中小企業を想定しているのか、それともいわゆる地域の大企業というのがメインのターゲットになるのか。- 中小企業が参加を希望した時に、簡単にこのプロジェクトに参加できるのか。あるいは多くの要件があるのか。
A3
中川室長:- 大変よく受ける質問であるが、大企業だけ、あるいは中小企業だけをターゲットにするといういずれでもなく、それは各地域が描く戦略によるものである。パンフレットにも具体的な企業名が出ているが、大企業も地域の中小企業もある。地域のプロジェクトのため、地域の産業、地域の会社をという視点が必ずある。
- 例えば、京都ナノテククラスターの場合、京都のナノテク関係の会社が、このクラスターに参加する以外に、このクラスターをきっかけとして、ものづくりやナノテク、あるいは関係の中小企業の集まり、フォーラムを自ら独自に作っている。
- 神戸クラスターは再生医療という最先端の医学を扱っており、中小企業とは非常に遠いと考えがちであるが、実際には神戸市がリーダーシップをとり、神戸の機械金属工業会が、再生医療のための医療器具(の開発・供給)において参画し、クラスターづくりに貢献している。
- 中小企業の活躍の機会は、それぞれの地域で違うので、ご関心があれば、各クラスターの中核機関にぜひコンタクトをとっていただきたい(パンフレットに連絡先を記載)。あるいは、このクラスタープロジェクトそのものでなくても、このクラスタープロジェクトをきっかけに形成された産学官ネットワークにも、中小企業が参画するチャンスがいろいろある。
Q4
来年のこの事業の評価について、期待される成果というのが定性的すぎてわかりづらい。難しいと思うが、例えばイギリスでは、基礎的な研究でも、「Value for Money」の考え方により数値目標の設定が評価に当たり必須であると聞く。どのような客観的基準で来年評価をするのか。- スポーツに喩えると、ママさんバレーチームを増やしていくのか、又は、国全体の政策としてオリンピックの金メダリストを育てるのかで、その方法は違う。この知的クラスターがナショナルチャンピオンを世界チャンピオンにするという政策とすれば、歯がゆい感じがし、また対象地域も多すぎる。それとも、各地域の振興が目的なのか。
A4
中川室長:- いろいろな定量的パラメータ、例えば、研究の成果としての論文数、事業化への繋がりとしての特許の申請数、地域の広がりとしての参加機関の数などを(基準として)検討している。しかしそうした数だけがそのクラスターを物語るということはなく、実際にはその内容に差があり、その地域の戦略性や特許のクオリティも含めたものなどが評価されるだろう。
- 我々があまり考えずに定量的な指標を示したとたんに、プロジェクトは硬直化をして間違ったメッセージが与えられる可能性もあり、注意が必要。活発な地域、そうではない地域の差を、事業の評価の時に反映できると考える。ただし、その方法論をどうすればよいか。それもITのクラスターとライフサイエンスのクラスターを同様には扱えないので、こうした諸点についても検討中であり、是非知恵を頂きたいと考えている。
- このプロジェクトを始めた時に、(今も時々使うが、)日本版のシリコンバレーを作るというスローガンを掲げたが、シリコンバレーが日本に15もあるのはおかしいという意見もある。そこで、中間評価を基に、スーパークラスターは30億円、ミニクラスターは1億円とするといった案も議論されたが、実際には、このような単純化された展開にはならないのではないか。
- 神戸と大阪の場合、広域のクラスターであるが、多くの外部資金や、産業クラスターのお金も入っており、それらがうまく組み合わされて活かされるのであれば、「知的クラスタープロジェクトの進め方」と「地域クラスターの在り方」は、少し切り分けて考えてよいのではないかと思う。逆に国が方向を示しすぎるのは地域の自主性をしばることになり要注意。その意味で金メダリストを目指すことと、地域の振興の両面を考慮することが必要。
- 地域事業の政策担当者は、日本地図ばかりを見てしまうが、国際という視野を抜きにしてはできないということを地域にも語りかける必要がある。
[閉会の辞]
斎藤尚樹 (科学技術政策研究所)- 次回セミナーの計画と、経済産業研究所および科学技術政策研究所のホームページにおける情報提供について説明。
この議事概要は、主催者の責任で編集したものである。