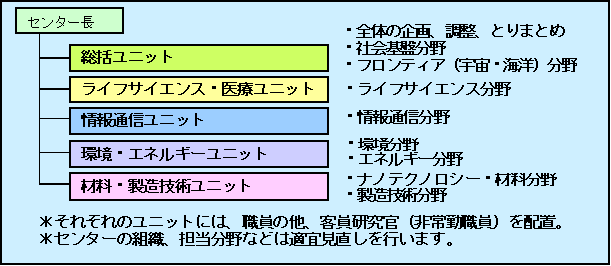
2001年1月に内閣府総合科学技術会議が設置され、従来以上に戦略性を重視する政策立案が検討されています。科学技術政策研究所では、戦略策定に不可欠な、重要科学技術分野の動向に関する調査・分析機能を充実・強化するため、2001年1月に新たに「科学技術動向研究センター」を設立しました。本センターでは、第2期科学技術基本計画に示されたライフサイエンス、情報通信等の重点分野の最新動向に係る情報の収集や今後の方向性についての調査・研究に、下図に示すような体制で取り組んでいます。本センターのメンバー構成比率としては、エレクトロニクス、エネルギー、材料、製薬等の民間企業からの出向者が半数、各省庁および財団法人や大学等の公的機関からの出向者が半数です。また、アドバイザーとして、大学教授などを「客員研究官」として各ユニットに配置しております。センターがとりまとめた成果は、適宜、総合科学技術会議、文部科学省へ政策立案に資する資料として提供します。センターの具体的な活動は以下の3つです。
わが国の産学官の研究者を「専門調査員」に委嘱して(2001年7月現在約2700人)、インターネットを利用して科学技術動向に関する幅広い情報を収集・分析する体制「科学技術専門家ネットワーク」を2001年3月から運営しています。このネットワークを通じて、専門調査員より国内外の学術会合、学術雑誌などで発表される研究成果等、注目すべき動向や今後の科学技術の方向性等に関する意見等を広く収集します。これらの情報に、センターが独自に行う調査・研究の結果を加え、毎月1回、「科学技術動向」としてまとめ、総合科学技術会議、文部科学省を始めとした科学技術関係機関等に配布します。なお、この資料は科学技術政策研究所のweb(http://www.nistep.go.jp)においても公開します。
今後、国として取り組むべき重点事項、具体的な研究開発課題等を明確にすることを目的とし、重要な科学技術分野・領域に関するキーテクノロジー等を調査・分析します。
さらに、重要な科学技術分野・領域ごとの科学技術水準を欧米先進国と比較し、我が国の科学技術がどのような位置にあるのかについての調査・分析も行います。
当研究所では、科学技術の長期的将来動向を総合的に把握するため、デルファイ法による技術予測調査をほぼ5年ごとに実施しています。これは、今後30年間の重要技術を抽出して、その重要性評価や実現予測時期を分析するものであり、センターは、多くの専門家の協力により本調査を引き続き実施します。
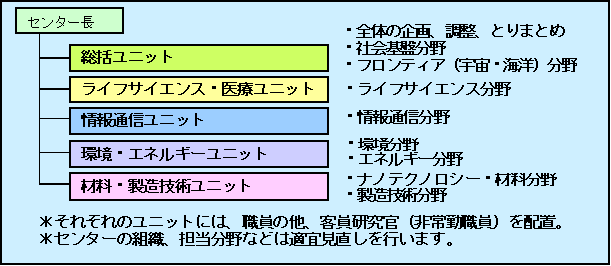
具体的な調査研究活動は、(1)科学技術専門家ネットワークによる科学技術動向情報の収集・分析、および(2)重要科学技術分野・領域の動向の調査研究からなり、その概略を図2に示します。なお、センターにおける科学技術動向調査研究の成果は、「科学技術動向(月報)」などとして取りまとめ、文部科学省における研究開発計画策定や、総合科学技術会議における科学技術基本計画の検討をはじめとする科学技術戦略の立案など、政策立案の際の基礎資料となります。また、これらの成果は科学技術関連の行政部局における研究評価、政策評価などの参考資料になります。なおセンターは、その成果を民間企業など行政部局以外へも幅広く公開していきます。
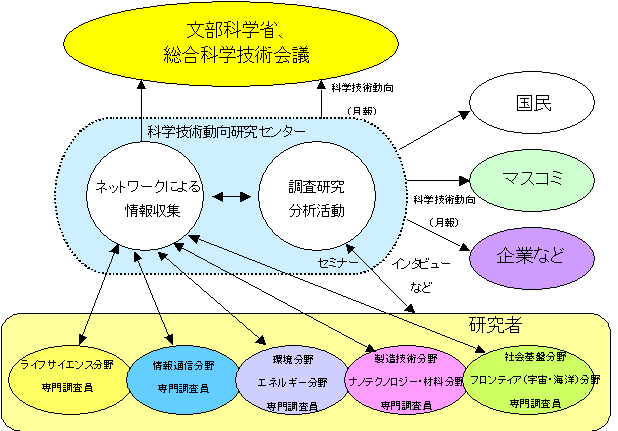
重要科学技術分野についての動向分析を的確に行うためには、多岐にわたる科学技術領域における最新の情報の収集が不可欠です。今日の科学技術は高度に専門化しているため、情報の収集に当たって、第一線の研究現場にいる研究者など高度の専門知識を持つ専門家の協力を得る必要があります。センターでは、インターネットを利用して、各分野における産学官の多数の専門家(以下「専門調査員」という)で構成する情報ネットワークを構築し、国内外の科学技術の動向に関する情報の収集・分析を行っています。
このネットワークを通じて、国内外の学術会合、学術雑誌などに発表される研究成果をはじめとする科学技術活動に関して、注目すべき動きを把握するとともに、今後の科学技術の方向性などに関する専門調査員の意見を広く収集しています。
センターは、専門調査員から提供された情報に、センター自らが収集した情報を加えて、分野別に整理・分析を行い、文部科学省、総合科学技術会議などに随時提供しています。さらにこれらの情報の主要点を「科学技術動向(月報)」の第1部のトピックスとしてとりまとめ、当研究所Webサイトで公開しています。
今後、国として取り組むべき具体的な重点事項、研究開発課題などを明確にすることを目的として、重要な科学技術分野・領域を対象に、それぞれの分野の進展を考える上で何がキーテクノロジーとなるのか、何がネックとなるのかなどの調査・分析をしています。調査研究テーマの選定にあたっては、行政部局の動向、社会・経済的ニーズなども踏まえ、重要と考えられる技術・課題などを絞り、可能な限り、重点的かつ集中的に取り組むこととしています。
調査研究にあたっては、センター自ら情報の収集・分析を行うとともに、外部専門家を招いた講演会の開催、外部専門家により構成する調査研究委員会の設置・開催など、多くの専門家の意見を集めることにも留意します。
この調査研究の結果については、「科学技術動向(月報)」の第2部の特集記事としてとりまとめ、当研究所Webサイトで公開しています。
また、重要な科学技術分野・領域ごとの科学技術水準を欧米先進国と比較し、我が国の科学技術がどのような位置にあるのかを調査・分析します。この調査は、文部科学省関連部局や総合科学技術会議が実施する科学技術水準に関する調査研究と連携をとりつつ実施します。
以上の調査研究の成果は、当研究所における他の調査研究活動と同様に「NISTEP REPORT」、「調査資料」などとして取りまとめます。
| 科学技術トピックス | 特集 |
|---|---|
| 専門調査員からの情報にセンターの取材による情報を追加した、最新の技術動向 | 注目すべき動向について、センター独自の取材や専門家を招いての講演会等により情報を収集、分析 |
| ライフサイエンス分野 |
|
|---|---|
| 情報通信分野 |
|
| 環境分野 |
|
| ナノテク・材料分野 |
|
| エネルギー分野 |
|
| 製造技術分野 |
|
| 社会基盤分野 |
|
| フロンティア分野 |
|
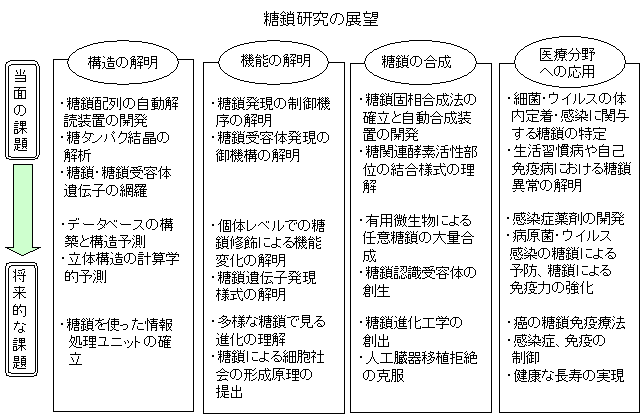

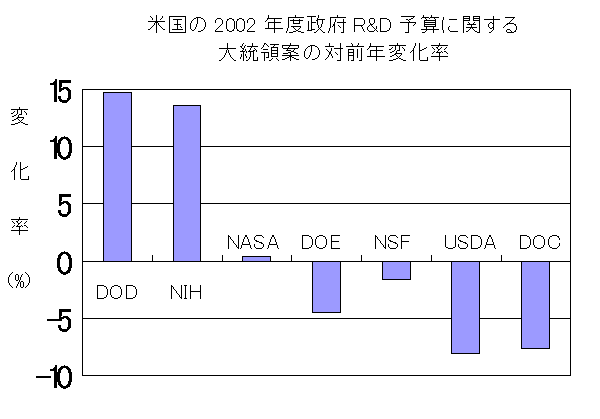
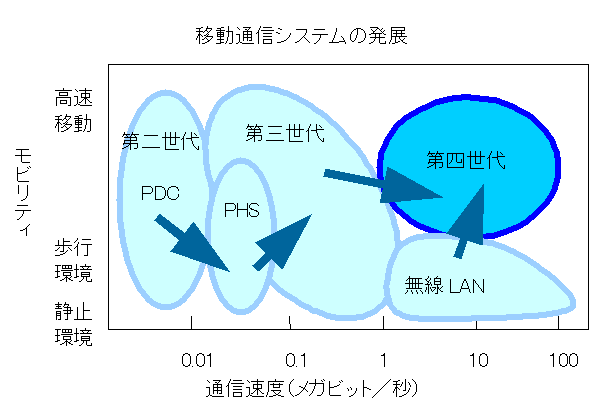
| 用途 | CNTを用いる利点 | 開発状況 |
|---|---|---|
| 走査型プローブ顕微鏡(SPM)探針 | より微細構造の観察が可能など多くの利点 | 実用化段階 |
| 電界放出ディスプレイ(FED)用エミッタ | 発光ディスプレイ低消費電力化が可能 | 試作段階 |
| 水素吸蔵材料 | 高い水素吸蔵能力を示す燃料電池用水素吸蔵材料 | 基礎検討段階 |
| リチウム二次電池負極 | 従来材料より大容量の負極材料 | 基礎検討段階 |
| 電界効果トランジスタ | 集積回路の高密度化などが可能 | 基礎検討段階 |
| 複合材料 | 高性能な樹脂等の強化、伝導性付与材料 | 応用検討段階 |