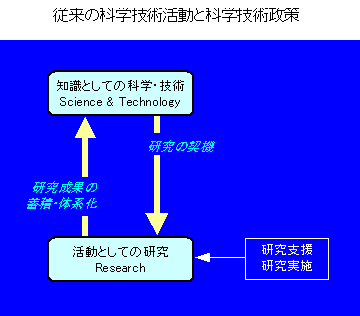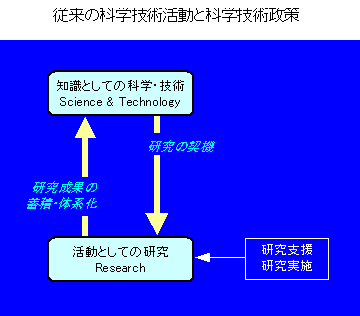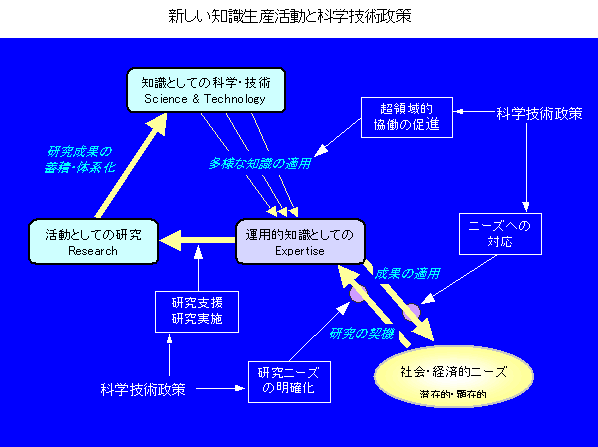科学技術政策システムの機能分化と再統合
担当:第2研究グループ
<研究活動の概要>
日本の科学技術政策は、ここ数年、行政改革に伴う省庁再編、新しいファンディング・システムの創設、産学連携体制の整備など、著しく変化しています。このような変化は長期的に見れば日本だけでなく世界的な現象であり、科学技術政策はイノベーション政策としての性格を強めるとともに、戦略性の重視、政策の対象・範囲の拡大、政策ツールの多様化といった変化が起きています。
このような科学技術政策の変化の背景として、そもそも科学技術活動ないし知識生産活動の様式の変化が起きているとの指摘があります。すなわち、従来の科学技術活動(下図)は、知識としての「科学・技術」と活動としての「研究」の相互作用とみなすことができたのに対し、新しい知識生産活動(次ページ図)は、社会・経済ニーズに立ち向かうために、「科学・技術」知識だけではなく応用的・運用的な専門知識が重要な要素となって展開されていると考えられます。そうだとすれば、このような変化や構造を総合的に理解することが科学技術政策研究の重要な課題となります。
本研究は、以上の認識のもとに、最近の世界的な科学技術政策の変動を理論的、実証的に跡付け、今後の科学技術政策の革新の方向を探ることを目的としています。とくに、この間の変化を、科学技術政策システム(政策主体、研究主体、中間的組織などの要素から構成され、さらに、これら相互間の機能的連結も含む)の再編過程、すなわち、科学技術政策に関わる機能の分化と再統合の過程として捉え、概念化し、体系的に整理することを目指しています。単なる理論的研究というだけでなく、制度設計の側面も有する政策的研究です。
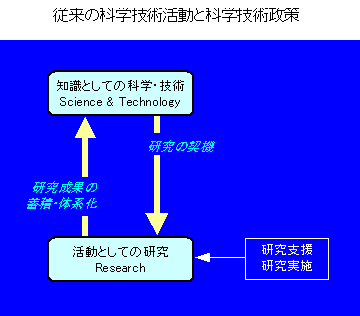
- 従来の「科学技術」には、知識としての「科学・技術」と活動としての「研究」の2面がある
- 知識としての「科学・技術」は、体系的で、後述のExpertise(専門知識)と比較して安定的
- 「科学・技術」の蓄積を踏まえて、「研究」の課題が設定される
- 「研究」の成果は、 「科学・技術」における新たな知識の蓄積となることが期待される
- このような科学技術活動の様式においては、設定された「研究」の支援や、場合によっては自ら研究を実施、運営することが科学技術政策の役割
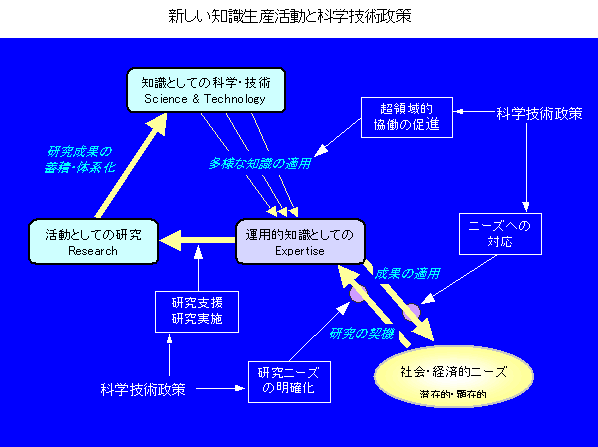
- 社会・経済的ニーズに正面から立ち向かうためには、「科学・技術」知識そのものを適用するのではなく、社会・経済的ニーズが発する課題に適合するような応用的・運用的な知識の利用が必要
- このような知識は、「科学・技術」知識とは別物で、Expertise(専門知識)と呼ばれる
例: ダイオキシンの性質や測定方法に関する知識が「科学・技術」知識であるのに対し、ダイオキシンの規制を制定・実施するための知識がExpertise(専門知識)
- このような社会・経済的ニーズに対応した新しい知識生産の様式においては、
- Expertise(専門知識)の活動を促進するために、超領域的な協働(collaboration)を促進することが必要(例:分野の異なる専門家間の協力の促進)
- 既存の知識だけでは十分でない場合もあり、新たな研究活動の支援、実施も必要
- さらに、いかに社会・経済ニーズを発見し、伝達するか、いかに専門知識(Expertise)を社会に適用するか、も焦点
- 科学技術政策は、上記の事柄が適切に行われるような基盤を用意したり、自らそうした活動をする必要がある