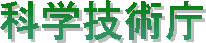
Science and Technology Agency
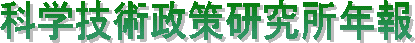
National Institute of Science and Technology Policy Annual Report

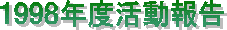
Research Activities in 1998
NISTEP
[ 目 次 へ ]

創立10周年記念式典における佐藤所長の挨拶

創立10周年記念懇親会場における中原政策研顧問による乾杯のご挨拶

竹山国務大臣科学技術長官のご挨拶

創立10周年記念コンファレンス会場の様子

第1回機関評価委員会の様子

西島機関評価委員長から機関評価の報告書を受け取る佐藤所長
1998年度
科学技術政策研究所年報
1.はじめに*
2.科学技術政策研究所の概要*
(1)業務の基本方針*
(2)組 織*
(3)予 算*
(4)1年間の主な活動*
3.国際会議*
(1)科学技術政策研究所創立10周年記念国際コンファレンス*
4.国内会議*
(1)科学技術政策研究所創立10周年記念式典及び記念誌*
(2)平成10年度地域科学技術政策研究会*
5.科学技術政策研究所機関評価*
6.調査研究活動の概要*
(1)第1研究グループ*
(2)第2研究グループ*
(3)第1調査研究グループ*
(4)第2調査研究グループ*
(5)第3調査研究グループ*
(6)第4調査研究グループ*
(7)情報分析課*
7.他機関等との連携*
8.情報処理システムの整備及び資料の収集整理*
(1)情報システムの整備*
(2)資料の収集整理等*
(3)所報の発行*
9.研究交流*
(1)国際研究協力( )書簡交換日*
(2)国際会議への出席及び海外出張*
(3)海外からの研究者等の来訪、招聘*
10.研究成果・研究発表*
(1)研究成果*
(2)講演会の開催*
(3)所内セミナーの開催*
11.参考資料*
(1)研究実績*
(2)顧 問*
(3)職員名簿*
(4)客員研究官制度・特別研究員制度による受け入れ*
(5)科学技術政策研究所の沿革*
新しい千年紀を目前にした現在、生活環境をも含めた経済社会システム全体が大きく変わりつつあります。特に情報通信技術、ライフサイエンスなどの科学技術の新たな展開により科学技術と社会との結びつきは質的に変わりつつあります。このような状況の中で、国際的な競争の激化、急速な少子高齢化の進行、環境問題の深刻化等の諸課題に適切に対処し、国民ニーズに対応した質の高い調和のとれた社会を実現していくためには、総合的な視点から科学技術の有効かつ多様な活用が必要不可欠と考えます。このため先見性をもった科学技術政策の必要性は増大しており、そのための基本となるべき科学技術政策研究への期待も益々大きなものとなっております。
創立10周年を迎えた1998年度においては、このような認識のもと、科学技術政策展開の基礎となる諸事項について理論的・実証的な調査研究の展開を図るとともに、いくつかの節目の活動を行いました。
調査研究活動については、「外国技術導入の動向分析(平成8年度)」、「日本の技術輸出の実態(平成8年度)」、「地域における科学技術振興に関する調査研究(第4回調査)」、「日本のベンチャー企業と起業者に関する調査研究」、「2010年代の国民生活ニーズこれに関する科学技術」などの調査研究について、その成果をとりまとめ報告書を作成しました。
調査研究以外の活動として、1998年7月には当所創立10周年記念式典を行うとともに、「新世紀の深みのある政策展開を目指して」と題する創立10周年記念誌を刊行しました。また、10月には科学技術を取り巻く国際社会の将来を展望し、その知見を具体的に政策立案過程につなげていくための新たなる政策研究の可能性について論議を深めるため「科学技術政策研究所創立10周年記念コンファレンス」を開催しました。さらに、外部有識者からなる科学技術政策研究所機関評価委員会を設置し、内閣総理大臣決定による大綱的指針に基づき機関評価を実施しました。
本報告は、調査研究を中心とした1998年度における当研究所の活動の概要をとりまとめたものであります。今後、機関評価を踏まえた必要機能の見直しを行い、調査研究等の活動を充実させていくこととしております。また、政府の決定した2001年1月の中央省庁改革に当たり新たに設置される文部科学省の下にあって、当科学技術政策研究所の役割は益々重くなっていくものと考えております。1998年度の活動もこのような大きな流れの中で位置づけていただければ幸いです。当研究所に対する皆様方の一層のご支援、ご協力を改めてお願い申しあげます。
1999年6月
科学技術庁
科学技術政策研究所
所長 佐藤 征夫
我が国は、21世紀を直前に控えて大きな転換期を迎えており、我が国の存立基盤を確実なものとしていくため、科学技術が果たす役割への期待が高まりつつある。このため、政府研究開発投資を対GDP比率で欧米主要国並に引き上げるべく拡充すること、我が国の研究開発システムを柔軟かつ競争的で開かれたものに抜本的に改善し、我が国の産学官全体の研究開発能力を引き上げること、研究成果を円滑に国民や社会、経済に還元していくことが科学技術振興の最優先課題となっている。
今後、科学技術のための政策に対するこれらの要請に応えていくためには、我が国の科学技術活動の動態と構造、科学技術を取りまく社会的な状況、国民の科学技術に対する意識などに関する深い洞察と分析がますます重要となっている。さらに、科学技術に対する要請の多様化に呼応し、地域における多様な科学技術の振興基盤に対しても、新たな視点に立った政策の展開が求められている。
また、地球環境、食糧、エネルギー等地球的規模でとらえるべき資源利用に係わる諸現象が現出しつつある中、21世紀において豊かで安定した国際社会を維持、発展させていくため、地球的な視野に立った資源の有効かつ適切な利用、そのために科学技術が果たすべき役割についての分析が必要となっている。
本研究所は、このような基本認識の下、「科学技術基本計画」を踏まえ、科学技術会議をはじめとする関係機関との密接な連携を図りつつ、科学技術活動及びそれに係わる諸政策に関する基礎的調査研究を多角的かつ総合的に推進することとし、当面、次のような調査研究業務を進めるものとする。
(I)課題対応型調査研究
科学技術政策の中で重要な位置付けが与えられていたり、あるいは今後、顕在化することが見込まれる課題を対象とする調査研究
イ.科学技術人材等の科学技術振興条件及び制度に関する分析
ロ.科学技術と人間・社会との関わりに関する分析
ハ.地域における科学技術振興及び科学技術の国際的展開に関する分析
ニ.政策立案及び政策形成過程に関する分析
(II)状況・方向性把握型調査研究
科学技術活動の状況及びその背景にある社会、経済等の状況を的確に把握し評価するとともに、将来の方向性を展望することを目的とする調査研究
イ.科学技術指標に関する分析
ロ.科学技術の動向及び将来予測並びに資源の総合的利用に関する分析
ハ.外国技術導入及び技術輸出の動向に関する分析
(III)理論展開型調査研究
政策分析・政策形成のための新しい概念や方法論の開発を目指して、科学技術政策に関する諸問題を理論的、実証的に解明し、政策研究基盤の構築・整備を図ることを目的とする調査研究
イ.技術革新プロセス、研究開発投資の経済効果等の科学技術の構造・動態や科学技術の経済社会への効果に関する分析
ロ.科学技術の研究開発推進システムに関する分析
ハ.体系的な科学技術指標の開発に関する理論的分析
このような調査研究はすぐれて国際性を有するものであることに鑑み、海外との情報交換、研究者の交流をはじめ、国際会議の開催、共同研究の実施、所内及び所外の有識者によるセミナーの開催等を積極的に進めることにより、科学技術政策研究における国際的なネットワークの構築に努め、本研究所の調査研究の効果的推進に資する。
さらに、科学技術政策情報データベースシステムの構築に資するため、科学技術指標データの定期的更新、イノベーションに関するデータの蓄積・分析を行い、データベースを整備するとともに、その維持改善に必要な情報処理システムの確立など、支援部門の整備充実に努めるものとする。
また、「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針」(平成9年8月内閣総理大臣決定)に沿って策定された「科学技術政策研究所における研究評価のための実施要領」(平成10年1月)に基づき本研究所の運営全般についての評価を行うため、外部有識者から構成される機関評価委員会(委員長:西島安則京都市立芸術大学長)を平成10年5月に設置した。機関評価委員会は、平成11年1月に評価結果の報告書を取りまとめたが、本研究所では今後、報告書において指摘された事項について、その具体的な取り組み方策についての検討を行うなど、評価結果を研究所運営に反映させていくこととする。特に、評価結果を踏まえつつ、今後10年間程度の科学技術政策研究の展望についての検討を行い、当面5年間程度の調査研究の進め方を含む運営方針を「中長期計画」として速やかに取りまとめることとする。
1999年3月末における本研究所の組織と任務は下のとおり。
1998年度末定員 46名
同年度参加客員研究官 延べ 14名
同年度参加特別研究員 延べ 23名(うち外国人研究者8名)
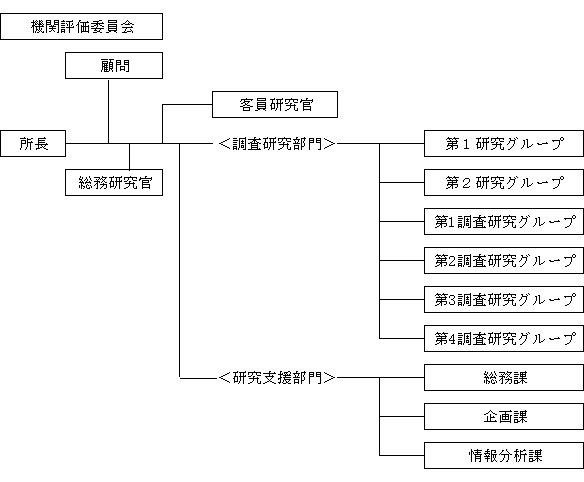
<研究グループ等の主な任務>
第1研究グループ :科学技術の経済社会への効果に関する理論的調査研究
第2研究グループ :科学技術の研究開発推進システムに関する理論的調査研究
第1調査研究グループ:科学技術人材等科学技術の振興条件に関する実証的調査研究
第2調査研究グループ:科学技術の人間・社会との関わりに関する実証的調査研究
第3調査研究グループ:地域における科学技術振興に関する調査研究
第4調査研究グループ:科学技術の動向及び将来予測に関する実証的調査研究
情報分析課 :技術貿易の動向に関する調査及び分析
注)1998年度の主な人事異動
第一研究グループ総括主任研究官:後藤 晃(1998年4月併任解除:一橋大学)
榊原 清則(1998年4月採用:慶應義塾大学)
企画課長:根本 光宏(1998年6月科学技術庁科学技術振興局へ転出)
植田 昭彦(1998年6月科学技術庁航空宇宙技術研究所より転入)
1998年度の予算を以下に示す。
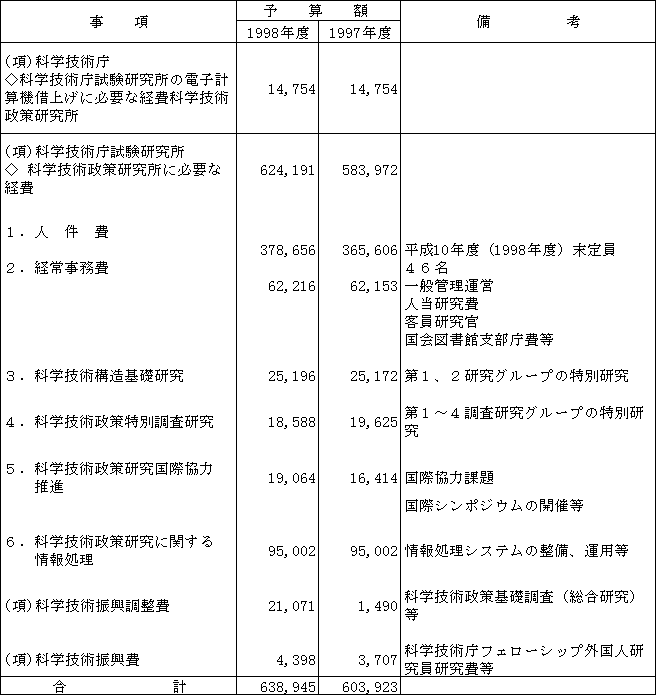
(単位:千円)
1998年度(平成10年度)第3次補正予算
(単位:千円)
|
事 項 |
予 算 額 |
備 考 |
|
インターネットによる研究成果公開の促進 |
60,480 |
報告書等の研究成果をホームページに掲載可能な形式に変換する。 |
- 国際会議
1998年10月8日〜9日科学技術政策研究所創立10周年記念国際コンファレンス
- 国内会議
1998年5月25日第一回科学技術政策研究所機関評価委員会
1998年6月24日第二回科学技術政策研究所機関評価委員会
1998年7月29日第三回科学技術政策研究所機関評価委員会
1998年8月26日第四回科学技術政策研究所機関評価委員会
1998年10月21日第五回科学技術政策研究所機関評価委員会
1998年7月1日科学技術政策研究所創立10周年記念式典
1999年3月16日〜17日平成10年度地域科学技術政策研究会
1999年3月26日第10回科学技術政策研究所顧問会議
- NISTEP REPORT
時 期
題 名
1998.5
<NO.57>「外国技術導入動向分析(平成8年度)」
1998.9
<NO.58>「日本の技術輸出の実態−平成8年度−」
1999.3
<NO.59>「地域における科学技術振興に関する調査研究(第4回調査)」
1999.3
<NO.60>「我が国製造業の空間移動と地域産業の構造変化に関する研究」
1999.3
<NO.61>「日本のベンチャー企業と起業者に関する調査研究−平成10年度」
1999.3
<NO.62>「2010年代の国民生活ニーズとこれに関連する科学技術」
- DISCUSSION PAPER
時 期
題 名
1998.10
<NO.7>「特許と文学論文の形態比較〜記述式・内容分析とインタビューによる執筆動因分析〜」
- 調査資料・データ
時 期
題 名
1998.4
<NO.53>「大学における新構想型学部に関する実態調査」
1998.5
<NO.54>「英国における研究評価−公的研究助成に見る評価”Value for Money”と”Selectivity”」
1998.6
<NO.55>「主要各国の科学技術関連組織の国際比較」
1998.7
<NO.56>「地域科学技術政策研究会(平成10年2月24日、25日)報告書−地域特性を生かした施策展開をどう進めるか−」
1998.6
<NO.57>英国及びニュージーランドにおける国立試験研究機関の民営化について
1998.8
<NO.58>テクノポリス調査研究報告書
1999.3
<NO.60>企業における女性研究者・技術者の就業状況に関する事例調査
- 講演録
時 期
題 名
1998.6
<NO.57>「韓国新政権下での科学技術関連政策の展開」
1998.4
<NO.58>「オランダの科学技術政策:行政と研究をむすぶ中間機構を中心として−「社会学的」科学技術政策研究序論−」
政策研主催及び(財)つくば科学万博記念財団の共催により、平成10年10月8日(木)から10月9日(金)までの二日間、星陵会館(東京都千代田区永田町)において以下のとおり当研究所創立10周年記念国際コンファレンスを開催した。
1.テーマ
科学技術政策研究の新たな挑戦 −グローバル知識社会を迎えて−
2.開催趣旨
21世紀を目前に控え、世界は人類が今世紀新たに手にした情報技術に支えられ、ますます知識社会への傾斜を強めている。経済活動がグローバル化した中で、産業活動は世界規模での大競争時代に入り、環境、食糧、エネルギー、資源等の従来からの世界的な課題に加え、特に我が国では高齢化、少子化社会への急激な移行も控えている。
この様な「グローバル知識社会」において、われわれはかって人類が経験したことがない速い変化と多様な課題や制約に直面し、既存の経済・社会システムのトレンド上の発想では、もはやほとんど対応が困難な状況に置かれている。
我が国には、世界の一員として、これらの課題に対処するための変革が、現在強く求められている。
このコンファレンスでは、科学技術を取りまく国際社会の将来を展望し、さらにその知見を具体的に政策立案過程につなげていくための新たな政策研究について、国内外の識者との議論を深め、21世紀の新しい社会システムに対応した科学技術政策研究のあり方について明確な指針を得ることを期待している。
3.構成
大臣挨拶、特別講演からなるPart1、将来の社会展望についての講演を中心とするPart2、今後の科学技術政策の課題とその中で政策研究が果たす役割についての議論を中心とするPart3の3部構成とした。
4.参加者
合計 322名
招待講演者 11名(日本を含む5カ国)
他 311名(一般参加者267名、当研究所関係者44名)
5.概要
Part1 開会挨拶と特別講演(司会:国谷 実 科学技術政策研究所総務研究官)
主催者を代表して佐藤科学技術政策研究所長より開会挨拶を行った後、竹山大臣よりの挨拶があった。その後、井村科学技術会議議員よりの特別講演が行われた。
竹山 裕(国務大臣・科学技術庁長官)
21世紀に直面する困難な課題の解決のためには、科学技術が大きな役割を果たしていく必要がある。科学技術創造立国のための政策の実現の基本となる政策研究に対する期待は大きい。今回のコンファレンスが21世紀の政策研究の発展の基礎となるような実り多いものになることを希望している。
井村 裕夫(科学技術会議議員)
テーマ:21世紀の科学技術ー生命科学を中心にー
科学と技術は、それぞれが別々の歴史をたどって発展してきたが19世紀後半から密接な関係になってきた。特に技術は、際限のない人間の欲望に基づいて発展してきた。現在の科学技術の重要分野としては、情報通信、バイオサイエンス、エネルギーの3分野があげられる。バイオサイエンスについては、個々の遺伝子機能の解明などにより、生物の進化、多様性などの生命の本質の解明を目指した研究が進んでいる。これらの研究の進展により、感染症の防止等の新しい診断及び治療技術の進展、人口増加に対応する食料生産技術の進展等が期待できる。21世紀は生物の世紀であり、生命に対する深い理解が必要であり、バイオサイエンスを今後どのように発展させていくかが大きな課題である。
Part2 シンポジウム:21世紀の社会展望
(司会:榊原 清則 科学技術政策研究所総括主任研究官)
「21世紀の社会展望」をテーマに、将来の科学技術政策を考えるにあたっての基礎となる将来の社会の展望について国内外の5名の有識者からの講演があった。さらにその後、講演者に対する質疑応答が行われた。
(1)Jerome Glenn(国連大学「これからの1000年プロジェクト」共同責任者、国連大学アメリカ評議会理事)
テーマ:これからの1000年
「これからの1000年プロジェクト」は、1994年に国連を中心として全世界的な規模で開始された未来研究であり、貧困の拡大、テロの凶悪化、情報技術の進展等の将来において予想される様々な可能性について、来世紀を展望する上で有益な指摘と提案を行っている。
(2)公文 俊平(国際大学グローバル・コミュニケーション・センター所長)
テーマ:21世紀情報文明と科学技術
コンピュータの「2000年問題」を克服した後に我々を待ち受ける21世紀の情報社会においては、知識分野における新しいバランスが生まれ、"智民(Netizen)"が中心的な役割を果たすことになる。また社会的なインフラとして分散型のNetworkが構築されることが予想される。
(3)Marjory Blumenthal(米国国家研究会議コンピュータ科学・情報評議会理事)
テーマ:情報技術と社会の変容
情報技術(IT)の進展は、これまで我々が描いていた素朴なユートピア的な未来像に対して修正を迫ることになるだろう。ITの進歩は予想以上の速さで社会を変容させるとともに新たな不確実性をもたらしており、IT社会の意味合いそのものをも変化させている。
(4)橋爪 大三郎(東京工業大学教授)
テーマ:2010年の若者像
21世紀においては、科学の果たす役割がますます重要になると予想され、その担い手としてより多くの優秀な若者の出現が期待される。しかし諸外国に比べると、現行の日本の社会制度及び教育制度は硬直的で、若者の科学離れを一層深刻なものとしている。
(5)桑原 輝隆(科学技術政策研究所総括上席研究官)
テーマ:世界各国における技術予測への取組み
わが国の技術予測は1970年に開始されて以来、大きな成果をあげている。近年欧米諸国を含む世界各地で、技術予測の重要性が認識され、各国においても実施され始めている。今後の技術予測においてはそれぞれの国における特徴、社会の特性に配慮しつつ、従来の実施方法を再検討していくことが必要である。
Part3 ワークショップ:科学技術政策の形成過程への貢献と今後の政策研究のあり方
(司会:平澤 科学技術政策研究所総括主任研究官)
英国、米国、独国、仏国及び日本において政策形成、政策評価などに関与するそれぞれの機関の代表者から、機関の役割、機能等についての講演を行った後、パネルディスカションを行い、政策形成過程へのより最適な貢献等のための国際比較等の議論を行った。
(1)平澤 (科学技術政策研究所総括主任研究官)
テーマ:導入講演
司会者からの導入講演として、今後10年間に科学技術をとりまく社会状況についての第1日目の議論のまとめが述べられた。続いて、科学技術政策と他の政策との相違点、各国の科学技術政策システムを比較研究するための枠組み等の議論のためのフレームが提出された。
(2)Luke Georghiou(英国マンチェスター大学工学・科学・技術政策研究所長兼教授)
テーマ:英国における科学政策への助言とマンチェスター大学工学・科学・技術政策研究所(PREST)の役割
英国の研究資金の流れと特徴、最近の政策の傾向、政策形成支援機関の概要、及びその一つであるPRESTの活動の具体例、例えば評価という文化を作っていったプロセスが紹介された。
(3)Bruce Don(米国科学技術政策研究所長)
テーマ:米国における科学技術政策の改善のための支援−分析において考慮すべきいくつかの将来の問題−
科学技術政策研究所(旧Critical Technologies Institute)の活動がどのように政策立案を改良、補助するかについての具体的な報告がなされた。例えば、研究開発、健康、環境、宇宙開発、教育各分野の政策分析をおこない、データベースを作成している活動等が報告された。
(4)Winfried Benz(独国学術評議会事務局長)
テーマ:ドイツの科学政策と連邦及び州政府に対する助言におけるドイツ学術評議会の役割
ドイツのシステムの特徴(連邦政府と州政府の並立的な関係)と大学および各協会ごとの研究所運営の概要が紹介されたのち、学術評議会の活動が紹介された。この機関は、1957年に設立され、科学技術政策の諮問活動を行うカウンシルとしては欧州で最も古い機関である。
(5)Alan Rodney(仏国教育・高等教育・研究・技術省 研究技術高等会議事務局長)
テーマ:フランスにおける助言及び助言者の歴史
政策の支援についての機能に関する考え方の説明があったあと、フランスの状況を説明するための独自の分類軸(政策のレベルと時間軸の2軸で構成される)をもとにフランスの各機関の付置付けと今後の変化の分析の説明があった。
(6)佐藤 征夫(科学技術政策研究所長)
テーマ:変わりつつある科学技術政策の枠組み
日本の科学技術政策の枠組みについて、科学技術基本法、科学技術基本計画、中央省庁等改革基本法等の最近の動向に触れつつ、科学技術会議の約40年の活動を中心に説明があった。続いて、国立研究機関の持つ研究実施と研究支援の二つの機能についての考えが述べられた後、科学技術政策研究所の使命及び機能についての説明があった。
パネルディスカッション
上記6名の講演者に下記の2名を加えてパネルディスカッションが行われた。
Don Kash米国ジョージ・メーソン大学教授
丹羽 冨士雄政策研究大学院大学教授(政策研客員総括研究官)
Kash教授から「次世紀におけるNISTEPの役割とは何か」という問題提起がなされた。そしてこの問題を考える上での科学技術の未来と情報化社会の未来についてのコメントが加えられたのち、「どのように予測できない対象をマネージしてゆくか」が今後の重要な課題であるとの提示があった。続いて丹羽教授より、政策内容分析、特に日本の科学技術会議の第11号答申を分析した例が紹介され、「各国における科学技術政策は総合的(comprehensive)になされているのか」という問題提起がなされた。さらに、政策内容の分析と政策システムの分析とを組み合わせることによって、政策支援を考える上での政策研究の枠組みが得られるのではないか、との問題提起がなされた。会場からは地域の科学技術政策のあり方、社会の意見を科学技術行政に反映してゆくシステムのありかた、宗教も含めた各国の文化風土と科学技術政策の関係、などについての質問が提起され、それぞれについてパネリストの意見が提示された。全般的に、21世紀の科学技術政策、そのなかでの政策支援のあり方と科学技術政策研究所の役割について示唆の多い議論が行われた。
1.科学技術政策研究所創立10周年記念式典
科学技術政策研究所は昭和63年7月1日に創立され、平成10年7月で10周年を迎えた。これを記念して、7月1日昼前、当研究所において科学技術政策研究所創立10周年記念式典を開催した。
科学技術庁からは、岡崎事務次官を初め官房・各局幹部、外部からは、井村・石塚科学技術会議議員、創立以降の歴代事務次官、政策研歴代所長、研究所顧問、客員研究官、旧在籍者等160名の方々にご参加を頂いた。
式は、冒頭佐藤所長の挨拶、政務多忙のためにご出席いただけなかった谷垣科学技術庁長官のご挨拶を岡崎事務次官が代読され、引き続きご自身の言葉で政策研に対する社会の期待の高さを述べられ、所長を初め職員の一層の活躍を期待する旨のご挨拶があった。さらに、石塚議員よりは、ご祝辞に加え、理論的な研究に加えて、具体的な社会のニーズに応えていくという政策研特有の成果を反映させることが重要とのご挨拶があった。
場所を改め、所内の懇親会場で、中原恒雄 政策研顧問(住友電気工業株式会社副社長)による乾杯のご発声で懇親を行った。
ご多用の皆様のご予定も考えて1時間あまりでお開きになったが、盛況裏に式典及び懇親会が終了することができた。
2.科学技術政策研究所創立10周年記念誌
「新世紀の深みのある政策展開を目指して」

A Collection Celebrating of the 10th Anniversary of NISTEP
当研究所は平成10年7月に10周年記念を迎えた。これを記念する行事として、10周年記念誌の発行等関連行事を検討するため、平成9年5月研究所内に科学技術政策研究所創立10周年記念行事企画委員会(以下「委員会」という。)を設置した。
委員会では、数次の審議を得て、10周年記念誌については当研究所の10年間の研究活動の成果を通覧するとともに科学技術政策研究の将来展望に目を向けた内容のものとするとの編集方針を決定した。
このため、谷垣科学技術庁長官、海外の政策研究機関の代表者を初めその衝に当たる方々から、ご祝辞を頂戴したほか、当研究所の創設や発展に当たりお世話になった方々の回想や提言を頂き、10周年を迎えるに当たり有意義な内容の資料とすることができた。特に科学技術政策研究所の記念誌に相応しく、21世紀の科学技術政策に関する長編論文を吉川科学技術会議会長とMeyer ? Krahmerドイツフラウンフォーファー財団ISI会長にご執筆を頂いた。
第3調査研究グループでは、平成11年3月16、17日に砂防会館(東京都千代田区)において、「平成10年度地域科学技術政策研究会」を開催した。本研究会では、都道府県及び政令指定都市の科学技術政策担当者等の参加の下、「科学技術を活用して地域再生に如何に取組むか」をテーマに、講演、報告及び討議が行われた。1日目は、富山国際大学の石坂誠一学長からの基調講演、科学技術庁の木阪崇司審議官及び通商産業省の羽山正孝審議官からの講演、本研究所における関係調査研究の報告並びに都道府県の政策担当者等からの施策展開についての報告が行われた。また、2日目は、本研究所の権田客員総括研究官が講演を行った後、参加者全員による自由討議が行われた。
本研究会には、36都道府県及び6政令指定都市から64人の科学技術政策担当者等の出席を得ることができた。本研究会の概要は次のとおりである。
1日目
−基調講演−
富山国際大学の石坂誠一学長(元工業技術院長)から「地域科学技術の振興と地域に展開する大学の役割」と題し、富山県における具体的な事例を挙げながら、「歴史的に見た地域と技術」、「農業技術の発展と地域性」、「売薬と現代医薬品製造業」、「富山県の金属加工業」、「富山県の新技術」、「中小企業振興」、「人間の重要性」、「地域科学技術振興の現状」、「地域の大学と科学技術振興」及び「地域を考える新しい大学への試み」等の内容にわたる講演が行われた。
―講演―
科学技術庁の木阪崇司審議官から「地域の科学技術政策について」、また通商産業省の羽山正孝審議官から「地域プラットフォームの整備について」との題名で、それぞれの省庁の施策に関連した内容の講演が行われた。
―本研究所からの報告―
中田上席研究官及び田中特別研究員から「地域における科学技術振興に関する調査研究(第4回)」に関して、休井特別研究員から「我が国製造業の空間移動と地域産業の構造変化に関する研究」に関して、また中田上席研究官から「地域科学技術指標策定に関する調査」に関して報告がなされた。
―地方公共団体からの報告―
北海道の山本主査から「北海道経済の構造改革と研究開発力・技術力」、山形県の阿部主査から「山形県の科学技術振興施策について」、広島県産業科学技術研究所の河野課長から「広島県産業科学技術研究所の活動について」と題して、各都道府県の科学技術振興施策に関連する報告がなされた。
2日目
―講演―
権田客員総括研究官から、「地方公共団体は科学技術の活用により地域再生に如何にして挑むべきか」と題した講演がなされた。
―自由討議―
上記の権田客員総括研究官の講演を踏まえて、参加者全員で「地方公共団体は科学技術の活用により地域再生に如何に取り組むべきか」というテーマに関して討議を行った。
1.評価体制等の整備
当研究所においては、「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針」(平成9年8月7日内閣総理大臣決定)を踏まえ、平成10年1月に「科学技術政策研究所における評価のための実施要領」及び「科学技術政策研究所機関評価委員会設置要領」を作成した。これらに基づき、研究所の外部から選任された評価者を構成員とする機関評価委員会を設置し、3年ごとに研究所の運営全般(調査研究課題全般も含む。)について評価することとした。
2.事前評価
機関評価に先だって、以下の事前評価を行った。
(1)所内の評価委員会による調査研究課題の評価
平成10年1月から2月にかけて、所内の幹部職員から構成される評価委員会において、政策研の設立以降、平成9年度末までの主要な調査研究課題についての評価を行った。この課題評価の結果は機関評価委員会に参考資料として提出した。
(2)2名の外国人専門家による事前の機関評価
平成10年3月、招聘した2名の外国人専門家(英国マンチェスター大学工学・科学・技術政策研究所のジョルジュ所長と独国フラウンホーファー協会システム・技術革新研究所のグルップ副所長)により、3日間にわたって事前の機関評価が行われた。この評価結果は機関評価委員会に参考資料として提出した。
3.機関評価
平成10年5月、西島安則京都市立芸術大学長を委員長とする機関評価委員会を設置した。委員長は、政策研所長より委嘱を受けたが、他の委員については委員長が所長に推薦をし、所長はその推薦を受けて委嘱を行った。機関評価委員会は、平成10年5月に第1回会合を開催し、同年10月までの約半年間に5回の会合を開催した。機関評価委員会は、政策研より提出された活動状況等についての資料についての検討を行った他、幹部職員との討議、行政側(科学技術庁)の関係者からの意見聴取等を実施し、報告書をとりまとめた。
4.機関評価の結果を踏まえた今後の対応について
今回の機関評価報告書において指摘された事項については、改善のための具体的な取り組みの方策についての検討を行い、実現に向けた努力を速やかに開始することとしている。また、機関評価の結果等を踏まえ、研究所の運営全般を含む今後5年間程度の活動計画を「中長期計画」として策定する予定である。
科学技術政策研究所機関評価委員会報告書の概要
1.はじめに
政策研の研究課題を含む運営全般についての評価を行うため、平成10年5月に西島安則京都市立芸術大学長を委員長とする10名の委員から構成される機関評価委員会が政策研に設置された。本委員会は平成10年5月から10月までに5回の会合を開催し、政策研の活動状況についての資料の検討、幹部職員との討議等を行い、報告書をとりまとめた。
2.機関評価にあたっての委員会の考え方
21世紀を目前に控え、科学技術政策の方向性を先見性を持って検討する必要性はますます増大しており、科学技術政策研究に対する期待は高まりつつある。本委員会は、この分野で中核的な役割を担うことが期待される政策研の運営全般について、設立以来過去10年間の活動実績を評価しつつ、今後10年間程度を展望して、政策研が将来のあり方を策定する際に反映できる意見をとりまとめた。
3.政策研の使命、機能及び役割
○ 政策研の使命は、政府の政策研究機関として、科学技術庁、科学技術会議などの行う国の科学技術政策の企画及び立案に貢献することにある。この使命を達成するために政策研が事実上兼ね備えている機能(①リサーチ機能、②データ分析・評価機能、③アドバイザリー機能、④トレーニング機能)を適切かつバランスよく活用していくことが重要である。
○ 具体的な活動にあたっては、その活動の成果の利用者が誰であるのかを意識し、活動目的を明確にした上で取り組むことが重要である。なお、その際に成果の利用者を公的な機関だけに限定するのではなく、産学官の全てに成果利用の対象者が存在するとの前提で考えるべきである。
○ 政策研の活動の成果が国の政策に一定の方向性を与え、行政庁における政策の企画及び立案に十分に生かされていくような努力が必要である。
4.過去10年間の活動実績の評価と今後の課題
科学技術立国を標榜する我が国において、政策研のような使命、機能を有する機関が設立され、存在してきたこと自体、大きな意味を持つものであり、この分野に多くの影響を与えてきた。本委員会の全般的な評価としては、政策研の活動はおおむね良好であり、また設立以降、この10年間でいい状況になりつつある。設立当初からの一定の経過を経て、現在は調査研究の体系化ができつつあり、管理部門を含めて定員46人の小規模な機関の最初の10年としては良好な成果を出している。
(1)調査研究
○ 重要と考える9つの調査研究分野(科学技術政策、技術革新過程/研究開発マネージメント、研究開発投資と経済成長、科学技術と人間・社会、地域科学技術政策、科学技術人材、科学技術と指標・統計、技術動向、技術貿易)についての評価を行った。
○ 調査研究活動は大きく①課題対応型調査研究、②状況・方向性把握型調査研究、③理論展開型調査研究の三つのカテゴリーに分類できるが、それぞれのカテゴリー毎に今後取り組むべき課題についてもとりまとめた。個々の調査研究課題の実施にあたっては、独立して分断されておこなわれるのではなく、政策研の持つ機能をバランスよく発揮しつつ横断的、総合的な観点からの取り組みがなされるべきである。
(2)組織及び人材
○ 調査研究部門における研究職と行政職をうまく組み合わせた現在の組織編成は、概ね良好に機能しており、今後とも研究職と行政職の双方の長所を活かしつつ、両者のベストミックスに配慮した組織とすることが必要である。
○ 科学技術政策研究に対する増大する期待に十分に応えていくためには、優れた能力を有した多様な人材の確保、増大のための努力が特に必要である。特に、調査研究の質の向上及び継続性の確保のため、職員の任期の長期化、客員研究官の増員、中核的研究者の育成等に努めるべきである。
○ 我が国の科学技術政策研究は緒についたばかりであり、連携大学院等による大学等の研究機関との連携を図りつつ若手研究者の育成、受け入れに取り組むことが必要である。
(3)運営
○ 国立の研究機関として民間のシンクタンクや大学等の研究機関と競合するのではなく、科学技術政策研究の推進のための総合力を発揮し、ユニークな活動に重点をおいた運営を行うことが望ましい。
○ 増大する調査研究課題に対応するため、調査研究の個々の性格に応じて、外部の調査機関等で対応できる部分についてはそれらの効果的な活用を図るなど、当研究所の資源は、情報を分析、加工、高度化する過程に集中して活用すべきである。このためには、当研究所の予算の増加を図るとともに、外部の競争的資金の導入、活用を図ることが必要である。
(4)外部機関との連携
○ 科学技術政策研究に関する産学官の組織化を推進する上で我が国の中核的な役割を担うことを期待する。
○ 国内外の関連機関との連携、情報交換を強めることが必要である。このため、例えばフリーゾーン(共通の研究の場)のような研究及び情報交流の場、拠点としての機能が必要である。また国際的に協調して解決すべき課題も増大しており国際協力の一層の強化を図ることが必要である。
(5)その他
○ 政策研の活動について広く理解を得るよう努めるとともに、成果物を政策の企画及び立案に適切に反映させていくための努力が必要である。
5.将来のあり方についての提言
○ 社会の状況の変化に適切に対応し、21世紀の社会システムに対応できる科学技術政策研究が行えるような体制の見直し、整備を図っていく必要がある。政策研においては、今後5年間程度の活動計画を「中長期計画」として策定するとの構想を有している。この構想は有効であると考えるが、より長期、例えば10年先を見据えた展望を含めることも必要と考えられる。この計画においては、本報告書において検討が期待されていることについて、その具体化のための方策が含まれることを期待する。
○ 科学技術政策についての政府の専門的な調査研究機関として、新たに設置されることが予定されている教育科学技術省の政策立案に寄与することはもちろん、総合科学技術会議における調査・分析などに対しても可能な限り貢献することが望まれる。
6.まとめ
科学技術政策研究をとりまく内外の状況は大きく変わりつつあり、それらの変化を的確に踏まえて適切に対応していくことが必要である。委員会は、本報告書において述べられている事項について、政策研において十分な検討が行われ具体的な取り組みがなされることを期待している。
(科学技術政策研究所機関評価委員会委員)
委員長西島 安則京都市立芸術大学長
池上 徹彦会津大学副学長兼NTTエグゼクティブアドバイザ
池澤 直樹(株)野村総合研究所産業コンサルティング部部長
小田切 宏之一橋大学大学院経済学研究科教授兼筑波大学社会工学系教授
笠見 昭信(株)東芝取締役専務
小林 信一電気通信大学大学院情報システム学研究科助教授
鳥井 弘之日本経済新聞社論説委員
弘岡 正明流通科学大学副学長
松本 和子早稲田大学理工学部教授
村上 陽一郎国際基督教大学教養学部教授
情報技術が知的生産性に及ぼす影響に関する国際比較
榊原清則
1.研究の目的及び性格
技術研究開発に従事する組織体において広義の情報通信技術(Information Technology、以下IT)が如何に利用されているか、その導入活用実態の調査と、それが組織の成果にどういう影響を与えているかを明らかにすることが本研究の目的である。
2.研究課題の概要
先端的なIT活用分野の例として、(1)インターネット技術を利用した部品、材料の調達活動、(2)製品開発における新世代3次元CADの利用、(3)企業の基幹業務への統合業務パッケージ(Enterprise Resource Planning、略してERPとよばれる)の利用をそれぞれとりあげ、特定事例の精査、関係者への聞き取り、質問票サーベイ等を組み合わせた調査活動を実施した。
また、利用可能な文献および資料を探索し、比較可能な欧米の事例の収集に努め、限定的な国際比較を試みた。
3.得られた成果・残された課題
まず上記の(1)については、科学技術政策研究所および慶應義塾大学大学院政策メディア研究科で鋭意調査し、関連データの収集をした。その結果、アメリカ企業と日本企業との間に、企業の資材調達面で、インターネット技術の活用実態が異なることが分かった。従来、ITの活用という点では各国ごとの違いを無視した収斂論が支配的である。ITの活用はやがて類似の組織実践に収斂するというのである。しかしこの種の収斂論は必ずしも正しくないことが、本研究では明らかになった。
次に(2)と(3)については、昨年度末から今年度初めにかけて、詳細な調査研究を実施中である。
4.特記事項
ITの意義をとりあげたのは政策研では初めてのことであり、まずは民間企業の活動におけるITのインパクトに焦点を当てた。大学や国研におけるITの意義の調査は今後の課題である。
5.論文公表などの研究活動
[1] 「ITを用いた資材調達活動の国際比較」をDISCUSSION PAPER No.9として1999年7月刊行予定。
研究開発の国際化における人事・組織管理とインフラストラクチャー
榊原清則、田中 茂
1.調査研究の目的及び性格
日本における研究開発の国際化は今後ますます進展すると予想されるが、本研究は人事・組織管理およびインフラストラクチャーを如何にしたら外国人研究開発者を引きつけ、またその能力を最大限に引き出せるのか調査・研究する。
2.研究課題の概容
[問題の設定]
(1)日本国内の国立試験研究機関、特殊法人研究開発機関、および民間企業における研究開発国際化の現状調査
(2)国際的研究開発組織の国内立地と国外立地の場合の人事・組織管理およびインフラストラクチャー上の差異調査(民間企業のみ)
(3)国際的研究開発組織の構成員に対する人事・組織およびインフラストラクチャー上の問題点と希望に関する調査(国研、特法、民間企業)
[問題設定概容]
日本国内の研究開発国際化の実状を調査し、外国人研究者から見て日本国内の研究開発環境の魅力を高める上で何が支障となっており、どう改善すべきか試案を提示する。
3.得られた成果・残された課題
平成11年2月〜3月に実施した国研、特法、民間企業に対するアンケート調査により日本国内における研究開発の国際化の現状や研究開発国際化に関する問題点、希望が得られつつある(現在集計中)。
4.特記事項
日本国内の外国人研究開発者に関する包括的情報は実務担当者の知る限りではみたことがない。従って、日本国内の外国人研究開発者の実状を調査研究することは多分今回が初めての試みではないかと思う。
5.論文公表などの研究活動
[1] 田中 茂:「日本企業の研究開発国際化の実状と国内研究開発体制への提言」をDISCUSSION PAPER No.8として1999年6月刊行予定。
[2] KIBA,T. and Collins,S.:「R&D performance in Japanese companies: a relative evaluation of overseas-based and domestic R&D」Science and Policy,25(1998),227.
半導体エンジニアの流動性に関する研究
榊原清則、青島矢一(一橋大学)
1.調査研究の目的及び性格
本研究は、国のイノベーションシステムを構成する重要な要素としてR&D人材の「流動性システム」に注目して、半導体の技術開発に関わる研究者・技術者を対象にした大規模質問票調査を基盤とした実証研究である。ここで「流動性システム」とは、R&D人材の組織間移動、専門領域間移動、機能分野間移動、地理的移動などの個々の移動パターンを構成要素としてそれらの間の相互関係を含むシステムを指している。この流動性システムの違いがイノベーションパターンとどのような関係にあるのかを明らかにするのが本研究の目的である。
2.研究課題の概要
技術的先端領域の研究者・技術者の流動システムとそのイノベーション活動との関係を明らかにするために、本研究では2つの方法で調査活動が行われた。1つは質問票調査である。学会名簿からランダムサンプルされた5000人の半導体エンジニア、半導体研究者に対して質問票を配布した。質問票では、企業間移動、地理的移動、専門分野間移動、機能部門間異動、アプリケーション分野間移動など8つの軸に沿った移動経験に関する設問を年表形式で用意した。もう1つの方法は、半導体企業で人材管理に関わっている人へのヒアリングである。大手半導体メーカー3社に対するヒアリングが行われた。ヒアリングの内容は質問票分析の解釈において活用されている。
3.得られた成果・残された課題
質問票に対しては約900人からの回答を得た。データは現在分析中である。初期分析では、回答者の内約4割の人は少なくとも一度は転職の経験があるという事実や、研究部門と開発部門の間でのローテーションの存在などが確認されている。今後さらにデータ分析を行っていく予定である。ヒアリングからは大手の半導体メーカー間では人材の移動が極めて少ないこと、また部門間では移動があり、特に近年の組織変革に伴って人材の戦略的な異動が検討されていることなどがわかった。
4.特記事項
本研究の特徴は流動性をシステムとして把握している点である。従来の研究は、組織間移動、地理的移動、組織内部門間異動をそれぞれ別々の現象として、社会学、経済学、組織論、人的管理論など異なるディシプリンの下で行われてきた。それに対して本研究では、イノベーションとの関係で流動性をとらえるためにそれら異なる移動を全て同じ土俵のもとで扱っている。こうした視点から行われた大規模調査は前例がなく、今後は海外での同様調査との国際比較に発展させていく予定である。
5.論文公表等の研究活動
平成10年度はなし。
研究開発過程の構造化分析
伊地知寛博
1.研究の目的および性格
本研究は、研究開発の機構論に属するもので、研究開発過程の実態をミクロ・レベルで捉え、研究開発の動的過程をシステムとして構造化し、その構造的特質から明らかにすることを目的としている。研究開発のメカニズムを明確にすることは、研究開発マネジメントを構想するうえできわめて重要である。本研究は、構造化の方法論を用いることで分析の客観化を意図している。
2.研究課題の概要
本研究では、これまでに本担当者らが開発してきた分析の方法論を用いて事例分析を行う。分析には研究開発のアウトプットを構成する学術文献および特許のデータベースを用い、学術文献や特許に表れる研究者・技術者の氏名を手がかりとして研究開発の組織過程を構造化して表現する。なお、この間、研究開発マネジメントの視点から各種の対象技術について分析を推し進めるとともに、政策分析への適用を考慮してきた。
3.得られた成果・残された課題
LCDについて、生産あるいは研究開発を行っていた主要な組織については全容を捉えるべく、これまでに、日米欧韓計16社・機関について分析を進めてきた。分析から、同一の技術に関する研究開発でありながら、組織によって研究開発過程にさまざまな形態があることが明らかになってきた。また、組織の中にLCDの研究開発に一貫して従事して、組織としての新たな知識・技術の生成をしていくコアとなるキーパーソンが存在して、しかも、その組織として持続して研究開発を行ってきている企業が、現在、LCD事業において主要な位置を占めていることがわかってきている。さらに、この人的資源としての研究者・技術者の蓄積と活用に関するマネジメントという観点から、当該技術分野のみならず関連する技術に関する知見を有する研究者・技術者を適切に共同・連携させ、ある程度の長期間、当該技術の研究開発に従事させることによって、人に体化された知識・経験を組織的に統合して利用していくことができることがわかってきた。この場合、過去の他の技術分野での活動からは直接的成果を生み出していなくとも、当該技術から見れば研究開発能力の蓄積を意味し、当該技術に関する活動を通して利用された、と見ることができる。なお、所見の補完等を目的として、先端的な技術開発をめざして近年になって新たに独自の展開を示している日米の企業もさらに対象に加えて、現在、分析を進めている。
4.特記事項
特になし。
5.論文公表等の研究活動
[1] Ijichi, T. and Hirasawa, R.「R&D organizational process on liquid crystal display : an internationally comparative analysis based on patents.」Proceedings of the Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, Portland, Oregon, USA, July 25-29, 1999, in press.
分野別研究開発投資行動の分析:技術融合下におけるシュムペーター仮説の検討
榊原清則、原田 勉(神戸大学)
1.調査研究の目的及び性格
本研究の目的は、日本製造業における研究開発投資行動を規定する経済的・技術的要因を明らかにすることである。研究開発投資は、企業の新製品開発やコスト削減などその競争優位性に大きな影響を及ぼす要因であると考えられる。本研究では、この企業レベルでの研究開発投資行動を分析対象とし、それが市場競争や技術的環境などによってどのような影響を受けているのかについて考察することにより、望ましい科学技術政策の在り方について新たな知見を得ることに主眼を置いている。
2.研究課題の設定
エレクトロニクス、機械、化学などの技術分野別の研究開発投資額の配分がどのような要因によって規定されているのかが本研究で取り上げる主要な問題である。ここで検討する主な仮説はシュンペーター仮説と呼ばれるものである。シュンペーター仮説とは、企業規模、市場支配力と研究開発投資額とは各々正の相関があるというものである。本研究では、この仮説を技術分野別研究開発投資額やその配分比率と企業規模、市場支配力との関連性がどのようなものであるかを主として検討することにより、シュンペーター仮説を新たな視点から再考する。
3.得られた成果・残された課題
本年度は、技術融合に関する先行研究を精読するとともに、総務庁「科学技術研究調査報告」に記載されている他業種への研究開発支出状況を概観し、それらの決定要因について、産業レベルで考察した。しかし、技術融合の決定要因は、企業レベルの特性に左右される可能性も高いので、今後は、ミクロデータの利用可能性を追求することとしたい。
4.特記事項
特になし。
5.論文公表等の研究活動
特になし。
知的ストックの成長が国際経済に及ぼす波及効果に関する研究
古賀款久、永田晃也(北陸先端科学技術大学院大学)
1.調査研究の目的及び性格
研究開発投資を通じて形成される知的ストックは、他の経済主体に正の便益をもたらすと言われている。このようなスピルオーバー効果が経済成長および生産性に与える効果を、閉鎖経済および開放経済体系の中で、定量的・定性的に把握しようというのが本研究の主眼である。
2.研究課題の概要
経済活動のグローバリゼーションの進展に伴い、科学技術と経済成長の関連においても、ますます国際的な相互依存関係が重要性を増している。研究開発投資が形成する知的ストックは一国内における生産性の高度化等に寄与するばかりではなく国際的なスピルオーバーを通じて他国の経済成長に多大な影響を及ぼす場合がある。本研究では、知的ストックのグローバルな分布状況を定量的に把握するとともに、地域間における知的ストックの相互依存的な経済効果を評価するための理論的・実証的分析を行い、開放経済における科学技術政策のあり方を議論することを目指す。
3.得られた成果・残された課題
知的ストックの成長、あるいはイノベーションは、経済成長の重要な要因の一つであるが、近年欧米に於いては、他国で開発された新技術・知識が、貿易・人的交流などを通じて国内に流入し、一国の経済成長を促進しうる点について、分析が進んでいる。本年度は、「知的ストックの蓄積と内生的経済成長」および「知識の国際的なスピルオーバー」に関する理論的・実証的枠組みを概観するとともに、過去に当研究所が開発したマクロ計量経済モデルの開放経済体系への拡張可能性について追求した。また並行して、企業レベルのデータに立脚した実証分析の可能性についても検討した。
4.特記事項
特になし。
5.論文公表等の研究活動
特になし。
研究開発と税制
古賀款久
1.調査研究の目的及び性格
本研究は、民間企業の研究開発投資を促進する目的で創設された試験研究費税額控除制度の有効性について、特に、増加試験研究費税額控除制度の投資促進効果を対象に考察することを主眼としている。また、諸外国の研究開発関連税制の特徴を整理し、わが国税制改革の判断材料を提供することを
も目的としている。
2.研究課題の概要
本年度の課題は、増加試験研究費税額控除制度の投資促進効果を、企業レベルのデータを用いて考察することである。本研究は、同制度が、企業の研究開発投資を実際に促進したのかどうか、また、もし促進していなければ、その制度的欠陥はどこにあるのか、について考察する。
3.得られた成果・残された課題
本年度は、増加試験研究費税額控除制度の投資促進効果を、企業レベルのデータを用いて考察した。同制度を通じて追加的に実施された研究開発投資は、減収額との比較で見ると、必ずしも我々の期待に沿うような効果をもたらさなかった。これは、一つは、同制度の適用が、企業の過去のパフォーマンスに制約されるという点によるものである。それゆえ、本年度の税制改革により、制度適用の基準となる過去の最高額の定め方に修正が加えられたのは朗報と思われる。ただし、推計方法、定式化などに問題が残っているため、今後はより正確な推計を目指すこととしたい。
また本年度は、上記課題と並行して、諸外国の研究開発関連税制について整理した。税額控除制度の対象となる試験研究費の範囲、繰り延べ・繰り越しの有無、等、各国税制にはかなりの相違が見られるが、これらの相違が、一国のR&D水準にどの程度の差異をもたらしているか、については、今後の調査課題としたい。さらに、今後は、わが国を含む各国の取得技術(特許権・ノウハウ等)に対する税制上の取り扱いに関しても整理し、技術取引と税制についての理解を深めたい。
4.特記事項
特になし。
5.論文公表等の研究活動
[1] 1998年度日本経済学会秋期大会(1998年9月12日:於:立命館大学琵琶湖キャンパス)において「増加試験研究費税額控除制度の有効性」論文報告
ベンチャ−ビジネス支援政策に関する研究
榊原清則、近藤一徳、前田昇、田中茂、古賀款久、綾野博之
1.研究の目的及び性格
本研究は、ベンチャービジネス支援のために講じられている多種多様な公的施策の意義を検討するために、その前提として、日本のベンチャー企業およびそれを担う起業家自身の特徴、概要など実態把握につとめ、米国のそれとの違いを究明することを目的とする。
2.研究課題の概要
本年度は、まず前半において、関連する資料の収集、文献調査を広範に進めた。また、適宜ベンチャービジネス経営者、創業者、ベンチャーキャピタリスト、業界関係者、ならびに政策関係者にインタビュー調査を行い、実態の把握に努めた。
その上で、年度後半の9月以降、大規模で体系的な郵送質問票をデザインし、それを送付、回収、データ分析をおこない、その結果を主として記述的な研究成果としてまとめ、報告書を作成した。
3.得られた成果
質問票サーベイの結果は、わが国でほとんど初めて、ベンチャー企業および起業者の体系的実態把握を行ったものとして、既に高い評価を得ている。
それによると、日本におけるベンチャー企業の創業は、新規上場会社数や開業率などの数字では低調に推移しているが、われわれのデータでは、上場志向をもった新規創業については着実に増えていること、それを支えているのは従来の銀行融資一本ではなく、公的支援をも含む「多元的」な支援構造であることがわかった。
4.特記事項
上記の調査結果をベースに、今後、より絞り込まれた仮説を立てて、それを検証するタイプの調査研究を進めるとともに、科学技術ベースのベンチャー企業に特に焦点を当てた調査を続行する計画である。その過程で、大学や国公立試験研究機関の意義も検討したい。
そして、国全体の知識生産システムの変容に与えるベンチャー企業の役割を、欧米諸国との比較においてさぐる構想を持っている。
5.論文公表などの研究活動
[1] 「日本のベンチャー企業と起業者に関する調査研究」NISTEP REPORT No.61として1999年5月刊行予定。
[2] 「ベンチャービジネス;日本の課題」POLICY STUDY No.2として1999年5月刊行予定。
[3] 「新ビジネスモデルによる日本企業の強さの変革−「科学技術・新産業創造立国実現」へのシナリオ−」POLICY STUDY No.3として1999年5月刊行予定。
研究開発関連政策が及ぼす経済効果の定量的評価手法に関する調査
(科学技術振興調整費調査)
榊原清則、伊地知寛博、古賀款久、永田晃也(北陸先端科学技術大学院大学)
1.調査研究の目的及び性格
本研究は、政府研究開発投資ならびに研究開発関連政策がどの程度、企業の研究開発投資を促進しているのか、あるいは、どの程度、わが国の経済成長に寄与しているのか、について、マクロ経済モデルを通じて定量的に評価するための基礎資料を提供することを主眼としている。
2.研究課題の概要
本研究では、過去に科学技術政策研究所において開発されたマクロ経済モデルをより精緻化し、様々な政策シミュレーションに対応出来るようにすることを目指している。本年度は、マクロ経済モデルの精緻化に不可欠ないくつかの変数―技術の陳腐化率・研究開発投資の懐妊期間―を収集するために、企業・大学・試験研究機関を対象とした大規模な質問票調査を実施するとともに、質問票調査を通じて収集された諸情報を基礎に、研究開発投資というブラックボックスの中身を探ることを目指す。
3.得られた成果・残された課題
技術の陳腐化率は、企業では平均8.7年、また大学等研究機関では12.1年であり、民間企業については先行研究とほぼ同程度であったが、公的研究機関については、若干長くなっている。また海外からの導入技術の寿命は、5年程度と国内技術よりかなり短いことが明らかになった。一方、研究開発の懐妊期間は、民間企業6年、研究機関9年と既存研究に比べて長くなっていることが明らかになった。これらの変数を入れ直したマクロ経済モデルの再推計、および、研究開発関連政策の経済効果については、現在分析中である。
4.特記事項
技術開発あるいは研究開発投資は企業特殊的な要素が強く、望ましい政策のあり方を検討する上では、マクロレベルの視点とミクロレベルの視点の双方が不可欠である。本研究は、研究開発関連政策の有効性について、マクロ経済モデルを用いた推計を進めると同時に、質問票調査に立脚したミクロレベルの視点を提供するという点では、類を見ない画期的な調査と言える。
5.論文公表等の研究活動
[1] 「研究開発関連政策の及ぼす経済効果の定量的評価手法に関する調査」1999年7月刊行予定
政策形成・研究開発実施過程における産学官のインタラクションに関する研究
(科学技術振興調整費流動促進研究制度)
伊地知寛博、榊原清則、平澤 、富澤宏之、藤垣裕子
1.研究の目的および性格
本研究は、科学技術政策の形成・執行過程および研究開発の実施過程における産業界と政府・公的研究機関・高等教育機関とのインタラクションについて、我が国にとって将来的に有効になると思われるシステムに関する含意を得ることを目的とする。
2.研究課題の概要
本研究は、政策形成・執行過程におけるインタラクションに関する、主としてマクロ・レベルの調査研究と、研究開発の実施過程における、主としてミクロ・レベルの研究から構成される。前者では、主要諸外国で実施されているインタラクションのシステムを、既存文献・資料等の調査のみならず、代表的な組織・機関等でのインタビューを通して実態の情報を収集し、比較分析を行う。あわせて、日本の現状とも対比させる。後者では、産学官の連携による研究開発の事例を取り上げ、特許・学術文献等の知的成果物に関するデータを収集し、これらを用いて、その形成動向を構造化して表現して分析する方法論等を援用して個人レベルでの研究開発組織過程を明確にするとともに、データのより詳細な整理・分析や、分析対象の研究者・技術者および関係者へのインタビューを通じて、その実態を明らかにする。
3.得られた成果・残された課題
本年度は、マクロ・レベルについては、現在、政策形成過程において産学官のインタラクション・システムに関して先導的な取り組みを行っているイギリスを対象として、主要な機関を訪問してインタビューを行うとともに、資料・文献等の収集を行い比較分析を進めてきた。たとえば、公的機関の運営に関するコーポレート・ガバナンスの構造や、独立して自発的に研究者の意見を代表して表明し政策形成に影響を与える機関、機関・委員会等の各代表者の選定に見る全体からの代表性の確保、政策形成における調整や情報交換の形態といった点に大きな差異が見られることがわかってきている。
また、ミクロ・レベルについては、構造化分析に先立って、まずデータベース検索を実施し、通常の統計からでは把握できない研究開発の実施局面でのインタラクションが、ミクロ・レベルでのデータから数量的に読みとれることを確認した。そして、統計上では不明であっても、個別には大学と民間企業の研究者による共同発明が多くありその形態も多様であるという実態や、成果に関する知的所有権の保有形態も種々あることを、データから示すことができた。
4.特記事項
特になし。
5.論文公表等の研究活動
特になし。
A Comparative Analysis of Network Dynamics in Environmental Policy and Technological Development(環境政策と技術開発におけるネットワーク・ダイナミクスの比較分析)
Mark Borden (STA Fellow:Manchester University, PREST)
1.調査研究の目的及び性格
本研究は、環境政策と戦略的技術政策との関係を分析することを目的とする。その際、特に、日英建設業を調査対象として、国の政策が、企業における環境にやさしい技術(Environmentally friendly Technology)の開発と採用に及ぼす影響を考察する。本研究の最大の目的は、政策・市場および技術の三者の関係を、ネットワークの形成とそれに伴う知識フローに焦点を当てて検討することである。
2.研究課題の概要
近年、科学技術政策の分野においては、環境への配慮とそれらの配慮が科学技術の発展に与える含意が、重要な課題となっていると同時に、このような関心は、環境政策と技術開発に関する調査を推進させている。本研究は、(1)環境政策と技術開発・技術普及とが実際にどの程度関連しているのか、(2)企業の技術開発戦略は、環境政策にどの程度反応しているのか、(3)市場におけるダイナミクスと環境政策とはどの程度影響し合っているのか、等の問題を検討し、政策的な含意を導くことを目標とする。
3.得られた成果・残された課題
日本の環境に関する政策の枠組みや産業界の動向、ならびに建設業における技術的イノベーションの展開について整理するとともに、建設業の主要企業や設計事務所および公益企業を対象としたケース・スタディを行った。そして,比較分析のためのフレームワークとして、(1)技術開発と環境政策の相互依存性,(2)企業における技術戦略と環境政策、(3)技術開発の方向と組織化、(4)環境政策による市場動向への影響およびその逆の影響,といった諸点に関する多くの分析視点を得た。今後は,イギリスにおいて、いくつかの指標をとって定量的な分析を進め、さらに分析を拡大しかつ深化させて比較を行って、論文等の公表を行うこととしている。
4.特記事項
特になし。
5.論文公表等の研究活動
[1] Mark Borden: 「Network dynamics in environmental policy and technological development:the construction industry in Japan and the U K」Seminar Presentation, Tokyo Institute of Technology, July 16th 1998
海外主要国の科学技術政策の形成過程と科学技術戦略に関する研究
平澤 、富澤宏之、藤垣裕子、
樟 良治、武内信雄、伊地知寛博
1.調査研究の目的及び性格
本研究は、我が国の科学技術政策システムにおける弱点の克服を図るために、諸外国で有効に機能している制度や運営の仕方について、実態的な調査を行い参考にすることを目的としている。特に、従来、我が国の科学技術政策システムは戦略的政策の形成機能、および社会一般からの要請を政策形成に反映させるメカニズムの働きが弱かったため、総合科学技術会議の設置をはじめとする行政機構の改革を実質化する過程で、これらの弱点の克服を図る際の参考となるような研究成果を得ることを目指している。
2.研究課題の概要
海外主要国の科学技術政策システムを対象に実態的な調査を行い、比較・分析を行った。その際には、単に基礎的情報の収集にとどまらず、科学技術政策形成の過程やその組織原理にまで踏み込んで明らかにするために、以下の諸点を中心に調査を行った。
・科学技術関連政策全体を一元的に統合するためのメカニズム。
・戦略的科学技術関連政策形成を担う組織と運営の仕方。
・複数の省庁間で、科学技術関連政策の分担を決める基準や組織、運営方策。
・原子力、宇宙などの長期大型開発課題の取り扱い方。
・基礎的研究分野の分野間のバランスや重点分野の策定の扱い方。
・上記の課題の運営を担う人材の育成・集積メカニズム。
・市民、生活者、社会一般からの科学技術に対する要請を政策形成に反映させるメカニズム。
3.得られた成果と残された課題
我が国の科学技術行政体制に参考にすべき点として、以下のような調査結果を得た。
(1) 意思決定者に対する補佐機能と情報集約機能の充実
米国の科学技術担当大統領補佐官は、大統領と毎週会う機会を持ち補佐機能を果たすと共に、彼が長を務めるOSTPがメンバーの共有メカニズムを介して情報集約機能を担っている。
(2) 戦略形成のための行政機関内外の支援体制の充実
米国には、STPIやCRSのような調査・分析を担う専属の支援機関のほか、アカデミー、学会、シンクタンク等が多様な支援機能を提供している。
(3) 政策立案を担うテクノクラートや専門的アドバイザーの養成
米国では学会から行政機関や議会に人材を派遣するフェローシップ制度やアドバイザーの集積を助けるグランド等が充実している。
(4) 行政組織と研究組織の中間に位置する組織(政策執行中間機構)の充実
独国のDFG、プロジェクト・エイジェンシー、マックスプランク研究協会のような、行政と研究現場の円滑な開発を維持するために、固有の政策執行機能をもった多様な組織が欧州諸国では発達している。
(5) 多元的チェック体制と循環的評価制度の充実
米国では、議会、行政、アカデミー相互間、さらには議会内部、行政内部の各レベルで相互チェックが行われ多元的な意思決定システムが実現している。また、欧州諸国では、社会を構成する各界からの代表者から成るパネルが同様の機能を担い、政策の客観性の向上及び多様な意見の反映に効果を発揮している。そして、このような体制のもとで、米国のGPRAのような事後の業績評価を中心とした循環型の評価システムに移行してきている。
一方、残された課題としては、議会や各種外部支援体制など、行政組織以外の科学技術推進システムの実態について、今後、本格的な調査が必要である。また、今回対象とした行政組織についても、絶えず続く変化に追随して情報を的確に把握分析していくためには、継続的な観測システムを整備する必要がある。さらに、今回の調査で対象とした政策形成システムの他に、それを運用するアクター(人)、運用すべき内容(コンテンツ)、運営システムについて分析を深める必要がある。アクターに関しては、特に、科学技術推進体制を担う実務的専門家をどのように養成し集積していくのかについて、各国の実態を参考にしつつ、問題点の認識を深める必要がある。コンテンツについては、戦略的政策課題の展開方向やその背景状況についても常時分析が必要である。運営システムについては、戦略計画の作り方、評価のあり方、等の理解が重要な課題として残されている。
4.特記事項
海外主要国の科学技術政策に関する調査は、従来から行われているが、本調査では、単に基礎的情報の収集にとどまらず、科学技術政策形成の過程やその組織原理にまで踏み込み分析する点に特徴がある。
5. 論文発表等の研究活動
[1] 科学技術振興調整費報告書「海外主要国の科学技術政策形成実施体制の動向調査」(調査報告:平成10年3月)1998年11月。
[2] 平澤 冷、富澤宏之、樟 良治、伊地知寛博、「主要各国の科学技術政策関連組織の国際比較」(調査資料・データNo.55)、1998年6月。
[3] 平澤 冷、伊地知寛博、富澤宏之、藤垣裕子、田中洋一、樟 良治、大熊和彦「原理的特徴から見た科学技術政策推進システムの比較研究」、研究・技術計画学会、第13回年次学術大会講演要旨集、pp.409-414(1998)。
科学技術の国家戦略目標形成のための調査
平澤 、藤原直也、富澤宏之
1.調査研究の目的及び性格
我が国の科学技術政策としては、近年大きく変化している社会と科学技術活動の実態に適合し、かつ将来の変化にも対応しうる、戦略的な政策が重要になってきている。しかし従来の日本の科学技術政策には、戦略的な構想が欠けており、またそれを支えるような政策研究も十分になされてこなかった。本研究は、いわゆる持ち寄り型、調整型、トレンド延長型といった従来の政策形成の枠を越え、社会的・人類的課題に対応しうる戦略的政策策定のための基盤的調査を目的としている。
2.研究課題の概要
戦略的な科学技術政策を策定するためには、世界と社会の状況を把握し、社会的・国家的・人類的な課題の明確化を一方の基礎とし、他方で研究・技術開発活動の実態と科学技術の進展についての把握が重要である。これらに関する研究を基礎として、次のような研究開発課題を展開させる必要がある。すなわち、研究開発の人材・資金の総量や最適配分を論じる研究開発資源論、組織や制度のあり方とその運営システムを論じる研究開発制度論ないし研究開発マネジメント論、さらには実際の政策形成に結びつけるために、戦略的な研究開発システムモデルの構築が必要である。
3.得られた成果・残された課題
(1) 「メガトレンド」調査(問題点の整理と内在論理の調査)
将来展望や近未来予測文献等から、メガトレンドの内容・信憑性を探り、問題点を整理した。
(2) 発想・展開法の検討 (価値開発手法の調査)
漠然とした目標を、具体的アクションプログラムにブレークダウンしてゆくプロセス等について、価値を発想(展開)してゆく方法論について調査し、手法を明らかにした。
(3) 国家戦略目標形成システムの検討
科学技術の国家戦略目標の形成を担う、機構、組織、制度のあり方について、我が国の状況を考慮し、それに適合するシステムについて検討を深めている。
(4) 統合価値評価法の検討(全コスト指標による、持続成長ある社会へと誘導する仕掛けの検討)
総合的政策形成手法構築のための事例的方法論について検討を深める。
4.特記事項
特になし。
5.論文公表等の研究活動
[1]Hirasawa, R.「Economic Crisis and Recent Performance of Science and Technology in Japan」 Congressional Research Service Seminar, 「The Asian Economic Crisis and Pacific Rim Science and Technology」CRS Washington DC. USA, December 1, 1998.
科学技術の形成過程における評価に関する研究
平澤 、舘 和夫、樟 良治
1.調査研究の目的及び性格
本研究は、研究開発活動のキー要素である機関、課題、人材の評価に関する理論的研究並びに国内及び海外の研究評価状況の実態把握を目的とする。また、さらに広い視点に立ち、国の科学技術政策を形成する過程における評価についても調査する。
2.研究課題の概要
科学技術基本計画において、研究開発活動を活性化し,優れた成果をあげていくため、研究開発機関及び研究開発課題の評価を行うとともに研究者の評価を行うことが謳われているとおり、組織、課題、人材の評価は研究開発活動のキー要素である。しかし,一般に広く使える確立された方法がなく、また、欧米に比較して我が国ではこの種の研究は盛んではない。そこで、公的機関に比較し、予算的、人事的制約の少ない民間研究開発機関における最近の研究開発マネジメント動向を調査するとともに、欧米における評価法についても調査を行い、それらの手法を公的機関に適用する際の考察を行う。
3.得られた成果・残された課題
本年度は、ドイツ、フランス、及びアメリカにおける、公的機関(内閣、省庁、研究所、助成制度を含む)の政策形成過程を含めた評価に係る組織、制度、体制、運用について文献調査及び現地調査を行った。
また、評価の原理的アプローチとして、人間活動に主眼をおいたシステム論、組織論等を基本とした評価論を別途構築しているところである。
4.特記事項
特になし。
5. 論文公表等の研究活動
[1]Hirasawa, R.「Evaluation of Publicly-Funded R&D: Basic Issues and Trends in Management」The International Workshop on Evaluation Systems for Government-funded R&D Projects and Programs, Tokyo, Japan, March 5, 1999
公共科学技術政策における経営改革推進のための評価の在り方
平澤 、武内信雄
1.調査研究の目的及び性格
公的科学技術関係研究開発機関が求められる使命を果たし、国として効果的・効率的な科学技術を振興するために必要な経営改革を推進するため、評価としてどんな体制で何をすべきか2年先程度を見た実施方策に関する研究を行う。
2.研究課題の概要
科学技術基本法以降の諸活動により我が国の組織改革の大枠が明らかにされ、次段階として、著しい科学技術の発展に対応すべく、国はこれまでの枠組を変えるための経営改革に動き出している。科学技術政策研究所は「科学技術の形成過程における評価に関する研究」で得られた評価の枠組み全体についての知見を基に、経営改革につなげる程に評価の議論を深める必要を認識した。
そこで、本研究では政策形成全体の動きをフォローしつつ、日本の評価の現状を調査・検討し、諸外国(特に、米国)の評価の現状を調査・検討し、日本の政策評価システムがどうあるべきかを考察することで、効果的・効率的な公共科学技術政策実施に必要な経営改革を推進するため、評価としてどんな体制で何をすべきか2年先程度を見た実施方策に関する知見を得る。
3.得られた成果・残された課題
本年度は、「国の研究開発全般に共通する評価の在り方についての大綱的指針」に基づき実施された研究評価に関する科学技術会議のアンケート及びそこで特徴のあった研究機関の面会調査等により、我が国の公的科学技術研究機関の評価の実態を分析した。
また、米国で実施している政府業績評価法(GPRA)の進捗状況及び問題点並びにカナダにおける評価の実施に関する考え方の現地調査を行った。
4.特記事項
特になし。
5.論文公表等の研究活動
[1]Hirasawa, R.「Japan’s Performance in S&T Policy」 PRIME Lecture Series, University of Ottawa, Canada, March 23, 1999.
ニーズ指向型公共技術経営のあり方
平澤 、数田幸司
1.調査研究の目的及び性格
本調査研究は、ニーズ指向型研究において、社会ニーズを反映させる政策形成メカニズムを検討し、技術の受容者の要求に根差した公共技術経営のあり方を考えるものである。
2.研究課題の概要
科学技術における知的生産の原理は、通常、パラダイムを遵守する立場からディシプリン内向的な動因に支配されることが多い。それに対して公共政策がめざすものは、科学技術の研究それ自体であることは稀で、多くは何らかの形で技術の受容者の要求に根差したものである。公的資金に基づく研究開発は、その成果が科学技術の枠内であることを目的とするシーズ指向型の研究の他は、大部分が目的の明確さにもよるが、ニーズ指向型と考える。そしてこのニーズ指向型の場合、研究を研究者のオートノミーに委ね、その知的生産の原理が支配する方向に研究が進められていくとすれば、政策目標が期待する成果とは当然異なる結果に至ることになり、この両者の乖離を避ける何らかの手段が必要になる。これが公共技術経営の課題であると考える。一般には、政策目標への誘導を刺激する環境や装置(例えば評価制度)を設置することになるが、政策目標の妥当性がシーズ側からも検討される必要があり、一方的な誘導メカニズムを想定するだけでは不十分である。
本調査研究では、現在、公共技術経営の中でも特にニーズ指向性の強い課題としてIntelligent Transportation System(高度道路交通システム)をとりあげ日米欧の取り組みを対象とした比較研究を実施している。
3.得られた成果・残された課題
調査・研究中のため現段階では、特になし。
4.特記事項
ニーズ指向性の強い課題において、社会ニーズを反映させる政策形成メカニズムのあり方の構築。
5.論文公表等の研究活動
特になし。
政府出資研究機関に対する機関運営評価の活用方法に関する研究
平澤 、韓 亨浩
1.調査研究の目的
現在情報・知識の発達による開放の加速化と技術革新周期の持続的な短縮等科学技術を巡った研究開発環境が急激に変化している。したがってこれに適応する研究開発システムを備え、研究競争力を持続的に向上させるために研究評価を明確にして行くことが各国の趨勢である。本研究は国家・社会に大きな影響を与える研究活動を遂行する公的研究機関に対する機関評価結果をいかに活用して行くようにするかを、日本等主要先進国と韓国との比較・分析を通じてその方法を導出して提示することである。これによって公的研究機関の研究競争力向上と関連政策及び制度に反映させて実現し、定着させて行くことに寄与しようとするものである。
2.研究課題の概要
本研究の対象は国家の公的資金支援を受けて公共的な研究を行う科学技術分野の公的研究機関として、韓国は政府出資研究機関に限定し、日本等先進国は国立(試験)研究機関及び特殊法人研究機関とした。本研究のためにこれまで関連文献を収集し、日本の関係研究機関を多少訪問してインタビュー調査を行った。
3.得られた成果・残された課題
韓国と日本の研究機関評価とその評価結果の活用は次の通りである。
韓国は1991年3月14日に『製造業の競争力強化対策』報告時に大統領の指示により国務総理室の主管の下に『関係部処合同評価団』を構成して22の科学技術を担当する政府出資研究機関に対する詳細点検及び機関評価を初めて実施した。その後科学技術処は『関係部処合同評価団』の提言に沿い1992年から1995年まで毎年機関評価を実施してきた。1996年からは毎年実施する定期評価(短期成果中心の自体評価)と3年ごとに外部の総合評価団が実施する総合評価(中長期発展戦略中心の評価)の両方が行われ、その評価結果は消極的ではあるが褒賞、研究課題の選定及び研究費の配分、機関長の任期等に反映している。
日本は1997年8月に『国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針』(内閣総理大臣決定)により、①評価過程等の明確化、②外部評価の導入、③評価結果の反映・公表等が原則化された。この大綱的指針の策定後約1年の間で、その対象になる関係15省庁の46機関では評価のための要領規定等の要領、整備、評価の実施、外部評価の導入、評価結果の活用措置、評価結果の公表等が進められている。特に研究評価結果の適切な活用のために課題の選択等への活用や、研究内容への反映、内容の見直し等への反映、資源配分等への活用、その他評価結果の様々な形での公表等の中で無理がない事項に対しては一部施行しているが大部分は各界の意見を聞いている最中である。
その他にも米国の行政実績成果法(GPRA;1993)による政府組織及び傘下機関評価と英国の公的研究機関評価の事例分析等の反映を考慮している。
4.特記事項
特になし。
5.論文公表等の研究活動
特になし。
企業環境とイノベーションプロセスの変化に関する調査研究
平澤 、須藤剛志
1.調査研究の目的及び性格
経済活動のグローバル化や情報技術の進展など、企業をとりまく環境の変化に対応するための技術経営が重要性を増している。我国の製造業は生産性の効率化を進めることで、競争力を保持してきた。しかしながら、今日においては国際化や情報化といった環境変化に対応するため、イノベーションプロセスが急速に変化してきており、技術経営戦略の見直しを図る必要が生じている。本調査研究の目的は、国レベルでのイノベーションの変化を比較分析することにより、企業経営の現状と課題を明らかにすることである。
2.研究課題の概要
米国マサチューセッツ工科大学(MIT)、独国フラウンフォーファ協会システム・イノベーション研究所(ISI)との共同プロジェクトで行われており、①特定産業におけるケーススタディによる企業の研究開発プロセスの分析、②研究開発投資額の大きな企業に対するアンケート調査による技術経営の変化の分析を実施している。アンケート調査に関してはMITが米国企業、ISIが欧州企業、政策研が日本企業に対してそれぞれアンケート送付から集計までを受け持ち、最終的に3所のデータベースを統合し、分析を行う。
3.得られた成果・残された課題
1) 我国電機産業を対象としたインタビュー調査を実施し、学術文献および特許のデータベースによる分析結果と比較することで、VCR、LCDに関する研究開発のメカニズムの分析を進めている。
2) 年間研究開発投資額1億ドル以上の企業に対するアンケート調査を日、米、欧州において実施し、回答の集計を実施している。我国においては送付先126社中98社より回答を得ており、技術経営の現状、国際化への対応、技術体系の選択等に関する単純集計を完了した。また、欧州及び米国の調査も終了し、現在それらのデータベースと統合し、国際比較あるいは業種比較を実施中である。
4.特記事項
本調査研究で得られたアンケート調査結果は会社名を匿名としてデータベース化され、日米欧の3所で共有されている。
5.論文発表等の研究活動
特になし。
科学技術指標の体系化に関する研究
富澤宏之、丹羽冨士雄(客員総括研究官)
1.調査研究の目的及び性格
本研究は、科学技術指標に関する基礎概念の明確化や理論的基盤の強化、および科学技術指標の体系的アプローチの具体的方法論の開発を目的とする。また、最近、我が国の政策策定の現場では、政策評価や政策目標設定への定量的手法を適用しようとする動きがあるが、その際の理論的基礎を強化することを目的としている。
2.研究課題の概要
科学技術指標に関する基礎諸概念や理論的基盤について、経済学、社会学等の社会科学や心理学における測定論などを参考にして理論構築を行った。特に、科学技術指標の体系化に対するシステム論アプローチの適用を中心に検討を進めた。
また、科学技術指標の作成・利用の実態から理論的な帰結を引き出すための分析を行った。特に、科学技術における様々な意思決定における指標の機能の特質を分析した。
3.得られた成果と残された課題
主要国における計量書誌学的指標の利用の実態や議論を分析し、科学技術指標と意思決定や政策策定との関係を検討した。欧州のいくつかの国における研究評価に対する計量書誌学的指標の活用状況の分析を通じて、研究評価における定量的指標の意義は、従来言われてきたように「評価の客観性の確保」と考えるのは適切でなく、「評価の明示性の確保」に本質的な重要性があることを明らかにした。並行して、指標論の立場から定量的指標の機能を、(1)対象についての認識や理解・把握、(2)理論形成および理論検証、(3)予測、(4)制御ないし操作、(5)狭義の評価、(6)意思決定、(7)指標を通じた認識の共有およびコミュニケーション、に分類・整理し、それぞれの場合における問題点を明らかにした。さらに指標の機能を一般化すると、定量的指標の意義は広い意味での「可操作化」にあるという結論に達した。今後は、このような基礎の上に、科学技術指標の適切な活用方法を明確にしていくとともに、数理的・システム論的諸手法の適用の可能性を探っていく予定である。
4.特記事項
特になし
5.論文公表等の研究活動
[1]丹羽冨士雄、富澤宏之「科学技術活動のマクロ構造分析」,『研究 技術 計画』Vol.12, No.1/2, pp.82-98 (1997)。(発行1998年)
[2]富澤宏之「科学技術活動の計量と研究評価(その1)計量書誌学的指標と研究評価」研究・技術計画学会、第13回年次学術大会講演要旨集、pp.33-38 (1998)。
科学技術活動の計量分析のための基盤データおよび手法構築に関する基礎的研究
富澤宏之、藤垣裕子
1.調査研究の目的及び性格
科学文献や特許のデータベース等を用いた定量的分析は、科学技術政策研究や科学社会学の経験的・実証的研究の基盤データとして欠かせないものとなっている。本研究は、このような基盤データの性質や分析手法を構築することを目的とする基礎的研究である。
2.研究課題の概要
科学文献や特許のデータベースの収録内容・データ構造を調べ、どのような定量データが抽出できるかを検討する一方で、科学技術政策研究や科学社会学において重要性の高い定量データを整理し、両者を比較して、実現性と重要性の両面から検討している。具体的には次のような点を中心に検討している。
・データベースからのメゾレベル・データ(産官学別の論文数、特許等)の抽出手法の検討
・分野分類の手法の検討
・論文、特許データベースと他の関連データベース(研究者ディレクトリ・データベース、企業情報データベース等)との連結可能性の検討
・各種科学技術指標との連関分析
・各種社会科学的分析の可能性の探索
3.得られた成果と残された課題
科学文献や特許のデータベースを体系的に整備し実際にデータ分析を行った結果、主としてメゾレベル・データの抽出手法に関して進展があった。論文データベースからは、著者の所属機関の種類別(産官学などの区別)の定量データの抽出手法を明らかにした。また、分野分類手法に関して検討した。
他のデータベースとの連結可能性については、特許データベースと企業情報データベース企業との連結を行い、業種別の特許件数等の集計方法を明らかにした。一方で、論文データベースと研究者ディレクトリ・データベースとの連結可能性について検討したものの、その有効な手法は今後の検討課題として残された。
4.特記事項
科学技術政策研究や科学社会学においては、定量データの方法論に関する検討は広く行われているものの、体系的に方法論を開発しようとするアプローチが充分ではなかった。本研究は、方法論に焦点を絞るとともに、実際のデータ抽出可能性の側と分析における有用性の側を中心に検討する。
5.論文公表等の研究活動
[1]富澤宏之「特許解析で見る技術開発動向 ―引用分析を中心として―」、CICSJ Bulletin, Vol.16, No.6 1998、pp17-20.
公的研究機関における研究開発マネジメント:研究組織における情報共有化構造の分析
田中 聡
1.調査研究の目的および性格
研究開発マネジメント(R&Dマネジメント)の研究は,企業を中心としたprivate-sectorでは盛んに行われている。技術管理,技術経営に関する国際専門誌や国際会議の数がそのよい例である。これに対し,public-sector,すなわち国立研究所や大学における研究マネジメントの研究は,それほど盛んであるわけではない。これは研究分野がより広範に及ぶこと,および大学,研究所における研究室運営が少人数で行われること,企業のように採算重視でおこなわれているわけではないこと,などを考えるとたしかにうなずける現象ではある。しかし,private-sectorでのマネジメント研究の興隆ぶりに比較すると,その実態に迫った研究は少ないのが現状である。
本調査研究の目的は,国立試験研究機関における研究計画策定過程の有効性という視点で,中核的な役割を担っているミドルクラス(研究企画の責任者およびリーダー層の研究者)を対象とした情報活動の現状および研究開発推進上の制約要因等を把握し,今後の科学技術政策研究のための基礎資料とすることである。また,独立行政法人化のあり方の議論に対しても寄与できると考えている。
2.研究課題の概要
研究組織においては,共有化の「場」を通じて,どのような情報が研究企画の責任者やリーダー層の研究者に提供されているのか,彼らは「場」を通じて得た情報がどの程度有用であると実感しているのか,などの知見を得るために,情報活動の方策・媒体ごとの細かい調査項目について検討を行った。
3.得られた成果・残された課題
本年度は,インタビュー調査および質問票調査により,組織レベルの研究計画策定過程の実態把握に取り組んだ。
最初に,研究職員数100名程度の1国立試験研究機関において,所長およびリーダー層の研究者などを対象としたインタビュー調査を行い,経常的に実施されている研究課題の策定過程に関する知見を得た。
次に,国立試験研究機関(自然科学系の71機関)を対象とした質問票調査に取り組み,約500名の研究企画の責任者およびプロジェクト研究のリーダーに対する調査票の郵送を完了した。今後,質問票調査データの集計分析を行う予定である。
4.特記事項
特になし。
5.論文公表等の研究活動
[1] 田中 聡、藤垣裕子、平澤 「研究組織の研究計画策定過程に関する調査研究」第13回研究・技術計画学会年次学術大会講演要旨集51-56(1998)
科学技術の優先分野投資の研究者アクティビティに与える影響の分析
〜ライフサイエンスを対象として〜
渡部康一
1.調査研究の目的および性格
本研究は、日本の科学技術における優先投資分野について、政策分析に加え、研究投資額と論文数の推移を分析することにより、政策およびそれを反映した研究投資が有効に成果産出に結実しているかといった反省的視点を得る。
2.研究課題の概要
我が国の研究開発分野においてライフサイエンスは、近年の科学技術の隆盛の中でもとりわけ発展が著しい分野であるが、投資に見合う成果が出ていないといった指摘も聞かれる。政策決定、予算配分、成果産出といった研究開発活動の一連の流れの中で問題点を指摘できれば、より効果的な科学技術政策の立案に貢献できるものと考えられる。そこで、我が国のライフサイエンス分野に焦点を当て、政策決定、予算配分、成果産出の各局面の特徴および相互の関連を分析する。
3.得られた成果・残された課題
研究開発全般に関して、その効率性を研究投資額の伸びに対する論文生産の伸びの観点から国際比較をすると、日本の論文生産性はさほど高くないことが示された。また、内閣、審議会等、関連省庁の各レベルでのライフサイエンス関連の取り組みを時系列で整理することにより、我が国のライフサイエンス政策の変遷の全体像を捉えた。論文分析からは、ライフサイエンス分野の日本の論文シェアは着実に伸びてきており、特に、がん研究は日本のライフサイエンス分野の中でも、成長の著しい分野であることが示された。今後、政策−研究投資−成果産出の相互関係について、詳細な分析を進めることが重要である。
4.特記事項
従来行われてきた研究開発に関する入出力分析では、ある時点における費用効果を扱うものが主であったが、本研究は、その時間的変化を政策決定から成果産出の一連の流れの中で捉えようとするものである。
5.論文公表などの研究活動
[1] 渡部康一、藤垣裕子「科学技術の優先研究分野投資の研究者アクティビティに与える影響の分析」,第13回研究・技術計画学会年次学術大会講演要旨集9-14(1998)
[2] Watanabe, K. and Fujigaki, Y. 「 Policy Analysis on the Selected Priority Area in Japanese Science and Technology Policy: Policy Change and Performance Analysis in Life-Sciences」 SOEIS project meeting, Amsterdam, Netherlands, December 5-8, (1998)
科学技術の形成過程における研究者のコミュニケーション構造分析
藤垣裕子、富澤宏之、渡部康一、田中 聡
1.調査研究の目的および性格
本研究は、欧州連合第12総局(科学技術政策関連)第4次Framework ProgramのTSER部門(Targeted Socio-Economic Research)プログラム「欧州科学技術情報の自己組織化(SOEIS:The Self-Organization of the European Information Society)」プロジェクトとの共同研究である。SOEISプロジェクトは欧州内の6つの大学:アムステルダム大学(オランダ)、ビーレフェルト大学(ドイツ)、サリー大学(イギリス)、ローマ大学(イタリア)、チューリヒ大学(スイス)、テラス大学(ギリシャ)の共同研究としてEUからファンドを得て1997年12月に発足した。これに対し、我が国の研究グループは、このSOEISプロジェクトのシスタープロジェクトとして位置づけられており、SOJIS(The Self-Organization of the Japanese Information Society)と呼ばれている。すでにEU第12総局に昨年6月に提出された研究アジェンダの報告書に、SOJISの存在が明記されている。SOJISのメンバーである。所内の4名(標記)に加えて、牧野淳一郎、林隆之(以上東京大学)、調麻佐志(信州大学)および平川秀幸(国際基督教大学)の協力を得た。
2.研究課題の概要
SOEISは7つのタスクから成っている。Task-1:理論的側面、Task-2:科学技術情報システムのモデル化、Task-3:EUの科学技術政策の分析、Task-4:科学技術情報の動態分析、Task-5:科学技術と社会との関係(市民へのアカウンタビリティ、および企業での知識共有プロセス分析)、Task-6:政策への含意、Task-7:科学技術ネットワークの可視化と理解および技術の科学者のコミュニケーションに与える影響である。日本からの貢献はこのうちTask2と4に関係し、「日本の科学技術における優先投資分野の政策分析:ライフサイエンスにおける政策変遷および論文生産の推移をめぐって」および「学問分野間の論文様式および引用様式の差違について」の分析である。
3.得られた成果・残された課題
特に日本のライフサイエンス政策分析を行い、欧州のそれとの比較研究を試みた。また学問分野間の論文様式および引用様式の差異については、自然科学、社会科学、人文科学の知識生産の様式の差を、論文形態の差異分析、インパクトファクター(被引用度数の指標化)によって考察した。
4.特記事項
特になし。
5.論文公表などの研究活動
[1] Fujigaki, Y.「A Future Perspective on STS and Scientometrics: Exchange and Integration Between Different Research Tradition in STS」EASST-Review, 17(2), 16-19.(1998)
[2] SOEIS Progress Report, 32-33.(1999)
[3] 林隆之、藤垣裕子「科学技術活動の計量と研究評価(その3)学問間の論文産出様式の差違について」研究技術計画学会第13回講演要旨集、45-50.(1998)
科学技術政策コンセプトの進化プロセスに関する研究
藤垣裕子、永田晃也(北陸先端科学技術大学院大学)
1.調査研究の目的および性格
本研究は、科学技術政策の歴史を政策コンセプトの進化プロセスと捉えて分析することを目的としている。
2.研究課題の概要
多様なステークホルダーの利害の調整を経て政策シナリオの設定が行われる公共政策の立案プロセスは、諸個人の認知、パースペクティブなどを他者と共有可能な概念(コンセプト)として表出する「コンセプト創造」のプロセスとして捉えることができる。たとえばCOE、研究組織の流動性(フレキシビリティ)、あるいは研究アカウンタビリティ論など、その年度、あるいは時代ごとにキーコンセプトとして現れる概念は、そのままその年度や時代に必要とされる政策のありかたをうまく反映し、またそれゆえに多様な利害の調整に役だっていると考えられる。本研究の目的は、明文化される政策コンセプトの時系列変化を捉え、科学技術政策の歴史を政策コンセプトのダイナミックな進化のプロセスとして捉える視点から検討することである。政策コンセプトがどのように生成され、正当化、普及、定着の過程を辿るのかを調べ、新しい政策コンセプトが生成されるための条件を抽出し、今後の政策立案におけるコンセプト生成に寄与することを目的とする。
3.得られた成果・残された課題
まず科学技術会議の過去の全答申(1960年の第1号答申から1996年の第23号答申まで、36年分)のデータベース化を行い、これを用いて語の頻度分析、共語分析(関連性尺度および共出現マトリクスに対する因子分析)を行った。その結果、新しいコンセプトの創出、例えばCOE、産学連携、地域科学技術などの出現を時系列的に追うことができた。これは、当時の公共ニーズと国際トレンド(海外からの要求、日米関係)を反映している。また各答申における語の出現頻度ランキングの動向による政策イシューの変化を追跡した。さらに共語分析によって、基本的な政策コンセプトの変化を追った。たとえば「基礎研究」という語は第1号答申(1960)においては「応用研究」という語とともに語られるのに対し、第11号答申(1984)では「社会的ニーズ」という語とともに語られ、第23号答申(1996)では「経済的ニーズ」という語とともに語られる。各期の社会政治的付置(たとえば大学と国研の関係など)の動きが共語マトリクスに反映され、各期のコンセプトの変化(基礎研究概念、科学技術という概念の変化)が語頻度、共語関連性尺度に反映されていることが示唆された。
4.特記事項
特になし。
5.論文公表などの研究活動
[1] Fujigaki,Y. and Nagata, A.「Concept Evolution in Science and Technology Policy」Science and Public Policy, Vol.26, No.6, 387-395.(1998)
[2] 永田晃也、藤垣裕子「科学技術政策コンセプトの進化プロセス(Ⅱ)」研究技術計画学会第13回講演要旨集179-184.(1998)
特許と学術論文に見る知識生産形態の比較
藤原直也、藤垣裕子
1.調査研究の目的及び性格
研究開発活動の成果としての「知識産出」の形態を概観した場合、特許と学術論文は、科学技術分野における二大産出形態であると言える。しかし我が国においては、官学研究セクター、特に大学における特許活動が不十分であるとの指摘が高まりつつある。本研究では、このような傾向が生じた原因を、特許と学術論文の内容や目的、これらを産出する科学者の執筆動因分析、学界における特許と学術論文に対する評価、などの観点から、比較、考察することを目的にしている。
2.研究課題の概要
本調査研究では、特許データベース検索等により産・官学の研究セクターの特許活動等を概観したのち、同一技術内容を記載した特許と学術論文の比較実例調査および学術論文と特許の双方を多数執筆されている研究者へのインタビューを実施することにより、両者の比較分析を試みた。
3.得られた成果・残された課題
上記分析の結果、まず特許データベース調査からは、日本の大学出願特許数は、日本の民間企業や米国大学の出願特許数に比べて、大幅に少ないことが示唆された。また、研究者へのインタビュー調査からは、官学研究セクターの知識産出形態は、多数の特許に発明者として名を連ねている研究者の多くでさえ、学術論文の執筆を優先し特許はさほど重要視しない「論高特低」の傾向が顕著に見られた。次に、学術論文と特許の記述内容の比較からは、学術論文における記述内容が当該論文で証明された事実にとどまるのに対し、特許では発展の可能性を膨らませて記述する傾向があること、学界では研究業績として特許活動は評価されないこと、等がインタビューにおいて指摘された。前者は、同一内容を記述した学術論文及び特許を実例とした調査においても確認された。
こうした現象が生じた原因を以下のように考察した。まず、学術論文と特許における内容の相違は、それぞれの執筆目的の相違を反映した特徴を有している。すなわち学術論文は、当該研究で明らかにされた事実に焦点を当て、再検証可能な情報を含む成果に公表を限定しており、これにより正確な知識の伝達とこれから展開する『新たな真理』の発見を促す役割を担っている。一方、特許は権利確保のため、厳密な定義による権利の明確化と幅広い記載内容による広範な権利の獲得を狙った記述が見られた。また、官学研究セクターにおける特許活動が低調である原因の一つは、学界における特許の評価が非常に低いことが主な原因であることが示唆された。さらに、学界における特許出願にかかわる支援制度が充実していないため、出願にかかわる作業が研究者にとって多大な負担となっていることもその一因と示唆された。
4.特記事項
特になし。
5.論文公表などの研究活動
[1] 藤原直也、藤垣裕子「特許と学術論文の形態比較〜記述形式・内容の分析とインタビューによる執筆動因分析〜」DISCUSSION PAPER NO.7(1998.10)
知識生産のモデル化と科学技術と社会との関係に関する研究
藤垣裕子
1.調査研究の目的および性格
本研究は、科学者の知識生産のメカニズムとその特徴をモデル化し、科学者共同体内部における知識生産と国民ニーズにあった知識生産との違いを明確にし、前者から後者への移行や統合がいかにして可能かについての考察を行うことを目的としている。
2.研究課題の概要
科学技術が巨大化し、かかる資金もその影響も大きくなるにつれて、科学技術と社会との関係は現在大きな課題の1つとなっている。しかしながら、科学技術の専門家と一般市民・社会との間のコミュニケーションは、うまくいっているとは言い難い。それは何故なのか。本研究では、この問題について、特に科学者の側の知識生産のメカニズムとその特徴をモデル化し、そのことを通じて、科学者共同体内部における研究の指向がいかにタコツボ化しやすいか、その理由を探る。同じモデルを用いて、科学者共同体内部の知識生産と国民ニーズに沿った知識生産との違いを明示し、前者から後者への移行や統合の可能性について議論する。
3.得られた成果・残された課題
まず第1に、科学者集団におけるジャーナル共同体(専門誌への投稿、編集活動にかかわる集団)を単位とした知識の妥当性境界(validation-boundary)についてモデル化を行った。第2に、この科学者共同体内部の知識生産と国民のニーズにあった知識生産とで妥当性境界がどのように異なるかを考察した。第3に、科学者共同体内部の知識生産を用いて、国民のニーズにあった知識への統合がいかにして可能か(学際研究における異分野コミュニケーション障害とその統合)について分析した。
4.特記事項
ジャーナル共同体という分析単位、およびvalidation-boundaryという概念は、本研究のオリジナルな概念である。
5.論文公表などの研究活動
[1] 藤垣裕子、ジャーナルシステムからとらえる科学のダイナミズム〜計測と認識論をつなぎ、異分野摩擦を超えるには, in『科学を考える〜人工知能からカルチュラル・スタディーズまで14の視点』(岡田猛ほか編、北大路書房、186-211.(1999)
[2] Fujigaki,Y.「The Citation System : Citation Networks as Repeatedly Focusing on Difference, Continuous Re-evaluation, and as Persistent Knowledge Accumulation」Scientometrics, 43(1), 77-85.(1998)
[3] Fujigaki,Y.「Knowledge as an Autopoietic System: Implication for Knowledge Society.」 Sociological Abstract, 121.(1998)
科学技術人材の流動化促進に係わる調査研究
和田幸男、前澤祐一
1.調査研究の目的及び性格
本調査研究では、国の全体(産学官)に亘る研究者・技術者の流動化が、将来の我が国の創造性豊かな研究者等の育成・確保にとって重要な点の一つと考え、その関係する諸課題の現状と促進策を調査研究する。しかし、研究者・技術者の流動化促進といっても、産学官のそれぞれの研究機関には固有な課題、必要性および流動化に係わるインセンティブがあり、それらの実態と諸条件を詳細に調査研究する必要がある。
2.研究課題の概要
科学技術人材の流動化問題は国研機関や国立大学および若手研究者・技術者だけの問題ではない。そこで、国全体の産学官に亘る研究者等(研究支援者及び補助者も含む)の問題として捉え、現状の実態と将来の少子化、高齢化社会のような社会情勢をにらみながら、柔軟かつ競争的な産学官に開かれた研究開発環境を実現する、人材流動化促進に関する諸策を検討する。
そこで産学官の研究機関およびそこで働く研究者・技術者等(研究支援者および補助者も含む)の両面からこれまでの流動実態と流動に係わる意識および課題等の調査研究を行い、それぞれの流動化促進環境整備に関する条件および課題の整理とそれに係わる望ましい政策を検討し提言を行う。
3.得られた成果・残された課題
1)得られた成果
産学官の研究機関とそこで研究に従事している研究者・技術者等((終身雇用、任期付任用およびポスドク支援制度研究者等)、研究支援者および研究補助者)の両面から、流動化に関係する転職、異動、任期付任用および高齢化社会下の研究環境における望ましい雇用形態等の実態および機関あるいは研究者等個人の意向に関係するアンケート調査を平成10年7月―10月に実施した。アンケート配布対象研究機関は、①;大企業研究機関、②;ベンチャー企業、③;国立試験研究機関(特殊、財団法人も含む)、④;地方公立試験研究機関、⑤;国立大学附置研究機関(共同利用研究機関も含む)、⑥;私立大学研究機関、に大別でき、その回答機関数および有効回答率は、それぞれ90機関と50%であった。一方、研究者等に対するアンケートの回答者数と有効回答率は、それぞれ1591人と58.3%であった。平成10年度は、主に研究機関を対象とした流動化関連のデータおよび機関としての流動化に関係する意向の動向を得ることができた。
2) 残された課題
平成11年度においては、研究者等を対象としたアンケートの結果を解析・評価し、前年度の結果とあわせてまとめ、流動化促進に係わる諸課題とそれに係わる政策提言を行う。
4.特記事項
特になし。
5.論文公表等の研究活動
特になし。
大学院における学際的カリキュラムの構造と運営に関する研究
佐野享子
1.調査研究の目的と性格
本研究は、日本の大学院における学際的カリキュラムがいかなる構造を持ち、どのような過程で運営されているのかを明らかにすることを通じて、大学院における学際的カリキュラムのあるべき方向性を示唆することを目的とする。
科学技術基本計画でも指摘されているように、今日社会と科学技術との関わりが密接になっており、科学技術の進歩にとって、自然科学と人文・社会科学との相互の関わり合いが重要になっている。このため今後は、科学技術人材=理系の人材といった図式にとらわれることなく、文系、理系の枠を越えた学際的な教育が望まれている。学際的な教育を行う上では、学際性と専門性をともに育成することが求められることから、学際性と専門性をともに追求する教育をいかに行うべきかという点を、特に本研究では明らかにしたい。
2.研究課題の概要
大学院における学際的なカリキュラムの構造は、教育の目的や当該研究科が教育研究を行う学問分野の構造、学士課程との接続の程度等によって異なることが予想される。またカリキュラムが機能するためには、指導体制を含めたカリキュラム運営(カリキュラムのplan-do-see)をいかに行うかが重要である。
本研究では、日本の大学院における人文・社会科学分野と自然科学分野を融合した教育を目的としたカリキュラム(以下文理融合カリキュラムという)に焦点を当てて、以下の研究課題を設定する。
1)文理融合カリキュラムの構造を明らかにする。
2)文理融合カリキュラムの構造と、カリキュラム構造との関連が予想される要因(研究科が対象とする学問構造、教育研究目的、研究科組織のタイプ、研究科設置の経緯等)との関係を明らかにする。
3)文理融合カリキュラムの構造とカリキュラム運営との関係を明らかにする。
4)日本の文理融合カリキュラムの進むべき方向性を示唆する。
3.得られた成果・残された課題
今年度は全国の大学院の関連資料を収集・分析し、学際的な教育を行っている研究科を抽出した。これらを対象として来年度は上記1)〜4)の課題を明らかにすることとしている。
4.特記事項
学際的なカリキュラムに焦点を当てた研究は、国際系、情報系の学部を対象とした研究はあるが、大学院や文理融合カリキュラムに焦点をあてたものは、日本においては管見のかぎり見られない。
5.論文公表等の研究活動
特になし。
理工系を専攻した女性の就業実態等に関する調査研究
横尾淑子、前澤祐一
1. 調査研究の目的及び性格
第1調査研究グループでは科学技術分野への女性の進出に関する一連の調査を行ってきた。本調査研究では、人数が大きく増加した企業に属する女性研究者・技術者に焦点を当て、その活用状況及び将来に向けての課題について検討することを目的とした。
本年度は、昨年度に引き続き人事担当者に対するインタビューを行うとともに、女性研究者・技術者に対する勤続状況アンケートを実施し、結果をとりまとめた。
2.研究課題の概要
女性の就業に関わる問題は職種を問わず共通であるが、研究者・技術者のもつ高度の専門性に関わる問題や対策もあり得ると考えられる。総理府や労働省等により女性の就業に関する調査は実施されているが、研究者・技術者に的を絞った調査は行われていない。そこで本調査研究では、専門性の維持および活用という観点からの検討を行った。
3.得られた成果・残された課題
(1) 就業状況
1) 女性の活躍機会拡大の効果として、人事は、社会的要請、優秀な人材の確保、女性の視点をプラス面として、部署限定、人事対応の複雑化、パワー低下の可能性、中途退職をマイナス面として挙げている。
2) 人事は、配置に当たり、本人の希望、体力や適性、受入態勢等を考慮している。女性は、職域限定を感じ、また社外との仕事のやりにくさを感じている。
3) 女性は、育児休業に当たり実務から離れる不安、復職後の不安、負い目を感じている。
(2) 現状での問題点と今後の可能性
1) 問題点は、受入態勢未整備、退職を見込んだ育成、育児休業への不安、復職後の機会喪失、復職後の処遇への不安、及び配偶者転勤に伴う退職である。
2) 女性の活躍機会を拡げるためには、保育施設の量的質的充実を図るとともに、休職中の情報入手、知識修得等専門性維持への支援、人材バンクシステム等中途退職者の専門性活用等に関する検討が重要である。
4.特記事項
なし
5.論文公表等の研究活動
[1] 横尾淑子、前澤祐一「企業における女性研究者・技術者の就業状況に関する事例調査」調査資料・データ−60(1999.3)
科学技術活動に係るコーディネート機能・人材に関する調査研究
前澤祐一
1.調査研究の目的及び性格
21世紀を目前に控え、新産業の創出、地球的諸問題の解決、国民生活の質的向上等多様な社会的・経済的ニーズに科学技術が積極的に貢献することが益々要請されている。このような中で、大学においては、膨大な知的資産を適切に技術移転することが必要となっている。また、国立試験研究機関は、近く独立行政法人に移行することとされており、従来に増して社会的・経済的ニーズへの機敏な対応、効率的で透明性の高いマネジメントを確立することが必要となっている。主としてビックプロジェクトの推進を担う特殊法人においては、巨額の研究開発投資に見合う成果が厳格に求められており、より効率的な研究開発マネジメントの確立が必要となっている。地域においても、経済を活性化し、地域に密着した新産業を創出していくため、大学、企業等と緊密に連携して行くことが重要となっている。民間企業においては、メガ・コンペティションの激化に対応して生き残りを図っていくために、研究開発戦略の機敏な発動が鍵となっている。
このような今日の状況において、研究者・技術者の育成、その能力を発揮させるための条件の整備もさることながら、総合的な科学技術力を高めていくためには、研究開発戦略の策定、研究成果の適切な移転・事業化等のコーディネート機能を一層充実させるとともに、この機能を担うコーディネート人材を育成・確保することが不可欠となっている。特に、今日、研究開発の推進においても“選択、集中、スピード”の考え方が求められており、新しいタイプのコーディネート機能・人材に対する期待が大きくなっている。
2.研究課題の概要
これまで、科学技術人材に関し研究者・技術者の育成・確保については、多くの調査研究が行われてきたが、コーディネート機能の重要性が正当に認識されているとはいえず、コーディネート機能・人材に焦点を当てた調査研究はほとんど実施されていない状況にある。このため、インタビュー調査、質問票調査等によりコーディネート機能・人材の現状、課題、今後の方向性を明らかにし、今後の産学官連携に係る施策、科学技術人材等に関する施策の立案等に資する。
3.得られた成果・残された課題
幅広い文献調査を行うとともに、大学共同研究センター、企業研究機関、地域研究機関、国立試験研究機関、特殊法人にインタビュー調査を実施した。また、上記機関に質問票を発送した(合計170機関)。これらの種々の調査結果を踏まえ、次年度には報告書刊行予定。
4.特記事項
特になし。
5.論文公表等の研究活動
特になし。
第4版科学技術指標に関する調査研究
第4版科学技術指標に関する検討チーム
丹羽冨士雄(客員総括研究官、主査)、前澤祐一、富澤宏之、古賀款久、
渡部康一、横尾淑子、大山真未、中田哲也、新名秀章、田村泰一
1.調査研究の目的及び性格
科学技術指標については、平成3年度に最初の報告書を作成して以来、ほぼ3年毎に改訂を行っており、最近では、平成9年度に第3版科学技術指標を作成したところである。
これについては、機関評価委員会においても高い評価を受けるとともに、OECD等の国際的動向をみても、戦略的な科学技術政策の策定に活用できる科学技術指標の開発のための様々な検討が行われているところである。
このような状況を勘案し、第4版科学技術指標を作成することとし、平成10年度においては、その準備のための検討を行った。
2.調査研究課題の概要
所内に第4版科学技術指標検討チームを設置し、科学技術指標作成の目的・意義、構成、内容等について検討を行った。
3.得られた成果・残された課題
(1)得られた成果
検討チームによる検討結果について、平成11年3月、報告書をとりまとめた。その概要は以下のとおりである。
1) 科学技術指標の目的・意義
2) 第4版科学技術指標の構成(案)
3) 第4版科学技術指標の内容(案)
4) 第4版科学技術指標を作成するに当たっての留意点
5) 第4版科学技術指標を作成するに当たっての基礎調査の検討
6) 第4版科学技術指標を作成するに当たっての体制について
7) 今後のスケジュール
(2)残された課題
上記を踏まえ、平成11年度において、第4版科学技術指標を作成する。
4.特記事項
特になし。
5.論文公表等の研究活動
特になし。
科学技術と人間・社会との関わりについての調査研究
國谷 実、大山真未、伊藤晃輔
1.調査研究の目的
本調査研究は、科学技術と人間・社会との調和を図るための施策の立案・推進に資することを目的としたものであり、平成9年度から平成10年度にかけて実施した。当グループでは、生命科学技術をはじめとする個別分野の問題状況に応じた政策的な提言を行うと同時に、合意形成手法等の横断的な対策についての見解を提示するべく本調査研究を行った。
2.研究課題の概要
本調査研究では、科学技術と人間・社会との相互作用を対象とした、さまざまな学問的アプローチによる科学技術と人間・社会に関する新しい取り組み(科学技術社会論、いわゆるSTS:Science,
Technology and Society)の研究の現状等を把握し、科学技術に関する行政諸事例について調査し、特に先端科学技術に対する法的規制について検討した。平成10年度には、生命科学技術分野、その中でも特に、クローン技術や生殖医療技術を取り上げ、その規制を考えるに当たって、いかなる規制が可能か、またいかにして規制を正当ならしめるか、の二点を軸として、調査検討を行った。
3.得られた成果・残された課題
具体的には、有識者による講演会、インタビュー、文献調査により、欧米各国の生殖医療技術に関する規制の内容と経緯等を調査し、生命科学技術に対する規制の限界として、学問研究の自由との関係、規制対象としての生殖医療技術の把握と合理的な規制方法の検討、特にヒトクローン児の創出に関しての規制を正当づける根拠としての科学的安全性、社会的秩序等について検討し、研究者の法的責任、規制の手段として国及び学会のガイドラインの法的性質について分析した。また、規制の前提としての社会的な合意形成の努力に関し、関係する当事者、合意形成手法について検討を行った。
今後、同様のアプローチにより、環境科学技術等についても、検討を行う予定。
4.特記事項
本調査研究の成果は、科学技術会議生命倫理委員会クローン小委員会及びヒト胚研究小委員のための検討の基礎資料として活用された。
5.論文公表等の研究活動
[1]國谷実、大山真未、伊藤晃輔、木場隆夫「先端科学技術と法的規制<生命科学技術の規制を中心に>」POLICY STUDY No.1として1999年5月に発表予定
[2]講演会の内容については「科学技術と人間・社会との関わりについての検討課題」調査資料No.62として1999年6月に発表予定
科学技術と人間社会との調和に関する社会システムについての基礎研究
木場隆夫
1.調査研究の目的及び性格
本調査研究の目的は、「科学技術と人間社会との調和」をいかに図るかについて基礎的な考察を行うものである。科学技術の専門家と一般市民との知識構造の違いと意見の齟齬という状況に着目し、その状況を打開する手だてとしてコンセンサス会議に注目した。1997年度の後半に日本で最初のコンセンサス会議が実験として行われた。その経過を観察し、その結果について分析を行った。
2.研究課題の概要
コンセンサス会議においては、特定の科学技術のテーマを選定し、それに利害関係のない市民十数名を選び、「市民パネル」とし、他方の「専門家パネル」は、市民パネルにその科学技術の状況についてわかりやすい説明をし、市民パネルとの間で質疑応答を行う。その後、市民パネルだけで議論を行い、その科学技術について意見をまとめる。こうしたプロセスを経て生み出された市民パネルの意見を分析すると、第一に、それらは公益の立場から議論をされたことが特徴であった。例えば、遺伝子治療の研究については情報公開を進め、安全性を確認する第三者機関が必要と結論づけた。また、遺伝子治療を体細胞に限定した現在のガイドラインが、生殖細胞を操作できるような技術が開発されれば、なしくずしになってしまうのではないかという懸念から現行のガイドラインを理論的に強固にする必要があるという指摘もあった。第二に、市民パネルは遺伝子治療を受ける立場になったときのことを考えインフォームドコンセントについて意見を述べた。現行の書式は分かりづらい。他に治療法がない重篤な患者に限って遺伝子治療を行うという現状は、患者に精神的な圧迫感を与えるので尊厳死やホスピスなどの選択肢を提示すべきだという意見もあった。
3.得られた成果・残された課題
会議の結果としては、遺伝子治療に関する公益を考えた意見と、患者の権利という視点からの意見が得られた。これまで科学技術に関する意思決定は、専門家が主として行うものであった。コンセンサス会議では専門家としろうとの意見の相互の発信と理解のうえに立って、新たな市民パネルの意見が導き出された。新たな政策形成の可能性が示唆された。残された課題としては、最終報告会での会場からのコメントとしては、利害関係者を交えた議論も考えておくべきだという意見があった。
4.特記事項
科学技術に関する社会実験という新たな手法で研究を行った。この研究結果の一部はPolicy Studyの中に取り込む予定。
5.論文公表等の研究活動
[1] 木場隆夫「日本におけるコンセンサス会議の試み」,研究・技術計画学会第13回年次学術大会講演要旨集,pp.232-235
[2] 木場隆夫「コンセンサス会議における市民の意見の形成についての考察」
STS NETWORK JAPAN Year-book '98,第7巻,(1998),pp.19-36.
地域における科学技術振興に関する調査研究(第4回調査)
中田哲也、田中誠徳、柿崎文彦、渡辺俊彦、権田金治(客員総括研究官)
1.調査研究の目的及び性格
本調査は、科学技術振興において「地域」が重要な役割を担っているという観点から、都道府県及び政令指定都市における科学技術振興施策の実態を把握し、これら地方公共団体における今後の科学技術施策推進に資するとともに、国の段階における施策策定・推進に適宜反映させていくことを目的に実施しているものであり、今回の調査で4回目である。
2.調査研究課題の概要
地域における科学技術振興の最も重要な担い手である都道府県及び政令指定都市における科学技術振興施策の実態を把握する。
3.得られた成果・残された課題
調査の結果、以下のことが明らかとなった。
1) 地域における科学技術関係経費が引き続き増加しており、その総額は国の科学技術関係経費のほぼ3割に相当すること。
2) 総額に占める公設試験研究所に係る経費の割合が低下し、理科系教育機関に係る経費の占める割合が増加するなど、施策の内容がいっそう多様化していること。
3) 科学技術振興のための都道府県における総合的推進体制の整備が着実に進んでいること。
4.特記事項
今回の調査においては、過去3回の調査との連続性に配慮しつつ、地域における科学技術振興施策を12の性格に分けて把握すること等によって、調査精度の向上に努めた。
5.論文公表等の研究活動
[1] 田中誠徳、中田哲也、権田金治「 地方公共団体における科学技術関係経費からみた科学技術政策」,第13回研究・技術計画学会年次学術大会講演要旨録313-317(1998)
[2] 中田哲也、田中誠徳、柿崎文彦、渡辺俊彦、権田金治「地域における科学技術振興に関する調査研究(第4回調査)」NISTEP REPORT No.59(1999.3)
地域における科学技術資源指標策定に関する調査研究
中田哲也、田中誠徳、柿崎文彦、渡辺俊彦、権田金治(客員総括研究官)
1.調査研究の目的及び性格
本調査は、平成8年度に実施した「地域科学技術指標策定に関する調査」において試みられた地域における科学技術革新のための科学技術資源計測手法の精緻化と、現実の地域経済に対する応用方策等について調査研究するものである。
2.調査研究課題の概要
地域における科学技術活動の重要な担い手である研究開発型中小企業に焦点を当て、その立地地域条件等について把握するためのアンケート調査及びインタビュー調査を実施する。
3.得られた成果・残された課題
アンケート調査及びインタビュー調査の結果、研究開発型中小企業が重視する科学技術資源の内容等が明らかとなった。
12年度においては、アンケート調査の内容等について詳細に分析を行うとともに、地域における科学技術資源に係る指標の策定を行うこととする。
4.特記事項
学識経験者等で構成する「研究開発型中小企業の立地条件等に関する研究会」を開催した。
5.論文公表等の研究活動
[1] 中田哲也、田中誠徳、権田金治「我が国製造業の空間集積に関する一考察」,第13回研究・技術計画学会年次学術大会講演要旨録318-323(1998)
我が国製造業の空間移動と地域産業の構造変化に関する研究
休井正人、柿崎文彦、権田金治(客員総括研究官)
1.調査研究の目的及び性格
本研究は、科学技術と地域経済との関連についての研究が近年重要視されているという背景をもとに、我が国製造業の立地動態について、その空間移動特性、及び地域産業の構造変化に関する解析手法の開発等を行い、地域における科学技術振興施策の企画・立案に対する基礎理論情報を提供することを目的とする。
2.研究課題の概要
解析の基本データは「工業統計(産業編)」(通産省発行)を利用し、全国の製造業事業所(従業員4名以上)に関する4つの産業状況変数(事業所数、従業者数、製品出荷額、付加価値生産額)について解析を行った。対象期間は1980年〜1994年の15年間、事業分類は日本標準産業分類の中分類(2桁コード、23業種)、地域区分は47都道府県とした。これらのデータから以下の各係数/指数を計算し、その時系列的な変化を業種別、都道府県別に比較・評価した。
(下記以外に変動係数、労働生産性についても計算、評価をおこなった。)
1) 産業立地特性指数(IIL:Index of Industrial Location)
2) 地域産業構造転換指数(ICRIS:Index for Conversion of Regional Industrial Structure)
3) 地域産業集積係数(CRIC:Coefficient of Regional Industrial Concentration)
これらの数値はいずれも各年度(1980〜1994)毎に計算され、その時系列変化を解析することにより産業の空間移動特性及び地域産業の構造変化に関する特性を見いだすことができる。
3.得られた成果・残された課題
産業立地特性指数(IIL)から得られる立地特性は業種によって大きな違いがあり、大別すると電気機器製造業に代表される「分散立地型産業」と繊維製品製造業に代表される「集積立地型産業」にわける事が出来る。地域産業構造転換指数(ICRIS)から得られる産業構造の推移も都道府県によって大きく異なるが、新規産業の参入誘致による成長地域、特定産業特化/新産地形成による成長地域等、5つの特徴のあるパターンに類型化できる。地域産業集積係数(CRIC)は、地域における産業の競争力を示すファクターであり、これによって産業の地域優位性が評価できる。
より詳細な分析のために、産業分類ならびに地域区分をより細分化しておこなうことが今後の課題である。
4.特記事項
国内の製造業に関して、その空間移動特性ならびに地域産業構造の変遷を解析したが、その手法として新たに考案した指数(IIL, ICRIS, CRIC値)を用いたことに本研究のオリジナリテイがある。
5.論文公表等の研究活動
[1] 休井正人、柿崎文彦、権田金治「我が国製造業の空間移動と地域産業の構造変化に関する研究」NISTEP REPORT No. 60(1999.3)
地域科学技術政策研究に関する国際会議(RESTPOR’98)
1.開催日
1998年11月21日〜24日
2.主催者
ノースカロライナ大学
3.開催場所
米国ノースカロライナ州チャペルヒル
4.参加者
8ヶ国(米国、カナダ、英国、アイルランド、ギリシア、ブラジル、韓国、日本)と2国際機関(EU、UNIDO)より約100名。政策研より佐藤所長、権田客員総括研究官、柿崎第3調査研究グループ主任研究官、休井特別研究員が参加。
5.テーマ
知識社会、技術革新と地域の情報化
6.概要
本国際会議は、「経済のグローバリゼーションの急速な進展の下、イノベーションを持続的に継続できる社会の実現のため、国全体の科学技術資源・枠組だけでなく、地域についての政策研究も必要」との問題意識に基づき、当研究所の主催により第1回会合を1993年に開催した。この会合の意義が高く評価され、継続的開催への期待が高まりを見せたため、当研究所等の主催により第2回を1995年に開催した。その後、1996年には第3回がEU主催によりベルギーで、そして第4回会合が1998年にノースカロライナ大学の主催で米国において開催された。RESTPOR‘98は「知識社会、技術革新と地域の情報化」をメイン・テーマに6つのセッションで構成され全体で30件の論文発表が行われた。
セッションA;情報技術と企業化の変化:地域開発のための意義
セッションB;情報技術と仮想地域
セッションC;情報社会における発明:知的所有権と大学の新形態
セッションD;マクロ政策的視点での知識社会
セッションE;情報社会と都市人口
セッションF;情報時代における知識指向プロジェクト:地域経済開発のための意義
7.論文公表等の研究活動
[1] Sato, Y.「The Structure and Perspective of Regional Science and Technology Policies in Japan」
[2] Gonda, K.「Semantic Space and the Information Society in Terms of the Emergence of Intelligence」
[3] Kakizaki, F.「The Role of Virtual Regions in the Emergence of Knowledge and Research & Technology Development
第6回技術予測日独比較
桑原輝隆、田中清隆
1.調査研究の目的及び性格
日独両国において、デルファイ法にて調査された技術予測調査結果を多角的に比較することにより、日独両国の将来の科学技術についての認識の一致点や相違点、あるいは今後の技術進展に際しての問題点等を明らかにすることを目的とする。これらの情報は、我が国における科学技術政策立案の基礎資料となるとともに、民間の技術開発戦略策定においても活用されるものである。
2.研究課題の概要
[問題の設定]
アンケート調査自体は日独両国において既に実施済みであり比較により、以下の事を明らかにする。
(1) デルファイ法による技術予測調査の普遍性の確認。(実現予測時期は、前回同様にほぼ一致しているかどうか)
(2) 両国で重要視されている技術に大きな違いがあるのか。あるならば何が推定されるか。
(3) その他各技術分野における日独の研究開発水準、必要とされる政策手段等についての比較分析。
[その問題を設定した理由]
既存のデータの比較により有用な情報を得られると考えられるため。
3.得られた成果・残された課題
調査対象分野、課題数は日本では「情報」、「ライフサイエンス」、「環境」等14分野1072課題、ドイツでは「情報と通信」、「サービス業と消費」、「保健と生命プロセス」等12分野1070課題である。これらのうち約3割が共通の課題となっている。また、調査項目は日本では、「専門度」、「我が国にとっての重要度」、「期待される効果」、「実現予測時期」、「現在第一線にある国等」、「我が国において政府がとるべき有効な手段」、「我が国において問題となる可能性のある事柄」で、一方、ドイツでは「専門度」、「重要性」、「実現予測時期」、「研究開発水準」、「包括条件と重要措置」、「起こり得る二次的問題」である。現在、日独共通課題に着目して上記質問項目についての日独の比較を進めている。
4.特記事項
1993年 ドイツ技術予測調査(日本の第5回技術予測調査のアンケート表を翻訳して調査を実施)
1994年 日独技術予測調査比較報告書(NISTEP REPORT No.33日独共同レポート)
1995年 日独ミニデルファイ調査報告書(日独共同調査)
1997年 日本の第6回技術予測調査
1998年 ドイツ技術予測(DELPHI’98)(技術課題の約3割が日本の第6回技術予測調査と共通)
5.論文公表等の研究活動
「長期技術展望の国際比較分析」NISTEP REPORTとして1996年6月刊行予定。
国民健康領域における科学技術の推進 ―ヒューマンヘルスケア支援技術を中心として―
香月祥太郎(客員研究官)、桑原輝隆
1.調査研究の目的及び性格
本研究は21世紀の高齢化社会における重要政策課題である国民健康領域、特にヒューマンヘルスケアを対象に、国民の求める健康の維持・管理と生活の質に対するニーズ、及びそれに対応する支援技術の全体フレームを明らかにし、従来の技術課題との関連性を踏まえて、望ましい支援技術の実現のための課題と方策を検討することを目的とする。
2.研究課題の概要
(1)ヘルスケア領域の技術課題と特徴を、これまでの技術予測結果を用いて明らかにする。また、ヘルスケア対象者の特性と、健常者を含むケアが必要とされる対象者(需要者)数を概算推計する。
(2)次に医療従事者及びへルスケア需要者からみたヘルスケアに対する意識とニーズを実態的に明らかにし、疾病予防の立場から医療技術、ヘルスケア支援技術への期待を分析する。
(3)ヘルスケアを支援する技術フレームと技術課題を、医療系、ソフト・ハード系、ヒューマンウェア系に分けて明らかにし、その実現のための問題点と対応策を検討する。
3.得られた成果・残された課題
[得られた成果]
医療機関、大学病院医師等との議論、文献調査通して問題の設定と確認を進め、以下の成果を得ている。
(1)第5回、第6回技術予測調査におけるライフサイエンス、保健・医療・福祉分野の技術課題を整理し、基礎研究、予防、治療、その他に分けて内容、重要性からみたヘルスケアとの関連性を分析した。
(2)ヘルスケア対象者の特性について、各種文献と医師等の医療専門家の意見を踏まえて疾患別に整理した。また生活習慣病と呼ばれる主要疾患の患者数等を基に、ヘルスケア需要者数を概算した。
(3)ヘルスケアについて、生活の質(QOL)、健康度等を考慮して概念設定し、対象とする領域を整理した。引き続きそれに対応する支援技術フレームについて検討を行っている。
[残された課題]
医療領域におけるヘルスケアの課題とニーズの実態を明らかにするため、健常者を含むヘルスケア対象者および医療従事者に対して実態調査が必要であり、次年度にアンケート調査を実施する。
4.特記事項
本研究は、これまで不明瞭であったヘルスケア領域に、健常者を含めたニーズと科学技術の側面から分を試み、その支援技術フレームの策定と実現ための方策を検討することに重要な意味をもつものである。
5.論文公表等の研究活動
平成10年度においては、この調査研究課題に関する論文等の公表は行っていない。
先端科学技術動向調査(加速器科学)
瀬谷道夫、桑原輝隆、田村泰一(情報分析課)
1.調査研究の目的及び性格
本調査研究は、メガサイエンスの一つである加速器科学を取り上げ、加速器科学にブレークスルーを起こす可能性のある(主として)新しい原理による小型加速器の研究開発状況を調べるとともに、今後の発展動向を予測調査し、加速器科学の多様な発展を支援する方策を考える上での基礎資料を提供することを目的とするものである。
2.研究課題の概要
近年加速器が大型化してきており、加速器科学が今後も長期にわたり従来型の大型加速器に頼らざるを得ないとなると、将来の加速器科学の多様な、かつ、国民生活により密着した発展を阻害することとなりかねない。このため、ニーズが高いと考えられる小型加速器に関する研究開発動向を調べ、その研究開発状況と直面する技術的な課題等を的確に把握し、支援すべき点を明らかにする。
具体的には、主として新しい原理に基づく加速技術の研究開発状況及びそれらの加速技術に基づく小型(先進型)加速器に関する具体的な提案を調査し、それらを加速器研究者に提示し実現性等に関する予測見解を収集する。また、加速器ビームユーザーを対象とする調査により、加速器でつくられる種々のビームの利用状況、将来的な加速器ビームのニーズを把握する。その際、上の小型(先進型)加速器に関する提案のまとめとそれらに対する加速器研究者の実現性に関する予測見解を紹介し、その開発ニーズも同時に把握する。
なお、これらの調査分析は、当研究所の委員会(先端科学技術動向調査委員会(加速器科学))により方向付けを行っている。平成10年度の上記委員会のメンバーを次頁に示す。
3.得られた成果・残された課題
本年度においては、(新しい加速原理等に基づく)小型(先進型)加速器等に関する具体的な提案の調査・まとめを行い、それらを加速器研究者に提示し、実現性等に関する予測見解を収集した(「ブレークスルー加速技術による小型加速器等に関する開発予測調査」:平成10年11月〜平成11年1月)。この調査により、いくつかの小型(先進型)加速器の実現時期の予測を行うとともに、直面する技術的課題等を把握できた。新たに得られた実現時期の予測は、過去の技術予測結果との比較により、研究の進捗を分析する基礎資料となるものである。
次年度においては、小型(先進型)加速器等に関する具体的な提案と実現予測結果を提示しつつ、加速器でつくられる種々のビームの利用状況及び将来的な加速器ビームのニーズ等を調査し、支援すべき点を検討・分析する。
4.特記事項
他の政策研究機関においては、このような調査研究については例がない。
5.論文公表等の研究活動
「ブレークスルー技術による小型加速器等に関する開発予測調査結果」を調査資料として1999年5月刊行予定。
先端科学技術動向調査委員会(加速器科学)委員(平成10年度)(敬称略、50音順)
委 員 上坂 充 東京大学 大学院工学系研究科 原子力工学研究施設 助教授
〃 遠藤 一太 広島大学 大学院先端物質科学研究科 教授
〃 小方 厚 広島大学 大学院先端物質科学研究科 教授
(平成10年9月末まで 文部省 高エネルギー加速器研究機構 教授)
〃 片山 武司 東京大学 大学院理学系研究科 原子核科学研究センター 教授
〃 北川 米喜 大阪大学 レーザー核融合研究センター 助教授
〃 熊谷 教孝(財)高輝度光科学研究センター 加速器部門長
〃 熊田 雅之 放射線医学総合研究所 主任研究官
〃 小山 和義 工業技術院 電子技術総合研究所 主任研究官
〃 佐藤 勇 日本大学 原子力研究所 教授
〃 佐藤 健次 大阪大学 核物理研究センター 教授
〃 竹田 誠之 文部省 高エネルギー加速器研究機構 助教授
〃 中島 一久 文部省 高エネルギー加速器研究機構 助教授
〃 中村 一隆 東京工業大学 応用セラミックス研究所 助教授
〃 西田 靖 宇都宮大学 大学院工学研究科 教授
〃 野田 章 京都大学 化学研究所 原子核科学研究施設 教授
委員長 平尾 泰男 放射線医学総合研究所 顧問
委 員 水本 元治 日本原子力研究所 東海研究所 中性子科学研究センター
陽子加速器研究室長 (主任研究員)
〃 矢野 安重 理化学研究所 サイクロトロン研究室
RIビームファクトリー計画推進室長 (主任研究員)
2010年代の国民生活ニーズとこれに関連する科学技術
斎藤 均、寺尾 博、新名秀章、瀬谷道夫、香月祥太郎、江幡禎則、桑原輝隆
1.調査研究の目的及び性格
本調査研究は、21世紀初頭(2010年代まで)の我が国の国民生活の状況について展望し、国民生活ニーズの中長期的動向を把握、これらに対応するニーズサイドからの重要技術課題と今後の科学技術の方向性を調査・検討することを目的とする。
2.研究課題の概要
科学技術政策の推進に当たっては、科学技術の発展動向に着目するとともに、社会・経済の将来ニーズを見通し、これらに対応するための科学技術の発展を政策的に図ってゆくことが重要である。科学技術基本計画において、生活者のニーズに対応した課題の解決は、研究開発の基本的方向の一つとして掲げられている。我が国は、21世紀初頭から人口が減少し高齢化が急速に進展すると予測され、環境制約も強まる。このような状況において、国民生活の質の維持・向上に直接関係する科学技術は、今後の科学技術政策を考える上で重要な要素である。展望の期間は2010年代までの約20年間程度とし、変動要素としては、上記の人口動態と環境制約の2点を考慮した。その他の要素については最近の傾向が続くと想定した。
3.得られた成果・残された課題
生活者ニーズの切り口を家計、生活時間、教育、老若男女共同参画社会、社会保障、健康維持と医療、食生活、住生活、生活廃棄物、情報、安全、生活関連社会資本の12分野に分類した。各分野について、データに基づく過去のトレンド、外国との比較、世論調査等に見られる人々の意識の把握を行うとともに、今後の高齢化の進展、環境制約の強まりを踏まえて、いくつかの中長期的課題を抽出した。これらの中長期課題について、現在の政策及び国内各層からの提案・論議などを考慮し、経済的、制度的、技術的対応の方向性をとりまとめた。
技術との関連が大きい中長期的課題については、第6回技術予測課題から関連するものを収集し、課題数、専門家の間での重要性評価、実現予測時期、技術の実現に何が必要とされているかなどを分析した。一例として「健康維持と医療」分野の結果を示す。この分野の中長期的課題は、がんの治療、生活習慣病に関する医療技術、個人の生活パターンに合わせたアドバイスシステム、高齢者に特有の疾病の予防と治療、心の病への対応、感染症への対応、アレルギー疾患への対応、患者の満足度の向上、横断的医療技術(脳研究・遺伝子治療・人工臓器等)の向上、医療についての社会的合意の形成の10項目である。これらの中長期的課題の技術予測での位置付けと、重要度指数と実現時期及び課題数の関係は図のようになる。
国民生活ニーズは極めて広い領域にまたがり、その内容と重み(重要性)も多様である。これまでにニーズへの対応がかなり進んだものもあれば、いまだ問題が残されたままのものも存在する。今後国民生活ニーズは、より質の高い生活と多様化した価値観を充足させるような生活環境の実現へと高度化する。このような個人個人のニーズに対応していくことが大きな課題であり、この際、個人の自己実現の基盤となる社会が安定し、持続的に発展するよう社会ニーズとの整合をとっていく工夫が一層必要となる。
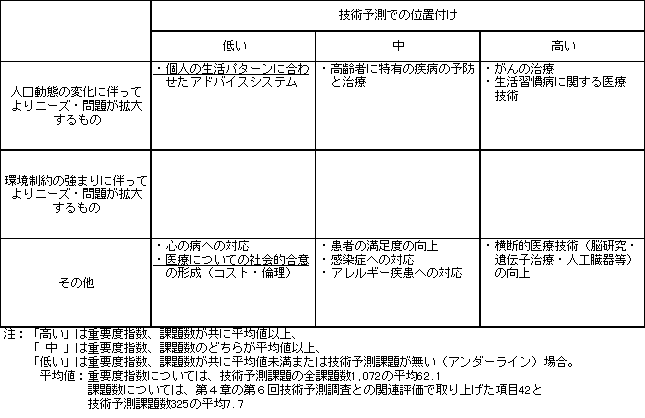
今回の調査研究から、生活者ニーズ対応科学技術の方向性として、①個人個人の人間性重視と自己実現、②多様なコミュニティの形成と共生、③技術の実現に向けての相互連携と結合、④予測・警鐘と意識への働きかけの4点が重要と考えられる。
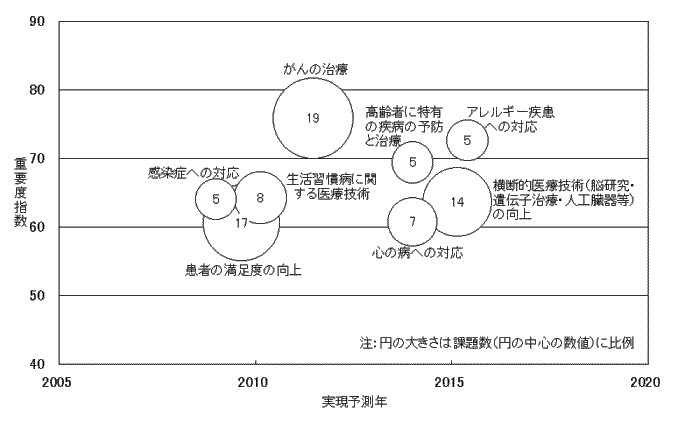
本調査研究は、国民生活全般にわたる将来展望とともに、ニーズ実現の具体策として個別技術レベルまで捉えようとする試みであり、この結果は、本年着手の第7回技術予測調査に反映させる方針である。対象とした国民生活の範囲の捉え方の適否、主たる長期変動要因が人口動態と環境制約の2点のみで充分かどうか、などについて検討した上で次の段階に進めていきたい。
4.特記事項
21世紀初頭の展望は各省庁・新聞社などが描いているが、産業・経済など分野が限定されている。国民生活の広い分野をカバーし、生活関連の科学技術の観点から扱われているものはない。
5.論文公表等の研究活動
[1] 斎藤 均、寺尾 博、新名秀章、瀬谷道夫、香月祥太郎、江幡禎則、桑原輝隆「2010年代の国民生活ニーズとこれに関連する科学技術」NISTEP REPORT No.62(1999.3)
外国技術導入の動向分析(平成8年度版)
山口 治、久野美津子、田村泰一、吉水正義、清家彰敏(富山大学)
1.研究の目的
我が国における外国技術導入の動向をより正確に把握し、技術貿易関連の研究における基礎的なデータを得ることを目的として、「外国為替及び外国貿易管理法」による技術導入契約の締結(変更)に関する報告書等に基づき、毎年度、我が国における外国からの技術導入の実績をとりまとめるとともに、最近の技術導入の動向について分析を行っている。
2.研究課題の概要
1)調査対象
「外国為替及び外国貿易管理法」に基づいて、提出された「技術導入契約の締結(変更)に関する報告(届出)書」で、平成8年度中(8.4.1〜9.3.31)に受理されたもの。
平成8年度新規技術導入契約 3,145件
平成8年度変更契約 1,216件
2)調査項目
1) 企業:業種分類、資本金規模
2) 導入技術:技術の内容、技術分類、技術の種類、先端技術
3) 契約相手先企業:相手先国・地域、資本関係
4) 契約条件:契約期間、対価支払方法、独占権・再実施権・クロスライセンスの有無
3.得られた成果・残された課題
○ 米国からの技術導入が依然として多く、6割を占めるが、ハード系技術については減少傾向にあり、特に今年度は、前年度に比べ1割以上減少。
○ ソフトウェア件数が横ばいの中、100億円以上の資本金規模の企業の導入が、3年前より一貫して増加傾向。
○ 権利取得を伴う技術導入がソフトウェアでは過去2年間の増加から減少に転じ、ハード系技術では若干増加。
○ 契約期間の「1年以上5年未満」の技術導入割合が、ソフトウェアで昨年度に続き、減少。
4.特記事項
本調査研究は法令に基づく報告書等の個票により分析を行っており、他の調査が追随することは困難である。
5.論文公表等の研究発表
[1]「外国技術導入の動向分析(平成8年度)」NISTEP REPORT No.57(1998.5)
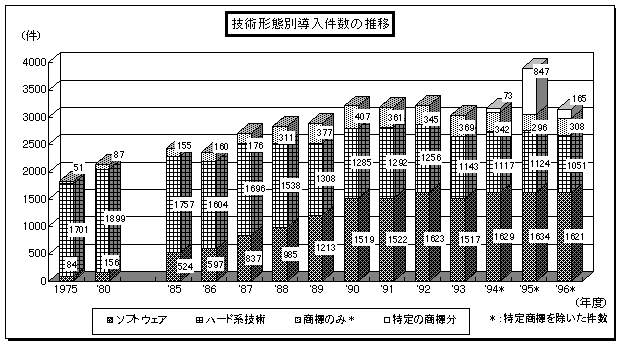
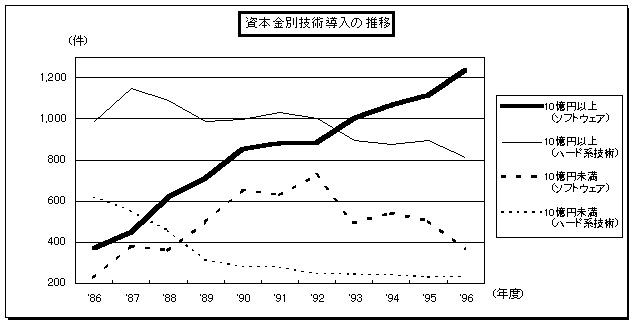
日本の技術輸出の実態(平成8年度版)
田村 泰一、久野美津子、山口 治、吉水 正義、清家 彰敏(富山大学)
1.研究の目的
外国との技術、ノウハウの取引、いわゆる技術貿易の実態把握は、我が国の技術水準、技術開発力に対する知見を得るだけでなく、我が国と外国との技術上の結びつき及び我が国の技術の国際的な波及の実態を把握する上で重要な意義を有している。
本調査研究は、技術の輸出について実態を分析し、政策立案のための基礎的なデータを提供することを目的としている。
2.研究課題の概要
(1)調査方法及び回収方法
1) 調査対象企業:資本金10億円企業で、研究開発活動をしている企業及び技術貿易と関連のある国内の民間企業(1,590社)
2) 調査対象契約:平成8年度(平成8年4月1日〜平成9年3月31日)の1年間で締結された技術輸出契約
3) 調査方法:郵送によるアンケート調査。宛先は各社の知的財産部門長もしくは研究開発管理部門長
4) 講習結果:回答企業数1,107社(回収率69.6%)
(2)調査項目
5) 企業:業種分類、資本金規模
6) 輸出された技術:技術の内容、技術分類、技術の種類、内包する特許数、先端技術
7) 契約相手先企業:輸出先国・地域、資本関係
8) 契約条件:契約期間、契約形態、対価受取方法、独占権・再実施権の有無
3.得られた成果・残された課題
○ ここ数年増加していた中国への技術輸出が、今年度は減少に転じ、中国への技術輸出が一段落した。
○ 米国への技術輸出は、今年度は大幅に増加し、3年連続して1位を占めている。
○ 技術内容については、5年連続して「輸送用機械」が1位を維持したが、前年度に比べて減少に転じ、一方、「鉄鋼」が大幅に増加し、2位に上昇した。
4.特記事項
特になし
5.論文公表等の研究発表
[1]「日本の技術輸出の実態(平成8年度)」NISTEP REPORT No.58(1998.9)
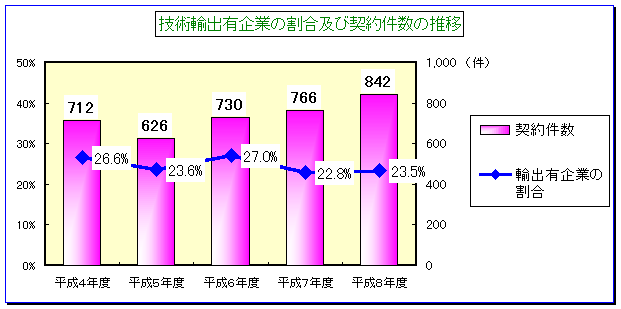
図1 技術輸出有り企業の割合及び契約件数の推移
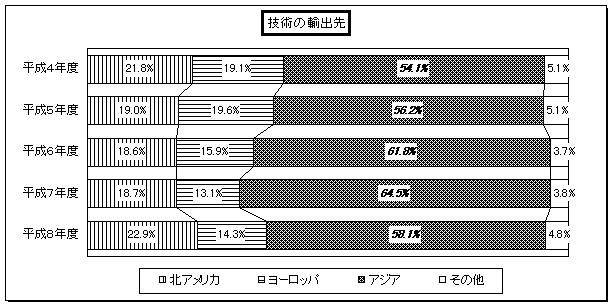
技術貿易収支の定量的分析
田村泰一、吉水正義、前澤祐一(1調)、清家彰敏(富山大学)
1.研究の目的
技術貿易収支の統計としては、日本銀行の「国際収支統計」、総務庁「科学技術研究調査報告」がある。これらは、対象とする技術範囲、業務範囲等の違いから、技術貿易額が異なっており、貿易収支の決定を困難にしている。
この技術貿易の収支については、技術に関する国際競争力示す資料として、社会的・学問的に関心が高いので、これを推定することはきわめて意義の大きいことである。
2.研究課題の概要
本調査では、既存の技術貿易統計との関係を踏まえ、分析可能な範囲で、技術貿易の対象とすべき技術の定義を検討し、それに基づく技術貿易の推定法を構築する。
また、最近取引件数が増加しているためにソフトウエアに関する技術貿易額が増加していることや、ソフトウエア自身が、日銀・総務庁の両統計でどのように扱われているかについて、検討委員会を設置して検討する。
3.得られた成果・今後の課題
○ 既存統計に対する検討点に合意が見られた。
○ 我が国の技術貿易の問題点を確認した。
○ 今後の対応として、両統計の構造解析、ソフトウエア流通に関係する技術輸出の定義等が必要であることの統一的認識を得た。
- これらを解決するために総務庁統計や通産省の統計を入手し分析することとした。
4.特記事項
特になし
5.論文公表等の研究活動
特になし
技術貿易検討会(五十音順)
委員浦田 秀治郎早稲田大学社会科学部教授
委員加藤 重治科学技術庁科学技術政策局調査課課長
委員木村 福成慶應義塾大学経済学部助教授
委員西村 吉正早稲田大学大学院アジア太平洋研究センタ―教授
委員清家 彰敏科学技術政策研究所客員研究官(富山大学経済学部助教授)
委員高橋 三雄麗澤大学国際経済学部教授
委員椿 広助筑波大学社会工学系助教授
委員長廣松 毅東京大学大学院総合文化研究科 教授
委員前澤 祐一科学技術政策研究所第1調査研究グループ総括上席研究官
委員丸山 芳樹通省産業省大臣官房調査統計部企業統計課課長
委員山内 健生総務庁統計局統計調査部経済統計課課長
委員吉水 正義科学技術政策研究所情報分析課課長
アジアの科学技術政策に関する調査研究
吉水正義、清家彰敏(富山大学)
1.研究の目的及び性格
90年代に順調な成長を続けてきたアジア経済は、いわゆるアジア危機によって大きく停滞している。このような経済状況下、アジアは、短期的には、経済危機の乗り切り、長期的には、科学技術政策により産業基盤を強化していく必要がある。また、これらを活用して、発展途上国において果たすべき科学技術政策の機能を見直していく必要がある。
2.研究課題の概要
本調査では、現在のアジアの状況を概観するために、アジアの科学技術政策に関する研究会を設置し、情報を収集する。その中に位置づけられている科学技術政策の果たしている役割について分析を行う。また、集めた結果を発展に必要な条件や政策として一般化する。
3.得られた成果・残された問題点
これまでに委員会を2回開催した。
第1回研究会(平成10年9月22日)
議題:アジアの科学技術政策研究についての大学等からの取り組み
出席者:小林 英夫早稲田大学大学院アジア太平洋研究所教授
島田 克美元流通経済大学経済学部教授
郭 陽春立教大学経済学部教授
岩内 透徳富山大学経済学部助教授
第2回研究会(平成10年11月30日)
議題:アジアにおける事業展開を実施中の各社の取り組み
出席者:池田 宏株式会社東芝アジア総代表
新井 昇株式会社東芝国際部アジア担当グループ長
後藤 壮輔財団法人資源協会地球科学技術推進機構参事・技術部次長
青山 修二株式会社ハートウエア21代表取締役
小林 英夫早稲田大学大学院アジア太平洋研究所教授
岩内 透徳富山大学経済学部助教授
○ 今後、金融界、商社等を招聘して研究会を開催し、中間報告書をまとめる。
○ 次に、中間報告書により、アジア諸国側から見た我が国の実態を調査する予定。
○ 最終的には貿易収支算出方法の理論の模索と研究作業の実施。
4.特記事項
特になし。
5.論文公表等の研究活動
特になし。
ソフトウエアにおける外国技術導入の動向分析
清家彰敏(富山大学)、田村泰一、吉水正義
1.調査研究の目的及び性格
これまでの調査によれば、日本は、ソフトウエアを米国から導入し、ハード系技術をアジアの各国へ輸出しているという構造が得られている。
本調査は、技術輸入から技術輸出に至るソフトウエアのフローを調査し、我が国のソフトウエアの技術貿易の構造を把握するものである。
2.研究課題の概要
「外国技術導入の動向分析」で得られたデータから、ソフトウエアに関する技術を内容別に再分類し、金額ベースで調べられている他の統計を活用しながら、詳細に分析し、技術貿易を実施する民間企業に対してインタビュー調査を行う。
3.得られた成果・残された課題
○ 1996年度は分析シミュレーションが1位で16.5%。1997年度は通信ソースコードが1位。ゲームは、1996年度が、4.1%。1997年度が4%である。
○ 通信・電子電気系が全体の29.7%である。
○ ソフトウエア開発は米国が群を抜いている。続いて英国、カナダと言った英語圏が強い。
○ OSは米国の占める割合が最大。
○ 業務用とゲームが米国の占める割合が最も小さい。
4.特記事項
本調査研究は法令に基づく届け出個表より分析しており、他の調査が追随することは困難である。
5.論文公表等の研究発表
[1]「ソフトウエアにおける外国技術導入の動向分析」NISTEP REPORTとして、1999年に発表予定。
技術導入取引の契約形態・企業内部化要因の分析
和田哲夫(郵政研)、吉水正義
1.調査研究の目的及び性格
技術は、他の財に比べて専有可能性などいろいろな点で異なることが指摘されており、この結果、技術の取引形態も特殊なものとなることが多い。国際技術取引でも、子会社に対する企業内部移転として行われる場合や、クロスライセンスなど、財一般と異なる特殊形態が使われている。国際企業論の観点から、技術移転の内部化の理由を問う研究が従来から行われてきたが、契約・特許単位の実証研究はまだ少ない。そこで、実証のため貴重な技術導入データを用い、どのような要因で技術導入取引に特殊契約形態が用いられるのか、経済学上の知見を得ることを目的とする。なお、平成10年度は電機・情報通信関係技術におけるクロスライセンスを中心に研究結果を得た。
2.研究課題の概要
米国から日本への特許許諾契約(資本関係のない企業間)と、それに含まれる特許を主な分析対象とした。契約毎にクロスライセンスによって対価の一部が支払われたかどうかを被説明変数とし、その契約中の米国特許に関する被引用特許数や、自己引用特許の比率を主な説明変数として、特許単位で計量分析を行っている。
3.得られた成果・残された課題
本研究では、まず一方向ライセンスで多くの企業に許諾されている特許にはクロスライセンスがほとんど見られないことが発見された。そして、現在の結果からは、自己引用比率で見た技術専有度が高い特許は、クロスライセンスでしか与えられない傾向が観察される。この自己引用比率は、企業が継続するイノベーションにおいて守るべき中心的な技術的能力を表すと思われる。
特許の技術開発インセンティブを考える上で、イノベーションの累積的な性質が重要であり、どのように企業間で技術契約を結べるかが重要だということが指摘されてきた。ここでは、累積的・相互補完的な技術の代表的な分野において、「特許化された技術での専有可能性」と技術取引の形態が関連を持っていることが示された。
4.特記事項
電気・情報通信技術では、イノベーションが累積的に起こり、また、技術間での補完関係が重要である。そこで、単独の企業の持つ特許だけでは足らず、複数企業の知的財産権を組み合わせることが必要であり、クロスライセンスが行われていることは知られているが、どのように使われているかについて、実証研究は今までほとんどない。
5.論文公表等の研究発表
[1] 「累積的イノベーションにおける技術専有とクロスライセンス」Discussion PaperNo.10として1999年6月に刊行予定。
榊原清則(第1研究グループ総括主任研究官)
・慶應義塾大学非常勤講師1998.4.27〜1999.3.31
・航空・電子等技術審議会専門委員
・(財)機械振興協会経済研究所「デジタルマニュファクチャリングに関する調査研究」委員会委員1998..9〜1999.3
・科学技術振興事業団総合評価委員会委員1998.10.1〜2000.3.31
・科学技術振興事業団総合評価委員会技術移転推進事業評価部会委員1998.10.16〜2000.3.31
平澤 (第2研究グループ総括主任研究官)
・(財)政策科学研究所理事1998.1.12〜2年間
・(財)政策科学研究所理事「平成10年度技術政策・技術経営の教育研究に関する調査」研究委員1999.1.13〜1999.3.31
・(社)リサーチ・マネジメント技術交流協会理事1998.5.6〜1999.3.31
・日本学術会議社会・産業・エネルギー研究連絡委員会委員1997.10.22〜2000.10.20
・日本学術会議社会・産業・エネルギー研究連絡委員会人工物設計・生産研究連絡委員会〃
・新エネルギー・産業技術総合開発機構地域コンソーシアム審査委員会1998.3.2〜1999.3.31
・新エネルギー・産業技術総合開発機構地域コンソーシアム審査委員会国際研究協力委員会1998.5.1〜2000.3.31
・新エネルギー・産業技術総合開発機構地域コンソーシアム審査委員会国際研究協力委員会研究協力プロジェクト推進委員会1998.5.1〜2000.3.31
・(社)日本工学アカデミー国立試験研究機関等小委員会1998.4.23〜1999.3.31
・工業技術院新規産業創造技術開発費補助金外部評価委員会委員1998.5.13〜1999.3.31
・(社)研究産業協会「JICRAD企画委員会」委員1998.5.28〜1999.3.31
・工業技術院産業技術審議会1998.6.17〜1999.3.31
・東レ経営研究所受託調査研究委員1998.9.1〜1999.3.31
・科学技術庁科学技術振興局「若手研究者・研究技術者の確保、活用等に関する懇談会」委員1998.10.23〜1999.3.31
・文部省学術国際局「日本ユネスコ国内委員会自然科学小委員会及び人文・社会科学小委員会世界会議のためのWG委員1999.1.26〜世界会議終了後まで
佐藤征夫(所長)
・科学技術と社会に関する国際会議組織委員会1997.10.30〜1998.4.30
田村泰一(情報分析課課補佐)
・(財)新技術開発財団調査選考委員承認日より2年
富澤宏之(第2研究グループ主任研究官)
・東京大学教養学部非常勤講師1998.4.1〜1998.9.30
藤垣裕子(第2研究グループ主任研究官)
・信州大学人文学部非常勤講師1998.4.1〜1999.3.31
・東京大学教養学部非常勤講師1998.4.1〜1999.3.31
・北陸先端科学技術大学院大学1999.1.18〜1999.1.19
大山真未(第2調査研究グループ上席研究官)
・(社)科学技術国際交流センター第4回アジア・太平洋科学技術マネジメントセミナー企画運営委員会委員1998.8.24〜1999.3.31
・科学技術会議生命倫理委員会(科学技術庁研究開発局生命倫理対策室)
標記委員会に参加し結果をPOLICY STUDY No.1として1999年5月に刊行予定。
木場隆夫(第2調査研究グループ上席研究官)、大山真未(第2調査研究グループ上席研究官)
・将来の科学技術に関する世論調査において(総理府・内閣総理大臣官房広報室)が実施した。
一般国民3000人に対する科学技術についての意識調査の質問作成分析調査に協力。
世論調査結果を冊子にまとめて発行。1999年2月6日、プレス発表を行った。
科学技術政策に関する研究調査活動を効果的かつ円滑に推進するため、情報処理システムの整備を行った。
1) ハードウェアの拡充整備
NISTEP情報システムは、UNIXワークステーション及びWindows NTサーバをサーバ機とし、パーソナルコンピュータ等をクライアント機とする、クライアント・サーバ型システムで、TCP/IPによるLANを構成している。クライアント機は、科学技術庁図書館にも設置し、科学技術庁図書館と科学技術政策研究所との間を、NTTデジタル公衆回線(INSネット64)で接続している。また、所内LANは、専用回線を経由して、省際研究情報ネットワーク(IMnet:Inter-Ministry Research Information Network)に接続されている。
本年度は、下記の点についての整備等を実施した。
・ウィルスチェック機能の強化
・所内コンピュータの性能向上
・「国立国会図書館 中央館・支部図書館ネットワーク」への接続
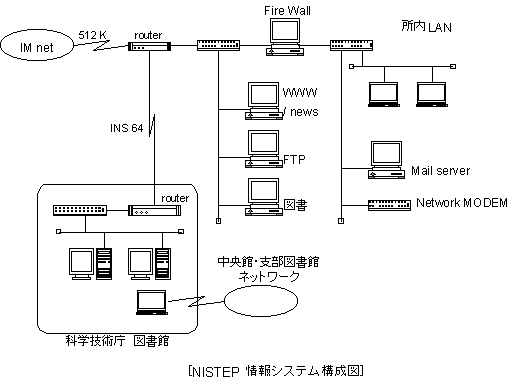
2) 内部データベースの利用
当研究所内で作成・保有しているデータベースは、下記の通りである。
・外国技術導入
3) 外部データベースシステムの利用
現在利用可能な外部データベース、情報サービスは、下記の通りである。
・国会図書館システム(NOREN)
・科学技術振興事業団システム(JOIS)
・総務庁統計情報データベースシステム(SISMAC)
・日本経済新聞社システム(NIKKEI Biz)
・情報発信
インターネットホームページに、政策研ニュース、人材募集、ワークショップ案内等の情報を掲載、公開している。更に平成11年6月頃を目標にホームページの刷新を予定している。
・研究成果の公開
NISTEPレポート、調査研究資料等の情報を、WWWサーバ及びFTPサーバに搭載し、インターネットを通じて公開している。平成10(1998)年度に掲載したものは、下記のものである。この他ホームページ刷新時期に合わせて平成10年度補正予算により作成した概要版(日英)などの掲載を予定している。
NISTEP Report No.57「外国技術導入の動向分析(平成8年度)」(概要)
NISTEP Report No.58「日本の技術輸出の実態(平成8年度)」(概要)
調査資料・データ No.53「大学における新構想型学部に関する実態調査」(概要)
調査資料・データ No.54「英国における研究評価−公的研究助成にみる評価"Value for Money"と"Selectivity"」(概要)
調査資料・データ No.55「主要各国の科学技術政策関連組織の国際比較」(全文)
調査資料・データ No.57「英国及びニュージーランドにおける国立試験研究機関の民営化について」(全文)
図書館(国立国会図書館支部科学技術庁図書館:所掌情報分析課)及び資料室においては、書籍の登録、検索、貸出整理等の業務を図書管理システムの運用により実施した。また図書館においては、新着図書速報等はMD掲示板に月1回掲示する等、図書情報の提供を行った。
この他、国立国会図書館及び、他支部図書館との間で所蔵図書の相互貸出を行った。
|
区分 |
蔵書冊数 | 本年度
増加数 |
外国雑誌 | 国内雑誌 | 特殊資料 | 選任職員 |
|
冊 |
冊 |
タイトル |
タイトル |
人 |
||
|
科学技術庁図書館 |
33,996 |
1,028 |
24 |
746 |
2 |
|
|
航空宇宙技術研究所分館 |
52,925 |
1,791 |
250 |
427 |
108,461 |
3 |
|
金属技術研究所分館 |
34,575 |
915 |
165 |
181 |
3 |
|
|
放射線医学総合研究所分館 |
57549 |
1,878 |
261 |
35 |
3 |
|
|
科学技術政策研究所資料室 |
6,433 |
257 |
45 |
55 |
1 |
当研究所の活動を広報するために、「科学技術政策所年報(1997年度版)」及び「政策研ニュース(111号から122号(月刊)まで)」を作成し発行した。
1.米国・科学財団(NSF)科学技術に対する社会意識に関する比較研究協力等(1989.1.5)
2.米国・ハーバード大学J.F.ケネディースクール科学と公衆政策計画:技術移転のメカニズムその他についての共同研究等(1989.2.27)
3.米国・シラキュース大学、技術と情報政策計画:国立試験研究機関に関する比較共同研究の実施等(1989.5.18)
4.英国・エジンバラ大学日本−欧州技術研究所(JETS):日米欧の科学技術政策の比較研究等(1989.6.2)
5.米国・マサチューセッツ工科大学(MIT)技術と政策計画:技術普及・移転メカニズム、人材問題等産業界をも視野におさめた科学技術政策全般(1989.6.8)
6.英国・サセックス大学科学政策研究所(SPRU):科学技術政策研究に関する情報と研究者の交流、研究交流セミナーの関係等(1989.6.1)
7.米国・オクラホマ大学と公衆政策計画:科学技術政策研究に関する情報と研究者の交流、研究協力(特に科学技術政策の比較検討等)やセミナ−開催等(特に科学技術政策の比較検討等(1989.12.15)
8.独国・フラウンホーファー協会システム・技術革新研究所(ISI):科学疑似湯津政策研究に関する情報と研究者の交流、研究協力やセミナーの開催等(特にイノベーション研究、科学技術の国際分析、新技術の可能性と影響、技術予測、R&Dマネージメントの国際比較)(1990.2.5、1998.11〔改訂〕)
9.米国・ヴァンダービルト大学、管理と技術計画:科学技術政策と技術マネージメント分野における研究協力(特に科学技術政策立案、テクノロジーの普及と移動のメカニズム)
(1991.6.10)
10.国連大学新技術研究所(INTECH):科学技術公共政策分野における研究協力(特に技術普及と移転メカニズム、科学技術政策の比較研究、科学工学における人的資源、地球的環境変化のマネージメント)(1992.12.3)
11.韓国・科学技術政策管理研究所(STEPI):科学技術政策研究に関する情報と研究者の交流、研究協力(1993.3.8)
12.中国・国務院発展研究中心:地域科学技術政策研究に関する共同研究打ち合わせ等(1993.4.30)
13.欧州共同体・第12総局未来技術学研究所(PROMPT):地域科学技術政策研究に関する共同研究等(1993.8.1)
14.英国・マンチェスター大学工学:科学技術における政策研究計画(PREST)研究者の受け入れ等 (1993.10.1/1997.11.7更新)
15.米国・ジョージメイソン大学:公共政策研究所研究者の受け入れ等
(1994.1.1/1998.5更新)
16.仏国・科学技術観測所(OST):研究協力のためのレター交換の実施等(1999.2更新)
17.中国・国家科学技術委員会科技促進発展研究中心:技術移転に関する共同研究、地域経済開発のための科学技術政策に関する共同研究の打ち合わせ等(1994.4.30)
18.仏国・研究技術総局(DGRT)(1994.5.20)
19.豪州・マードック大学科学技術政策研究所:研究協力のためのレター交換の実施等(1994.7.1)
20.米国・タフツ大学:研究協力の合意(1994.8.22)
21.仏国・ルイ・パスツール大学:技術予測及び研究開発マネジメントに関する共同研究(1994.10.21)
22.豪州・科学技術会議:技術予測に関する共同研究 (1994.11.29 1999.4.22更新)
23.米国・オレゴン大学:技術革新過程における中小企業役割に関する共同研究(1995.3.14)
24.米国・シカゴ科学アカデミー国際科学リテラシー開発センター:科学技術に対する社会意識に関する比較共同研究の実施等
25.韓国・科学技術処国際協力局:研究者の受け入れ
26.蘭国・アムステルダム大学(1998.4.)
27.国際機関・国際応用システム分析研究所(1998.6.)
28.仏国・フランス鉱山大学社会技術革新センター:科学技術政策研究(1995.6.28)
29.独国・ミュンヘン大学人間研究センター(HWZ)(1998.11.)
30.国際機関・国際応用システム分析研究所(IIASA):科学技術政策研究に関する情報と研究者の交流、研究協力、セミナー開催等(1998.6)
31.米国・ワシントン大学:科学技術政策研究に関する情報と研究者の交流、研究協力、セミナー開催等(1999.1.)
(2)国際会議への出席及び海外出張
1.AAAS科学技術政策コロキアム参加
(米国、98.4.28-5.4)出席者:第2研究グループ平澤総括主任研究官
2.エジンバラ大学日欧科学技術政策研究所での地域科学技術振興に関する会合参加
(英国、98.5.19-5.25)出席者:第3調査研究グループ権田客員総括研究官
3.英国王立学会出席ほか
(英国、98.5.25-5.31)出席者:第1研究グループ榊原総括主任研究官
4.国際シュムペーター学会で論文発表ほか
(オーストリア、98.6.10-6.17)出席者:第1研究グループ後藤客員総括研究官、古賀研究官
OECD/CSTP/NESTI会合出席
(仏国、98.6.13-6.19)出席者:第1研究グループ富沢主任研究官
5.国際社会学会議で論文発表
(カナダ、98.7.24-8.3)出席者:第2研究グループ藤垣主任研究官
市民参加型テクノロジーアセスメントに関するワークショップ(デンマーク議会技術委員会主催)出席
(デンマーク、98.8.31-9.5)出席者:第2調査研究グループ木場上席研究官
6.科学技術政策に関する国際ワークショップ参加ほか
(オーストリア、98.9.16-9.21)出席者:佐藤所長
7.科学技術政策に関する国際ワークショップ参加ほか
(オーストリア、スイス、98.9.16-9.24)出席者:第2研究グループ藤原特別研究員
8.欧州連合会議テクノロジーアセスメント研究集会
(ベルギー98.9.30-10.5)出席者:第2調査研究グループ木場上席研究官
9.日中女性科学者広州シンポジウム出席
(中国、98.10.4-10.9)出席者:第1調査研究グループ横尾研究官
10.APEC第2回サイエンスパーク国際会議
(オーストラリア、98.10.19-10.24)出張者:第3調査研究グループ権田客員総括研究官
Forum Mondial de I'innovation参加
(仏国、98.11.15-11.23)出張者:第1研究グループ前田客員総括研究官
11.地域科学技術政策研究国際会議研究発表及び討議
(米国、98.11.18-11.27)出張者:第3調査研究グループ権田客員総括研究官
(米国、98.11.19-11.26)出張者:佐藤所長
(米国、98.11.19-11.26)出張者:第3調査研究グループ柿崎主任研究官
(米国、98.11.20-11.26)出張者:第3調査研究グループ休井特別研究員
12.Congressional Research Service(議会調査機関)において最近の日本の科学技術状況について講演
(米国、98.11.28-12.3)出張者:第2研究グループ平澤総括主任研究官
13.科学技術情報の自己組織化プロジェクトの中間報告会参加
(オランダ、98.12.4-12.12)出張者:第2研究グループ藤垣主任研究官、渡辺研究官
14.仏首相府計画総庁での日本の科学技術政策に関する講演及び討論
(仏国、99.1.19-1.24)出張者:佐藤所長
15.AAAS(米国科学技術振興協会)年次総会参加
(米国、99.1.20-1.25)出張者:第2調査研究グループ大山上席研究官
18.開発と企業セミナー参加
(フィリピン、99.2.14-2.20)出張者:情報分析課吉水課長
19.政策形成研究開発実施過程における産学官のインタラクションに関する研究
に伴う調査(英国、99.2.16-2.27)出張者:第1研究グループ伊地知研究官
20.ベンチャービジネス支援政策に関する調査
(米国、99.3.8-3.19)出席者:第1研究グループ前田客員総括研究官
21.大学における技術系ベンチャービジネス振興策研究の実体調査
(米国、99.3.10-3.22)出席者:第1研究グループ榊原総括主任研究官
22.ローマ法皇庁科学アカデミー主催The Study Week ”Science for Survival and SustainableDevelopment”参加
(バチカン市国、99.3.11-3.18)出張者:佐藤所長
23.科学技術政策について
(ドイツ、エジプト、カナダ、99.3.12-3.28)出張者:第2研究グループ平澤総括主任研究官
24.加速器に関する先端科学技術動向調査
(米国、99.3.21-3.31)出張者:第4調査研究グループ瀬谷主任研究官
25.加米の評価に関する調査
(米国、99.3.21-4.1)出席者:第2研究グループ武内上席研究官
26.米国における研究開発の国際化調査
(米国、99.3.31-4.11)出張者:第1研究グループ田中上席研究官
1.韓 亨浩(Mr. Han Hyung-Ho):韓国科学技術処 技術協力部 研究管理課長
研究課題:国立研究機関の研究評価とその応用
滞在期間:平成9年8月21日〜平成12年8月20日
所属グループ:第2研究グループ
招聘制度:韓国政府派遣
2.Dr. John Mark Boden:英国マンチェスター大学工学科学技術政策研究所(PREST) Visiting Research Fellow
研究課題:環境政策と技術開発とのネットワークダイナミクスに関する比較解析
滞在期間:平成9年12月1日〜平成10年11月30日
所属グループ:第1研究グループ
招聘制度:STAフェローシップ制度
3.Dr. Itzhak Wirth:米国Associate Professor of Management, College of Business Administration/Management Department, St. John’s University
研究課題:研究開発マネージメントにおける戦略的選択肢:日本の医薬品産業における新製品開発の場合
滞在期間:平成10年6月15日〜9月14日
所属グループ:第1研究グループ
招聘制度:STAフェローシップ制度
4.Dr. Steven Wayne. Collins:米国Assistant Professor, Program in Interdisciplinary Arts & Science,University of Washington, Bothell
研究課題:日本の地域科学技術の政策形成過程における政府と地方公共団体の役割分担などの相互関係をイノベーションシステムの視点から研究する。
滞在期間:平成10年9月4日〜12月3日
所属グループ:第3調査研究グループ
招聘制度:科学技術庁STAフェローシップ制度
5.Dr. Eva Maria Ruhnau:独国Director, Human Studies Center, Ludwig-Maximilians-Univerisity of Muinch
研究課題:将来の知識社会の形成のための、国際的規模の学際的研究及び科学政策を推進。情報社会から知識社会への変化に関連した学際的研究及びその応用、特に日本の「場」の概念とドイツの「Syntopy」の概念との比較研究を行う。
滞在期間:平成10年10月6日〜11月5日
所属グループ:第3調査研究グループ
招聘制度:科学技術庁外国人研究者招聘制度
6.Dr. Lars Klyver:デンマーク議会事務局長
研究課題:科学技術と人間社会に関する研究(特に、コンセンサス会議における経験)
滞在期間:平成10年10月11日〜10月18日
所属グループ:第2調査研究グループ
招聘制度:科学技術庁国際客員官制度
7.Dr.Yi-Tzuu Chien:米国国立科学財団(National Science Foundation(NSF)),Director, Div. of Information, Robotics and Intelligent System
研究課題:Multi-media Technologies for Information Access: A Study of Japanese Public Policies for Research and Development
滞在期間:平成10年10月24日〜11月23日
所属グループ:第1研究グループ
招聘制度:招聘制度:STAフェローシップ制度
8.劉 海波(Dr. Liu Haibo):中国社会科学院数量経済与技術経済研究所,Post-doctoral Fellowship
研究課題:「科学教育興国」と「科学技術立国」:中日国家振興戦略の比較
滞在期間:平成11年1月5日〜平成13年1月4日
所属グループ:第2研究グループ招聘制度:
招聘制度:STAフェローシップ制度
9.Dr. John P. Walsh:米国イリノイ大学、社会学助教授
研究課題:研究開発関連施策が及ぼす経済効果の定量的評価手法に関する調査
滞在期間:平成11年2月7日〜2月20日
所属グループ:第1研究グループ
招聘制度:科学技術庁 振興調整費ソフト調査制度
10.Dr. Loet Leydesdorf:蘭国,University of Amsterdam, Faculty of Psychology, Department of Social Science Informatics教授
研究課題:科学技術の形成過程における研究者のコミュニケーション構造の日欧比較研究
滞在期間:平成11年2月7日〜2月20日
所属グループ:第1研究グループ
招聘制度:科学技術庁 振興調整費二国間型制度
11.Dr. Peter van den Besselaar:蘭国,University of Amsterdam, Faculty of Psychology, Department of Social Science Informatics教授
研究課題:科学技術の形成過程における研究者のコミュニケーション構造の日欧比較研究
滞在期間:平成11年2月7日〜2月20日
所属グループ:第1研究グループ
招聘制度:科学技術庁、振興調整費二国間型制度
12.Dr. Josephine Anne Stein:英国、 University of East London(Principal Research Fellow), University of Manchester, PREST(Honorary Senior Research Fellow)
研究課題:(ECプロジェクト)「外国政府が国内科学技術に及ぼす影響についての米日を対象とした研究」について
滞在期間:平成11年3月1日〜3月10日
所属グループ:第2研究グループ
招聘制度:招聘制度:政策研外国人招聘滞在費
13.Dr. Sara Nerlove:米国、Program Manager, Small Business Innovation Research (SBIR) Program, Division of Design Manufacturing and Industrial Innovation, NSF
研究課題:Comparison of U.S.-Japan Policies on Small and Medium-Sized Businesses
滞在期間:平成11年3月28日〜4月29日
所属グループ:第3調査研究グループ招聘制度
招聘制度:STAフェローシップ制度
14.Dr. George O’Neill Consultant(NSF)
研究課題:Comparison of U.S.-Japan Policies on Small and Medium-Sized Businesses
滞在期間:平成11年3月28日〜4月29日
所属グループ:第3調査研究グループ
招聘制度:STAフェローシップ制度
NISTEP REPORT
1) 外国技術導入動向分析(平成8年度)
(NISTEP REPORT NO.57 1998.5)情報分析課
2) 日本の技術輸出の実態(平成8年度)
(NISTEP REPORT NO.58 1998.9)情報分析課
3) 地域における科学技術振興に関する調査研究(第4回調査)
(NISTEP REPORT NO.59 1999.3)第3調査研究グループ
4) 我が国製造業の空間移動と地域産業の構造変化に関する研究
(NISTEP REPORT NO.60 1999.3)第3調査研究グループ
5) 日本のベンチャー企業と起業者に関する調査研究−平成10年度−
(NISTEP REPORT NO.61 1998.3)第1研究グループ
6) 2010年代の国民生活ニーズとこれに関連する科学技術
(NISTEP REPORT No.62 1999.3)第4調査研究グループ
調査資料・データ
7) 大学における新構想型学部に関する実態調査
(調査資料・データ53 1998.4)第1調査研究グループ
8) 英国における研究評価−公的研究助成にみる評価-”Value for Money”と”Selectivity”-
(調査資料・データ54 1998.5)第2研究グループ
9) 主要各国の科学技術政策関連組織の国際比較
(調査資料・データ55 1998.6)第2研究グループ
10) 地域科学技術政策研究会(平成10年2月24日、25日)報告書
(調査資料・データ56 1998.7)第3調査研究グループ
11) 英国及びニュージーランドにおける国立試験研究機関の民営化
(調査資料・データ57 1998.9)企 画 課
12) テクノポリス調査報告書
(調査資料・データ58 1998.8)第3調査研究グループ
13) 企業における女性研究者・技術者の就業状況に関する事例調査
(調査資料・データ60 1999.3)第1調査研究グループ
DISCUSSION PAPER
14) マクロモデルによる政府研究開発投資の経済効果の計測
(DISCUSSION PAPER NO.5 1998.3)第1研究グループ
15) 大学からの技術移転成功事例におけるアクター分析
(DISCUSSION PAPER NO.6 1998.3)第2研究グループ
16) 特許と学術論文の形態比較〜記述形式・内容の分析とインタビューによる執筆動因分析〜
(DISCUSSION PAPER NO.7 1998.10)第2研究グループ
1) 国内講演
98.5.14前田 昇(情報分析課客員総括研究官)
「次世代ビジネスモデルにおける科学技術の位置づけ」
6.29堀部政男(中央大学法学部教授)
「情報科学技術の高度化と法的対応」
7.23加藤尚武(京都大学文学部研究科教授)
「先端技術と倫理」
7.28夏井高人(明治大学法学部)
「ネットワーク社会における法とカテゴリーの変容」
8.3長岡 昌(科学ジャーナリスト)
「科学技術と社会の調和」
99.1.11倉本昌昭((財)科学技術広報財団理事長)
「社会とコミュニケーションにおける科学技術への関心喚起と理解増進」
2.1金城清子(津田塾大学国際関係学科教授)
「体外受精の開いた道−生殖医療の未来を考える−」
2) 海外からの研究者による講演
98.4.10Larry N.Dumas(米国 Jet Propuldion Laboratory 副所長)
「ジェット推進研究所の研究運営について」
6.2崔 亨燮(Choi,Hyung-Sup)(韓国 科学技術連合会総連合会長)
「韓国新政権下での科学技術関連政策の展開について」
6.18Don E.Kash(米国 ジョ−ジメイソン大学教授)
「イノベーションの3類型−企業戦略と公共政策への示唆−
99.1.18Ben Martin(英国 サセックス大学科学技術政策ユニット長)
「英国のフォーサイトプログラムについて」
1.26 「科学技術政策研究の将来」
2.19Philip Shapia(米国 ジョージア工科大学助教授)
「米国における地域科学技術振興政策について」
3.2Van den Besselaar(蘭国 アムステルダム大学社会情報学部博士)
「EU 第4次及び5次フレームワークプログラムの概要及びプロジェクト概要の紹介」
3.8Josephine Anne Stein
(英国 マンチェスター大学工科科学技術政策研究所(PREST)博士)
「欧州と米国における科学アドバイザリ・システム民主化」
98.9.3Dr. Itzhak Wirth(STAフェロー特別研究員)
「研究開発マネージメントにおける戦略的選択肢:日本の医薬品産業における新製品開発の場合」
9.10佐野享子(第1調査研究グループ上席研究官)
「豊かな人間性の育成と教育制度の革新について〜教育改革プログラムのめざすもの〜」
9.15田村泰一(情報分析課長補佐)
「日本の技術輸出の実態(平成8年度)」
12.2Steven W.Collins(ワシントン大学教養学部助教授)
「日本の地域科学技術政策について」
99.1.26権田金治(第3調査研究グループ客員総括研究官)、中田哲也(第3調査研究グループ上席研究官)
「地域における科学技術振興に関する調査研究(第4回調査)」
2.16斉藤 均(第4調査研究グループ上席研究官)、新名秀章(第4調査研究グループ上席研究官)、寺尾 博(第4調査研究グループ特別研究員)
「2010年代の国民生活ニーズとこれに関連する科学技術」
2.17権田金治(第3調査研究グループ客員総括研究官)、柿崎文彦(第3調査研究グループ主任研究官)、休井正人(第3調査研究グループ特別研究員)
「我が国製造業の空間移動と地域産業の構造変化に関する研究」
2.18榊原清則(第1研究グループ総括主任研究官)、前田昇客員(第1研究グループ総括主任研究官)、近藤一徳(第1研究グループ特別研究員)
「日本のベンチャー企業」
2.19Philip Shapira(ジョージア工科大学助教授)
「米国における地域科学技術振興政策について」
2.25横尾淑子(第1調査研究グループ上席研究官)
「企業における女性研究者・技術者の就業状況に関する事例調査」
3.8Josephine Anne Stein(マンチェスター大学・工科科学技術政策研究所首席研究員)
「欧州と米国における科学アドバイザリ・システムの民主化」
3.31Sara B.Nerlove (NSF SBIR Manager)
「Small Business Innovation Research: A U.S Federal Program to Support Innovation-Based,High-Risk Research Leading to Commercialization.」
3.31George J.O’Neill(NSF SBIR Manager)
「State Government Support of Innovation at Small Enterprises.」
1. NISTEP REPORT(表題末尾の*は英語版があることを表す。)
<NO.1>「理工系学生の就職動向について」*
(第1調査研究グループ,1989.6)
<NO.2>「科学技術に対する社会の意識について」*
(第2調査研究グループ,1989.6)
<NO.3>「アジアのエネルギー消費構造の実態把握と地球環境に関する今後の課題について(中間報告)」(第4調査研究グループ,1989.7)
<NO.4>「地域における科学技術振興に関する基礎調査」
(第2研究グループ,1989.3)
<NO.5>「共同研究における参加企業に関する調査研究」*
(第3調査研究グループ,1989.8)
<NO.6>「科学技術連関モデルの理論的枠組み」
(第1研究グループ,1989.9)
<NO.7>「自然科学系博士号取得の量的日米比較」*
(第1調査研究グループ,1989.12)
<NO.8>「我が国の主要企業における『基礎研究』について」*
(第1調査研究グループ,1990.1)
<NO.9>「特許出願からみた研究開発の動向」
(第2研究グループ, 1990.3)
<NO.10>「表彰制度からみた我が国の科学技術動向」
(第2調査研究グループ,1990.3)
<NO.11>「地域における科学技術振興に関する基礎調査」
(第4調査研究グループ,1990.3)
<NO.12>「大学の進学希望者の進路選択について」*
(第1調査研究グループ,1990.8)
<NO.13>「バイオテクノロジーの開発利用とその影響に関する調査研究−バイオテクノロジーの実用化とその課題−」
(第4調査研究グループ,1990.9)
<NO.14>「研究開発のダイナミックス」*
(第1研究グループ,1990.9)
<NO.15>「企業(製造業)が『造る集団』から『考える集団』に」*
(第3調査研究グル−プ,1991.3)
<NO.16>「我が国と海外諸国間における研究技術者交流―統計データによる調査―」
(第2調査研究グループ,1991.3)
<NO.17>「科学技術に関する社会的コミュニケーションの在り方の研究」*
(第2調査研究グループ,1991.3)
<NO.18>「国際技術移転の進捗度の測定と分析に関する一考察」*
(第3調査研究グループ,1991.4)
<NO.19>「体系科学技術指標」*
(第2研究グループ,1991.9)
<NO.20>「国立試験研究機関と基礎研究」*
(第1調査研究グループ,1991.9)
<NO.21>「アジア地域のエネルギー消費構造と地球環境影響物質(SOX、NOX、CO2)排出量の動態分析」*
(第4調査研究グループ,1991.9)
<NO.22>「科学技術連関モデルの開発―数量評価と科学技術への含意―」
(第1研究グループ,1992.3)
<NO.23>「地域における科学技術振興に関する調査研究―都道府県及び政令指定都市の科学技術政策の現状と課題―」
(第4調査研究グループ・第2研究グループ,1992.8)
<NO.24>「青少年に向けた科学技術活動関連情報発信の新しいあり方−高校生の進路選択意識と科学技術観の分析から−」
(第1調査研究グループ,1992.10)
<NO.25>「第5回技術予測調査−我が国における技術発展の方向性に関する調査−」
(第2調査研究グループ,1992.11)
<NO.26>「国家科学技術プログラムの動学的分析(中間報告)−フレームワークの検討と予備的分析−」
(第1研究グループ,1993.1)
<NO.27>「アジア地域のエネルギー利用と地球環境影響物質(SOx、NOx、CO2)排出量の将来予測」*
(第4調査研究グループ,1993.3)
<NO.28>「我が国の大学における基礎研究−大学研究者による講演に基づく一考察−」
(第1調査研究グループ,1993.3)
<NO.29>「日本企業にみる戦略的研究開発マネジメント」*
(第2調査研究グループ・第2研究グループ,1993.7)
<NO.30>「女性研究者の現状に関する基礎調査」
(第1調査研究グループ,1993.7)
<NO.31>「R&D購買力平価の開発」*
(第3調査研究グループ,1994.3)
<NO.32>「地球環境問題における企業対応の現状と評価」
(第4調査研究グループ,1994.3)
<NO.33>「日独科学技術予測比較報告書」*英文のみ
(技術予測調査研究チーム,1994.4)
<NO.34>「科学技術が人間・社会に及ぼす影響に関する調査」
(第2調査研究グループ,1994.3)
<NO.35>「数値シミュレーションによる技術貿易継続契約の構造解析」
(第3調査研究グループ,1994.8)
<NO.36>「日本の技術輸出の実態(平成4年度)」
(第3調査研究グループ,1994.11)
<NO.37>「科学技術指標」−日本の科学技術活動の体系的分析−
(科学技術指標プロジェクトチーム,1995.1)
<NO.38>「サイエンス&テクノロジーパークの開発動向に関する調査研究」
(第2研究グループ,1995.2)
<NO.39>「地域における科学技術振興に関する調査研究(第2回調査)」
(第4調査研究グループ、第2研究グループ,1995.3)
<NO.40>「生活関連科学技術課題に関する意識調査(中間報告)」
(生活関連科学技術政策調査研究プロジェクト・チーム,1995.3)
<NO.41>「日本の技術輸出の実態(平成5年度)」
(第3調査研究グループ,1995.12)
<NO.42>「日独技術予測調査」
(技術予測調査研究チーム,1995.12)
<NO.43>「日本企業の海外における研究開発のパフォーマンスに関する調査」
(第2調査研究グループ,1996.2)
<NO.44>「女子の理工系専攻への進学における要因に関する調査研究」
(第1調査研究グループ,1996.3)
<NO.45>「生活関連科学技術課題に関する意識調査」
(生活関連科学技術政策調査研究プロジェクトチーム,1996.3)
<NO.46>「外国技術導入の動向分析(平成6年版)」
(情報分析課,1996.11)
<NO.47>「日本の技術輸出の実態(平成6年版)」
(第3調査研究グループ,1996.11)
<NO.48>「イノベーションの専有可能性と技術機会−サーベイデータによる日米比較研究−」
(第1研究グループ,1997.3)
<NO.49>「先端科学技術動向調査(物質・材料系科学技術)」
(情報分析課,1997.6)
<NO.50>「科学技術指標−日本の科学技術活動の体系的分析−」
(科学技術指標プロジェクトチーム,1997.5)
<NO.51>「地域科学技術指標策定に関する調査−地域技術革新のための科学技術資源計測の試み−」
(第3調査研究グループ,1997.3)
<NO.52>「第6回技術予測調査−わが国における技術発展の方向性に関する調査−」
(技術予測調査研究チーム,1997.6)
<NO.53>「日本の技術輸出の実態−平成7年度−」
(第3調査研究グループ,1997.7)
<NO.54>「外国技術導入の動向分析−平成7年度−」
(情報分析課,1997.11)
<NO.55>「研究開発投資の活発な企業が求める高学歴研究者・技術者のキャリアニーズに関する調査研究」
(第1調査研究グループ,1997.12)
<NO.56>「地域における科学技術振興に関する調査研究(第3回調査)」
(第3調査研究グループ,1997.12)
<NO.57>「外国技術導入の動向分析−平成8年度−」
(情報分析課,1998.5)
<NO.58>「日本の技術輸出の実態−平成8年度−」
(第3調査研究グループ,1998.9)
<NO.59>「地域における科学技術振興に関する調査研究(第4回調査)」
(第3調査研究グループ,1998.11)
<NO.60>「我が国製造業の空間移動と地域産業の構造変化に関する研究」
(第3調査研究グループ,1999.3)
<NO.61>「日本のベンチャー企業と起業者に関する調査研究−平成10年度」
(第1研究グループ,1999.3)
<NO.62>「2010年代の国民生活ニーズとこれに関連する科学技術」
(第4調査研究グループ,1999.3)
2. DISCUSSION PAPER
<NO.1>「技術知識の減衰モデルと減衰特性分析」
(第1研究グループ,1997.1)
<NO.2>「21世紀に向けた国の科学技術推進システムの在り方−国の科学技術活動の変革に向けて−」
(第2調査研究グループ,1997.5)
<NO.3>「日本と米国の科学及び工学における大学院課程の比較」
(第1研究グループ,1997.6)
<NO.4>「研究開発投資の決定要因:企業規模別分析」
(第1研究グループ,1997.11)
<NO.5>「マクロモデルによる政府研究開発投資の経済効果の計測」
(第1研究グループ,1998.3)
<NO.6>「大学などからの技術移転成功事例におけるアクター分析」
(第2研究グループ,1998.3)
<NO.7>「特許と文学論文の形態比較」〜記述形式・内容分析とインタビューによる執筆動因分析〜
(第2研究グループ,1998.10)
3. 調査研究資料(調査資料、調査資料・データ)
<NO.1>「ユーレカ計画の概要」
(第3調査研究グループ,1989.3)
<NO.2>「Outline of Science and Technology activities in Japan」
(第3調査研究グループ,1989.5)
<NO.3>「大学教官学位取得状況調べ(中間報告)」
(第2調査研究グループ,1989.12)
<NO.4>「日本の国家研究開発活動の変遷過程及びその特徴」
(尹文渉[韓国科学技術院科学技術政策研究評価センター],1990.3)
<NO.5>「東アジア諸国の科学技術政策について」
(第3調査研究グループ,1990.7)
<NO.6>「新材料の開発・利用とその影響に関する調査研究報告」
(第4調査研究グループ,1990.9)
<NO.7>「Enhancing Future Competitiveness ― The Japanese Government's Promotion of Basic Research―」
(ジャニス・M.・キャシディー特別研究員,1990.10)
<NO.8>「戦後日中科学技術発展状況比較研究」
(張 晶特別研究員,1991.1)
<NO.9>「太陽活動と地球温暖化―地磁気活動を指標として―」
(第4調査研究グループ,1991.3)
<NO.10>「科学技術政策史関連資料集」
(第1調査研究グループ,1991.3)
<NO.11>「日本の基礎研究についての考察」
(張晶特別研究員,1991.3)
<NO.12>「我が国と海外諸国間における研究技術者交流統計図表集」
(第2調査研究グループ,1991.3)
<NO.13>「Defining Basic Reserch in Japanese Companies & Science in Japanese Companies : A Preliminary Analysis」
(ダイアナ・ヒックス特別研究員,1991.9)
<NO.14>「先端科学技術情報モニタリングシステム中間報告」
(第2調査研究グループ,1991.9)
<NO.15>「科学技術政策用語英訳集」
(第1調査研究グループ,1991.10)
<NO.16>「外国技術導入の動向分析−平成2年度(1990年度)−」
(情報システム課,1991.11)
<NO.17>「ScienceandTechnologyPolicyinJapan」
(ピーター・スタール特別研究員,1992.2)
<NO.18>「Researchand Development Consortia and Cooperative Relationships in Japan's Superconductivity Industry」
(ジェラルド・ハネ特別研究員,1991.12)
<NO.19>「経験哲学から見た科学技術への取り組み」
(森本盛特別研究員,1992.1)
<NO.20>「自然科学系研究者のバックグラウンド及び活動状況に関する調査」
(第2調査研究グループ,1992.2)
<NO.21>「Strategy for Improving industrial Technological Bases」
(何翔皓特別研究員,1992.3)
<NO.22>「共体験に基づく知識創造の循環プロセス―高炉操業エキスパート・システムの開発事例をめぐって―」
(第1研究グループ,1992.9)
<NO.23>「広い空間と時間でとらえた科学技術とその政策目標」
(森本盛特別研究員,1992.9)
<NO.24>「自然科学系課程博士を増強する条件」
(第1調査研究グループ,1992.11)
<NO.25>「外国技術導入の動向分析―平成3年度(1991年度)―」
(情報システム課,1993.1)
<NO.26>「我が国の技術貿易統計―収支統計の定量的検討の試み―」
(第3調査研究グループ,1993.1)
<NO.27>「研究開発費の国際比較における購買力平価の利用について
(第3調査研究グループ,1992.12)
<NO.28>「工学部卒業生の進路と職業意識に関する日米比較」
(第1調査研究グループ,1992.12)
<NO.29>「科学技術史観の認識論的基礎―知識創造と日本の技術革新・研究序説―」
(第1研究グループ・第2研究グループ,1993.2)
<NO.30>「産業発展、地域開発及び地域政策形成の重要性の増大―日本における産業の普及及び発展の形態についての地域定量分析―」
(第4調査研究グループ,1993.2)
<NO.31>「技術開発の多角化に関する計量分析」
(第1研究グループ,1993.3)
<NO.32>「情報技術振興のための政府助成共同研究―日本の西欧への挑戦―」
(第1研究グループ,1993.3)
<NO.33>「日本製造業における競争力の源泉―素材関連技術を中心とした一考察―」
(第1研究グループ,1993.6)
<NO.34>「日本企業における知の創造:競争優位の次元」
(第1研究グループ,1993.9)
<NO.35>「日本における政府研究機関」
(第1調査研究グループ,1993.10)
<NO.36>「製品開発段階における技術知識の動態―『研究開発における知の構造と知の動態(1)』中間報告―」
(第1研究グループ,1994.3)
<NO.37>「外国技術導入の動向分析―平成4年度―」
(情報システム課,1994.3)
<NO.38>「優れた研究者が備える条件と研究活動の特性−長官賞受賞者の特性を探る−」
(第2調査研究グループ,1994.6)
<NO.39>「外国技術導入の動向分析―平成5年度―」
(情報分析課,1995.3)
<NO.40>「韓国の電子産業における対日依存と今後の課題」
(第3調査研究グループ,1995.4)
<NO.41>「東南アジアの日系企業の活動状況」
(第3調査研究グループ,1995.6)
<NO.42>「数値解析による技術貿易契約期間の推定」
(第3調査研究グループ,1995.6)
<NO.43>「契約期間から技術貿易の構造を解析する」
(第3調査研究グループ,1996.3)
<NO.44>「技術進歩と経済成長」
(第1研究グループ,1996.8)
<NO.45>「パーソナルコンピュータの技術移転に関する調査研究」
(第2調査研究グループ,1996.12)
以下「調査資料・データ」と変更
<NO.46>「自然科学系博士課程在学生数に関する調査分析」
(第1調査研究グループ,1997.1)
<NO.47>「2010年科学技術人材を考える」
(第1調査研究グループ,1997.2)
<NO.48>「韓・日両国における科学技術諮問・審議機構の比較」
(第3調査研究グループ,1997.5)
<NO.49>「日本企業とフランス企業の研究開発マネジメントに関する比較調査研究」
(第2調査研究グループ,1997.5)
<NO.50>「日中の技術移転に関する調査研究」
(情報分析課、第3調査研究グループ,1997.6)
<NO.51>「東アジア諸国のエネルギー消費と大気汚染対策−概況と事例研究−」
(第4調査研究グループ,1997.6)
<NO.52>「地域科学技術政策の現状と課題−地域科学技術政策研究会報告書−」
(第3調査研究グループ,1997.10)
<NO.53>「大学における新構想型学部に関する実態調査」
(第1調査研究グループ,1998.4)
<NO.54>「英国における研究評価−公的研究助成にみる評価"ValueforMoney"と"Selectivity"」
(第2研究グループ,1998.5)
<NO.55>「主要各国の科学技術関連組織の国際比較」
(第1研究グループ,1998.6)
<NO.56>「地域科学技術政策研究会(平成10年2月24、25日)報告書−地域特性を生かした施策展開をどう進めるか−」
(第3調査研究グループ,1998.7)
<NO.57>「英国及びニュージーランドにおける国立試験研究機関の民営化について」
(企画課,1998.6)
<NO.58>「テクノポリス調査研究報告書」
(第3調査研究グループ,1998.8)
<NO.60>「企業における女性研究者・技術者の就業状況に関する事例調査」
(第1調査研究グループ,1999.3)
4. 調査研究資料(講演録)
1)竹内 啓 東京大学先端科学技術研究センター教授
「先端科学技術の社会的影響<動向第1回>」(1988.10)
2)石井 恂 麻布大学教養部教授
「1990年代の科学技術政策<動向第2回>」(1988.10)
3)Prof.Don E Kash米国オクラホマ大学教授
「総合化社会<国際比較第1回>」(1988.11)
4)内田盛也 帝人株式会社理事
「科学技術政策と知的所有権のかかわりについて<動向第3回>」(1988.12)
5)西部 邁 評論家
「反原発運動における技術思想について<動向第4回>」(1988.12)
6)平澤 東京大学教養学部教授
「ソフト化社会における政策研究<動向第5回>」(1988.12)
7)Prof.Christopher Freeman英国サセックス大学名誉教授
「産業技術における基礎研究の役割<国際比較第2回>」(1989.2)
8)石坂誠一 人事院人事官
「科学技術に関する人材の確保<動向第6回>」(1989.2)
9)梅原 猛 国際日本文化研究センター所長
「日本人の自然観<動向第7回>」(1989.2)
10)Prof.Lewis M .Branscomb 米国ハーバード大学教授
「米国における科学技術の諸問題<国際比較第3回>」(1989.2)
11)武者小路公秀 国連大学副学長
「国際化社会における知的交流の課題<動向第8回>」(1989.2)
12)弘岡正明 住友化学工業株式会社研究主幹
「新化学時代の産業展開と諸問題<動向第9回>」(1989.3)
13)青木昌彦 京都大学経済研究所教授
「今後の経済発展と科学技術政策<動向第10回>」(1989.3)
14)井内慶次郎 前国立教育会館長
「大学院制度の弾力化について<動向第11回>」(1989.3)
15)立川圓造 日本原子力研究所東海研究所化学部長
「電解核融合の現状<動向第12回>」(1989.4)
16)軽部征夫 東京大学先端科学技術研究センター教授
「バイオセンサーの現状と将来<動向第13回>」(1989.5)
17)加藤秀俊 放送教育開発センター所長
「国際社会における技術格差の問題点<動向第14回>」(1989.5)
18)村上陽一郎 東京大学先端科学技術研究センター教授
「明治期における我が国の科学技術政策」(1989.6)
19)田村 明 法政大学法学部教授
「未来の都市をめざして」(1989.3)
20)米本昌平 三菱化成生命科学研究所社会生命科学研究室長
「1970年代のアメリカにおけるバイオエシックス論争」(1989.6)
21)後藤 晃 一橋大学教授
「日本のR&Dシステム再考」(1989.12)
22)野田正彰 神戸市立外国語大学教授
「社会の変化が個人に及ぼす影響について」(1989.9)
23)Heinz A.Staab西独マックス・プランク協会理事長
「西独マックス・プランク協会の組織と国際協力における役割」(1990.3)
24)Prof.Rolf D. Schmidドイツ国ブラウンシュバイク工科大学教授
「統合後のドイツのバイオテクノロジー戦略について」(1990.11)
25)権田金治 東京電機大学理工学部教授
「科学技術と地域開発」(1991.4)
26)小林信一 文教大学国際学部専任講師
「文明社会の野蛮人―若者の科学技術離れを巡って―」(1991.5)
27)小山内裕 藤倉電線株式会社取締役研究開発本部副本部長
「光ファイバーの開発―低損失限界への挑戦―」(1992.4)
28)渕 一博 (財)新世代コンピュータ技術開発機構常務理事研究所長
「第五世代コンピュータの開発―未完の革命―」(1992.5)
29)外村 彰 日立製作所基礎研究所主管研究長
「電子線ホログラフィー開発の経緯」(1992.6)
30)鈴木章夫 三菱重工業株式会社名古屋航空宇宙システム製作所宇宙技術部長
「日本のロケット開発に於ける技術革新」(1992.7)
31)蒲谷勝治 ヤマハ発動機株式会社マリン事業本部船艇事業本部副事業部長
永海義博 ヤマハ発動機株式会社マリン事業本部技術部実験課主任
「アメリカズカップ・ヨットの開発とレース戦略」(1992.8)
32)伊藤博之 本田技研工業株式会社参事
「ホンダ・シビックの開発」(1992.2)
33)神田泰典 富士通株式会社パーソナルビジネス本部副本部長
「マルチメディアとFMタウンズ」(1992.9)
34)王寺睦満 新日本製鐵株式会社技術開発本部設備技術センター所長
「我が国におけるLD転炉技術の導入と発展」(1992.10)
35)相沢 進 セイコーエプソン株式会社専務取締役
「セイコーエプソンにおける技術開発―新事業創造の事例と事業開発理念の功罪―」(1992.11)
36)森本 盛 客員研究員
「科学技術意識形成過程の分析」(1993.3)
37)前川善一郎 京都工芸繊維大学教授
「複合材料技術の社会への浸透過程について」(1992.12)
38)白石忠志 東北大学法学部助教授
「技術の排他的利用と独占禁止法」(1993.2)
39)柳原一夫 客員研究官
「地球温暖化のメカニズム(宇宙・太陽・地球)」(1993.5)
40)富田徹男 特許庁審判部審判官
「特許制度などから見た技術の伝播」(1993.4)
41)前間孝則 国際技術総合研究所副所長
「軍用技術から民生技術へ−戦前日本の航空機産業の転換−」(1993.4)
42)石井 裕 NTTヒューマンインタフェース研究所主幹研究員
「コラボレーションメディアのデザイン」(1992.12)
43)長谷川龍雄 元トヨタ自動車株式会社専務取締役
「日本における自動車技術の起こりと展開−私の体験−」(1993.8)
44)吉田庄一郎 株式会社ニコン取締役副社長
「半導体製造装置ステッパの開発」(1993.9)
45)佐藤秀樹 株式会社セガ・エンタープライゼス常務取締役
「アミューズメントからマルチメディアの研究開発へ」(1994.2)
46)市川惇信 人事院人事官
「研究評価について」(1996.11)
47)河本英夫 東洋大学教授
「オートポイエーシスにもとづく研究評価論」(1996.12)
48)森 俊介 東京理科大学教授
「システム論から見た評価の方法」(1997.1)
49)木嶋恭一 東京工業大学
「評価へのソフトシステムアプローチ」(1997.1)
50)山之内昭夫 大東文化大学教授
「企業における研究評価の視点」(1997.2)
51)川崎雅弘 科学技術振興事業団
「科学技術基本法下における評価」(1997.4)
52)板倉省吾 (株)パスコ
「通商産業省の政策評価(産業政策と産業技術政策)」(1997.4)
53)Dir. Rosalie T. Ruegg米国国立標準・技術研究所経済性評価室長
Prof. Philipe Laredo仏国鉱山大学イノベーション社会学センター教授
「科学技術の形成過程における評価をどう取り扱うか−研究評価から政策評価まで−」(1997.11)
54)Dr. William A. Blanpied U S National Science Foundation
「米国における科学政策について」(1997.11)
55)近藤隆雄 多摩大学経営情報学部教授
「サービスマネージメントにおける価値づくりについて」(1997.5)
伊藤利朗三 菱電機(株)専務取締役開発部長
「製品開発における価値づくりについて」(1997.5)
朝岡勝義(株)東芝情報・通信システム新規事業企画室担当部長
「経営におけるコンセプトエンジニアリングについて」
56)Dr. William G. Wells, Jr. The George Washington University School of Business and Public Management Project Management Program Director
「米国連邦政府における科学技術政策形成」(1998.3)
57)崔 亨燮 韓国科学技術団体総連合会会長
「韓国新政権下での科学技術関連政策の展開」(1998.6)
58)prof. Arie Rip University of Twente.the Netherlands
「オランダの科学技術政策:行政と研究を結ぶ中間構を中心として〜「社会学的」科学技術政策研究序論〜
5.その他
1)ソフト系科学技術に関する調査報告書
(第1調査研究グループ,1989.3)
2)第1回科学技術政策研究国際コンファレンス予稿集[英文](1990.2)
3)日本の科学技術政策史
(科学技術政策史研究会編集、科学技術政策研究所監修,1990.12)
4)NISTEP Review Vol.1[脚注](1990.12)
5)第1回科学技術政策研究国際コンファレンスプロシーディングス[英文]
(猪瀬 博、児玉文雄、川崎雅弘編集,1991.1)
6)第2回科学技術政策研究国際コンファレンス予稿集[英文](1991.1)
7)NISTEP Review Vol.2[脚注](1992.3)
8)第2回科学技術政策研究国際コンファレンスプロシーディングス[英文]
(岡村総吾、野中郁次郎、村上健一編集,1992.3)
9)第3回科学技術政策研究国際コンファレンス予稿集[英文](1992.3)
10)日・米・欧における科学技術に対する社会意識に関する比較調査
(第2調査研究グループ,1992.3)
11)第3回科学技術政策研究国際コンファレンスプロシーディングス[英文]
(岡村総吾、坂内富士男、野中郁次郎編集,1993.3)
(注) NISTEP Reviewは、当所の研究者が外部の研究集会や学会誌等で発表した研究論文を当研究所として取りまとめたものである。
(2)顧 問(五十音順)
猪 瀬 博 学術情報センター所長
植之原道行 日本電気(株)特別顧問
岡村 總吾 東京電機大学名誉学長
川崎 雅弘 科学技術振興財団常務理事
佐波 正一 (株)東芝相談役
中原 恒雄 住友電気工業(株)副会長
林 雄二郎 (財)未来工学研究所副理事長
藤井 直樹 (株)サンシャインシティ社長
牧 野 昇 (株)三菱総合研究所取締役相談役
向 坊 隆 日本原子力産業会議会長
吉 川 弘之 日本学術会議会長
吉 村 融 政策研究大学院大学長
| 所 属 | 職 名 | 氏 名 | 在 職 期 間 | |
| 所長 | 所長 | 佐藤 征夫 | H9.7.1〜 | |
| 総務研究官 | 総務研究官 | 國谷 実 | H9.10.10〜 | |
| 所 | 併 | 丹羽冨士雄 | H3.10.1〜H10.4.30 | |
| 総務課 | 課長 | 安藤 忠志 | H9.4.1〜 | |
| 課長補佐 | 併 | 飯山 泰之 | H8.7.1〜H10.5.1 | |
| 課長補佐 | 併 | 太田 政孝 | H10.5.1〜 | |
| 庶務係長 | 多田 敏行 | H10.4.1〜 | ||
| 主任 | 五島登美子 | H4.1.1〜 | ||
| 吉沢 道子 | S63.7.1〜 | |||
| 冥加 暁弘 | H8.5.1〜H10.4.9 | |||
| 細貝 智之 | H10.4.9〜 | |||
| 併 | 吉武ミツエ | H10.4.1〜 | ||
| 経理係長 | 林 淳 | H9.4.1〜 | ||
| 秋田のぞみ | H6.1.1〜 | |||
| 用度係長 | 併 | 飯山 泰之 | H10.4.1〜H10.5.1 | |
| 用度係長 | 併 | 太田 政孝 | H10.5.1〜 | |
| 自動車運転手 | 巣山 忠浩 | H8.4.1〜H10.6.30 | ||
| 自動車運転手 | 井口 直孝 | H10.6.30〜 | ||
| 事務補助員 | 美濃部友理子 | H10.10.1〜 | ||
| 企画課 | 課長 | 根本 光宏 | H8.6.26〜H10.6.30 | |
| 課長 | 植田 昭彦 | H10.6.30〜 | ||
| 課長補佐 | 小野 秀明 | H9.7.16〜 | ||
| 国際研究協力官 | 山口 治 | H7.11.1〜 | ||
| 企画係長 | 併 | 小野 秀明 | H10.4.1〜 | |
| 井山 哲 | H10.4.1〜 | |||
| 業務係長 | 宮本 祐吾 | H9.1.1〜 | ||
| 神田由美子 | H10.2.1〜 | |||
| 事務補助員 | 鈴木恵理子 | S61.12.25〜 | ||
| 情報分析課 | 課長 | 吉水 正義 | H9.7.16〜 | |
| 課長補佐 | 田村 泰一 | H8.10.1〜H11.3.10 | ||
| 課長補佐 | 併 | 吉水 正義 | H11.3.10〜 | |
| 情報係長 | 併 | 山口 治 | H7.11.1〜 | |
| 資料係長 | 併 | 山口 治 | H9.4.1〜 | |
| 分析第1係長 | 石黒 裕康 | H9.7.1〜 | ||
| 分析第2係長 | 併 | 山口 治 | H7.11.1〜 | |
| 調査官 | 併 | 佐々木 学 | H8.11.1〜H11.3.31 | |
| 調査官 | 下村 智子 | H10.11.16〜 | ||
| 併 | 衛藤 康子 | H8.11.11〜 | ||
| 併 | 吉沢 道子 | H10.4.1〜 | ||
| 技術補助員 | 久野美津子 | H10.4.1〜 | ||
| 事務補助員 | 川口 幸子 | H8.7.16〜H10.7.16 | ||
| 事務補助員 | 清水亜矢子 | H10.7.15〜 | ||
| 事務補助員 | 大柳 康司 | H11.3.2〜H11.3.31 | ||
| 第1研究グループ | 総括主任研究官 | 榊原 清則 | H10.4.1〜 | |
| 主任研究官 | 瀬谷 道夫 | H6.6.16〜 | ||
| 研究員 | 古賀 款久 | H9.4.1〜 | ||
| 研究員 | 伊地知寛博 | H10.5.1〜 | ||
| 芳賀沼聡子 | H8.5.1〜 | |||
| 併 | 田中 茂 | H10.4.1〜 | ||
| 事務補助員 | 下田眞奈美 | H6.4.2〜 | ||
| 第2研究グループ | 総括主任研究官 | 平澤 冷 | H9.10.1〜 | |
| 主任研究官 | 柿崎 文彦 | S63.7.1〜 | ||
| 主任研究官 | 富澤 宏之 | H8.10.1〜 | ||
| 主任研究官 | 藤垣 裕子 | H8.10.1〜 | ||
| 併舘 和夫 | H9.7.14〜H10.6.15 | |||
| 併 | 武内 信雄 | H10.6.16〜 | ||
| 併 | 渡部 康一 | H9.7.1〜 | ||
| 事務補助員 | 宇井 幸子 | H9.10.14〜H10.7.11 | ||
| 事務補助員 | 中澤 真弓 | H10.7.21〜 | ||
| 第1調査研究グループ | 総括上席研究官 | 前澤 祐一 | H8.5.10〜 | |
| 上席研究官 | 和田 幸男 | H9.7.1〜 | ||
| 上席研究官 | 舘 和夫 | H8.6.1〜H10.6.15 | ||
| 上席研究官 | 武内 信雄 | H10.6.16〜 | ||
| 上席研究官 | 併 | 佐野 享子 | H10.7.21〜 | |
| 研究官 | 横尾 淑子 | H10.5.1〜 | ||
| 吉田 道治 | H8.5.1〜H10.4.30 | |||
| 併 | 横尾 淑子 | H4.8.17〜H10.5.1 | ||
| 事務補助員 | 大貫佐知子 | H5.7.1〜 | ||
| 第2調査研究グループ | 総括上席研究官 | 事務取扱 | 國谷 実 | H9.10.10〜 |
| 上席研究官 | 木場 隆夫 | H7.7.17〜 | ||
| 上席研究官 | 大山 真未 | H9.4.1〜 | ||
| 研究官 | 渡部 康一 | H9.7.1〜 | ||
| 研究官 | 下村 智子 | H10.1.11〜H10.11.16 | ||
| 事務補助員 | 併 | 大貫佐知子 | H9.7.25〜 | |
| 第3調査研究グループ | 総括上席研究官 | 渡辺 俊彦 | H9.7.16〜 | |
| 上席研究官 | 中田 哲也 | H10.4.1〜 | ||
| 上席研究官 | 飯山 泰之 | H8.7.1〜H10.5.1 | ||
| 上席研究官 | 太田 政孝 | H10.5.1〜 | ||
| 研究官 | 横尾 淑子 | H5.10.1〜H10.5.1 | ||
| 併 | 柿崎 文彦 | H9.7.16〜 | ||
| 事務補助員 | 三島 眞理 | H7.4.10〜 | ||
| 第4調査研究グループ | 総括上席研究官 | 桑原 輝隆 | H9.7.1〜 | |
| 上席研究官 | 佐々木 学 | H1.1.25〜H11.3.31 | ||
| 上席研究官 | 齋藤 均 | H9.4.1〜H11.3.31 | ||
| 上席研究官 | 田中 茂 | H10.4.1〜 | ||
| 上席研究官 | 新名 秀章 | H10.4.1〜 | ||
| 併 | 瀬谷 道夫 | H9.7.16〜 | ||
| 事務補助員 | 綱嶋美波子 | H10.5.1〜H10.9.30 | ||
| 事務補助員 | 楠瀬 文子 | H10.10.1〜H11.1.31 | ||
| 事務補助員 | 早坂 ルミ | H10.10.28〜 |
1) 科学技術特別研究員
綾野博之科学技術振興事業団
加藤みどり科学技術振興事業団
2) 特別研究員
国内関係機関等より
古閑知明社団法人海外電力調査会研究員(九州電力)
田中清隆社団法人海外電力調査会研究員(九州電力)
田中 聡社団法人海外電力調査会研究員(中部電力)
伊藤晃輔社団法人海外電力調査会研究員(関西電力)
樟 良治東京電力株式会社
数田章司東京電力株式会社
新井英彦日本原子力研究所高崎研究所
寺尾 博日本電気株式会社
藤原直也株式会社神戸製鋼所
田中誠徳三重県
須藤剛志三菱電機株式会社
休井正人日本鋼管株式会社
近藤一徳(株)シー・エー・シー
3) 客員研究官(五十音順)
青島矢一一橋大学商学部専任講師
亀岡秋男(株)東芝研究開発センター特別研究室技監
香月祥太郎三井情報開発(株)顧問
後藤 晃一橋大学イノベーション研究センター教授
権田金治東海大学教授(国際政策科学研究センター長)
清家彰敏富山大学経済学部助教授
寺本義也北陸先端科学技術大学院大学教授
永田晃也北陸先端科学技術大学院大学助教授
丹羽冨士雄政策研究大学院大学教授
原田 勉神戸大学経営学部助教授
平野千博岩手県立大学総合政策学部教授
深尾京司一橋大学経済研究所助教授
前田 昇ソニー(株)カードシステム事業室長
宮林正恭理化学研究所理事
和田哲夫郵政省郵政研究所主任研究官
1947年12月 経済安定本部資源委員会事務局設置
1949年 6月 (資源委員会は資源調査会へ改称)
1952年 8月 (資源調査会は総理府の附属機関へ)
1956年 5月 科学技術庁設置
資源調査会事務局は科学技術庁資源局となる。
(資源調査会は科学技術庁の附属機関へ)
1968年 6月 資源調査所設置(科学技術庁資源局廃止)
1988年 7月 科学技術政策研究所設置(資源調査所改組)
科学技術庁科学技術政策研究所
広報委員会
委員長國谷 実
委 員田中 茂
藤垣 裕子
佐野 享子
伊藤 晃輔
新舩 洋一
岡本 信司
太田 政孝
植田 昭彦
吉水 正義
宮本 祐吾
事務局企画課
情報分析課
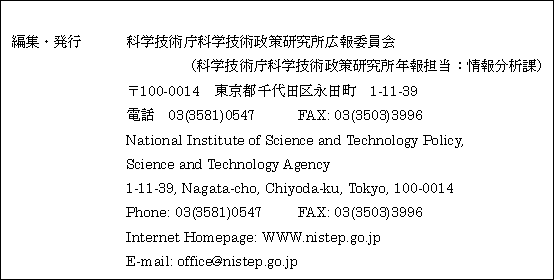
National Institute
Of
Science
And
Technology Policy
科学技術政策研究所