
 |
No.98 NOV/DEC 1996 | |
| 科学技術庁科学技術政策研究所 | ||
| NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE | ||
| AND TECHNOLOGY POLICY |
| 目次 [Contents] |  講演会紹介 Highlight of the Lectures at NISTEP 講演会紹介 Highlight of the Lectures at NISTEP |
 研究会 Research Meeting 研究会 Research Meeting | |
 最近の動き Current Topics 最近の動き Current Topics |
政策研においては、より広範囲な科学技術政策研究に資するため、外部の講師を招いて講演をお願いしているところである。本稿では、「科学技術の形成過程における評価に関する研究」の一環として、人事院の市川人事官にお願いし、先日行われた講演の概要を紹介する。同氏は東京工業大学工学部教授、同大学院総合理工学研究科長、国立環境研究所長を経て、現職に就かれている。
Ⅰ.講演会紹介/Highlight of the Lectures at NISTEP
人事院人事官 市川 惇信
1.評価について
我が国には研究評価に関して3つの神話がみられるが、これを否定することから始めたい。まず、「我が国には研究評価がない」であるが、評価はすべての活動の基本構造である計画・実行・評価サイクルの構成要素であり、すべての活動に普遍的に存在する。評価が”ある”か”ない”かではなく、評価が”明示的”か”暗黙的”かである。したがって、我が国にも研究評価はある。次に、「評価は客観的でなければならない」であるが、評価は評価主体による主観的評価があるだけで客観的評価は存在しない。明示的評価システムは評価主体の主観の表明である。最後に、評価は「公平公正でなければならない」であるが、評価は明示された評価システムの下でのみ公平公正である。

意思決定主体と評価システムの関係において、評価システムが意思決定主体から分離され評価対象に明示されているのが「明示的評価」であり、意思決定主体と評価システムが分離していないか、あるいは内部的には分離していても外部からそれが見えないのが「暗黙的評価」である。評価規範(何をもって「よし」とするか)を意思決定主体により定められるものが「内部評価」であり、外部から定められるものが「外部評価」である。ここでいう”内部”、”外部”はいわゆる評点者が内部か外部かによるものではない。
明示的評価は暗黙的評価に比較して、次のような特性がある。
評価システムは評価主体(内部評価においては意思決定主体と同一、外部評価においては意思決定主体と異なる)、評価対象、評価目的(評価規範を評価システムに機能分解できる範囲で記述したもの)、評価時期、評価方法(評価過程の具体的手続き)の4W1Hで構成される。評価システムを設計するとはこれら4W1Hを定めることである。評価システムにおける評価方法とは、評価対象を属性で構成される多次元空間から評価項目軸で構成される多次元の評価空間に位置づけた上で、さらに意思決定空間に位置づける変換過程である(図表1参照)。前者の変換過程はできるだけ普遍的かつ客観的に行い、主観の導入は後者の変換過程である評価空間から一次元の評価尺度への変換に限定するのが望ましい。また、最後の評価尺度への変換にあたっては属性空間、あるいは評価空間に位置づけた評価対象の並び方を十分に分析する必要がある。
明示的評価に対する不安の中で大きなものは、それが暗黙的評価との相関が良くないのではないかとの懸念である。これは明示的評価システムの設計に対する懸念に他ならない。このため、明示的評価結果は適時暗黙的評価結果と照合してチェックされるべきである。
2.研究評価に関する幾つかのこと
評価の4W1Hは対象、研究分野ごとに異なるので、それぞれに適した評価システムを一品生産する必要がある。また、芸術や哲学のように評価システムを持ち込まない方が良いと思われる分野も有り得る。
評価尺度は入力指標、状態指標、出力指標に区分されるが、できるだけ出力指標に着目するのが良い。入力あるいは状態を考えるのは評価対象がなすべきことである。
評価は階層構造になっているから、上位の評価主体の評価規範に連動して、評価対象がより下位の評価対象を評価するシステムを作る。
ブレークスルーを生み出そうとする研究組織では、研究者又は研究グループの評価システムにおける評価空間への位置づけは外部データ(論文数、引用数、学会賞の数、等)を用いるのが適当である。内部データを用いると研究者相互間の刺激的な交流を阻害する恐れがある。研究費配分などはゼロサムゲームとなり、パイの分捕り合戦になる。
評価データ間には通常強い相関があるが、だからと言って、そのうちの一つのみを選定すると評価対象の行動がそれに応じて変化し、評価目的に合致しなくなる恐れがある。
研究組織、研究者の処遇を決定する場合を除いて、評価対象全体を評価することは意味がなく、特に良いものと悪いものを同定し、それに対して処置すれば良いことが多い。
3.研究組織の共同体化と老齢化
テニース以来の組織論によれば、組織は「共同体」と「機能体」に分類される。共同体とは組織自体及びその構成員の生き残りと安寧を目標とする組織である。機能体とは規定された目標を達成するよう機能分解が行われ、分解された機能を実現する要素からなる組織をいう。現実の組織は共同体と機能体を極限形とする中間形として表現できるとされてきた。しかし、研究組織をこれで表現しようとすると、多くの点で問題を生じる。例えば、構成員の可視性を考える。図表2に示すように共同体においては構成員は見えなくてよい。機能体においても、ある機能を実現するポストには一定以上の能力がある限り誰でもよい。誰であっても組織全体として目標が達成されるよう、部分の機能が設計されているからである。しかし、研究組織では「何某がいる」ことがその研究組織の認知につながる。このことは組織に第三の型が存在することを意味する。これを「進化体」と呼ぶ。この第三の型を含めて考えれば、現実の組織は極限形である共同体、機能体及び進化体が作る三角形の内部の点として表現される。
我が国の国公立研究機関においては、本来進化体であるべき研究組織が共同体化する例が見られる。すなわち、研究組織は研究成果をあげるための組織にもかかわらず、それを構成する研究者の生き残りと安寧のための組織と化することが多い。
共同体化の指標として次のことがあげられる。
ソ連のノーベル物理学者ピョートル・カピッツァは、物理工学研究所50周年の記念講演で研究組織の老齢化として次の症状をあげた。
老齢化及び共同体化は、劇症急性の症状ではない。研究組織が健康体ではあるが何となく元気がなくなるという形で現れてくる。組織にこのような症状の兆候がないかどうか、管理者は常に注意しなければならない。一旦老齢化し共同体化した研究組織が自己努力により回復することは極めて難しい。内部規範からすれば何の問題もないからである。これを自覚させるためには、外部の規範による評価を受けることが必要になる。
今、我が国に緊急に必要なものは研究組織を評価するシステムである。
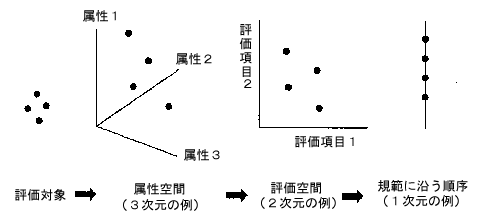
| 組織属性 | 共同体 | 機能体 | 進化体 |
| 組織目的 | 構成員の心地良さ | 規定された特定目的 | システムの進化 |
| 運営原理 | 公平・平等 | 最小費用で最大達成 | 進化への最大貢献 |
| 組織評価 | 結束力 | 目的達成能力・実績 | 貢献能力・実績 |
| 組織構造 | 単層 | 階層 | アドホックネットワーク |
| 構成員評価 | 内部評価:安定基準 | 内部評価:達成基準 | 外部評価・貢献度 |
| 構成員可視性 | 見えない:交替不要 | 見えない:交替可能 | 構成員により組織が可視 |
| 情報配分 | 公平・平等 | 構造に沿ったルートで | 相互触発 |
| 組織例 | 家族、地域社会、学会 | 企業、行政組織、軍隊 | 研究組織、設計事務所 |
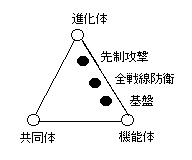
第3調査研究グループ
地域における科学技術の振興は経済活動のグローバリゼーションの進展とともに近年ますます重要性を増している。特に、我が国においては地域における産業の空洞化が加速される中で、域内経済開発のための施策の展開が緊急の課題となってきたが、そのための有効な政策手段は地方公共団体においてのみならず、国においても見いだされていない。
「地域における科学技術活動の活性化に関する基本指針」(科学技術会議第22号答申)にも示されているように、域内経済開発の有効な手段の一つが科学技術資源の活用による技術革新(リージョナル・イノベーション)の推進である。
しかし、科学技術資源の空間的集積は地域によって極端に異なっているという現状認識はあるものの、地域における科学技術資源に関する定量的な現状把握が十分でなく、地域科学技術指標として位置づけられるべき事項についての理論も明らかになっていない。
このため、平成8年度科学技術振興調整費によるソフト調査として「地域科学技術指標の策定に関する調査」がなされることとなり、地域科学技術資源の域内経済開発のための潜在的可能性を計測するに必要十分な地域科学技術指標の理論的基礎に関する調査及び地域科学技術指標策定のための検討がなされることとなった。
この調査の一環として、科学技術政策研究所において地域科学技術資源の調査方法、地域科学技術指標の理論的基礎並びに開発の手法に関する研究を行うこととなり、このため、専門家等による「地域科学技術指標研究会」を設置し、専門的意見をいただいている。
研究会は、権田金治客員研究官(東海大学教授)を座長とし、専門家、地方自治体職員、科学技術政策研究所職員等10名で構成されている。研究会は、10月に第1回会合を開催した後、月1回の頻度で開催されており、平成9年3月までにひととおりのとりまとめを行うこととしている。
(地域科学技術指標研究会メンバー)
| 座 長 | 権田 金治 | 科学技術政策研究所客員研究官(東海大学教授) |
| 副座長 | 添嶋 一 | 科学技術政策研究所第3調査研究グループ総括上席研究官 |
| メンバー | 森 俊介 | 東京理科大学教授 |
| 〃 | 中山 健 | 千葉短期大学助教授 |
| 〃 | 調 麻佐志 | 信州大学講師 |
| 〃 | 加藤 勝敏 | (財)日本立地センター立地総合研究所主任研究員 |
| 〃 | 植田 秀史 | 神奈川県企画部科学技術政策室長 |
| 〃 | 平田 泰宏 | 岐阜県総務部政策審議監 |
| 〃 | 横田 慎二 | (財)未来工学研究所主任研究員 |
| 〃 | 坂田 和徳 | 科学技術政策研究所第3調査研究グループ上席研究官 |
○ 研究会等/Research Meetings ・10/24(木) 第1回地域科学技術指標研究会 ・10/31(木) 第1回技術予測委員会 ・11/14(木) 第2回地域科学技術指標研究会 ○ 講演会等/Lectures at NISTEP ・11/6(水) 「研究評価」について 市川惇信 (人事院人事官・東京工業大学名誉教授) ○ 主要来訪者一覧/Foreign Visitors to NISTEP ・10/11 趙 盛豹( Cho Seong-Pyo ) (韓国 慶北国立大学助教授) ・10/19〜11/27 Miss Viola Peter (ドイツ フラウンフォーファー協会技術革新研究所研究員) ・10/25 趙 泰燮( Joe Tai-Surp ) (韓国 科学技術処技術協力局技術協力二課) ・10/28 Herbert J.Allegeir (EU 未来技術学研究所長) ・10/28 具 本興( Ku Bon-heung ) *韓国日本地自体科学技術研究団として来日 ・10/31 張 家生 ほか4名 (資訊応用発展協会理事) *台湾日本シンクタンク考察研究団として来日 ・11/13 Wasiak Waciaw ほか3名 (ポーランド 情報処理センター長) ・11/26 李 憲圭( Lee Hun-Gyu ) (韓国 科学技術政策管理研究所科学技術処派遣研究官) 金 東源( Kim Dong-Won ) (韓国 科学技術院教養課程部助教授) ○ 海外出張 ・10/5〜10/15 陸第2研究グループ特別研究員(香港) ・10/14〜10/26 平澤第2研究グループ総括主任研究官(欧州) ・11/4〜11/11 後藤第1研究グループ総括主任研究官(米国、カナダ) ・11/7〜11/11 永田第1研究グループ主任研究官(米国) ・11/30〜12/16 根本企画課長(米国)