
 |
No.96 SEP 1996 | |
| 科学技術庁科学技術政策研究所 | ||
| NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE | ||
| AND TECHNOLOGY POLICY |
| 目次 [Contents] |  研究ノート Research Note 研究ノート Research Note
|
 国際会議報告 International Conference 国際会議報告 International Conference
| |
 最近の動き Current Topics 最近の動き Current Topics
|
政策研では積極的に外国人研究者を受け入れているが、本稿では先月号に続き、STAフェローにより米国オレゴン大学から来日し、本年6月から8月まで第1研究グループ特別研究員として在籍したサミュエル・コールマン氏の研究成果の概要を紹介することとしたい。同氏はノース・カロライナ州立大学日本センター副所長、ノース・ウェスタン・リザーブ大学人類学科助教授を経て、現在オレゴン大学人類学科助教授である。
第1研究グループ サミュエル・コールマン
日本における生命科学研究の将来は玉虫色である。生命科学研究は多大な可能性を秘めるが、同時に、月並みに終わってしまう恐れもある。日本は世界でも有数の科学者を産み出し、また過去15年間の国際的研究出版物は量、質共に飛躍を遂げている。その一方、生命科学分野における国際的出版物の絶対的数量、及びインパクトは、例えば応用物理学などの分野にははるかに及ばない。また、日本人生命科学者達自身も、西洋の実績との比較において日本の研究成果を高く評価してはいない。
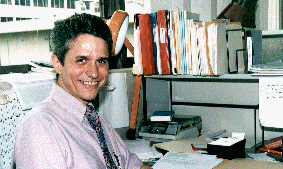
第一研究グループ 特別研究員 S.K.Coleman
勿論、このような実績の大きな理由は研究資金の問題である。日本における基礎生命科学に対する資金、特に大学における研究資金の不足は長年の問題であった。日本政府の科学研究への資金増加はこの問題を多少は緩和するのに役立つであろう。しかし、この展開は、どうすれば資金を最も効果的に運用できるかという問題にポリシーメーカーの注意を向けさせることになる。そして、ここに、より大きい組織的構造の問題が介入する。その問題とは、流動性、実績に基づく報酬制度、そして、ジェネラリストとスペシャリストとの緊張関係などである。
日本の大学院の組織に関する問題は周知の事実で、しばしば「硬直」などという言葉を使って表わされている。では、政府や企業ではどうか。ほとんどの基礎研究は大学で行なわれると信じられているが、政府研究機関や企業研究所にも目が向けられねばならない。というのは、それらの機関は、大学院で基礎研究に必要な技術や能力を身につけた研究者に雇用機会を提供し、またある意味では、大学院によって供給される基礎研究結果(すなわち情報)の消費者としての役割をも果たしているからである。
しかし、日本の政府や企業では、大学院博士課程で、またポストドクターとして養成された、高度な基礎研究における才能の受け入れ体制が整っていない。例えば、課程博士号取得者には特別のキャリア・パス(昇進をも含む職業上の報酬)がない。事実、政府研究機関においては、博士号を所有する同年齢グループの研究者は所有しない者より給料が安いという例さえある。反面、企業では課程博士を雇用する代わりに、雇用後自社内で養成した論文博士を研究要員として使っている。
大学院で習得した基礎研究技術能力の所有者(即ち課程博士)が採用、昇給において報われない原因は様々である。例えば、課程博士取得者の知識や興味の幅は狭すぎる、という研究マネージャーからの訴えをしばしば耳にする。そして、そういう批判は無根拠だとはいえない。というのは、今の講座制度では大学院生の圧倒的多数が大学4年生の時から一つの研究室(「部屋」)に入り、博士課程修了までずっと一人の教授の研究テーマに専念しているからである。
しかし、問題点は課程博士達自身にのみあるわけではない。政府の研究機関や民間企業の研究開発部門の方にも問題の源泉がある。その一つは、能力と年功序列の排他的関係である。年功賃金制は70年代から衰えてきてはいるが、依然として「年功序列」を支えているグループは存在する。その一つとして、労働組合の果たす役割の可能性があげられる。日本生産性本部(現、社会経済生産性本部)が、各国を代表する電機・電子・通信系と化学系の大企業を対象として、1988年から89年にかけて実施した国際比較調査によると、日本では技術者の6割位が労働組合に加入しており、その加入割合はイギリスの3倍、ドイツの4倍、アメリカの60倍にも相当している。日本のバイオ関係産業の技術者がどれほど労働組合に加入しているかははっきり知られていないが、バイオ産業のみが例外的に低いとは考えられない。そして、一般に日本の労働組合は「年功序列」による処遇を支持してきた。また、これは現段階では逸話に過ぎないが、製薬会社の研究開発管理者に対して私が行なったインタビューの中で、労働組合が年功序列を離れた待遇システムは研究者と他の社員との「差別」であるとして反対し、年功序列制度を守るよう要求したという話を色々と聞いた。政府の研究機関の場合は、労働組合が研究活動の実績に基づいた優遇を拒否したという実例が幾つかある。また、研究開発の管理者は、部下の扱いに関して、これまでに行われてきた、ジェネラリストにふさわしい年功序列方式に慣れており、個人的な基礎研究能力所有者の評価や特別報酬制度を面倒なことと考えている。また、専門的によい評価を与えられれば与えられるほど研究者はエゴイスティックになる恐れがあるという意見も聞かれた。
どこの国でも運営上ジェネラリスト対スペシャリストという対立は見られる。「博士」という称号や出版物の著作者であることは、社内成績にくらべるとはるかに携帯的な資格である。こういう面では日本も例外ではない。現に、私の日本での調査によると、そういう資格を持っている研究者が、勤務先の企業をやめる実例が少なくなかった。しかし、ジェネラリストとスペシャリストの対立を解消することは日本では特に難しそうに思われる。なぜならば、日本では流動性が少なく、職場での上下関係が西洋よりはっきりしているからである。
大手会社の社内研究活動や研究人材育成を見ると、日本企業では高度な研究開発に課程博士等は必要ないのではないかという意見が出るだろう。もしその意見が正しければ、日本では大学院や課程博士取得者が、西洋の大学院やPh.D.のように、最先端の研究能力の提供には重要な役割を果たさないということになる。それに対して、80年代の蛋白工学研究所、大阪バイオサイエンス研究所等の設立は、企業自体が企業内における基礎科学研究の現状に満足していないという事実の現われではないだろうか。また、日本の製薬会社は、グローバルな競争に脅かされており、それを乗り切る方法は創薬にいたる斬新な発想しかないと言われている。企業内における、課程博士を所有する基礎研究者の待遇の現状を見ると、そのような発想をもたらすような環境が整っているとは思えない。また、現在の企業研究開発の状態がそのまま続くとすれば、日本企業が日本の基礎生命科学の国際評価の改善に大いに貢献できるようになるということは想像し難い。
勿論、基礎科学研究能力の推進は西洋における研究開発運営の単なる模倣に任せてはならない。現状の背景には、一方に職業の安定性と人材確保、他方に充実した個人研究者のキャリアの発展性、という相反する根本的な問題がある。日本企業の運営の特徴をふまえた上での、個人研究者のキャリア開発方法の総括的な研究が望まれる。そのような研究の成果は、西洋においても応用できる研究開発管理の方法を生み出す可能性を持つのではないだろうか。
6月から8月の三ヶ月間にわたるNISTEPでの滞在期間を、私は以前から行なっていた生命科学における組織問題の研究(特に民間企業に焦点をあてた)のための最新情報を得、完成させるために費やした。私が研究した問題、特に私が驚きの目で見たことはほとんど、NISTEPの人々はよくご存じであった。しかしながら、私の研究方法や観察が、少しでも日本の研究者の皆さんのお役に立てることがあれば、それより嬉しいことはない。
(なお、コールマン氏は非常に日本語が堪能であり、今回の原稿も氏自ら日本語で書かれたことを 最後につけ加えさせていただきます。)
Ⅱ.国際会議報告/International Conference
東海大学教授 権田金治
科学技術政策研究所が93年(第1回、於:岩手県八幡平)、95年(第2回、於:神奈川県湘南国際村)に開催した地域科学技術政策研究(Regional Science and Technology Policy Research)国際ワークショップの第3回会議がEC主催で開催(於:ベルギー、ブリュッセル、期間:1996年9月19日〜21日)された。EC側は、ⅩⅡ総局を中心にⅠ、Ⅲ、Ⅴ、ⅩⅢ、ⅩⅥ、ⅩⅩⅡの各総局が開催を支援し、特別顧問として日本から権田金治 東海大学教授、米国からマイケル・ルーガー(ノースカロライナ大学教授)が参加して開催された。
今回の会議は、統一テーマである "Global Comparison of Regional RTD and Innovation Strategies for Development and Cohesion" 「開発と統合のための地域における研究・技術開発と技術革新戦略の国際比較」の下に、オープニング会合、8つのパラレル・セッション、全体会合等が行われた。
次回会合については、1998年5月に米国のチャペルヒル(ノースカロライナ州)で開催されることとなった。
以下、今回会議プログラム概要、筆者の印象、及び今後の課題を記して会議参加報告とする。
○ 講演会等/Lectures at NISTEP
○ 主要来訪者一覧/Foreign Visitors to NISTEP