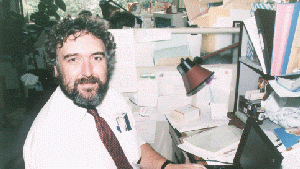| |
No.95 AUG 1996
|
| |
| |
| 科学技術庁科学技術政策研究所 |
| NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE |
| AND TECHNOLOGY POLICY |
政策研では昭和63年の設立当初より積極的に外国人研究者を受け入れ、開かれた研究体制の構築に務めてきた。本稿では、STAフェローにより英国マンチェスター大学から来日し、平成6年8月から平成8年8月まで第1研究グループ特別研究員として在籍したブレンダン・バーカー博士の研究成果の概要を紹介することとしたい。同研究は、自動車、建設、包装の3部門に焦点を当てつつ日本企業が新材料への需要に対応しながら、環境への影響を改善するためにどのような戦略的対応をとりつつあるかを調査したものである。
Ⅰ.研究ノート/Research Note
日本における新材料技術と環境
New Materials Technologies and the Environment in Japan
第1研究グループ ブレンダン・バーカー
<序論>
- 一般に製品、特にその材料が環境に与える影響に関する懸念は、ここ数年、日本を含め世界中で顕著に増大している。この環境懸念の高まりによって、企業に環境パフォーマンスの改善を迫る圧力が増している。環境立法の増加、廃棄物処分コストの増大、消費者圧力、環境破壊と浄化に対する責任は、企業にさらに持続可能な行動を採用させる重要な要因である。持続可能な行動とは、化石燃料や原料などの再生不能資源の節約とリサイクル不能な廃棄物 (特に有毒物質や有害物質) の発生量の抑制を意味している。
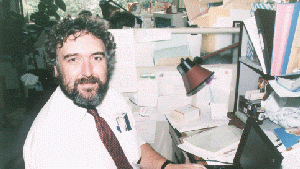
第一研究グループ 特別研究員 B.BARKER
産業活動の環境への影響に関する議論では、材料が決定的な重要性を持つ。材料は産業の中心であり、実際、すべての経済活動 の基となる装置、構造物、機械の性能は究極的にはそれを作る材料に依存する。企業 (延いては日本経済) が環境パフォーマンスをさらに改善しようとすれば、材料を開発し利用する新しい方法が必要となるであろう。
環境特性の向上した材料に対する需要の増大と平行して、その需要を満たす能力も増大する。この相互作用の結果、環境に優しい新しい材料とそれらを使う新しい方法が現れ始めている。本研究の目的は、この相互作用の性質を調べ、政府の役割と、技術と市場の接点において活動している企業の役割を調べることである。特に、自動車、建設、包装の三部門に焦点を当ててみた。
日本は、これらの問題を調べる場所として最適である。日本は、材料の研究開発に高い優先順位を置いてきた1)。 さらに、一連の環境災害の結果として、強力な環境制度を確立している2)。したがって、環境に優しい新しい材料の開発と使用を奨励する規制と、この需要を満たす材料を創出し供給する能力を支える技術基盤の両方を持っている。この意味で、日本は上に概説した諸問題を調べるための天然の「実験室」を提供する。
<材料の使用と環境>
- 材料に関する性質と現象は、その組成と構造に密接に関係する。また組成と構造は、エネルギーと知識を必要とする合成と加工の結果である。新材料の開発はますます集中的な科学研究によって支えられており、その研究は基礎的な性質を持つことが多い3)。 実際、新しい材料を従来の材料から区別する主な特徴のひとつは、微細構造 (ナノの領域に及ぶことも増えている) の制御である4)。したがって、新しい材料の特徴は、その知識集約度の高さにある5)。この (研究開発、コンサルタント業、サービスサポートなどの形で埋め込まれた) 知識の増大は、脱物質化や脱炭素化などに関連した現象にみられるように、効果的にエネルギーと物質を置き換えている6)。このため、新しい材料には環境パフォーマンスの改善を示す一般的な傾向がある。
さらに、科学的な専門知識の向上は、最小の環境影響を示す材料の創出を支援してきた。このような「エコ材料」は、ライフサイクル分析のような適切な分析技法に導かれたグリーンデザインとともに、製品の使用期間中およびその後における材料の環境への影響を減らす重要な方法を提供する。しかし、環境への材料の影響を著しく減少させるには、材料の使用方法をより根本的に変えることが必要とされよう。
<材料システムと環境>
- 環境への影響を根本的に減らすには、材料システムに変更が必要だろう。材料システム(mate-rials systems)という用語は、材料の最初の採取から最終処理までの材料の流れ (製品の生産・使用・処分の際に発生する廃棄物を含む) をいう。特定の材料技術に基づいてはいるが、このようなシステムは強い組織的な構成要素を持つ。企業は一般に、その材料基盤と連動している。すなわち、企業における機械、訓練システム、経験の集積は、材料または関連する材料の小グループと結びついているのが普通である。さらに、このようなシステム内での組織間関係は、イノベーションにとって重要である。本研究の示すところによれば、企業の技術的な適応能力と産業構造の中での機能の間には密接な関係がある7)。
Dahmenは、企業がどのようにその (事業) 環境に影響し、また影響されるかを理解するため、「開発ブロック」という概念を導入した8)。この考え方はネットワーク理論家によってさらに展開された。 Lundvall は、特にイノベーション・プロセスにおける利用者と生産者の関係に着目して、この問題を議論している9)。
経済活動は従来、線型ないし開放システムの材料フローでおこなわれてきた。そこでは、資源が経済活動を通じてほとんど一方向にだけ流れ、最後に廃棄される。このようなシステムは、資源の枯渇と廃棄物の増加という両方の点から見て持続不可能である。持続可能な材料システムとは、入力としてごく小量の資源を必要とし、システム内でより多くの資源を再利用し、ごく小量の廃棄物がシステムを離れるというものである10)。
材料の開発・使用・処分のシステミックな性質に対する認識は、現在日本に現れつつある全産業的な対応の大きな要因のひとつである。一般に、既存の強固な企業間関係 (例えば自動車産業に見られる関係) は、新たに現れつつあるエコロジカルな材料システムを支持してきた。このことは、既存の構造を通じて働く新しい材料システムを、産業界が発展させようとしてきた事実を反映している。
<結論>
- この日本における研究は、新しい材料および工程の創出と採用において、環境問題がますます重要な要素になっていることを示した。環境への影響は、材料の最少化、リサイクル可能性、耐久性、生分解性を支えるエコ材料の使用と設計の変更を通じて削減されつつある。日本の産業は、政府の支援を得て、これらの変化を推進する新しい材料システムを展開しつつある。ただし、部門によってそれぞれ段階が異なり、業界自体が主導権を取ってきた部門もあれば、政府が大きな役割を果たしてきた部門もある。いずれの場合においても、これらの新しい材料システムの開発促進には、政府の規制 (または将来の規制に対する企業の見通し) が決定的に重要であった。
(注)
- 1) Brendan Barker, Hugh Cameron and Luke Georghiou (1993), An International Comparison of Government Support for Materials Science and Tecnology, SERC 材料科学工学委員会への報告書
- 2) T. Shirai and T. Salusbury (1993), Environmental Issues and Control Technologies in Japan, 在東京英国大使館からの報告書
- 3) Brendan Barker, Paul Hooper and Alan Irwin (1992), The recycling of plastics in cars: case study on the UK, in P. Groenewegen et al, Technological Innovation in the Plastics Industry and its Influence on the Environmental Problems of Plastic Waste: Report on the Automotive Industry, 欧州共同体委員会 SAST への報告書
- 4) P. Cohendet, M. Ledoux and Zuscovitch (1988), New Advanced Materials, Economic Dynamics and European Strategy , 欧州共同体委員会FAST計画からの報告書、11月 27-28日。
- 5) Barker (1991), Engineering Ceramics and High Temperature Superconductors: Two Case-Studies in Materials Innovation, 博士論文, マンチェスター大学
- 6) 例えば、Oliviero Bernardini and Riccardo Galli (1993), Dematerialisation: Long Term Trends in the Intensity of Use of Materials and Energy ,Futures, May, pp 431-448 を参照。
- 7) Povl A Hansen and Goran Serin (1994), Materials development and the adaptability of the industrial structure , Technological Forecasting and Social Change , Vol 46, pp 125-137.
- 8) Erik Dahmen (1988), Development Blocks, Industrial Economics, Scandinavian Economic History Review and Economic History, Vol XXXVI, No 1.
- 9) B. A. Lundvall, (1988), Innovation as an interactive process: from user producer interaction to the National System of Innovation, in G. Dosi, Technical Change and Economic Theory, Pinter.
- 10) 例えば、Robert A. Frosch (1995), Adapting Technology for a Sustainable World, Environment, Vol 37, No 10, pp 16-24, 34-37 を参照。
Ⅱ.用語解説/ Technical Term
科 学 技 術 指 標
第1調査研究グループ
- 指標とは、簡単に言えばある物事を知ろうとするときのモノサシであり、科学技術指標とは、客観的な統計データを適切に加工しこれに基づき分析することにより、科学技術活動の実態を把握するためのモノサシを提供しようとするものである。科学技術指標は、科学技術政策の立案のための基礎資料になるばかりでなく、科学技術の現状について、科学技術政策研究者や一般国民に対し正確で客観的な情報を提供する上でも重要である。また、科学技術指標に関する国際的情報交換を通じて、世界的視野からみた我が国の科学技術の実態を把握することも重要となっている。
科学技術活動は、研究開発投資、科学技術人材、科学技術基盤、研究交流、研究成果の社会への発信、地域の科学技術活動等非常に広範多岐にわたるので、科学技術活動の全体像を明らかにするためには、個別の科学技術指標の体系化を図ることが重要である。このような観点から、政策研では、平成3年9月に初めて体系的な科学技術指標を作成し、さらに、平成7年3月には第2版を作成・公表した。この第2版では、最新のデータを取り入れ、指標数及び指標の分析を充実させるとともに、我が国の科学技術活動を総合的に示す合成指標を開発した。この合成指標は、多数の科学技術指標について、因子分析や主成分分析を行い、指標間の構造を明らかにしたり、数個の指標に集約し、一国の科学技術活動の全体像を把握することを目的としたものであり、今後重要性を増すものと考える。
科学技術指標は、科学技術の進展に応じて適宜改訂することが重要であり、第3版については、遅くとも来年末までに作成・公表することを目標に作業を進めている。
Ⅲ.最近の動き/Current Topics
- ○ 主要来訪者一覧/Foreign Visitors to NISTEP
- ・6/4〜9/3 Dr. Samuel Kataoka Coleman
- (米国オレゴン大学助教授)
- ○ 海外出張報告
欧 州 出 張 報 告
第1研究グループ総括主任研究官 後 藤 晃
- 筆者は、6月3、4、5日にストックホルムで開かれた国際シュムペーター学会の第6回大会に参加した。以下ではその概要を報告する。
- 国際シュムペーター学会は、ケインズとならんで近代的な経済学の確立に中心的な役割をはたし、とりわけ経済の動態的発展の研究に貢献し、イノベーションという概念を初めて導入したシュムペーターの名前を冠した国際的な学会であり、技術進歩、イノベーションを研究する世界の学者がそのメンバーとなっている。その学会誌JOURNAL OF EVOLUTIONARY ECONOMICSは、この分野の代表的な雑誌となっている。
今回の大会のテーマは、「参入、競争と経済成長:企業、イノベーター、起業家と市場競争」であり、100をこえる論文が発表された。なかでは、二つのタイプの研究が注目された。第一は、産業の生成から熟成までのプロセスについてのシミュレーションによる研究である。このタイプの研究はかつてNELSONとWINTERが行ったが、その後、それほど注目されなかった。それが、最近、進化論的産業・技術発展のプロセスを研究する方法として再び関心をあつめている。今大会では、その関心のリバイバルのきっかけのひとつともなった論文をかいたKLEPPERが新しい論文を発表したほか、上述した、最初にこの方法をおおきく取り上げたNELSONとWINTERも、NEW GENERATIONのシミュレーション分析を発表した。このようなアプローチにより、市場構造の時間を通じた変化に技術、新企業の参入などがどのような役割を果たしているかということを理解するのには役立つものの、このアプローチによってどのような事柄の解明に役立つのかということについては、さらなる検討が必要であるようにおもわれた。
第二は、産業のイノベーションにおける大学の役割についての研究である。このテーマについては、かなりの数の論文がヨーロッパ、米国の学者によって報告され、この問題にたいする幅広い関心が存在することが知られた。報告された論文のおおくは、産業のイノベーションと大学の存在の関係についての計量的な研究であったが、なかでは、バイオ企業と大学の関係について計量的、かつ実体的に検討したAUDRETCHやACSの研究が興味深かった。わが国でも基礎研究の振興が重要な政策課題として論議されており、基礎研究の主要な担い手である大学のイノベーションにおける役割について一層の研究が必要であると感じた。
なお、私は、本学会の理事であり、学会の前日にひらかれた理事会にも出席したが、次次期の会長にイギリスのメトカーフ教授(マンチェスター大学)をえらんだ。(次期会長はウィーン大学のミューラー教授)。また、任期満了となった後藤の後任の日本からの理事に馬場靖憲氏(東大)を推薦し受理された。
�


 研究ノート Research Note
研究ノート Research Note
 用語解説 Technical Term
用語解説 Technical Term
 最近の動き Current Topics
最近の動き Current Topics