
 |
No.93 JUN 1996 | |
| 科学技術庁科学技術政策研究所 | ||
| NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE | ||
| AND TECHNOLOGY POLICY |
| 目次 [Contents] |  所長挨拶 Director's Remarks 所長挨拶 Director's Remarks
|
 レポート紹介 Highlight of the New Report レポート紹介 Highlight of the New Report
| |
 最近の動き Current Topics 最近の動き Current Topics
|
6月25日、科学技術政策研究所長に就任いたしました宮林正恭でございます。
科学技術政策研究所は効果的な科学技術政策研究を強化、充実してゆくため昭和63年、科学技術庁に設置されました。以来設立8年目を迎える今日まで、国際的視野に立った政策、イノベーションの基礎となる理論を確立するための研究、政策上の重要課題となっている諸事項に関する実証的調査研究を進めるとともに、国際的にも多数の海外機関との研究交流、国際コンファレンスの開催など広く世界に開かれた研究所として活発な活動を続けて参りました。
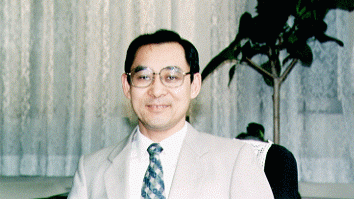
Ⅰ.レポート紹介 Highlight of the New Report
第3調査研究グループ
契約期間に大きな差ー日本の技術貿易の特徴① 技術輸入の契約期間は一般に技術輸出の契約期間に比べて長い。
② 技術輸出では建設業、鉄鋼業などの業種の契約期間は短く、化学工業、特に医薬品工業、電気機械工業、自動車工業などの業種の契約期間は著しく長く技術輸入の契約期間は業種による著しい違いはない。
③ 技術輸出の契約期間は対アジア地域で若干短く、対欧米で長く、また、技術 輸入の契約期間は各地域で差はそれほどみられない。
1.目的及び手法
技術貿易の契約期間から技術レベル、技術の種類や中身、技術に対する考え方、技術貿易についての戦略、相手側との力関係などが類推できると考えられる。
本報告書では、総務庁統計「科学技術研究調査報告」に収録された1971年以降の技術貿易の統計から、技術貿易の契約期間を数値解析すると共に、その結果と実際に技術貿易に携わっている各業界の実務担当者への聞き取り調査の結果とを併せ、我国の技術貿易の構造を考察した。
数値解析には、先に報告した指数関数減衰モデルを用い、全業種について継続する契約件数が最初にあった契約件数の10%以下に減衰するまでの期間を求め、契約期間とした。表1〜表3にこの解析法から推定された契約期間値をまとめた。
数値解析により推定した契約期間ならびに各業界関係者からの聞き取り調査の結果、我が国の技術貿易について冒頭に述べたような特徴が明らかになった。以下に詳しくのべる。
2.結果
特徴1: 全産業の技術輸出と技術輸入の契約期間を比較すると、技術輸入の契約期間が技術輸出の契約期間に比べて長い。
その理由として、技術輸出では継続期間が短いノウハウの割合が多く、長期間継続する基本特許が少ないが、技術輸入ではその逆の傾向があるためと考えられる。
実際これまでの当研究所の調査によれば1993年度に新規に結ばれた技術貿易の契約に特許とノウハウが含まれる割合は技術輸出で40%、90%であるのに対して、技術輸入ではそれぞれ50、60%であり、技術輸出では技術輸入に比べてノウハウの割合が高いという結果が得られているからである。
この件につき業界筋に対する聞き取りを行ったところ、我が国の輸出技術はノウハウが主体の物が多く、輸入技術は基本特許など特許が主体の物が多いとのことであり、契約期間が異なる原因として、技術の主体が継続期間の長い特許か継続期間の短いノウハウかに依存するという推測に対する裏付けが得られた。
特徴2: 技術輸出では建設業、鉄鋼業などの業種の契約期間は短く、化学工業、特に医薬品工業、電気機械工業、自動車工業などの業種の契約期間は著しく長い。一方、技術輸入の契約期間は業種による著しい違いはない。
これまでの当研究所の調査結果を見ると、技術輸出の中身は各業種に関連の深い分野の技術が大半を占めるのに対して、輸入技術の中身は広く種々の分野に関する技術であることが明らかにされている。従って技術輸出においては、技術内容の違いにより契約期間がばらつくのに対して、技術輸入では各業種が種々の分野の技術を導入しているため契約期間が平均化され、業種間では違いがみられなくなるものと類推される。
実際、業界筋に対する聞き取り調査の結果を見ると、「建設、鉄鋼などの業種では、大きな工事やプラント輸出などに付随する技術としての設計図面、技術指導、工程や品質管理技術などが主であり、契約期間は概して短い。これに対して電気、自動車など製品を製造する技術、コンピュータソフトなどが主体の技術の契約期間は長くなる。特に、医薬品などR&Dや臨床試験などに時間と費用のかかる業種では長期間に亘りその費用を回収しようとするため契約期間は長くならざるを得ない」とのことであり、技術輸出の場合技術分野によって契約期間の長さが長くなったり短くなったりしている現状が確認された。
特徴3: 技術輸出の契約期間は対アジア地域で若干短く、対欧米で長い、一方、技術輸入の契約期間は概して長く、各地域で差はそれほどみられない。
業界筋の話し等からその理由を考えると、アジアの中には政策上契約期間を短めにするよう要請しているところもあること、また、技術の中身もアジア向けのものは継続期間の短いノウハウが主体であることが技術輸出の契約期間が短い理由であると考えられる。これに対して、対欧米の場合には継続期間に関する規制はなく、技術の中身も継続期間の長い特許がらみのものが多くなっているため契約期間が長くなっていると考えられる。
業界筋の話から一貫して感じられることは、契約期間の長短は、対価の受け払い方法や、技術レベル、相手先国との力関係、交渉力の違い、需要供給の関係などが複雑にからんで決まってくるものであるということであった。
本報告では、数値解析により推定した契約期間ならびに各業界における聞き取り調査の結果、技術輸出と技術輸入、業種別、国・地域別にその構造を類推した。本解析は、総務庁統計における新規契約件数を土台として技術貿易の契約期間を求め、これから構造の類推を試みたものであることから、新規契約件数の把握が解析の精度に影響を与えると考えられる。
| 業 種 | 年度区分 | 契約期間(年) |
| 全産業 | 全期間 | 2.5 |
| 〜1979 | 9.6 | |
| 1980〜85 | 7.6 | |
| 1986〜 | 10.2 | |
| 農林水産業 | 全期間 | 8.5 |
| 鉱業 | 〃 | 5.8 |
| 建設業 | 〃 | 2.8 |
| 製造業 | 〃 | 9.4 |
| 食品工業 | 〃 | 7.2 |
| 繊維工業 | 〜1985 | 9.1 |
| 1986〜 | 4.7 | |
| パルプ・紙工業 | 全期間 | 8.6 |
| 出版・印刷業 | 〃 | 7.7 |
| 化学工業 | 〜1979 | 13.2 |
| 1980〜83 | 11.9 | |
| 1984〜 | 23.6 | |
| 総合化学・化学繊維 | 全期間 | 10.2 |
| 油脂・塗料工業 | 〃 | 21.3 |
| 医薬品工業 | 〜1984 | 31.1 |
| 1985〜 | 44.8 | |
| その他の化学工業 | 全期間 | 12.9 |
| 石油・石炭製品工業 | 〃 | 4.8 |
| プラスチック製品工業 | 1984〜 | 9.2 |
| ゴム製品工業 | 全期間 | 33.5 |
| 窯業 | 〃 | 6.5 |
| 鉄鋼業 | 〃 | 4.7 |
| 非鉄金属工業 | 全期間 | 11.5 |
| 金属製品工業 | 〃 | 6.1 |
| 機械工業 | 〜1983 | 4 |
| 1984〜 | 10.5 | |
| 電気機械工業 | 全期間 | 24.1 |
| 電気機械器具工業 | 全期間 | 21.7 |
| 通信・電子・電気計測器工業 | 〃 | 23.1 |
| 輸送用機械工業 | 〜1985 | 17.6 |
| 1986〜 | 43.1 | |
| 自動車工業 | 全期間 | 42.5 |
| その他の輸送用機械 | 〃 | 16.8 |
| 精密機械工業 | 〃 | 7 |
| その他の工業 | 〜1985 | 3.7 |
| 1986〜 | 22.4 | |
| 運輸・通信・公益業 | 〜1984 | 6.3 |
| 1985〜 | 2.6 |
| 業 種 | 年度区分 | 契約期間(年) |
| 全産業 | 全期間 | 17.6 |
| 1981〜 | 17.3 | |
| 農林水産業 | 全期間 | 8.5 |
| 鉱業 | 〃 | 11.1 |
| 建設業 | 〜1984 | 11.1 |
| 1985〜 | 6.7 | |
| 製造業 | 1981〜 | 17.8 |
| 食品工業 | 全期間 | 13.1 |
| 繊維工業 | 全期間 | 13.2 |
| パルプ・紙工業 | 全期間 | 14.2 |
| 出版・印刷業 | 〃 | 14.7 |
| 化学工業 | 1981〜 | 26.8 |
| 総合化学・化学繊維 | 1980〜 | 21.9 |
| 油脂・塗料工業 | 全期間 | 41 |
| 医薬品工業 | 1980〜 | 44.4 |
| その他の化学工業 | 全期間 | 17.8 |
| 石油・石炭製品工業 | 〃 | 19.6 |
| プラスチック製品工業 | 1984〜 | 14.7 |
| ゴム製品工業 | 全期間 | 40 |
| 窯業 | 〃 | 17.6 |
| 鉄鋼業 | 1980〜 | 18.1 |
| 非鉄金属工業 | 1983〜 | 20.2 |
| 金属製品工業 | 全期間 | 18.4 |
| 機械工業 | 1981〜 | 19.1 |
| 電気機械工業 | 1985〜 | 17.5 |
| 電気機械器具工業 | 1979〜85 | 16.6 |
| 1986〜 | 18 | |
| 通信・電子・電気計測器工業 | 1986〜 | 15.4 |
| 輸送用機械工業 | 全期間 | 25.2 |
| 自動車工業 | 1979〜 | 20.2 |
| その他の輸送用機械 | 1983〜 | 29.3 |
| 精密機械工業 | 全期間 | 22.7 |
| その他の工業 | 〜1980 | 18.1 |
| 1981〜 | 4.6 | |
| 運輸・通信・公益業 | 全期間 | 3.4 |
| 国・地域別 | 契約期間(年) | |
| 技術輸出 | 技術輸入 | |
| 全地域 | 9.3 | 17.3 |
| アジア地域 | 8.6 | − |
| インド | 9.5 | − |
| インドネシア | 8.3 | − |
| 韓国 | 7.8 | − |
| シンガポール | 11.5 | − |
| タイ | 13.2 | − |
| 中国 | 4 | − |
| 台湾 | 9 | − |
| マレーシア | 9.8 | − |
| フィリッピン | 10.1 | − |
| 北アメリカ地域 | 13.1 | 17.7 |
| 合衆国 | 13.1 | 17.9 |
| カナダ | 9 | 10.7 |
| ヨーロッパ地域 | 10.4 | 17.5 |
| イギリス | 12.9 | 17.6 |
| イタリア | 9.9 | 12.4 |
| オランダ | 10.1 | 18.9 |
| スイス | 13.2 | 17.1 |
| スウェーデン | 8.6 | 18.5 |
| スペイン | 11.2 | − |
| ドイツ | 11.4 | 19.8 |
| フランス | 8.9 | 17.2 |
| ベルギー | 8.9 | 17.5 |
| オセアニア地域 | 10.6 | 16.1 |
○ 研究会等/Research Meetings
○ 講演会等/Lectures at NISTEP
○ 主要来訪者一覧/Foreign Visitors to NISTEP
○ 人事往来
○ 海外出張
○ 海外出張報告
所長 尾藤 隆
企画課 堀田 継匡
新たな国際共同研究関係の構築のためヨーロッパ及びアメリカの諸機関を訪問し、その動向調査及び情報交換を行った。機関の概要は以下のとおり。
1.スウェーデン産業技術開発国家委員会(NUTEK):3月25日訪問
Heinegard副所長以下を訪問
産業技術開発国家委員会(NUTEK)は通産省(法案作成と予算要求のみを行い、施策の実施は下部委員会が実施)傘下にあり職員数は約400人。経済や産業の発展、長期的なエネルギーシステムの発展に等を所掌する機関である。
現在、ビジネス、エネルギー、地域開発、技術研究開発及びアナリシスの5部門に分かれている。
スウェーデンの公的研究機関は大学が中心。科学技術に関しては、科学的研究と教育の調整一般は教育省の責任。産業に係わるものは通産省の責任。過去1年半の間に政権交代があったが基本的には1993年策定の政策を踏襲したが若干の変化があったとのことであった。
2.EU12総局:3月26日訪問
Draxler 第12総局社会経済研究担当局長以下を訪問
現在EUがおこなっている第4次フレームワーク研究開発計画の個別計画の1つである「目標型社会経済研究に関する研究・技術開発・実証個別計画」についてその概要、実施状況について先方より説明があった。
また当方より日本の科学技術政策の展開として、科学技術に関する研究開発の振興を図るための枠組み法として、科学技術基本法が成立し、これに基づき、科学技術基本計画の策定に取り組んでいる旨説明。また、我が国の科学技術関連予算、研究開発の動向等について説明した。
3.フラウンホーファー協会技術革新研究所(ISI):3月28日
Grupp 副所長以下を訪問
フラウンホーファー協会技術革新研究所(ISI)はフラウンホーファー協会
において自然科学及び技術を担当している機関である。外部評価等について当方より質問を行った。
4.応用システム解析国際研究所(IIASA):3月29日
Jager 副所長を訪問
応用システム解析国際研究所(IIASA)は17の国から構成されるコンソーシアムによって支援された学際的な非政府研究機関である。東西冷戦中に東西の架け橋として設立された。しかし東西冷戦の終結により新たな方向性を摸索しているとのこと。
現在、1)地球環境、2)経済変換と技術、3)システム解析手法の開発の3つに特化している。2)は社会主義経済から市場経済への転換に努力しているロシアの希望によりおこなわれている。
米国はNSF、日本は通産省の協会が主要スポンサー。今のところ先進国のみだがいずれ途上国も参加する予定である。
当方よりは日本の科学技術関係予算の概要、主な科学技術施策の概要等について1時間程度の講演を行った。
5.国立科学財団(NSF):3月29日訪問
Bardon 国際プログラム部長以下を訪問。
当方よりJISTEC及びJRDC共同の科学技術センターを米国西海岸(サンフランシスコ)に設置し、我が国の科学技術活動の広報あるいは情報交換の窓口としたいとの説明を行った。
JAPAN PROGRAMとしては現在STAフェロー事業に対する応募が急増しているとの発言があり、センターの役割につき特段の関心を示した。
また、当方より科学技術基本法に基づく科学技術基本計画の策定(本年6月を目途)に政策研として既存のデータにより改革に参画していく旨説明した。加えて政策研が開かれた研究環境を有することを掲げ、調査研究活動における協力を続けたい旨を述べ、NSFも同意。