
 |
No.92 MAY 1996 | |
| 科学技術庁科学技術政策研究所 | ||
| NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE | ||
| AND TECHNOLOGY POLICY |
| 目次 [Contents] |  レポート紹介 Highlight of the New Report レポート紹介 Highlight of the New Report
|
 最近の動き Current Topics 最近の動き Current Topics
|
第1調査研究グループ
1.目的理工系に進学する女子の人数は、最近増加する傾向にある。しかし、他の専攻や諸外国と比較すると、女子が占める割合は小さい。この調査では、女子を理工系から遠ざける要因が存在していると考えられることから、理工系、とくに女子の占める割合の小さい工学系に着目して、女子の専攻選択に関わる要因を明らかにすることを目的とした。

2.方法
大学の理工系学部に在籍する男女および経済系学部に在籍する女子に対するアンケート調査を実施し、女子の専攻選択に関わる環境要因(環境により影響を受ける心理を含む)の分析を行った。アンケート調査の概要は以下のとおりである。
<アンケート調査の概要>
3.結果
(1)専攻選択と性別
現在とは逆の性別ならば工学を志望するかどうかを見ると、女子は、理工系、経済系を通じて、もし自分が男子ならば工学を志望したいとする者が、女子であることを前提として(今選び直す場合)工学を志望したいとする者よりも多くなっている。たとえば、理学女子では 17% が 28% に、経済系女子では 7% が 21% になっている。理工系男子は、もし自分が女子ならば、人文科学や社会科学を専攻するという意識をもつ者が比較的多い。たとえば、工学男子では人文科学が 6%が 23%に、社会科学が 14% が 24% になっている(図1参照)。
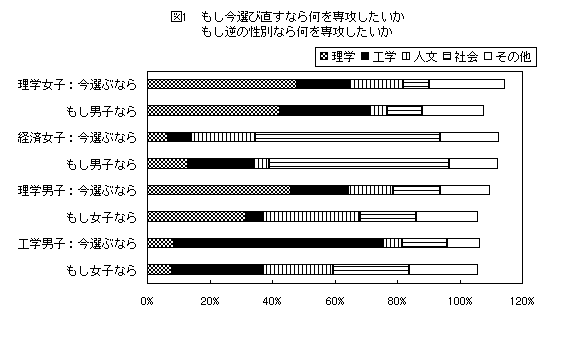
(2)専攻選択と体験、得意科目、就職
①興味・関心を引き起こす体験
小学校高学年までに理科系を選択した者の動機を見ると、「学校の成績」「学校の授業・実験」と並んで、「生き物・自然への興味」「親」「生活の中での発見・驚き」「書物・番組」「機械いじり」といった日常生活での体験が多い。しかし、「親」を除くと、女子は男子より日常生活での体験を動機とした者が少ない。
②得意科目
工学専攻と物理の得意意識の関係を見ると、工学専攻者には物理を得意とする者が多い。一方、女子は、男子に比較して物理に苦手意識をもつ。 女子も男子も、女子が工学を専攻するためには、男子である場合以上に物理が得意でなければならないと考えている。物理が同程度に得意であっても、女子であることが工学選択のハードルを高くしている(図2参照)。
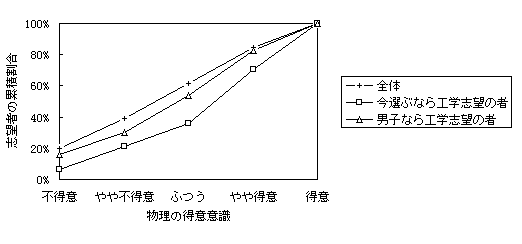
③就職
工学を専攻したことは就職に関してどの程度有利と意識しているのかを見ると、男子は工学を最も有利と考えているが、女子は、男子ほど有利とは考えていない。
就職にあたって、女子は仕事・処遇に性差のないことや育児制度の充実など、男子と対等に仕事を続けるための事項を考慮している。育児制度の充実などの条件整備については、女子は自分と結婚相手の双方の問題と捉えているのに対し、将来職場の同僚となる男子は、家庭と仕事の関わりに関する問題が自分の問題でもあるとは捉えていない(図3参照)。
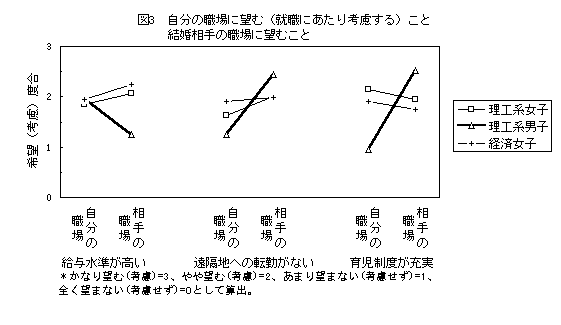
④大学生活における満足度合
大学の生活面を見ると、工学女子においては、更衣室・休憩室・トイレなどの施設、相談できる友人の数などの満足度合が少ない。
⑤両親などの意見
両親の賛成度合を見ると、機械や電気を専攻する女子に対する両親の賛成度合は男子より低い。両親ともに文系出身の場合はそうでない場合よりも。女子の理工系選択に賛成する度合が低い。
4.結論
男女が同じ立場で自由に理工系を選択できるようにするためには、専攻選択に関わる女子ゆえの影響を小さくする対策をとることが重要である。具体的な対策としては次のことが考えられる。
第2調査研究グループ
1.概要
近年、日本企業の研究開発活動の海外拠点数は増加している。本研究は、海外拠点における研究開発活動(以下「海外R&D」と略記。)がどのような成果をあげているかという観点から調査したものである。従来の海外R&Dに関する研究は、どの国にどの業種が研究所を設置しているか、といった進出形態に関する分析が中心であった。本研究は、本格化して5〜10年を過ぎた海外R&Dの成果について企業がどうみているかを問う最初の試みである。
海外R&Dについての知見は少ないので、まず電機、医薬品産業についての海外R&Dの実態分析を行い、次いで海外R&Dのパフォーマンスに対する評価方法を探った。また、政策的な意味合いを模索し、本研究の限界について記す。

2.研究方法
電機、医薬品産業で海外R&Dを行っている大手企業についてケーススタディを行った。文献、統計調査を行ったのち、インタビュー調査を行った。インタビュー調査は、1995年4月〜10月にかけて、電機・医薬品の2業種の主要企業19社の本社研究開発管理部門担当者(主に部長クラス)を中心として行った。調査の対象は大企業が中心であり、また調査対象の海外R&D拠点は、主として本社研究開発管理部門が管轄するところである。それらは基礎研究や、要素技術開発など技術的に高度な分野を担当する拠点が多い。(それに対して、今回調査の対象ではない企業の事業部が所轄する海外R&D拠点は、製品の改良や現地市場対応を目的とするものが多いとみられる。)
インタビューにおいては、主に以下を質問した。
①海外R&Dの概要(設置地域、規模、進出動機等)
②海外R&Dのパフォーマンスに関する、企業の研究開発管理担当者の主観的な評価
「同種の研究開発を行っている自社の海外と日本の研究開発拠点と比べた場合のパフォーマンスの相対評価」を以下の6項目について尋ねた。
i)論文作成、ii)特許等知的所有権の取得、iii)アイデアの産出
iv)新製品の開発、v)技術目標の達成スピード、vi)波及効果 (注)
| (注)ここではパフォーマンスとは、研究者個人または組織の業績という意味で用いている。海外R&Dの研究内容について、研究段階を主とする場合と、開発段階を主とする場合に分けて聞いた。研究段階とは事業化、商品化が先の段階の研究で、開発段階とは事業化、商品化が近い段階の研究を指す。研究段階については新製品開発は質問から除外した。開発段階については、論文作成を除外した。 |
3.主な結果
(1)実態分析
①海外R&D拠点は小規模である。(図1)
研究者が39人以下のが拠点が四分の三以上を占める。
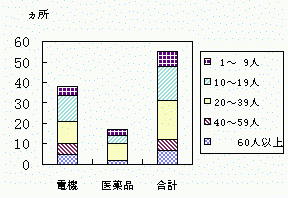
②研究拠点を設置する動機としては、両業界とも厳しい技術革新競争に直面しており、そのため海外の技術開発力を求めて海外研究拠点を設ける例が多い。
③海外研究拠点では日本人研究者は少ない。ほとんどが現地の研究者で研究を行っている。
④研究所を設置している国は電機では米国が半分以上、医薬品でも米国が多い。英国、ドイツが次いでいる。
⑤特に医薬品において、日本と比べ、外国の研究開発コストが相対的な有利であることにメリットを感じているという企業が多かった。
これについてはマクロ的な日本と海外(例えば米国)との研究開発コスト比を表すR&D購買力平価(1995年には1ドル155円程度と見積もられる)と為替レート(1995年には1ドル100円程度)は大きく乖離している状況がみられる。
(2)パフォーマンス評価
①研究段階による違い
「研究段階を主とする海外R&Dは、日本の同種の研究拠点よりもパフォーマンスが優る」のに対して、「開発段階を主とする海外R&Dは、日本の同種の拠点よりもパフォーマンスが劣る」という結果になった。(図2)
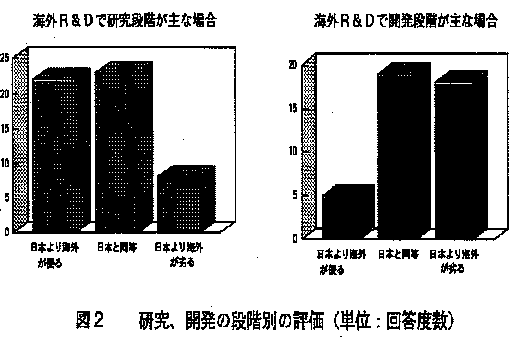
②アイテム別の特徴
アイデア産出では海外の研究開発拠点のパフォーマンスが優り、特許、新製品開発では日本の研究開発拠点のパフォーマンスが優る。
(3)副次的なデータとして、企業が作成する外国語(主として英語)による論文数のうち、海外研究開発拠点が関与しているもののシェアを調べたところ、1984年には2.8%であったものが、1994年には6.6%に上昇した。
(4)海外と日本で研究開発を行うことによる相乗効果は、あまり現れていない。
4.原因についての考察
なぜこのような研究と開発の段階別でパフォーマンスが違うのであろうか。諸文献や他で観察される事柄からその原因について考察した。
(1)海外の方が研究段階でパフォーマンスが高い原因としては、以下が挙げられる。
①当該分野における外国の研究水準が高い
②研究人材が豊富で、流動的である
③日本より外国の方が創造性を重視する教育を行っている
④現地の研究社会と直接コミュニケーションをすることにより、情報が得られる
⑤海外研究所では組織の専門性が高い
(2)海外の方が開発段階でパフォーマンスが低い原因
開発段階においては、製造、企画、マーケティング等の企業の他部門や試作や部材供給などの関連企業との協働が重要であるが、日本に存在するそれら組織と海外開発拠点の協力が十分取れないことが大きな原因とされる。
5.政策的な含意
インタビューした企業ではほとんどが、今後ますます海外R&Dは進展するとしている。以上の結果が、日本企業の海外R&Dの全体的な傾向を表すとすれば、政策的な意味合いとしては、海外研究協力基盤の整備、日本の基礎研究の充実と国内R&Dシステムの整備、国際摩擦への配慮をしていくことが考えられる。
6.限界と残された課題
本調査の対象は、2業種で、大企業が中心であり、また本社が直接管轄する海外R&Dの拠点であった。一般に海外R&Dとイメージされる場合よりも、基礎研究や、要素技術開発などの技術的に高度な分野を担当する拠点が多い。従って、本結果はそれらを調査範囲とした場合の限定的なものである。
なお、日本企業の海外R&Dのパフォーマンスについては、本調査方法をもとに、より大規模なアンケート調査を科学技術庁で実施している。他業種や、企業の事業部所轄のより規模の小さい開発、改良を行う海外R&Dについては、その結果から分析できるものと期待している。
○ 講演会等/Lectures at NISTEP
第2研究グループ主任研究官 柿崎 文彦
3月26日〜4月6日の期間米国ワシントン,D.C.等に出張した。今回の出張の目的の中心は米国における最近の科学技術政策の動向を調査することである。筆者が調査の拠点としてアポイントをとった機関は National Science Foundation(米国国立科学財団、通称「NSF」と呼ばれている。)である。NSFは1950年に設立された米国連邦政府の一機関であるが、大統領府には直接属さず、法律に定められたミッションの遂行を行う独立の機関である。同じ性格の機関として著名なものにNASAが挙げられる。NSFのミッションを簡潔に述べると、大学に対する研究費の交付と科学技術活動の評価を目的とした統計等の収集及び公表である。調査の拠点としてアポイントをとったのが後者の活動に着目したのはこのためである。WWWを利用できるならば、NSFの活動等の詳細は(http://www.nsf.gov/)から情報を得ることができる。
今回の出張で最も幸運であったのは、NSFの諮問機関である National Science Board(科学審議会, NSB)が隔年に公表する Science and Engineering Indicators のとりまとめが最終段階にあったことである。NSBは産学の有識者25名から構成され、事務局長をNSFの Neal Lane長官が務めている。実際に報告書を作成するスタッフは社会・行動・経済科学局の科学資源研究部(Science Resources Studies Division, SRS)である。約50名のスタッフとほぼ同数のアシスタントが協力して作業を行っている姿は壮観である。最終稿を調整しているため、このセクションに米国の科学技術政策に関する資料がすべてそろっている。(http://www.nsf.gov/sbe/srs/stats.html/にSRSが公表している科学技術関連統計のデータ等が掲載されておりダウンロードも可能である)。
筆者の関心事の中心は米国の連邦政府機関における研究開発活動の見直しについてであった。一例として、東西冷戦の終焉に伴い国防総省あるいはエネルギー省傘下の国立研究機関はその存在の是非が問われた経緯があり、実際に研究開発費も削減されている。この背景には連邦政府による連邦政府機関の徹底した研究評価の結果であることがわかった。それは、米国議会の強い要請が働き、大統領府直属の機関である行政管理予算局が国立研究機関の研究開発費並びにその成果に徹底した調査を行い、研究開発成果の約50%しか民生用に転換されていないという結果が報告されたためである。
クリントン政権では雇用拡大・環境保全・経済成長、科学技術でのリーダーシップを国家目標とし、このため科学技術は重要施策の一つとなっている。しかし一方で、財政均衡という別の大きな国家目標もあるため研究評価並びに手法の開発が改めて強く認識されている。これについては1993年に上下両院の全会一致で可決され法律となった The Government Performance Results Act(GPRA, ゲプラと発音する)に関する説明を受けた。これは政府機関における公的資金の利用とその成果をプログラムごとに定量的な評価を加えること、及び定量的手法を開発することの責務を定めた法律で、究極の研究評価とも言えるであろう。どの政府機関にもGPRAの専任担当者がいるものの、法律の解釈を始め、具体的な運用については今になっても明確な判断がつかないでいるようである。
久々に旧知の人々に会うことができ、また多くの有益な情報を得ることができた。改めて海外との研究交流の重要性を痛感した次第である。
米国の東海岸にも遅い春が訪れ、帰国の途につく日、ワシントンは満開の桜で彩られた。