
 |
No.91 APR 1996 | |
| 科学技術庁科学技術政策研究所 | ||
| NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE | ||
| AND TECHNOLOGY POLICY |
| 目次 [Contents] |  巻頭特集 Preface 巻頭特集 Preface
|
 国際会議報告 International Conference 国際会議報告 International Conference
| |
 最近の動き Current Topics 最近の動き Current Topics
|
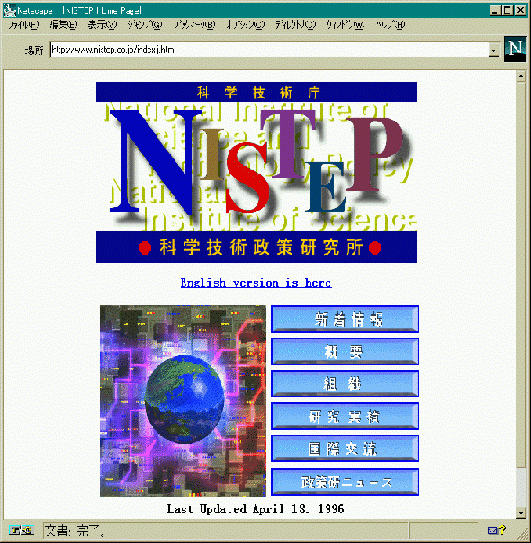
科学技術政策研究所は本年3月18日よりインターネットにホームページを開設しました。アドレスは「http://www.nistep.go.jp」となっておりますので、インターネットを利用可能な方は接続してみて下さい。ホームページには、沿革、組織などの当研究所のおおまかな紹介のほか、交流のある海外の教育・研究機関、当研究所が発表したレポートおよび調査研究資料の一覧等が掲載されています。
「研究実績」のページには、従来電話等で問合せの多かった、レポートの種類、内容、閲覧及び入手の方法が掲載されています。
レポート類の電子媒体による入手(ダウンロード)は、従来は ftpでのみ可能でしたが、ホームページからもできるようになりました。レポートの参照方法は、まず一覧表の中からレポートを選択して、目次や概要を見て、関心があればレポート内容を入手(ダウンロード)する、という流れで行うことができます。
提供しているレポート類の種類及び内容についても、従来はテキストのみで12種類でしたが、48種類が可能となり、それらのすべてに図表を添付しています。
今後、これらの情報の拡充を図るとともに、新たに発表されるものはすべてインターネットでも提供していく予定です。
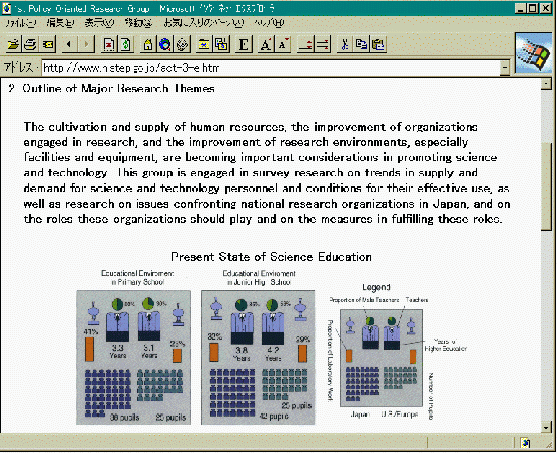
この政策研ニュース(No.91)もホームページを通して見ることができます。印刷物は白黒ですが、ホームページのニュースにはカラー写真を掲載しています。
「OECDオスロマニュアルの改訂に関するワークショップ」に出席して
第一研究グループ 後藤晃
1996年3月6日、7日にパリのOECD本部で開催された表記の会合に出席した。以下にその背景、概要などを報告する。OECDではかねてより研究開発活動の数量的なデータ収集のためのガイドラインとしてフラスカッティ・マニュアルを発表しているが、これに加えて1992年にイノベーションの質的な側面について企業へ質問票調査を行いデータを集める際のガイドラインとしてオスロ・マニュアルを作成、発表した。この背景には、2月に政策研の主催でおこなわれたイノベーション調査についてのワークショップでみられるような、質問票調査をもちいて占有可能性や技術機会のようなイノベーションに重要な影響を与える要因についての実態を明らかにする研究への関心の高まりがある。
1992年のオスロ・マニュアルの公表以後、ヨーロッパで Community Innovation Survey と呼ばれる調査が実施されており、さらにいくつかの国でも同様の調査が実施された。これらの経験を生かすとともに、あらたにサービス・セクターのイノベーションをも対象に含める可能性などをめぐってオスロ・マニュアルの改訂作業がかねてよりおこなわれていた。今回の会合もその一環である。日本でも政策研により同様の調査がおこなわれており、筆者はこの結果を報告した。会合にはOECDメンバー諸国の代表に加えて、ロシアと韓国がオブザーバーとして参加した。
議論の中心となったのは、サービス・セクターのイノベーションを調査対象に加える事に伴いマニュアルにどのような修正が必要となるかという点であった。元々、マニュアルは製造業を念頭において作成されているために、製造業とは多くの点で異なりまたその内部も多様なサービス・セクターを含めることに伴い、かなりの再検討が必要となったのである。
なお、サービス・セクターは我が国経済の中でも大きな比重をしめているが、そこでの技術進歩についての研究はあまりおこなわれておらず、今後の重要な研究分野となるものと思われる。
○ 研究会等/Research Meetings
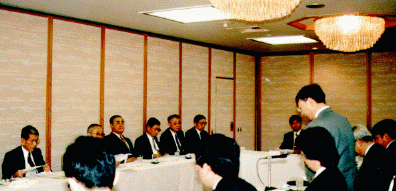
○ 講演会等/Lectures at NISTEP
○ 主要来訪者一覧/Foreign Visitors to NISTEP
○ 海外出張
○ 海外出張報告
第2調査研究グループ 岡本 信司
「生活関連科学技術課題に関する意識調査」及び「科学技術の公衆理解に関する国際比較研究」の一環として、豪州地域の研究機関、行政機関、博物館等の現地調査を実施した。産業科学技術省においては、豪州における科学技術に関する国民意識調査及び国際比較研究を実施した研究担当者に研究の詳細に関するヒアリングを行った。
この調査は、豪州国民の科学技術への関心や科学技術に関する用語の理解度、事例を挙げて真偽を質問する等のアンケート調査を実施して、各国の調査結果との国際比較を行ったものであり、最終的には3部からなる研究調査報告書にまとめられて、昨年6月に公表された。
当地の新聞記事によると豪州国民の科学技術に関する理解度が他の国に比較して非常に高いことが強調されている。
当初、私は調査手法等の信頼度について若干の疑問を持っていたが、ヒアリングの結果、かなり信頼性の高い調査であることが判明した。
産業科学技術省の研究担当者は、調査手法をはじめこの種の調査に関して非常に幅広い知識を持っており、豪州の研究ポテンシャルの高さを感じた。
ただ、残念なことに予算等の問題で今後の継続的な調査の計画はないとのことであった。
なお、本年11月にメルボルンにおいて、「科学技術のコミニュケーションに関する国際会議」の開催が予定されており、科学技術の公衆理解の国際比較研究を行っている各国の研究グループも参加を予定している。
連邦科学産業研究機構(CSRIO)においては、生活関連科学技術に関連して地球環境(地球科学技術)研究の調査を行った。
CSRIOは科学技術庁の地球科学技術調査研究促進費による「地球温暖化の原因物質の全球的挙動とその影響等に関する観測研究」の国際共同研究に参画している。
この研究は平成2年度から開始されており、豪州、米国、ニュージーランド等が参画して、国際学術連合(ICSU)が策定する「地球圏−生物圏国際共同研究計画(IGBP)」を構成する「地球大気化学国際共同研究計画(IGAC)」及び全球海洋フラックス国際共同研究計画(JGOFS)」等の国際プロジェクトと密接に連携している。
研究の内容は、地球温暖化に影響している大気微量気体及びエアロゾルに着目して、航空機、船舶等各種観測方法による大気中濃度の観測研究及びそれらの化学、放射特性を解明するための実験的研究を実施することにより、地球温暖化のメカニズムを解明するものである。
この研究において、CSRIOは西太平洋における航空機による観測を実施している。
豪州においては、観光資源としての環境保全等も含め地球環境問題に関する関心が非常に高く、今後の研究の進展が期待される。
また、科学技術の普及啓発活動に関連して、国立科学技術センター、パワーハウス博物館、オーストラリアン国立海洋博物館・シドニー海洋博物館等の調査を行った。
これらの博物館は、単なる展示のみでなく実際に体験したり直接触れたりすることができるコーナーが随所にあるところが特徴的であった。
このような博物館活動やTV番組を利用した普及啓発活動により、豪州国民の科学技術に対する興味・関心や理解度が向上したことは大変興味深い。
企画課 吉水 正義
近年東南アジア諸国において、科学技術政策研究を計画または実施する国が増加している。わが国がOECD加盟国等の科学技術政策研究実施国との研究協力等で実績があることから、これらの国々から共同研究及び研究者交流(当研究所の研究者の相手機関への派遣もしくは先方研究者の当研究所での研究滞在等)の要請が多い。こうした要請に応えるために、タイ、マレイシア、インドネシア、フィリピン各国において、該当機関の共同研究及び研究者交流受け入れ機関等の状況を調査した。
「タイ」では、タイ科学技術開発庁(NSTDA)が、当研究所へ技術予測の専門家派遣を要請しており、受入体制を調査した。日本から専門家を派遣した場合には、NSTDAが窓口となり、これに対応すべく人材を準備中である。また、NSTDAでは、これらの調査研究についての経験がないため、チェンマイ大学への依頼によりすでに技術予測の調査報告書を作成していた。その担当者が日本人専門家を派遣した場合のカウンターパートとなる。
「マレイシア」では、マレイシア科学技術情報センター(MASTIC)から技術予測をマレイシアで実施するための研究者(2名)が当研究所での研修を終了しているので、帰国後の研修成果の活用状況を調査した。当該研究者が技術予測調査を進めており、委託先との打ち合わせを行っていた。今後さらに質問票の作成及び集計後の解析といった具体的な作業が必要となる時点で、日本へ技術予測の専門家を要請したいということであった。
「インドネシア」では、共同研究の可能性についての意見交換を行った。インドネシア科学技術院(LIPI)では研究者が科学技術指標の研究その他について、日本での研修を計画しており、日本の研究機関(埼玉大学)と日本の関連機関(日本学術振興会)に接触し、回答待ちであるということであった。候補者は、LIPIの国際協力課長で、科学技術指標の他特許等知的所有権についても強い関心があり、日本滞在中に研究したいとのことであった。そのためか日本語を理解していた。
「フィリピン」では、技術予測の調査に係る専門家を当研究所に派遣依頼しており、受入体制を調査した。フィリピン科学技術省(DOST)が受入窓口となり、体制は、DOSTの筆頭局である計画評価局が中心となり、DOST及びその傘下の付属研究所からの人員構成となっていた。計画評価局では技術予測調査の実施と科学技術指標研究の計画があり、技術予測調査についてはすでに第1回目の質問票を発送していた。DOSTでは、タイミングとして、例えばこの集計が終わる頃に当研究所に専門家派遣を要請したいとのことであった。また、DOSTの付属研究所であるフィリピン工業技術開発院(ITDI)の研究者から、当研究所において「Human Resouces」についての研究滞在が可能かどうか聞かれた。
「おわりに」調査した4国のうち3国から技術予測調査に係る専門家派遣の要請があり、当研究所に対する期待の高さを感じた。国ごとに調査研究の準備状況に差があり、当研究所からの専門家を派遣した場合にも、相手国により、幅広い対応が必要であるようだ。また先方機関が、日本からの派遣専門家に、「なにをしてほしいのか」については、先方機関でもはっきりしたものがないように感じた。
総務研究官 林 光夫
3月13−20日中国北京、広州に出張し、科学技術政策研究関係機関などを訪問した。1、主な訪問先は、
2、中国では、従来、行政が生産計画を立て、国の研究所が設計開発を行い、企業が生産し、製品が配分される仕組みになっていたが、科学技術を経済の発展により以上に貢献させるため、市場ニーズを踏まえた競争を目指した改革が、1985年から実施されてきている。具体的には、1)国あるいは地方政府から研究開発部門に対する予算の支出を削減する代わりに独自性のある運営を認め、研究開発の成果については、研究開発部門自ら、あるいは、企業との契約で生産・販売し、利益については内部での配分を認める、2)研究開発部門の研究者には、兼職の立場で、企業を設立し、あるいは、運営に参画することを認める、3)技術の売買を認める、4)研究者には、本人の希望によって、より適性の発揮できる勤務先を選択できるようにする等の方策が採られている。この様な改革の中で、広東省においては、広く省外、外国から優秀な研究者を招聘するため、優秀な研究者に対して、車の提供、広い住居の支給などの措置を講じている。
3、広州においては、この様な改革に対応し成長をしているパソコンソフトの開発を行う企業、食品添加物の開発生産を行う企業を訪問したが、いずれも活気のある職場となっていた。ただし、パソコンソフトについては、中国語の特殊性(仮名、カタカナがない。発音の高低差により意味が異なる。地域差が大きい。事実、広州では、中国語のテレビに中国語の字幕が出ていた。)により、入力方式がいろいろあり、今後、入力方式が淘汰されていくことに対する不安が示された。また、同社が開発するレジスターには、ブラックボックスが設けられており、ここには、売買の記録が残されるが、購入者にはアクセスできず、税務当局のみが使用できる設計になっているとの事であった。
4、科学技術政策研究の面では、次のような話があった。