
 |
No.90 MAR 1996 | |
| 科学技術庁科学技術政策研究所 | ||
| NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE | ||
| AND TECHNOLOGY POLICY |
| 目次 [Contents] |  巻頭特集 Preface 巻頭特集 Preface |
 講演会紹介 Highlight of the Lectures at NISTEP 講演会紹介 Highlight of the Lectures at NISTEP | |
 用語解説 Technical Term 用語解説 Technical Term | |
 最近の動き Current Topics 最近の動き Current Topics |
 「イノベ−ション調査国際ワ−クショップ:専有可能性と技術機会」開催
「イノベ−ション調査国際ワ−クショップ:専有可能性と技術機会」開催
第1研究グループ
科学技術政策研究所は1996年 2月28日に日本科学技術情報センタ−会議場において、「イノベ−ション調査国際ワ−クショップ:専有可能性と技術機会」を開催した。当研究所では一昨年度よりイノベ−ションの実態に関する国際比較を目的として、欧米の大学、研究機関との共同研究プロジェクトを推進してきた。今回のワ−クショップは、この共同研究プロジェクトによる調査デ−タの報告とディスカッションを通じて、各国のイノベ−ション・システムに関する相互理解を深めるとともに、国際比較上の課題等を検討することを目的として開催したものである。当日は15カ国から約 100名の一般参加者を得て、活発な質疑応答が行われた。
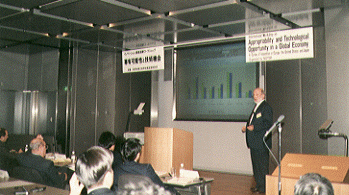
○各セッションの報告者
| セッション1.基調講演
Richard Nelson (Columbia University) セッション2.日本側調査結果の報告
後藤 晃 (科学技術政策研究所) セッション3.米国側調査結果の報告
Wesley Cohen (Carnegie Mellon University) セッション4.欧州側調査結果の報告
Anthony Arundel コメント Sidney Winter (University of Pennsylvania)
|
1.専有可能性と技術機会の概念
前述の共同研究プロジェクトは、1980年代にネルソン、ウィンタ−等が米国企業を対象として、 イノベ−ションの専有可能性 (appropriability)と技術機会 (technological opportunity)の実態を明らかにした画期的な調査の国際比較版としての性格を持っている。
専有可能性とは、企業が行ったイノベ−ション(新製品や新工程などの技術革新)から、その便益のどれだけを自ら獲得することができるかを意味する。専有可能性を確保できることは、企業の研究開発投資にとって重要なインセンティブである。ネルソン等は質問票調査によって、専有可能性を確保する手段には、特許による法的な保護の他に、先行的な市場化によるリ−ドタイム、技術情報の秘匿、補完的な販売・サ−ビス努力などのバラエティがあることを明らかにした。
また技術機会とは、企業の研究開発が効果的にイノベ−ションに結び付く機会を意味しており、例えば、関連する学問分野で次々に新しい技術知識が生み出されている時には、企業にとって豊富な技術機会が存在することが見出だされている。
2.調査結果の概要
今回の共同研究は日米欧においてほぼ同様の質問票を用いた調査を行い、上記の論点につき、国別・産業別の比較、検討を行おうとするものである。日本側調査では、資本金10億円以上で研究開発を行っている製造業の 1,219社が対象とされ、 643社の回答が得られた(回収率52.7%)。米国および欧州でも、大規模なサンプル調査が実施された。
以下では、日本側調査結果の概要を中心に、国際比較上のトピックを紹介する。
(1)研究開発活動の目的
日本企業の研究開発費がどのような目的のために投下されているのかを調査した結果によると、製品イノベ−ションを目的とする割合が約81%と高く、工程イノベ−ションを目的とする部分は約15%に過ぎない。この点は、従来マンスフィ−ルド等の欧米の研究者から、日本企業の研究開発は工程志向が強いと言われてきたこととは、逆の傾向を示している。むしろ絶え間ない製品開発努力が日本企業の強みであるとする説を、今回の調査は裏付ける結果となっている。
(2)専有可能性のメカニズム
日本企業においては、専有可能性を確保する方法として、製品イノベ−ションについては、製品の先行的な市場化や特許による保護が重視され、工程イノベ−ションについては、生産プロセスに関わる補完的な製造設備・ノウハウの保有や、技術情報の秘匿などが重視されている(図1)。
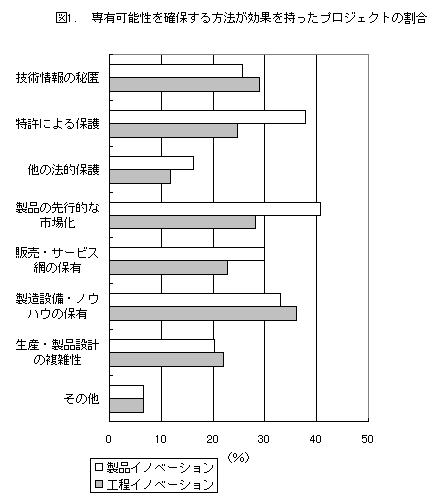
専有可能性のメカニズムにみられる製品イノベ−ションと工程イノベ−ションの相違は、つぎのように要約できよう。製品イノベ−ションの場合、製品に体化された技術情報がいずれスピルオ−バ−することは避けられない。そこで製品を先行的に市場化し、他社がキャッチアップしてくるまでの間に利益をあげることが重要となる。一方、工程イノベ−ションは生産設備に体化されているので、当該の設備を用いた生産プロセスに関わるノウハウを保有・管理することが重要となる。また、設備は製品と異なり社外へ出ることはないので、技術情報を機密にすることによって専有可能性を有効に確保できる。
この調査結果を米国デ−タと比較したところ、専有メカニズムの相対的な重要度に、いくつかの対称的な差が観察された。例えば、製品イノベ−ションの専有可能性を確保する上で、製品の先行的な市場化についで重要な方法は、日本企業においては特許であるが、米国企業では技術情報の秘匿の方が重視されている。また、米国企業では生産・製品設計の複雑性が、工程イノベ−ションの専有可能性を確保する方法としてかなり重視されているが、日本企業における重要度は低い。
但し、専有可能性を確保する上で特許は主要な方法の一つではあるが、必ずしも最も重要な方法ではないことを示唆する点では、いずれの調査結果も80年代の米国調査と整合的である。
この点に関連して今回の調査では、競合他社のイミテ−ションを遅らせる効果という観点から特許の有効性を捉えている。日本の調査結果によると、自社のイノベ−ションに対する他社の模倣ラグは、製品イノベ−ションでは特許化した場合2.63年、特許しなかった場合1.98年、工程イノベ−ションでは特許化した場合2.35年、特許化しなかった場合2.03年と評価されている。すなわち特許は、競合他社によるイノベ−ションの模倣を、製品については0.65年、工程については0.32年だけ遅らせる効果を持つ。概して特許の効果は、工程イノベ−ションよりも製品イノベ−ションにおいて顕著であると言える(図2)。
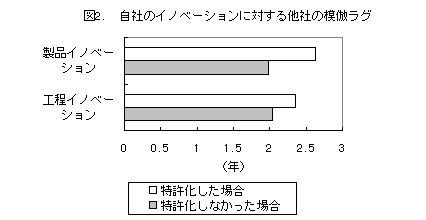
また、生み出されたイノベ−ションが、どの程度、特許出願の対象となっているかをみたところ、製品については約半数、工程については約 7割ものイノベ−ションが特許出願されていないという結果を得た。工程イノベ−ションの出願比率が極めて低いことの背景には、模倣ラグの効果が製品よりも短いという要因の他に、生産プロセスにはコ−ド化し難い暗黙知が多く含まれており、イノベ−ションの新規性を示すことが困難であるといった要因が影響しているものと考えられる。
(3)技術機会を生み出す情報源
ここでは技術機会に関連するデ−タとして、どのような情報源がプロジェクトの提案や遂行に役立ったかに関する調査結果をみる。
情報源としては、自社内のソ−ス(他部門)、当該企業が属する産業内部のソ−ス(競合他社)、垂直的な企業間関係の中にあるソ−ス(顧客や供給業者)、産業外部のソ−ス(大学等)といった様々なものが考えられる。日本の調査結果によると、新規プロジェクトの提案、既存プロジェクトの遂行のいずれについても、顧客から情報を入手したとする回答頻度が最も高く、ついで生産・製造部門や他の研究開発部門といった自社内のソ−スが活用されている。企業の研究開発において、市場や生産現場からの情報のフィ−ドバックが非常に重視されていることが窺える(図3)。
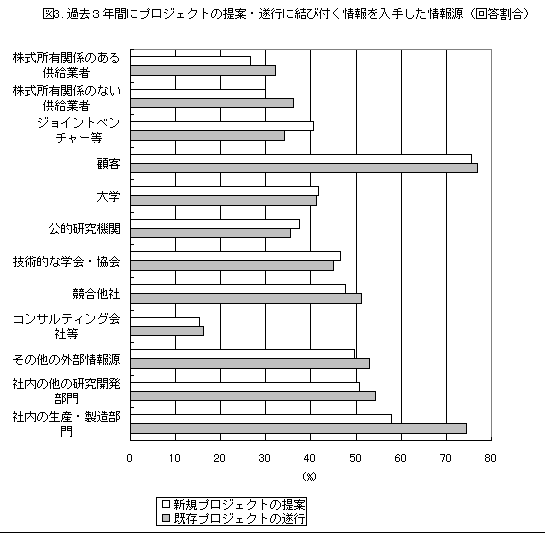
なお、米国側の報告によると、米国企業では新規プロジェクトの提案においては日本企業と同じく顧客および社内の生産・製造部門が情報源として活用されているが、既存プロジェクトの遂行では社内の生産・製造部門の情報が最も重視されており、これについで株式所有関係のない供給業者から情報を入手したとする回答割合が高くなっている。
3.今後の課題 以上に述べた点は、産業計のデ−タによる要約であるが、各デ−タには産業ごとの異なった特徴も見出されている。今回の国際比較に当っては、産業を35部門に分類したデ−タを用意している。それらは産業間の相違に配慮したイノベ−ションの促進策を立案する際に、有用な基礎情報を提供するであろう。
また、今後の研究課題としては、前述のように専有可能性を確保するメカニズムに国ごとの対称的な差異が存在する場合、そこにどのような要因(例えば市場の条件、企業の戦略、法制度等の相違)が影響しているのかを明らかにすること等が挙げられる。ウィンタ−のコメントによって指摘されたように、専有可能性を確保する方法は相互に排他的な関係にあるのではなく、複数の方法が補完的に用いられているものと考えられる。そのような専有メカニズムの相互関係を明らかにすることも、今後の重要な研究課題となろう。
 講演会紹介/Highlight of the Lectures at NISTEP
講演会紹介/Highlight of the Lectures at NISTEP
「仏国 ルイ・パスツール大学付属ベータ研究所の概要」について

【はじめに】文学や哲学を通じて知っていた日本に、2週間半の間滞在できたことに感謝します。 日本(東京)の印象は、小さい店や親切な人々が住んでいるすぐ近くに、大きな近代建築があるというように、伝統的なものと近代的なものとが混在していることです。また、混雑している電車の中でも皆さん礼儀正しく、優しく、攻撃的でないところに感激しました。
【ベータ研について】ベータ研は大学に付属する研究所ですので、教育に係る業務と、研究に係る 業務の両方があります。政策研は、静かな環境で研究業務に没頭できるので、このような日本の組織を羨ましく感じます。研究活動については、企業レベルと国レベルの研究開発の経済学、予測方法、科学技術の評価、さらには、科学技術関連の公共施策及び計画の評価研究については共通しています。特に国レベルの研究については、政策研が優れ、地域レベルでは、ベータ研の方が進んでいると思います。ベータ研には6の研究グループ、マクロ経済学、数理経済学及び計量経済学、革新技術の経済学、科学技術の管理学、労働技術及び雇用の経済学、並びに経済哲学及び経済史があります。研究発表の面では、かなりの成果を挙げています。
【外国機関との連携】ベータ研が政策研と研究協力を行っているように、政策研の研究協力の相手である、ドイツのフラウンフォーファー協会(ISI)といくつかの共通の研究計画について、関係を深めています。その他、イギリスのSPRU、オランダのマーストリヒト大学(MERIT)が挙げられます。デンマーク、イタリア、ベルギーとも協力関係がありますが、これらは、数理経済学での研究協力です。大学関係では、米国とで教授の交流が盛んに行われています。
【研究成果について】欧州の科学技術計画(欧州宇宙機関における宇宙開発プロジェクト)の経済 的波及効果についてベータ研のグループが行った評価結果を説明します。
第1目標は、参加した企業内で新しい知識が生まれ、企業のネットワークができること。第2は、欧州内で研究開発の協力体制を築くことにより、団結が促進すること。第3は、より恵まれない国を支援するために国境を越えて知識や能力を普及させることでした。ルイ・パスツール大学はこれらについて、聞き取り調査をしました。
プロジェクトで得られた第1の成果は、納税者が人工衛星の研究に1ECU を支払ったとすれば、数年後に人工衛星の1ECU 分を得ることとなります。(計画が約10年進行した段階で、少なくとも3ECUに相当するスピンオフをもたらす。) 第2は、スピンオフやその他の形により欧州内での共同研究成果を得る。企業レベルでの技術進歩や、人的資本の改善、国際市場における商業イメージ等々。第3は、相対的に恵まれない国や小企業への技術や能力の移転については、4種類の経済的利益、すなわち、新製品、新工程等の技術的効果、商業的効果、組織に関する効果及び人的資源に関する効果を観察したことです。(以上)
本記事は、平成8年2月1日に当研究所で行われた平成7年度科学技術関係外国人研究者招へい制度により招へいしたフランス ルイ・パスツール大学教授・附属ベータ研所長 Jean Alain Heraud 氏の講演より抜粋した。
FUGIグローバルモデル
第4調査研究グループ
NISTEP REPORT No.27「アジア地域のエネルギー利用と地球環境影響物質(SOx,NOx,CO2)排出量の将来予測」では、アフガニスタン、パキスタン以東のアジア25ケ国を対象に、同地域でのエネルギーの将来予測と各国での将来における環境対策の想定を行い、両者の組み合わせにより、西暦2000年、2010年における地球環境影響物質の排出量を推計している。本調査研究では、このエネルギー消費量の将来予測にあたって、エネルギー消費が経済活動と連動していることから、経済活動と連動した形での比較が可能となるようにグローバル経済モデルを用いることとし、第6世代のFUGIグローバルモデル6.0(M62)を用い算定を行ったところである。このFUGIグローバルモデルのFUGIとは、Future Of Global Interdependenceの意であり、1977年に大西・茅・鈴木氏によりIIASA(国際応用システム研究所)のグローバル・モデル・シンポジウムに発表された第1世代のFUGIモデルの発展したものである。第1世代のFUGIモデルは、世界全域を15地域に分類し、方程式の数も約1,800本であったが、この第6世代モデルは、世界を180国・地域に分類しており、方程式の数も約35,000本にのぼる大規模なモデルである。FUGIモデルは、それぞれの国ないし地域モデルが複雑な国際的相互依存関係を通して互いにリンケージしている本格的なグローバルモデルであり、1981年以来国連の国際経済社会予測展望部での世界経済の長期予測や国連の開発戦略の予測シュミレーションに用いられてきた実績がある。
FUGIモデルは、前述の通り世界を主要な国・地域に分類し、それぞれの国ないし地域が互いに貿易、国際金融、物価等の複雑なネットワークを通じて地球的な相互依存関係を形成しているとするところに構造的特質があり、ここに用いられる各国モデルは全て共通ということではなく、先進市場経済タイプ、発展途上市場経済タイプ、計画市場経済タイプという大きな3つのカテゴリーに分けられている。各国別モデルは、さらに、①環境、②開発(経済)、③平和と安全保障、④人権といったサブシステムから成り、労働力と生産、GDPの支出構成、所得分配、物価、金利、国際収支、外国為替等主要な変数は、経済モデルの中にほとんど網羅されている。
このFUGIモデルは、さらにグレード・アップが図られ、現在では第7世代モデルが構築され稼働中である。ますます精度の高い各種シュミレーションが可能であり、その有効的な活用が期待されている。
○ 研究会等/Research Meetings
・2/23(金) 地球環境保全技術の進歩に関する調査研究会
○ 主要来訪者一覧/Foreign Visitors to NISTEP
・1/18〜2/2 Dr.Jean Alain HERAUD (仏国 ルイ・パスツール大学付属ベータ研究所長)
・2/20〜2/26 Ms.Kerstin Cuhls (独国 フランフォーファー協会システム技術革新研究所)
○ 海外出張
・2/18〜2/25 前田情報分析課長(米国)
・2/25〜3/8 丹羽研究所付(米国)
・2/25〜3/8 岡本第2調査研究グループ上席研究官(豪州)
・2/25〜3/10 渡辺第3調査研究グループ総括上席研究官(東南アジア)
○ 海外出張報告
情報分析課 前田 義幸
米国における先端科学技術動向及びネットワークに関する新環境についての状況を以下の機関において調査した。
RAND クリティカル技術研究所
国立科学財団 ネットワーク・コミュニケーション部
スタンフォード大学工学部日米技術経営研究センター
サンマイクロシステム ソラリスプロダクト