

 |
| 今村 努 科学技術政策研究所長 |
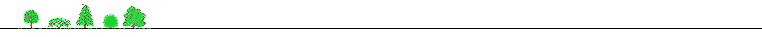
8月1日付けで科学技術政策研究所長に就任いたしました今村努です。
複雑化・高度化する社会・経済の構造的変化の中で、科学技術の果たすべき役割は益々増大しております。我が国においても、二期にわたる「科学技術基本計画」の策定、中央省庁再編に伴う新たな科学技術行政体制の発足、公的研究機関や国立大学の法人化などいわば「大変革」の時代を迎えております。こうした時期に、将来の経済・社会の発展に資する科学技術政策立案の重要な一翼を担う研究所長に就任したことは、私にとりまして身の引き締まる思いで一杯です。
これまで私は、主として原子力・宇宙開発などの大規模かつ国家的な研究開発プロジェクトの推進に永年にわたり携わってきました。これらの研究開発においては、将来の経済・社会のニーズを十分に見据え、先見的かつ総合的な視点から研究開発を進めることに加え、グローバルな視点からのアプローチも重要なポイントとなっています。昨今の報道では、我が国の国債の格付け引下げ、IMD(国際経営開発研究所)の国際競争力ランキングで日本が30位にダウン、と我が国の将来性に対する世界の厳しい見方を象徴するようなデータが伝えられていますが、科学技術面では依然として世界第一級の水準を保持していることは心強い限りです。
1988年、科学技術庁傘下の研究所として発足した当研究所は、歴代所長やスタッフ各位のご尽力もあり、技術予測、地域科学技術振興、理工系人材育成など、将来の我が国に「元気」を与えてくれる科学技術政策の展開をリードする重要な成果を上げてまいりました。当研究所の役割は、今日のように将来の見通しが不透明な「大変革」の時代にあって、こうした変革が何によってもたらされたのか、将来採るべき進路はいずれか、といった問いかけに対し、誰も知らない「答え」を書いていくことではないでしょうか。そしてこのことこそが、昨年9月に間宮前所長の指導の下策定された「中期計画」に目標として示された「世界第一級の中核的研究機関」のあるべき姿であると私は考えています。
当研究所が発足して14年になりますが、科学技術政策研究はまだまだ歴史の新しい分野であり、解決すべき課題やアプローチ手法も広範かつ多岐にわたります。私といたしましては、これまで科学技術政策研究に携わり、礎を築いて来られた諸先輩方の成果に立脚し、益々発展させることができるよう、所員と一体となって微力ながら充実した研究環境の整備等に全力を尽くす所存でございます。今後とも引き続き皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。
 I. 海外事情
I. 海外事情 |
| うつのみや ひろし 2000年8月より科学技術政策研究所 第4調査研究グループ(現 科学技術動向研究センター)特別研究員。2002年8月より九州電力(株)エネルギーソリューション部 ガス事業グループ勤務 |
下田客員研究官(東京工業大学フロンティア創造共同研究センター教授)と筆者は、去る5月16日にフィンランドのヘルシンキで開催されたVTT(国家技術研究センター: Technical Research Center of Finland)主催の「Flower Day Seminar(日本とフィンランドの発展における産業革新、経済実績及び技術予測の比較による展望に関するセミナー)」に参加した。その後、5月17日にVTT研究者等との間で「技術予測における日本・フィンランドの相互協力に関するワークショップ」が開催された。
「Flower Day Seminar」では、主に3つの講演が行われた。フィンランドでは、国家レベルのイノベーション研究として、貿易産業省の下部機関のVTTで「Sfinnoプロジェクト」が実施された。最初の講演では、VTT技術研究グループPalmberg上席研究官から、「フィンランドのイノベーションの起源、性質及び成功」と題してその成果の概要が紹介された。次に下田客員研究官から、「日本におけるイノベーション科学技術政策及び技術予測」について講演が行われた。最後に、フィンランド科学技術政策会議事務局のチーフプランニングオフィサーHalme氏から、前述の2つの講演を踏まえ、「日本とフィンランドの発展における政策の展望」について講演が行われた。
このワークショップでは主に、1)共同セミナーや国際会議を通じて研究成果やベンチマーク等の情報交換を積極的に推進していくこと、2)JSPS(日本学術振興会)フェローシッププログラム等を活用して人材交流を積極的に実施すること、など日本・フィンランドの相互協力における今後の目標及び形態について意見交換を行った。
現在、フィンランドは、従来から技術的優位にあった木材加工産業に加え、情報・通信関連のハイテク産業においても、高い技術力をもつ国となっている。フィンランドの経済基盤はこれら産業に大きく依存しており、近年、次期産業創出の目的で、国家レベルによる技術予測を推進する必要性が高まっている。今後、同国においては技術予測調査が科学技術政策や技術開発計画の立案に当たっての有効なツールとしてますます利用されることが予想される。当研究所が、平成13年7月に対外発表した第7回技術予測調査は同国でも高い関心を呼んでおり、国際協力強化の観点から、この分野での日本の果たすべき役割は大きいと感じた。
 II.レポート紹介
II.レポート紹介 |
| おだぎり ひろゆき 筑波大学教授、一橋大学教授を経て、2001 年 4 月より科学技術政策研究所第一研究グループ総括主任研究官。一橋大学大学院経済学研究科教授併任。専攻は産業組織論・企業経済学・技術革新の経済学。著書として、『日本の企業進化』(後藤晃氏と共著、1998、東洋経済新報社)、『企業経済学』(2000、東洋経済新報社)、『新しい産業組織論』(2001、有斐閣)など多数 |
2000年6月26日、クリントン米大統領(当時)出席のもと、米国立衛生研究所(NIH: National Institutes of Health)のコリンズ博士とアメリカ民間企業セレーラ・ジェノミクス社のベンダー博士が共同でヒトゲノムの全貌を明らかにしたと宣言した。この発表が大きな反響を呼んだのは、もちろん、ヒトゲノムの全体像を人類史上初めて明らかにしたという技術的意義によるが、さらにわれわれを驚かしたのは、その当事者の一方が民間企業であったという事実である。1980年代からのアメリカでのいわゆるプロパテント(特許強化)政策により特許による専有可能性が拡大されてきたとはいえ、ヒトゲノムのような基本的情報を民間企業が開発・供給するというビジネスが成立しうるという事実は多くの人々にとり驚きであった。
さらに驚きであったのは、この企業が1998年に設立されたばかりのいわゆるバイオ・ベンチャー企業であったことである。ヒトゲノム解読については、当初は米国立衛生研究所を中心とした公的研究機関がプロジェクトを進めてきたが、途中から参入したセレーラ社が大量の資金を市場から獲得し、精力的に解読を進め、一時は国際ヒトゲノム計画プロジェクトを凌駕する勢いであった。この 1 例はバイオテクノロジーのようなハイテク産業におけるベンチャー企業の重要性を如実に示している。
しかし、バイオ・ベンチャー企業については日米格差が大きい。ベンチャー企業とは何を指すか、バイオテクノロジー関連企業として何を含めるかについて統一的な基準がなく、厳密な日米比較がなされてきたとはいえないものの、いくつかの事実はアメリカに対しての日本のバイオ・ベンチャー企業の存在の小ささを裏付ける。例えばその数は、米国の約1,300社に比べ、日本では200社ともいわれる。また、特許出願動向によって日米のバイオ基幹技術における出願人の種別による出願比率をみると、日本人による日本への出願のうちベンチャー企業が11%を占めるのに対し、米国人による米国への出願のうちベンチャー企業は30%を占める。このため、筆者が科学技術政策研究所ディスカッション・ペーパー No.19で明らかにしたように、日本の大手製薬企業も、技術導入先・提携先として、アメリカのバイオ・ベンチャー企業を多用しているのが実情である。
しかし、バイオテクノロジーのような科学知識の発展と密接に結びついたサイエンス型産業においては、ベンチャー企業が産学官連携の要として効果的な役割を果たすと期待される。大学に密接につながりを持つ基礎研究重視の企業文化、科学技術の進歩に対応して柔軟に修正できる研究体制、研究成果が研究者の報酬や名声につながるインセンティブ・メカニズム、などを大企業で維持するのは難しい。しかも、規模の経済性の役割の縮小、アウトソーシングなど外部資源活用の余地の拡大、ベンチャービジネスへの資金調達ルートの多様化と拡大、国立大学教官の兼業規制の緩和などにより、ベンチャー企業で研究事業を繰り広げることへの障壁も緩和されてきた。
よって、ベンチャー企業はバイオテクノロジーにおける新たなイノベーションの起爆剤の役割を果たすものと期待され、その日米格差は日本の関連産業の発展に対して致命傷となりかねない。こうした問題意識から、筆者は経済産業研究所の中村吉明研究員と共同で、日本のバイオ・ベンチャー企業をいくつか選んで、面会方式で質問表に基づいてインタビューをおこなった(なお、この調査においては経済産業省生物化学産業課の協力を得たことを記して感謝したい)。また、調査結果を、科学技術政策研究所が1999年に実施し2000年にとりまとめた「日本における技術系ベンチャー企業の経営実態と創業者に関する調査研究」(調査資料-73)とも比較した。
質問票調査において「起業時の障害」として多くあげられたのは、「スタッフの確保(研究者・技術者)」と「資金調達」という人的及び資金的資源の獲得の困難さであった。スタッフについては、研究開発を主導的におこなえる博士号取得者に対するニーズが高いにもかかわらず、これらの研究者は大学及び大手企業の研究機関等に偏在しており、ベンチャー企業での採用を困難にしている。米国に比較してバイオ関係で博士号を取得する人間が少ないことや、企業においても大学においても労働の流動性が低いという日本の雇用慣行が、ベンチャー企業の設立・育成に対してマイナスに働いている。
資金調達については、支援施策として「研究開発補助金の充実」や「事業資金補助」が期待されている。しかも、量的な支援とともに、補助金執行の柔軟性の確保と事務的煩雑さの解消が多くあげられた。このほか、生物学的実験をおこないうるような実験室(ウェットラボ)を備えた入居先不足や財務・会計、法務等のスタッフ不足も起業時の障害となっている。アメリカでは、これら業務についての経験者が豊富で流動性が高く、また起業時にベンチャー・キャピタルが人材を紹介することも多いため、スタッフ確保に問題が少ないのに対し、日本では、この関係の修士や博士の学位を取得した人員が少ないことに加え、財務・会計を専門としている者が大企業等に偏在しており、流動性が低いことが起業への障害になっている。特に知的財産権関連では、バイオテクノロジー分野に精通しており、海外や国内の特許訴訟にも十分に対応できるような弁理士の絶対数が少ないことが、バイオ・ベンチャー企業、特に地方のバイオ・ベンチャー企業にとっての悩みとなっている。
このように、日本のバイオ・ベンチャー企業の環境は未整備であり、雇用や金融のシステムなど社会的・経済的な制度や慣行に依存しているところも多いため、一朝一夕に改善することは難しい。しかし、資金供給制度、税制、年金制度、教育制度などの改革により政策的に対応できるところが多いことも確かであり、今後一層の実態把握と政策的対応が進められなければならない。
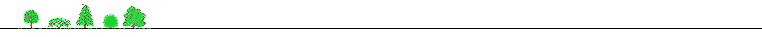
 |
| おじま のりお 1981年科学技術庁入庁。政策研企画課長、資源エネルギー庁統括安全審査官、 国際原子力機関原子力エンジニア等を経て、2000年6月から2002年7月まで、 政策研第一調査研究グループ総括上席研究官。 2002年7月より理化学研究所RIビームファクトリー計画推進本部。 |
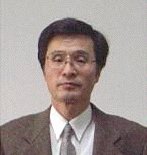 |
| すずき けんいち 2001年4月より任期付研究官として民間から採用。 専門分野は有機合成化学、原子力工学、環境化学。 現在の担当領域は科学技術系の人材育成。 |
第 2 期科学技術基本計画において、我が国が目指すべき姿として「知の創造と活用により世界に貢献する」との基本理念が掲げられた。
この理念を達成するに当たっては、ノーベル賞に代表される国際的科学賞を受賞できる程度の力量を備えた研究者(本報告では「国際級研究人材」と言う。)の育成・確保が急務である。そのためにはまず、このような人材が世界各国にどのように分布しており、我が国がどのような位置付けにあるかを明確にし、然る後にこのような人材がどのような教育環境・研究環境で最も良く育成されるかを調査し、効果的な育成・確保方策を構築していく必要がある。
このような考えの下、①国際的科学賞受賞者数、②国際的科学アカデミーの外国人会員数及び③論文被引用度世界ランキングの分析に基づき、国際級研究人材の国別分布及び我が国の位置付けを明らかにしようとした。
その結果を、我が国と欧米主要国との比較の形で示すと、以下のとおりである。
| 比率 | |||
|---|---|---|---|
| 国際的科学賞 | アカデミー会員 | 論文被引用度 | |
| 日本 | 1 | 1 | 1 |
| アメリカ | 10.4 | 9.5 | 5.9 |
| イギリス | 1.7 | 2.5 | 1.0 |
| フランス | 0.9 | 1.3 | 0.2 |
| ドイツ | 0.8 | 1.0 | 0.4 |
単純比較では、日本を1とすると、アメリカは 5.9 〜 10.4 倍、イギリスは 1.0 〜 2.5 倍、フランスは 0.2 〜 1.3 倍、ドイツは0.4〜1.0倍となり、幅はあるものの、アメリカが飛び抜けたトップの座にあり、イギリスが日本の上、フランスとドイツが日本と同程度と推察される。
なお、参考として人口あたりの比率を以下に示す。
| 人口あたりの比率 | |||
|---|---|---|---|
| 国際的科学賞 | アカデミー会員 | 論文被引用度 | |
| 日本 | 1 | 1 | 1 |
| アメリカ | 4.9 | 4.5 | 2.8 |
| イギリス | 3.7 | 5.4 | 2.1 |
| フランス | 1.9 | 2.8 | 0.4 |
| ドイツ | 1.3 | 1.5 | 0.6 |
人口あたりで見れば、アメリカは日本の2.8〜4.9倍となり、飛び抜けた優位性は見られなくなるものの、それでもトップの座は変わらない。一方欧州の評価が上がり、イギリスは2.1〜5.4倍、フランスは0.4〜2.8倍、ドイツが0.6〜1.5倍と日本を少しリードしていることになる。
3 種類の評価の中では、論文被引用度の値で日本が相対的に高く評価されている。このことは、国際的科学賞受賞者及び国際的科学アカデミーの外国人会員が、既に業績評価の固まった人を対象としているのに対し、論文被引用度は比較的最近の研究成果を反映しているものであることから、過去よりも最近の方が、日本人研究者のレベルが上がってきていると捉えることも可能かも知れない。しかし、このことについて確たることを言うには、当然のことながら今後さらなる調査研究が必要である。
 III.最近の動き
III.最近の動き| ・8/1 | 所長 間宮 馨(新所属: 文部科学省文部科学審議官) |
| ・8/1 | 〃 今村 努(旧所属: 文部科学省研究開発局長) |
| ・7/3 | Mr. Hartmut Krebs: 独国NRW(ノルトライン・ヴェストファーレン)州教育科学研究省次官 |
| Ms. Martina Munsel: 同省国際課日本担当 | |
| Ms. Astrid Becker: (株)エヌ・アールダブリュージャパン代表取締役社長 | |
| Ms. Regine Dieth: 同社プロジェクトマネージャー | |
| ・7/19 | Dr. Norman Neureiter: 米国科学技術担当国務長官顧問 |
| Mr. Kevin K. Maher: 在日米国大使館科学技術・環境担当公使 | |
| ・7/22 | Dr. Ziqi Liao: 東京大学丹羽清研究室外国人客員研究員(客員教授) |
| ・7/5 | 「革新的原子力技術とその開発体制」 |
| 鳥井 弘之: 東京工業大学原子炉工学研究所教授 | |
| ・7/18 | 「我が国大学における生命科学の研究と教育推進の危機的状況」 |
| 柳田 充弘: 京都大学大学院生命科学研究科長・教授 | |
| ・7/25 | 「バイオリソースの現状と我が国の方策」 |
| 小原 雄治: 国立遺伝学研究所副所長・生物遺伝資源情報総合センター長 |
| ・ | 「国際級研究人材の国別分布推定の試み」(調査資料 - 87 2002年7月) |
| ・ | 「日本のバイオ・ベンチャー企業 - その意義と実態 -」(DISCUSSION PAPER No.22) |
| ・ | 「The Role of Overseas R&D Activities in Technological Knowledge Sourcing: An Empirical Study of Japanese R&D Investment in the US」(DISCUSSION PAPER No.23) |
| ・ | 「科学技術動向 2002 年 7 月号」(7 月 29 日発行)
|
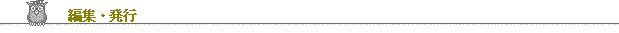
文部科学省科学技術政策研究所広報委員会(政策研ニュース担当: 情報分析課 news@nistep.go.jp)