政策研ホームページへ
 | No.154 2001 8
|
文部科学省 科学技術政策研究所
NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY POLICY
|
遠山文部科学大臣を迎えて政策研の紹介をする間宮所長
| 目次 [Contents]
|
|
| 
| Ⅰ.レポート紹介
| 地域における科学技術振興に関する調査研究(第5回調査) −NISTEP REPORT No. 70 −
第3調査研究グループ主任研究官 柿崎文彦
|
|
| 
| Ⅱ.海外事情
| 科学技術統計の整備をめぐる動向 ― フラスカティ・マニュアル改訂を中心に ―[後編]
第2研究グループ主任研究官 富澤宏之
|
|
| 
| Ⅲ.最近の動き
|

Ⅰ.レポート紹介
地域における科学技術振興に関する調査研究(第5回調査) −NISTEP REPORT No. 70 −
第3調査研究グループ主任研究官 柿崎文彦
 地方公共団体(都道府県及び政令指定都市)は、地域における科学技術振興の重要な担い手となっている。本調査研究は、地域における科学技術振興施策を体系的に把握することを目的に、平成2年度より概ね2年ごとに実施しているもので、今回が第5回となっている。
1.調査方法
平成11年度(1999年度)において、地方公共団体が実施した科学技術に関連する事業、及び経費の決算額をアンケート調査により把握した。今回の調査では、国庫支出金、施設整備費、公設試験研究機関等における研究課題等の評価を新たに調査項目に加えた。
2.調査結果の概要
(1)科学技術行政の総合的推進
都道府県の9割以上に相当する45団体において、①科学技術政策専任部署の設置、②行政部内の協議会等の設置、③科学技術会議等の設置、④基本計画等の策定、のいずれかが実施済みとなっており、地方公共団体において科学技術行政の推進するための体制の整備は進展している。
(2)科学技術関係経費の構造
地方公共団体(都道府県及び政令指定都市)は、地域における科学技術振興の重要な担い手となっている。本調査研究は、地域における科学技術振興施策を体系的に把握することを目的に、平成2年度より概ね2年ごとに実施しているもので、今回が第5回となっている。
1.調査方法
平成11年度(1999年度)において、地方公共団体が実施した科学技術に関連する事業、及び経費の決算額をアンケート調査により把握した。今回の調査では、国庫支出金、施設整備費、公設試験研究機関等における研究課題等の評価を新たに調査項目に加えた。
2.調査結果の概要
(1)科学技術行政の総合的推進
都道府県の9割以上に相当する45団体において、①科学技術政策専任部署の設置、②行政部内の協議会等の設置、③科学技術会議等の設置、④基本計画等の策定、のいずれかが実施済みとなっており、地方公共団体において科学技術行政の推進するための体制の整備は進展している。
(2)科学技術関係経費の構造
- 平成11(1999)年度に、都道府県及び政令指定都市において支出された科学技術関係経費(決算ベース)は約7,840億円で、平成9(1997)年度の前回調査に比べ約9%の減少となっている。
- 地域の財政支出額の総額に占める科学技術関係経費総額の割合は、都道府県で1.3%、政令指定都市で1.0%、全国平均では1.2%となっている。前回調査では、それぞれ1.4%、1.1%、1.4%となっている。なお、平成11(1999)年度において、地域の財政支出額は64兆5,437億円で、前回調査時の62兆987億円から3.9%の増加となっている。
- 事業性格別に科学技術関係経費を見ると、公設試験研究機関の約3,598億円(総額の約46%)、理科系高等教育機関の約2,616億円(総額の約33%)等となっている。前回調査と比べると、それぞれ約9%、約12%の減少となっている。
- 科学技術関係経費に占める国庫支出金の総額は約397億円で、科学技術関係経費総額の約5%となっている。事業性格別には、公設試験研究機関に約230億円(国庫支出金総額の約58%)、理科系高等教育機関に約65億円(国庫支出金総額の約16%)等となっている。
- 科学技術関係経費に占める施設整備費の総額は約1,354億円で、科学技術関係経費総額の約17%となっている。事業性格別に見ると、公設試験研究機関に約558億円(施設整備費総額の約41%)、理科系高等教育機関に約490億円(施設整備費総額の約36%)等となっている。
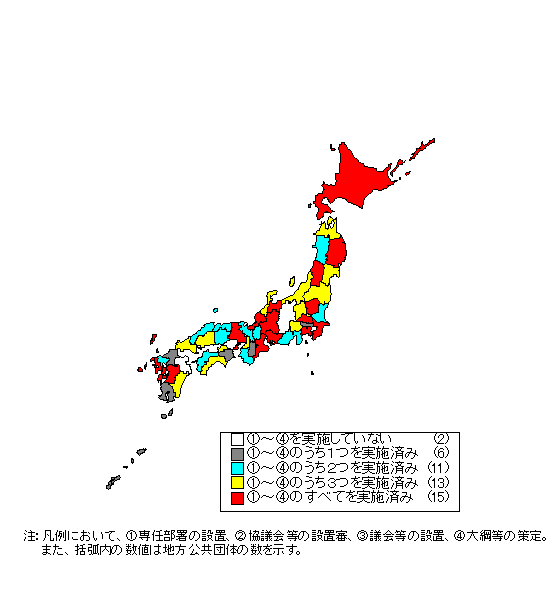
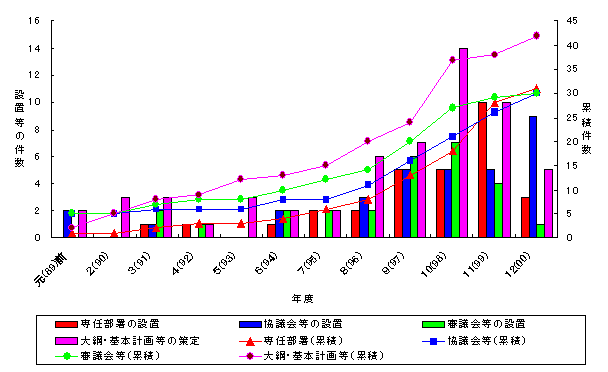
(3)経常的な科学技術関係経費
- 科学技術関係経費総額から、公設試験研究機関の再編整備、あるいは理科系高等教育機関の新設等の施設整備費を差し引くと、地域において研究活動等のために経常的に支出される経費と位置付けることができる。
- 地域の経常的な科学技術関係経費総額と人口規模を比較すると、概ね人口の多い都道府県において科学技術関係経費が多くなる傾向が見られる。一方、人口1人あたりの科学技術関係経費は、人口1人あたりの県内総生産に比べ偏差が大きくなっている。
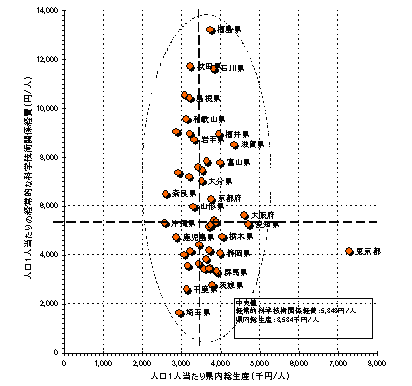
(注)政令指定都市の所在する道府県のデータは、政令指定都市との合計になっている。
(4)公設試験研究機関における研究課題評価等の実施状況
目次へ

Ⅱ.海外事情
海外最新動向:
科学技術統計の整備をめぐる動向 ― フラスカティ・マニュアル改訂を中心に ―[後編]
第2研究グループ主任研究官 富澤宏之
 現在、研究開発統計の調査方法や各種定義について定めたOECDのフラスカティ・マニュアルの改訂作業が約10年ぶりに行われている。同マニュアルの改訂項目は科学技術に関する様々な動向を反映している点で興味深いため、前号に引き続き、本年5月に開催された会議の模様を中心に、関連する動向を報告する。
(5) 各種の分類と調査手法
今回の会合では、研究開発統計における様々な分類の見直しについての検討に多くの時間が割かれた。(以下は主要項目)
現在、研究開発統計の調査方法や各種定義について定めたOECDのフラスカティ・マニュアルの改訂作業が約10年ぶりに行われている。同マニュアルの改訂項目は科学技術に関する様々な動向を反映している点で興味深いため、前号に引き続き、本年5月に開催された会議の模様を中心に、関連する動向を報告する。
(5) 各種の分類と調査手法
今回の会合では、研究開発統計における様々な分類の見直しについての検討に多くの時間が割かれた。(以下は主要項目)
- 科学分野分類の見直し
従来からの大分類(6大分野)は維持しつつ、中分類についてのみ見直しをすることとなり、今後タスク・フォースを設けて議論を進めることとなった。
- 社会経済目的分類の見直し
現行の分類を維持することとし、EU の分類であるNUTS の改訂を受けて将来的に改訂することで合意された。今後タスク・フォースを設けて議論を進めることとなった。
- 産業セクタの分類
複数の産業に属している多国籍企業の産業分類の問題点が議論された。各企業を1つの産業に分類してしまうと産業分類のブレが大きくなるが、事業所単位に調査することによりその問題を回避でき、地域別データも正確に把握できるとの意見も出された。しかし結論として、統計単位を企業単位とするこれまでの基準は変更しないこととされた。
- 製品分野分類
従来より製品分野別データの重要性はマニュアルに示されていたが、今回、調査の方法論上の問題点や、研究開発費に加えて研究者数データを収集する必要性が議論された。研究者数の調査については、回答者の負担等のため実施は困難であるとの意見が出された。その他、データ収集の負担についての整理がなされ、調査方法については今後の検討課題とされた。
(6) 調査の方法論
国際比較可能性を向上させるため各国共通の標準的な調査方法論を開発すること及び産業部門について標準的質問票を開発することについて提案がなされた。標準的な調査方法論については、①継続的又は臨時的に研究開発を行っている企業は、すべて調査対象とすること、②一定の産業分野(10の産業分野)を調査対象とすること、③少なくとも従業員数10 人以上の企業を調査対象とすること、などが合意された。
また、産業部門における標準的質問票の開発については、重要な課題との認識で一致したものの、今回の改訂では扱わず、タスク・フォースを設置して議論を続けることとされた。
(7) 研究開発協力の指標の開発
米(NSF)より、研究開発協力(R&D co-operation)に関する指標について、特に「戦略的な研究協力」(SRP: strategic research partnerships)に関する指標をマニュアルに含めるべきかとの提案が行われた。これについてはマニュアルに含めることは時期尚早であるとされ、今後、タスク・フォースを設けて検討を進めていくこととなった。
(8) 改訂作業の今後のスケジュール
- 2001年9月中旬:リード国の草案提示
- 2001年10月24日-25日:リード国による会合
- 2001年11月−2002年3月:コンサルタントによる新しい草案の作成
- 2002年6月末:NESTI会合において新しいマニュアル案の提出
- 2002年秋:科学技術政策委員会において採択のための新しいマニュアル案の提出
3. OECDにおけるその他の関連動向
フラスカティ・マニュアル改訂会合に引き続き開催されたNESTI会合では、イノベーション活動の測定に関する国際的な基準を定めたオスロ・マニュアルの改訂を来年以降行うことが決定された。また、NESTIが関係する最近の活動として、特許の国際比較性向上を目指してOECDが開発に取り組んでいるパテント・ファミリー(Patent Family)の指標や、バイオテクノロジー統計に関する取組、科学技術人材の国際的な流動性に関する取組、欧州委員会を中心に実施されているベンチマーキング活動等について紹介が行われた。
欧州圏においては、欧州委員会を中心として調和のとれた統計データの収集や、指標の開発及び分析活動が実施されており、これらの活動を通じて密な情報交換を図るとともに、データの共通化に向けた取組が行われている。また、米国においても、新たな指標の開発を行うなど、科学技術指標への積極的な姿勢が感じられる。
4. 最近の世界的動向についての歴史的理解
以上、OECDのフラスカティ・マニュアル改訂会議およびNESTI会合の概要を述べたが、本稿の冒頭(前号)でふれたように、科学技術統計・指標の拡充や見直しは世界的に進行している。これは明らかに科学技術統計・指標に対するニーズの高まりの反映であるが、その背景には、科学技術政策の重要性の増大と質的変化があり、さらには科学技術自体の大きな変化や冷戦終結といった科学技術政策を巡る状況の変化が背景となっていることを忘れてはならない。特に、国際競争の激化、グローバリゼーションの進展、ITを軸としたイノベーションが与えた大きなインパクト、などの変化と関連付けて、最近における科学技術統計・指標の拡充・見直しの状況を理解することが重要である。
このような理解を深めるために、歴史的な流れについて理解しておくことは有用である。下記の表は、OECDの科学技術政策委員会の第75回会合(2000年10月12-13日、パリ)に提出された資料より引用(原文は英語)したものであるが、過去50年間ほどに科学技術指標がどのように進展してきたかが示されている。特に90年代に科学技術指標の種類や対象範囲がそれまでに比して著しく拡大したことがよくわかる。
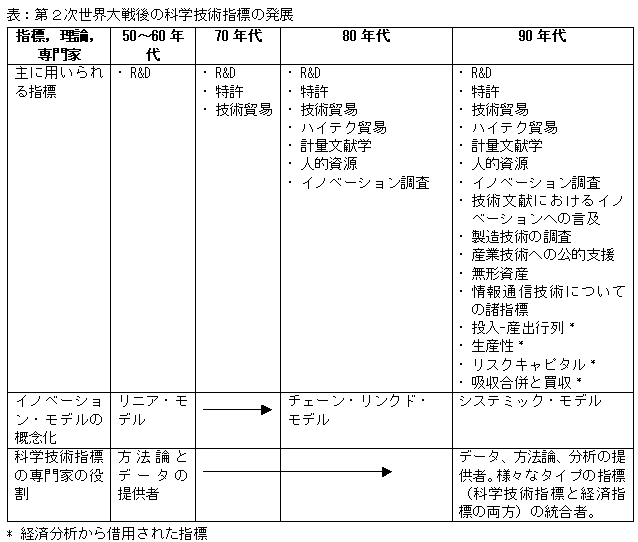
出典:OECD, "Report on the Activities of the Working Party on National Experts on Science and Technology Indicators (NESTI)", DSTI/STP(2000)26, September 2000.
目次へ
 Ⅲ.最近の動き
Ⅲ.最近の動き
 8月6日(月)午後、遠山文部科学大臣が移転後間もない当研究所に来訪されました。所長より資料に基づき当研究所の主な調査研究課題を説明、大臣との意見交換を行いました。
8月6日(月)午後、遠山文部科学大臣が移転後間もない当研究所に来訪されました。所長より資料に基づき当研究所の主な調査研究課題を説明、大臣との意見交換を行いました。
所長より組織概況、主な調査研究成果、セミナー等開催実績につき説明を行い、これら成果等を文部科学省、内閣府等の政策スタッフにも提供し、各種政策への反映も図られることから、高い評価を受けているとの説明。大臣からは最近の成果の多さに対し「なかなかアクティビティが高い」との感想を頂きました。
その後大臣は所内を視察され、職員とのコミュニケーションをはかりつつ、科学技術政策研究所を後にされました。
○ 主要来訪者一覧
8/2 | Mr. Kevin K.Maher:駐日米国大使館公使 |
8/6 | Mr. Gil Hwan Oh:ETRI-IT Technology Management Research Institute, | | Knowledge Management Department, Director 韓国 |
○ 講演会・コンファレンス
8/1 | 「岩手県における産学連携について」 |
| 小山 康文:岩手大学地域共同研究センター助教授 |
目次へ

編集後記
7月最後の土日にかけて、永田町合同庁舎から霞ヶ関郵政事業庁舎10Fへの、当研究所の引っ越しが行われました。新庁舎は、桜田通りを挟んで文部科学省本館(旧文部省庁舎)の斜向かいに位置し、9Fに科学技術・学術政策局、11Fに研究開発局、12Fに研究振興局が前週に移転を完了しており、これで文部科学省別館として全ての部署が揃いました。
会議室や図書室の独自スペースがなくなってしまい、研究所としての機能は必ずしも良くなったとは言えませんが、近代的なビルであることと地理的便利さという利点を生かし、科学技術政策研究の中核的機関として活動を続けていきますので、今後ともよろしくお願い致します。
文部科学省科学技術政策研究所広報委員会(政策研ニュース担当:情報分析課)
トップへ






 地方公共団体(都道府県及び政令指定都市)は、地域における科学技術振興の重要な担い手となっている。本調査研究は、地域における科学技術振興施策を体系的に把握することを目的に、平成2年度より概ね2年ごとに実施しているもので、今回が第5回となっている。
1.調査方法
平成11年度(1999年度)において、地方公共団体が実施した科学技術に関連する事業、及び経費の決算額をアンケート調査により把握した。今回の調査では、国庫支出金、施設整備費、公設試験研究機関等における研究課題等の評価を新たに調査項目に加えた。
2.調査結果の概要
(1)科学技術行政の総合的推進
都道府県の9割以上に相当する45団体において、①科学技術政策専任部署の設置、②行政部内の協議会等の設置、③科学技術会議等の設置、④基本計画等の策定、のいずれかが実施済みとなっており、地方公共団体において科学技術行政の推進するための体制の整備は進展している。
(2)科学技術関係経費の構造
地方公共団体(都道府県及び政令指定都市)は、地域における科学技術振興の重要な担い手となっている。本調査研究は、地域における科学技術振興施策を体系的に把握することを目的に、平成2年度より概ね2年ごとに実施しているもので、今回が第5回となっている。
1.調査方法
平成11年度(1999年度)において、地方公共団体が実施した科学技術に関連する事業、及び経費の決算額をアンケート調査により把握した。今回の調査では、国庫支出金、施設整備費、公設試験研究機関等における研究課題等の評価を新たに調査項目に加えた。
2.調査結果の概要
(1)科学技術行政の総合的推進
都道府県の9割以上に相当する45団体において、①科学技術政策専任部署の設置、②行政部内の協議会等の設置、③科学技術会議等の設置、④基本計画等の策定、のいずれかが実施済みとなっており、地方公共団体において科学技術行政の推進するための体制の整備は進展している。
(2)科学技術関係経費の構造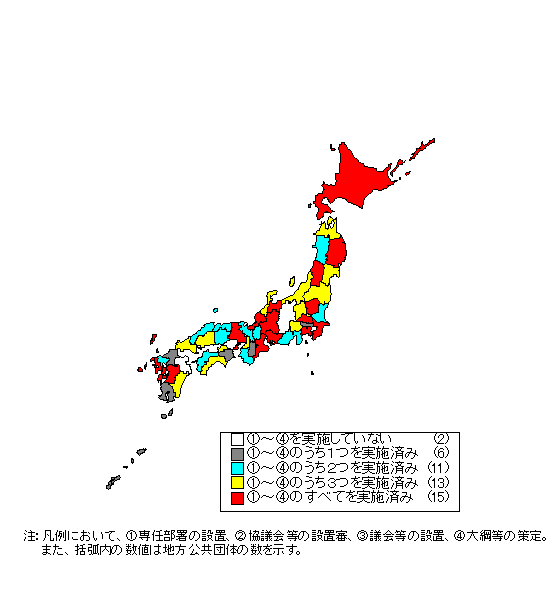
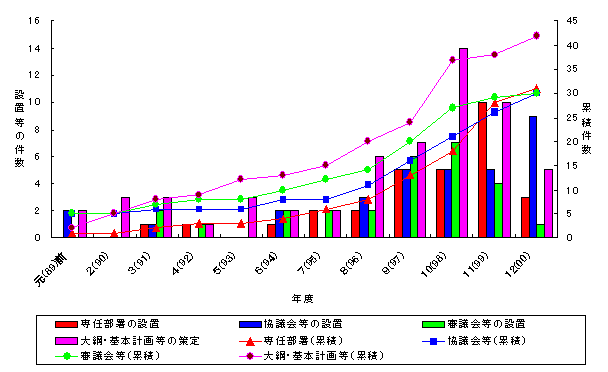
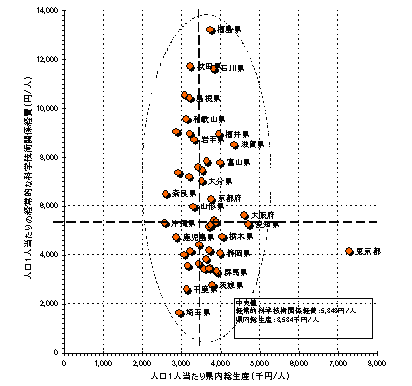

 現在、研究開発統計の調査方法や各種定義について定めたOECDのフラスカティ・マニュアルの改訂作業が約10年ぶりに行われている。同マニュアルの改訂項目は科学技術に関する様々な動向を反映している点で興味深いため、前号に引き続き、本年5月に開催された会議の模様を中心に、関連する動向を報告する。
(5) 各種の分類と調査手法
今回の会合では、研究開発統計における様々な分類の見直しについての検討に多くの時間が割かれた。(以下は主要項目)
現在、研究開発統計の調査方法や各種定義について定めたOECDのフラスカティ・マニュアルの改訂作業が約10年ぶりに行われている。同マニュアルの改訂項目は科学技術に関する様々な動向を反映している点で興味深いため、前号に引き続き、本年5月に開催された会議の模様を中心に、関連する動向を報告する。
(5) 各種の分類と調査手法
今回の会合では、研究開発統計における様々な分類の見直しについての検討に多くの時間が割かれた。(以下は主要項目)
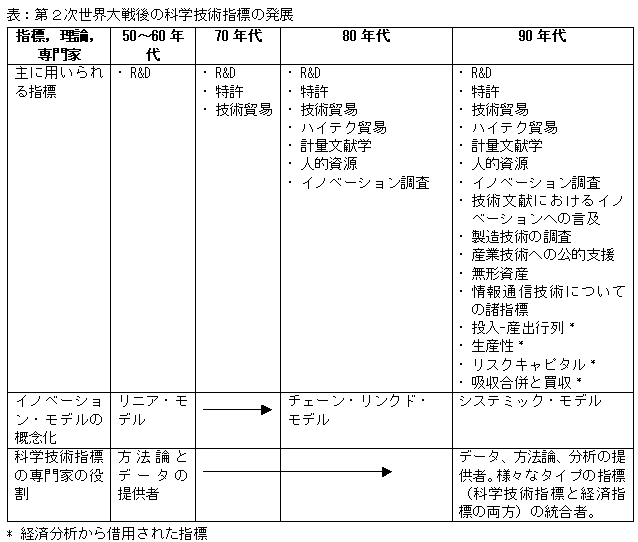
 8月6日(月)午後、遠山文部科学大臣が移転後間もない当研究所に来訪されました。所長より資料に基づき当研究所の主な調査研究課題を説明、大臣との意見交換を行いました。
8月6日(月)午後、遠山文部科学大臣が移転後間もない当研究所に来訪されました。所長より資料に基づき当研究所の主な調査研究課題を説明、大臣との意見交換を行いました。![]()