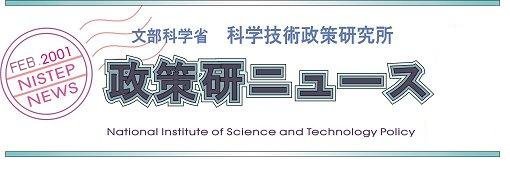
NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY POLICY
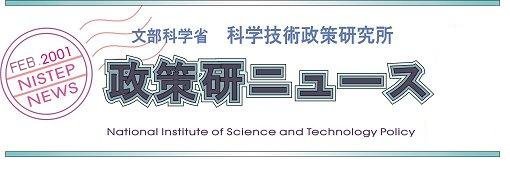 | No.148 2001 2 |
| 科学技術庁 科学技術政策研究所
NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY |
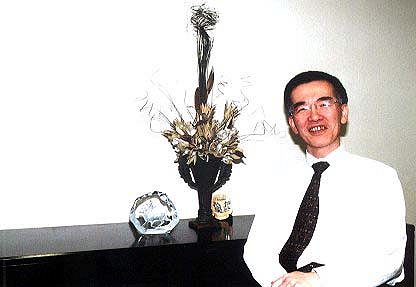
|
永野 博総務研究官
| 目次 [Contents] | 
| 総務研究官挨拶 | 総務研究官 永野 博
|

| Ⅰ.論説紹介 | 科学技術に関する国民意識調査について(その6)−英国の状況− 第2調査研究グループ上席研究官 岡本 信司
| |

| Ⅱ.トピックス | 国際コンファレンス:起業家精神とナショナル・イノベーション・システム 第1研究グループ
| |

| Ⅲ.最近の動き |
|
よろしくお願いします!
総務研究官 永野 博
政策研には初めての赴任ですがそれほど違和感は感じていません。一番の理由は、政策研設立直後、3回に亘り下田や大磯で開かれた国際会議に続けて参加したからかもしれません。偶々、国際課長や調査課長をしていたので参加しただけですが、科技庁にも凄い研究所が出来たものだと感心した覚えがあります。科学技術白書(私が担当したのは平成3年版)の作成に当たっては世界の論文の動向分析などで魅力的な分析を出していただき、白書に花を添えていただきました。お蔭様で多くの新聞が社説に取り上げてくれ大いに気を良くしたものです。今でも感謝しています。
近年、科学技術の重要性が認識され予算が増えてまいりましたが、役所は、日々の忙しさ、あるいは瞬間的な対応の連続からか、なかなか観念論、情緒論から抜け出せません。経済政策であれば、国民一人一人の生活と直結するせいか、国家の運営上不可欠であり、昔から経済学が学問分野として存在しますし、どういうわけかノーベル賞まであります。科学技術政策は、社会からの期待もいまいちのせいか、あるいは対象とする領域がそれほど明確ではないせいか、複合的な理由だとは思いますが、そのよって立つ理論を豊かにしたり、実証していこうという圧力には欠けるような気がします。
21世紀のスタートとともに始まる第2期科学技術基本計画には5年間の政府の投資額として24兆円という金額が掲げられる見込みです。こうなってきますと、政策担当部局からの基礎理論や実証データに対する期待も高まる気配があります。今回の省庁再編では、内閣府、総合科学技術会議、文部科学省等が誕生し、政策研では科学技術動向研究センターが発足しました。センターは総合科学技術会議が総理に対して月例科学技術報告を作成する際に定期的に情報を提供することになっていますが、これは何千人にも及ぶ政策研のネットワークがあったからこそ可能になったのだと思います。私はこれを政策研の無形の知的資産が顕在化し、活用されるほんの一例ととらえたいと思います。政策研で研究、調査している課題には重要なものが多く、職員の数と比較するとテーマ数が多すぎるほどです。政策研の内部はもとより外部との連携を図り、更にマーケッティングにも若干気を配れば、政策研の意義を認識する人が増えることは間違いありません。
期待が大きいということは、期待に沿えないと逆にがっかりされてしまうかもしれません。政策研に今求められていることは余裕を持って頭を使い、政策現場と接点を持って先導的な知的価値を生み出していくことであり、政策研にはその材料にこと欠きません。私もそのような観点から可能であれば皆様のお役に立ちたいと考えています。
科学技術に関する国民意識調査について(その6)−英国の状況−
第2調査研究グループ上席研究官 岡本信司
1 はじめに
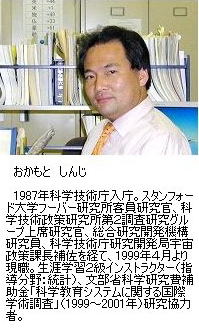 科学技術に関する国民意識調査は、欧米諸国をはじめ世界各国においても実施されており、その結果が科学技術政策に反映されるとともに時系列比較、国際比較等の調査研究も行われている。
科学技術に関する国民意識調査は、欧米諸国をはじめ世界各国においても実施されており、その結果が科学技術政策に反映されるとともに時系列比較、国際比較等の調査研究も行われている。
本稿では、執筆者が参加している英国の国際学術雑誌 "Public Understanding of Science"のメーリング・グループから情報を得た英国の状況について紹介する。
2 英国における科学技術に関する意識調査の状況
英国では、国際学術雑誌 "Public Understanding of Science"が刊行されていることからわかるように科学技術の公衆理解に関する研究について、長い伝統と歴史を持っており、Science
Museum (London)のDr John Durantを中心とする研究者グループがその中核を形成して欧州における研究グループの指導的な役割も果たしている。
英国における科学技術に関する意識調査については、1989年にScience Museum、オックスフォード大学等が実施した「科学技術の理解に関する世論調査」以降、1996年に1回実施されており、今回報告書が公表された2000年1月の調査が最新調査となる。
また、英国は欧州連合(EU)のメンバーとして、EUが行っているEU加盟15ヶ国による意識調査であるユーロバロメータ調査に参画しており、科学技術全般については1989,1992年の計2回、バイオテクノロジーに関しては、1991,1993,1996,1999年の計4回実施されている(ユーロバロメータ調査については、政策研ニュース2000年9月号No.143に紹介しているので参照されたい)。
3 「英国における科学コミニュケーションと科学に対する公衆の態度」の概要
"A Review of Science Communication and Public Attitudes to Science in Britain"
(1)調査概要
本報告書は、以下の2つの調査で構成されている。
ここでは、特に国民意識調査について紹介する。
〔国民意識調査:「英国における科学、工学、技術に関する公衆の態度調査」
("Public Attitudes to Science, Engineering and Technology in Britain")概要〕
1)調査対象:英国における16歳以上計1,839人
……… (英国人1,239人、スコットランド在住400人、英国在住少数民族200人)
2)調査手法:訪問面接法、無作為所在地抽出法(random location sampling)で荷重補正
3)調査時期:2000年1月
4)報告書公表:2000年11月(標記報告書として公表、
なお一部内容については既に英国科学白書で公表)
5)実施主体:Office of Science and Technology及びWellcome Trust
6)調査実施機関:Taylor Nelson Sofres Group
(2)調査結果概要
(調査結果のポイント)
(科学技術に対する英国公衆の態度分類)
英国民の意識調査結果を統計的多変量解析手法である(探索的)因子分析及びクラスター分析によって以下の6グループに分類した。各グループの主な特徴は以下のとおり。
なお、本報告書は、Wellcome Trustの以下のHPから直接入手が可能である。 http://www.wellcome.ac.uk/en/1/mismiscnepub.html
4 おわりに
国際コンファレンス:起業家精神とナショナル・イノベーション・システム
(2000年11月29日-30日:於:科学技術振興事業団地下会議室)
第1研究グループ
第一研究グループは昨年11月29日30日両日に「起業家精神とナショナル・イノベーション・システム」と題する国際コンファレンスを開催した。当日は150人近くの専門家が出席し、終日熱心な討論が展開された。以下では同会議の概要をセッション毎に整理する。
Session 1. Overview : 概観
本セッションでは、起業家企業の新規創業とNational Innovation Systemsの現状・課題について、後藤晃氏(一橋大学)とRobert Kneller氏(東京大学)の論文報告、並びに各論文に対するコメントが行われた。後藤氏は、今後わが国経済が一定の成長率を維持する上では技術革新の重要性が一層増すこと、及び、技術革新を活性化するためには如何なる体制が望ましいか、の二点を議論した。これを受け、児玉文雄氏(東京大学)は、産業―大学―政府3者間の交流および情報フローをより効率的に進めるためには、新たな「仲介機関」の出現が待たれる点を追加した。一方、Kneller氏は、独自の聞き取り調査を基礎としてわが国のバイオベンチャー企業に関する様々な特性を報告した。Kneller論文に対し、大滝精一氏(東北大学)はバイオベンチャー企業育成が今後の最重要課題の一つであることを確認した上で、バイオベンチャー育成に係わる諸問題を産学連携の文脈の中で整理した。
Session 2. The Role of Universities: 大学の役割
Dasher氏(スタンフォード大学)は、Silicon Valleyにおけるイノベーションについて、とくに大学からのspin-offとして新たに見られる組織形態を"entrepreneurial organization(起業的組織): EO"と概念化し、このEOの役割や特徴について議論した。産学関係におけるEOの役割は、技術市場の重要な部分を担い大学の技術のライセンスを受ける唯一の集団であると述べられた。また、大企業とEOとの関係がイノベーションの推進の上で重要であると指摘した。これを受けて、日本への含意として、産学関係や大学の機能を明確に再形式化をした上で設計していくことが重要であるとのコメントがなされた。
塚本氏(東京工業大学)は、大学からの技術移転の指標から見た日米独英比較、およびこれらの研究大学についてのケース・スタディを示し、今後のこの課題に対する日本における政策展開への含意を示した。とくに、結論として、技術移転機関(TLO: technology licensing office)やビジネス・インキュベーションを支援する組織の設立や促進、発明帰属の再考(国立大学の独立行政法人化後は大学による機関所有へ)、産学共同研究のためのシステムの改善といった点が重要であることを指摘された。また、大学自体の内部のマネジメントや大学の研究者による発明に関する権利の取り扱いに関する現状と今後の方向などについて、コメントがなされた。
Session 3. High Tech Industries : 先端技術産業
本セッションでは、地域経済と技術及び地域先端技術産業の技術・経済評価に関する2件の報告が行われた。まず、Roger R.Stough氏(ジョージメイソン大学)は、ワシントンDC地域などを研究対象として取り上げ、地理的な面から見た技術・経済・雇用等に関する検討結果を報告した。政策分析においては、テクノロジーを伴った雇用が、他の民間雇用を促進させるような施策と比べ早く効果があるとした。吉川智教氏(横浜市立大学)は、経済学者の立場からのコメントとして、日本でも同様な現象が見られることを新潟県燕市を例として解説した。次いで、岡田羊祐氏(一橋大学)は、特許データと産業の経済特性との相関に関する報告を行った。医薬品業界を例に、後願特許数・先行特許の引用数・クレーム数・出願国数に関する数値解析結果の日米比較を行い、両国の技術格差は1980年までは明瞭でなかったものの近年では著しい格差があると指摘した。この報告を受けて、Lennart Stenberg氏(スウェーデン大使館)は、特許件数の違いだけで論じる事は難しく、重要性はむしろイノベーションに関する違いにある点をコメントした。
Session 4. Start-ups in Japan :日本のベンチャー企業
本セッションでは、榊原清則(科学技術政策研究所)が、わが国の起業家企業の実態と課題について報告した。榊原は、科学技術政策研究所において実施した質問票調査を基礎に、わが国の起業家企業の特徴を幅広い角度から整理した。榊原が指摘した主な点としては、1980年代以降IPO志向企業が増加している点、経営者は平均53歳であるが近年高齢化の傾向にある点、わが国の起業家は実務経験豊富なCraft型経営者と高学歴なElite経営者に大別される点、並びに、IT・バイオ等の新しい分野では若い起業家が増えている点、が挙げられる。榊原論文を受け、飯塚哲哉氏(ザイン・エレクトロニクス株式会社)は、今後、若い経営者の新規創業を促進するためには、旧来の銀行借入への依存体質から脱却することが最重要であると指摘した。
Session 5. Stimulating Entrepreneurship :起業家精神の涵養
本セッションでは、Arnoud De Meyer氏(INSEAD)、及び、忽那憲治氏(大阪市立大学)の報告が行われた。De Meyer氏は、欧州におけるイノベーション促進プログラムの概要について整理した。欧州では、1980年代に入ると、各種規制の緩和、人的流動性促進、情報交換によるインフラ形成等の技術革新促進政策が取られると同時に、破産法の改正、人々の技術に対するイメージの改善等への努力も行われた。De Meyer氏に対して西村吉雄氏(日経BP社)は、国家を超えた欧州全体のイノベーションを推進することが有意義であると指摘した。一方、忽那氏は、株式公開市場における価格決定方式の変更とその経済効果について論じた。忽那氏は、1997年9月に導入されたBook Building方式は、有価証券の引受け・売出しを担当するアンダーライターに価格決定の主導権を与えることを通じ、適正な公開価格を実現し、これまで小規模企業が直面していた不利益を解消したと論じた。
Session 6. Implication to Innovation: イノベーションの意義
Rickne氏(チャルマース工科大学)は、イノベーション・システムというコンテキストにおける新規の技術基盤企業の展開とパフォーマンスという課題について、バイオマテリアルの領域を対象にして3つの地域を選定して行った分析を基にして、まず、広義での資源の"connectivity(連結性)"という概念を用いた資源フローのネットワークを議論した。次に、地域イノベーション・システムの"functionality(機能性)"について4つの指標を通して定量的に分析した。政策的含意として、イノベーション・システムについてはアクターよりも機能性について焦点が置かれるべきこと、機能性に関する全体論的な見方が肝要であること、機能間のフィードバック・ループを伴うイノベーション・システムのダイナミクスに関して理解する必要があることなどを指摘した。
山口氏(21世紀政策研究所)は、概念的に、科学と技術との関係、産業界における研究と大学における研究との関係を、歴史的推移や、特許や論文の定量的推移に関する日米比較を通して整理した。そして、学問領域を拡大させていく場として産学関係の"field of resonance(共鳴場)"が必要との立場からその特徴を議論した。
Session 7. The Agenda for the Future: 未来への手だて
本コンファレンスの最終講演となるこのセッションでは、前田昇氏(高知工科大学)がハイテクベンチャーの始動に関する講演を行なった。前田氏は、日本文化は起業家には不適であるとする見方は誤りであること、しかし、研究開発型のベンチャーがなぜ日本では育たないかという問題設定が重要であることを提起した。この根源はハイテクベンチャーを担う人材不足にあり、十分な教育が施されたハイテク起業家の供給源たる機関として大学、国立研究所、企業を挙げ、これらの機関に対する十分な政策的支援が必要であるとした。これを受けたArnoud De Meyer氏は、誰がベンチャーの創生者になり、発展のための駆動力をどのように得ていくかという問題について、日本は独自のモデル化が可能なはずであり、その見方において前田氏の提案は興味深いと評価した。
まとめ
本コンファレンスでは、起業家精神とナショナル・イノベーション・システムにかかわる問題を、日・米・欧における調査研究を基礎に幅広く議論した。具体的な論点としては、各国におけるイノベーションに関わる諸局面の実態や種々の制度等の現状、ならびにこれらの課題、および、各国における起業家企業の経営実態と直面する問題点、を柱に、日米欧の事例分析等を踏まえた経験的研究ならびに計量経済学的分析の結果が紹介された。各国のイノベーション・システムは、一面では、その生成過程で、径路依存的な側面を持ち合わせているため、単純な比較は難しい。しかし、同時に、各国の実情・経験の中には、わが国の起業家企業を取り巻く環境に酷似する点もいくつか見受けられる。特に、資本市場の整備とその影響、産業における科学的知見の重要性の増大、バイオ・ベンチャーに代表される産学連携の加速、人材の流動性に関する変化、等は、わが国においても指摘される点である。これらの点は、今後、ナショナル・イノベーション・システムを検討するうえで有力な手がかりになると言えるだろう。
![]()
編集後記
◆ 暖冬と言われていた今年の冬も、年を越したとたんに厳しくなりました。早く花のたよりを聞きたいものです。
◆ これから年度末に向けて、レポート発表記事を花のたよりとともにご紹介できると思いますが、今回はその狭間でちょっとさみしい気がします。
◆ 省庁再編により政策研ニュースの送付先もそれに合わせて再編したつもりですが、不都合等ございましたら下記宛にご連絡ください。(S)
文部科学省科学技術政策研究所広報委員会(政策研ニュース担当:情報分析課)