 |

| No.123 1999 1 |
| 科学技術庁 科学技術政策研究所 NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY |
 |

新年明けましておめでとうございます。
昨年は、本研究所の創立10周年にあたり、記念の式典や国際コンファレンスを開催し、10周年誌を発行するほか、外部有識者による機関評価を受けるなど、節目の年でありました。創立10周年記念コンファレンスでは、予想以上に多くの方々の御参加を賜り、科学技術の将来に対する深い関心、科学技術政策研究に対する大きな期待が寄せられました。また、半年にわたって毎月のように開かれた機関評価委員会は、学習型とも言うべきもので得るところの多いものでしたが、委員会の方々からの政策研に対する期待の大きさに身の引き締まる思いが致しました。
情報通信技術等の飛躍的な進展により、科学技術と社会との結びつきが強く意識され、また、グロ−バルな競争の激化を背景に、産業の競争力の源泉が科学技術であるとの認識が高まり、各国において、科学技術政策に対する期待が増大しております。企業の競争力を左右する因子が、時代とともにコストから質に、さらに、スピ−ドへと移り、今や、俊敏さ(agility)であるとされていますが、情報化の進む新世紀においては、他との差別化を可能とする独自の特徴が重要になると思われます。科学技術政策作りにおいても競争の時代を迎えており、各国の特色を生かしたものが求められています。
米国が日本の科学技術システム等を徹底的に調査研究し、科学技術強化を軸とした政策を推進することなどにより、現在の圧倒的とも言える米国優位の状況をもたらしたことは、周知のことであります。また、英国では、技術予測やパネルディスカッション等を組み込んだ独自のフォ−サイトプログラムを実施し、政府による研究開発支出の優先付け及び科学界と産業界との協力関係強化を図り、さらに、仏国も、昨秋から各国のシステムの比較をすることにより、国際競争下での研究・技術革新に関するフランスの役割と戦略に関する調査を開始しております。
日本では、科学技術基本法の制定、科学技術基本計画の閣議決定等により科学技術予算の増額が図られていますが、昨年の中央省庁等改革基本法の成立により、科学技術行政体制の大枠が変更されることとなりました。今後、日本の特徴を生かした政策策定のために、従来の体制や政策のレヴュ−を通して、これからのグロ−バル知識社会において日本の強みとなりうる特徴を抽出し、それを生かしたビジョン作りが必要と思われます。
今年は、政策研にとって、新たな10年の最初の年であるばかりでなく、科学技術政策の新たな枠組みが明確にされる年でもあり、機関評価委員会報告書の提言等を踏まえ、客員研究官の増員、関係機関との連帯の強化拡充等を図りつつ、新たな10年の大きな飛躍を目指した活動の年にしたいと考えております。
今年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
Ⅱ.研究グル−プ等の研究紹介(特集)
年頭にあたり、研究グル−プの今年の抱負と、特定課題について語っていただきました。

〈今年の抱負をお聞かせ下さい。〉
一研は総括が昨年4月に着任し、またその後、メンバーが続々と加わった関係で、少し落ち着きに乏しい年でした。今年はその反省から、基本的にはもう少し腰を据えた体勢で、調査研究活動にじっくり取り組むべき年であろうと考えています。
今年の抱負については、基本的には前年に取り組み始めた研究活動を継続するということですが、まだ活動途上で、成果を公表していないものについては、鋭意成果志向で作業を継続するとともに、4月の新年度以降、新しいテーマ、トピックについても積極的に取り組んでいきたいと考えています。
おもな研究課題としては、以下のものが継続中で、今年も活動の柱となるべきものです。第1は、情報技術(Information
Technology)が知的生産性に及ぼす影響に関する国際比較調査です。第2は、研究開発の国際化における人事・組織管理とインフラストラクチャーの研究で、国研および民間企業の双方を対象に、いま調査を進めています。第3は、政策形成・研究開発実施過程における産官学のインタラクションに関する研究です。第4に、研究開発関連政策が及ぼす経済効果の定量的評価手法に関する調査があります。これは振興調整費ソフト調査です。第5に、研究開発との関連で税制をめぐる広範な論点が取り上げられ、研究中です。
なお、以上のほかに「ベンチャーと国際化の視点による新ビジネスモデルの創造」プロジェクトというのが一研を中心に進行中です。これは民間企業から客員として来ていただいている方々と、われわれ一研のメンバーとが連携して作業を進めている、野心的なプロジェクトです。
ベンチャービジネス関連のこのプロジェクトは、今年も重要テーマの一つとして、一研のメンバーのみならず客員その他の方々とも広く連携しながら、鋭意研究を進めてゆくつもりです。そして、研究を進める過程で、できれば堅固なデータ・ベースを構築し、より定量的な志向を持った調査研究へと展開していきたいと考えています。
一研ではさらに、大学からの客員として2名をお招きしています。この方々には「半導体エンジニアの流動性に関する研究」および「研究開発におけるコミュニケーションの研究」を進めていただいています。今年も、その作業を継続していただく予定です。
以上のとおりですが、(1)4月の新年度からはさらに新たなメンバーを加え、より充実した研究体制を組みたいと考えていること、(2)今年の多分下半期に、「科学技術を基盤としたベンチャービジネスに関する国際ワークショップ」を開催する方向で検討中であること、以上の2点を追記しておきます。

〈今年の抱負をお聞かせ下さい。〉
私がNISTEPを併任しはじめた95年は、科学技術基本法が制定された年であり、御承知のように、その後基本計画の策定とその実質的展開、さらには行政改革の提起とその実態化が矢継ぎ早に進行し、科学技術政策関連政策のホットな課題には事欠かない幸せな時期でした。そのような千載一遇の時期に研究現場の中枢で、その推移に立合えることになりました。そのため、従来、NISTEPではあまり取り組まれていなかった課題対象型の研究に力を注ぐこととなりました。しかし、このうねりは既に下降局面に入り、研究のフェーズも課題研究の第一波としては取りまとめの段階に入っています。
科学技術関連政策の形成システムに関する国際比較研究からは多くの示唆が得られており、単なる組織構造の問題だけではなく、その運営制度や、それらを支えるエキスパートの養成や集積メカニズムにいたるまで、システム全体としての一貫性の確保が重要であり、そのための課題対応に必要な論理化が図られています。
一方、予測、戦略、評価といった科学技術政策を推進する上で重要な諸局面を貫く、測定論(メトリックス)と形成論の体系を整備することを目指した理論展開型の研究においても、豊富な事例を手掛かりにして実態との乖離を避けつつ、操作性に優れた理論の展開を意図しています。このような認識のもとでの研究は、NISTEPという政策形成部署に近い刺激的な研究現場において初めて明確に意識することができました。
このような基盤が継承発展されていくためには、様々な仕掛けが必要であろうかと思います。例えば、科学技術関連政策の国毎のウォッチャー・ネットワークの維持。単に情報収集を継続するだけではなく、それを読み込み分析を深めていく研究者のネットワークである必要があります。また、NISTEPフォーラムの開催。課題対応型の研究成果は、単に印刷物として配布されるだけではなく、その課題に責任のある担当官や意思決定者をまじえた検討に供されるべきです。さらには、政策形成の担当者とのインフォーマルな交流を確保するためのセミナーや講演会の共同運営。研究の方向性を見定めるうえで重要であり研究の自己目的化を避け、研究成果のユーザーやニーズ状況を知る必要がある。等です。
今年は、従来の2研の枠だけではなく、このような視点からNISTEP全体で取り組むべき課題に対しても関与していきたいと思います。戦略的政策形成に必要な指標の整備、政策形成に適用できるフォーサイトのあり方、信頼性の高い政策評価を可能とするための政策分析やインパクト分析の深化等取り上げるべき問題は多いと思われます。

〈今年の抱負をお聞かせ下さい。〉
当グループでは、科学技術活動の基盤として特に重要な人材の育成・確保について調査研究を実施するとともに、主として科学技術政策の企画・立案のための基礎資料を提供することを目的に、体系的な科学技術指標の開発を行っています。
人材の育成・確保に関しては、これまで高校生、大学生の進路動向の調査研究等を通じ青少年の科学技術離れの実態を明らかにし、政府、大学等に対し重要な問題提起を行うとともに、この問題を解決するための各種政策提言を試みてきました。現在は、従来の調査研究をさらに発展させ、科学技術活動を取り巻く新たな状況に対応すべく、多角的な視点から人材の育成・確保に関する調査研究の展開を図っています。例えば、創造性豊かな科学技術人材の育成、高齢化・少子化社会における研究環境の活性化のためには、今後科学技術人材の流動化を促進することが不可欠となっており、研究者等の流動実態と流動に係わる意識及び課題等の調査研究を進めています。また、近年益々複雑化する社会的・経済的諸問題を解決するためには、いわゆる文理融合型の人材を育成することが重要であり、学際的カリキュラムの構造と運営について大学院に焦点をあて分析を進めています。さらに、これからは女性の有する科学技術の能力を最大限に生かすことが重要との認識から、理工系を専攻した女性の就業実態等に関する調査研究を実施しています。
科学技術人材の育成・確保は、科学技術創造立国を目指す上で鍵となるものであり、文部省国立教育研究所とも協力しつつ、従来にも増して積極的に調査研究に取り組んでいきたいと考えています。
〈「科学技術指標研究」についてお聞かせ下さい。〉
本研究は、科学技術活動の状況を的確に把握し評価するために、定量的なデータに基づいた科学技術指標の体系を開発することを目的としており、複雑で多岐にわたる科学技術活動全体を把握するための方法論に関する理論的研究に加えて、実際のデータ収集・加工、得られたデータを用いた分析、分析手法の開発を含む総合的な研究課題といえます。
科学技術指標の報告書は、平成3年9月に発行して以来、ほぼ3年毎に発表しており、最近では、平成9年5月に公表しました。版を重ねる毎に改善に努めており、例えば、これまで合成指標の開発、研究開発成果に関する指標の開発、産業における研究開発の多様化の分析、研究開発の国際化に関する分析、研究開発の地域構造に関する指標開発、などを行ってきました。
本研究の成果は、科学技術白書に多く引用されているほか、例えば研究支援人材の育成や地域科学技術活動の強化の重要性を示すことなどを通じて、科学技術会議の各種答申に間接的ではあるものの影響を与えていると考えています。
科学技術指標は、科学技術政策の企画・立案を行う上で重要な基礎資料となるものであり、今後日本の科学技術活動の国際的位置付けをさらに明確化するなど、より一層の充実に努めていきたいと考えています。

〈今年の抱負をお聞かせ下さい。〉
科学技術と人間・社会という調査研究テーマは、政策研が発足して以来の大きなテーマで、過去いろいろなアプローチで取り組んできまし
た。ごく簡単に振り返ってみても、この十年の前半は世論調査の分析、国際比較など国民の科学技術に対する意識調査を進め、科学技術を推
進して行くに当たっての理解やコンセンサスに関する基礎的な認識を深めてきたところですし、後半はどちらかと言えばこうした認識をふまえ
て行政が具体的にどのような施策を講じたらよいか、かなり具体的なテーマに即しながら調査してきました。しかし、最近は科学技術の進歩の早さと、これを享受する国民の生活や意識の多様化などからSTS等の新しいアプローチも出てきていますし、一方生命倫理や情報科学などはその進展に施策がなかなか追いつけないような状況も見えてきています。
政策研としては行政に比較的近い立場にあることをうまく利用し、理論的な調査だけではなく、行政にもすぐ活用できるような解決策を見いだせる調査をしてみたいと思っています。特に、行政改革の中で新しく総合科学技術会議が設置されることとなっていますが、この「総合」の中には自然科学と人文・社会科学の総合という趣旨も含まれていると聞いています。第2調査研究グループの調査などもっともその問題に近いところにあるわけで、こうした問題を先取りして解決に資したいと思っています。個人的には、単に自然科学の研究者と人文・社会科学の研究者が集まると答えが出るようなものではなく、それぞれの問題意識や学問の方法論の前提までさかのぼって根源的に考える必要さえあるように思います。その意味ではうまく行けば新しい学問がそこからは開けるかもしれません。
〈「生命倫理」についてお聞かせ下さい。〉
生命科学、特に生殖科学ではクローンとかES細胞とか全く新しい問題が最近特に新聞を騒がせています。すでに申し上げたような意味で、こうした生命倫理の問題もグループの中のもっとも関心の深いテーマです。従来、科学技術と人間・社会の問題は社会学的なアプローチが多かったようですが、生命倫理の問題はむしろ法律、倫理、行政学などの観点から考えなければいけないと思います。これらは西洋では千年単位の歴史のある学問でもあり、政策研としては新しいアプローチとなるわけでやりがいがありますが、一方で行政との連携もいろいろ強める必要を痛感しています。
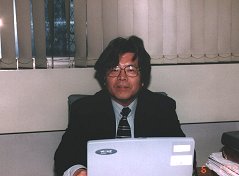
〈今年の抱負をお聞かせ下さい。〉
当グループでは、地域における科学技術振興に関する実証的調査研究を行っています。今年、当グループが手がけなければならない課題はいろいろありますが、とりわけこれから力を入れて取り組んで行かなければならない、むずかしいが、しかし重要な課題について簡単にお話して、抱負に代えさせて頂きたいと思います。
地域における科学技術振興は、地域に集積している科学技術資源や地域の伝統・文化に大きく依存して展開されていますので、これからの地域の科学技術振興政策を考える際には、それらの要素との深い係わり合いの中で、地域ごとに異なった特性を活かした政策の実現が是非とも必要となります。従って、それぞれの地域(地方公共団体)が効果的な政策の展開を図ることができるようにするための一つの重要なツールとして、各地域における科学技術の実情やそのポテンシャルを推測できるような指標の開発が必要となります。現在、当グループでは、この指標の開発の研究に取組んでいるところです。また地域に展開する中小企業の研究・技術開発活動の実態や地域の技術革新(リージョナル・イノベーション)に関する研究も行っています。これは、技術革新に関する基盤的研究でありますが、上述の指標の開発に関連して欠くことのできない重要な研究ともなりますので、今後積極的に取組んで行きたいと考えております。
〈「RESTPOR」についてお聞かせ下さい。〉
「RESTPOR」(レストポール)とは、「REgional
Science and Technology POlicy Research」の頭文字から創ったユニークな国際会議名のことです。日本語では「地域科学技術政策研究に関する国際会議」と名付けています。この国際会議の発祥は、1993年に当研究所が世界の研究者に呼びかけて岩手県で開催したのが始まりです。開催の趣旨は、経済のグローバリゼーションが急速に進む中で、イノベーションを持続的に継続することができる社会の実現を図るために、国全体だけではなく、地域の科学技術資源・枠組についての政策研究が必要であるとの問題意識のもとに実施されました。この会議の開催の結果、その重要性が認識され、開催の継続への期待が高まりました。その後、引続いて第2回が1995年に日本(神奈川県)で行なわれたのち、1996年に第3回がEU主催によりベルギーで開催され、そして昨年(1998年)11月に第4回が米国ノースカロライナ大学の主催によりノースカロライナ州チャペルヒルで開催されるに至りました。次回の第5回の会議は、2000年に日本で開催されることが決まり、当研究所が主催することになります。
折しも世界経済が大きく揺れ動き、様々な地球規模の難題が次々と発生する中で、科学技術が担う役割はかってないほど人類にとって重要かつ大切なものとなっています。従って地域の科学技術政策の研究においても、世界の科学技術政策の研究としての視座に立って、的確にかつタイムリーに国際社会に貢献できる提言を構築することが強く望まれます。かかる意味において、2000年のRESTPORの開催は、まさしく世界の科学技術政策の研究にとって大変意義深いものとなるように寄与することが望まれます。当研究所としては、内外の関係機関の協力の下に、この期待に最善を尽くして応えなければならないことは言うまでもありません。担当部署の一部署としてその責任を痛感するとともに、この場をお借りして関係各位の皆様方の暖かいご支援をよろしくお願い致します。
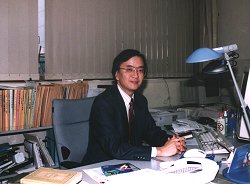
〈今年の抱負をお聞かせ下さい。〉
当グループの担当は、科学技術の動向及び将来予測に関する調査研究です。
科学技術の総合的な動向に関するものとしては、日本の第6回技術予測調査とこれに対応して実施されたドイツのDELPHIⅡの比較分析を昨年より進めており、まもなくまとまる予定です。また、特定の分野に着目して、より詳細な分析をするものとして、加速器科学の動向調査を行っています。ご存じのように、加速器科学は素粒子や原子核物理学を中心とするビッグサイエンスですが、その応用は物質・材料科学、生命科学、医療利用、産業利用など非常に広く、これらの領域の技術革新を支えていく上でも重要なものになっています。しかし、基礎研究の発展のために必要となる加速器を従来の方式で建設するには非常に大きな投資が必要で、先進国でも一国で負担するのは困難になりつつあります。そこで、2、30年くらい先を考えて、そのころ利用できる可能性のあるコンパクトな新しい加速技術について調査をしています。昨年国内の開発者向けアンケート行い、今年は、海外の開発者へのアンケート及び国内の各応用分野の利用者へのアンケートを実施する予定です。
また、将来の科学技術を展望する上で、社会の動向を考え、将来どのようなニーズが顕在化するかというアプローチも重要になります。この一環として、昨年より、科学技術基本計画の主目標の一つとなっている「生活者ニーズへの対応」を取り上げて、今後20年間程度の間に社会的にどのような変化が起こり得るか、これに伴ってどのような社会的ニーズが生まれあるいは強まるのか、これらを解決するための技術の見通しはどうかなどの問題意識の調査を進めています。具体的には、2007年をピークに減少に転ずるといわれている人口の動態と地球環境からの制約の強まりを基軸にして、食生活、住生活、医療などいろいろな断面から分析し、春頃にレポートをまとめる予定です。
また、世論調査などで常に関心事のトップにくる健康の問題について、これまで政策研ではあまり取り上げてきませんでしたが、病気になる前の健康な状態の人々も含めたヘルスケアの問題を取り上げ、科学技術の視点から分析する研究も進めることにしています。
〈「技術予測調査研究」についてお聞かせ下さい。〉
政策研が技術予測を担当した第5回調査以降、技術予測はドイツ、イギリスなどのヨーロッパ諸国をはじめとして、中国、韓国といったアジア諸国など非常に多くの国で取り組まれるようになってきました。国際機関においても、OECDがセミナーなどを主催してきているほか、APECのプロジェクトとして技術予測センターがタイのバンコクに昨年設立されています。このような動きに対応して、今年政策研ではAPEC技術予測センターと協力して東京で国際会議を行う予定で、現在準備を進めています。また、21世紀の開始年であり、中央省庁が新体制に移行し、総合科学技術会議が発足する2001年に向けて、次の第7回技術予測調査を実施する計画を進めています。現在、科学技術会議にテーマ申請をしていますので、その結果で春過ぎからプロジェクトが開始されることになると思います。

〈今年の抱負をお聞かせ下さい。〉
日本の技術貿易構造を把握するため、外国との技術、ノウハウの取引といったいわゆる外国技術の動向調査を行い、我が国の技術水準や技術開発力に関する知見を収集し、これまで科学技術白書や通商産業ハンドブックといった技術貿易動向の把握が必要な政府機関や、調査機関に基礎資料を提供してきました。
今年は、これらの調査を継続して実施するとともに、これまで調査を進めてきた技術貿易収支に関わる知見、ノウハウを元に、技術貿易収支に関する構造を明らかにするための分析を行います。
また、技術輸入の構造に関しては、日本は技術導入の約8割を北アメリカからコンピュータのソフトに関する技術を導入しているわけですが、そのソフトウエアに関する技術貿易構造の分析を行い、構造を把握することにより我が国の情報科学技術分野の政策担当者に基礎資料を提供します。さらに、技術取引の特殊な形態として、企業内部化要因の調査分析等を行い、構造を分析します。
一方、EUのユーロがスタートしました。これに見られるようなヨーロッパ圏、これまで基幹となっていたアメリカ圏、及び第3極としてのアジア圏が注目を浴びています。当研究所でも、アジアの科学技術に関する実態調査を実施すべく、アジアの専門家による研究会を開催しています。政策研究及び政策立案に携わる政府機関や調査機関に有用な基礎データを提供できるようになればと考えています。
情報分析課は、図書等の提供、定期刊行物の刊行や情報システムの開発・管理業務といった研究支援部門の一翼を担っておりますが、こちらの支援業務を粛々と実施し、かつ、これらの調査業務を実施したいと考えています。
〈「技術貿易収支に関する調査研究」についてお聞かせ下さい。〉
技術貿易の関連統計では、当研究所の技術貿易に関する報告書の他に、総務庁の科学技術研究調査及び日本銀行の国際収支統計月報があります。これらの統計には、技術輸入額、技術輸出額が報告されていますが、両統計の差が年々開き、それぞれの統計で入超、出超という結果が出ています。技術輸出が多いのか技術輸入が多いのかについては関心が多く、技術貿易収支に関する基準値を作成する必要がありました。
現在、情報分析課では、所内外の有識者、技術貿易統計作成者からなる技術貿易統計検討委員会を設置し、既存統計の調査法、集計法を精査しています。これにより、定量化の方法を考案し、過去に遡って、技術貿易収支の基準値を求めることとしています。
今回の調査では、官公庁で出されている統計を利用することを考えており、統計を保有している機関と調整を進めているところです。
Ⅲ.トピックス

私は現在、政策研と共同で「半導体エンジニアの流動性に関する研究」を行っております。この研究は、日本で半導体開発に携わってい
るエンジニアや研究者に焦点を当てて、それらの人々の流動性の実態を明らかにすることを主たる目的としています。国際比較も念頭に置
いています。ここで流動性という場合に対象としているのは、転職に代表される企業間の移動はもちろん、勤務地の移動や専門分野間の移
動、企業内部での機能部門間の異動なども含んでいます。これら様々な移動・異動の間に存在する相互依存関係に注目しているのが本研究
調査の特徴といえます。年内に5000部を越える質問票を半導体開発者に配布することを予定しています。質問票では、回答者が過去に経験した移動や異動経験を組織間、専門間、部門間など8つの軸に沿って年表形式で尋ねています。十分な回答が得られれば、日本だけでなく世界的に見てもあまり例のない詳細なデータになるため、私自身結果を非常に楽しみにしております。
このような研究を始めようと思ったきっかけを簡単にご説明したいと思います。私が、エンジニアの流動性の調査をやりたいと思ったのは1996年の初めです。当時私は米国MITで博士論文を書き終わった頃でした。博士論文で私が扱っていたのは、自動車企業の新製品開発における過去のプロジェクトから現在のプロジェクトへの知識移転の問題でした。その研究の中で私は、新製品開発プロジェクトのメンバーが世代を越えてどのようにプロジェクト間を移動しているのかを調べました。わかったことの1つが、世代を越えて同種のプロジェクトを継続することの重要性と問題点でした。製品開発に必要となる知識のうちいくつか重要なものは人に体現されています。したがって特定の人なりグループを移転・継続することが開発成果にとって重要になる。しかし同時に過去のパターンに引きずられるという点でイノベーションにとってはマイナスの影響が出ることもある。簡単にいえばそんな結果です。続いて、知識の体現者としての人の移動のもつイノベーション活動への影響の問題を、企業内部のプロジェクト間(製品間)だけでなく、企業間の移動や専門領域間の移動など様々な移動にまで範囲を拡げて、さらにそれらの間の相互関係にまで突っ込んで理解したいと思ったのが本調査研究の出発点です。
日本の技術者・研究者の企業間移動は極めて固定的であるといわれます。イノベーションを起こすためにはもっと流動性を高めなければいけないといわれます。しかしこうした議論をするためには、まずどの程度固定的なのかを事実としてきちんと理解しておく必要があります。同時に、流動性を高めた時に生じる代償も把握しておく必要があります。本研究がそうした理解に貢献することを私は期待しています。

1.はじめに
インドネシアの研究・技術担当大臣へのアドバイザーは1982年当時のハビビ研究・技術大臣(現大統領)より科学技術に関するアド
バイスを行う顧問の派遣依頼があり、これを受けてそれ以来派遣されている。
私は1997年6月よりジャカルタに勤務している。当初はASEANの中核国家として経済発展をとげていたインドネシアの息吹を感じ
ていたが、着任後しばらくしてタイのバーツ下落に始まるアジアの経済混乱に巻き込まれ、98年3月に研究・技術大臣から副大統領に就
任していたハビビ氏が5月には大統領に就任されるといった政治的大変動を経験した。
研究・技術大臣も3月には国家開発企画庁副長官のラムラン氏が任命されたが、5月にはラムラン大臣は工業・商業大臣に就任され、後任にBPPTの副長官であったズハール氏が就任された。インドネシアの政治的変動を引き起こしたアジア経済危機はタイ、マレーシアでは徐々に回復軌道に乗りつつあり、インドネシアにおいても一時1ドル=15000ルピアまで下がった通貨も、IMF等からの支援により7550ルピアまで回復している(危機の前は1ドル=2500ルピア)。
しかし、来年6月には総選挙が予定されており、それに向け誕生した100ともいわれる政党間の駆け引き、また汚職・縁故主義に反発する学生達によるデモとそれによる交通渋滞、失業者増大に伴う犯罪の急増(高速道や一般道における車への襲撃)が報告されており、社会情勢はなかなか安定化の兆しをみせていない。このような中、我が国もインドネシアに対する支援を積極的に表明しているが、その重点課題はソーシャル・セーフティ・ネットの強化(食糧、特に米の確保と流通経路の確立、医療サービスの提供、雇用機会の確保、ドロップアウトの防止)、自然災害対策・予防、貧困対策、外貨獲得に資する裾野産業の育成、ルピア下落により困難に直面している中小企業の支援、生活産業基盤の整備等が挙げられている。したがって、我が国との協力においても、最先端の科学技術ではなく、このような面に資する科学技術支援が期待されている。
2.体制
インドネシアの内閣は正副大統領、4人の調整大臣、20人の各省大臣及び12人の国務大臣の総勢38名からなっている(現在副大統領は空席)。このうち研究・技術を統括する国務大臣がズハール氏であり、BPPT(技術応用評価庁)の長官を兼ねている。ズハール大臣はバンドン工科大学、東京電機大学で学士号を取得し、その後オーストラリア、米国で勉学を続け、インドネシア大学の教授でもあった。
国営電力会社の社長も経験しており、エネルギー分野についても造詣が深く、石炭の液化等に関心をもっている。
研究・技術担当大臣の諮問機関として研究諮問委員会(DRN)があり、各分野の専門家から構成され、5ヶ年計画の作成を行っている。第6次5ヶ年計画は来年3月までとなっている。研究・技術担当大臣の下に120名からなる事務局(RISTEK)があり、各省庁からの研究・技術関連予算について、5ヶ年計画に沿っているかどうかのチェック等を行っている。
研究・技術担当大臣が長官を勤めているBPPTはインドネシアに必要な技術の評価、計画の総合調整を行うために1978年に設立された。民間において必要な技術の指導もその活動の中に含まれている。総勢3200名であり、その内博士が80名、修士卒が370名、大学卒が1400名と高学歴者集団である。将来は政府、民間企業における科学・技術のコンサルタント的な役割をはたすことを目指している。
BPPTには以下のような10の研究センターが設置されている。
・材料部品構造強度研究所(スルポン)
・空気力学・ガス力学・振動研究所(スルポン)
・エネルギー・エネルギー資源研究所(スルポン)
・エタノール研究所(南スマトラ島・ランプン)
・流体力学研究所(東ジャワ・スラバヤ)
・陶磁器芸術開発センター(バリ)
・海岸工学研究所(中部ジャワ・ジョグジャカルタ)
・熱力学・エンジン・推進システム研究所(スルポン)
・バイオテクノロジー研究開発センター(スルポン)
・プロセス技術研究所(スルポン)
設置場所に記されたスルポンというのは、ジャカルタから南西30kmのところに建設されたスルポン研究学園都市のことである。我が国の筑波研究学園都市と同じような構想で建設されたが、ジャカルタからのアクセスでは高速道路が途中までしかなく、若干まだ不便である。ここにはこのほか原子力庁の多目的研究炉、インドネシア科学院の研究機関もおかれている。
また、BPPTはバルナ・ジャヤと呼ばれる研究船を4隻所有し、海洋開発、漁業開発等に利用されている。
この他の科学技術関連機関としては、LIPI(インドネシア科学院)、BATAN(原子力庁)、BAPETEN(原子力規制庁)、LAPAN(航空宇宙庁)がある。これらは直接大統領の下にあるが、研究・技術担当大臣の大きな調整力を受ける。また、農業省、工業・商業省等の他省庁にも付属の研究所がある。
インドネシアの工業化の牽引力を果たすべく、航空機、造船、車両、工作機械、爆薬等の分野についてそれぞれ国営の製造会社があり、これらをたばねる戦略企業庁の長官をハビビ大臣は兼務していたが、これらの企業は現在他の大臣の管轄下にある。
Ⅵ.平成10年政策研ニュ−ス記事総目次
| 平成10年を迎えて | 佐藤征夫 | 1月号 | |
| <レポート紹介> | |||
| 外国技術導入の動向分析(平成7年度) | 山口 治 | 1月号 | |
| 研究開発投資の活発な企業が求める高学歴研究者・技術者 | |||
| 書のキャリアニーズに関する調査研究 | 和田幸男・前沢祐一 | 2月号 | |
| 研究開発投資の決定要因・企業規模別分析 | 後藤晃・古賀款久・鈴木和志 | 2月号 | |
| 地域における科学技術振興に関する調査研究(第3回目) | 坂田和徳 | 3月号 | |
| マクロモデルによる政府研究開発投資の経済効果の計測 | 永田晃也 | 4月号 | |
| 英国における研究評価(公的研究助成にみる評価「Value | 舘 和夫 | 5月号 | |
| for Money」と「Selectivity」) | |||
| 大学などからの技術移転成功事例におけるアクター分析 | 新井英彦 | 5月号 | |
| 大学における新構想が他学部に関する実態調査 | 吉田通治・神田由美子・前沢祐一 | 6月号 | |
| 「総合科学技術会議」が担うべき機能 | 平澤 冷 | 6月号 | |
| 公的資金による研究機関のあり方 | 平澤 冷 | 7月号 | |
| 外国導入技術の動向分析(平成8年度) | 情報分析課 | 7月号 | |
| 科学技術政策のための評価とチェック | 平澤 冷 | 8月号 | |
| 行政機構内外における科学技術政策推進の多米の支援体制 | 平澤 冷 | 9月号 | |
| 日本の技術輸出の実態(平成8年度) | 情報分析課 | 11月号 | |
| <研究会等紹介> | |||
| 第7回国際技術経営会議 | 第2研究 | 1月号 | |
| 平成8年度地域政策研究会の開催について | 第3調査 | 1月号 | |
| 平成9年度地域科学技術政策研究会の開催結果報告 | 坂田和徳 | 1,3月号 | |
| 先端科学技術動向調査(加速器科学)委員会 | 第4調査・情報分析課 | 2月号 | |
| 国際ワークショップ「アジア圏の地域科学技術協力」の開催 | 第3調査 | 2,4月号 | |
| STS(科学技術社会)国際会議 | 第2調査 | 2,4月号 | |
| 遺伝子治療を考える市民の会議からの報告 | 第2調査 | 4月号 | |
| 研究開発に関する民間資金動向及び活用方策に関する懇談会 | 民間資金動向調査チーム | 5月号 | |
| The Science and Technology Diplomats Circle of | |||
| Tokyoへの技術予測の説明会 | 第4調査 | 6月号 | |
| 技術貿易統計検討会の開催 | 情報分析課 | 10月号 | |
| 第4回地域科学技術政策研究に関する国際会議 | 柿崎文彦 | 12月号 | |
| <講演会> | |||
| 「技術戦略論の主な問題・情報技術と新たな企業モデル」について | 榊原清則 | 3月号 | |
| <海外事情> | |||
| 韓国工学アカデミー主催シンポジウムでの講演 | 佐藤征夫 | 1月号 | |
| International Foresight Conferenceへの出席 | 古閑知明 | 1月号 | |
| オランダアムステルダム大学及びフランス鉱山大学との連 | |||
| 携研究及び共同研究の調査 | 藤垣裕子 | 2月号 | |
| 「国家研究開発体制の新しいモデル」に関する第2回国際会議出席及び発表 | 藤垣裕子 | 2月号 | |
| 「1997年度技術・経営戦略米国調査」 | 渡辺俊彦 | 2月号 | |
| APEC技術予測センターの発足について | 桑原輝隆 | 3月号 | |
| 米国科学技術振興協会(AAAS)での講演 | 佐藤征夫 | 3月号 | |
| ドイツ・EU の科学技術政策の形成過程に関する調査 | 富沢宏之 | 4月号 | |
| 「科学技術情報の自己組織化」プロジェクト会議参加と発表 | 藤垣裕子 | 5月号 | |
| ベトナムの科学技術研究調査 | 吉水正義 | 5月号 | |
| スイス連邦政府における科学技術政策の事情について資料収集 | 柿崎文彦 | 5月号 | |
| 仏国及び独国の研究評価に関する調査 | 舘 和夫 | 5月号 | |
| 国際シュムペーター学会出席 | 古賀款久 | 8月号 | |
| OECD 科学技術指標専門家会合等への出席 | 富沢宏之 | 8月号 | |
| 国際社会学会議出席 | 藤垣裕子 | 9月号 | |
| 第一回EUROPTA ワークショップ出席 | 木場隆夫 | 9月号 | |
| 欧州科学技術政策ワークショップ出席 | 佐藤征夫 | 10月号 | |
| フィンランド海外貿易協会98年度総会出席 | 権田金治 | 11月号 | |
| <用語解説> | 藤垣裕子 | ||
| サイエントメトリックスについて | 3月号 | ||
| <コラム> | |||
| 外国為替・外国貿易管理法及び法令等の改正について | 田村泰一 | 1月号 | |
| 調査研究レポートNO.55 の背景 | 和田幸男 | 2月号 | |
| 地域科学技術政策研究の経緯と今回調査研究報告書 | 坂田和徳 | 3月号 | |
| AAAS(トリプルエイエス)について | 佐藤征夫 | 3月号 | |
| 欧州の研究評価を活かせ | 舘 和夫 | 5月号 | |
| 英国出張記 | 榊原清則 | 7月号 | |
| IIASA を訪問して | 藤原直也 | 9月号 | |
| IMD訪問記 | 藤原直也 | 10月号 | |
| EPTA年次会議出席 | 木場隆夫 | 10月号 | |
| <トピックス> | |||
| 日本東京の空の下で | 韓 亨浩 | 2月号 | |
| 国際客員研究官滞在記 | Laydesdorff | 4月号 | |
| 人物紹介(榊原清則) | 古賀款久 | 4月号 | |
| Mark Boden氏の日本雑感 | Mark Boden | 5月号 | |
| 創設期の政策研を振り返って | 長濱 元 | 6月号 | |
| 政策に反映する調査研究を | 上原 哲 | 7月号 | |
| 活力ある政策研への期待 | 尾藤 隆 | 7月号 | |
| 創立時の雰囲気 | 平野千博 | 7月号 | |
| 創立10周年記念誌の刊行 | 情報分析課 | 7月号 | |
| 創立時の研究とその後の展開 | 馬場靖憲 | 8月号 | |
| ItzhakWirth 氏の日本雑感「友への手紙」 | Itzhak Wirth | 8月号 | |
| 「個の発信」によるネットワーク価値創造の時代へ | 前田 昇 | 9月号 | |
| 科学技術政策研究への期待 | 香月祥太郎 | 9月号 | |
| 企業社会と政策研 | 清家彰敏 | 9月号 | |
| 政策科学への煉獄 | 永田晃也 | 10月号 | |
| 私と日本についてのこと | スチーブン・コリンズ | 10月号 | |
| マレイシアの科学技術政策について | 松崎忠男 | 11,12月号 | |
| タイにおける科学技術の受容について(雑感) | 塚本 勝 | 12月号 | |
| <最近の動き> | |||
| 科学技術政策研究所における研究評価 | 企画課 | 2, 5, 6月号 | |
| 任期付き研究員を採用 | 企画課 | 5月号 | |
| 創立10周年記念事業(式典) | 情報分析課 | 7月号 | |
| 創立10周年記念事業(国際シンポジウム) | 企画課・情報分析課 | 10月号 |
中間機構(intermediate-layer)とは、行政レベルと研究実施レベルとの間をつなぐインタフェース的機能を果たす組織群のことを指す。この中間層の担う役割は、行政と研究の間の意見調整および緩衝役、資金配分、配分決定のための研究評価、技術予測の政策への反映、双方の意見を取り入れた国の科学技術政策における長期展望の議論、などである。各国の科学技術システムを比較研究する際、この中間機構のしくみを探求することは、各国のシステムの特徴を描き出す上で役にたつ。たとえば、英国ではリサーチカウシルがこの中間機構に相当し、中間機構を担う層はそれほど厚くない。オランダではこの機構を担う層は厚く、NWO(科学技術財団)、大学連合、科学技術予測委員会、アカデミーなど多くの組織がある。ドイツでは例えば代表的なものとして、マックスプランク研究所群と政府との間に、マックスプランク学術振興協会が存在している。このように、中間機構は省庁など行政機構とは独立したものであることが特徴である。これに対し、日本の科学技術庁は、行政レベルとこの中間層の機能の両方を果たしていると考えられ、省内の局によってこの機構が役割分担されていると考えられる。欧州の近代科学技術システムにおいては中間層が独立していく傾向があるが、日本では1つの庁のなかに2つの機構が同居しているのが特徴である。中間機構の概念、および欧州各国と日本のシステムとの比較は、科学技術政策の研究者であり、かつ STS(科学技術社会論)研究者のArie Rip氏が、当研究所において行った講演録に詳しく収録されている(科学技術政策研究所講演録No.58、オランダの科学技術政策:行政と研究をむすぶ中間機構を中心として〜「社会学的」科学技術政策研究序論〜参照)。
○ 機関評価結果のとりまとめについて
昨年5月より政策研の運営全般(調査研究課題全般を含む。)についての評価を行ってきた機関評価委員会(委員長:西島安則京都市立芸術大学長)は、1月13日に評価結果の報告書をとりまとめ、公表した。報告書では、政策研の過去10年間の活動実績全般について、定員46人の小規模な機関の最初の10年としては良好な成果を出していると評価している。一方、今後の調査研究活動の進め方、組織及び運営のあり方等についての指摘もなされている。当研究所では、今後、報告書において指摘された事項について、その具体的な取り組み方策についての検討を行うこととしている。(評価結果の概要は2月号に掲載します。)
○ 海外出張
| ・12/4-12 | 藤垣2研主任研究官、渡辺2研研究官(オランダ) |
| ・12/10-15 | 桑原4調総括上席研究官(ハンガリ−) |
本年は、1900年代最後の年である。これから、1年弱で2000年となることもあり、とりあえず2000年を、そして今後の少なくとも10年間を視野に入れた政策研ニュースの編集を目指したい。
行政改革大綱「中央省庁等の改革にかかる大綱(案)」が示された。省庁の再編、審議会の改廃、試験研究機関等行政法人化等の諸問題が議論され具体化されている。科学技術政策の進め方についても一新されるのであろう。当研究所の成果が活用されるような組織形態であることを祈るとともに、活躍の場を広げて参りたい。
本ニュースは、年頭に当たり所長を始め各研究グループ等からの本年の抱負を掲載した。この目標に沿って、所内の活動が活発に行われるよう切に願うとともに、編集に関わる我々もこの目的達成に俊敏さ(agility)をもって力を尽くして参りたい。読者の皆様の今後とも一層のご支援をお願い申し上げます。(T)